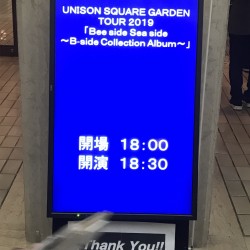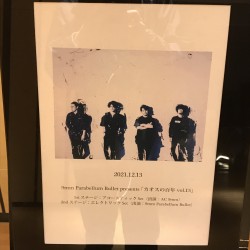昨年には日比谷野音でもワンマンを行い、現在ライブハウスシーンを席巻しているsmall indies table所属のバンドの中でも独自の立ち位置を築き始めている、埼玉県越谷市の4人組バンド、KOTORIが越谷というよりは春日部にほど近い東武動物公園で主催フェスを開催。小学生の頃に1度だけ行ったことがあるこの会場をこうした形で再訪することになるとは思わなかった。
東武動物公園内の遊園地エリアにあるイベントスペースにはフジロックのレッドマーキーをイメージしたという、普段からイベントなどが行われているのだろう屋根と椅子が常設のPHOENIX STAGEと、芝生の上に作られたORION STAGEの2ステージが。各ステージ入場時にはリストバンドチェックとともに消毒も都度行われるという感染対策っぷり。
野音ワンマンをはじめとして、KOTORIは何でこんなにもというくらいの雨バンドであり、この日も朝からしっかり雨が降っているだけに、PHOENIX STAGEに屋根があるというのは実に嬉しいところだ。
11:00〜 Cody・Lee (李) [ORION STAGE]
ORION STAGEのトップバッターにしてこのフェスのトップバッターであるのはCody・Lee (李)。昨年11月のBAYCAMPでもオープニングアクトとしてフェスの始まりを鳴らした5人組バンドである。
フジファブリックのSEでメンバー5人が登場すると、BAYCAMPの時は女性と見間違うくらいに髪が長くて金髪だった力毅(ギター)が被っているハットで隠れて見えなくなるくらいに髪が短くなっている。対照的にニシマケイ(ベース)は髪が長く、緑と銀が合わさったような独特な色合いに。
そしてより山内総一郎っぽい見た目(志村正彦ではないのが世代ということだろうか)になった高橋響(ボーカル&ギター)がギターを鳴らしながら歌い始めた「I’m sweet on you」でスタートすると、その高橋のボーカルに尾崎リノ(ボーカル&ギター)の声が重なり、男女ツインボーカルとして曲のポップさをより引き立てる。
きのこ帝国へのリスペクトと愛情を感じさせるフレーズを随所に挟む、レイドバックした雰囲気の「drizzle」ではしかし間奏で高橋の
「TORI ROCKで1番良いギター!」
という言葉に続けて、力毅が暴れるように動きながら轟音ギターをかき鳴らす。このサウンドのコントラストはフジファブリックときのこ帝国だけではなく、もっと激しいサウンドのバンドからの影響も感じさせるが、このバンドはそれを隠すどころか自分たちでアピールするかのように自分たちの音楽の中にそうした要素を入れている。それは聴いている側からすると何かと発見があって面白かったりするものである。
BAYCAMPでライブを見た時はメンバーの出で立ちと音楽性から都会的な空気を感じたりもしていたが、こうして自然でしかない会場でライブを観るとこうしたシチュエーションもよく似合う。それが一変するのはオリエンタルなダンスサウンドという、まさにフジファブリックの変態的とも評されてきた部分の影響を強く感じる「我愛你」から「WKWK」という流れ。特に「我愛你」はこの曲でこのバンドの存在を知ったという人も多かったのか、曲が始まるや否や雨が降る中でもぴょんぴょん飛び跳ねる人の姿がよく見える。
高橋はその雨が降っている様を
「KOTORIは日比谷野音の時も雨でしたね(笑)僕も観に行きましたけど、KOTORIが雨を連れてきてる感じだけど、野音にもいた僕が雨を連れてきてると言われても反論の余地がない(笑)」
と、早くも屈指の雨バンドとして認知されてきているKOTORIの雨バンドっぷりをもしかしたら自身が原因かもしれない可能性を匂わせて笑わせると、サビで高橋と尾崎の声が重なる瞬間に一気にパッと視界が開けていくようなスケールを持った、これから先このバンドがもっとたくさんの人に聞かれることになる可能性を感じさせる「桜町」で壮大に締めた…と思いきや、そのまま力毅がノイジーなギターをかき鳴らしまくり、原汰輝のビートがパンクに突っ走るショートチューン「When I was cityboy」を追加し、ポップなバンドというイメージを最後にひっくり返してみせた。そこにこのバンドのライブバンドっぷりを感じた人もたくさんいるはずだ。時間ちょっと押したけど。
1.I’m sweet on you
2.drizzle
3.我愛你
4.WKWK
5.桜町
6.When I was cityboy
11:30〜 リーガルリリー [PHOENIX STAGE]
普段から動物のショーみたいなのが行われていそうなPHOENIX STAGEはORION STAGEと1分くらいの距離という近さであるが、着いた時にはすでにリーガルリリーの3人はステージに登場して1曲目を始める瞬間だった。
おなじみの上手には髪がさらに長くなったゆきやま(ドラム)、真ん中には金髪の海(ベース)、下手には中学生かのようなたかはしほのか(ボーカル&ギター)が並び、昨年リリースされたアルバム「bedtime story」の物語の始まりを告げる導入的な「ベッドタウン」で始まり、そのまま「GOLD TRAIN」へと繋がる流れはアルバムと同様であり、ライブでもすっかり定着したと言っていいだろうが、六本木EX THEATERでのワンマンを経たばかりということもあって、3人それぞれの音の強さがさらに増している。
1人1人それぞれが化け物みたいな凄まじい音を鳴らしていて、それがバンドとして一つに合わさることによってさらに大きな怪物になっているかのようだ。しかもそれをメンバーは無自覚にやっているかのようですらある。ただ自分のスイングで思いっきりバットを振っているだけなのに、そこにボールが吸い寄せられていくかのような感覚すらある。
それは海のゴリゴリの重いベースのイントロから始まり、
「私は私の世界の実験台」
というたかはし独自の世界観が炸裂するような歌詞を経て、ゆきやまのダンサブルなビートがサビでポップに着地させるという忙しない展開を見せる「1997」もそうであり、ここまでは「bedtime story」そのままの曲順なのだが、ここで4月にリリースされたばかりの新作EP「the World」のリード曲である「東京」が挟まれる。
「東京」というタイトルであり、歌詞にもそのフレーズは多々登場するのだが、それでも歌い出しが
「ナイジェリアの風が ライターの火に話しかける
君はどこから来たんだ」
というものであるため、この「東京」はこれまでに様々なアーティストが歌ってきた「地方出身者から見た東京という街」という曲でもなければ「東京で暮らしてきた人が綴る等身大の東京」という曲でもない。(たかはしは東京の福生市出身であるが)
ただひたすらにたかはしが頭の中で描いている「東京」。それはきっとたかはし自身にしか見えていないものであり、我々が理解できるものでもないのだが、未だかつてこんな「東京」という曲があっただろうかと思う。やはりとんでもないバンドだ。
「bedtime story」の世界に戻ったかのようにポップなメロディとサウンドの「林檎の花束」を演奏したかと思いきや、最後にはゆきやまのあまりにも強靭すぎるビートのアレンジによって獰猛さを増し、それがあまりに凄すぎて見ていて感動すらしてしまう「リッケンバッカー」で締めるのだが、ライブでは毎回演奏されるバンドの代表曲であるこの曲も、こうして最後に演奏されることはほとんどなかった。むしろそうならないようなライブを作ってきた感すらあったのだが、今こうしてこの曲を最後にするライブを作るようになったのは「bedtime story」と「the World」という作品を作り、その曲たちを軸にしたライブをするようになったからじゃないかと思う。それは「リッケンバッカー」を軸にして最後にそこに辿り着くように…という流れとは真逆のものだが、最後にこの曲があるからこそ、
「音楽よ、人を生かせ」
というフレーズが今の音楽業界が置かれている状況に切実に響く。こうして音楽を聴くことやライブを観ることで心が動く。感動することができる。それが生きる理由になっている。音楽は決して不要不急なものなんかじゃない。誰にも理解してもらえなかったとしても、これは「僕だけのロックンロールさ」。
1.ベッドタウン
2.GOLD TOWN
3.1997
4.東京
5.林檎の花束
6.リッケンバッカー
12:00〜 mother [ORION STAGE]
なんとも検索しづらい名前のバンドであるが、かつて10代限定フェスで優勝してシーンを騒がせたバンド、Shout it Outのボーカルだった山内彰馬(ボーカル&ギター)が結成したバンドである。
ギターは鈴木陸生(ex.赤色のグリッター)、ベースが谷川将太朗(ex.Rocket of the Bulldogs)、ドラムが畝狹怜汰(ex.SUNNY CAR WASH)という確かなスキルと経験を持つメンバーたちである。
「青春」をひたすらに歌っていたShout it Outはライブでもその溢れんばかりの衝動を大きくて速いバンドサウンドに乗せて炸裂させていたバンドだったが、motherでの山内は突っ走る衝動だけではない雄大なメロディを、元から定評のあった歌唱力をフルに生かす形で鳴らしている。とはいえやはり生まれたばかりのバンドだからこその衝動は感じるけれど。
とはいえまだ音源を1曲もリリースしていない(最近音源付きのグッズを出し、その曲も演奏した)ということで、「あの山内の新バンドか」という興味を持って集まった観客もまだどうやって向き合えばいいのかを探っている感じもしたが、どうやっても年齢を重ねるにつれてリアリティを失っていかざるを得ない青春を歌っていたShout it Outは遅かれ早かれバンドが終わるか、方向性が変わらざるを得ないと思っていた。
結果的にはバンドは終わってしまい、山内はその後に自分がやりたいことをじっくりと見定めてからこのバンドを始動させたように感じる。だからこそこのメンバーをしてポップにすら感じるところもあるこのバンドの曲たちは、今の山内が本当にやりたいことを鳴らしているのだろう。
山内のShout it Out時代の相棒であった(後期Shout it Outはメンバー脱退を経て2人組だった)細川千弘は今はこのフェスの主催バンドのKOTORIのドラマーになっている。そのKOTORIのフェスが山内のバンドを呼ぶということは、山内と細川は決してケンカ別れしたわけでもなく、関係性が良いままでバンドを終えたということ。実際に山内もKOTORIへの感謝を口にしていたし、形が変わって青春のすべてが終わっても山内と細川の物語は、音楽は続いている。同じバンドで音楽を作っていた2人は、今は違うバンドで同じフェスを作っている。
12:30〜 COUNTRY YARD [PHOENIX STAGE]
KOTORIの所属しているsmall indies tableや近い存在であるTHE NINTH APOLLOというレーベルのバンドやレーベルそのもののTシャツ以外に、PIZZA OF DEATHのTシャツを着た人も会場にちらほらと見かけたのは、PIZZA OF DEATH所属のこのCOUNTRY YARDが出演するからであろう。
やはりPHOENIX STAGEに着くとすでにメンバー4人がステージに登場しており、1曲目の「Chaising」がスタートしたところだったのだが、動物園の中の椅子ありのイベントスペースというとてもパンク・メロコアバンドが立つような場所には思えないところでShunichi Asanuma(ドラム)が牽引するツービートのパンク・メロコアが鳴らされている。
メロコアならではの美メロをそのまま真っ直ぐに響かせることのできる澄んだ声の持ち主であるKeisaku”Sit”Matsu-uraがベース&ボーカルということで、長髪に髭というワイルドなHayato Mochizukiとメガネをかけた知的なYu-ki Miyamotoのギター2人が曲によって自在にサウンドやフレーズを変化させる。この辺りはこのバンドの後輩に当たるフォーリミに通じている部分でもあるのだが、Mochizukiのコーラスもまたバンドの美メロを引き立てる大きな要素になっている。
とはいえ世の中の状況的にも、そもそもの客席の形状からしてもモッシュもダイブもできないし、「In Your Room」のコーラスパートで一緒に歌うこともできない。観客はただ腕を上に挙げているのだが、Matsu-uraはその観客の姿を指差したり、コーラスパートでは「心で歌ってくれ」とばかりに胸のあたりを叩いたりする。観客の思いがしっかり響いているということを示すように。
「シャバの皆さん、COUNTRY YARDです。俺たちずっとワンマンツアーはやってたんだけど、対バンっていうのがすごく久しぶりで。このフェスに来たらたくさん他のバンドがいて対バンだ〜!って(笑)
ちょっと前にラジオを車の中で聴いていたら、The Songbardsの皆さんが電話でゲスト出演していて。俺もThe BeatlesとかOasisが好きだから、「バンド名はOasisの曲から取ったのかな?」って気になって聴いてて。そしたら今日のフェスのフライヤー貰ったら、The Songbardsの名前もあって。今日対バンでライブ見れるじゃん!って」
と、どこからどう聴いてもパンク・メロコアバンドでありながらも、自分たちとは全く違う音楽性のバンドのライブを楽しみにしているのも、結成からはもう10年以上経っているバンドとしてライブハウスで様々なタイプのバンドと対バンをするという文化の中で生きてきたからなのだろうし、The Songbardsを気に入っているというところからもこのバンドのメロディに対するこだわりが垣間見える。
「まだ昼だけど、夜の歌を」
と言って演奏された「Tonight」で雨が降っていて空が暗いということもあって、まさに夜になったかのような感覚になると、ラストの「I’ll be with you」ではコーラスパートで今までのライブと同じように観客を煽りながら、Matsu-uraは自身のマイクスタンドをぐるっと回して客席の方に向ける。もちろんそれでも観客は両腕を高く挙げながらも声を出して歌うことはない。するとMatsu-uraがそのマイクの向きに合わせるように回り込んで客席に背を向けながら歌う。
それはきっとこのバンドが今までのライブハウスでのライブと全く同じライブをやっているということだろう。確かに我々の楽しみ方は変わってしまった。パンクバンドとしては見たい景色が見れなくなってしまったかもしれない。それでもこうして、パンクやメロコアバンドはどんな世の中の状況であっても、どんな場所であっても戦っていくことができる。それを確かめさせてくれたのは、COUNTRY YARDのパンク・メロコアとしての矜持だ。
1.Chaising
2.Passion
3.Purple Days
4.In Your Room
5.Tonight
6.I’ll be with you
13:00〜 初恋 [ORION STAGE]
motherに続いてこれまた検索しづらいなぁというバンド名であるが、これは実はフジロックなどにも出演したことがあるバンド、突然少年がコロナ禍中に活動休止するにあたって名前を変えたバンドである。
なので最初からこのバンドのことを目当てに来ていたであろう、突然少年のファンらしき人たちも最前列のあたりにはいたし、メンバーが出てきてから「あれ?突然少年じゃね?」と気づいた人もいたようだし、鳴らしている音によって「カッコいいバンドだな」と思った人もいたようだという、かなり入り組んだ客席のリアクションになっている。
とはいえメンバーが同じであるし、名前が変わったからといって急に音楽性が変わるような器用な人たちでもないわけで、冴えない男たちが冴えない日常や冴えない人生をひっくり返すためのロックという突然少年のスタイルは変わることはない。それは大武茜一郎(ボーカル&ギター)の綴るシュールな歌詞と、やたらと歌っている間にマイクスタンドが下がってくるというのも、とだげんいちろう(ベース)の巨漢であれど素朴な出で立ちも、カニユウヤ(ギター)の華やかな見た目とテクニカルなギターも。特にカニユウヤは忘れらんねえよのサポートをしていた時もあったが、精神的な不調で突然少年から離れたりしていただけに、こうして元気にギターを弾いている姿を見れるのは嬉しい。
なかなかKOTORIとは距離が近いようには感じないところもあるのだが、大武は越谷EASY GOINGというKOTORIの本拠地と言えるライブハウスで出会ってからもう7年くらいの付き合いであり、
「KOTORIは一生の友達です」
と言うくらいの深い仲であるという。どこからどう見ても善人でしかないこのメンバーたちがそこまで言うというあたりにKOTORIのメンバーの人間性と、このフェスがこのご時世でこのメンツによって開催できていることを改めて感じさせる。
しかしこのバンドのすぐ後にはPHOENIX STAGEでこの日の出演者の中ではトップクラスに知名度のあるyonigeが控えていることから、曲が終わるにつれて観客がそっちに移動してしまうという事態になってしまい、とだも
「みんな帰っちゃう…」
と少しショックを受けていたようだ。こればかりは仕方ないことではあるが。
そんな素直なメンバーであるが故に大武は、
「今日物販持ってきてるんですけど、全然売れなかったらこの動物園の動物たちと暮らさなきゃいけないくらいに帰れなくなるんで、人助けと思って買ってください」
と言って残っていた観客から爆笑を引き出すと、最後に演奏された曲は「シチューとほうれん草のおひたし」という日常の風景が目に浮かんでくる歌詞のAメロからサビで一気にパンクに疾走していく曲。
なぜこのバンド名に変えたのかは自分にはわからないが、バンド名が変わっても3人の持つ衝動や魅力は全く変わっていない。何というか、これこそがロックバンドをやろう!という高校生の頃の気持ちをいくつになっても思い出させてくれる。
13:30〜 yonige [PHOENIX STAGE]
2日前にO-EASTでツアーファイナルを終えたばかりのyonige。KOTORIとはつい先日までsmall indies table tourを回っていた戦友と言える仲である。
SEもなしにサポート2人を含めた4人がステージに登場すると、まぁ当然なのだが出で立ち自体は全く変わることなく、ツアーと同様に「健全な社会」のオープニング曲である「11月24日」からスタートし、緊張感のあるイントロと歌い出しからサビで一気にホリエ(ドラム)とごっきん(ベース)によるリズムが躍動感を増していく。このグルーヴにはこの状況下でもツアーを回って練り上げてきたものの強さを感じられる。
雨こそ降っていてもこうして野外のフェスで聴くことによって、元々夏フェスの会場で単曲入りのCDが先行販売されていたことを思い出す「リボルバー」では満員の観客が思い思いに腕を上げたりして楽しんでいる姿が見える。もうすっかりyonigeの代表曲と言えばこの曲なのかもしれない。牛丸ありさ(ボーカル&ギター)はワンマンでは思いっきり歌詞を間違えていたが、この日は歌詞を間違えることなく凛とした声を高い屋根に向かって反響させている。本当に良いボーカリストになったと思う。
ツアーでの牛丸の弾き語り的な始まり方とはまた違う、音源通りのアレンジで演奏された「2月の水槽」はツアーのように次の曲にそのまま繋げるという形ではないために音源通りの尺でアウトロをバシッと切る。それもまた新鮮である。
ごっきんのベースがうねりまくって波のようなグルーヴを生み出し、牛丸のボーカルが進化していることがサビを聴けばすぐにわかる「往生際」、淡々としたサウンドと温かな演奏がこうしてこの東武動物公園という会場でフェスが開催されていることの幸せを感じさせてくれる「あかるいみらい」と、「健全な社会」の曲を続けると、牛丸がアコギに持ち替えてツアー同様のオーガニックなアレンジになったのがこの会場の雰囲気に実によく似合う「サイケデリックイエスタデイ」と、ワンマンにおける深い部分、濃い部分を抽出してフェスのセトリを作っているかのよう。もはやフェスだから盛り上がる曲をやろうというような考えは全く持っていないのだろうし、これが今見せたいyonigeのモードということだろう。
そのまま牛丸のアコギと土器大洋のエレキギターの音がロックバンドのサウンドとして絡み合う「ピオニー」で「健全な社会」のモードをひと段落させると、
「TORI ROCK FES、yonigeははつしゅちゅじょう…はちゅしゅつじょう…」
と、初出場が全く言えずに噛みまくる牛丸だったが、この日もツアーで演奏されていた新曲を演奏し、徹底的に今見せたいyonigeを見せ、それはまた新たなモードに突入していることを示した。
それにしても30分で8曲も演奏するというのはパンクバンド並みのペースであるし、フェスでそうした内容のライブができるくらいに今のyonigeのライブは引き締まっている。ワンマンが自分たちのやり方で流れを作っているだけに、もはやフェスに向いているタイプのバンドではなくなってきているのかもしれないけれど。
1.11月24日
2.リボルバー
3.2月の水槽
4.往生際
5.あかるいみらい
6.サイケデリックイエスタデイ
7.ピオニー
8.新曲
14:00〜 The Songbards [ORION STAGE]
雨の中であるが、すでにステージに立っているメンバーの姿を見るだけで爽やかな気持ちになるのは神戸出身の4人組バンド、The Songbardsである。
COUNTRY YARDのMatsu-uraもMCで触れていたが、おそらくは曲タイトルからバンド名をつけたであろうOasisよりも、特に上野皓平(ボーカル&ギター)と松原有志(ギター&ボーカル)のスタイリッシュな出で立ちとハーモニー、柴田淳史(ベース)のハイトーンコーラスによる心地良いサウンドと歌は初期The Beatlesを彷彿とさせる。あくまでもJ-POPではなくてロックバンドであるというところも。
「KOTORIから直接電話かかってきて、何かやらかしちゃったかな?と思ったらこのフェスの誘いだった(笑)」
と笑わせてくれた上野は「窓に射す光のように」では少し喉の調子が悪かったのか、それとも野外フェスならではの開放感ゆえに力が入りすぎたのか声がひっくり返るような瞬間もあったが、その野外フェスで演奏されるからこそ、こうして雨が降っている中ではなく、また太陽の光が我々とバンドを照りつける中で聴きたいと思わせる「夏の重力」「太陽の憂鬱」という夏曲を連発し、CM曲で知ったという人にも、KOTORIやその周りにいるバンドに比べたらポップな歌モノバンドというイメージを持っている人にも最後には松原がアグレッシブに右脚を上げながらギターを弾いたりというライブバンドとしての確かな力を見せた。こうしたロックバンド主催のフェスにも出れるし、テレビからも曲が流れる。そんなかなり稀有な位置にこのバンドはいる。
14:30〜 Bearwear [PHOENIX STAGE]
Kazma(ボーカル)とkou(ベース)によるバンド、Bearwear。すでにインディーズ界隈ではそれなりに話題になっているバンドであるが、このTORI ROCKが野外フェス初出演となる。
ギター2人とドラムをサポートに加えた5人編成で、Kazmaがピンボーカルというのも今やラウドバンドくらいでしか見れない編成であるが、そのKazmaがウィスパーボイスで歌い、メンバーたちが音を構築していく「2222」からはポストロックの要素を、ギターが体を沈み込ませるように轟音を鳴らし、Kazmaもシャウトするようなボーカルに転じる「May」からはハードコアの要素を感じるという意味では昔、サマソニの深夜にライブを見たMogwaiを彷彿とさせる。あまり音楽性的にはKOTORIと近しいようには見えないけれど、ポストロック的な構築美とkouのコーラスでメロディを立たせるという手法はKOTORIの中にも間違いなく存在している要素だ。
だからこそKazmaも
「Bear(熊)ってバンド名についてるから、動物枠で動物園で開催されるTORI ROCKに呼んでもらえたのかな(笑)」
と笑わせながらも、
「こうやってここに来て、こういう景色を見れて、いろんなことを考えたと思うけど、KOTORIを信じて良かった」
と音楽性を超えたKOTORIへの信頼を感じさせた。
5月にリリースされたばかりのシングル「madoromi」「Carry On」もともに凶暴性と知性、轟音が重なっていくことの美しさを感じさせてくれたが、このTORI ROCK FESがKOTORIと仲の良い、似たタイプのバンドの集まりというフェスではなく、やっている音楽は違うけれどバンドとしての精神を共有して活動している者たちが作り上げているということを示してくれたのがBearwearだった。KazmaのMCの声がボーカルの時とはだいぶイメージが違ったのは驚きだったけれど。
15:00〜 tricot [ORION STAGE]
タイムテーブルが発表された時に「こっちのステージなの!?」と1番驚いたのがこのtricotである。中嶋イッキュウ(ボーカル&ギター)はジェニーハイにも参加して知名度を上げているし、バンドとしても数々のフェスの大きなステージに立っているからだ。
スッと4人がステージに登場すると、上手のイッキュウは鮮やかな金髪、真ん中のヒロミ・ヒロヒロ(ベース)はピンク、下手のキダ・モティフォ(ギター)は茶髪、3人を後ろから支える吉田(ドラム)は全く変わらぬ黒髪という色とりどりの髪色で、1曲目の「右脳左脳」から聴いていて実にノリにくい変拍子のリズムを連発するのだが、メロディとイッキュウの色っぽいボーカルによってそれすらもポップに聴こえてくるというのが、ここまでにいろんなバンドを見ているとこのバンドのものでしかないということを実感する。
それは「よそいき」、タイトルにもなっているフレーズの歌唱が心地よい「WARP」というあたりでも変わらないが、そうした開放感というよりはむしろこの4人だけで純粋培養させてきた密室性を感じさせるようなサウンドであってもイッキュウは
「雨降ってるけど、こうして野外でライブか出来るのが本当に久しぶりで嬉しい」
とこのフェスに出演できている喜びを語る。アメリカやアジアのみならずヨーロッパに至るまで様々なフェスにこれまでに出演してしたtricotですらもこうして野外フェスに出演してライブをするのが久しぶりであるという事実に、世界そのものが変わってしまったことを実感せざるを得ない。
メジャーデビュー以降はフェスでもこれまでの代表曲を並べるというよりも今のバンドの姿を見せるというようなセトリを組むことが多いだけに「おもてなし」はこの日の中で唯一と言っていいインディーズ期の代表曲と言える曲であるが、この社会の情勢の中でこのタイトルの曲を演奏する(東京オリンピック誘致の際に某キャスターが使っていた言葉だ)というあたりにこのバンドなりのメッセージを感じるというのは考えすぎだろうか。
ヒロミのベースが一気にリズムを走らせ、イッキュウがハンドマイクで歌うことでキダのギターもよりフリーキーに、本人も飛び跳ねまくりながら弾く「おまえ」から、リリースされたばかりの、tricotの代名詞でもある変拍子を生かしながらもドラマの主題歌というタイアップもあってかキャッチーなメロディがより際立つボーカルになっている「いない」と連発すると、
イッキュウ「トリコを入れ替えるとコトリになるから、実質TORI ROCKはうちらのフェスでもある」
キダ「それはちゃう」
と息ぴったりの漫才のような2人のやり取りから、ラストはtricotの音楽世界の深淵に引き摺り込むような「potage」。決してド派手なわけではないけれど、こんな音楽をやっているバンドは他にはいないという点で、tricotは今でもフェスに出ればその存在の特異さが際立っているというか、それは今の方がよりそう感じられるものになっている。
tricotは以前yonigeと2マンツアーを行い、そこでは互いのカバーをやったりもしていたくらいに仲が良いのだが、このtricotのライブをyonigeの牛丸とごっきんは2人で1つの傘に入って見ていた。yonigeは近年はライブ中にほとんどMCをしないために2人の仲睦まじいやり取りやごっきんの牛丸へのツッコミを聞く機会も少なくなっているけれど、今でもその姉妹のような関係性は変わっていない。またコロナが開けたらその2組でツーマンツアーをやって欲しいと思う。
1.右脳左脳
2.よそいき
3.WARP
4.おもてなし
5.おまえ
6.いない
7.potage
15:30〜 さよならポエジー [PHOENIX STAGE]
早くもPHOENIX STAGEもトリ前というポジションなのだが、その位置に出演するということもあるが、音楽性としてもKOTORIと最も近いところにいると感じる出演者がこのさよならポエジーである。
オサキアユ(ボーカル&ギター)とナカシマタクヤ(ドラム)の2人に加えて長身長髪のサポートベースを加えた3人編成で登場すると、これぞTHE NINTH APOLLOのバンドだよな、というような疾走感あるストレートなギターロックを鳴らしていくのだが、KOTORIがただそれだけのバンドではないように、このバンドがそうしたよくいるタイプのバンドであるわけではない大きな要素はオサキの描く歌詞にあるだろう。
文学的というと実に抽象的でもあるが、短編小説を読んでいるかのような歌詞はまさに文学的だ。しかもそこに描かれるのは大多数の共感を得るためのラブストーリーなどでは全くない、オサキの脳内にのみ描かれるような、そしてそれを聴き手自身で風景を解釈するようなもの。それが轟音ギターに乗って紡がれていくというのはTHE NINTH APOLLOの他のバンドともまた違う持ち味である。
「TORI ROCKだからか鳥が音楽を聴きに来てる」
というようにこのステージの屋根には鳥が飛び交い、演奏の合間にはその鳥たちの囀りも聞こえてくる。まさにTORI ROCKというような光景になってきている。
前半は少しボーカルの聞こえがよくない(見ていた位置が悪かったのかもしれないが)と感じるところもあったが、中盤以降はそこがしっかりと聞こえるようになるというのはバンド側の経験でもあり、音響側の経験でもあるだろうが、オサキは
「この曲で横山が俺たちを見つけてくれた」
と言って、最後にKOTORIとの出会いの曲である「二束三文」を演奏したが、この曲の
「でもそれなりの才能で 俺は俺を救ってやろう」
という歌詞は結果的にオサキが、活動を一時休止もしたこのバンドがKOTORIをはじめとした様々な人たちに救われてここまで来たことを示していた。とことんライブハウスバンドというイメージのバンドであるが、こうした野外フェスの大きなステージでライブを見ることもこれから増えてくるのかもしれないと思うオーラを確かにこのバンドは放っていた。
1.金輪際
2.pupa
3.0830
4.前線に告ぐ
5.ランドマークス
6.二束三文
16:00〜 bacho [ORION STAGE]
朝から続いてきたORION STAGEも早くもというかいよいよというかトリ。任されたのはKOTORIが敬愛するバンド、bacho。若手主体ということもあるが、この日の出演者の中では1番のベテランバンドである。
KOTORIとは何度も対バンをしている間柄であるし、このバンドのことを知っている人がたくさんいるということは満員になっているORION STAGEの客席を見てもわかることなのだが、頭にタオルを巻いて気合いを感じさせる北畑欣也(ボーカル&ギター)が畳み掛けるように言葉を紡いでいく「ビコーズ」から観客の拳が上がり、飛び跳ねまくる。みんながbachoのライブを待っていたことが実によくわかる光景だ。
少しギターが外れているような感じもしたが、「決意の歌」「萌芽」という曲の歌詞はKOTORIがこのフェスを開催しようとした思いをそのまま代弁してくれているようですらあるし、北畑はそのKOTORIの思いを汲み取り、誰よりも理解しているかのようにこの日の日付や場所などを曲中に入れたりする。KOTORIやさよならポエジーのメンバーに愛されている伊藤知得も観客のことを指差しながらベースを弾く。見た目はクールに、でも熱さがわかるギターを弾く三浦義人とは対照的であるが、そのステージの佇まいからしてメンバーの人間性が伝わってくるかのようだ。
タイトルがそのままサビのフレーズになっている、bachoのエモーショナルなギターロックバンドとしての最新系とも言える新曲「Boy Meets Music」はこの場所で演奏されることで、KOTORIがbachoの音楽と出会った瞬間、あるいはこうしてこのフェスでbachoの音楽と初めて出会った少年の衝撃をそのまま歌にしているかのようであるが、その曲を終えると北畑は
「ここにいる人は優しい人だと思う。いろんなものを我慢したり押さえつけてライブを見て。自分の優先順位が高いものを守って、でも他の人の優先順位が高いものをバカにするなよ」
と言った。ついつい他の人の意見や反論を否定したくなってしまうようなご時世。それは我々音楽好きがライブに行くこと、あるいはこうしてフェスが開催されることに対しても向けられることでもあるのだが、もしそうした視線を向けられても、「じゃあ○○はいいのか」というようなことを言うと同じことをしていることになってしまう。改めてbachoの音楽が北畑やメンバーの意思とイコールなものであるのと同時に、自戒の意味でも本当に強く響く。
そんなMCを経ての「最高新記憶」ではまさにこれまでの記憶を更新するかのようにメンバーは北畑に合わせてマイクを通さずとも思いっきり歌っている。観客は同じように歌うことはできないけれど、またさらに最高を更新するときにはきっと観客も一緒に歌うことができているはずだ。
それで終わってもおかしくないくらいの大団円感もあったのだが、バンドはそのまま次の曲の演奏に入り、終わりかと思っていた観客を歓喜させる。しかもそれが屈指の名曲、人気曲である「さよなら」であったのは、KOTORIのために自分たちの持ちうる全てを使い果たそうという意思が感じられた。そこからはなぜKOTORIが決して多くの人が知っているという存在ではないこのバンドを敬愛しているのかが本当に良くわかった。
巷に溢れる「エモい」という形容をその言葉と音と観客の拳でもって全て蹴散らすかのようなエモーショナルな音楽。
前にSiMが主催フェスのDEAD POP FESTiVALで「セカンドステージのトリって主催者はライブ見れないんですよ。自分たちのライブの準備をしなくちゃいけない時間だから。だからそこに出てもらうのは本当に信頼して任せられるバンドじゃなきゃいけない」ということを言っていた。それはそのまま今年のこのフェスにおけるbachoの存在に当てはまるものだった。
1.ビコーズ
2.決意の歌
3.萌芽
4.Boy Meets Music
5.最高新記憶
6.さよなら
16:30〜 KOTORI [PHOENIX STAGE]
長かったような、でもずっとライブを見ていたのであっという間だったような1日。いよいよトリであり主催者であるKOTORIの登場である。時間が早いのはこの東武動物公園の閉園時間が早いからである。
bachoのライブが全部終わったのを確認してからメンバーが登場すると、まずはサウンドチェックとして演奏をするのだが、もうその時点で気合いが漲っているのがよくわかる。
実際に4人が満員の観客が待ち構える前に登場すると、横山優也(ボーカル&ギター)が静謐なサウンドの中で
「音楽で大切なものを守れますように」
と歌い、曲が進むにつれて壮大なスケールを獲得していく「We Are The Future」でスタート。上坂仁志は前半はギターを弾かず、途中からギターを加えるのがこの曲の展開に大きな貢献を果たしているし、この日、様々なバンドのライブでほぼ全部袖にいた、つまり誰よりもライブを見ていた細川千弘(ドラム)はそうした出演者たちのライブで得たものを全て放出するかのように立ち上がって叫びまくっている。そんな中でいつものように客席よりもメンバーの方を向いて冷静にリズムを刻む佐藤知己(ベース)の落ち着きっぷりは逆に凄いが、ここまでにこの日を作ってきたバンドたちのライブが、このフェスを生み出したこの場所がまさに音楽で大切なものを守るためのものになっている。この曲のタイトルは決して大言壮語なものではない。
「EVERGREEN」「ジャズマスター」という多くの人が抱く「フェスのトリとしてのKOTORIのセトリ」を体現するかのようなアッパーなギターロック曲の連発っぷりはCOUNTRY YARDや初恋というパンクをルーツにする出演者との共振を感じさせるし、そうした激しい曲での細川のドラミングはもはや鬼神と言ってもいいレベルだ。間違いなくKOTORIは細川がドラマーになってから変わった。その細川の元相棒である山内の新バンドのmotherのライブを見て昂ったところもあるのだろう。
「奇跡みたいな日々
最高の仲間よ
僕らはいつだって
繋がっていられるさ」
という歌詞がこの日、このフェスを1バースで示している、まるでこの日のために作られたかのようでもあるが、逆にKOTORIがこうしたフェスを作ることを予見していたかのような「unity」から、
「本当はぶっ飛ばし系でいきたいんだけど、新しい僕たちも見て欲しいなって」
と言って演奏されたのはリリースされたばかりのニューアルバム「We Are The Future」収録の「Anywhere」。穏やかなサウンドを4人で重ねていくというのはこれまでの曲とは全く違うけれど、横山はインタビューで
「今はアッパーな曲を作るモードじゃなかった」
と語っていた。コロナ禍で横山の作る曲や心境に大きな変化があったということだろうけれど、こうした音楽性の変化は先にアッパーなギターロックからの方向転換を図ったレーベルメイトのyonigeに通じるところとも言えるし、横山の囁くようなボーカルはBearwearの持つ要素であるとも言える。
「君が望むのなら どこへでも行けるよ」
という、英語歌詞の中で唯一挟まれる日本語のフレーズはKOTORIがこれからもあらゆる方向性の音楽に向かっていけることを示しているのかもしれない。
「ちょうど夕方5時くらいかな」
と言って再びアッパーに転じていくのは「夕方5時の帰り道のサイレン」というフレーズが出てくる「RED」であるが、
「忘れたくない ことばかりが増えたな
ここへ来て 良かったなって思うよ
泣きそうになるくらい 真っ赤な夕日を見たよ
ここじゃなきゃ 見られない気がするよ」
という歌詞はまさに今こうしてKOTORIが見ている景色、そして我々が見ているKOTORIが作った景色をそのまま歌っているかのようだ。全てがここで鳴らされるための音楽と曲であるかのような感じすらしていた。
しかしながらそこから「素晴らしい世界」へと繋がっていくことによるバンドが発する衝動たるや。上坂も身を沈めるようにしてギターを弾いているし、細川も何度も立ち上がって叫びながらドラムを叩いている。椅子ありというステージの特性ゆえにこの状況じゃなくてもモッシュやダイブはできない場所だけど、みんな本当はそうして楽しみたいのを我慢しているんだろうな。幕張メッセのREDLINEでのこの曲を演奏している時の映像は本当に凄かったもんな、と思っていると間奏で横山は
「今日、帰ったら暑いお風呂に入って、上がったら飲めない人でもビールでも飲んで忘れてください」
と言ってから佐藤のベースが鳴らされて最後のサビへと突入してさらなる衝動をバンドが放ち、それが声が出せなくても腕を上げたりしてそれが伝わっていることを観客が示していたが、こんな景色が見れたこの日のことを忘れられるわけがないのだ。寝落ちするくらいにビールを飲みまくったとしても。
「雨止んでる?」
と屋根の下に入り切らずにその奥の芝生エリアで見ている人たちに横山が問いかけると、確かに先程よりは雨が弱くはなっているのだが、まだ止んでいないのに横山が止んだと思い込んで喜んでいると、
「今日、楽屋にほとんど出演者がいなかったんですよ。普通ならフェスだと楽屋エリアで出演者が駄弁ったりしてるんだけど、全然そこにいなくて。みんなライブを見てた。それが嬉しくて。良いフェスを作れてるのかなって」
とステージ裏の景色を語る。その言葉を口にしているまさにその瞬間も、ステージ袖にはたくさんの出演者たちがKOTORIのライブを見ていた。それは個人的には京都大作戦のステージ袖の景色を思い出させた。出演者の誰もが主催バンドのために力を貸して、フェスを成功させようと思っている。いつかコロナが明けたらその袖にいる出演者たちが最後にステージにみんな出てこれるような景色がこのフェスでも見れたらと思う。
「雨が止んで窓の向こう
遠くに未来が見えたらもう
もうその手を離していい
君はもう何処へでも行ける」
という「羽」のフレーズは横山が雨が上がっていたことを観客に確認してから演奏されるのもわかるくらいに、その景色を想定してセトリに組み込んだのだろうけれど、雨バンドと言われるようになったからこそこうした曲のフレーズがよりドラマチックに響く。決して毎回ライブで雨が降るというのも悪いことではないのかもしれないと思った。
そんなライブの最後に演奏されたのは、
「今日はもう帰ろう
夢を見よう」
と、1日の終わりとその続きの日があることを歌うショートチューン「遠き山に陽は落ちて」。この状況じゃなかったら、この日のこの曲でどんな景色が見れたのだろうかということを考えていた。
アンコールで再びメンバーが登場すると、横山はツアーファイナルの「都内某所」になっていた会場が両国国技館であることを明かすと、明らかに客席からは驚きのリアクションが。
両国国技館自体は割とライブでも使われているし、サンボマスターやthe band apartや中村一義(100s)というロックシーンのアーティストもライブを行っているが、確かに今の若手バンドで敢えてあの場所でやろうとするバンドはいないだろうし、行ったことがない人がほとんどだと思う。だからこそ、
「これからも面白いことをやっていこうと思ってるんで!」
という言葉はこの東武動物公園でフェスをやったバンドとしての説得力に満ちている。
そしてバンドの中でも初期の曲であり、このバンドが若い頃に見ていた景色を歌にしたと思われる「4号線」はこんなフェスを、こんな日を作れるようになった今のKOTORIだからこそより響く。この曲を作った時にメンバーはこうした景色を思い描いていたのだろうか。
「また来年もTORI ROCK FESやるぞー!」
と言って最後にトドメとばかりに演奏されたのはショートチューン「kaze」。余韻が残るようでもあり、すぐに終わることで切り替えられるようでもあり。その終わり方もなかなかフェスの最後に演奏する曲としては実に珍しいものだ。そこにKOTORIだからこそのフェスの最後の瞬間が刻まれていた。
今年、スペシャ列伝ツアーでライブを見た時も書いたけれど、自分はそれまではKOTORIを割と「普通のバンド」だと思っていた。それはTHE NINTH APOLLOやsmall indies tableというレーベルにいる近くのバンドがことごとく凄いバンドたちだからなかなか突出して見えなかったというのもあるけれど、こうして主催フェスに行ってみると、全く普通のバンドではなかったと思い知る。普通のバンドだったら東武動物公園でこんなロックフェスは作れないどころかやろうとしないし、こんな凄いメンツを集めた後に全てを掻っ攫っていくライブをすることはできない。普通だと思っていたバンドは完全に唯一無二のバンドになっていた。
そんなバンドのフェスは来年もここでできたらと思う。このフェスがなかったら小学生の頃以来にこの場所に来ることなんてなかっただろうから。でも両国国技館のキャパでワンマンをするバンドとして、来年以降コロナ禍の状況が改善されていたら、もう今年のステージ規模では収まり切らない。なんならKOTORI自身が来年にはさらに大きなバンドになっているだろうし。
そうなった時にどうするのか。越谷により近いところとして、さいたまスーパーアリーナという選択肢だってあるし、もはやそこも射程内に入っていると言えるだろう。でもなんだか、またここでこうしてフェスを体感して、KOTORIのライブが見たいと思った。
紛れもなく「We Are The Future」であり、この日、この場所は素晴らしい世界だった。やっぱり、最高な時は気づいた時には終わっていたけれど、ビールでも飲んでも忘れないよ。
リハ.ラッキーストライク
1.We Are The Future
2.EVERGREEN
3.ジャズマスター
4.unity
5.Anywhere
6.RED
7.素晴らしい世界
8.羽
9.遠き山に陽は落ちて
encore
10.4号線
11.kaze
文 ソノダマン