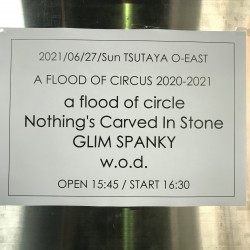まだコロナ禍になるなんて全く想像していなかった、2020年の1月。SUPER BEAVERは代々木体育館でツアーファイナルワンマンを行い、そこでアリーナも含めた新たなツアーの告知も行ったのだが、その告知の2ヶ月後あたりからライブというものがなくなってしまった。ひたすらにライブをして生きてきたSUPER BEAVERにとっては非常に大きなダメージであったことが渋谷龍太(ボーカル)のインタビューなどから語られているし、上杉研太(ベース)と藤原”33才”広明(ドラム)がコロナに感染したりもした。華々しい15周年イヤーは他のバンド以上に困難な年になってしまったと言っていいかもしれない。
しかしながら年明けの豊洲PITでのワンマンを皮切りに、バンドは今年は感染対策を施してツアーを行いながら、フェスやイベントにも軒並み出演し、制限がある中でも自分たちの生き方を取り戻してきた。そんな1年の集大成と言えるのが東名阪のアリーナツアーであり、この日のさいたまスーパーアリーナの2日目はツアーファイナルとなる。本来なら1年前に見れていたのがようやくやってきた、ビーバーのアリーナワンマンである。
検温と消毒を終えて場内に入ると、4日ぶりのさいたまスーパーアリーナはこの日は500LVの最上階客席まで使ったモードとなっており、こんなにたくさんの人が入るのか…という気持ちになる。
開演前には物販紹介ややたらライブ後にビールを飲みに行きたくなるような映像が流れる中、17時を少し過ぎた頃に場内が暗転すると、観客が一斉に立ち上がって身構えるようにしてステージの方を向く。SEもなしに暗闇の中で、前の方の客席から拍手が起こり始めたことで、メンバーがステージに現れたことがわかる。
ステージのライトが灯ると同時に高いセットになっている藤原がリズムを刻み始め、それに呼応してメンバー背後の立体的な造りのLEDに心電図かのような映像が映り、藤原がハイハットだけではない音を刻み、柳沢亮太のギターと上杉のベースがそこに重なった瞬間に心電図が波打つのが激しくなる。20枚くらいは使われているであろうLEDの豪華さも完全にアリーナ規模のものになっているが、そうしてメンバーが音を鳴らし始めた後で、いつものようにロックスターとしてのオーラと色気を纏ったフロントマンの渋谷がステージに登場し、おなじみの
「レペゼンジャパニーズポップミュージック、フロムライブハウス、SUPER BEAVERはじめます」
という口上から、まさに号砲というような炸裂音の特効とともに「ハイライト」が鳴らされる。LEDにはさりげなく曲を彩るような映像が流れるが、ステージ両サイドのスクリーンには演奏しているメンバーの顔がアップで映し出されている。それによって上杉の髪色の赤さなんかが遠くでもよくわかるのだが、渋谷はマイクスタンドで歌うというスタイルゆえ、ステージを左右に動く時もマイクスタンドごと持って移動し、その目線は400LVの上の方、つまりはステージから1番遠い席の人の方に向いており、そこに向かって手を振るような仕草を見せる。ビーバーのライブがどんなに規模が大きくなっても近くに感じられる所以と言えるような姿勢であり、一緒に歌うことができない観客たちが両腕を高く挙げると、その分俺たちが歌うとばかりにメンバーのコーラスが会場の隅々までしっかりと響く。渋谷はインタビューで
「観客が歌えなくなったから、メンバーがコーラスに手を抜けなくなった(笑)」
と言っていたが、そのメンバー全員で歌うコーラスにこそ、ビーバーのライブに来ているという感覚を得ることができる。1曲目にして早くもハイライトになるような光景が広がっていた。
「今日がここにいるあなたの、突破口になりますように」
と言って演奏された「突破口」では
「今をやめない やめない やめない」
という歌い出しでのドラムの連打で藤原の顔がスクリーンに映し出されるのだが、本当に「顔で叩く」というドラマーの最たる存在がこの男であると思うくらいに、思いっきり一振り一振りに感情を込めて音を鳴らしているというのがその表情からよくわかるのだが、
「正々堂々」「威風堂々」「正面突破」
という3つの4文字熟語のフレーズほどビーバーを一言で説明できる言葉もない。その全てを自分たちのスタイル、スタンスとして、何のギミックも、時代に合わせる器用さもなく、正々堂々、威風堂々、正面突破でこのさいたまスーパーアリーナでワンマンを2daysできるようなバンドになった。生き様がそのまま歌詞に、音楽になっているということが開始10分ですでにわかる。
藤原が細かくカウントを刻むというライブならではのイントロのアレンジに柳沢のオルタナなギターが重なっていくというオープニングは
「ロックスターは死んだ でも僕は生きてる」
というセンセーショナルな歌い出しで始まる「27」であるが、やはりファイナルということで漲っているのか、柳沢のコーラスが渋谷のボーカルに被るくらいに大きい。かと思えば上杉はステージ左右に伸びた花道の方へ歩いて行って演奏し、渋谷は台の上に立って堂々とした立ち振る舞いで歌う。
「27」も「突破口」も、「死なずに生きる」「そして続ける」という同じことを歌詞にしている。こうして続けて演奏されることによってそれがよくわかるのだが、そうして1人たりとも欠けることなくバンドを続けてきた結果としてこの日がある、このさいたまスーパーアリーナにたどり着いている。
スポーツ選手にしても余力を残して辞めるのもその人なりの引き際の美学かもしれないけれど、自分はボロボロになったとしても少しでも長く続けようとする方がカッコいいと思う。それはSUPER BEAVERの15年間の歴史を知れば知るほど、続けることの方が辞めることよりも圧倒的に難しいということがわかるからだ。まだその歴史の半分くらいしか共有できていないけれど、だからこそこれから先もずっと続いていて欲しいと思っている。
渋谷は改めて観客に挨拶しながら、
「150人規模のライブハウスすら10年間ソールドアウトしなかったバンドがさいたまスーパーアリーナに立てています。紛れもなく、あなたのおかげです」
とバンドの歴史を感じざるを得ない言葉で観客に感謝を告げ、この日のファイナルはWOWOWで生中継されているということで、カメラ目線で中継を見ている人にも挨拶するのだが、コロナ禍で配信ライブを行ったりした経験によって、会場に来てくれるからこそという考えにも少し変化があったようだ。それは来ることができない理由がある人とも向き合わざるを得ない時代になったことによる結果である。
そんな中、渋谷の歌い出しに合わせて柳沢、上杉、藤原の3人が手を叩き、観客もそれに合わせて両手を高く挙げて手を叩く「美しい日」ではその手を叩く客席の様子がLEDに映し出され、それが曲が進むにつれてステージ上のメンバーを映し出すように変化していく。そのメンバーはステージ上のカメラマンに目線を向けたりと、まさに「美しい日」でしかない幸せな景色が広がっていく。それは誰かにとって音楽やライブというものが、たかがそれくらいと言われるようなものであったとしても、ここにいた人にとっては揺るぎない事実だ。
この日はステージ左右だけでなく、正面にも花道が伸びていた。渋谷がそこに歩き出しながら歌い出したのは、ライブで聴くのが実に久しぶりな気がする「証明」。(いろんなライブのセトリを見てやっている日があったのは知っていたが)
「あなたの目に映る顔を見て 僕の知らない僕を知った」
というサビの締めのフレーズ含めて、ポップミュージックのクリシェと言えるような歌詞であるが、それすらもここまでボーカルとコーラスと演奏に感情を込めることによって、全く薄っぺらさを感じさせないどころか、これがSUPER BEAVERっていうバンドの素晴らしさなんだよなとすら思えるものになる。それは
「一人」
では全員のコーラスを重ねるけれど、
「独り」
では渋谷のみが歌うという押し引きの妙によるものでもあるけれど、それも間違いなくどうすれば曲が聴き手に響くのかということを極限まで考えた結果だろう。だから前述のサビの締めのフレーズがこの上なく「決まった」という感覚をいつも与えてくれるのだ。
そんなビーバーらしさは柳沢が観客に両腕を高く掲げさせる「青い春」からも感じられる。それは柳沢が書いたこの曲の歌詞を渋谷が「あまりに青過ぎる」という理由で一度は歌うのを拒んだというエピソードからもわかることであるが、それくらいに何の衒いも深読みのしようもないくらいにストレートかつ青い歌詞だ。でもそんな歌詞にここまで感情を込めることができる。ポップミュージックを自称しながらも、ロックバンドである、なんならラウドやパンクな要素をビーバーから感じることができるのはそうした部分だ。
コロナ禍になる前まではみんなで大合唱できていたこの曲を歌えないのはやはり少し寂しいところもあるけれど、それでもこの両手がいっぱいに伸びる景色は、ビーバーとあなたがいるからこそ見ることができるものである。ただそれだけでどうしようもなく感動してしまうのはここにいた人、ビーバーのライブを見たことがある人ならわかると思う。
そんな中、渋谷はこのツアーの大阪でのライブに新幹線で前日入りする際に盛大に車内でコーヒーをぶちまけてしまい、駅員たちと総勢7人で拭き取り作業を行い、その車両の乗客全員に謝ったというエピソードを語る。渋谷のことを知る人はその中にいなかったんだろうか、とも思うし、こんな派手な見た目の兄ちゃんがいきなり全力で謝ってきたらどう思うんだろうか、とも思う話である。
するとステージはそれまでの明るい輝きから一転して、炎が噴き上がるのがよくわかるくらいに薄暗い、ビーバーがずっと本拠にしてきた地下のライブハウスを思わせるような雰囲気に変えてしまうような演出(これもアリーナならではのものだ)とともに「mob」が演奏される。
メンバーのコーラスも他の曲に比べるとトーンもキーも低めであるが、いわゆるモブキャラというものはともすればライブの観客という存在と言えなくもない。どうしたって「その他大勢」と感じてしまうくらいにたくさんの人がいるからだ。でもこの日は全くそうは感じなかったのは、いつだって「あなた」と一対一で対峙してきたビーバーがこの日この規模になってもそのままでこちらに向き合っていたから。
「僕らずっと 個々にちゃんと 心持った 人間でいよう」
ビーバーのライブを見ると様々な感情が湧き上がってくる。その感情があることによって、そうした人間であることができているのがわかる。少なくともこの場では自分は「その他大勢」ではないんだと思える。
上杉のみを背後のLEDが真っ赤に照らして重いベースの音が鳴らされると、そんな噴き出した炎に加えて、スモークまでもがメンバーを覆い尽くすような勢いで噴き出されていくのは「正攻法」が演奏され、「突破口」ともどもこのバンドの生き様そのものとして
「正攻法でいい まっすぐでいい まっすぐがいい」
というフレーズが歌われる。この後に渋谷は
「エスカレーターやエレベーターがあることも知っている。でも階段を1段ずつ上がっていきたい」
と言っていたが、まさにその言葉通りの楽曲であるだけに、思考や精神がそのまま音になっているというこの日何度思ったかわからないことを再び思わせてくれるし、そうして1段ずつ登ることによって、目にできる景色を全て自分で見たいのだろう。エレベーターやエスカレーターに乗っていたら通り過ぎてしまうようなものさえも。渋谷は曲終わりで
「口だけの奴!」
など、自分たちの生き様に反するような人間に中指を立てていたが、それもまたそうした人の存在によってバンドが苦渋を舐めてきたからという経験によるものであり、ある意味ではそうした存在も反面教師的に今のバンドのスタンスに影響を及ぼしているのだろう。
渋谷は曲によってマイクスタンドだったりハンドマイクだったりを持ち替えるのだが、柳沢と上杉がそれぞれ上手と下手の花道へと展開する中、これはワンマンならではの選曲と言える「らしさ」では中央の花道へと歩きながら歌い、曲中にも関わらず、
「あなた自身に大きな拍手を!」
と言うと観客が自分自身に拍手を送るのだが、その拍手の大きさゆえにこの会場にいる人たちが自分に拍手を送ってくれているようにも、自分もまた他の人一人一人に拍手を送っているかのようにも思えた。それはやはりビーバーが観客を「たくさんの人」ではなく「一人」として向き合ってくれるバンドだからだ。もちろんこの日会場にはたくさんフォロワーの方が来ていたのもわかっているが、顔も名前も住んでる場所も年齢も全く知らない人だけれど、そんな人と互いにこうしてここに来たことを称え合っているような、そんな感覚が確かにあった。渋谷はそんな客席を花道の最先端に座り込むようにしてじっくり見ながら歌っていた。
渋谷がステージ中央に戻ってマイクスタンドを握りしめるようにすると、背面のLEDには曲の歌詞が全て映し出されていく。それは「愛しい人」のものであるのだが、こうして実際に渋谷が歌いながら歌詞を見ていると、ビックリするくらいに難しい単語がひとつも使われていない。なんなら子供でもわかるくらいの単語しかない。しかしその誰でもわかるような単語を使って、ビーバーにしか歌えない歌詞にする。
「パッと一言じゃ 言い表せないのが愛だ」
というサビのフレーズはその最たるものであり、それでも渋谷は自分に、自分以外のこの日の客席にいる1人1人に、
「愛してます!」
と言う。
「我々にとって、あなたが愛しい人です」
とも。そう言われると、この曲の聞こえ方がまた変わってくる。2人のラブソングではなく、バンドと観客の絆、約束の曲であるかのように。そしてこうしたバラードと言える曲がアリーナを包み込むくらいのスケールの歌唱力で歌われているというところに、ビーバーがこのキャパで当たり前のようにワンマンが出来る様になった理由と説得力を感じられる。
それは
「こういう状況になって音楽が鳴らせないのが辛いんじゃなくて、あなたに会えないのが何よりも辛かった」
という言葉を口にしてからの「人として」もそうだ。
「活動で示していく」
とも渋谷は言っていたが、
「信じ続けるしかないじゃないか
愛し続けるしかないじゃないか」
という歌詞もまたバンドと観客相互の気持ちそのものとして響き、
「馬鹿だねって言われたって
カッコ悪い人にはなりたくないじゃないか
人として 人として かっこよく生きていたいじゃないか」
というフレーズには改めて「カッコ悪い」「カッコいい」ということについて考えさせられる。
それは今の状況で言うならば、声を上げない、マスクをちゃんとする、規制退場のアナウンスが流れるまでその場でちゃんと待つという、コロナ禍のライブにおいて定められているルールをしっかり守ることだと自分は思っている。何を言おうと、それを守っていないと説得力なんか感じない、カッコ悪いな、って思ってしまうから。せめて自分が好きなバンドのライブに来ている時には、そのバンドに自分たちのファンはカッコ悪いって思わせたくない。そういう意味ではこの曲はきっとこれからも聴き手の状況、世の中の状況によって響き方が変わる曲になるんだと思う。
ビーバーは「現場至上主義」という言葉を掲げてこれまで活動してきた。それはこうしてライブをやる、会いに行くということが何よりも大事だということであるし、この日もその思いは全く変わっていないということを口にしていた。それがそのまま曲になったのが
「名前を呼ぶよ 名前を呼ぶよ あなたの意味を 僕らの意味を
名前を呼んでよ 会いに行くよ 命の意味だ 僕らの意味だ」
という、こうしてライブをしに行く、いろんな場所にいる「あなた」に会いに行くということをそのまま歌った「名前を呼ぶよ」であり、この後半になってメンバーのコーラスはさらに強さを増しているようにすら感じる。今はそうすることはできないけれど、代々木体育館までのように、観客もメンバーの名前を呼ぶようなことがまた出来る様になったら、と思う。代々木の時は藤原を呼ぶ声がやたらと物々しくて、渋谷に
「敵が来てるの?(笑)」
と言われたりしていたことすらも、こうして声が出せなくなったことによって、随分昔のことのように感じてしまう。
ここまでに演奏された曲からもわかる通りに、明らかにこの日は一つのバンドの集大成と言えるような、あらゆる意味で今のビーバーを形作っている曲ばかりが演奏されてきた。そんな中で最も古い、それこそ6〜7年前に自分がフェスのオープニングアクトで初めてビーバーのライブを見た時から演奏されていた曲である「東京流星群」が、ここで鳴らされるのを待っていたかのように、ステージ上に出現したミラーボールが輝く中で演奏される。観客が歌えない分、これまでの合唱パートを担う柳沢、上杉、藤原の歌唱にもこの上ないくらいの気合いを感じるが、自分が初めて見た時にはビーバーがこんな規模まで来るなんて全く思っていなかった。何なら「普通のバンドだな」くらいに思っていた。それは今なら普通じゃなくて「普遍」だったということがよくわかるし、結局ビーバーはその頃から変わらないままで、真っ直ぐに、正攻法でここまで来ることができた。そんなことを思い出していたからか、この日のミラーボールによる流星群の輝きは本当に美しかった。
そしてここでせっかくなので、渋谷以外の3人からも一言という時間が設けられるのだが、基本的には上杉も柳沢も来てくれたあなたへの感謝を告げるというのは変わらないし、そうした言葉が本当に真面目な人だなと思う。藤原だけは
「じゃあドラムの人」
と適当に紹介されていたのが面白かったけれども。
そんな3人の後に渋谷は、
「これからもたくさんお世話になります!こちらもたくさんお世話します!あなたがいるから生きてて良かったと思ってます。あなたにとっての生きてて良かったになりたい」
と、自分の、自分と同じようにこのバンドの音楽と生き様、メッセージに惹かれてここに来た1人1人の思いを背負うようにして、柳沢がキャッチーかつ耳に入るだけで楽しくなるようなイントロのギターを奏でる「予感」で花道を歩き出しながら、
「ライブハウスで見たいですか?やりましょう。ホールでも見たいですか?ホールでもやりましょう。またアリーナでも見たいですか?またできるように精進します!」
と、これからもどんな場所でもライブをやっていくという意思を伝えた。だからこそ、
「楽しい予感のする方へ」
というフレーズがより説得力を持つ。これから先ももっともっと楽しいことをやってくれることをバンドが約束してくれているからだ。渋谷は
「声は出しちゃダメですよ!」
と言いながらも煽るように客席にマイクを向けていたが、それはまた我々が声を出せるようになった時もこうして変わらないパフォーマンスをするためでもあり、どこか出せなくても声を心から引き出そうとしているかのようにも見えた。それはもちろんWOWOWで画面越しに見ている人の声すらも。
この日、何度渋谷は観客に
「愛してます!」
と言っただろうか。その「愛してます!」がそのまま曲となって客席に放たれていくのが、
「青臭いとか言われようと、ロックバンドが「愛してる」って目の前の人に言えないでどうするんだと思ってます」
と言って演奏された「アイラヴユー」。
「今僕らに 必要なのは 想う気持ち 想像力
今あなたに 必要なのは 想われてる その実感」
という歌詞からして、コロナ禍において一層顕著になってしまったように感じる人と人との分断も、想像力や実感、何よりもこのバンドの音楽をもってして乗り越えていく、分かり合えなくても認め合うという人の温かさがまだ確かに存在していることを感じさせてくれる。
そして最後に放たれたのはやはり今やビーバーのライブの最後の曲として完全に定着した感すらある新たな名曲「さよなら絶望」。
思えば、今年は絶望することばかりだった。「仕方ない」と思っていた去年から何も前に進んでないんじゃないか、むしろより音楽やライブを必要としていない人の言葉に精神がやられそうになる1年だった。男鹿フェス、ミリオンロック、ロッキン、ラブシャ…ビーバーのライブが見れるはずだったフェスは今年もことごとく行けなくなってしまった。
そんな年になってしまったからこそ、この曲は間違いなくこの2021年を代表する曲になった。それは自分が勝手にそうして味わった絶望にこの曲で別れを告げようとしていたからなのかもしれないが、今はメンバーだけで歌っているこの曲を我々が思いっきり歌えるようになった時に、本当の意味で絶望とさよならできるのかもしれない。
「さよなら絶望 絶望 何のための爆音だ
抗ってやろうぜ 抗ってやろうぜ 抗ってやろうぜ
涙目でもいい さよなら絶望」
明らかにさらに出力を上げたバンドサウンドによって爆音で鳴らされるこの曲を聴きながら、どれだけ絶望したとしても抗ってやろうと思った。それは、抗わないとまたこのバンドのライブすら見れない、この曲をこうしてライブで聴けないようになってしまうかもしれないから。それは絶対に嫌だから、音楽で抗っていく。それが生きる力に、理由になっている。それはビーバーのような、その理由になってくれるバンドがいてくれるからだ。
アンコール待ちの時間にスクリーンにいきなり
「緊急告知」
という文字が出現すると、12月にアルバム「東京」のリリースと、それに伴う全国のホールツアーの開催が発表された。それは去年の年明けの代々木体育館の時に次のツアーが発表された時のことを否が応でも思い出し、今回こそは無事に全公演開催されるように、とも思うが、初日が学生時代に行ったことがある千葉は松戸森のホールであるということに驚きすぎて、他の日程が全く入ってこなかった。V系バンドの方々や氷川きよし、さらには時にはスピッツも来るという場所であるが、あの会場でビーバーのライブを見れたら色んな感情が爆発しそうだ。帰りにボーリングをしたりと、色んな思い出がある。僕らは大人になったんだ。
そんな告知映像の後に再び4人がステージに戻ってくると、渋谷は長い髪を結いている。それがどこかより男らしさを感じさせる姿になっているのだが、
「楽しい予定をたくさん用意してます」
と言ったように、ビーバーはツアーが終わるといつもさらにその次をちゃんと発表してくれる。それは楽しい予感を、会える日を、約束を、生きる理由を常に用意してくれているということであるが、そもそもこのツアーがこの日で終わっても今月はまだライブが9本も控えているというあたりがさすがのライブバンド過ぎてビックリする。もう休むという概念はこのバンドにはないようだ。休むくらいならよりいろんな場所に、いろんな人に会いに行く。実にこのバンドらしい生き方だ。
そうした告知の後に演奏された、正真正銘このツアー最後の曲は「時代」。渋谷は歌い出しの
「わたしは あなたの何ですか?
あなたは わたしの光です」
というフレーズをマイクを通さずに歌う。それでもハッキリと聞こえる。その声量に心底驚きながら、
「生きている 生きている それぞれの場所で
時代とはあなただ」
と歌う。ああ、もしかしたらこうしてライブに足を運ぶことによって、ビーバーが重ねる時代を、歴史を自分が、それぞれ1人1人が作っているのかもしれない。そんな存在になれていたらそんなに嬉しいことはないし、この曲のコーラスは今はメンバーだけでしか歌っていないけれど、きっと観客1人1人の声が何万にもなって重なればもっと映える。もっと凄い景色を見せてくれるはず。それはこうしたアリーナでもそうであるし、何ならそのさらに先にあるであろうスタジアムやドームならよりそう感じられるだろうと思う。
「もっと良い景色を見せてあげます。我々にも見せてください!」
と渋谷は言っていた。このバンドでそれを見に行きたい。きっとその時代が必ずくる。その時にはこの曲のコーラスだって歌えるようになってるはず。もうその景色は脳内に浮かんでいる。
演奏が終わると最後にステージに残った藤原があらゆる方向の客席に投げキスを飛ばすようにして、クスッとするような笑いを起こしながらステージから去っていった。藤原自身コロナに感染してしまったり、その前にも体調不良でサポートドラマーにライブを託したりしてきた。それだけにこのツアーをこの状況の中で回りきったことによって、解放された部分もあるんだろうな、と思うくらいに晴れやかな表情だった。
会場に行く時もそうだったが、帰りも親子でライブに来ているであろう人たちを見かけた。親は40〜50代くらいだろうか。子供は中学生くらい。どちらが先にビーバーに出会ったのかはわからないし、どうやって共有したのかも知る由もないけれど、ライブハウスだけでやるバンドじゃなくて、アリーナでもできるバンドだからこそそうした人たちが一緒に来ることができる。その光景だけでなんだかグッと込み上げてくるものがある。
それは「親がライブに行くなと言っている」という話もコロナ禍になってからよく耳にした。そんな世の中になっても親子でライブに行くことができるバンドがいるということの頼もしさたるや。自分はどんなに好きだったとしても親と一緒にビーバーのライブには行けないけれど。親の横で泣いている顔は見られたくないから。
1.ハイライト
2.突破口
3.27
4.美しい日
5.証明
6.青い春
7.mob
8.正攻法
9.らしさ
10.愛しい人
11.人として
12.名前を呼ぶよ
13.東京流星群
14.予感
15.アイラヴユー
16.さよなら絶望
encore
17.時代
文 ソノダマン


![[Alexandros] 「12/26直前の年末パーティー」 〜1部・2部制〜 Zepp Tokyo 2021.12.17 [Alexandros] 「12/26直前の年末パーティー」 〜1部・2部制〜 Zepp Tokyo 2021.12.17](https://moretzmusic.com/wp-content/uploads/2022/07/217-250x250.jpeg)