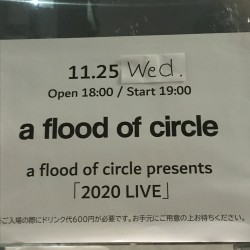昨年は11月に開催されたBAYCAMPでライブを見ることができたとはいえ、各地で対バン(自分がチケットを取っていた川崎はKANA-BOONだった)を迎えたツアーなども含めて、ソーシャルディスタンスを求められるようになったコロナ禍の状況になってしまったことによって、これまでに自らの抱える衝動をステージ上でぶち撒けるというスタンスのライブをしてきたtetoにとってはなかなか厳しい一年だったことは間違いない。
そんな中であっても、新たに東西の野音でワンマンを開催。この日の日比谷野外大音楽堂はtetoにとって初の野音ワンマンとなる。椅子がある会場でのライブというのもバンドのこれまでのスタンスからするとなかなか意外な選択であったが、これはある意味ではこの状況特有のものなのかもしれない。
昨年にもコロナ禍であってもSPECIAL OTHERSがこの野音でワンマンをやったのを観に来たので、今年初野音であっても久々という感覚はないが、この日は降水確率100%ということで、雨の降る中での野音というのは実に久しぶりであるし、初野音ワンマンが雨というのもある意味tetoは持っているなとも思う。
17時30分開場、18時30分開演という野音にしては遅めの開始時間(野音は野外という性質から音出しの時間制限がある)であり、検温と消毒をしてから場内に入ると、1席ずつ赤いテープで座ってはいけない席が表示されてはあるけれども、整理番号順の席指定というのも野音にしては珍しい。
それまでは小雨だった雨足が少し強まってきた18時15分になると、おなじみのAT FIELDのP青木がステージに登場しての前説。
「ライブを守っていくためにルールの遵守を」
というのは主催するBAYCAMPでも口にしてきたことであるが、
「最高の野音日和ですね」
という言葉には失笑せざるを得ないし、野外でのBAYCAMPがやたら雨が降ってきた歴史を持っているのも、ある意味ではこの男が雨男なんじゃないかとすら思えてくる。
18時30分になると、それまで流れていたBGMが止まり、おなじみのNirvana「Sliver」という野音に似つかわしくないような轟音オルタナサウンドが流れる。雨が降っていてこの時間ということもあってか、暗転という概念がないくらいにすでにあたりは暗くなっているが、バンド名が書かれたフラッグが背面に張られたステージは照明と電飾によってより一層、光を放つように輝いている。
こんな気候、天候でも半袖Tシャツに短パンという、いついかなるどんな状況のライブであっても出で立ちが変わらないんじゃないかとすら思える福田裕介(ドラム)、珍しく客席を煽るような仕草をしながら歩いてきた佐藤健一郎、髪色も赤ならば服装も赤のジャージという、コンビニの前にいそうなヤンキーのような山崎陸(ギター)、そしてコートを羽織った小池貞利(ボーカル&ギター)の4人がステージに登場すると、いきなり小池がステージ上でもんどり打つようにして動き回りながら歌う「高層ビルと人工衛星」からスタート。
この日比谷野音は隣の駅がオフィス街である霞が関(なんなら野音に1番近いのはそっち)なこともあり、ステージの奥にもたくさんの高層ビルが聳えたっている。日々そこで働いている人たちはこのバンドのライブや、雨の中でそれを見る我々のことを嘲笑っているのだろうか。そんなことが頭に浮かぶのはこの曲をこの会場で演奏している時くらいだろう。
実に久しぶりのワンマン、さらにはメンバー自身も意識を持っているであろう歴史ある日比谷野音でのライブということで、果たしてどんなセトリを組んでくるのだろうか?とも思っていたのだが、小池が暴れ過ぎて歌えていないサビを、叫ぶようにして歌う山崎と、あくまで冷静に高音を重ねる佐藤というコーラスを務める2人のキャラがこの瞬間だけでもわかる「暖かい都会から」、昨年配信リリースされたという意味では最新と言っていい「もしもし?もしもさぁ」、福田のドラムアレンジによって進化を遂げ、観客が椅子があってもその場で飛び跳ねまくりながら腕を上げる「Pain Pain Pain」と、新旧の、これぞtetoというイメージの強い性急なギターロックが続く。この序盤だけでこれだけキラーチューンを連発してくるというあたりに、この後にどんな曲たちが聴けるんだろうか?とワクワクしてくる。なぜか動きが激しいわけではない佐藤のマイクスタンドが倒れていたが、まだこの段階では雨はそこまで強くはなかった。
小池「2年ぶりのワンマンで、初めての日比谷野音で雨ですよ」
山崎「しかも雨は今日だけ(笑)俺たちがライブ終わったら止むらしい(笑)」
小池「なんかそれって試されてる感ありますよね。「雨でもtetoやれんのか」って。やれますよ(大きな拍手が起こる)
この雨でデイジーっていう花を咲かせてみせますよ」
と、自身の雨の引き寄せっぷりを自虐的に語るも、だからといってバンドがやることは変わらないとばかりに「ねぇねぇデイジー」で気合いを新たにすると、福田による4つ打ちのリズムが雨に打たれながらも心地よく体を踊らせる「ラストワルツ」と続くのだが、昨年配信リリースされた、レイドバック気味のサウンドにバカンス的なフレーズが並びながら最後には
「きっと今年の夏はいつか取り返すから」
と、昨年の何も出来なかった夏だからこそ生まれた「夏百物語」ではローディーが演奏中の山崎の隣に来て耳打ちするように話をしている。その会話の後にアンプをいじったりして、山崎のギターがよりクリアに聴こえるようになっただけに、前半はまだ野外でのライブのサウンドの作り方を模索しながら演奏していた部分もあったのだろう。
すると小池が、
「新曲やります。たくさん新曲あります。まずはこの日のテーマソング!」
と言って演奏された新曲「光とロマン」は、なるほど「LIGHT ON EARTH」というライブタイトルからしてもこの日のテーマというのもわかるが、サウンド自体はタイトルとは裏腹にオルタナ色が強い曲。
さらには続け様に
「俺もあんたらも止まらない、止められない」
と言って演奏された新曲「止められない」はそのタイトルと言葉通りの性急なギターロック。それはtetoのシグネチャー的なものでもあるのだが、去年の配信曲も含めてこうしたタイプの曲は久しぶりな感じがする。
そして新曲連発の最後の曲はタイトルこそわからないが、どこかマーチ的なリズムで、tetoのメロディの美しさが最大限に発揮された、一聴しただけで新たな名曲が生まれたことがわかる曲。
「○○病棟の女の子に向けて書いたラブレター」
的なことを言ってから演奏されただけに、おそらくは明確に歌いたい相手や景色が小池の中には描けているのだろうけれど、
「居場所はあるけど 居るべき場所がわからない」
というtetoらしいキラーフレーズも随所に含みながら、どこか聴き手に力を与えてくれるような感覚があった。
それは「強く背中を押す」とか「手を取って一緒に走りだす」というような力の与え方ではない。むしろtetoのメンバー(特に小池)はそうしたものを「うぜぇ」と一蹴するようなタイプの人間だ。
だからこそきっとtetoを聴いている人もそうした、わかりやすすぎる応援ソングみたいなものを聴いて力が湧くような人たちではないはず。でもこうしたtetoの曲を聴くことによって、部屋で寝転がってコーラでも飲みながら「まぁ生きてるからいいか」と思えるような、そんな力の与えられ方。それはポジティブには感じられないかもしれないけれど、決してネガティブでもなければ絶望しているわけでもない。
そんな新曲祭りから一転して、
「今日、来れなかった母親に捧げます」
と小池が言って演奏されたのは、
「副業であかぎれた母の手」
と、どこかそうした心の中の懐かしい部分を呼び起こしてくれるような「忘れた」。
2年前のSWEET LOVE SHOWERでも小池はアル中で記憶がなくなってきているという自身の祖父について話していた。
「もう家族のことも覚えてないけれど、tetoの曲を聴くと「貞くんは本当に良い歌を作るね」って言ってくれる」
と。「忘れた」ではそんな家族の辛い記憶なども歌詞として綴られているが、そうした言葉の端々からはちゃんと彼が家族から愛を注いでもらってきたんだなということがわかるし、その家族のくれた優しさを小池自身がtetoのファンに分け与えているような。
tetoには「忘れた」のようなテンポの、じっくりと浸るようなタイプの曲もあるために中盤はそうしたブロックかな?とも思ったのだが、小池がギターを下ろしてハンドマイクで歌い、山崎がステージ前にスライディングしてきてギターを弾く「this is」はむしろそうしたタイプとは真逆の、みんなで大合唱する性急な曲。今はこの曲を我々が歌うことはできないが、
「fuck forever」
と大きな声で歌うことの気持ち良さを今までのライブで体験してきているし、
「これは俺たちとあなた達のための歌です!」
と小池も曲中に叫んでいただけに、またその全員で大合唱できる日が来ることを願っているし、絶対にその日が来ると信じている。小池はハンドマイクであることをいいことに、マイクのコードで縄跳びをしたりしていたけれど。
「俺は「正しい」か「正しくないか」なんてどうでもいい。「面白い」か「面白くないか」だけ」
と言って、アルバム「超現実至上主義宣言」のバージョンや弾き語りよりもはるかに速いテンポでの小池の歌とバンドの演奏というまたしても新しいアレンジになった「光るまち」では
「あのライブハウスは無くなった 僕らも会うことは無くなった
それでも今もこれからもこうして」
というコロナ禍になる前に書かれたのに、コロナ禍のこの状況を歌っているとしか思えない歌詞が、今ここにいてtetoのライブを見れているということがどれだけ幸せなことなのかということを実感させてくれる。そしてそれは、これからもこうして何回でも会って、何回でも体験したいことなのだ。
小池は曲最後には
「どうする?」
と答えることができないことをわかっていながらも観客に対して問いかけ、思いっきり溜めに溜めてから、
「終電はもう逃そう」
と歌った。
アレンジからしても銀杏BOYZの「人間」に影響を受けていることは間違いない曲であるが、決して速いテンポでもなければ盛り上がる曲でもない。でもそんな曲でも観客は拳を上げてバンドの演奏に応える。辺りは真っ暗な中で光を放つこのステージは、まさにここが「光るまち」そのもののようだ。その様を見ていたら、なんだか15年前にこの日比谷野音で銀杏BOYZのワンマンを見た時のことを思い出した。あれはまだ夏の終わりにさらわれるような秋の季節だった。
それはまさにまだ少年だった頃の夢を見ているかのような感覚でもあったのだが、とびっきりの美しいメロディでもって
「夢見る時代ならもう過ぎた
それでももう一度見た夢が心地良くて
裸のままあなたにただただ逢いたくて
きっともう一度だけ僕等も輝かしい時間があるのさ」
と歌う「夢見心地で」がまさに夢見るような時代を過ぎて大人になってしまっても、その歌詞のとおりに今ここでこうしてもう一度夢を見ているんじゃないかと思わせてくれる。
もちろん銀杏BOYZとtetoは違うバンドだけれど、その衝動を炸裂させるようなライブと、ノイジーであるけれどメロディが美しいという共通点は、今でも自分がそうしたバンドにこそ心を揺さぶられているという変わりなきことに気づかせてくれるし、それはCRYMYのような後発バンドにも受け継がれてきているものでもあると思う。
そうしたノイジーとキャッチーの狭間にあるものをサイケデリックさをまぶした音像で見せてくれるのは「溶けた銃口」であるが、
「置いてきたあの季節や光景や、
あの星は時代を超えて遊泳し続けているんだろう」
というサビの歌詞もまた「光るまち」同様にコロナ禍以前に書かれたものであるのにコロナ禍のことを描いたことであるかのように響く。この曲でのそれはある意味では「夏百物語」に通じるものであるが、これからはそうした置いてきた季節や光景が生まれることなく、常に今ここでそれを感じられることを願って止まない。
tetoがこの日比谷野音でワンマンをやるとニュースが出た時に「あそこで聴いてみたいな」と思った曲がある。それが「蜩」だ。サウンド的にはtetoならではの性急なギターロックであるが、この日比谷野音では夏や秋にはライブ中、MCや曲間で虫の鳴き声が聴こえる。それが蜩のものであるかどうかはわからないし、この時期はまだそれを聴くことはできないが、続く「9月になること」も含めて、またいつか秋にこの会場でtetoがワンマンをやるのを見たい。もちろんその時には虫の鳴き声が聴こえるくらいに晴れていて欲しいと思うくらいにこの終盤になって雨はより激しさを増していた。
「新しいライブの形みたいな、俺たちも去年配信ライブやったりしたけど、もうそういうの飽きた(笑)」
と、実にtetoらしい理由でこうしてリアルに観客を前にしてライブをしていることが1番飽きないし楽しいということを逆説的に曲としても伝えるのが「手」。
最後にtetoがワンマンをやったつい2年前までは、こうしてライブをやって生きていくことが、馬鹿馬鹿しいくらいに平坦な日常だった。でもそれがコロナ禍によってそう思えない、特別過ぎるものになってしまった。
「でもあなたの、あなたの手がいつもあたたかかったから
目指した明日、明後日もわかってもらえるよう歩くよ」
という歌詞から感じられる温かさと優しさ。こうしてリアルなライブをやり続けるしかないし、それを見てわかってもらうしかない。そんなtetoというバンドの生き様がこの曲には集約されている。雨は冷たく寒いけれど、この曲が聴けたことで心の中は確かに暖かくなっている。
「いつまでもドキドキしていたい!」
と、今やレギュラーになっているBAYCAMPのメッセージにも通じることを小池が口にしてから演奏された「invisible」で
「焦がれる程に恋してみたい
溢れる程に愛してみたい
透明のままであれば叶うことはないのでしょう そうか」
という真っ直ぐなメッセージが響き渡ると、
「魅了したいされたいされ続けていたい、し続けていたいよ
あのトワイライトのように
何度も何度も何度も何度でも輝いて生きてたいよ
あのトワイライトのように 僕は」
というフレーズが今もtetoというバンドの活動指針になっているんじゃないかというくらいに、我々はtetoに魅了され続けているし、バンドが輝いて生きているということがステージに立って演奏している姿を見ているだけでわかる「あのトワイライト」と、ライブがいよいよクライマックスに向かっているのがわかるが、小池は終盤になるにつれてマイクスタンドを定位置よりも前に持っていって、あえて自身が雨に打たれながら歌う位置に移動している。ああ、これがtetoのライブなんだよなということを、その後先考えない衝動的なパフォーマンスによって思い出させてくれる。
1曲がそこまで長くはなく、ライブのテンポも実に良いバンドとはいえ、ここまでですでに20曲。それでもまだ終わる気配なく、
「今日はこの曲を歌いに来ました!」
と言って演奏された「拝啓」ではステージの電飾が「teto」という文字を映し出し、小池はステージ端まで走って行ったりしながらも、
「拝啓 今まで出会えた人達へ
刹那的な生き方、眩しさなど求めていないから
浅くていいから息をし続けてくれないか」
という、おそらくこの日最も伝えたかったであろうフレーズをしっかりと歌う。
今まで出会った人達の中にはもう二度と会いたくないと思うような人だって誰にもいると思うし、バンド稼業をやってれば一層そういう大人もたくさんいたことだろうと思う。それでも、そんな人にすら「息をし続けていてくれないか」(=生きていてくれないか)と歌う。
そんな会いたくないような人であっても、その人がいたからこそ今の自分がいて、今の人生を生きれている、そんなことをこの曲は改めて教えてくれる。1人で高音コーラスを務める佐藤の貢献度の高さも見逃せないこの曲のポイントだ。
そして雨足が強まる中、いよいよ最後の曲へ。
「君に嫌われないようにと
なんとなく言っちゃった夢が
今では本当になってさ
なんだか笑える話だよな
君に気に入られるようにと
なんとなく始めたバンドは
今でも楽しくやれててさ
たまには遊びにでもおいでよ」
という歌詞が今のtetoというバンドのリアルを伝える「LIFE」だ。
「今でも楽しくやれててさ」
と歌うこの曲を演奏している限りは、tetoは大丈夫だと思うし、その姿から得体の知れない力をもらえるこちら側からしたら、たまにはどころかできる限りたくさん遊びに来たいのだ。去年はその機会がほとんどなかったけれど、今年からはまたいろんな場所に会いに行けますように。この曲を最後に聴けたことで、2年前リリースの「超現実至上主義宣言」の先へ改めてバンドが歩みを進められるような気がした。
演奏が終わってステージから去る際に山崎はステージ前にできた水溜りにヘッドスライディングしていたが、その見事な滑りっぷりはかつて千葉ロッテの試合が雨で中止になると毎回グラウンドに出てきて水溜りにヘッドスライディングしていた、諸積兼司の姿を思い出させてくれた。
アンコールではワンマンではおなじみの福田が先に出てきて1人でのMC。金髪になったことを改めて告げながら、
「前に来ると結構雨きますね。ドラムは全く濡れないんで、いつも通りに楽しく叩かせてもらいました」
と、話している最中に3人も「もういい」とばかりにステージに登場。
小池は髪が赤くなった山崎、結婚した佐藤に触れるも、福田には「何もない」とバッサリ切り捨てながら、
「本当はまだ10曲でも20曲でもやりたいんですけど、道端で財布を失くしたんで、紛失届出しに行かなきゃいけないから2曲だけで」
という、「ライブ前に行っておけよ!」という理由で演奏されたのは実に久しぶりに聴いた感じがする「My I My」。
「毎日ドキドキしたいね 毎日サボってたいね
会いに行けばだなんてそんな簡単に言わないでよね
毎日恋を更新したいね 毎日遊んでたいね
やけに沈みかける夕日が無駄に染みていくよね
あぁそっか時が経つってこんな感覚だったのなら
1日1日にいちいち遊ばれたらキリないね」
という韻を含んだ言葉遊びが印象的な曲であるが、毎日ドキドキしたいというのはバンドとして、個人として小池の今も変わらない心境そのものであるだけに、こうして初の野音という舞台のアンコールでも歌うことができるのだろう。
そして小池は
「さっきも言ったけど、俺には正しいか正しくないかはわからない。面白いか面白くないかだけ。だから正しいかどうかはみんなが決めればいいと思うんだけど、いろんなバンドがツアーをまたやるようになってるのも正しいのかどうかは俺にはわからない」
と、改めて今のコロナ禍だからこそ考えざるを得ない、定義せざるを得ない自身の心境を口にすると、
「tetoじゃないんですよ、新しい風を吹かせるのは。あなた達なんです!」
と言って、残っている体力・気力を全てぶち撒けるように演奏された「新しい風」。この日の野音には冷たいけれど、また新しく何かが始まっていくような予感を感じさせる風が吹いていた。それを「何か」ではなくて確かなものとするために、小池はステージから去った後に再び現れて
「またツアー再開します!」
と宣言し、山崎はまたも水溜りに向かってヘッドスライディングした。今度はさっきよりも滑らなかったけれど、雨だからこそできるパフォーマンスをするという山崎のサービス精神と機転の速さを感じさせてくれたのだった。
ツアー再開と、新曲の連発からはtetoがここからまた新しい季節に向かっていくということを感じさせるし、ライブができない中でもバンドとしての活動は止まっていなかったということが伝わる。
コロナ禍になる前に作った曲がコロナ禍の今にこんなに響いてくるということは、コロナ禍に作った曲はその後の時代に聴いた時にも響く普遍性を持つことになるということだ。そんな時代にもこうしてtetoがライブをしてくれているように。
去年もこの日比谷野音でライブを見ているとはいえ、野外ライブ自体がめっきり減ってしまった。自分はあまり雨に打たれるライブの機会はそう多くはないし、日比谷野音で雨が降ったライブもあんまり経験がない。
それでも野外フェスでは何度か雨、それも豪雨に見舞われたこともあるし、そうした状況ではライブを見ることは心を折られることも多い。ライブどころじゃなくなってしまうというか。
でもこの日のライブはどんなに雨が降って、ライブ後にスマホを打つ手が震えるくらいに寒くても、心が折れたり、集中力が途切れたりすることは全くなかった。それはtetoがそういうライブをしてくれるようなバンドだったからだ。
それは小池が客席に飛び込んだりして、観客もダイブをしたりという衝動の分け合い方をしてきたtetoが、このコロナ禍の状況や椅子がある会場でも変わらないライブができるバンドであるということを証明していた。
「この状況でもtetoやれんのか」
という音楽の神からの問いに、tetoは自らのパフォーマンスでもって答えたのだ。数々の伝説を生み出してきた日比谷野音の歴史に、また新しい伝説が加わった一夜となったのだ。
1.高層ビルと人工衛星
2.暖かい都会から
3.もしもし?もしもさぁ
4.Pain Pain Pain
5.ねぇねぇデイジー
6.ラストワルツ
7.夏百物語
8.光とロマン (新曲)
9.止められない (新曲)
10.新曲
11.忘れた
12.this is
13.光るまち
14.夢見心地で
15.溶けた銃口
16.蜩
17.9月になること
18.手
19.invisible
20.あのトワイライト
21.拝啓
22.LIFE
encore
23.My I My
24.新しい風
文 ソノダマン