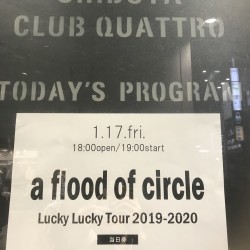昨年の秋にホールツアーを行ったとはいえ、これまでのベテランバンドらしからぬ、リリースを引っ提げてのものやリリースがなくてもツアー三昧だったGRAPEVINEからしたらやはりめっきりライブがなくなってしまったこの1年間だった。
そんな中、緊急事態宣言が発令された東京、しかも政治の中枢とも言える霞ヶ関に隣接した日比谷野音でのワンマンは2021年のGRAPEVINEの初ライブであり、この会場でワンマンを行うのは実に6年ぶり。
そうしたライブ自体の希少さや会場の特別さ(ホールとかでワンマンやるとだいたい即完する)からか、今回のライブはキャパ100%で開催された、およそ3000人という野音の収容人数をフルに使ったものであるが、今回も即完でチケットを取れなかったという理由で行けないという人も多々いたようである。
予報では若干の雨という懸念もあったが、実に野音日和と言っていいような青い空が広がる中、検温と消毒を経てから客席に入ると、確かに常設の椅子にフルで人が座っているのだが、こうした状況を受けて行くのをやめたという人もいて、席が結構空いたりしてるんじゃないかとも思ったが、ほとんどそういうこともなく、会場は満員と言っていい状態。どんな状況になろうともGRAPEVINEのライブは見たい。昨年のホールツアーもそうだったが、観客のそうした強い意志をこの時点で感じることができる。
開演時間の17時を少し過ぎた頃、特に何のSEもなしにフラッとという形容が実に似合う歩調でメンバー5人が登場。(アー写に写ったり写らなかったりと基準がよくわからないが、ベースの金戸覚とキーボードetc.の高野勲はもはやメンバーの人数にカウントしていい存在だろう)
田中和将(ボーカル&ギター)がおなじみの揉み手のようにした手を頭上に掲げ、あらゆる方向の観客に来てくれたことの挨拶とばかりに頭を下げると、亀井享(ドラム)と西川弘剛(ギター)が静かにイントロに連なる音を奏で始める。
GRAPEVINEのライブはホールなどだと終始座って見ている人も多いし、バンドサイドも「好きなように好きな形で見てくれ」というスタンスだ。(だからこそ「寝てていい」とも田中は言う)
しかしながらその奏で始めた音が明らかに「FLY」のイントロであることがわかると前の方の席の人から徐々に立ち上がっていく。立ち上がって、腕を空に向けて高く掲げて日比谷野音でのGRAPEVINEのライブに浸りたい。そんな思いにさせるには最適のオープニングナンバーで、田中の癖のあるボーカルもバンドの力強いサウンドも開放感たっぷりに青空に溶け合っていく。
かと思えば同名タイトルの小説から着想を得た、GRAPEVINEの不穏なロックサウンドを代表する1曲と言ってもいい「スレドニ・ヴァシュター」、と思ったらこうした野外の会場で休みの日に聴けるのが世の中の喧騒と今自分たちがいる場所が切り離されて、争いや諍いや不安などのない特別な空間の中にいるかのような気分にさせてくれる「放浪フリーク」と、野音に合わせたかのような選曲なのかと思ったら、いやそうじゃないかもしれない、と序盤からこちらを翻弄してくるというのはさすが自他共に認める天邪鬼バンドの本領発揮である。
「雨降らなそうやね。新曲とかもやっていくんで、耳かっぽじって聴くように」
と、晴れたことへの嬉しさを感じさせるが、それはメンバーの共通認識なのか、西川も自身のサウンドを構築するようにしながらギターを弾いていても、その表情からは笑顔であることがよくわかる。
「我々は「行くぞー!」とかみんなで歌うみたいな不謹慎なことをするバンドじゃありませんので(笑)
良い演奏だと思ったらとびきりの拍手で、マスクの下の笑顔で示してください」
とも言っていたが、マスクをしていないが故にメンバーの笑顔はハッキリとわかる。
亀井がドラムパッドを叩くことによって同期のサウンドも取り入れたサウンドに歌謡性を感じるメロディが融合することによって、一部のファンから強い人気を誇る「Darling from hell」から、近年は夏フェスに出演した時にもよく演奏されるようになったので、天邪鬼なメンバーも曲の役割を理解するようになったのか、この野音でのライブが決まった時から是非ここで聴きたいと思っていた「風待ち」の美しくも優しいメロディが穏やかに野音に広がっていく。
半袖Tシャツで見ている人もいるくらいの陽気。夏というにはまだ早い時期だけれど、
「夏の感じがしました」
と言うにはちょうどいい季節。
2001年にシングルリリースされているので、もう20年前。まだ自分が子供だった頃からよく聴いていた曲であるが、
「あれ?いつの間にこんなに疲れたのかなあ
まだいけるつもり ちょっとはつらい
また花は咲き 枯れました
たまにはあなたの顔 見れないもんかなあ」
というサビの歌詞は大人になった今こそ沁みるし、肉体的というよりも精神的に疲労を感じることの方が圧倒的に多くなってしまったこのご時世での心境に重なる。それは今目の前で田中が歌い、バンドが演奏しているのを見ていられるからそうした今だからこそ思うことを感じることができる。
すでに5月末に2年ぶりの新作アルバムがリリースされることが発表されているし、田中もMCで新曲を披露するということを口にしていたが、ここで早くも1曲目の新曲。これが田中がアコギを弾いていた「風待ち」とは真逆の、90年代から2000年くらいの田中がギターを弾きながら飛び跳ねまくっていた時期のGRAPEVINEのロックバンドさを彷彿とさせるようなロックチューン。近年はこうした曲がなかっただけに、今になってこうした曲が生まれてきたのが驚きだ。歌詞には田中らしい社会への風刺や皮肉を含んでいるようにも感じられたが、アルバムがリリースされたらこの曲はライブで演奏されるのを待ち望まれる曲になる予感がしている。
田中と亀井のコーラスから始まり、亀井がコーラスから口笛に変化、高野はテルミンまで操作するという、何じゃこりゃ的な構成とアレンジの曲もGRAPEVINEが演奏することによってバンドの実験精神を感じさせながら、決して借り物のサウンドやジャンル感を感じさせないまとまりになっているのが「Golden dawn」。
かと思えば美しいメロディとストレートなバンドサウンドで演奏され、曲最後には田中が
「どんな面をしてせめて裏切らないと
云わせておくれ
それだけは途切れぬよう」
と声を張り上げて歌う「無心の歌」と、見事にサウンドもテンポもバラッバラな曲たちが次々に演奏されていく。
普通なら「前半が勢いのある曲ゾーン」「中盤はミドル〜バラードの聴かせるゾーン」「後半でクライマックスを迎えるためにキラーチューン連発ゾーン」とある程度タイプの似た曲を固めてブロックを作って演奏するというバンドが多いが、GRAPEVINEのライブにおいてはそうした通常の方程式は全く通用しない。だからこそ常に「次は何の曲が来るのか」というワクワクした気持ちや緊張感を持ったままライブを見ることができる。それはそうした単純な分別ができないくらいに多彩なタイプ、サウンドの曲を生み出してきたからだろうけれど。
田中は基本的には楽曲の解釈は聴き手に任せるというタイプであるし、だからこそ聴き手に読解力を求める発言をしたり、素直に「こういう意味の曲です」ということを認めたりしないタイプなので、
「このまま目を塞いでいれば怖くはない
禍々しい世界を見ないでいいのに
このまま手を繋いでいれば怖くはない
その目を開けたら朝が来るように」
というフレーズのある「アルファビル」をこの日演奏したのも、コロナ禍がさらに混沌としてきている今の状況だからなんじゃないかとこちら側としては勘ぐりたくなるのだが、きっとそう言うと
「そもそもコロナになる前に出てる曲やん」
と一蹴されるのだろう。でも確かにこの日のこの曲は自分にはそうした意味を込めて演奏したように感じられた。
その「アルファビル」のアウトロからシームレスに繋がるというライブアレンジだっただけに、
「こんな曲「Burning tree」(「アルファビル」収録の2015年リリースのアルバム。前回の野音ワンマンはこのアルバムリリース時のタイミングだった)に入ってたっけ?」
と思わず思ってしまった新曲は、先程の新曲ほどはアッパーではないが、でも落ち着いてた雰囲気の曲というわけでもない、つまりはやはりGRAPEVINEのロックバンドらしさを感じさせる曲。落ち着いたように感じるのだとすれば、それはバンドの演奏の安定感がそう感じさせるのだろう。
「弁天」からの「すべてのありふれた光」という流れはリリースされている中での最新作である2019年の「ALL THE LIGHT」の収録曲のものであるが、救いをもたらす神仏の類いのようなものへの皮肉とも取れる「弁天」も、今やライブにおいても欠かせない曲となった「すべてのありふれた光」の
「悪意が裟婆を乱れ飛んでる
世界なんか塗り替えてしまえ
ありふれた未来がまた
忘れるだけの 忘れるための
それは違う
何も要らない
何にも無くても 意味が無くても
特別なきみの声が
聞こえるのさ 届いたのさ
きみの味方なら
ここで待ってるよ」
という素直極まりない(バインの中では)歌詞も、今の状況で聴くことによって、今この世界を生きる人々へのメッセージのように響く。悪意が乱れ飛んでる世の中なんか、本当に音楽の力で塗り替えてほしいのに。
高野のシンセがホーンの高らかなサウンドをかなり大きめに発する「MISOGI」ではサビで観客たちが腕を高く挙げる。GRAPEVINEのライブにおいてはワンマンでも1,2曲あるかないかという光景であるが、それがこんなに捻くれまくった曲で起こるというのが実にGRAPEVINEのファンらしく感じる。
アルバムの告知をしてから、
「あと6万曲やります」
と嘯いて、この終盤に来てこの日最大のレア曲として演奏されたのは「JIVE」だろう。カップリングコレクションとしてもCD化されているとはいえ、アルバム未収録曲であり、脱退した元リーダーの西原誠作曲という曲。前に西原が作詞作曲した「窓」を演奏した時は本人が客席に来ていたという理由だったが、もしかしたらこの日も?と思ってしまうくらいにこの曲がここで演奏されたのがあまりに唐突過ぎる。こうしてたまに過去のカップリング曲をライブでも演奏するバンドとはいえ。
そうしてある意味観客を弄んで喜んでいるようにも見える田中が間奏で手拍子をし、観客も同じように手拍子をするのは、こちらもライブではもはや欠かせない、高野のシンセによるホーンの音が響く「Alright」。
特に観客に手拍子を求めているわけではないだろうし、実際にそれをやらない人もいるわけだが、ここまでこうした観客の所作を必要としないバンドも本当に珍しいとつくづく思う。メンバーはやらなくてもリズムに合わせて観客側が手拍子するようになるバンドや曲もあるのに、全くそういう曲がない。それはそもそも手拍子に適したリズムの曲がほとんどないからかもしれないが、こうしてライブを観に来ている人にとっては自分が自発的に何かアクションをするというよりも、ただただバンドが曲を演奏する姿を見て、音に浸っていたいのだろう。そう思わせるくらいの演奏技術と安定感を兼ね備えたバンドであることは間違いない。
「いざ青春の二次会のスタート」
というフレーズは近年屈指のキラーフレーズだと思っているが、メンバーたちも早くライブの後に打ち上げや二次会ができるような世の中になって欲しいと思っているんじゃないだろうか。それはこれまでに何度となくGRAPEVINEのライブ後に祝杯をあげてきた我々観客もそうである。
「雨が上がって…」
という情景描写から始まり「○○をして」という行動の連鎖を言葉遊びのように連ねて行く新曲はサウンド的にはGRAPEVINEの不穏なロックサイドと言っていいタイプの曲である。
この日はそうしたタイプを象徴する曲である「豚の皿」や「CORE」という曲は演奏されなかったけれど、それは野音ということもあるのか(「豚の皿」は夜の野音が良く似合うけれど)、あるいはこうした新曲を演奏することによって、バンドの濃い部分よりも新しい部分を見せるという意識があったのか。いずれにせよ新曲にもそう感じるタイプの曲があるということは、そうした方面でのGRAPEVINEらしさはこれからも失われることがないということである。
先日、アルバムに先駆けて先行配信された「Gifted」はメロディこそ亀井節と言えるキャッチーなもの(そうした部分をドラマーが担っているというのも実に変わったバンドである)であるが、タイトルから想起されるような温かさとは全く異なり、
「神様が匙投げた
明らかに薹の立った世界で
狩る者と狩られる者と
ここでそれを嗤っている者
どれもこれももういい
さよなら」
と、やはりどこかこの今の世界や社会の現状を田中ならではの筆致で表しているように感じる。
この曲も含めてこの日は新曲を4曲演奏した。もちろんまだ他の曲によってイメージは全く変わるだろうけれど、タイトルからしてある意味ではGRAPEVINEらしからぬ肯定の光を感じさせた「ALL THE LIGHT」とは異なり、新作はロックバンドさを強く感じさせるものに回帰するんじゃないだろうかという感覚を得た。とはいえ歌詞のみが先に公開された「ねずみ浄土」などのサウンドやアレンジによってはそのイメージはあっさり覆されるかもしれないが。
ただ言えるのは、もうアルバムとしては17枚目になるが、新しい作品が出るというニュースが出るだけで、GRAPEVINEが今も我々をワクワクさせてくれるということ。
この日もそうだが、GRAPEVINEのライブには派手な演出らしきものは全くない。この日のステージも照明があるだけ。よくあるバンドのフラッグみたいなものすらない。ある意味では殺風景なステージとも言えるかもしれない。
しかしだからこそすっかり暗くなった野音にメンバーの姿がかろうじて見えるくらいの薄らとした照明のみが光り、黄金律と言えるメロディを歌い進めて、最後の
「僕らはまだここにあるさ」
のフレーズにたどり着いた瞬間に、メンバーの頭上にあるミラーボールが光り輝く(この瞬間のためだけのミラーボールだろう)という「光について」の演出にグッとくるのだ。派手な演出や最先端の技術を使わなくても見ている人の記憶に焼き付くような素晴らしく、美しい瞬間を作り出すことができる。それはGRAPEVINEが長い年月をかけてスタッフとともに磨いてきたライブの作り方の結晶そのものだ。まだ開演からしばらくは明るかったが、この瞬間には空にはもう月が浮かぶくらいに暗くなっていた。この曲をこの日本編最後のこの位置で演奏する理由が確かにあったのだ。
アンコールでは田中がライブTシャツに着替えて登場し(かなりこの時間は肌寒くもなっていたけれど、やはりライブをすると暑くなるんだろうか)、改めてアルバムのリリースとそれに伴うツアーでの再会を、
「どんな世の中になっているかわからないけれども、まだマスクは外せないやろうなぁ」
と、我々の顔がちゃんと見える状態になるのを待っているかのように口にした。
GRAPEVINEはコロナ前とそれ以降でライブ自体は全くと言っていいくらいに変わらない。声を我々が発したり、みんなで歌うような曲も全くない。モッシュやダイブだって今は起きようがない。(昔はライブハウスでそうしたノリもあった)
でもやっぱり変わってしまったものがあった。ことさらにそれを取り戻そうとは口にしないが、それがまた見れるようになるのをメンバーも待っているのだ。
そんな思いが野音によく似合う西川の開放的なギターサウンドとして現れているのはこちらも今やライブに欠かせない曲になった「Arma」。
「例えばほら
きみを夏に喩えた
武器は要らない
次の夏が来ればいい」
という歌詞の通りに、今年の夏は去年は見れなかったこのバンドのライブが見れますように。それは6月から始まるアルバムのツアーが無事に終わりを迎えているように、ということだ。
暗くなった夜空とステージだからこその魅惑的な照明が映えるのは「光について」に次ぐバンドの代表曲と言っていい「スロウ」。近年はこうしてこの2曲をライブで演奏する頻度がかなり多くなっているが、活動歴が長いバンドであるほど「久しぶりにライブに来た」という人も多くなるだけに、そうして久しぶりに来た時にこの曲が聴けたら嬉しいだろうなと思うし、毎回聴いていてもこうして夜の野音というシチュエーションで聴くことによって、ホールツアーの時とはまた違った感覚になる。
そんなライブの最後に演奏されたのは、田中がアコギに持ち替えて歌い始めた「smalltown, superhero」。いわゆるライブの最後を締め括るバンド最大のキラーチューンという曲でもなければ、最後に最高の盛り上がりを、という曲でもない。むしろことごとくそうした要素の真逆を行くようなタイプの曲。
しかし、
「音は聴こえないんだ
色だけが焼き付いていたんだ
遡って 坂を登って
見ていたんだ
見ていたんだ
わかっていたんだ」
という最後のサビを聴いていると、確かにこの日のライブのあらゆる場面が脳内に焼き付いているという感覚になる。それは野音の入り口にある坂を登るところまで遡って。それは考えすぎなのかもしれないが、GRAPEVINEはライブで演奏されている全ての曲に何かしらの意味や意図があるんじゃないだろうかと改めて思わされた。それはまたアルバムがリリースされて曲が増えるとさらに理由も増えていく。メンバーの去り際の笑顔まで含めて、本当に幸せな時間だった。
まさに緊急事態宣言が発令されたこのタイミングでこうして都内でライブが開催されて、それを見に来ているということが正しいのかどうかはわからない。それは誰が正しいか正しくないか決められることでもない。
でも音楽やライブやエンタメは不要不急でもないと思っている。殺伐とした今の日々や社会を生きていく中で、こんな平和な雰囲気を感じながら、子供の頃から聴いているバンドの音楽にただ浸っている。そんなささやかなことでも救われるような気持ちになる。せめて、それくらいのことは享受できるようであっていて欲しい。強い主張を口にするわけではないけれど、この日に日比谷野音でGRAPEVINEのライブを見て感じたのはそういうものだった。
1.FLY
2.スレドニ・ヴァシュター
3.放浪フリーク
4.Darling from hell
5.風待ち
6.新曲
7.Golden dawn
8.無心の歌
9.アルファビル
10.新曲
11.弁天
12.すべてのありふれた光
13.MISOGI
14.JIVE
15.Alright
16.新曲
17.Gifted
18.光について
encore
19.Arma
20.スロウ
21.smalltown, superhero
文 ソノダマン


![[Alexandros] 「ALEATRIC ARENA 4DAYS」 日本武道館 2021.10.26 [Alexandros] 「ALEATRIC ARENA 4DAYS」 日本武道館 2021.10.26](https://moretzmusic.com/wp-content/uploads/2022/07/68-250x250.jpeg)