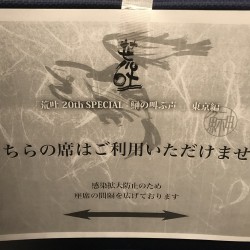7月にHump BackはZepp Hanedaで対バンライブをやっているのだが、そこに招いたのはベースのぴかがかつて観客として足を運んでいた存在である、04 Limited Sazabysである。
そんなフォーリミの幕張メッセでのワンマンを観た翌日に観るのがHump Backのワンマン、しかも日本武道館ワンマンであるというのはあの対バンツアーの続きを勝手に作り出しているという感じすらする。しかもその日本武道館を単発のワンマンでもなく、ツアーファイナルでもなく、ツアーの中盤の1つの公演として行う(しかも翌日が千葉LOOKでツアー)というのが大阪のバンドらしいし(昨年大阪城ホールでもワンマンをやっているが、そちらの方が思い入れが強かったりするのだろう)、どこかHump Backらしさも感じる。
検温と消毒を経て日本武道館の中に入ると、ステージも含めてライブハウスの延長であるとしか思えないくらいにシンプルな作りであり、両サイドにスクリーンがあるというくらいしか普段のライブとの違いがない。観客のほとんどが10〜20代前半の若い人に見えるというのも、Hump Backがその世代のヒーローと言える存在になっていることがよくわかる。
18時ピッタリになった頃に場内が暗転すると、おなじみのハナレグミ「ティップティップ」のSEが流れて3人がステージに登場すると、椅子に座っていた観客も一斉に立ち上がる。メンバーの出で立ちは普段と全く変わらないもので、武道館という舞台だからといって特別なことをしないということが伺えるのだが、林萌々子(ボーカル&ギター)が曲に入る前に、
「いろいろ考えてきたんやけど、今日は本当に来てくれてありがとうございます!それしか言えないわ!」
と言った瞬間にギターを鳴らしながら
「夢はもう見ないのかい?
明日が怖いのかい?」
と歌い始めて「拝啓、少年よ」でスタートし、ぴかは「そんなに!?」と思うくらいに頭を振りながらベースを弾き、サビではステージ中央に出てきてぴょんぴょん飛び跳ねまくる。気合いを感じられるけれども、それでもいつも通りとも言えるのだが、この曲がこの日特別だったのは、
「馬鹿みたいに空が綺麗だぜ」
というフレーズ通りに東京は雲ひとつないくらいの秋晴れの空だったということ。まるでこの曲がこうして日本のライブ会場の象徴的な場所である武道館で鳴らされるからこそ、そうなったかのように。
「楽しい曲やりまーす!」
と言って演奏されたのは「ACHATTER」の1曲目である、疾走感あふれるサウンドでメンバー3人の声が重なる「宣誓」。この曲がここで演奏されることによって、このライブが集大成的なものではなく、ツアーの中の1本のライブであるということを改めて実感させてくれるのだが、「生きて行く」で林が
「先生 僕は今 武道館で歌ってます!」
と言うと、やはり武道館という単語の持つ力がこの日を特別なものに感じさせてくれる。林が間奏でマイクスタンドをぶっ倒すというのはいつも通りのライブそのものでもあるのだが。
とはいえ、武道館には魔物が住んでいるという話もよくある。武道館に浮き足だって、自分たちのライブが出来なくなってしまったり、あるいは普段なら起こらないようななんらかのアクシデントが起きたりするということである。
そんな雰囲気を林は察知したのか、ぴかと美咲(ドラム)に
「ちょっと背中を叩いてくれ」
と言って気合いを入れてもらう。見ている分にも少し緊張感のようなものもあったけれど、それは歌唱に表れていたというよりは会場全体の空気として表れていたように思う。それを林はきっと察知していたのだろう。いつもと変わらないライブをやっているようでいて、やはりどこか違うというのを自分自身が感じていると。
そんな気合いを入れた後に、
「今、恋してる奴もたくさんおるやろう!」
と言って演奏された、この曲からようやくステージ両サイドのスクリーンにメンバーの演奏する姿が映る「恋をしよう」の
「擦り切れるほど聴いた安いラブソング
僕には響かなかった 君は泣いていた
どうか どうか 笑っておくれよ」
という歌詞はHump Backのような、決して安いラブソングを歌わないバンドのライブに来ている人にこそ響くもの、この曲が自分のためのものであると感じるものがあるはずだ。
それは「プレイリスト」にも通じるテーマでもあるのだが、ライブをやりまくって生きてきたバンドは曲をやるにつれてライブの空気を自分たちのものに変えていけるという能力があって、それはHump Backもそういうバンドであるだけに、スタート時よりも音が武道館に馴染んできているのがよくわかる。それはこの曲のサビの思いっきりキャッチーなメロディという要素によるものかもしれないけれど。
さらに
「きみの歌になりたかった
強く強く 想っていたんだけど
きみの春になれなかった
何も何も言えなかった」
という「きみは春」と、前作アルバム「人間なのさ」収録の「恋をしよう」と「ACHATTER」収録曲の2曲が続けて演奏されることによって、Hump Backが変わらないものを歌い続けているバンドであることがよくわかる。特に「きみは春」は常々
「あなたの青春になりたい」
と口にしてきたHump Backだからこその曲であり、ここにいる人の青春に、春にHump Backの音楽はすでになっているはずだ。
「めっちゃ良い居酒屋でキンキンに冷えた生ビールを飲むのもいいけど、家でお笑い番組見ながら飲む缶ビール、なんなら金麦を飲んでる方が美味しいって思うもんやな」
と、武道館とライブハウスの違いを飲酒する身としては、なおかつ金麦を愛飲している身としては実にわかりやすい例えで口にすると、
「缶ビール一本くらいじゃ酔えない
安上がりって割と好き」
というまさにその例え通りの歌詞が登場する「遊覧船」からはそれまでの疾走感あふれるギターロックというHump Backのパブリックイメージとは違った形の曲が続く。林も酔っているかのような動きをしながら歌うこの曲は削ぎ落とされながらも重いリズムがこのバンドならではのブルースを感じさせてくれるのだが、間奏では一気に林のギターが歪んでいくというなかなかに一筋縄ではいかない展開の曲であり、この曲をいきなり聴いたらもしかしたらHump Backの曲とは思わないかもしれない変化球である。
それはキャッチーかつ、どこかキュートさも感じられるラブソング「マイユー」もそうであり、美咲が金属音を叩く音が多めなのが良いアクセントになっているのだが、その美咲がダンサブルなリズムを叩き出し、そこにぴかのうねるリズムが加わる「ひまつぶし」はぴかのコーラスも含めて、「ACHATTER」がバンドの幅をさらに広げたアルバムであることを感じさせるのと同時に、「夜になったら」リリース当時はどこか頼りなさを感じていた美咲のドラムが力強さを獲得し、その強さと手数も含めて完全に覚醒したことを感じさせるものになっている。もちろん林の歌もぴかのベースとパフォーマンスもそれぞれ進化しているが、これだけいろんなタイプの曲を演奏できるようになったのはその美咲の覚醒によるものが1番大きいと思う。
そんなかつてないほどに振り幅の広い「ACHATTER」の曲の中で、
「僕の部屋においで」
というフレーズが純真そのものとして響く「ヘイベビ」はそれに続くのが
「新しいレコードを買ったんだよ」
というものだからだろう。実に情景や関係性が浮かんでくる歌詞であるが、Hump Backには人間同士のラブソング的な歌詞の曲もあるけれど、それ以上に音楽へのラブソングが多いんじゃないかとも思う。
そして「ACHATTER」の中でもバラード枠と言えるような、林の歌声が武道館を包み込むように伸びていく「新しい朝」ではスクリーンに映るメンバーの姿がモノクロになっている。それはこの姿も1秒後からしたら過去のものであり、それを経て新しい朝に向かっていくかのように感じられたのだが、この曲から一転して夜の情景を描いた「サーカス」へと繋がると、疾走感溢れるギターロックというわけではないHump Backの曲のグルーヴが巨大な一つの塊となって武道館を飲み込もうとしているのがよくわかる。やはり曲を演奏し続けることによって、このバンドは緊張から解放されながら武道館を自分たちのホームに変えているのだ。
しかしながらぴかは、
「昨日、友達とカレー食べてたら「明日武道館やけど、どうなん?」って言われて。あんまり思い入れもないし、普通やなって言ったんやけど、実際に来てみたらめちゃくちゃ緊張している(笑)」
と、まだ緊張から解けていないようだ。飛び跳ねる姿からして最も緊張を感じていないようにも見えたのだが、それはチャットモンチーのラストライブでドラムを叩いた時に袖で見ていた林とぴかが号泣していたのに、本人が「え?なんで2人泣いてるん?」と全くプレッシャーを感じていなかった美咲の方がそうだったのかもしれない。
だからか、林は
「もっと爆発したい!」
と言うと、その着火役を美咲に託したのかもしれない。明らかに振られて戸惑っている感じも見て取れたのは、林が
「普段やらないことをやったらもっと爆発できる気がする」
と言うように、叫んだりしないという美咲による
「やるぞー!」
の叫びから、その美咲のドラムが時に細かく刻まれ、
「最高速度」「平成賛歌」
という4文字熟語で3人の気持ちが重なるように声も重なる「閃光」の
「ねぇ こんな夜は君と君の犬を抱き締めたいよ」
というフレーズが武道館ワンマンというプレッシャーをも感じるであろうこの日の夜の3人の心境としても重なっていくのだが、気合いを入れたことによってか、音がさらに強くシャープに聴こえてくる。それは
「どうやら僕らは騙されたみたいだ
ロックンロールの神様ってやつに」
と歌う「HIRO」でもそうであるが、
「神様なんかいないぜ
ハナから信じちゃないぜ」
と歌っていたこのバンドも、ロックンロールには神様がいることをわかっている。それは少なからず、自分たちがロックンロールの神様に見そめられたバンドであるという自負があるからだろうし、一途なくらいにロックンロールだけを信じて武道館まで来たバンドなんだから、ロックンロールの神様というものがいるのなら、今このバンドに絶対に微笑んでくれているはずだ。
林の歌が冒頭から素晴らしい伸びを見せ、スクリーンに映る際の表情が完全に武道館のプレッシャーから解放されたかのような笑顔になっている美咲のドラムもより力強さを見せる「オレンジ」を演奏すると、なぜか
「もう1回「宣誓」やろ」
と言って、すでに演奏した「宣誓」をもう1回演奏するという自由さを見せる。もしかしたらこの曲はこれから盟友であるハルカミライの「ファイト!!」のように1回のライブで複数回演奏される曲になるのかもしれないし、当然この2回目の方が3人とも実に伸びやかな、楽しそうな演奏を見せてくれたのである。
すると林が客席を見渡し、バンドのグッズを身に纏った人がたくさんいるのを見ると、自身と美咲はチャットモンチーのタオルを取り出して客席に掲げて見せる。
「初めて武道館に来たのがチャットモンチーの武道館で。次が先輩のライブ、その次が友達のライブで、今日が自分たちのライブ。チャットモンチーのライブを観に来た時のタオルはこんなに色褪せてしまったけれど、みんなもHump Backのグッズを色褪せるまで使ってな」
という言葉は、ぴかが「思い入れもあんまりない」と言っていたこの武道館にHump Backが立つ理由と、ここに立つからこそ継承できるものがたしかにあることを示していた。あの時チャットモンチーを客席で見ていたバンドが、今は武道館のステージに立つようになった。それはきっとこの日客席にいた人が、いつか武道館のステージに立つようになるということである。そうやって音楽は、バンドは繋がっていく。自分自身もこの武道館で見ていたチャットモンチーはもう見ることはできない。でもこの日のHump Backのライブはどこかあの武道館の続きを見ているような感覚も確かにあったのだ。
すると林はタオルを置くと、ギターを爪弾きながら、
「この前、少年が同級生を刺してしまった事件があっただろう」
とブルースを歌うように言葉をその場で紡いでいく。
「少年、君のその手は誰かを傷つけたり、ましてや自分を傷つけるためのものではないんだぜ
少年、君のその手は愛するものや、大切なものを抱きしめるためにあるんだぜ
僕はここにいるみんなを、僕が愛する音楽で、ロックンロールで抱きしめたいんだ」
という言葉を、林自身も少し涙ぐみながら口にしていく。
もうあの少年を救うことはできないし、この言葉も届くことはない。人によってはこれを字面だけ見て「綺麗事だ」と判断する人もいるだろう。それでも、ここにいる人をあの少年のようにしないことはできる。ここにいる人を救うことならできる。
そう思うのは、やっぱりわざわざロックバンドを聴いてライブまで来るような人はどこか人生全てが上手くいっているわけではない人だと思っているからであるし、何よりも自分自身が春のJAPAN JAMの時に林の
「ルールを守るのはロックじゃないし、誰かに決められたことに従うのはカッコよくない!でも大切なものを守ろうとするのはめちゃくちゃロックやし、めちゃくちゃカッコいい!みんなJAPAN JAMを、フェスを、ライブを守ってくれて本当にありがとう!」
という言葉に救われたからである。遠回りを一切しない、どストレートな言葉だからこそ、それが心に最短距離で届く。そんな言葉の力を林は持っているし、その源泉にあるのはロックへの、バンドへの絶対的な愛と信頼だ。それはきっと自身もロックに、バンドに救われたことがあるという経験があるから。あの少年がロックを、このバンドの音楽やライブを知っていたら、少しくらいは結果が変わっていたんじゃないかと学生の頃の自分のことを振り返ると思わずにはいられない。
そんな言葉の後に演奏された「番狂わせ」は「ACHATTER」のリード曲であり、最もはっちゃけた曲でもあるのだが、その言葉の後だからこそ、この日はそうした曲の持つ空気が全く違っていた。スクリーンを通してでもわかる、林の視線の強さ。それがそのままロックバンドの強さ、カッコ良さを感じさせるものになっている。
「やることやっても足らんくらい しょうもない大人になりたいわ」
「泣いたり笑ったり忙しい おもろい大人になりたいわ」
という歌詞を、年齢的に大人である自分が聴いていて思うのは、大人になるのは決して悪いことでもつまらないことでもないということ。大好きな音楽で泣いたり笑ったりさせてくれる、こういうバンドがいてくれるから。
そのバンドの意志を示すかのように
「ロックンロールを弾いた
スリーコード エイトビートに乗って
僕らの歌よ どうか突き抜けておくれよ」
という歌詞が武道館の天井にまで突き抜けるような「ティーンエイジサンセット」で林は最後のサビ前に
「ロックンロールは若者のものだ!」
と叫んだ。もちろんそうだと思うし、そうであって欲しいと思う。40代や50代になっていきなりロックに目覚めるなんてことはそうそうないだろうし、1番ロックが響くのは若者の時期だと思っているから。でもそれはただ単に今10代や20代前半の人たちだけのものであるという意味ではないはず。かつて若者だった頃にロックンロールに衝撃を受けた、それこそ若者の頃にチャットモンチーの初武道館を見ていた、そして今もこうしてHump Backの初武道館を見に来ている自分のようなやつのものでもある。自分はこの言葉をそう受け取っていた。
そしてライブがクライマックスを迎えていることを告げるのは、3人が向かい合ってイントロのキメを打つことでさらにバンドのグルーヴが加速し、観客はコロナ禍になる前はおなじみであった「ワンツー!」のカウントを声は出さずに指で表現する「短編小説」。
林はその曲中で、
「ずっとHump Backを信じてきた!Hump Backを信じてくれ!」
と叫んだ。このバンドを信じるに足る理由。それはここまでのライブで見せてきてくれたものでもあり、この曲がりようがないくらいの音楽への、聞いてくれる人への真っ直ぐさ。少しでもそこに不純さが混じっていたらバレてしまうくらいに。そんなバンドであり人間だからこそ、信じられる。信じたくなる。
それは一気に曲とサウンド、さらには林の歌唱のスケールが大きくなる「クジラ」でも同様だ。
「もういっそ いっそのこと この空駆け抜けて
そういつか いつか 光になるのさ
いっそ いっそのこと この街駆け抜けて
そう 一歩一歩 あるき出すのさ」
という本当に真っ直ぐな姿勢と歩みがそのスケールにこの上ないくらいの説得力を感じさせてくれる。やっていることはライブハウスと全く変わらないけれど、それがこの規模にふさわしい、いや、もっと広い場所で鳴り響いているのを見たくなる。
そして林は
「15歳の時にこのバンドを始めて、メンバーがいなくなって1人きりになったこともあった。そんな時もずっと「Hump Back」って名乗ってきた。意地みたいなものもあったんやろうと思う。でもこの2人に出会って、この3人のHump Backになって、もうそうじゃないなって思った。今は1人になってもHump Backとは言えない。この3人だからHump Backだって言える。ずっと続けていきたいけれど、誰かが辞めたいって言ったらその時にバンドは終わる。それは少し寂しいものでもあるけれど、そう思えるようになったのが本当に愛しく思う」
と、林が曲を書いて歌う、その後ろで2人が林の曲を演奏するという形ではなく、本当にこの3人だからこうした曲になっていて、こうしたバンドになれていることを口にする。変わった、強くなったのは美咲だと思っていたけれど、その美咲とぴかの存在によって林も変わった。誰かがいなくなったら終わってしまうバンドになったからこそ、このバンドをできる限りたくさん観たいと思う。
そんな言葉を聞いて涙が溢れてしまった観客も何人もいたと思う。するとそれをわかっているかのようにバンドはここで「ACHATTER」収録の美しい、でも素朴なバラード「きれいなもの」を演奏した。
「君のかわいい その小さな目から
ぽつりと 涙がこぼれたよ
花のような 星のような 君の小さな小さな涙は
とても綺麗だったんだ」
というサビのフレーズは、そんな涙を流してしまうことすらもその音で抱きしめてくれるかのようだった。
そこから再び走り出すように演奏されたのは、
「今 目に見えないものを探してる途中」
という初期の時期に編まれたフレーズが今に結び付いたかのようでいて、それでも武道館に立ってもなおもまだ探してる途中であるとすら感じさせる「いつか」であり、さらに
「今のこの3人の曲!」
と、この曲を作詞作曲し、一部ボーカルも務めるぴかがタイトルコールをした、まさにこのバンドのことそのものを歌った「スリーピース」の
「朝焼けに染まるステージを
何度も立ち続けている
いつか別れが来るだろう
その時まで鳴らし続けていこう」
というフレーズが、まるで林が書いたものと思えるくらいに、ぴかと林は同じことを考え、同じことを歌詞に書いている。だからこそ、この曲ではさらに3人の人間そのものが鳴っていた。
そして観客の体が自然と揺れるようなサウンドでライブをしては次の街へと向かっていくロックバンドの生き方そのものを歌ったような「僕らは今日も車の中」でヒップホップというかリーディング的な林のボーカルによる
「僕らの夢や足は止まらないのだ」
というフレーズが、この武道館でのライブを終えてもまたすぐに次のライブをする街へと車を走らせるバンドの姿を想起させる。実際にこの2日後には千葉LOOKという武道館からのキャパの振れ幅があまりに大きい会場でツアーなのだが、車の中でも3人でいろんなことを楽しそうに話したり、いろんな景色を見て感動したりしているであろう姿が浮かぶ。それがこれから先も変わらないものであることも。
そんないつものライブハウスでのライブとは変わらないようでいて、それでもやはり記念すべき初の武道館ワンマンの最後に演奏されたのは林が弾き語りのようにサビを歌ってから2人の音が加わってバンドサウンドになるという、この3人のバンドの成り立ちを思わせるような形で始まった「星丘公園」。
コロナ禍になる前は観客で大合唱することもあった、
「君が泣いた夜に ロックンロールが死んでしまった 僕は飛べない」
というフレーズを今は3人だけで歌うからこそ、3人のそれぞれの声がハッキリと聞き取れる。
「明日になれば忘れてしまうのさ」
というフレーズを聞いた瞬間、明日になっても、その先もこの日のことを忘れてしまうことなんてできないだろう、と思っていたら、林が
「今日のことは忘れないから!」
と叫んだ。ああ、最後の最後にバンドと我々が一つになった。そんな感覚があった。
「もう時間が止まればいい」
の歌詞は先程の歌詞とは違って、本当にその通りになればいいのに、と思っていた。
アンコール待ちでは特に誰かが率先したわけでもない、暗い武道館の場内を照らすように観客がスマホライトを振ると、ステージに戻ってきたぴかは
「あれってスタッフさんが裏で仕込んでたわけじゃないですよね?…凄い綺麗だった」
と、本当に特別な瞬間の特別な景色を見れたかのように口にするのだが、林はいたって普通に、
「あ、撮影とか禁止なんで。すいません」
と言ってマイクスタンドの前に立ってギターを持つ。
「何か言い残したことないか?今日、おとんもおかんも来てるやろ?」
と林が2人に振ると、ぴかは
「今までありがとう」
と両親に感謝を告げ、林も同じように両親に感謝を告げるのだが、最後に美咲は
「萌々ちゃん、ぴか、ありがとう」
とメンバーに感謝を告げる。最も天然なようにも見える美咲はこの最後に最も言うべきことを言ったように感じた。それはこの日のライブが、ここまでの3人での歩みがその言葉を引き出させたのかもしれない。
そして
「最初に出したCDに入ってる曲!」
と言って演奏したのは「夜になったら」の1曲目に収録されている、初めて聴いたこのバンドの曲である「月まで」。
「夢で逢えたらベイビー
なんて考える間も無く
今日が終わるよ」
というフレーズは、
「君はどうだい?」
と問われて、そうだよなと思うくらいにこの記念すべき日が終わっていってしまうことを感じさせたのだが、このシンプルなギターロックをこの武道館で鳴らしているこの姿は、初めてこの曲を聴いた時にはまだ想像できていなかった。チャットモンチーの「こなそんフェス」など、いろんなライブを積み重ねて、ここに立つ姿がイメージできるようになった。それはライブハウスでライブをやりまくって生きてきたバンドだからだろう。
そんな日の最後の最後に鳴らされたのは「LILLY」。
「夜を越え 朝迎え 君に会えたらそれでいいや」
というフレーズを林が、またこうして我々に会えるようにと願いを込めるようにして高らかに歌う。我々も同じようにまたこうしてHump Backに会えたらと思う。武道館だからこその特別な演出やいつもと違うパフォーマンスは何一つない、だからこそかつてとあるバンドのボーカリストが残した
「ライブハウス武道館へようこそ」
という言葉を2021年の今にこんなにも強く感じさせてくれた。いつも通りのライブのようでいて、やっぱり特別な、どうあっても忘れられない、Hump Backの初武道館ワンマンだった。
Hump Backのライブには本当に若い人が多い。きっと自分も今10代や20代前半だったら、何とかしてチケットを取って、この時代にわざわざCDを買ってきたりして、このバンドのことを追いかけるような人生になっていただろうなと思う。
それはハルカミライもそうであるが、10代の時の自分が最も必要としていた、欲しかったのは、誰かをぶん殴るためのロックではなくて、部屋で1人で音楽を聴いているような自分のことを抱きしめてくれるようなロックだったからだ。Hump Backはそんなバンドであり、結局、自分は今でもそんなバンドのそんなロックを何よりも必要としている。そんなことを改めてわからせてくれた武道館ワンマンだった。そんな、しょうもない大人になりたいわ。
1.拝啓、少年よ
2.宣誓
3.生きて行く
4.恋をしよう
5.プレイリスト
6.きみは春
7.遊覧船
8.マイユー
9.ひまつぶし
10.ヘイベビ
11.新しい朝
12.サーカス
13.閃光
14.HIRO
15.オレンジ
16.宣誓
17.番狂わせ
18.ティーンエイジサンセット
19.短編小説
20.クジラ
21.きれいなもの
22.いつか
23.スリーピース
24.僕らはいつも車の中
25.星丘公園
encore
26.月まで
27.LILLY
文 ソノダマン