いよいよ最終日。開場時間くらいには雨がぱらついたものの、3日間の中で1番天気が良いと言ってもいいレベルで、地面のぬかるみもほとんどなくなっていて全体的に過ごしやすい気候。
9:55〜 マカロニえんぴつ [FOREST STAGE] (Opening Act)
この日のオープニングアクトはマカロニえんぴつ。すでにオープニングアクトじゃなくて普通のスロットで出ても良くない?と思うくらいの勢いを見せている4人組バンドであり、やはり朝10時のオープニングアクトとは思えないくらいにたくさんの人が詰めかけている。
「おはようございます、マカロニえんぴつです!」
とはっとり(ボーカル&ギター)が挨拶をすると「レモンパイ」「ブルーベリー・ナイツ」というCHOSHOKU代わりと言ってもいいようなモーニングな曲を連発し、このバンドの持ち味である、長谷川大喜のキーボードの音色を生かした心地よいサウンドとメロディに浸っていく。
そんな中であくまでロックバンドであるという部分を担うのがポップなイメージには似つかわしくないフライングVを弾く田辺由明のギターと目立たないがしっかりとボトムのサウンドを支えながら重さを持った高野賢也のベース。この辺りのバランス感覚も抜群であるが、小気味好い発音の「洗濯機と君とラヂオ」、「ハートロッカー」というあたりではその内に秘めるロック魂をしっかりと感じさせてくれる。
はっとりは実は山梨県出身であり、この場所でのライブは凱旋と言っていいものになるだけに、いつも以上に気合いが入っているというか、得てして夜型生活の人が多いミュージシャンはフェスの朝イチでは真価を発揮できないこともあったりするが、そんなことは一切感じさせないくらいに気合いに満ち溢れている。
そのはっとりは
「みんな色々苦しいこととかが多い人生かもしれないけど、やりたいことだけやって生きていけますように。それは難しいことかもしれないけど」
と言った。それはこのバンドがこれからもやりたいことだけをやって生きていくという宣言的なものであるが、自分が普段から抱えてる思いそのものだ。だから自分はこのバンドに惹かれるのかもしれないし、その後に演奏されたリリース間近の新作ミニアルバム「season」に収録される「Mr.Children」のような反語の組み合わせのタイトルである「ヤングアダルト」は年齢的には大人であっても大人になりきることができない自分のような人間のために歌われているかのように思えてしまった。
この曲がそう思えたということはきっと自分はこれまで以上にこれからこのバンドのことをさらに好きになっていくと思う。自分がそう思うということはほかにそう思う人もたくさんいるはず。つまり、ただでさえオープニングアクトという位置を飛び越えているこのバンドは来年以降もっとたくさんの人が見れるようなステージに立つはずなのである。
リハ.鳴らせ
リハ.ミスター・ブルースカイ
1.レモンパイ
2.ブルーベリー・ナイツ
3.洗濯機と君とラヂオ
4.ハートロッカー
5.ヤングアダルト
10:25〜 Saucy Dog [Mt.Fuji STAGE]
2年前にオープニングアクトとして出演し、昨年のFOREST STAGEを経て、ついにMt.Fuji STAGE初進出となった、Saucy Dog。春フェスまでの飛躍的な成長を見ているとそれも当たり前のことであると思える。
石原慎也(ボーカル&ギター)の澄んだ声がこの山中湖に響く「真昼の月」でスタートすると、秋澤和貴(ベース)とせとゆいか(ドラム)によるリズム隊が力強くサウンドを引っ張っていく「ゴーストバスター」「バンドワゴンに乗って」というまさにロックバンド感が強い曲を続ける。
初のMt.Fuji STAGEということで、石原は何度も晴れていればそこから富士山の姿を見ることができるステージ背面を覗き込んでいたが、この日はそれを見ることはできず。また来年以降のお楽しみだ。
この自然に溢れた空間がよく似合う最新曲「雀ノ欠伸」も披露されたが、歌詞の内容としては夕暮れの時間により似合いそうな感じもするだけに、来年以降その時間帯への出演も期待したくなる。
日常の風景を切り取ったバラード曲「コンタクトケース」では石原の歌唱力と声量をフルに発揮。音源のイメージでいるとビックリしてしまうくらいに素晴らしいそれはこのバンドをライブバンドたらしめている最大の理由になっている。
そしてラストはやはりこの場所での再会を約束する「いつか」。石原の歌唱はここにきて頂点に達した感があったが、今の若手バンドでここまでバラードをライブでやるのを待たれているバンドもそうそういない。最前にいる観客たちのこの曲に聴き入っている顔がそれをより強く感じさせた。
1.真昼の月
2.ゴーストバスター
3.バンドワゴンに乗って
4.雀ノ欠伸
5.コンタクトケース
6.いつか
11:05〜 HY [LAKESIDE STAGE]
実はこのフェスがこの場所で初開催された2007年から出演している、HY。当時はまだ若手と言ってもいいような立ち位置だったが、今やすっかりベテランとなってこのLAKESIDE STAGEのトップバッターを務める。
現在ギターの宮里悠平が療養中ということでサポートギターと、さらにはサポートキーボードを加えた編成で登場すると、午前11時に目を覚ましてよと君の声が僕を包む大名曲「AM11:00」からスタートし、朝早くから集まった観客を歓喜させる。新里英之(ボーカル&ギター)、仲宗根泉(キーボード&ボーカル)の男女ツインボーカルの美しさと名嘉俊(ドラム)のラップのキレ。名曲はいつになっても色褪せることはない。
HYなりのポップなラブソングである新曲「大好きだもの」でバンドの今のモードを見せながら、新里が「366日」を演奏しようとするのだが、この曲でメインボーカルを務める仲宗根が観客からの歓声が小さくて不貞腐れてステージ上で座り込む→観客がサビを大合唱する→ヤル気になるというベテランならではの煽りというか小芝居を見せる。歌い始めるとやはりそのボーカルの美しさにうっとりしてしまうが、初めてライブを見た2004〜2005年あたりはまだ沖縄ののんびりした人たちというイメージだったこのバンドのメンバーがこんなキャラになるとは全く予想だにしていなかった。
新里が観客に好きな色を尋ねてそれを歌詞に入れてコール&レスポンスする「no rain no rainbow」では新里が目立つ客を探している時になぜかトイレットペーパーを掲げてる客がおり、その人を指名すると当然のように好きな色は「白」だと答えて爆笑を巻き起こす。この日の虹がかかりそうな空の下で聴くのが実によく似合う曲だ。
そしてラストは「ホワイトビーチ」。新里が踊りながら歌う一方で仲宗根はピアノを弾かずになぜかひたすら「オイ!オイ!」と観客を煽りまくる。(全然そんなタイプの曲じゃないのに)
その姿を見た新里は演奏後に、
「こんないーずの姿が観れたのは初めてです(笑)みんなありがとう!」
と仲宗根のテンションの高さに驚きながらも観客への感謝を告げた。
持ち時間が短いとはいえ5曲は短い。とはいえ物足りない感じはない。それは代表曲をしっかりやりながらも今の自分たちの姿をしっかり見せるというフェスのセオリーをしっかり守っているから。もう「AM11:00」にしろ「ホワイトビーチ」にしろ15年以上も前にリリースされた曲であるが、全く古臭さは感じないし、今でもみんなが曲を知っている。HYが作ってきた名曲はきっとこれからも聴き続けられていくんだろうな、ということを改めて感じた35分だった。
1.AM11:00
2.大好きだもの
3.366日
4.no rain no rainbow
5.ホワイトビーチ
11:55〜 BLUE ENCOUNT [Mt.Fuji STAGE]
いつものようにリハから完全全力投球のBLUE ENCOUNT。だが田邊駿一から、
「うちのリーダーの江口雄也、本日大遅刻しました!」
と暴露されると、辻村勇太(ベース)にも
「いやー、今日は良いベースを弾いてくれるんだろうなぁ(笑)」
と言われる。その一部始終を見ていた高村佳秀(ドラム)はずっと笑っていたが、その4人の姿からも今バンドの状態が良いことが伝わってくる。
本番では「DAY × DAY」からスタートし、高村の高速ツービートパンクな「だいじょうぶ」といういわゆる「エモい」と言われることも多いブルエンの魅力を全開にしていき、ダイバーが続出。
さらにはドラマタイアップの新曲「バッドパラドックス」も披露されるのだが、この曲はそれまでの2曲とは違い、同期のサウンドを取り入れて田邊のボーカルにもエフェクトをかけた、キャッチーなダンスナンバー。新曲やリリースのペース速さとクオリティからして、やはり今このバンドは過去最高にノッているのかもしれない。インタビューでは田邊は毎回うじうじしているように感じるけれど。
田邊のまくしたてるような早口ボーカルのある「Survivor」、オリエンタルなギターリフが印象的な「VS」と近年のこのバンドのライブを担うキラーチューンを連発すると、田邊は「もっと光を」を演奏しようとするのだが、
「この曲やれば盛り上がるのはわかってる。でも盛り上げたいからやってるわけじゃない。必要だと思ってるからやってる。単なるフェスの賑やかしバンドだって括られるのが嫌なんだよ。
あんたらだってそうでしょ?単なるフェスの客って一括りにされるの嫌でしょ?あんたらには1人1人の人生やドラマがあって、それでここまで来たんでしょ!」
と演奏前にこの曲を演奏する意味、自分たちがこのフェスのステージに立つ意味を語る。
いわゆる「ONAKAMA」を形成するフォーリミやオーラルがこのフェスでLAKESIDE STAGEに立ち続け(ブルエンも立ったことはある)、スペシャのレギュラーを務める中で悔しさも間違いなくあるはず。でもきっと今のブルエンはそういう周りのことは関係なしに自分たちがやりたいことをやろうとしている。今まで田邊のMCは数え切れないくらいに聞いてきたが、この日が今までで1番
「自分は田邊のこの熱さが好きなのかもしれない」
と思った。
そうして「もっと光を」をしっかりと観客1人1人に突き刺さるように演奏すると、最後に演奏されたのは今年リリースのミニアルバム「SICK(S)」に収録されている「アンコール」。
未だ初期衝動を感じさせる激しい演奏に乗せて
「共に行こう 先は長い
エンドロールはまだ早い
アンコールは待っている」
というフレーズは一時期は終わってしまうんじゃないか?と不安に感じることもあったブルエンがまだまだこれからも続いていくこと、バンドがたくさんの人に求められていることをわかっていることを示している。アンコールは求められないとできないものだから。これからもこのバンドのアンコールは続く。
リハ.…FEEL?
リハ.Never Ending Story
1.DAY × DAY
2.だいじょうぶ
3.バッドパラドックス
4.Survivor
5.VS
6.もっと光を
7.アンコール
12:40〜 高橋優 [LAKESIDE STAGE]
かつてこのフェスに初出演した時はまだ新人のオープニングアクトだった、高橋優。今やたくさんの人にその存在を知られる歌うたいとなってこのフェスに久しぶりの凱旋。
バンドメンバーに続いて高橋優がステージに登場すると、そのバンドという形態であることの強さを感じさせるロックな始まりの曲「STARTING OVER」からスタートすると、ここで早くも高橋優の存在を一躍世間に知らしめた「福笑い」へ。
「あなたが今楽しんでいるのか
「幸せだ」と胸張って言えるのか
それだけがこの世界の全てで
隣でこの歌唄う 僕の全て」
という歌詞はフェスというたくさんの多様な人々が一堂に会する場でこそ歌詞が本当に染みるし、こうしてこの場所でこの曲を聴いていると「幸せだ」と胸を張って言える。
そんな歌うだけで感動するような空気で満たしたかと思いきや、
「今日この会場に向かおうと思ったらですね、道がめちゃくちゃ渋滞してるわけですよ。それでこのまま車で行ったら1時間くらいかかって時間に間に合わないと。だから今日、私高橋優は自転車で会場入りしました!いつになってもそういう初心を忘れずにいたい、という曲を歌います!」
と、果たしてそれは初心を忘れないことなのか、とも思ったりもしたが、自転車で会場入りというワードは観客を笑わせていたし、何よりも「プライド」に入る前のMCとしては実にピッタリなものであった。
高橋優はやはり「福笑い」などのポップな曲を歌う人というイメージが強いが、かつてはBRAHMANやTHE YELLOW MONKEYのコピバンをやっていたくらいにロックへの憧憬と影響が強い男であり、それはこの曲フェスでやるの?という「象」で最大限に発揮される。フェスという場を自分の持つ様々な要素をしっかりと見せるものとして使うというのは高橋優の曲をあまり知らないようなロックバンドのファンの人にも「高橋優ってカッコいい曲あるんだな」と思ってもらえる最大のチャンスである。
高橋優はスペシャでかれこれ3年くらい「ローカリズム」というゲスト所縁の地をバスで回るという旅番組をやっているのだが、その番組を見たことがある人?と問いかけるとさすがスペシャのフェスなだけにたくさんの手が上がる。数々の豪華ゲストを招いてきた番組であるが、実際に視聴者の前でライブをやったことがない(番組が始まってからは初出演)だけに、ようやく見てくれている人がこんなにいる、ということを視認できた様子。
さらには今回番組とのコラボで「高橋優の秋田丼」という、ご飯に秋田名物の漬物「いぶりがっこ」をまぶして上にハムカツを乗せたメニューが販売されているのだが、高橋優がエゴサーチした結果、スペシャキッチンの中で1番人気がないんじゃないかというツイートをたくさん見てしまったという。
とはいえやはりそのアーティストの出演日がそのメニューが1番売れる日になるはずで(きゃりーぱみゅぱみゅのきゃりーたぴたぴというタピオカブームを意識したメニューは毎日大人気だったけれど)、この日の秋田丼の売り上げはきっと前日までとは違うものになっていたと信じたいところである。
そんな自虐的なことを吹き飛ばすかのような「明日はきっといい日になる」はこの日が日曜日なために翌日が仕事だったり学校だったりする人たちに勇気を与えると同時に、この曲が聴けて嬉しかった、というような空気が会場内に満ちていく。
そして最後は直前にこのステージに出たHY同様に晴れたこの会場の空気によく似合う「虹」で締め、久しぶりのラブシャ出演でその歌に聞き惚れるとともに、しっかりと爪痕も残した。
スペシャでレギュラー番組を持っているアーティストは基本的に毎年このフェスに出ているが、そんな中ではトップクラスに出ていないアーティストだ。そもそもが毎年いろんなフェスに出まくるというタイプではないし、旅番組の集大成的なフェスを秋田で主催しているというのもある。でもこうしてここでライブを観ると来年以降もまたここでこの人の曲を聴きたくなる。番組が入れ替わる頻度が高いスペシャにおいては高橋優はもうベテランVJと言える立ち位置にいることだし。
1.STARTING OVER
2.福笑い
3.プライド
4.象
5.明日はきっといい日になる
6.虹
13:30〜 Official髭男dism [Mt.Fuji STAGE]
高橋優が終わってMt.Fuji STAGEに行ったらビックリした。これもう観れる場所ないんじゃん?というくらいに凄まじい超満員だったから。そんな期待を寄せられているのはOfficial髭男dism。このフェスには初出演である。
ホーン隊とパーカッションを加えた大人数編成というのはこの広いステージによく似合う中、大型タイアップでたくさんの人にバンドの存在を知らしめた「ノーダウト」からスタートすると、もう完全にこの超満員の観客がみんな待っていた、聴きたかった、という熱気に満ちている。
藤原聡(ボーカル&キーボード)がハンドマイクを持ってステージを左右に動きながら歌う「FIRE GROUND」はこのバンドのルーツと持ち味の一つであるファンクさを強く押し出した曲であり、「ポップなバンド」というイメージだけしか持っていない人が見たらさぞビックリすることだと思う。
そんなイメージの自分たちだけではない部分も見せると、藤原は
「スペシャは学生の頃からずっと見てました。My Chemical Romanceとか、スペシャルを見て知ったアーティストもたくさんいます。だからこのフェスにずっと出たかった」
とスペシャから音楽を教えてもらったこと、だからこそこのフェスに強い思い入れがあることを語る。もしかしたら島根にいる時からこのフェスをスペシャの放送で見ていたのかもしれない。
人生を映画、ではなく映画のフィルムの長さに例えた歌詞が秀逸な「115万キロのフィルム」からはこのバンドのポップな部分を遺憾なく発揮し、藤原のボーカルも後ろまで超満員の観客にまで届かせるように美しく響く。楢崎誠はベースのみならず時にはシンセを弾く(サックスも吹ける)というマルチプレイヤーっぷりでバンドのカラフルかつポップなサウンドを構成する上で重要な役割を果たす。
大ヒット曲「Pretender」を歌詞の通りにキレイに響かせると、ラストはこの夏を彩った「宿命」。テレビ朝日系の夏の高校野球のテーマソングとして起用されただけに、野球ファンとしてもこの曲を聴くと今年の夏のドラマを思い出す。そうしてこのバンドの曲はたくさんの人たち1人1人の生活や人生のテーマソングになっていく。
藤原が口にしたMy Chemical Romanceなどのロックバンドの影響を微かに感じるところもあったが、やはり総じてポップなバンド、ポップなライブという印象だった。そう思うということはこれからもっとたくさんの人の前で、大きなステージで演奏するようになるということだ。
リハ.Tell Me Baby
1.ノーダウト
2.FIRE GROUND
3.115万キロのフィルム
4.Stand By You
5.Pretender
6.宿命
14:15〜 10-FEET [LAKESIDE STAGE]
自身主催のフェス、京都大作戦を最大規模の2週開催しながらも、開催週以外は日本中のあらゆるフェスに出演しまくっている、10-FEET。このフェスにおいてもレギュラーと言える存在。
おなじみの「そして伝説へ…」のSEが鳴り出して観客がタオルをステージに向かって掲げるとメンバーが登場。音を鳴らし始めたと思ったら、いきなりTAKUMA(ボーカル&ギター)が
「10-FEETでした!ありがとうございました!」
と言って何にもしないでライブを終えて帰ろうとする(NAOKIはマジでベース置いて袖に掃けてた)のだが、そんなネタをやって笑わせた後に「RIVER」を演奏してくるというギャップというか落差というか。もちろん初っ端からダイバーが続出するし、TAKUMAは
「流れゆく山中湖〜」
と毎年おなじみの歌詞を変えて歌うが、山中湖は川ではないんだよな、と毎年ここでこの曲を聴くたびに思う。
観客が飛び跳ねまくる「1 size FITS ALL」、巨大サークルモッシュを生み出した「goes on」と客席も曲によって景色を変えていく中、TAKUMAが
「ヤバい曲ができました」
と言って演奏された最新シングル「ハローフィクサー」は同期の音を過去最高クラスに取り入れた華やかな曲。リリース時のインタビューでも言っていたが、10-FEETのバンドとしての新たなチャレンジが見えるし、今までやっていなかったことをやるのが1番自分たちがワクワクできることなのだろう。
しかしTAKUMAはダイバーが落とした靴を客席から拾いあげて、それで電話するフリをしながらその靴を観客に投げ返す。他にも靴が落ちていたらしいが、それは時間がないので後回しにしながら「その向こうへ」「1sec.」でさらにダイバーを続出させると、
「死ぬなよ。自分を傷つけるなよ。またライブ来いよ」
と観客にメッセージを投げかけて、最後に「ヒトリセカイ」を演奏した。TAKUMAは、というか10-FEETは誰のことも否定しない。例えそれが他の人に迷惑をかける自分たちのフェスに来ている人だとしても。だからこそTAKUMAと10-FEETのこうした言葉に救われる人も多いと思う。
去年はSiMのマネをして観客に「goes on」のギターを弾かせようとしたらヤバTのこやまが出てきてギターを弾いたりという、その日その場所にいないと見れないようなライブを見せてくれた。でもそれは毎回そうだ。例えやる曲が変わらなくても10-FEETのライブは毎回その日にしか見れない。だからこれだけたくさんフェスに出まくっていても飽きることがない。
1.RIVER
2.1 size FITS ALL
3.goes on
4.ハローフィクサー
5.その向こうへ
6.1sec.
7.ヒトリセカイ
15:05〜 King Gnu [Mt.Fuji STAGE]
昨年はオープニングアクトだった、King Gnu。もはやテレビ出演は当たり前というくらいの存在になり、初進出を果たしたMt.Fuji STAGEも超満員。髭男もそうだが、今のこのバンドの勢いがうかがえる。
ステージにはバンドロゴのオブジェが置かれる中でメンバーがステージに登場すると、常田大希(ボーカル&ギター)が拡声器を持って歌う、新たな時代のアジテーションソング「Slumberland」からスタートし、井口理(ボーカル&キーボード)がその美声を響かせる「Sorrows」と、今年リリースのアルバム「Sympa」の収録曲を連発するのだが、ブラックミュージックのエッセンスが色濃い「Vinyl」を含めて、勢喜遊のドラムが凄まじい。もともと演奏技術はズバ抜けたバンドであるが、原曲よりもはるかに増した手数は正確無比過ぎて、ともすれば機械のように感じてしまうくらいなのだが全くそんなことは感じず、むしろ人間の持つ熱量によってそれを為し得ているとすら感じられる。
常田と井口というフロントマンに目立ちがちであるが、新井和輝のベースも含めてライブを観るとそのリズム隊のあまりの強さにそちらにばかり目が行ってしまう。常田はインタビューで明確にアッパーな方に行こうと思った、と語っていたがそこにはこのリズム隊の2人による貢献が計り知れないほど大きい。
観客に「ダイエット成功おめでとうー!」と声をかけられた井口が、
「うっせーデブ!どうせお前デブだろ!」
となぜか毒づく中、観客に「歌え!」と合唱を促すも井口のボーカルの上手さとキーの高さになかなかついていけない「Prayer X」から「白日」という流れはこのバンドの持つメロディの力を最大限に発揮する流れであるし、盛り上がりが重要視されるフェスにおいては求められることの少ないバラードをたくさんの人に求められているというあたりも凄いことである。
そんな中で演奏された新曲「飛空艇」はバンドのグルーヴがうねりまくるロックチューン。この曲こそバンドの高い演奏技術あってこそのものであるし、それはライブで観るとより一層そう思える。
「命揺らせ 命揺らせ」
というサビのさを締めるフレーズを
「もう覚えたろ!歌え!」
と井口が合唱を促すが、さすがにまだ覚えきれていないというか、曲に聴き入ってしまって大合唱というところまでは至らず。
そうした観客に歌わせまくるというライブの作り方はこのバンドの音楽性を考えると少々意外ではあるのだが、それはこのバンドが歌の力をしっかりとわかっているからだろう。
そしてラストの「Flash!!」ではメンバーの鳴らす音がバチバチに絡み合う中、間奏で井口はスプレーを噴射しまくりながら踊るというパフォーマンスを見せた。井口はそうした挙動から「ヤバい奴」というイメージを持たれているだろうけれど、自分にはそれは「こうすればこうなるな」というのがある程度わかっているであろう知性的なものを感じる。というかある程度そうした部分を持ち合わせた人間の集まりでないとこの音楽は作れないと思う。
ブレイクしたあたりの春フェスではやはり満員ではあったけれど「白日」が終わったらごっそり人が移動していくという光景も見えた。でもこの日は全くそんなことはなかった。というかそんなことができないレベルまでこのバンドはしっかり達している。アート性とポップさをどの次元で融合できるのかというこのバンドの戦いはブレイクした時よりも何段階も上のステージへ移行している。
リハ.Tokyo Rendez-Vous
1.Slumberland
2.Sorrows
3.Vinyl
4.Prayer X
5.白日
6.飛空艇
7.Flash!!
15:50〜 東京スカパラダイスオーケストラ [LAKESIDE STAGE]
近年はMr.Childrenの桜井和寿などの大物ボーカリストとコラボが続き、ロックファンを驚かせ続けている、スカパラ。30周年を超えても落ち着くことなく、というかより一層フェスに出まくるようになっている気さえする。
最新のえんじ色のスーツを着たメンバーたちが登場すると「DOWN BEAT STOMP」でのっけから踊らせまくったかと思ったのもつかの間、ここからは事前に予告されていたゲストボーカル陣が次々に登場。
まず口火を切ったのは出番を終えたばかりのOfficial髭男dismの4人。自身のライブ時の衣装を着て登場すると、甲本ヒロト(ザ・クロマニヨンズ)がボーカルを務めた「星降る夜に」を4人で歌唱。すでに他のライブでもコラボしているとはいえ、この曲を髭男のメンバーが歌うというのは少し意外。ヒロトがパンク・ロックンロールの生きる伝説みたいな人であるために「銀河と迷路」みたいな曲の方が似合うような気がしていたが、髭男が歌うことによってこの曲の持つポップさが際立つ形になっていたのでこれはそれを狙っての選曲だったのかもしれない。
氷結果汁のCMソングとしておなじみの「Paradise Has No Border」では谷中敦(バリトンサックス)を筆頭にしたホーン隊が前に居並んで圧巻の演奏を見せると、久しぶりのコラボとなるASIAN KUNG-FU GENERATIONのゴッチが黒いスーツにサングラスという出で立ちで登場すると、アジカンとスカパラがバンド同士でコラボした「Wake Up!!」を演奏。ステージ衣装の突っ込みどころの多さに定評のあるゴッチのビシッと決まったスーツ姿もレアなものであるし、サングラスをかけていてもゴッチが本当に楽しそうなのが伝わってきた。これもまた出演日が同じフェスという場だからこそできることだ。
今回はスカパラのライブにゲストボーカルで出演という形であるが、10-FEETのライブにスカパラホーンズが出演することもよくあるだけに、もはや一緒にやり過ぎてて当たり前みたいになっているゲストがTAKUMAであるが、グレーのスーツにハットというフォーマルな出で立ちはいつもとは全く印象が違う。自身も踊りながら歌うTAKUMAの楽しそうな顔は少年のようですらあるが、こうして何度となくコラボをしているのは両者がともにライブをやりまくっていて、こうしてフェスで同じ日に出演していることの結果でもある。
ここまでのゲストはみんな事前に出演が発表されてきたアーティストたちであるが、ここでサプライズゲストとしてステージに登場したのは、このためだけにこの場所に来た、エレファントカシマシの宮本浩次。メンバーとお揃いのえんじ色のスーツを着て「明日以外すべて燃やせ」を歌うその姿はまるでずっとこのスカパラのボーカリストとして歌ってきたかのよう。衣装の効果もあったからか、あるいはほぼ同年代のアーティストだからか、この日のゲスト陣の中では最も自然にスカパラの中に溶け込んでいた。
そしてラストはおなじみの「ペドラーズ」で踊らせまくり、演奏が終わると谷中敦は客席をバックにセルフィーを撮った。最近は毎回やっていることであるが、ゲストボーカリストたちがみんな少年のように楽しそうな顔をしているのはスカパラのメンバー自身が少年のような心を持ったミュージシャンだからなのかもしれない。
30周年を超えてもライブシーンの最前線で戦い続けているだけでも本当に凄い。でもそれだけじゃなく、いつも「この日、この場所でしか見ることができないもの」を見せてくれる。ゲストボーカルが加わる以外の曲をもっと聴きたいスカパラファンの方もいるかもしれないけれど、こうしてゲストが総登場するライブをするのはスカパラのメンバーが来てくれた観客たちに最高に楽しんで欲しいと思っているから。実際、ゴッチや宮本がスカパラで歌う姿が見れて最高に楽しかった。
1.DOWN BEAT STOMP
2.星降る夜に w/ Official髭男dism
3.Paradise Has No Border
4.Wake Up!! w/ Gotch (アジカン)
5.閃光 w/ TAKUMA (10-FEET)
6.明日以外すべて燃やせ w/ 宮本浩次
7.ペドラーズ
16:25〜 カネコアヤノ [WATERFRONT STAGE]
ライブ時間以外は水上バーとしても営業している、WATERFRONT STAGE。2019年のこのステージの最後のアクトとなるのは新進気鋭の女性シンガーソングライター、カネコアヤノ。
ギター、ベース、ドラムというバンド編成でおかっぱ頭でギターを持ったカネコアヤノが登場すると、「とがる」から時折叫ぶようにして歌う。CDで聴いた時にはフォークや歌謡曲というイメージが強かったし、実際にカネコアヤノの紡ぐメロディと生活感のある、情景がすぐに頭に浮かぶような歌詞、さらにはカネコアヤノのボーカルからもそうしたイメージを受けるのだが、そうしたライブならではの歌い方やメンバーの演奏(モヒカン頭にサングラスのいかにもなベースのパフォーマンス含め)はパンク・ロックンロールにそのイメージを鮮やかに塗り替えてみせる。
MC一切なしでひたすらに曲を連発するという手法はカネコアヤノの音楽とライブの魅力を最大限に伝えるものになっていたが、あまりにライブが良すぎて「CDと全然違うじゃん!」とも思ってしまう。よく「音源とライブは別物」とも言われるが、それをこんなにも感じさせてくれるアーティストはそうそういない。それくらいにライブが良い。
最近いろんなフェスに出演するようになっているが、ロッキンではかなり厳しい客入りだったらしい。確かにCDを聴いただけだとあまりフェス向きな音楽とは感じないかもしれない。でもライブを観るとフェスがどうとかではなく、こんなにもライブで見た方が良さがわかるな、と思う人はあんまりいないと思う。赤坂BLITZでのワンマンが平日ですらチケットが手に入らないということになっているのも納得。
この日はWATERFRONT STAGEでは収まりきらない観客が集まっていただけに、来年はMt.Fuji STAGEで見たい。演奏中にステージの後ろの山中湖の湖面に映る太陽は本当にキレイだった。
1.とがる
2.カウボーイ
3.さよーならあなた
4.エメラルド
5.光の方へ
6.恋しい日々
7.愛のままを
17:05〜 Aimer [Mt.Fuji STAGE]
初出演にして始まる前からMt.Fuji STAGEを満員にしている、Aimer。ロッキンではSOUND OF FORESTの番人的な立ち位置になっているだけに、このフェスでも初出演だとFOREST STAGEだったりするんじゃないだろうか?と思っていたけれど、相応のキャパのこのステージへの出演とあって一安心である。
JAPAN JAMで見た時はアコギとキーボードとパーカッションというアコースティックな感触が強い編成であったが、この日は通常のバンド編成。そんな中で真っ白な衣装にメガネをかけたAimerがステージに登場し、今年2枚同時リリースした「Sun Dance」「Penny Rain」のうち、「Sun Dance」の実質的なオープニングナンバーである、デジタルサウンドを取り入れたダンスナンバー「ONE」からスタートし、憂と影を帯びたAimerの独特の歌声がダンサブルなサウンドでポジティブなエネルギーに満たされていく。
アコギをメインにした「コイワズライ」ではそのAimerの声で
「悲しい時こそ 寂しい時こそ
大事なことがあるんだよ」
と歌われるが、このスロットはもうトリの前。3日間のこのフェスの終わりの時が近づいてきている時間帯であり、どうしても寂しい思いが募ってくる。だとしたらそう思うこの瞬間にも大事なことがあるんだろうか。
「ここで歌えることを本当に幸せに思います」
とAimerが口にしてから歌ったのは最新シングルの「Torches」。アルバムが2枚も出たばかりにもかかわらずシングルが出るというのはとんでもないリリースペースであるが、こうして新しい曲を歌えることをAimer自身が楽しんでいるのかもしれない。
徐々に太陽の色がオレンジに変わっていく時間になると、「STAND-ALONE」からはAimerが内に抱えるダークな部分もフェスの短い時間でしっかりと見せていく。2枚のアルバムが全くタイプの違う内容になったことが象徴的であるし、それはベスト盤においてもそうであったが、およそフェスという場に相応しくない猟奇的とも言える歌詞の「I beg you」もAimerの持つポップなだけではない魅力を伝えるものになっている。
とはいえやはりフェスとなると持ち時間が短いだけにあっという間に最後の曲へ。最後に演奏されたのはRADWIMPSの野田洋次郎が提供した「蝶々結び」。例えばさユりの「フラレガイガール」もそうだし、このフェスの直前に見たRADWIMPSのワンマンの時の三浦透子の「グランドエスケープ」もそうだし、洋次郎の作った曲は歌うのが本人でなくても洋次郎の姿が見えるくらいの節みたいなものがある。そのくらいに洋次郎が作る曲な洋次郎以外の誰にも作れないものであるということであるが、Aimerはそれを自分のものにしながらもやはり洋次郎節を感じさせる。そしてそれによってAimerはこういうフェスに来るようなロックファンから発見されたのである。
歌い終わると丁寧にAimerは観客に頭を下げたが、神殿のようなMt.Fuji STAGEの作りや、そこに背後から射し込む夕暮れの明かりとそこに降り注ぐAimerの魔力を纏った声…まるでこのステージでワンマンをやっているかのようにあまりに似合いすぎていた。それはただ単にキャパに見合うというものではなく、Aimerがこの景色に最も似合う存在だったということだ。
1.ONE
2.コイワズライ
3.Torches
4.STAND-ALONE
5.I beg you
6.蝶々結び
17:50〜 ASIAN KUNG-FU GENERATION [LAKESIDE STAGE]
かつてはこのフェスのこのステージで大トリを務めたこともある、アジカン。今年はその一つ前の時間帯に登場。
初日に自身のバンド、the chef cooks meのボーカルとして出演したシモリョーもサポートキーボードとしてメンバーと一緒にステージに登場すると、当たり前だがゴッチはスカパラの時のスーツ姿ではなくいつも通りのラフな姿で、「ホームタウン」ツアーのオープニングを担っていた「UCLA」でスタートし、静かにゴッチが語りかけるメロ部分からサビでゴッチが腕を上げると一気にエモーションが炸裂していく。
喜多建介のギターソロが今日も炸裂する名曲「荒野を歩け」も「ホームタウン」収録曲という最新モードを示す序盤だったが、映画のタイアップ曲ということやフェスでも毎回演奏されてきた曲ということもあってか、「ラルラルラ」というコーラス部分では合唱している人も多く、今やこの曲はアジカンの代表曲の一つと言ってもいい存在になっていることを実感する。
かと思えば伊地知潔が4つ打ちのリズムを刻む「君という花」と新旧の代表曲が並ぶという流れになり、当然のように「らっせーらっせー!」の大合唱が。最近はやらない日も多くなってきた曲なだけに聴けて嬉しかったという人も多いんじゃないかと思う。
ゴッチが軽く挨拶すると、新曲と言って演奏されたのは「Dororo」。春フェスや「ホームタウン」ツアーの前半戦では両A面の曲である「解放区」が演奏されることも多かったが、タイトルにもなったアニメが完結してからはこの曲が演奏されることも多くなってきている。
「闇の奥に光が在って 遠く声を確かめ合って
濡れた指先で撫でるように いつか君に触ってみせるよ」
というサビのフレーズを聴くと、百鬼丸とどろろの旅とアニメの後日談を頭の中に浮かべてしまう。
「このフェスには初開催された年にトップバッターで出たのをよく覚えています」
とゴッチが2007年に出演した時のことを回想していたが、すでにロックシーンの中で最も巨大な存在と言っていい立ち位置になっていたアジカンがトップバッターで出演したのは、出番が終わった後に同じ日に開催される他のフェスに出演したからであり、当時ライブスケジュールが発表された時に「ダブルブッキング?」と言われていたのを思い出す。まだメインステージがMt.Fuji STAGEだった頃で、その年は2日とも天気が悪くてすごく寒かったことを思い出す。
山田貴洋のベースから始まるセッション的なイントロの演奏の「センスレス」から、ゴッチが高くギターを掲げてかき鳴らす「Standard」とツアーなどではおなじみの曲たちをフェスという場でも堂々と鳴らしてみせる。
「こうやって毎週どこかでフェスが開催されていて、日本中に俺たちが演奏する場所がある。本当に嬉しい」
とゴッチが語る。フェスが多すぎると言われることもある今のシーン。そんな中でNANO-MUGEN FES.を主催して日本のフェスシーンを作ったアジカンが今の状況を楽しみ、希望を感じている。こうして毎週のようにフェスに行っている我々のように。いつかはまたNANO-MUGENをやって欲しいという思いが強いのはあのフェスがあったからこうしていろんなフェスに行くようになったとも言えるからであるが、これからも毎年いろんなフェスのステージに立つアジカンの姿が見れるはずだ。
そしてラストはそうした状況すらも、まだ始まったばかりと歌う「ボーイズ&ガールズ」。
「リライト」も「ソラニン」もないし、「Re:Re:」あたりもやっていないというのはかなり攻めたイメージが強く見えるかもしれない。でもアジカンが「リライト」や「ソラニン」だけのバンドなら20年経ってこんな大きいステージに立てていない。常に自分たちをアップデートしていくという意識を「ホームタウン」というアルバムとそのツアーで見せていたし、この日演奏した曲たちも近年のアジカンのライブを担ってきた曲たちだ。そう考えると毎回ツアーに行っている身であっても、このバンドが生み出してきた名曲の多さに改めて唸らされてしまう。
1.UCLA
2.荒野を歩け
3.君という花
4.Dororo
5.センスレス
6.Standard
7.ボーイズ&ガールズ
18:30〜 ストレイテナー [FOREST STAGE]
かつてはLAKESIDE STAGEにも立ったり、ライブ後にホリエアツシ(ボーカル&ギター&キーボード)が普通に飲食ブースを歩いたりしていた、ストレイテナー。久しぶりの出演で若手アーティストが熱演を繰り広げてきたFOREST STAGEの3日間を締めくくる。アジカン→テナーというこのタイムテーブルの流れも実にたまらないものがある。
おなじみのSEでメンバー4人が登場すると、セッション的な演奏からイントロに繋がる「DONKEY BOOGIE DODO」からスタート。最近再びセットリストに入ってきているみたいだが、
「僕らは歌い踊ろう SWEET LOVE SHOWERで!」
と歌詞をこの場所に変えて歌うホリエのアレンジはやはり見ていて実に昂ぶるポイントだ。
ひなっちこと日向秀和のゴリゴリのベースラインからサビで一気にメロディの光が拓けていく「DAY TO DAY」を演奏すると、ホリエがキーボードを弾きながら歌うのは「灯り」。秦基博とのコラボソングであるが、この暗くなった夜の野外という景色が実に似合う選曲。
さらに最新曲「スパイラル」とバンドの今のモードをしっかり見せていくが、そこからうかがえるのはこのバンドがメロディをしっかりと聞かせていくというスタイルになっているということだ。それでいてやはりこのメンバーであるロックバンドなだけにソリッドな部分は失われていない。
そして「Melodic Storm」で合唱という名の嵐を巻き起こすと、最後に演奏されたのはホリエが
「まだ夏は終わらないぜ!」
と言いながらも
「今年最後の海へ向かう」
と歌う「シーグラス」。それはこのバンドがこのフェスが終わってもまだまだいろんな場所に演奏しにいくということを示していた。
アンコールを求める観客の前にメンバーが急いで登場するも、
「ごめん、アンコールの時間なくなっちゃった!」
と言って曲は演奏せずに4人が肩を組んで一礼した。それでも全員がステージに出てきてくれるのがこのバンドらしいな、と思った。
「スペシャにはインディーズの頃からずっとお世話になってます。今の日本の音楽シーン、特に俺たちみたいなバンドシーンがあるのはスペシャのおかげだと思っています」
とホリエは語っていた。テナー自身もシンペイがレギュラーコーナーを持ったりと、スペシャと縁深い人生を歩んできただけに、何年かに1回じゃなくて、毎年のように出るバンドであってもいいのに、と思うくらいに「シーグラス」をMt.Fuji STAGEで山中湖の湖面が見える中で演奏する姿を見たい。
1.DONKEY BOOGIE DODO
2.DAY TO DAY
3.灯り
4.スパイラル
5.Melodic Storm
6.シーグラス
19:35〜 SEKAI NO OWARI [LAKESIDE STAGE]
今年の大トリは実に8年ぶりにこのフェスに帰還することになった、SEKAI NO OWARI。まだ当時は「世界の終わり」名義だったし、4人が真っ白い服を着て活動していた時期だった。果たしてどんなパフォーマンスでこの3日間を締めくくるのだろうか。
だいぶ予定時間を遅れて(Mt.Fuji STAGEのトリのMISIAが結構押してた気がする)メンバーがステージに登場すると、いつものようにフォーマルな服にメガネをかけたNakajin、黒いドレスに金髪がよく似合うSaori、ピエロでしかないDJ LOVEに続いて、赤みが強い紫色の髪に大きなネックレスを着用して、どこか胡散臭い占い師みたいな出で立ちのFukase。自然が多い野外フェスの夜の時間に聴くからこそまさにカーニバルだと実感できる「炎と森のカーニバル」から始まるのだが、あまりにライブを見るのが久しぶり過ぎてビックリしてしまったのは、リズムが生音になっているということ。メンバーの後ろには馬の頭のようなものを被ったドラマーとウッドベース奏者がおり、ライブならではの音のダイナミズムをかつて以上に感じさせてくれるようになっている。
今年このバンドはダークな「Eye」、ポップな「Lip」というコンセプトによって収録曲を分けたアルバムを2枚同時にリリースしているのだが、その中でもダークなバンドの姿勢を示す「ANTI-HERO」、山下公園やみなとみらいあたりの景色が頭に浮かんでくる「YOKOHAMA blues」、さらにはFukaseがCMに出演して話題を呼んだ「RAIN」と新作収録曲を連発するのだが、Fukaseがベースを弾いたり、Nakajinがパーカッションを叩いていたりと、メンバーのマルチプレイヤーが進行したことによって、より「楽団」というイメージが強くなっている。ファンクラブ向けのライブではDJ LOVEがドラムを叩いていたというし、そうした弛むことのない向上心がこのバンドをなんでもできる存在たらしめている。
この山中湖の夜空に最高に似合っていたのが「スターゲイザー」。デジタルなサウンドの上をFukaseの「スターゲイザー」というタイトルフレーズが輝く。あまり星は見えなかったが、湖畔の対岸に見える民家の明かりはまるで星空のように美しく感じた。
「8年ぶりの出演です。僕らはちょっとフェスシーンっていうところから離れていたんですけど、こうしてみんなが最後まで残ってくるていて本当に嬉しいです」
とNakajinが挨拶すると、
「僕の原点のような曲」
とFukaseが言って演奏されたのは「銀河街の悪夢」。かつてのFukase少年の心境をそのまま歌詞にしたかのような曲がここにいるたくさんの人に共有されていく。
そしてバンドにとって大きな転換点的な曲となった「RPG」から、あっという間のラストはやはり「Dragon Night」。ステージからは炎が噴き出し、Nakajinはフレーズごとにギター、パーカッション、さらにはバンジョーと楽器を使い分け、SaoriはFukaseの隣でアコーディオンを弾く。そしてEDMサウンドに合わせて飛び跳ねまくる観客たち。8年前にMt.Fuji STAGEに出た時は曇っていて
「富士山が観れるステージって聞いてたのに〜」
とSaoriが言っていた、まだ昼が似合う若手バンドだった。それがまさかこんなバンドに進化するなんてあの頃は全く想像していなかった。曲、演奏、見せ方…全ての面でこのステージの夜、つまりトリに相応しいバンドになっていた。だからこそより一層、終わった後に上がった花火が美しく感じられた。
でもきっと、今のこのバンドのワンマンの映像を見る限り、ワンマンはフェスの何倍も、というか比べ物にならないくらいに素晴らしいんだろうな、と思う。
それこそ8年前にこのフェスに出ていた時期前後は自分も毎回このバンドのワンマンに行っていた。まだ「EARTH」しか出ていなかった頃の渋谷公会堂や日本武道館、代々木体育館、自分の住んでるすぐ近くの市川市文化会館など。でもそれこそ「RPG」リリース後あたりから少し離れてしまうという実にわかりやすいロックバンドリスナーだったのだが、この日たくさんの「新しい日本のポップミュージック」を生み出そうというアーティストの最高到達点であり最先端にいるのがセカオワだと思った。それを余すことなく体験できるであろうワンマンに久しぶりに行ってみたいと思った。それはこのバンドが再びこのフェスに戻って来なかったら芽生えなかった感情だ。そういう意味でも、最大限の感謝を込めて、おかえりなさい。
1.炎と森のカーニバル
2.ANTI-HERO
3.YOKOHAMA blues
4.RAIN
5.スターゲイザー
6.銀河街の悪夢
7.RPG
8.Dragon Night
ライブ後にスクリーンに映し出されたこの日のハイライト的な映像を見たり、クロージングDJのTENDREを少し見たり。終わってしまったあとにこんなにも帰りたくないと思うフェスはそうそうない。
それはこのロケーションの素晴らしさ、この場所の持つ魔法のような力によって見ることができた奇跡のようなライブの数々。そして全然関係ない参加者にすらも挨拶してくれる民間の駐車場の方々や、毎年お世話になっている民宿の方などのこの場所で生活している人たちの優しさ。そうし全ての要素が来年も絶対にここに来ようと思わせてくれる。
このフェスが開催され始めた2007年頃は、まだ9月や10月にフェスはほとんどなかった。だから今年のあいみょんやセカオワのように、このフェスが最後の夏フェスというアーティストばかりだった。だからこそ夏の最後の思い出をこの場所に刻むような素晴らしいライブをたくさん観てきたし、このフェスで見て良くなかったライブというのは全くない。
そんなこのフェスに自分は初回から来ている。どんなに好きなフェスであっても今から初年度の年に戻って参加することはできない。ロッキンのように。でも運良く自分はこのフェスのその瞬間に居合わせることができた。
でも2008年と2009年だけは自分は参加していない。社会人になって、フェスに行くということが難しくなってしまったタイミングだった。(ロッキンだけは無理矢理行った)
だからこそ、その会社を辞めた時に真っ先にまた絶対行ってやろうと思ったのがこのフェス、この場所だった。それから10年、今でもずっとその想いが変わらないからこそこうして行き続けている。
そのくらい思い入れが強いフェスだからこそ、楽しければ楽しかったぶん、終わってしまうとより一層寂しくなってしまう。でもまた来年になればあそこに行けると思えば、それは1年間生きていくための原動力になる。そうやって生きていく理由が増えていく。まだまだ死ねないし、やめられない。だから山中湖、また来年。あるいはどこかプライベートで遊びに行くことができたなら。
文 ソノダマン
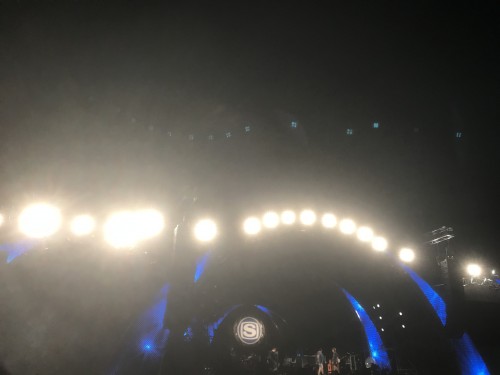

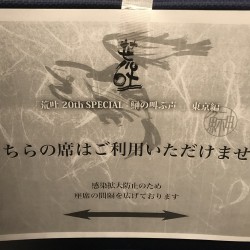
![LIQUIDROOM 15th ANNIVERSARY 「THE THREE KINGS」 THE BAWDIES / the telephones / [DJ] FREE THROW 恵比寿LIQUIDROOM 2019.8.19 LIQUIDROOM 15th ANNIVERSARY 「THE THREE KINGS」 THE BAWDIES / the telephones / [DJ] FREE THROW 恵比寿LIQUIDROOM 2019.8.19](https://moretzmusic.com/wp-content/uploads/2019/08/4-250x250.jpeg)


