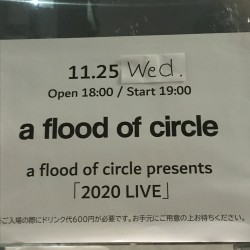昨年は11月にぴあアリーナMMにて開催されたが、例年は夏に東扇島公園、冬に川崎クラブチッタでオールナイト開催されている、BAYCAMP。
そのBAYCAMPの若手主体の見本市的なライブハウスでのイベントが「DOORS」。昨年9月にも新木場STUDIO COASTで開催されており、本来は2月に開催予定だったのが延期になってのこの時期の開催である。
検温と消毒、さらには来場者フォームへの入力を済ませてから入場すると、敷地内にはフードトラックも並び、普段は物販などで使われている場所に設置されたDJブースからは低音が外まで響いてくる。
客席は足元に立ち位置が表示されたスタンディング方式であり、メインのDOORS STAGEとセカンドのGOLDEN STAGEの2ステージ制というのはこの新木場STUDIO COASTでのフェスの形である。
11:40〜 湧 [Welcome act]
ステージ背後には光る花のような装飾が施されているのが、BAYCAMPのEAST ISLAND STAGEを彷彿とさせる、GOLDEN STAGE。Welcome actとしてこのステージに最初に立つのは京都のバンド、Marie Louiseのボーカルの湧。
フライングVを持って1人ステージに登場すると、挨拶から弾き語りがスタート。
「生きてるのが作業みたい」
というパンチラインが深く強く刺さるのは歌とギターだけという弾き語りだからこそであるが、
「OLになりたいな」
という歌詞はどこかクリープハイプなどの影響なども感じる。それは決して突飛な言葉を使うことなく強い歌詞を描けるというスタイルも含めて。
ギターからシンセに持ち替えて同期の音も使うという、弾き語りというだけではない自身のマルチプレイヤーっぷりを見せながらも静謐なサウンドと歌を響かせていくのだが、途中でドラマーが加わるとその生のビートによって一気にサウンドはロックに振り切っていく。
リリースしたばかりの最新アルバムから曲では
「もうすぐ夏が来るよ〜!」
と言って演奏されたが、
「生き残り同士 生きろ 生きろ」
という歌詞は冒頭の「作業みたい」な日々を超えて掴んだ生へのエネルギーを感じさせるというストーリーを描き、
「ずっとBAYCAMPに出るのが夢だった。夢は必ず叶うとか、努力すれば報われるみたいな無責任なことは言いたくないけど、言霊みたいなものは必ずあると思う。口にしないと叶うものも叶わない」
と、このBAYCAMPが夢の一つだったことを自身の言葉として発し、やはり最後もドラムが激しいビートを刻み、湧はフライングVを掻き鳴らしながら歌った。次はバンドとしての形で見てみたいと思った。
12:15〜 Helsinki Lambda Club [DOORS STAGE]
開演前には主催者のP青木の挨拶。この状況であるが故にライブ制作会社としての厳しい現状が言葉の端端から伝わってくるが、まだ時間あるからと言ってWelcome actの湧や、この日のトリのAwesome City ClubについてP青木なりの言葉で紹介をする。結果的にはこの後のタイムテーブルは時間押しまくることになるのだが。
メインステージであるDOORS STAGEのトップバッターは、昨年のBAYCAMPにも出演し、このBAYCAMP関連のイベントの番人的な存在のバンドになりつつある、Helsinki Lambda Club。
メンバーが登場すると、まだ早い時間ということもあってか観客の目を覚まさせるようなアラームの音が鳴り、それが止まるとVAN HARENライクなイントロが鳴る「午時葵」からスタート。その壮大な、このバンドの持つポップさが広いステージだからこそより強く実感できる。橋本薫(ボーカル&ギター)はやや髪が短くなっている印象。
ラジオのDJのようは曲紹介コメントから、一気に熊谷太起のギターがノイジーに振り切れる「ミツビシ・マキアート」では独特のステップを見せる変態ベーシストの稲葉航大がその長い髪を思いっきり髪を振り乱しながら演奏し、かと思えばサイケポップな「何とかしなくちゃ」、ローファイヒップホップな「IKEA」と、曲ごとに目まぐるしくサウンドが変化していくが、全て借りてきたような感じが全くないのは音楽マニアが揃うメンバーだからこそ、もともと自分たちの中にあるものをアウトプットしているだけだからである。そのサウンドをガラッと変える最大のスイッチは熊谷のギターである。
橋本は昨年11月のBAYCAMP出演時にその行き届いた感染症対策に驚いたことを語ると(BAYCAMPはダスキンと提携して消毒スタッフも動員している)、さらに深いところへ誘うような「Good News Is Bad News」、
「立食パーティーをやらなくちゃ
何がなんだってやらなくちゃ
お洒落と消毒は徹底してね
足りないものはないようにしてね」
という歌詞が今の政治や社会に向けられた橋本なりの視線であるようにも感じる、昨年リリースのアルバム「Eleven plus two / Twelve plus one」収録の「Shrimp Salad Sandwich」と、バンドの今の形を提示することがそのまま今の状況を鳴らすことと同義となっている。
すると橋本は
「新木場STUDIO COASTのメインステージに立つのは初めてです。少しは広いステージが似合うバンドになってきたんじゃないかと思ってます」
と、何度となく出演してきているだけに意外にもこっちのステージに立つことが初めてであり、7月にはこの会場でワンマンをやることを告知する。
UKFCのオーディションを勝ち抜いてこの新木場STUDIO COASTのセカンドステージに登場して以来、UKFCには何回も出演しているし、Czecho No Republicの主催フェスでもセカンドステージに立っている。だからこそいつも飄々としていながらも、メンバーにとってもこのステージに立てるようになるのは一つの目標だっただろう。
そのUKFCに初登場した時からの持ち曲であるラストの「シンセミア」は、同じ曲であっても当時とは全く違う風格のようなものを感じた。
「盛り上がる以外の方法を」
という歌詞の通りに、盛り上がる以外の方法でこのステージまで到達したこと。それは橋本のアウトロでの言葉にならないようなシャウトからも溢れ出ていた。
幅広すぎる音楽性ゆえになかなかわかりやすく売れたり、一気にステージが大きくなることはない、本当に1歩1歩進んできたバンドだ。デビュー当時から良いバンドが、良いバンドっぷりを少しずつ更新してきたような。
あのオーディションを勝ち抜いて出演したUKFCのライブを自分は見ていた。その時は稲葉の挙動がとにかく癖になるくらい面白いし、「ユアンと踊れ」のような曲に独特の捻くれた魅力を感じていた。だからこそ、この日メインステージに立つ姿と橋本の言葉にはつい感情的になってしまった。あのバンドがここまで来たのかと。
そんなバンドがワンマンで立つこのCOASTのステージ。ここに初めて出演した瞬間を見届けた者としては、行くしかないんじゃないかと思っている。
1.午時葵
2.ミツビシ・マキアート
3.何とかしなくちゃ
4.IKEA
5.Good News Is Bad News
6.Shrimp Salad Sandwich
7.シンセミア
13:00〜 時速36km [GOLDEN STAGE]
昨年はこうしたフェスやイベントがほとんど開催されなかっただけに、若手バンドのライブを見る機会も少なかった。
そんな中でもまだコロナ禍でライブがなくなる前の昨年2月の渋谷CLUB QUATTROで開催されたイベントに出演していたので、時速36kmは自分にとっては昨年ライブを見た数少ない若手バンドの一つである。
4人がステージに現れると、仲川慎之介(ボーカル&ギター)がいきなりその衝動をぶち撒けるように叫ぶようにして歌う「スーパーソニック」からスタートし、Tシャツに短パンというライブキッズスタイルのオギノテツ(ベース)もマイクを通さずに叫びまくっている。
その姿を見て、わずか1年、しかもライブがほとんど満足に出来なかった期間もあったにもかかわらず、「変わった」と思った。
確かに前に見た時もライブの方が音源よりもはるかに良いバンドだと思ったし、それはステージから、メンバーから衝動を感じたからこそそう思ったのであるが、その衝動の質やレベルが圧倒的に変わっている。むしろ満足にライブが出来なかった期間があったことによって、こうしてライブが出来ることの喜びや楽しさを改めて感じながら音を鳴らせるようになったというか。
だから「銀河鉄道の夜明け」「アトム」と、フォークの要素が強い曲も多々あるこのバンドの中でもそうした要素よりも、とにかくギターを大きな音で掻き鳴らして、ベースと爆音を速く強く刻みまくるんだ、という意識を感じるようなキラーチューンを連発していく。
「BAYCAMP、初めて出させていただいてありがとうございます。こうして出れるというのは、関係者の方が僕らのライブを見て、あいつらを呼んでみようと思ってくれたからだと思ってますので本当に感謝していますし、いつも僕らのライブを見に来てくれる方々がいるから、そうして関係者の方が観に来てくれた、全てのことがこのステージに繋がっていると思います」
と、前髪が長い故に表情まではハッキリと見ることはできないが、仲川は自分なりの言葉で本当に嬉しそうにこのステージに立てていることの感慨を語った。
そして夏にリリースすることが決定しているフルアルバムからの新曲「鮮烈に」もそのタイトル通りに鮮烈な衝撃が走るような、このバンドの中ではかなり尺が短い、駆け抜けるようなロックサウンド。
さらには
「ファンファーレと熱狂」
という、このバンドのロックの衝動の源泉が伺えるようなフレーズも登場する、バンドにとっての最大のキラーチューン「夢を見ている」ではかつてのようにサビを観客が一緒に歌うことは今はできない。
それでも石井”ウィル”開が小さいステージの上で高くジャンプしてギターを弾き、松本ヒデアキがスティックを高く振り下ろしてドラムを打つ。その姿を見て観客は腕を挙げる。その光景を見ていると、この状況であっても自分はまだ、これからもずっとロックバンドという存在に夢を見ていると思う。
そしてラストは
「何度でも ハロー」
という締めのフレーズが激しいサウンドの中でも再会のためのテーマとして響く「ハロー」。わずか30分のライブとは思えないくらいの体力の使い果たしっぷりは、それも理解できるくらいの濃密なインパクトと余韻を我々に与えてくれた。
昨年このバンドのライブを見たイベント。トリのPK Shampooのライブ時にこのバンドのメンバーやCRYAMYのメンバーが次々にステージから客席にダイブしていった光景を見て、これから先はこのバンドたちがロックシーンを引っ張っていくようになるのかもしれないと思った。
今はまだ見ることができないその景色がまた見れるようなライブハウスを取り戻せる時には、このバンドにそういう存在になっていて欲しい。そう思えるライブを見せてくれるバンドになった。
1.スーパーソニック
2.銀河鉄道の夜明け
3.アトム
4.鮮烈に
5.夢を見ている
6.ハロー
13:45〜 ドミコ [DOORS STAGE]
昨年11月のこのフェスではアリーナ規模の会場を2人だけのサウンドで飲み込んだ、ドミコ。昨年のこの会場での「DOORS」はトリだったが、今回はこの前半での登場。
ステージ中央のアンプの上にはおなじみの「Domico」の電飾が光る中、下手には髪型がサッパリした感じの長谷川啓太(ドラム)が、上手にはより髪がバランス良く伸びた感じがするさかしたひかる(ボーカル&ギター)が登場し、さかしたが自身のギターをループさせて重ねていく「おばけ」「化けよ」から濃密なサイケデリック空間を生み出していくのだが、そのさかしたの曲終わりでの
「サンキュー!」
の言い方の強さが明らかにかつてとは違ったものになってきているのは、基本的にはステージ上ではほとんど喋らないし、表情なども感情の変化をあまり感じせないタイプでありながらも、彼なりに今の状況でもライブができていること、それを観に来ている人がいることへの思いが現れているんじゃないかと思う。
ドミコはそんな昨年からの状況においてもツアーを周り、しかも1日2公演もやったりしてきただけに、このコロナ禍でもトップクラスにライブを重ねてきたバンドであるし、進化してきたバンドでもある。それが感じられるのはさかしたのギターと長谷川のドラムの音はもちろん、さかしたのボーカルもだ。
初めて見た時はボーカルを音の一つというような感じで使っているように感じていたのが、今はそれを歌として歌っているかのような。それこそがライブを重ねてきたことによって獲得してきたボーカル力の向上である。
オクターバーなどを駆使してさかしたがギターの音を重ねていくのも、今この瞬間に鳴らしている音の重なりであるだけに、ライブごとに違ったものになる。だからこそ自分は昨年見た時よりもサイケデリックさを感じたのだろうし、その重なっていく音はこの広いステージならではの照明と同様に、一層目が赤で二層目が青、それが重なることによって紫になっていくという変化を見せる。そう考えると、派手な演出などを用いるバンドでは決してないけれど、こうした広いステージに立つべくして立つようになったバンドと言えるだろう。
そんなサイケデリックさを一気にノイジーなギターによってロックンロールに転換するのが、今やこのバンドのライブの締めの定番になりつつある「ペーパーロールスター」。間奏やアウトロではセッション的な、さかしたが長谷川のドラムに近づいたり、逆に離れていったりという距離感がそのまま音の大きさ、激しさに繋がっていく。そしてそれがキメでの音の爆発を巻き起こす。その爆発が収まる前にステージから去っていくというのも、めちゃくちゃ潔いと思う。
リハ.まどろまない
リハ.united pancake
1.おばけ
2.化けよ
3.噛むほど苦い
4.なんていうか
5.ロースト・ビーチ・ベイベー
6.問題発生です
7.びりびりしびれる
8.ペーパーロールスター
14:30〜 岩崎優也 [GOLDEN STAGE]
デビュー時に少し話題になった、SUNNY CAR WASHというバンドがいる。andymori直系のギターロックサウンドはもちろん、他のバンドを名指しでガンガンディスるという心臓の強さでもって話題になったりしたのだが、そのバンドのボーカルの岩崎優也は2019年に体調不良で活動を休止、その間にはドラムが脱退、ようやく昨年活動再開を発表したと思ったらコロナでライブができないという、デビューからの短期間であまりにも激しい浮き沈みを経てきた。
そんな中でのこの日は岩崎優也という単独名義での出演のため、ソロ活動もしているし、1人で弾き語りという形でもライブがしたいんだろうな、と思っていたのだが、ステージに出てきたのは完全にバンド編成の3人組、しかも「それだけ」「ラブソング」というSUNNY CAR WASHの曲を演奏するという、性急でありながらも素朴極まりないSUNNY CAR WASHのライブそのもので、岩崎も曲間では普通に
「SUNNY CAR WASHです」
と挨拶をする。これは誰しもが、それこそ岩崎を観にきたサニカーのファンまでもが全く予想していなかったサプライズである。
岩崎も長髪の羽根田剛(ベース)も時折飛び跳ねたりしながら演奏するのだが、あまりにも長いライブのブランク故か、完全に音もボーカルもヘロヘロである。力強さとか精密さとか、そうしたものとは程遠い。
でもそれがサニカーらしさというか、体調を崩して活動を止めざるを得なかったのがわかるくらいに、ちょっとでもバランスが崩れたらそのまま崩壊してしまいそうな儚さが満ち溢れている。その姿がこれまでの活動や曲の説得力になっているのだ。
ミラーボールを指差して岩崎が羽根田に、
「球があるね。球…好き?地球も球だもんな」
と、あまりにも意味不明過ぎる問いかけをするあたりは心配になったりもするが、「ムーンスキップ」あたりからはかなり調子を取り戻すというか、会場の空気がこのバンドのものに変わってきていたのを感じていた。驚きが歓迎や喜びに変わっていたというか。
そうした頃にはすでにライブは後半、10代の持つ衝動を音にして炸裂させるような「ティーンエイジブルース」はやはりandymori直系と呼ばれていたことを思い出すが、あまりにも安定という言葉とは対極にいるというところもandymori直系だからこそなのかもしれない。やはり最後に放たれた、バンド最大の名曲「キルミー」を聴きながらも、どうかこの人やこのバンドを誰も殺さないように、と思っていた。それくらい、復活したといっても1年先どころか1日先の保証すらも感じられないライブ。でもそれこそがロックバンドというものなのかもしれない。
1.それだけ
2.ラブソング
3.とっこ
4.デイドリーム
5.BBB
6.ムーンスキップ
7.ティーンエイジブルース
8.カーステレオ
9.キルミー
15:15〜 NOT WONK [DOORS STAGE]
昨年、アジカンのZepp Yokohamaでのライブのゲストで、NOT WONKの加藤修平がソロで出演していたのを見た。今回はようやくバンド形態でのライブが見れる機会である。
メンバー3人が登場すると、フジ(ベース)がイントロで手拍子を叩く、このご時世でもライブの楽しみ方としては過不足ない「spirit in the sun」からスタートするのだが、アジカンのゲスト時のピアノやギターを弾きながらのソロの時にも感じたように、加藤のボーカルはまるで聖歌を歌っているかのように美しい。それは今年リリースされた、よりR&Bに接近したサウンドの新作アルバム「dimen」の曲でより顕著であるし、実際にライブ冒頭はそのアルバムの曲順通りの流れである。
フジだけでなく加藤も手拍子を叩いたりしながらも、
「大変な状況の中ですけど、開催できて素直に良かったと思ってるし、こうして久しぶりにライブができて楽しい」
と、率直な感想を口にする。北海道の苫小牧でインディペンデントな活動を続けているバンドであるが、やはり北海道も(特にライブハウスが多い札幌は)今はなかなかライブをやるのが厳しいんだろうなと思う。いろんなバンドが札幌のライブを延期したり、ライブハウスが閉店したというニュースを目にしてきただけに。
しかしNOT WONKは今でこそサウンドはかなり、というか大幅に変化してきたが、当初はHi-STANDARDやELLEGARDENの影響も感じる(英語歌詞という部分も含めて)パンクバンドであった。
後半ではそうしたバンドのパンクな、というよりもグランジやオルタナ、さらにはハードコアの要素を強く感じるサウンドへと転じていき、だからこそ加藤のボーカルもそうしたサウンドに合わせた、丁寧にというよりも衝動的に叫ぶというものに変化するのだが、そこからは影響を受けたパンクバンドというよりも、北海道に脈々と流れるハードコアにも通じる先輩たちの血のようなものを感じる。(加藤はソロでもキウイロールの曲をカバーしていた)
それはやはりライブをすることを楽しいと感じているからこその開放感も感じさせたのだが、ラストの「dimen」からの「the place where nothing’s ever born」は今のバンドの音楽性を強く示すようなムーディーなサウンドで、立ち位置の決められた観客たちの体を心地良く揺らしていた。
1.spirit in the sun
2.in our time
3.slow burning
4.Down the Valley
5.dimensions
6.This Ordinary
7.the place where nothing’s ever born
16:00〜 さとうもか [GOLDEN STAGE]
今や岡山出身のアーティストで最も有名になった存在といえば藤井風であるが、藤井風同様に岡山出身のシンガーソングライターである、さとうもかがこのイベントに出演。
ここまでの出演者は全てバンド編成だったが、ステージに現れたのは金髪を結んださとうもかただ1人で、ギターを抱えてバックトラックを流すという形での「オレンジ」を歌い始めるが、ギターも決してメインのサウンドではないだけに、ほとんどカラオケ状態というのはこのイベントにおいて逆に斬新である。
それはそのポップなサウンドもまた然りで、エッジの立ったロックなサウンドを浴び続けてきた後だからこそ、「Lukewarm」は歌詞の通りにどこかぬるい風呂に浸かっているかのような心地良さに包まれる。
さとうもか本人のボーカルはやや不安定なところもあるが、
「こんなに人がいるライブハウスは久しぶり!」
と言っていただけに、これからこうしてライブを重ねていくことでもっと安定していくと思われる。
本人は発売日をちゃんと把握できていなかったが、翌週の5月26日にメジャーデビューシングルをリリースするということで、そのシングルに収録される「Destruction」をいち早く披露すると、ギターを下ろしてハンドマイクでのカラオケ歌唱となる、関ジャムでも紹介された「melt bitter」へ。
メロウかつアーバンなサウンドのポップソングであるが、バックトラックはほとんどがバンドサウンドの楽器で構成されている曲なだけに、ライブでもそうしたバンド編成で演奏されたらもっと曲の良さやライブの良さが引き出されるんじゃないかと思う。今の若手ヒップホップアーティストもほとんどがバンド編成でライブを行っているだけに。
そんな中で出色だったのがバックトラックを使わないでアコギの弾き語りで演奏された「愛ゆえに」。きっとこの曲を家でイヤホンで聴きながら自身の恋愛を思い返す若い人もたくさんいるんだろうなと思うし、それはさとうもか自身の経験による歌詞だろうからこそ、この自身の歌とギターのみという音で鳴らされているのが沁みてくる。
そして最後は再びバックトラックを流しながら、メジャーシングル収録のカップリング曲「いちごちゃん」と、タイトル曲「Love Buds」の連打という、徹頭徹尾最新モードかつ今のさとうもかのポップモード。
それこそリリース時に話題になった、夏の到来を期待させる「Glints」のような曲の方がこのイベントに来ている観客のウケは良かったかもしれないが、それ以上に今新しく世に出ていく曲の方がはるかに自信を持っている。そんなメジャーデビューへと足を踏み出すさとうもかの現在を感じられる30分だった。
1.オレンジ
2.Lukewarm
3.Destruction
4.melt bitter
5.愛ゆえに
6.いちごちゃん
7.Love Buds
16:45〜 羊文学 [DOORS STAGE]
ライブハウスでの2ステージ制であっても、やはり動員には結構差が出る。目当てのアーティストではない時間は外でケバブやラーメンを食べたりするというのも長丁場のイベントでは欠かせない時間であるし、それもまたフェスやイベントの楽しみ方でもあるからである。
そんなこの日の中でも動員力としてはおそらく最高クラスだったのが、羊文学。今のこのバンドの注目度の高さを示している。
SEが鳴ると、塩塚モエカ(ボーカル&ギター)と河西ゆりか(ベース)が揃いのドレスを着て登場。スリーピースバンドゆえに立ち位置も対称ということもあって、どこか写鏡の双子であるかのよう。長身ドラマーのフクダヒロアは全身真っ黒の服で髪も顔が隠れるくらいに長いのでより黒く見える。
「涙が出るほど美しい
全てが思い出に遠ざかる」
というフレーズが、こうしてライブで聴くと遠くなってしまったかつてのライブの景色を歌っているようにも聴こえる「mother」のソリッドなロックサウンドがどこか緊張感というか、会場の空気を引き締めるように鳴らされると、河西のうねりまくるベースがここにいる全ての女性をエンパワメントするかのような「Girls」、さらには
「わたしだけが一番可愛くなきゃやだ
両手いっぱいのハッピーをつかんでなきゃ嫌だ
ごまかさないで、大変身よ!」
という女性の心理をUSのインディーロックやオルタナに強い影響を受けたバンドサウンドで鳴らす「変身」と、ここまでは昨年末にリリースされたアルバム「POWERS」のオープニング通りの曲順である。
「POWERS」は非常に評価も高いアルバムであるし、羊文学の音楽性を貫いたままで遠くまで届くようなものになっているだけに、メンバーも自信を持っているのだろう、それ以前にもキラーチューンや代表曲があるにも関わらず「砂漠のきみへ」、さらにはアルバムを締め括る、真っ白な照明がステージに降り注ぐことによって神聖なイメージを与える「ghost」と、アルバムのレコ発ツアーに来たかのように「POWERS」の曲を連発していく。時にはコーラスも務めるフクダはドラムの椅子が高いのもあるのか、ドラムセットそのものがとても低く見え、なんなら常に立ったままでドラムを叩いているかのようですらある。
「音楽好きな人がこんなにたくさんいて嬉しい」
と、塩塚はMCらしいMCもなく曲を連発していくのもオルタナバンドの影響を感じたりもするのだが、自分は以前塩塚のトークイベント的なものを見たことがあり、その時は誰か止める人がいなければ時間を気にしないで延々と喋ってるんじゃないかと思うくらいに喋りまくっていたし、その内容が「いろんなアーティストのインタビューを読みまくってきたインタビューマニアだから」というくらいに音楽愛に溢れたものであった。それだけにこうしてライブでほとんどMCをしないのはバンドのスタンスとしてであろう。
そんな塩塚がステージ上で走るようにしてギターを弾く姿と、ここまではクールなイメージが強かった表情が笑顔に変化する「あいまいでいいよ」ではその塩塚のボーカルに絡む河西のコーラスが曲のポップさを引き立てている。
ここまでは全曲が「POWERS」の収録曲という最新モードであるが、終盤になっての「天気予報」はこの日初の「POWERS」以前の曲。であるのだけれど、
「僕らが憧れた未来予想のその先は
ドキドキするような未来を運ぶかい?
いつか来る時代に憧れた彼らの火を
ワクワクするような未来で繋ぐかい?」
という不敵なサビの歌詞はまるでリリース当時からこうした状況の未来が来てしまうことを予期していたかのようですらあるし、塩塚のオーラはそうした予知能力すら持っているんじゃないかと思わせる。
そしてラストは
「ゆめのなかで
わたしみたの
大魔神が恐竜にたべられる」
というシュールな歌詞によって始まる「ラッキー」。
「ラッキーデイ、今日は
理屈じゃないとこで
しあわせが訪れる
そんなひになる」
という歌詞はバンドからの観客へのメッセージであるかのようであり、バンド自身がライブをすることで自分たちにとってこの日を「ラッキーデイ」にしているようでもあり。観客にとってもこの日こうしてこのイベントに来ることができて、このバンドのライブを見ることができている。それは誰になんと言われようとも紛れもなく「ラッキーデイ」と呼べるものになったはずだ。
リハ.Step
リハ.ロックスター
1.mother
2.Girls
3.変身
4.砂漠のきみへ
5.ghost
6.あいまいでいいよ
7.天気予報
8.ラッキー
17:30〜 東京初期衝動 [GOLDEN STAGE]
去年のDOORS、そしてBAYCAMPにも出演、ワンマンでも毎回P青木が前説を務め、ツアーでは運転手もやっているというくらいに、P青木はこのバンドに賭けている。それはかつて彼がGOING STEADYと出会った時のようなものをこのバンドに感じているのかもしれない。そんな4人組バンドの東京初期衝動、今回のDOORSにも出演。
おなじみのSEであるTommy february6「je t’aime☆je t’aime」のサビが始まってから登場した希(ギター)の髪色は赤味の強いピンクが混じっており、あさか(ベース)とともにジャージを着用して登場すると、しーなちゃん(ボーカル&ギター)はストイックに身体を鍛えているのが見ただけでわかる出で立ち。
しーなちゃんがギターを持つと、1曲目はリリースされたばかりの最新シングル「Second Kill Virgin」収録の「春」からスタートするという意外な立ち上がり。これまではいきなり「再生ボタン」というキラーチューンをぶちかまして初めて見る人を掴みながら、自分たちのスイッチを入れるという形が多かっただけに。
しかしラウドかつノイジーでありながらもメロディの立ちっぷりはこのバンドの最大の持ち味であるし、しーなちゃんがただ叫ぶように歌うのではなく、聴かせるような歌い方に艶が増してきているのはストイックに身体を鍛えていることと無関係ではないだろう。TOSHI-LOWやTAKUYA∞がそうであるように。
バンドはあさか加入後初となるツアーをこの状況下でも回りきり、小さいライブハウスでバンドのグルーヴと個々の演奏力を鍛えてきただけに、コーラスが曲のキャッチーさを際立たせるために非常に重要な「BABY DON’T CRY」でもそのあさかのコーラスがしっかりバンドに溶け込み、欠かせないものになっていることがわかる。それはなおのドラムの安定感もあるからこそ。
そんな中でしーなちゃんがギターを下ろしてステージ上を歩き回りながら、バルコニー的な席で見ている人のすぐ前まで行って歌う(この日ここまでこのステージで動いていた人は他にいない)「高円寺ブス集合」ではバニラの求人のサビのメロディのメンバーによる大合唱に、歌えない観客側も拳を振り上げる。この曲で一気に観客側の動けないし声は出せないけれど盛り上がりたいという意識が変わったと思う。歌っている内容は全人類が受け入れられるものではないかもしれないが、この曲はこうしたイベントにおいては大きな武器と言えるだろう。しーなちゃんがあさかの肩を組むようにしてコーラスをもっとできんだろとばかりに煽っていたところも含めて。
「どこまで行けるか どこまでやれるのか」
というフレーズにこの新木場STUDIO COASTの広いメインステージでワンマンをやる姿を期待せずにはいられない「STAND BY ME」から、客席の頭上のミラーボールが輝く「流星」という美しいメロディの曲の流れはやはりこのバンドはこっちのステージよりももう大きいステージの方が似合う存在だよな、と思うし、実際に昨年のBAYCAMPではぴあアリーナのステージに立っても全く違和感がなかった。あの時はまだ新体制になってすぐだっただけに、今はより似合うようなバンドになれているはずだ。
「Second Kill Virgin」の中でも出色、あさか修行ツアーで演奏された時にも会場の空気が変わった、静謐なサウンドに
「君で埋まる写真フォルダ
足りない君とギガファイル」
というしーなちゃんの上手い単語選びと切なさを増幅させるサビのギターのノイジーさがバンドの新しい一面を感じさせる「blue moon」から、同じく「Second Kill Virgin」収録の、今年の夏はこのバンドが貰うという宣誓のようなはっちゃけサマーソング「さまらぶ♡」の「グイグイ」のコーラスは早くも観客にも浸透している。まだ自分は夏の野外フェスでこのバンドのライブを見たことがないのだが、この曲をリリースした今年はその姿を見れるような世の中や音楽シーンの状況になって欲しい。
すると「再生ボタン」をこの終盤で演奏し始めるのだが、ギターを弾きながら歌っていたしーなちゃんが突如としてギターを下ろして客席に突入していこうとする。しかしながらそれは今の状況では絶対に阻止しないといけないP青木がしーなちゃんを掴んでステージに引き摺り戻すという攻防が何度も繰り広げられ、後ろからその光景を見ていたなおは笑いが止まらずに演奏に集中できなかったという。
さらにしーなちゃんは着ていたTシャツを脱ぎ捨てて客席に放り投げ、自身にペットボトルの水をぶっかけていたのだが、そうしたパフォーマンスをしたのはP青木への絶大な信頼感があるからだろう。自分たちがどんなことをしてもダメなことは止めてくれる、良いことは背中を押してくれる。だから東京初期衝動はこんな状況でもバンド名の通りに衝動を音だけではなくその身をもってしても曝け出すことができる。これからもそうした部分は失われることなくもっと凄い景色を我々に見せてくれるはずだ。
そして最後はそうしてしーなちゃんが水を被った状態でギターを持って演奏された「ロックン・ロール」。その轟音ギターサウンドに乗せて歌われる
「ロックンロールを鳴らしているとき
きみを待ってる ここで鳴ってる いつかきっと」
のフレーズは、完全にこの日も決まっていた。紛れもなくライブハウスでロックンロールがまだ見ぬたくさんの人を待つために鳴らされていたのだった。
ライブ後、物販にいたら東京初期衝動のメンバーが全員いた。そこでついに初めて少し実際に話すことができたのだが、しーなちゃんはずっと自分の銀杏BOYZのライブレポを見てくれていたという。確か2017年の銀杏BOYZの初武道館あたりでフォロワーの関係になって、それ以前もそれ以降も銀杏BOYZのライブを観に行けばしーなちゃんは必ず客席にいたのを見かけていた。
そんな人がバンドを始めて、自分が銀杏BOYZを見てきたライブハウスに出演している。その姿を自分は見ることができている。そうして向こうも自分のことを知ってくれている。なんだか本当に面白いことだなぁと思うし、今でもかつて銀杏BOYZのライブの客席で見ていた頃と同じ感覚をしーなちゃんに、このバンドに抱いている。来週からはまたツアーが始まる。そこでまたロックンロールが鳴ってる。
リハ.再生ボタン
1.春
2.BABY DON’T CRY
3.高円寺ブス集合
4.STAND BY ME
5.流星
6.blue moon
7.さまらぶ♡
8.再生ボタン
9.ロックン・ロール
17:40〜 DJ石毛輝 [DJ LOUNGE]
エントランス近くにあるDJブースは持ち時間がライブステージより長い(転換時間がないから)ので、本来ならば東京初期衝動が終わってからでも半分以上はDJ石毛輝を見れたはずなのだが、ライブステージの時間が押しまくっていたことによって、かなり後半しか見れないという事態に。そうした時間が押すのもまた夏の東扇島公園でのBAYCAMPでは当たり前のことであったのも今や懐かしさすら感じる。
Daft Punk「One More Time」はバンドが解散してもこの音楽でずっと踊り続けていようという石毛なりのメッセージであるはずだし、それは一時期サブスクなどから音源が消えた電気グルーヴの「虹」もそうであるはず。そうした音楽への愛を感じさせながらも楽しく踊らせてくれるようなDJは、
「2000年代の音楽も良いものです」
というコメントとともに最後にFriendly Firesの「Paris」(昔サマソニで見た時にボーカルのエドが割と小太りな体型で独特なダンスを踊りまくっていたのは忘れられない)をかけるのだが、石毛はマイクを持ってこの曲を歌う。やはり歌詞も含めて歌い慣れている感があるのはこの曲への愛情ゆえであるが、曲のハイトーンボーカルは石毛が歌うのがめちゃくちゃ似合っていたし、そんななかなか見ることができない場面が見れて嬉しかった。
石毛輝はDJの前もいろんなバンドのライブを自分の目で見ていた。NOT WONKのライブ中、自分のすぐ近くでずっと音に乗りながらも、「どうやっているんだろう?」というのを確認しながら見ているように感じた。そうした若手バンドを今でもずっとチェックしている部分もまた、本当にこの人は音楽が好きなんだなと思うし、ずっとリスナーとして、音楽好きとして自分が目指している姿だ。
19:00〜 崎山蒼志 [GOLDEN STAGE]
メディアなどでその存在を取り上げられたりもしている存在である、崎山蒼志がこの日のGOLDEN STAGEのトリ。この若き駿才への期待が伺える位置である。
ステージにはエレアコを持った崎山蒼志ただ1人。いきなり話題になった頃の冴えない少年という感じのアー写から比べると大人っぽくなったな、と思うけれど、バックトラックを鳴らしながら自身でギターを弾いて「Undulation」を歌い始めると、その清洌かつ情熱的なギターの音に身体が覚醒されていくかのような感覚。ギターが上手いというのは当然であるが、そこに上手さだけではない何かしらの感情が乗っかっていることによって、こちら側の感情も揺さぶられるというか。
「Heaven」から彼の名を一躍知らしめた「五月雨」と、基本的には同じスタイルで演奏されていくのだが、ともすれば眠くなることも多々ある弾き語りというスタイルであっても全くそうはならないどころか、そのギターの音によって目を覚まされていくような感覚だ。初めてライブを見たが、ギターだけでここまで思える人というのはなかなかいない。
「歌いながら弾くのめちゃくちゃ難しいんですよ。後で音源を聴いて比べてみてください」
と、こんなに上手いギターを弾きながらも難しさをアピールする、というかだからこそこの曲たちを演奏できるのだろうとすら思える「逆行」「踊り」という曲たちが続くと、
「映画「花束みたいな恋をした」の中に「今のBAYCAMPには崎山蒼志が出ている」って会話するシーンがあるんですけど…今、出てます!まさに今BAYCAMPに崎山蒼志が出てます!」
とアピールして観客を笑わせると、諭吉佳作/menとのコラボ曲である「むげん・」ではその諭吉佳作/menのボーカル部分も含めた大部分を打ち込みで流し、自身はボーカルパートを歌うだけという、「ギターこんなに上手いのに弾かずにボーカルだけ!?」という驚きを与えると、最後のサイケデリックな「Video of Travel」もそのサウンドは打ち込みのトラックに任せ、歌い終わるとすぐにステージから去っていった。なんだこの終わり方は!?とも思うけれど、そうした部分も含めてBAYCAMPに、音楽シーンに新しい風が吹き始めていることを感じていた。
先日、崎山蒼志のイスラエル・パレスチナの空爆、紛争についてのツイートが流れていた。その映像を見た彼が心を痛めていることを感じさせる内容だったのだが、そうした社会についてのことをツイートするミュージシャンはそんなに多くない。考えていないわけではないけれど、楽しいことだけを発信して欲しいと思っている人もたくさんいるだろうからだ。いわゆる音楽に政治を持ち込むなという人もいるわけで。
でもそうしたことを自身のアカウントで発信できるというのは本当に真摯な人だと思ったし、近年では彼と近い場所にいる長谷川白紙もそうしたことを迷うことなく発信している。それが彼らの若いファンの人が考えるきっかけにもなると思う。今、世界中がこうした状況になって、社会や政治が音楽やエンタメと直結したものであると改めて自覚せざるを得ないだけに。
1.Undulation
2.Heaven
3.五月雨
4.そのままどこか
5.逆行
6.踊り
7.むげん・
8.Video of Travel
19:50〜 Awesome City Club [DOORS STAGE]
崎山蒼志も「花束みたいな恋をした」の話をしていたが、その映画への出演とインスパイアソングによって、まさかの大ブレイクを果たしたAwesome City Clubがこの日のトリ。個人的にはインディーズ時代に夏のBAYCAMPに出演したのを見ているだけに感慨深い。
ベース、ドラム、キーボードに加えて男女コーラスのメンバーも加えた8人編成、PORIN(ボーカル)が青く染まった髪と青いドレスというのは先日JAPAN JAMで見た時と変わらないが、その時は1曲目に演奏していた「ceremony」をリハでやっていたため、この日はPORINとatagi(ボーカル)も含めて全員パーカッションやシェイカーを鳴らしまくるという楽団のようなパフォーマンスによる「Sing out loud, Bring it on down」からスタート。やはりそのパフォーマンスをしているメンバーたちは実に楽しそうである。
ボーカル専任的な形になったことによってatagiの歌唱も大幅に進化していることがわかる「アウトサイダー」から、「Don’t Think, Feel」ではPORINが歌いながらモリシー(ギター)の肩に腕を回してマイクを向けてコーラスを歌わせるという、楽しくて仕方がなくてテンションが上がっている状態なのがよくわかる。
PORINの
「乾杯」「嘘つき」
のフレーズの破壊力が抜群な「今夜だけ間違いじゃないことにしてあげる」はメンバーもステップを踏みながら演奏する姿が観客をより踊らせてくれるのだが、インディーズ時代からずっと出演し続けているイベントなだけあり、atagiが初めて出演した、クラブチッタ川崎の冬のBAYCAMPのDJブースでアコースティックライブを行った時の思い出を語り、その時に演奏していた「青春の胸騒ぎ」を今の形で演奏するというあたり、浮き沈みがあっても変わらずに誘い続けてくれたこのイベントへの特別な思いを感じさせるし、その頃の曲ということでPORINはキーボードを弾きながら歌う。そんな姿を見ることができるのも実に久しぶりだ。
するとatagiが崎山蒼志が触れていたように「花束みたいな恋をした」の劇中で
「5年前のBAYCAMPにはAwesome City Clubやフレンズが出ていたけれど、今のBAYCAMPには崎山蒼志や長谷川白紙が出ている」
というシーンがあったことについて話し、そうして若手アーティストがたくさん出てきて音楽シーンが更新されていく傍らで、すっかり若手という立ち位置でもなくなった自分たちが今でもこのイベントに出演できていることへの感謝を告げると、そうして目の前に見える景色が巡っていく、回っていくことを歌ったという新曲「またたき」の壮大なメロディとサウンドが会場に響くと、前日にミュージックステーションに出演した際にもらった番組のシールをモリシーがギターに貼っていることに触れながら、最後に演奏されたのはこのグループをミュージックステーションやこうしたイベントのトリにまで連れて行った「勿忘」。
春の別れの情景を歌った曲ということで、このグループの鮮烈なデビューを告げた春の名曲「4月のマーチ」からもう6回も春が巡ったことに思いを馳せていた。その間にはメンバーチェンジもあっただけに、縮小していく一方になるかと思っていた。
それでも昨年11月のBAYCAMPでのライブがまだオーサムは終わっていないということを自らの音で示していたのだが、こうして今が過去最高の状態になっているのは、オーサムを続けるという選択をした3人が諦めることなく音楽に向かい続け、今の形態だからこそできる形を突き詰めてきたからであるということを「勿忘」を演奏している姿を見ていたら感じた。その姿は彼らと同じくらいのキャリアで音楽を続けているアーティストたちに希望を与えてくれているだろうし、日々を生きる我々の明日へ向かっていく力になる。オーサムがそんなことを思わせてくれるアーティストになるなんて全く想像してなかったが、
「みんながほっこりした気分で帰れるように」
というアンコールで「夜汽車は走る」を演奏した姿も含めて、名実ともにオーサムはこの大きなイベントでトリを務めることができるようなアーティストになった。その歴史の中でこのBAYCAMPが果たしてきた役割は、きっと他のどのフェスやイベントよりも大きい。このイベントがあったから、彼らは諦められなかったのかもしれない。
リハ.ceremony
1.Sing out loud, Bring it on down
2.アウトサイダー
3.Don’t Think, Feel
4.今夜だけ間違いじゃないことにしてあげる
5.青春の胸騒ぎ
6.またたき
7.勿忘
encore
8.夜汽車は走る
終演してからかなり時間が経って、もうほとんどの人が帰っている段階になってP青木が挨拶をしに出てくるというタイミングの悪さがまたポンコツっぷりを示しているが、P青木が代表を務め、このBAYCAMPを作っているAT-FIELDはライブ制作会社である。ライブがなくなったり、無観客になったりすると収入がなくなってしまう。
だからこそP青木は自分たちが先頭に立って去年のBAYCAMPを開催したりして、ライブ業界を動かそうとしてきた。そうしてしっかりと対策をした結果も出してきた。夏のBAYCAMPでは何時間も帰りのシャトルバスを待たされたり、トイレが全く使えなくなったりした苦い記憶もあるけれど、これからもP青木がキュウソネコカミや東京初期衝動のライブで前説をする姿を見ていたい。つまりはAT-FIELDも、BAYCAMPも、ずっとなくなって欲しくないのだ。今、これまでで最もP青木のことを心から応援しているし、少しでも力になれたらと思っている。
文 ソノダマン