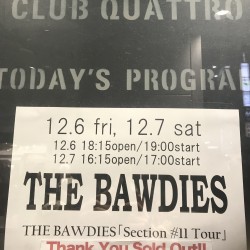コロナ禍になる前から、主催フェスの京都音博こそ定期的に開催したりしているものの、近年はライブもそこまで以前ほど多くは行っていないし、リリースのペースもだいぶ穏やかになった。それだけに4月にリリースされたアルバム「天才の愛」は実に久しぶりのオリジナルアルバム(昨年には未発表曲を集めた「thaw」をリリースしているが、新作としては2018年以来)となったし、だからこそこうしてワンマンを見るのも実に久しぶりな、くるり。
この状況でも各地を巡ってきた「天才の愛」リリースツアーはこのZepp Hanedaがファイナルの地となるのだが、この日は2daysの初日というセミファイナル。
検温と消毒を経て中に入ると、先日の9mmや1週間前のキュウソネコカミと同様に客席には椅子が並ぶ中、開演時間の19時ちょうどくらいになると、岸田繁(ボーカル&ギター)、佐藤征史(ベース)に加え、サポートメンバーの松本大樹(ギター)、石若駿(ドラム)、野崎泰洋(キーボード)という5人でステージに登場。やはりファンファンがいなくなったというのは、最後にライブで見れなかったということも含めて少々寂しい感じもある。
「立っていいのか?どうなのか?」という感じで前の方の席の人から順番にゆっくり立ち上がっていくのがくるりのライブらしくて笑ってしまうが、それぞれが楽器を持つと、1曲目はいきなりの「琥珀色の街、上海蟹の朝」。リリース時に俄かに盛り上がっていたシティポップバンドブーム的なものに、くるりならではの圧倒的な音楽の知識と引き出し、それを自分たちの曲にできるセンスと技術を持ってトドメを刺したと言える名曲。岸田は軽快なラップも聞かせる中、女性コーラスもいない編成であるが、佐藤と野崎が演奏しながら岸田のボーカルにコーラスを重ねていく。
そのコーラスも務める野崎がイントロのピアノの音を奏でて始まったのは至上の名曲「ばらの花」。石若のあまりにも正確過ぎるかつ力強い、さすが今の若手ドラマーの中でNo.1と称され、星野源や常田大希らの曲にも参加している男のビートはこうしたくるりの名曲たちにまた新たな命を吹き込んでいる。個人的には音源にコーラスとして参加していたフルカワミキが先日久しぶりにライブで姿を見せてくれたので、本家コーラスバージョンにもほんの少しだけ期待したのだが、さすがにそれはなし。
とはいえ、サビの
「安心な僕らは旅に出ようぜ
思い切り泣いたり笑ったりしようぜ」
というフレーズが放つ、今だからこその説得力たるや。それはどうしても不安にならざるを得ない今の世の中の状況だからこそ、なかなか旅に出ることもできないし、声を出して思い切り泣いたり笑ったりすることもできない。そうすることができるような、安心な僕らでいられる世界に早く戻って欲しい。そう思うとこれまでに音源でも、様々な編成でのライブでも数えきれないくらいに聴いてきたこの曲がまた違ったように聴こえたのである。
岸田がアコギに持ち替えると、素朴かつ穏やかな、くるりの持つ魔法のようなメロディの美しさを感じさせてくれる「さよならリグレット」、さらには決してみんなで声を合わせて合唱するようなタイプのバンドではないけれど、佐藤と野崎の
「飛び出せハイウェイ」「久しぶりだぜ」
というコーラス部分を観客みんながきっと歌っていたであろう「ハイウェイ」と、新しいアルバムが出たばかりにもかかわらず、自分は一体今何のツアーに来ているんだろうか、と思わず自答してしまうくらいの名曲の連打に次ぐ連打。しかもそれがさすがくるりと思えるような安定感のある、この編成だからこその演奏で披露されていく。
昨年リリースの「thaw」が、ライブでは何度も披露されているけれど音源化はしていない曲などを収録したアルバムだったように、くるりは割とライブでガンガン新曲を演奏し、それがすぐに音源になることもあれば「thaw」のように忘れた頃に音源化されることもあるし、時にはそのまま音源化されないということもあるバンドである。
だからこそアルバムが出たばかりだというのに、そこにすら収録されていない、全く聴いたことのない新曲(「ポケットの中から」という歌詞が印象的な、素朴かつポップなメロディの曲)が演奏されても特段驚くこともないのだが、曲のアウトロが長尺かつ濃厚なセッション的なものになっていくというのはさすがに少し驚く。このあたりは近年の「Tokyo OP」や「大阪万博」のプログレ感に通じるところもあるけれど。
そんな新曲の後の「鍋の中のつみれ」はまさに鍋に投入されていく具材が出てくる歌詞のシュールさにクスッとしてしまうのだが、それでも演奏のキレは全く変わらないし、最近ではリーガルリリー(この日ワンマンが被っていた)がカバーしていることで若い人にも知られるようになった「三日月」のメロディには思わず浸ってしまう。なんだかこうして夜にライブハウスに来てくるりのライブを見れていることが本当に幸せなことのように感じられるような。
曲間もほとんどなく次々に名曲たちが放たれていくという構成はストイックかつコンセプチュアル…と思っていたらここで岸田が口を開く。
「「天才の愛」っていうアルバムを出しまして…その曲全然やってないですけど(笑)」
と、確かにここまで1曲もアルバム収録曲をやっていないだけに、この辺りではもう今回はそういう、これまでのキャリアを総括するような名曲たちを演奏するツアー的なものだとすら思うようになっていた。
そんな中でまたアルバムのさらに先をいく新曲を演奏してしまうのが実にくるりらしいのだが、この新曲は
「クマゼミとアブラゼミ」
などのフレーズが否が応でも夏を想起させる、でもそれは海やプールでみんなではしゃぐというものではなく、どこか長閑な、畳の上で寝そべって扇風機に当たりながら「暑いな〜」と思って過ごしているような、そんな夏。岸田は今は京都に生活の居を戻しているが、そこから見えている夏の風景はそうしたものなのかもしれない。
前半はいわゆるくるりの代表曲と言えるようなシングルになった名曲が披露されてきたのだが、この辺りからは「この曲を今やるのか!?」という隠れた名曲も演奏されていく。
その際たる曲が「アンテナ」収録の「花と水鉄砲」であるが、時系列的にはロックバンドとダンスミュージックとの融合にひとまずの完成を見たくるりが再度ギター、ベース、ドラムというロックバンドとしてのグルーヴに向き合った作品であり、だからこそこの5人の編成でのロックバンドさを感じさせてくれる。キーボードも入っているけれど、牽引している石若のドラム含めて、ロックバンドとしてのくるりを実感させてくれるものだ。
岸田「大谷翔平が久しぶりに17号ホームランを打ちましたね」
佐藤「最近、四球ばかりだったから久しぶりにライブ前にスカッとしましたよね〜」
岸田「あなた、大谷翔平は好きだよね」
佐藤「ツアー行くとホテルでテレビつけたらちょうどいい時間にエンゼルスの試合がやってるんですけど、前に7回までノーヒットに抑えていた試合(2018年4月8日のアスレチックス戦)を見たら、なんて美しい人なんだと。その立ち振る舞いとかも含めて。僕の推しメンになりました(笑)
50歳過ぎたあたりで繁君みたいにプロ野球の試合を見に行くようになるかもしれないです(笑)」
と、野球マニアの岸田だけでなく、これまでほとんど野球に興味がなさげだった佐藤すらも虜になるくらいの力を大谷翔平が持っているということを野球ファンとしても改めて感じさせるやり取りから、
岸田「野球ファンにもそれぞれいろんな見方があるんですよ。私は重箱の隅をつつくような、なんj民ですから(笑)(野球まとめサイト。DeNAの倉本寿彦のように世間ではあまり知名度がなくてもこのサイトでは誰もが知る有名人になったりするようなマニア御用達サイト。広告に出てくる漫画がだいたい胸糞悪くなるようなものばかりなのはなんとかして欲しい)
そんな野球マニアが作った野球の曲を」
と、「天才の愛」から最初に披露されたのは、奈良県の高校野球の名門校である天理高校の応援曲に岸田が歌詞をつけるという形の、まさにリアル野球狂の詩と言えるような、岸田の野球愛が極まって音楽になった「野球」。
応援団のフレーズをそのままファンファンが吹いていた、野球ファンなら誰しもが聴き馴染みのあるトランペットのフレーズは野崎がキーボードで奏で、松本もピート・タウンゼントのように右腕をぐるぐると回しながら楽しそうにギターを弾く。(むしろ「野球」という曲で腕をグルグル回すのは、ロッテ、巨人、ヤクルト、西武と日本で長くプレーした、ブライアン・シコースキーの腕グルグルパフォーマンスへのオマージュなのかもしれない)
そうした演奏に岸田はプロ野球の現役スター選手から、もう引退した、あるいは亡くなってしまったレジェンド選手までの名前を次々に歌詞として乗せていく。
「緒方 かっ飛ばせよ(翼)
誠也 かっ飛ばせよ(石原)
エルドレッド 松山 長野 長野 長野」
というラインは岸田の広島カープ愛を感じさせるし、何よりも長野久義の3連呼。FAの補償で広島に来た、元巨人のスター選手を岸田が心から信頼していることがよくわかる。
その後には「ワンちゃん」(王貞治。言わずと知れた世界のホームラン王)「チョーさん」(長嶋茂雄。言わずと知れたミスタープロ野球)に続いて
「ノムさん ありがとう」
と歌われる。捻くれていて、自らヒールを演じているところもあった野村克也を岸田はきっと心からリスペクトしていたんだろうし、なんなら野村監督の著作を読んで自身の野球観を形成してきたのかもしれないし、野村監督の掲げたID野球が現代のプロ野球の礎になっていることも岸田はきっとわかっている。でもそんなノムさんももう亡くなってしまった。だからこそ唯一歌詞の中で「ありがとう」と歌われていることに聴いていて涙が出てしまう。
そんな中で後半に唐突に出てくる「戸柱」。現役選手とはいえ決してスター選手と言えるような存在ではない(なんならレギュラーですらない)DeNAのキャッチャーがこの歌詞に名前を連ねていることに最初はビックリして歌詞カードを凝視してしまったが、アジカンのゴッチなどもこの「戸柱」には驚いていたようだ。というか野球好きなら間違いなく驚く。
そんな「野球」も、きっと全員が全員わかるわけではない。野球に興味がない人からしたら全てが意味不明な歌詞の曲だろう。それでもこの日、1番観客が腕を挙げたりして盛り上がっていたのはこの曲だった。それは
「かっ飛ばせ かっ飛ばせ みんな」
というフレーズが全てのプロ野球選手、全ての野球をプレーしている人、そしてこの曲を聴いている全ての人へのエールとなっているからだ。
ロックバンドが好きな野球ファンにとっての野球ソングの金字塔と言えばBUMP OF CHICKENが打席に向かう打者の緊張感と恐怖を見事に描いた「ノーヒットノーラン」だろうし、近年ではクリープハイプの尾崎世界観がヤクルトスワローズファンとして球団とコラボしたりもしている。
でもかつてBase Ball Bearに「絶対に俺の方が野球好きやで!」と謎の対抗心を燃やしていた(ベボベはメンバー全員全然野球に詳しくない)岸田の野球愛はやはり常軌を逸しているレベルだったということがわかったのが「野球」という曲であり「天才の愛」というアルバムなのだ。いつか岸田と居酒屋で酒を飲みながら野球の話を朝までしてみたいものである。「オマリー」だけで2時間はいける自信があるだけに。
もうある意味では一つのクライマックスを超えてしまった感じもするが、当然まだライブは終わりではなく、「thaw」収録のポップなメロディとロックなバンドサウンドの融合という形のくるりの女の子シリーズ「さっきの女の子」から、こちらも「今この曲やるの!?」という「ハム食べたい」へ。
もともとはクラシックとロックの融合を試みた名盤「ワルツを踊れ」に収録の曲だが、その曲が今このメンバーによって演奏されることによってこれまでで最もロックさを感じられるものになっている。この曲からそう感じる日が来るとは、と「ワルツを踊れ」のツアーに行った時のことを回想すると何故だか感慨深くなってしまう。それはあれからくるり自体もまたたくさんの出会いと別れを繰り返し、自分自身もそうしてここまで生きてきたからだろう。
しかしこうして久しぶりにくるりのワンマンに来て思うのは、その演出のシンプルさ。というか照明以外に何の演出もない。それはこの規模、このキャリアのベテランバンドにしてはかなり珍しいとも思うけれど、だからこそそれが名曲を今のバンドの演奏で聴かせるということに注力しているように感じる。
それは「潮騒のアリア」「loveless」という近年のくるりのメロディの美しさを感じるような、一周というよりも何周か回ってシンプルにポップな曲をくるりというバンドが演奏することという境地に辿り着いたかのような。どこかで聴いたことがあるような懐かしさを感じながらも、この曲のメロディが脳内に焼き付くかのような。
松本がバンジョーに持ち替えて演奏されたのはもちろん「リバー」。これまでもライブの大団円を描いてきた、くるりの代表曲の一つである。それこそファンファンと吉田省念が加入した際にはそのメンバーたちとのテーマソング的な形でクライマックスに演奏されていたし、こうした世の中の状況になる前はこういうライブハウスでも観客同士がビールを飲みながら肩を組んでこの曲を歌っているという光景を見かけたこともあった。決してモッシュやダイブや合唱が起こるバンドではないけれど、それは自分たちがライブを見る位置が決められることのないスタンディングでのライブだったからだ。ああいう日々が少しでも早く戻ってきて欲しい。
それは岸田も佐藤も同じ想いであるようで、ステージに出てくる直前までメンバーもマスクをしているという。だからこそステージに出てくる時にマスクを外して酸素を思いっきり吸い込むと生きている感じがすると。だからこそ観客も含めて早くみんながマスクをしなくてもいい世の中に戻って欲しいと。
それは岸田なりの、観客の表情をしっかり見てライブがしたいという思いであるようにも感じた。この曲を聴いて笑っている人、楽しんでいる人、泣いている人。くるりは全く観客に媚びるような活動をしてこなかったというのは常にその時に作りたい曲を作り、演奏したい曲を演奏するという音楽家としての表現欲求に基づいたそのディスコグラフィーを見ればわかることであるが、それでもこうしてライブを見に来てくれる人、自分たちの音楽を聴いてくれている人の存在を心から大事に思っているのだろう。
だからこそそうした言葉の後に演奏された曲は文句なしにくるりの名曲でありながら、くるりのライブに来たならみんなが聴きたい曲をバンドが演奏してくれているように感じた。
それはイントロを聴くと今でも胸が高鳴る瑞々しさを湛えている「ロックンロール」で野崎も立ち上がってキーボードを弾き、それまでずっと座ってライブを見ていた人たちもイントロが鳴った瞬間に反射的に立ち上がるという光景からも明らかであるが、やはり数えきれないくらいに聴いてきても全く飽きることがない。それこそがリリースから20年近く経ってもこうして鳴らされ続けている理由なのだろうし、それはこれから先も全く変わらないはずだ。
そして最後の曲もまた岸田のギターのイントロが鳴らされただけで胸がざわつくような感覚に陥る「東京」。これまたいろんな場所で、なんなら東京ではない場所でも聴いてきた曲であるし、日本武道館という東京の象徴とも言える場所でも聴いてきた曲であるけれど、ことライブハウスという面では最寄りの天空橋駅からこのZepp Hanedaへ向かう道のりで見える羽田空港の飛行機の発着場の風景はどこよりもここが「東京」であり、そこで「東京」を聴くことができているという事実に胸が熱くなった。
「今年の夏は暑くなさそう」
というフレーズは年々90年代という時代を感じさせるように、もう6月から真夏日となるくらいに今年の夏も暑くなりそうだけれど。
割とすぐにアンコールにメンバーが出てくると、
岸田「さーて…」
佐藤「もう曲やるんかと思った(笑)」
岸田「さーて、来週のサザエさんは?的な(笑)」
と、メンバーの入れ替わりがどのバンドよりも激しくともこの2人の全く変わることがない空気感に笑わせながらも、「さよならリグレット」のカップリングに収録(カップリング集にも収録されたけど)された「pray」という、これぞくるりの隠れた名曲という曲を演奏するのだが、
「祈ろう 祈ろう 全部捨てちまいな
金も服もピカピカのギターも」
というサビが今聴くと、先ほど岸田が言っていたように、マスクをしなくてもいい世界に戻ることを祈っているようであるし、
「Everythings gonna be alright」
というアウトロのフレーズを何度も叫ぶようにして歌っていた岸田の姿からは、そう強く思ってこれから先も生きて音楽を奏でていくという強い意志を感じさせた。
そして岸田が来てくれた観客に感謝と健康を告げながら最後に演奏されたのは「奇跡」。ドラマチックな展開もない、穏やかで緩やかなサウンドで鳴らされる「奇跡」。でも「奇跡」とはそういうものなのかもしれない。この世の中の状況が瞬時に劇的に良くはならないだろう。それでもこうして少しずつ前に進みながら生きていく。その果てに「奇跡」と言えるような日々が待っていれば。その時にもこの音楽たちをこうして聴くことができていれば実に幸せなことだと思えるはずだ。そこにはくるりとしての願いが確かに込められていたはずだ。
演奏が終わると5人全員がステージ前に出てきて揃って一礼した。その際にくるりに携わってきた歴としても人生においても先輩である松本が石若の背中のあたりをポンと叩いた。野崎も含めて、このサポートメンバーたちはやってきた音楽も出自も世代も本当にバラバラだ。きっとくるりがなかったら出会うことすらないような3人。それでもそれぞれが抜群の演奏力を持っていることだけは共通していて、その3人がくるりという場所があることでこうして同じバンドで演奏することができる。
きっとくるりにはファンの数だけそれぞれの好きな形というものがあると思う。「ファンファンがいないと」という人もいれば「大村達身が好きだった」という人も、「クリフ・アーモンドやクリストファー・マグワイアのドラムのパワーが好きだった」「あらきゆうこのドラムが1番合っている」「山内総一郎がギターを弾くくるりをまた見たい」「アヒト・イナザワがドラムだった時を見れたのはレアい」「やっぱりもっくんとの初期のスリーピースこそ至高」など、他にも数えきれないくらい。
でもかつてはメンバーが加入しては脱退していく様を離職率になぞらえて「ロックバンド界一のブラック企業」とも言われていたくるりは、こうして全く異なる才能のある音楽家同士を繋ぎ合わせるハブ的なバンドになった。そしてそれぞれがくるりで経た経験をまた違う場所で生かし、発揮していくことでまた違う音楽家同士の結節点となる。それはきっとこれからも続いていくはず。くるり、かっこいいぜ。
1.琥珀色の街、上海蟹の朝
2.ばらの花
3.さよならリグレット
4.ハイウェイ
5.新曲
6.鍋の中のつみれ
7.三日月
8.新曲
9.花と水鉄砲
10.野球
11.さっきの女の子
12.ハム食べたい
13.潮風のアリア
14.loveless
15.リバー
16.ロックンロール
17.東京
encore
18.pray
19.奇跡
文 ソノダマン