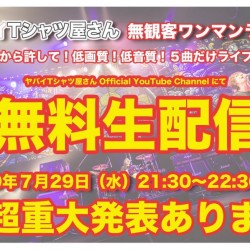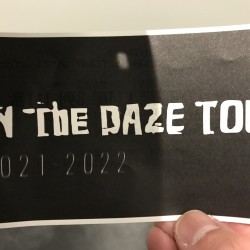去年は配信でのライブがメインになっていたが、今年に入ってからは9mm Parabellum Bulletとの2マンライブを皮切りにツアーも回ってきた、THE BACK HORN。
3月には昨年完遂できなかった、最新作アルバム「カルペ・ディエム」のツアーを再開したが、そのツアーで開催が告知されたのが、東北の震災を経験してリリースされた2012年のアルバム「リヴスコール」を携えたストリングスとのKYO-MEIツアー。ほぼ10年を経て再び向かい合うことになった「リヴスコール」の今の姿とは。
平日とはいえ18時30分という早めの開演時間だったことから、仕事が終わってから急いでZepp Hanedaに到着し、検温と消毒を済ませて場内に入ると、すでにSEが終わって1曲目が始まっていた。ギリギリ間に合わなかったというかなんというかであるが、なのでステージ上ではすでに白いシャツを着た山田将司(ボーカル)が歌い、菅波栄純(ギター)、岡峰光舟(ベース)、松田晋二(ドラム)が演奏しているのだが、下手の光舟の後ろにはキーボード、上手の栄純の後ろにはヴァイオリン×2、ヴィオラ、チェロのストリングス隊という、feat.ストリングスのタイトルがついたこのツアーならではの編成で「リヴスコール」の1曲目の「トロイメライ」を演奏している。
「生きること」「生命力」をテーマにしたアルバムのオープニングを告げるだけに、壮大なメロディとサウンドはそれはストリングスとの相性も良いというか、まぁこうしてストリングスの音が入るのも実に納得な曲であるよなぁとも思うのだけれども、果たして全ての曲でこうしてストリングスを入れるのだろうか?とも思っていたし、そもそも「リヴスコール」の曲だけをやるのか?というところも含めてどうなるのか非常に楽しみだったのだが、「リヴスコール」の曲順通りとはいえアッパーなロックチューンである「シリウス」でもストリングスとキーボードが参加し、栄純のギターによるリフをさらに華美に壮大に昇華している。将司は少し声を張るような歌唱がキツそうなところもあるけれど、とはいえそれがライブそのものの評価を下げるものにはならないというのはバクホンのファンはみんなわかっているはずだ。
この曲でもこうしてストリングスを入れるとは、と思っていたらビックリした。次の曲は「リヴスコール」の収録曲ではない「ブラックホールバースデイ」を演奏し、しかもこの曲にもストリングスが入っているからである。キメのリフをストリングスがバンドとともに打つことによって、この曲の持つカオスさがさらに引き出されるアレンジになっているのだが、まさかこの曲でストリングスを入れないだろうと思うような最たるタイプの曲であるこの曲にこうしてストリングスアレンジを施すというあたりに、バンドとストリングス隊、キーボードのメンバーたちが一緒になってアレンジを熟考した結果であろうし、光舟がサビ前で腕を高く挙げる姿からはメンバーがこのライブを本当に楽しんでいることがよくわかる。
「音楽の素晴らしさをともに実感していきましょう!」
と松田は最初のMCで言ったが、この最初の3曲だけでもバクホンがその音楽の素晴らしさを存分に感じさせてくれている。それは目の前で、しかもライブハウスで鳴らされている、生のストリングスの音の迫力も含めて。
そのストリングス隊とキーボードがいったんステージを捌けると、バンドのみで「リヴスコール」の中では異彩を花っているが、バクホンというバンドの持つ要素の一つである不穏さやおどろおどろしさをサウンドに落とし込み、人間の心の闇の部分を歌った「超常現象」へ。この曲の歌詞を書いた将司は
「アイドルの画像で快楽」
のフレーズで自らの陰部をこするような仕草を見せる。この部分だけを見るとこの曲の歌詞を書いたのが、地上波のテレビ番組に出演したことによってヤバいキャラであることが世間にもバレてしまった栄純のものであるように感じてしまうが。
そのバクホンの持つ人間の闇を描いた部分は初期の頃の方が強かった。というか当時はきっとそうしたものを歌うことがバンドやメンバーにとってリアルだったのだ。それを感じさせてくれるのがバンドにとって今でも名作と称えられるアルバム「イキルサイノウ」のタイトルになった歌詞が登場する「ジョーカー」である。
真っ赤な照明に照らされながら、将司はステージを這いつくばったり暴れ回るようにして歌い、栄純は頭をブンブン振りながらギターを弾く。今では優しく寄り添ってくれるようなタイプの曲も多くなったバクホンが、今でもこうした闇や影の部分を持ち続けているということがよくわかる。
「子供の絵はわりと不自由だ 大人の絵はわりと自由だ
俺はどうなんだ?
変換ミスや言い間違いや思いつきや無駄の向こうに
無限の宇宙が広がっている気がした」
という栄純が書いた歌詞にハッとさせられる「自由」は「リヴスコール」の曲であり開かれたサウンドでありながらもバンドのみという形で演奏されたのが少々意外ではあったが、一転してバクホン特有の重みを持った「グレイゾーン」からは再びストリングス隊とキーボードが加わり、タイトルとは裏腹にステージからはカラフルな照明がメンバーたちの姿を照らしている。そのストリングスのサウンドと照明の効果がこの曲の持つイメージを新たなものにしてくれるのだが、それは力強く踏み出していくような歩幅をストリングスがさらに大きくしてくれるような「いつものドアを」もまたそうだ。それは松田が
「こうしてストリングスとやることで、曲の新たな景色を見てもらうことができたら」
という言葉をバンドの演奏とアレンジが、つまりは目の前で鳴っている音がそのまま証明してくれているかのようだ。
とはいえ将司はこの曲では喉がかなりキツそうでもあったのだが、それでも歌うことを諦めないどころか、常に全てを振り絞るように歌い続けている。その手加減の出来なさが喉の負担になっているのかもしれないが、それこそが将司が常に100%以上の力を持ってライブに向き合っていることの証明であるし、その姿は実にロックだと言える。
「リヴスコール」の後、アルバムとしては「運命開花」に収録されている曲であるということがバンドが「リヴスコール」以降、震災以降に歩んできた道のりと音楽性というよりもメンバーの精神の変化を感じさせるのは「シュプレヒコールの片隅で」であるが、ストリングスのサウンドがまるで中世の戦争映画の一場面で流れる挿入歌のように響く。何よりもそう感じさせるような情景描写の歌詞がストリングスによってさらにはっきりと引き出されている。ストリングスがこんなに歌詞を際立たせてくれるものだったとは、ということに改めて気付かされるし、それはとかくライブだと歌詞よりもサウンドによって感情を昂らせてきたバクホンだからこそよりそう思うのかもしれない。
それはこちらは映画のエンディングテーマ(それこそバクホンファンを自認し、この曲が収録されたシングル「この気持ちもいつか忘れる」でコラボした住野よる原作とかの)に使われていそうなくらいの壮大さをストリングスによって獲得した「君を隠してあげよう」もまた然りであるが、この曲はまさに「リヴスコール」以降のバクホンの曲と感じさせてくれる。それは曲や音の中に微かだけど確かな温もりや優しさを感じることができるからだ。
フェスやイベントなどの短い持ち時間ではほとんど喋ることがないだけに、武士の絵柄が入った自身のアンプとともに寡黙な男というイメージも持たれていそうな光舟が率先して喋るMCというのもワンマンならではであるが、その内容は
「マツ(松田)が曲作りの合宿で穿いてるズボンのポケットの袋部分を外に出して歩いているのは何故なのか」
という実に緩い、バクホンの4人の普段の関係性や人間性が感じられるもの。松田の回答は
「普段はそこまで潔癖ではないんだけど、寝てる時とかにポケットの中にゴミが入るのが嫌だから」
という、なんじゃそりゃとツッコミたくなるもの。また、将司が美味いものを食べた際に箸をダーツの矢みたいに前に向ける仕草にも言及していたが、栄純はそうしたそれぞれの癖を全て
「人それぞれ違う価値観が集まってるのがTHE BACK HORNである」
と半ば強引にまとめてみせたのだった。
そんなMCの間にストリングス隊は一旦またステージから捌けるものの、キーボードのメンバーはそのままステージに留まる。
そうしてバンド+キーボードという、普段のバンドともストリングスを加えたのとも違う形で、かつ将司がギターを弾きながら演奏されたのはリリース当時にプロ野球選手が次々に出演する野球用品のCMタイアップとなり、多くの人にTHE BACK HORNというバンドの名前を知らしめた「夢の花」。栄純が将司のボーカルに重ねるコーラスもかなり強めであるが、何よりもキーボードがメロディを牽引することによって、この曲、さらにはバクホンの持っている歌謡性が強く感じられる形になっている。
それは同じ編成で演奏された「星降る夜のビート」も狂乱のモッシュ&ダンスという原曲のイメージがムーディーなダンスホールで踊るというものに変貌している。キーボードが入っただけでここまで曲の見える景色が変わるというのはバクホンの曲が持っている潜在能力の高さゆえだろう。こうしてこのツアーでの新たな景色が見える形で聴いたことによって「リヴスコール」というアルバムがますますそれぞれの観客の中で大事なものになっていくのは間違いないだろう。
するとここで再びストリングス隊が登場し、ストリングスを活かした終盤の壮大な曲のゾーンへ入っていくのかと思いきや、松田のドラムが刻み始めたのはこれまでにも数え切れないくらいに聴いてきたリズム。それは「コバルトブルー」のものであり、なんとこの曲にもストリングスが加わる。栄純のギターリフをさらにスケール大きく飛翔させるようなストリングスの音色はやはりこの曲で何度となく見てきた、感じてきた景色を新しいものにさせ、将司は声が出せないのをわかっていても観客を煽りまくる。
さらには「リヴスコール」の収録曲の中では毎回ライブで演奏される曲に成長した「シンフォニア」でもやはりストリングスが入るのだが、
「絶望的な状況 妄想は制御不能」
というフレーズで栄純が煽るようにして観客が手拍子をするのだが、その部分ではストリングス隊が弓を持って煽るような仕草を見せる。(キーボードも腕を振り上げて煽る)
ただ演奏に参加するだけではなくて、バクホンというバンドのことや曲を理解して、ともにこのライブを最高のものにするために自分たちが出来ることは全てやるというあまりに強いプロフェッショナル精神。それこそがもしかしたらこのバンドとストリングスという形のライブを素晴らしいものにしている1番の力なんじゃないだろうか。しかもそうしたパフォーマンスをしている全員が笑顔だった。音楽を鳴らしている、ライブをやっている喜びが溢れているように。バクホンがこのツアーを回ったということは、そうした我々が名前を知ることがなかった音楽家を救い、音楽家のままでいられるようにしていたのかもしれない。
そして栄純の重厚なギターリフの裏でもストリングスが勇壮さを持って響く「戦う君よ」と続いたことにより、ステージはもちろん、客席も全席指定で声が出せないとは思えないような熱量が満ちていく。気づくと汗をかいているくらいに。
そんな熱さの中で将司は
「さあ走り抜けよう この歌を胸に抱きしめ今」
のフレーズの2回目の部分で両腕を広げた。それはつまり将司がマイクを通して歌わなかったということだ。コロナ禍になる前は観客がみんなで合唱していた部分。今は声が出せないことがわかっていても、目の前にこうしてライブを見に来てくれている人がいる。あるいは配信でこのライブを見てくれている人がいる。その人たちの心の声を受け止めようとしているかのようだった。その将司の姿に思わず目が潤んでしまった。
その将司は歌い終わると、
「今日、品川から京急線に乗って天空橋まで来たんだけど、品川で目の前にTHE BACK HORNの「アサイラム」の時のTシャツを着て、俺たちのグッズのバッグに缶バッジとかをいっぱいつけた2人組がいて、俺が後をつける感じで同じ電車に乗ってたんだけど(笑)、スタードッキリ訪問みたいに「どうも〜」って声かけようかなとも思って(笑)
でも天空橋で降りてエスカレーターに乗ったらその人が俺に気付いて。写真撮ったりしたんだけど、こういう状況になって、自分たちの住んでる街からこうやってライブを見に来てくれるって本当に嬉しいことだなって改めて思った」
と、実に将司らしいファンとのこの日のエピソードを語ると、
「これからもずっとこの歌を歌っていきたいと思います」
と言って演奏されたのは「世界中に花束を」。震災が起きた後にバクホンが配信した、「リヴスコール」の軸になっている曲。ストリングスが加わるのも実によく似合う曲であるのだが、まだ震災後にライブが再開し始めた2011年の5月にライブで初めてこの曲を聴いた時のことを今でもよく覚えている。
この4人が元々持っている優しさや温かさが全て音楽に注がれた、どんな人が聴いても良い曲だと思ってもらえる曲がバクホンに生まれたと思った。自分自身、震災の後に何度となくこの曲を聴いて力を貰ったり、いろんなことを考えるきっかけを貰ったりした。
あれから10年経って、震災とはまた違う形でこの曲の持つメッセージが強く響くような時代になった。いや、もしかしたら人同士がいがみ合い、貶し合うことが10年前よりも可視化された今においてこそこの曲はより強く響くのかもしれない。
そうしたことは起こらない方が絶対良い。自然災害も、パンデミックも。でもそれはきっとまたこの先も起きてしまうし、そうしたことがなくても人は亡くなってしまう。自分も災害やコロナが関係なく、近しい人が亡くなった時になぜかこの曲が頭の中で流れていた。そうしてこの曲はこれからも生きていく限りはその人の中で鳴り続ける。それはこの曲がいつどんな時代や状況であっても生きる人のための曲であり続けていくということだ。
「僕ら何処へ行く
何処へ行ってもまた此処に帰るだろう」
という、インディーズ時代の作品のタイトルを取り入れた曲を締める歌詞を、将司は思いっきり溜めてから歌った。それはバクホンにはこうして帰る場所があるということの感慨を示しているようだった。
アンコールでは4人だけで登場すると、将司がアコギを弾きながら歌う「リヴスコール」の締めの曲である「ミュージック」を。「世界中に花束を」というある意味ではクライマックスを描くような、アルバムの最後になるような曲が最後にはならなかったのは、バクホンの音楽の力を信じることを震災後の日本の状況の中で歌ったこの曲が生まれたからだ。この曲にストリングスを入れないというのは少し意外ではあったけれど、
「夜が明け それぞれの朝が始まってゆく
今日も音楽がそこで鳴っているよ」
という歌詞は不要不急の最たるものと言われることもあったこの状況でもこうして音楽が鳴り止むことがないということと不思議なくらいにリンクしている。今日もここで音楽が鳴っている。
「一歩一歩、できることをやって進んでいきましょう」
という将司の言葉が
「一歩また一歩 歩み続けてくんだ
顔が向いてりゃ前向きだろう」
という、今この状況の世の中のことを歌詞にしたんじゃないのかとすら思ってしまうフレーズと重なり、
「電光石火で駆けてゆけ 満身創痍青い空の下で
一点突破で賭けてゆけ 誠心誠意君を想い歌う」
というバクホンの生き様そのもののような歌詞へと連なっていく、アッパーなロックナンバー「ラピスラズリ」へ。本当にこうしてライブで改めて聴いていると「リヴスコール」はバクホンにとって最高傑作と言ってもいい強度とメロディの強さ、そして優しさを持ったアルバムなんじゃないかとすら思える。もちろん「イキルサイノウ」や「ヘッドフォンチルドレン」という思い入れの強いアルバムたちが他にもたくさんあるのだけれど。
そして最後に再びストリングス隊とキーボードが登場すると、この編成だけに今回は最後くらいは壮大なバラード曲を演奏してしっとり終わる…のかと思っていたが、メンバーが音を鳴らしてイントロを作ってから将司がいつものように歌い始めたのは「刃」だった。本当にブレない。光舟はキーボードの前に歩いて行って、自身のベースアンプの上に立つようにして、この編成での演奏を本当に楽しんでいたのだが、ストリングスというどちらかというと洋の楽器たちがこの曲の持つ和の部分をさらに強く引き出している。それはある意味では定型化したように感じるストリングスの入ったJ-POPが日本人の琴線に最も響くということを証明しているかのようだったし、それは取り入れ方次第ではロックバンドでしかないバクホンのような音楽でもそう感じることができるのだ。
光舟は最後のコーラスパートでマイクスタンドが自身の前に置かれても全く使わなかった。それは観客の声を聞こうとしていたのだ。もちろん今はそれを聞くことはできない。でも今までだってずっとそうしてきたし、きっとまたそうなる時が来るという願いを込めているかのようだった。
演奏が終わると将司は最後にストリングスやキーボードのメンバーを見送り、
「また必ず生きて会おう」
と言った。その言葉がそのままアルバムになったのが「リヴスコール」であることを、我々はこのライブを見たことによってわかっていた。きっとこれからも生きる力が欲しくなった時に何回でもこのアルバムを聴くのだろう。
客電が点いて終演を告げるアナウンスが流れると拍手が起き、その後に規制退場をアナウンスするスタッフが
「感染対策にご協力いただきありがとうございました」
とアナウンスすると再び拍手が起きた。今のTHE BACK HORNのライブは曲と曲の間の拍手、曲が終わってMCでメンバーが話し始めるまでの拍手が非常に長くて大きい。
それはどうすればこの状況でもこうしてライブをやってくれていることの感謝を声が出せない中で最大限に示せるかということによるものであるが、バクホンのファンの人たちはそれを本当にわかっている。つまりは優しい。自分もそうでありたいと今年になってライブを見るたびに思うけれど、それは「リヴスコール」というアルバムを作ったバンドだからファンもそうした優しさを持っているのかもしれない。
そうして今年になってからはツアーにも2回参加するなどしてライブをよく見るようになったTHE BACK HORNであるが、それまではワンマンも行ったり行かなかったりというスケジュールなどによって変わったりしていた。
でも今はこうしてライブをやってくれるんなら出来る限り観に行きたいと思う。それは自分自身がこの状況の世界を生きていく中でTHE BACK HORNの音楽やライブが何よりも力になるということを潜在的に理解しているんじゃないかと思う。そしてこんなに音楽の力の凄さを感じさせてくれるライブをやってくれるから、またバクホンに会いたくなるんだよ。
1.トロイメライ
2.シリウス
3.ブラックホールバースデイ
4.超常現象
5.ジョーカー
6.自由
7.グレイゾーン
8.いつものドアを
9.シュプレヒコールの片隅で
10.君を隠してあげよう
11.夢の花
12.星降る夜のビート
13.コバルトブルー
14.シンフォニア
15.戦う君よ
16.世界中に花束を
encore
17.ミュージック
18.ラピスラズリ
19.刃
文 ソノダマン