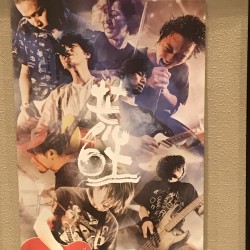前日に続いての横浜アリーナでのTalking Rock! Fes.。どこか前日よりも会場や座席にゆとりがあるように感じられるが、もともと京都大作戦と日程が丸かぶりだったことを考えるとそれも致し方ないところであると言える。京都大作戦は関東からも毎年たくさんの人が参加してきたフェスなだけに。
11:00〜 Vaundy
すでにワンマンはZepp規模で行っており、開演前に挨拶をした吉川編集長も見ているらしいが、多くの人にとっては初めてライブを見ることになるであろう、Vaundy。自分自身もJAPAN JAMでNulbarichのゲストで出演したのを見たことがあるだけなので、本人メインのライブを見るのは初めて。
開演時間になると、本人とバックバンドのメンバーが登場しているのはわかるのだが、ステージが暗く、さらにはステージ両サイドのスクリーンにも「Vaundy」のロゴが映し出されているだけで、ステージ上が全く映らない。つまりはVaundyの顔やバンドメンバーが誰であるかということがハッキリとはわからないのである。
そんな暗いステージ、暗い会場の中をムーディーなサウンド、Vaundyのスムースなラップとボーカルによる「不可幸力」からスタートするのだが、サビの歌唱を聴いた時に一瞬でわかった。この声は間違いなく本物だと。歌が上手い、歌唱力があるというのはもうライブをやる前から散々いろんなところで評価されてきたことであるが、それだけじゃなくてライブ会場の全てを掴み、持っていける声。初めて見たのがこの横浜アリーナでのライブであるだけに、そのキャパにはまだ早い存在なんじゃないか…と思っていた自分の予測はこの時点ですでにあっさりと消え去っていた。完全にアリーナクラスの会場をもこの声が支配している。
「不可幸力」ではVaundyはハンドマイクを持ってステージを歩き回りながら歌っていたが、「benefits」ではギターを弾きながら歌うことによってロックなイメージを持つし、「napori」では再びその声に酔いしれるようなラブソング…と1曲ごとにくるくるとサウンドを変えていく。それがわかりづらさ、捉えづらさにもつながっていたのも間違いないところだが、そこに一本大きな軸としてあるのがやはりこの声である。
「あっついな…」
と大きな体であるだけに早くも汗をかいており、タオルで顔を拭いたりしながら、この男の存在を知らしめた「東京フラッシュ」で観客の腕が上がりながら体を揺らせると、
「新曲、聴いてもらってますか?」
と観客に問いかけてから演奏されたドラマ主題歌に起用されている「花占い」は新曲とは思えないくらいにすでにたくさんの観客がこの曲を待ち望む曲になっている。こんなにアウェー感がないものなのかというくらいに観客が腕を挙げている姿を見て、もうこの男は単独でもこの規模のステージに立つべき存在なんじゃないかとすら思っていた。
そんな中でアッパーに突き抜けるメロディがよりVaundyの声の力を示す「怪獣の花唄」のただオシャレなだけでもムーディーなだけでもない、みんなのうたになっていてもおかしくないくらいのポップさはとかく声に意識が集中してしまいそうな中にあって、自分のようなロックリスナーすらも「めちゃくちゃ良い曲だな…」と思わざるを得ないクオリティとパフォーマンスで感服させられてしまう。
やはり最後まで暑がりながら、
「横浜アリーナ、初めて来たんですけど、凄いな。広いな。また来たいな」
と言って最後に演奏されたのは今年配信でリリースされた「しわあわせ」。
薄暗いステージに希望を可視化したかのような真っ白な光の柱が聳え立つ。その光がVaundyの姿を、声をより神聖なものに感じさせ、
「変わらない 変われないよ 僕ら
今もしっかり握っている
ちぎれない ちぎらないよ 僕ら
今もしっかり繋いでる手
溢れ出す願い込めて僕らは
今から君の見てる方へと
やるせない夢が醒めた頃に
また しわをあわせて」
というフレーズが感じさせる希望と、人間同士の存在の尊さ。そこに説得力を持たせているのはやはり圧倒的な声。感動して涙が出そうになっていた。それくらい、上手いを超越した、感情を揺さぶることができる声。
何かと議論の的になったりもしている存在でもあるし、はっきりとその顔はまだ認識できていない。でもこの日このステージ上にいたVaundyは間違いなく2つの意味で本物だった。これから何度となくこの横浜アリーナのステージに立つ存在になる。前日の秋山黄色のように、トップバッターにして完全にかっさらっていった。
1.不可幸力
2.benefits
3.napori
4.東京フラッシュ
5.花占い
6.怪獣の花唄
7.しわあわせ
12:15〜 ハルカミライ
Vaundyの余韻を掻き消すかのように、リハから関大地(ギター)、須藤俊(ベース)、小松謙太(ドラム)の3人が出てきてリハから曲を演奏しまくっているのはおなじみのハルカミライ。ついにパンクバンドとしてこの横浜アリーナのステージに立つ日がやってきたのである。
リハで曲を演奏していた3人がそのままステージに残り、開演時間になると橋本学(ボーカル)が合流するという、登場時間という概念が全くない、時間になった瞬間にすぐにライブが始まるというハルカミライのスタイルもすっかりおなじみであるが、「君にしか」「カントリーロード」という流れもすっかりおなじみである。
須藤はベースをステージ上に置いてゆっくりと歩き回り、関はアンプの上でギターを弾いてそこから大ジャンプを決めるという、ステージから客席に突入することはなくてもハルカミライらしいというか、ハルカミライでしかないライブは橋本もやはり暴れ回り、ステージの端の方まで歩いたりステージ上をスライディングするという「ファイト!!」「俺達が呼んでいる」へと繋がっていくのだが、横浜アリーナの観客がみんな腕を上げてこのバンドのパンクロックに目を輝かせている。
「そこの黒いマスクの姉ちゃん、目を逸らさないでくれよ。怖くないよ。優しいよ。そこの遅れてきた兄ちゃんもありがとうな。お前がいるここが、世界の真ん中!」
と、先日のDEAD POP FESTiVALの時もそうだったが、橋本はどんなに会場が大きくなっても、観客一人一人のことを本当に良く見ている。あれだけ激しく動き回り、Tシャツを脱いで上半身裸になって歌っていても、自分に向けて歌っている。自分に向けて歌っているということは、ここにいる一人一人に向かって歌っているということだ。だからどれだけステージから遠くなって、スクリーンで見るような距離になっても離れてしまった感じは全くしないし、Vaundyとは全く違うタイプだけれど、その歌の力がアリーナ全体に響いている。声量があるのはもちろん、そこにどれだけ思いを込めて歌うことができるか。ハルカミライのライブを見るといつも上手さよりももっと大事なものがあることを教えてくれる。
徐に上半身裸の小松がドラムセットから橋本の横まで出てくると、
「話すこと考えてきたんだけど、こいつの元気な姿を見ていたら全部吹っ飛んじゃった!(笑)」
と言って「世界を終わらせて」の歌い出しを4人全員で並んで歌う。その姿はこの曲においてはおなじみのものであるが、毎回そうしようと決めているのではなく、その場でそうなっているのだということがよくわかる。
「スーパースターやヒーローも意味がなくなっちまうくらいの」
というフレーズを、我々からしたらスーパースターやヒーローでしかないハルカミライが歌う「PEAK’D YELLOW」では客席最後列で飛び跳ねていた女性2人組を見つけ、
「1番後ろの姉ちゃんたち、楽しそうだな!」
と声をかける。こんなに広い会場でもそこまで見えている。よく広い会場になっても「1番後ろまでちゃんと見えてるから!」と言うアーティストがいるけれど、それを口にしなくてもハルカミライには本当に1番後ろまでちゃんと見えている。さらには、
「ルールを守ってる俺たちとお前たちが1番カッコいいぜー!」
とも。ハルカミライはこの状況になってから、かつてのように客席に飛び込むようなライブをやっていない。我々もハルカミライと一緒に歌っていない。ただ腕を上げ、手を叩くのみ。前日のHump Backの林もそうだけれど、ハルカミライも今の状況で1番カッコいいロックバンドの形をわかっている。ルールを破るのがロックやパンクなんじゃなくて、大切なものを守るためにそれを守る。
コロナ禍になる前から橋本はインタビューで
「殴るんじゃなくて抱きしめるのがパンク」
と言ってきたが、その姿勢は全くブレていない。むしろより強固になっている。そんなバンドに「カッコいい」と言ってもらえることのなんと嬉しいことか。
そして「ヨーロービル、朝」では薄暗い中でメンバーを白い光が背後から照らす。もうこれしかないというような演出によって神々しさすら感じるバンドの音を鳴らす姿。パンクバンドが横浜アリーナのステージに立っている。それを最も感じさせてくれる瞬間だった。
「眠れない夜に私」
と橋本が歌い始めた「アストロビスタ」がこの日も大団円を描き出す。パンクロックに、音楽に救われて生きてきたドキュメントと言えるようなこの曲の中で橋本は、
「こういう日があればまた1つ2つ、やっていけるよな」
と言葉にした。その言葉で涙が溢れてきてしまった。やりきれないようなことがたくさんあるような世の中でも、こうしてハルカミライがステージに立って、ライブを見ることができればやっていけるって思える。
いつものように残った時間でこの日4回目の「ファイト!!」でこの日もあいつのことをぶっ飛ばしまくると、
「日本中のすべてのロックフェスと一緒に歳を取っていこうぜー!」
と橋本は叫んだ。ロッキンや京都大作戦をはじめとした、中止になってしまったフェスへの思いがこの一言に集約されていた。
自分自身、毎年ロックフェスに行くことを楽しみにして1年を生きてきた。そのフェスで最後に花火を見たりして「また来年こうしてここで花火を見れていられるように」と思いながら。間違いなく、ロックフェスと一緒に歳を取ってきた。
きっとハルカミライだってそうだ。今年、この後もハルカミライはありとあらゆるフェスの出演者に名前が載っている。もし万が一a nationあたりからオファーが来ても、呼ばれたら全部出る、ライブが出来るんならそこへ行ってライブをする。そんな生き方のバンドだ。そんなバンドだから、いつもその日にしか絶対に見れないライブを見せてくれる。だからこうしてハルカミライのライブを見るのがやめられない。この日のライブも間違いなくそういうものだった。
リハ.ファイト!!
リハ.ウルトラマリン
リハ.100億年先のずっと先まで
リハ.Tough to be a Hugh
リハ.ファイト!!
1.君にしか
2.カントリーロード
3.ファイト!!
4.俺達が呼んでいる
5.春のテーマ
6.世界を終わらせて
7.PEAK’D YELLOW
8.ヨーロービル、朝
9.アストロビスタ
10.ファイト!!
13:20〜 Saucy Dog
年明けの日本武道館での対バンライブに、Saucy Dogはハルカミライを招いていた。その2組が並んでいるタイムテーブルにはTalking Rock!からの愛を感じる。その対バンライブの前日には武道館でワンマンも行ったSaucy Dog、ついに横浜アリーナに進出。
いつものように、せとゆいか(ドラム)、秋澤和貴(ベース)、石原慎也(ボーカル&ギター)が一人ずつ順番に登場して観客に頭を下げ、3人が集まって気合いを入れると、この日は「煙」からしっとりとスタート。ハルカミライのようなライブの派手さはないけれど、スリーピースならではの一つ一つの音をしっかり感じられるし、石原の澄み切ったボーカルはこうした広い会場の方が見合っているかのように伸びやかだ。
青い照明が海のように、あるいは青春の真っ只中にいるかのようにメンバーを照らす「シーグラス」、石原のボーカルの伸びがさらに増す、個人的にはこの曲の歌い方が非常に好きな「雀ノ欠伸」ともはやすっかりフェスでもおなじみのキラーチューンが続くと、せとが
「今日、ここに来るまで本当に楽しみだった。いろいろフェスが少なくなってきてるからこそ、みんなもそう思って来てるんだろうなって自分がお客さんとしてフェスに来ていた時のことを思い出していた」
と、今でこそこんなに大きなステージに立つようになっているけれど、自分たちと同じようにフェスに行き、それを楽しみ、それがこのステージにまでつながっているということがよくわかる話をする。
配信リリースされたばかりの「週末グルーミー」のタイトル通りに日常の週末の何気ない風景を描いた歌詞が
「自分が見たい未来だけを信じて」
と結ばれることで我々に微かでも確かな未来への希望を感じさせると、「ゴーストバスター」でアッパーに振り切れたかと思ったら石原が思いっきり歌詞を飛ばし、
「歌詞忘れちゃった!」
と素直に口にする。その姿に可愛さを見出した人もたくさんいるものと思われるし、自分ですらそう思ってしまった。
それでも石原がステージの端まで歩いて行ってギターを弾く「バンドワゴンに乗って」でさらにアッパーに加速すると、
「Talking Rock!ってロックってついてるじゃないですか。だからロックってなんだろうなって改めて考えていて。誰になんと言われようと自分自身に自由であることがロックだと思っていたんだけど、それは一歩間違えると自分勝手になってしまって、そのぶつけ合いになるとただのケンカになっちゃう。僕自身、そうやってケンカしてきてしまったこともあるし、メンバーともケンカしてことも何回もある」
と自戒の念も込めて口にしたのだが、それはきっと今の傷付け合いになってしまっているSNS上の状況への石原なりのメッセージだ。熱いことや説教臭いことは言わない。ただ自分自身のことを振り返ってその経験を踏まえたことを語るというのが実に石原らしいと思った。
そうして最後に演奏されたのは「いつか」かと思ったら「sugar」だった。武道館の時は序盤に演奏されていたこの曲は今やこの状況でのライブを締めることができる曲に成長した。アッパーな曲ではない、むしろ聴かせるような曲でさえも、ライブを重ねてきたことによって。アリーナのライブの最後にこうした曲を演奏できるバンドはそうそういないし、それがSaucy Dogとしてのこうしたフェスでの戦い方だ。それを確かに示した横浜アリーナのステージだった。
リハ.メトロノウム
リハ.新曲
リハ.ナイトクロージング
1.煙
2.シーグラス
3.雀ノ欠伸
4.週末グルーミー
5.ゴーストバスター
6.バンドワゴンに乗って
7.sugar
14:30〜 BLUE ENCOUNT
BLUE ENCOUNTは今やこの横浜アリーナでワンマンを行うくらいになったバンドであるが、本気のリハでは演奏はゴリゴリなのに、
田邊駿一(ボーカル&ギター)「辻村さん、地元ですけど、今日はお母さんは来てないんですか?」
辻村勇太(ベース)「たかこは来てないです(笑)」
田邊「今日はノーたかこです!(笑)」
とメンバーの空気が実に自然体なものなのも、すでにこのステージでワンマンをやっているという経験と自信によるものだろう。ちなみに吉川編集長は高村佳秀(ドラム)の「たかむラップ」をひたすらやらせようとしていた。
本番で元気いっぱいにメンバーが登場すると、
「横浜アリーナ、踊ろうぜー!」
と田邊が叫び、矛盾や悩みを抱えたままで踊るための「バッドパラドックス」からスタートし、田邊のファルセットボーカルとダンサブルなリズムによって観客は早くも腕を上げて飛び跳ねまくっている。熱いイメージのブルエンという曲ではないけれど、今のブルエンの幅の広さを感じさせてくれるこの曲がすでにライブの定番曲になっている。
すると「Survivor」からは江口雄也(ギター)のリフやタッピングと変幻自在のギターが炸裂しまくっていく。
「機械のような奴らに 支配される前に居場所を探せよ!」
というフレーズはタイアップアニメの主人公の少年たちに重なるものだったのが、今はこの状況を生きる我々へのメッセージとして響く。我々の居場所は間違いなくここや、こうしたライブの場だ。それはブルエンにとってもそうであるはず。
ブルエンはフェスなどでも毎回かなりセトリを変えてくるバンドであるが故に、ファンそれぞれがその日のセトリを予想したりしているのも実に楽しいのだが、この日は「ロストジンクス」「DAY × DAY」とブルエンの定番曲にして代表曲、いわゆるど真ん中と言えるような選曲が続く。ただなんというか、この日はそうした曲を自分が求めていた感もある。それはそのままブルエンの熱さや強さを感じたかったということなんじゃないかと思う。沈んだり削れたりしていく精神を音楽で奮い立たせてくれるような。田邊の声には少し不安に感じるところもあったけれど、それでも高村と辻村は我々が声を出せなくてもいつもと変わらないように観客を煽るように「オイ!オイ!」と声を出し、それに合わせて観客も腕を挙げるという形で応えている。
すると田邊が不意に歌い始めたのは「もっと光を」。やはりこの曲を歌うと田邊の声が本調子ではないんじゃないか?というのがより頭に過ってしまうけれど、
「悲しい記憶に寄り添うたび 答えを求めるの
これ以上誰かがこの思いを繰り返さないように」
「優しい希望に触れるたびに溢れた弱さだって
これから誰かが抱きしめるよ だから近くにおいで」
「戸惑いと間違いと向き合って気がついた
光は誰もくれない だから進むんだ」
というフレーズたちが我々を奮い立たせてくれるのは全く変わらない。むしろ今だからこそそれはより強く響いてくる。最後のサビ前の、今までだったら観客全員で大合唱する部分を、バンドはそれまでと同じように観客に預けた。もちろん誰の声も聞こえない。響くのはリズムだけだ。その光景は美しくもあるけれど、たまらなく寂しくもなる。でもまたいつか必ず横浜アリーナでこの曲をみんなで歌えるようにという思いが明日からの世の中を生きていくための力になる。その景色が必ず見れるように。
そしてきっと言いたいことがたくさんあるであろう田邊は
「本当にそこまで言うか?ってくらいに外の奴らに言われまくるよなぁ。
いろんなフェスがいろんな決断をしている。悲しい決断も多いけれど、大切な人を守るためにした決断なら間違いじゃないんじゃないかって。でも主催者がこのフェスをやるって決断してくれて、あなたがこのフェスに来るって決断してくれたから、このフェスが開催されている。クソみたいな日常、クソみたいな世の中だけど、俺たちに歌う場所を与えてくれてありがとうございます!」
と思いを堂々と口にして、4人で深く頭を下げた。鳴り止まないんじゃないかというくらいの拍手が起きていた。信じられないくらいに至る所から攻撃されまくっていたJAPAN JAMでも田邊は
「傷付けられても傷つけるな。傷付けてくるやつと同じになってしまう」
と言っていた。その言葉を聞いていたから耐えられる、気にしないでいれることもたくさんあった。あれから2ヶ月経って、ロックフェスに関する状況は良くなるどころかさらに悪くなってきている感すらある。でもブルエンがこうしてステージで演奏していて、田邊が我々に言葉をかけてくれるのならば、少しは前向きになれるような。
そんな中で最後に演奏されたのは「ハミングバード」だった。
「だけど まだ終わりじゃない
明日こそは。と願い 歌う」
と歌われる、アリーナワンマンでも最後に演奏されたのもよくわかるような壮大なスケールを持った曲。その曲は
「夢中で飛び込んだ世界は正解だ」
と締められる。今もロックに、ロックフェスに夢中でいるままだ。それは自分にとっては何にも変え難い正解だ。それを示してくれるバンドがBLUE ENCOUNTというバンドだ。
実は自分はブルエンを2013年の時点ですでにライブを見ている。解散してしまった、ねごとが自身のライブに招いたのを見ていたからだ。あれからもう8年も経っているというのが信じられないけれど、あの時はこんなにもこのバンドに救われるようになるなんてことも全く想像していなかった。
リハ.VOLCANO DANCE
リハ.NEVER ENDING STORY
1.バッドパラドックス
2.Survivor
3.ロストジンクス
4.DAY × DAY
5.もっと光を
6.ハミングバード
15:35〜 SHISHAMO
ライブ前に再びステージに出てきた吉川編集長がSHISHAMOの宮崎朝子(ボーカル&ギター)とのインタビューがいつも本当に面白いと話していたが、SHISHAMOを見出したMUSICAの鹿野淳も昔は宮崎は大人を全く信用しようとしていなかったと言っていた。そんな宮崎とTalking Rock!が信頼関係を持っていることがわかるような、今回のフェスへの出演である。
メンバーが順番にステージに登場すると、まるでバスケットボールの選手かと思うようなタンクトップ姿の宮崎に目が行くという完全に夏仕様かと思いきや、逆サイドの松岡彩(ベース)はロンTを着ているという対称っぷり。吉川美冴貴はいつもと全く変わらないTシャツ姿である。
その宮崎が
「Talking Rock! Fes.!」
といつものようにコール&レスポンスを仕掛け、レスポンスができない観客は拍手で応えると、宮崎がギターを弾き始めて「君と夏フェス」からスタートするのだが、夏フェスが中止になりまくっている中で聴くこの曲は今までと全く違うように響く。今年はこの曲で描かれているような光景を体験できる人がどれくらいいるのだろうか。きっと開催されても100%何も考えずに楽しめるという人もほとんどいないだろう。
「忘れられない夏になるかも」
という宮崎が感情を思いっきり込めるように伸ばして歌っていたフレーズを良い意味で捉えられるような夏にできるだろうか。
宮崎がイントロで辿々しくもキーボードを弾く姿が実に新鮮な「君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵!!!」は宮崎が
「久々のライブで緊張してる」
というからこその辿々しさもあったのだろうけれど、宮崎の畳み掛けるようなボーカルの迫力は緊張を全く感じさせることはない。
しかし曲間では吉川がトイレに行った後に消毒液を手につけたら実はハンドソープだったという天然っぷりで観客を笑わせ、宮崎は失笑気味というのも実にSHISHAMOらしい。
SHISHAMOは先月末に最新アルバム「SHISHAMO 7」をリリースしたばかりということもあり、その中から「かわいい」(浅野いにおによるこの曲をテーマにした書き下ろし漫画を読めるので初回盤の購入を勧めたい)、さらには宮崎の恋愛ストーリーテラーっぷりと、
「なんて欲深い生き物なんでしょう」
という歌い出しのフレーズの引き込みっぷりが素晴らしい「中毒」という曲を披露。SHISHAMOはアルバムごとに大人なサウンドに変化していくということがよく取り上げられているが、個人的にはそれに加えてこうした歌詞の進化が本当に素晴らしいと思う。
そんな新曲群をフェスのセトリに組み込むことによって、今のSHISHAMOの姿を見せてから、「ねぇ、」からはライブでの定番曲が続くのだが、スクリーンにはメンバーを背後から捉えた映像が映り、そこに歌詞が投影される「明日も」の、
「ダメだ もうダメだ 立ち上がれない
そんな自分変えたくて 今日も行く」
「良いことばかりじゃないからさ
痛くて泣きたい時もある
そんな時にいつも
誰よりも早く立ち上がるヒーローに会いたくて
痛いけど走った 苦しいけど走った
報われるかなんて 分からないけど
とりあえずまだ 僕は折れない
ヒーローに自分重ねて
明日も」
という、全ての歌詞を載せたいくらいにフェスがなくなってしまって心が折れそうな中でもこうして我々のヒーローたちに会いに来ている週末という現状に、かつてないくらい響いてくる。前日、この日とライブを見てきたアーティストたちが、自分たちが1番辛いであろう中でも我々に走り方を教えてくれる。それはSHISHAMO自身もそうだ。今になってこの曲がこんなにも刺さるなんて。
そんな「明日も」に続く形でスクリーンに歌詞が映し出される中で演奏された「明日はない」というコンボはきっとこれからもこうしたフェスでのSHISHAMOのライブを締めるものになっていくんだろうけれど、果たしてそれを今年あと何回見れるだろうか。そんな状況だからこそ、いつもと変わらずにステージに立っているように見える3人の姿が本当に頼もしく見えた。
SHISHAMOがこのフェスに出るのは実に7年ぶりだという。まだメンバーは10代だった。ベースがすでに松岡になっていたのか、まだ松本彩だったのかはわからないけれど、その話を聞いてSHISHAMOというバンドが今や長い歴史を持つバンドになったんだなと思った。アルバムも7枚も出しているんだもんな。
そうして過去に思いを馳せながらも今はせめて少しでも、忘れられない夏にしたい。
リハ.好き好き!
リハ.ロマンチックに恋して
リハ.恋する
1.君と夏フェス
2. 君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵!!!
3.かわいい
4.中毒
5.ねぇ、
6.明日も
7.明日はない
16:45〜 the LOW-ATUS
今勢いのあるアーティストが並ぶ中で明らかにタイムテーブル上で異彩を放っているのが、TOSHI-LOWと細美武士によるthe LOW-ATUSである。
吉川編集長も東日本大震災をキッカケに始まった2人の活動がこうしてthe LOW-ATUSとなったことをインタビューしたということを話していたが、これまでのライブでも酒を飲みながら好き放題話しまくるという形だっただけに、サウンドチェックでBRAHMAN「今夜」を2人で歌ったかと思いきや、
TOSHI-LOW「音が響きすぎる。こんな広いところでやらなくていいんだよ。渋谷アピアとかでやればいい」
細美「アピアって?」
TOSHI-LOW「キャパ80人くらいのハコがあるんだよ(笑)」
と、始まる前から笑わせてくれる。
本番でも全く変わることなく椅子に座り酒を飲みながら、
細美「カメラさん、MAN WITH A MISSIONのライブ撮ったことあります?あれみたいに俺の鼻から上だけをスクリーンに映してください(笑)」
TOSHI-LOW「あ、じゃあ俺も。(モニターを確認すると顔が全部映ってる)
全部出てんじゃん!自分で椅子の高さ調整すんの!?(笑)」
と、笑いを堪えろというのが無理なくらいに爆笑トークを展開してなかなか歌が始まらず、ようやく「サボテン」を歌い始めると、本当にマンウィズのライブみたいに鼻から上しか映さないようなカメラワークをするというカメラマンのノリの良さに、めちゃくちゃ良い曲を歌っているはずなのに客席からはクスクスという堪えきれない笑い声が漏れてしまう。
細美「みんなトイレタイムか、ご飯タイムかってくらいに人いなくなった(笑)」
TOSHI-LOW「一面真っ青!(横浜アリーナの座席は青)」
と、まさかの休憩時間にしている人の多さすらも笑いに変えながら、
TOSHI-LOW「the LOW-ATUSってカッコつけてる名前を改名しようと思って、昨日寝ないで考えてきた。今日はSUPER BEAVERとかキュウソネコカミとかSHISHAMOとか動物の名前のバンドが多いじゃん?だから俺たちもそれを見習って、「いきものがかり」に改名します!(笑)」
と言いながらその後に歌い始めたのは「ロウエイタスのテーマ」なので、いきものがかりに改名した意味が全くない。
この日のタイムテーブルでこのthe LOW-ATUSの次の出番はキュウソネコカミである。ということは、いろんな人がなんらかの形でコラボするんじゃないかと予想していたであろう、ゲストとしてステージに招かれたのはキュウソのヤマサキセイヤ。
「サブカル女子」で「細美武士」というフレーズを使ったことを今になっても問いただされるという公開処刑となり、
細美「TOSHI-LOWが「俺の曲も作れよ!」って言って作ったのが「TOSHI-LOWさん」(笑)曲のタイトルに「さん」ってつけないだろ!(笑)
しかもTOSHI-LOWは俺みたいにいじって欲しくてそう言ったのに、TOSHI-LOWを崇め奉るみたいな曲になってるし(笑)」
と詰められまくる中、
TOSHI-LOW「セイヤだけじゃ役不足だからもう1人呼ぼう」
と言って呼び出されたのは、某雑誌でTOSHI-LOWと対談していた、この日のトリのSUPER BEAVERの渋谷龍太。
TOSHI-LOW「ぶーやんを無駄遣いします(笑)」
と言うと、その渋谷が
「「お腹痛い」って歌ってるけど、お腹痛いのは怖い先輩にいきなり呼び出されたこっちです」
と前口上を述べて始まった「みかん」は音源でも細美が歌いながら笑ってしまっているのがそのまま収録されているが、セイヤと渋谷が
「お腹 お腹痛い」
のフレーズでコーラスを添えながら、やっぱり全員笑ってしまう。最後には腹巻を巻いたセイヤが腹を出すという展開になり、渋谷は座り込んでしまう。
歌い終わると次の出番のセイヤは解放されたが、
TOSHI-LOW「お前がステージにいれば人が増えるから」
という理由で渋谷は帰してもらえず、嫌そうな顔をしていると、まだあまり付き合いがないという細美にTOSHI-LOWが
「素人ナンパモノのAVに出てくるような見た目してるじゃん」
というわかりやすいのかわかりにくいのか全くわからない紹介をして、ようやく開放する。
しかしもう持ち時間が全然ないのにまだ3曲しかやっておらず、
細美「絶対間に合わないじゃん(笑)吉川、2分だけ押させて!」
とお願いするとすぐに
TOSHI-LOW「いいって!」
と返事を聞いていないのに無理矢理了承させて、「通り雨」「いつも通り」という喋ってる姿とあまりにギャップのある歌を響かせる。やはり細美の歌はアコギと歌だけという形でも、いや、だからこそ強い力を持っているということがわかるし、TOSHI-LOWのボーカルもまたOAUの活発な活動を経てより深みが増しているように聞こえる。特に「いつも通り」の
「どこへ行くも 肩を並べよう」
というフレーズはこれからもこの2人がこうして一緒に歌い続けていくという未来を感じさせてくれた。それがどれだけ希望を与えてくれるかというのは、この2人を見てきた人ならわかるはずだ。
この状況のフェスでこんなに笑えるなんて全く思ってなかった。この2人のことだから怒りやシリアスな方向に持っていこうとすればいくらでもできるはず。でもそうはしない、こちらにひたすら「楽しい」という感情を満たしてくれる。しかもそれを後輩たちとともに作ることによって、より一層この日でしか得られない楽しさにしてくれる。それは間違いなくこの2人の愛情によるものであるし、それを見せてくれる機会を作ってくれて、いつも2人にインタビューをしてきたTalking Rock!には本当に感謝しかない。
リハ.今夜
リハ.丸氷
1.サボテン
2.ロウエイタスのテーマ
3.みかん w/ ヤマサキセイヤ、渋谷龍太
4.通り雨
5.いつも通り
17:50〜 キュウソネコカミ
セイヤがthe LOW-ATUSに呼び出されたことによって、まず間違いなく演奏されるであろうと思われていた「TOSHI-LOWさん」を圧倒的なパワーでリハで演奏していた、キュウソネコカミ。リハから観客は立ち上がって本編と全く変わらない様子であったが、トリ前という実に重要なポジションでの出演ということに、Talking Rock!がキュウソのことを本当に評価してくれているのがわかる。
メンバー5人が登場すると、重たいサウンドのイントロによる「ウィーアーインディーズバンド!!」でセイヤは
「今日は日々のモヤモヤを少しでも削りに来ました!」
と叫んだ。その姿、目力は先ほど先輩たちにいじられていたのとは全く別人と言っていいものだった。キュウソとしてステージに上がったからには、キュウソとして鳴らす音楽、伝えたい思いがあるというように。
5色の照明がメンバーそれぞれを照らす「5RATS」での前のめりなほどの気迫とメンバー全員によるコーラスの迫力はキュウソというバンドの持つ本質の部分をこの上なく抉り出してくれるが、
「推し合い、推され合いながら生きていこう」
という意識を持って観客と向き合ってきたバンドだからこそ「推しのいる生活」では我々がバンドやアーティストのことを心配したりしているのと同じように、キュウソもまた我々が抱えざるを得ない今だからこその不安ややるせなさを少しでも吹き飛ばしてやろうという意識を感じざるを得ない。その相互作用が単なる慰め合いではなくて、一緒にこの苦しい状況を乗り越えていくためのものになっている。
そんな思いを一気に放出するのは「The band」。オカザワカズマ(ギター)は自身の立つ下手側の端の方まで行って観客の少しでも近くでギターを弾き、セイヤの叫ぶような熱のこもった
「ロックバンドでありたいだけ」
というフレーズが強く刺さる。それはそのまま、ロックバンドであることがロックフェスに出ることになるからである。音楽を鳴らし続ける場が存在していて欲しい、そんな願いがこもっていた。
アウトロのドラム連打だけでなく、曲中でもソロを入れるという形で自身の演奏をアピールしていたソゴウタイスケを
「2日間の中で1番上手いドラマーとは言わんけど、1番長いドラムソロやってたやろ!」
とセイヤはなぜかベタ褒め。そうした形でキュウソをアピールするということらしいが、明らかに褒められ過ぎていたソゴウはいつものように謙遜気味。
そこから
「なめんじゃねぇ!」
の叫びがキュウソだけでなくロックバンド、ロックフェスの声を代弁するかのような「ビビった」から、フェスでこんなにもこうした熱いサイドのキュウソの面を連発しまくるとは、と思う「わかってんだよ」と続くのだが、これは間違いなく今の状況を受けてこそのセトリだろう。
「僕はただ生きているだけだった」
というサビの歌詞。ただ生きているだけの日々を意味のあるものにしてくれたのはロックフェスだった。そのために1年頑張って生きて働いて、その日を目指してきた。それは我々もそうであり、バンドもそうなのかもしれない。あのフェスの景色を見るために。この曲が出た時にそれまでのキュウソらしからぬ熱さにたくさんの人が驚いていたけれど、今ではこうした面こそがキュウソというバンドの最大の持ち味であり芯の部分と言っていいだろう。
そしてソゴウがイントロのドラムを叩き始めたのは「ハッピーポンコツ」であるが、ここまでの景色を見てきたヨコタシンノスケ(キーボード)は
「やっぱ必要なんじゃない?ロックフェスいるでしょ!色々キツいことを言われたり目にするかもしれないけど、ここにいる人だけはロックフェスを肯定していきましょう!
でも思い詰めないで!頑張り過ぎないで!8割くらいでいいから!」
と、どこか目を潤ませながら思いを叫んでいた。立場は違えど、我々と同じようにロックフェスを愛し、だからこそ気づいたり悲しんだりする。自分はキュウソのことを紛れもなくロックスターだと思っているけれど、ほかのロックスターたちとは違う親しみやすさをずっと感じさせてくれる。だから今でも我々と同じような気持ちをロックフェスにも抱いているバンドなんじゃないかと思える。
キュウソはロックフェスが楽しいだけのものじゃないということを身を持って知っているバンドだ。ロッキンではPARK STAGEのトリを務めた位置にも関わらず、
「GRASSに立てなかったのめちゃくちゃ悔しいー!!!」
と泣きそうな顔で叫び、VIVA LA ROCKではホルモンと被ったことによってガラガラになってしまい、ステージ上で弱い姿を見せてしまったこともある。
でもそうした悔しい経験がのちにどちらのフェスでもメインステージに立つための原動力になった。
「バンドやってて本当に良かった!」
と言えるような景色を見ることができるようになった。キュウソというバンドのストーリーにおいて、ロックフェスはそのままバンドが強くなってきた歴史そのものであり、この日我々が見ていたキュウソもそうした経験をしてきたからこそこのステージに立っている。そんなバンドだからこそ、フェスがなくなっていくのが自分のことのように、ではなくて自分のことなのだ。特に今年は5日間でたった40組しか出演できないロッキンのGRASS STAGEに立つバンドに選ばれたということは本当に嬉しかったのだろうし、周りの出ることができない仲間たちの思いも背負ってそこに立とうとしていたはずだ。
キュウソのそうした思いを感じて思わず泣きそうになってしまうけれど、カワクボタクロウ(ベース)はサビ前のキメでいつものように目元でピースサインをしたり、力瘤を作ったりする。そうしたメンバーの姿が泣きそうになりながらも我々を笑顔にしてくれる。ああ、やっぱりキュウソをロックフェスで見続けることができる世の中であって欲しい。
やっぱり、ロックフェスは必要だ。こんなにたくさんの人に生きていく力と笑顔と涙を与えてくれるのだから。こんなに感情が揺さぶられる1日は人生において他にない。そんな人がたくさんいる。
リハ.おいしい怪獣
リハ.TOSHI-LOWさん
リハ.メンヘラちゃん
1.ウィーアーインディーズバンド!!
2.5RATS
3.推しのいる生活
4.The band
5.ビビった
6.わかってんだよ
7.ハッピーポンコツ
19:00〜 SUPER BEAVER
いよいよ2日間の最後のアクト。そのライブの前にはやはり吉川編集長が出てきて挨拶とトリのアーティストの呼び込みを…と思っていたら、
「どうも、Talking Rock!編集長の吉川です。今日皆さんに言いたいことは、ロッキンオンJAPANは買わない、MUSICAは買わない、音楽と人は買わない、Talking Rock!を買ってください」
と話し始めたのは、メガネをかけてポロシャツを着用し、口調まで吉川編集長に似せたTOSHI-LOW。すぐさま本物が出てきて交代となるのだが、知らない人からしたら「他の雑誌を貶すやつ」と捉えられてもおかしくないけれど、TOSHI-LOWはロッキンオンのインタビューを受ける時は必ず渋谷陽一社長とのツーショット写真を撮り、ロッキンやCDJにもOAUで毎回出演している。
かつては関係性が悪かったMUSICAの鹿野淳とも主催フェスのVIVA LA ROCKに出演するなど、近年は友好的になり(ビバラ出演時に「昔はお互いクソガキだった」と振り返っていた)、音楽と人では渋谷龍太と対談し、主催イベントには毎回のように出演しては金光編集長をいじりまくっている。
つまりこれは全ての雑誌とその作り手との間に確固たる信頼関係を築いているTOSHI-LOWにしかできないパフォーマンスだ。the LOW-ATUSはその全ての雑誌でインタビューを受けている。
そんな思いがけない呼び込みを受けて(?)、2日間のトリとしてSUPER BEAVERがオンステージ。本来ならばすでに他のフェスでもその大役を果たしていたはずだったのが惜しくてならない。
4人がステージに現れると、渋谷龍太(ボーカル)はthe LOW-ATUSにゲストで出た時は結いていた髪をほどき、赤いシャツを着た完全ロックスターモードで、藤原”33才”広明(ドラム)にピンスポットが当たり、リズムを刻み始める。
かなりの間、リズムを刻んでいるとそこに柳沢亮太のギターが鳴り、次の瞬間には渋谷が
「ロックスターは死んだ まだ僕は生きてる」
と歌い始める。まさかの「27」始まりに驚きを含んだ拍手が起きる。渋谷は
「もはや終わればと思った 挫折もあったな」
というフレーズに思いっきり感情を込めて、語気を強めて歌う。そのフレーズを最も伝えたいというように。そして最後の
「時間が解決してくれる もう その通りだと思う
でも正しくは 生き続けている 自分で導いている
歓びを 楽しさを 過去すらも 変えるような出会いを」
というフレーズに至って思う。この1週間ほどの悲しい知らせの数々や、それに伴う人と人との諍いも、時間が経てば解決してくれるのだろうかと。でも、ロックスターは自分の目の前でこうして生きている。
そんなシリアスなスタートから一変するように
「いつだって、いつだって、始まりは青い春」
と言って始まった「青い春」では観客が思いっきり両手を掲げ、Bメロでも高く腕を上げて手拍子をする。
「会いたい人がいる 胸の奥をずっと 掴むあなたが
くじけそうならば 今度は僕らが 笑わせたいんだよ
あなたが生きる意味だ と 伝えたら 笑うかな」
というフレーズが本当に我々に歌いかけてくれているようで、笑いながらも涙が溢れてくる。こうして自分の、ここにいる1人1人の目の前で歌うのが生きる意味だと言っているかのような躍動感と幸福感に溢れた歌と演奏。この日、SUPER BEAVERのTシャツを着た人が本当にたくさんいた。間違いなく1番多かった。そんな人たち1人1人の期待や思いに最大限の誠心誠意という言葉が似合うパフォーマンスで応えている。
藤原のスネアの連打が楽曲にスピード感を与え、それがロックバンドとしてのSUPER BEAVERの音の強さ、
「今をやめない やめない やめない」
「正々堂々 威風堂々」
という歌詞が意思の強さを感じさせる「突破口」では最後に渋谷以外の3人の声が重なり合う。そのフレーズの、もはやコーラスというよりもそれぞれがボーカルとして思いっきり歌っているかのような声量。伝えたい思いや言葉をどうすれば真っ直ぐに、一直線に伝えられるかということを体と心で理解しているバンドだ。
柳沢のアルペジオが藤原と上杉研太(ベース)のグルーヴするリズムに乗る「予感」で渋谷も観客も軽やかに踊る姿は、
「楽しい予感のする方へ 心が夢中になる方へ
正解なんて あって無いようなものさ 人生は自由
今 予感のする方へ 会いたい自分がいる方へ
他人の目なんて あって無いようなものさ 感性は自由」
という歌詞そのもののようだ。そう思わせてくれるバンドだから、みんなこうして最後まで残ってライブを見ているのだ。
「「27」でバシッと始まるのがカッコいいんじゃないか、って思ってたんだけど…まさかライブ前にステージに上がることになるとは(笑)」
とthe LOW-ATUSのライブにゲスト出演することになって予定が狂ったことを話していたが、
「こうなるんじゃないかと思って、少し練習していた(笑)」
と、あの見事な口上は練習の成果であることが明らかになる。
そんな演奏中とは異なる朗らかさもthe LOW-ATUSの2人が与えてくれたものかもしれないが、そんな中で演奏された「愛しい人」の
「ぱっと一言じゃ 言い表せないのが 愛だ」
というフレーズと壮大なメロディがアリーナ規模に相応しいラブソングとして鳴り響き、メンバーそれぞれのコーラスが強く響く「アイラヴユー」へ。リリース時期が近いということもあるけれど、サウンドは違っても全く同じことを歌っている。それはバンドの、ソングライターの柳沢のブレない姿勢そのものだ。その姿勢が青臭く感じてしまいそうな歌詞やメッセージに最大限の説得力を持たせている。
「我々17年目のバンドですが、10年目までは全くフェスに出たことがなかった。若気の至りで突っぱねていたのではなくて、ただ誰からも相手にされていなかった。そんな中でTalking Rock! Fes.は我々のことを呼んでくれた。そんなバンドがこうして横浜アリーナで開催されていて、そのトリを仰せつかっているというのは我ながらドラマがあるんじゃないかと」
と、バンドにとってのフェスの体験をしたのがかつてのこのフェスだったことを語る。その頃からこのバンドのことを見ていて、評価してきた。それがこの日や、ここに至るまでのバンドの日々に繋がっていることを考えると、Talking Rock!に本当に感謝しかない。こうしてこの日のトリをこのバンドにしてくれたことも。
そんな思いが曲からも溢れるのが最新シングル「名前を呼ぶよ」。
「助けたい人に ずっと助けられている
ありがとう なんて こっちの台詞なのに
何ができるかな 今何ができるかな
考えた途端に とめどなく思い浮かぶ 顔 顔
そうか これが生きること」
というありふれているようでいて、実にビーバーのものでしかないなと思わせてくれるような歌詞。「愛しい人」もそうだけれど、最近の曲からは本当に優しさを感じる。それは何かとギスギスしていたり、せざるを得ないような状況の今だからこそ、こうした曲が、音楽が必要なんだと思わせてくれる。
「トリなのでアンコールの時間をいただいておりますが、最後の順番にやるだけと思っていますので、このまま最後の曲を演奏させていただきます!」
と言って捌けることなくそのまま演奏されたのは「さよなら絶望」。もはやコーラスのレベルを超えた上杉の叫ぶような歌唱。そこには間違いなく絶望を吹き飛ばそうとしているバンドの姿があったけれど、本当の意味で絶望にさよならをすることができるのは、この曲のコーラスを我々がメンバーと一緒に歌えるようになった時だ。
「さよなら絶望 絶望 何のための爆音だ
抗ってやろうぜ 抗ってやろうぜ 抗ってやろうぜ
涙目でもいい さよなら絶望」
というフレーズを。そんな絶望に抗うためのロックであり音楽。音楽にまつわることで感じてしまう絶望から引っ張り上げてくれるのも、やっぱり音楽なのだ。SUPER BEAVERはそうして我々1人1人を引っ張り上げてくれるバンド、音楽になった。確信と誇りと責任と覚悟。その全てを持ち合わせた、文句なしの大トリとしてのパフォーマンスだった。
1.27
2.青い春
3.突破口
4.予感
5.愛しい人
6.アイラヴユー
7.名前を呼ぶよ
8.さよなら絶望
ライブが終わると初日と同様に吉川編集長が最後の挨拶に登場して喋り始めるのだが、感極まって泣いてしまい、喋れなくなってしまう。そこにはこの状況だからこその重圧があったことも口にしていたが、自分はTalking Rock!を何冊か購入して読んだことがあるが、このフェスに来るのは初めてだったので、吉川編集長の関西人らしい軽い口調に「吉川編集長ってこういう喋り方の人なのか」と少し驚いていた。
そういう人が感極まるなんて全く思っていなかった。だからこそその姿に2日間本当に楽しませてもらった、音楽から力を貰った身としてももらい泣きしてしまいそうになったのだが、ステージ袖から走ってきて編集長を抱きしめる4人。それはライブを終えたばかりのSUPER BEAVERだった。その姿は彼らの音楽や言葉がそのまま人間そのものであることを表していて、また泣いてしまいそうになった。本当に頼もしいバンドだし、そんなバンドがこのフェスを、吉川編集長を本当に愛しているのがわかる。
「これからも音楽を、ライブを、堂々と楽しんでください」
という吉川編集長の言葉に、ああ、それで良いんだよな。正解かはわからないけど、こうしてこのフェスに来て、今の状況の中でライブを見ることは間違ってないんだよな、と思えた。今年でTalking Rock!は25周年。30周年の時にはこうしたモヤモヤが微塵もないような、本当の意味での祝祭になりますように。その時までTalking Rock!を絶対に続けてもらわないといけない。
文 ソノダマン