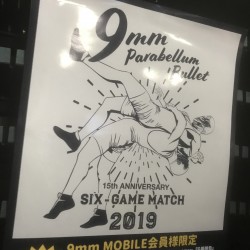SKY-HIは自粛期間中にも新曲を次々と作り、さらには自宅からの配信ライブという、これはロックバンドにはできんな、というフットワークの軽さで今の世界の状況に対する活動を見せていた。
そんなSKY-HIが今回はライブ会場からの配信ライブを開催。ライブ前の本人のコメントには
「オンラインライブは生のライブの代替品には絶対にならない。でも劣化版であってもいけない」
と書かれていたが、それをどうやって証明するのか。何やらいつものライブとは違う仕掛けを用意しているようで、これは是非とも自分の目で見て確かめないと、ということで3500円払ってオンラインライブのチケットを購入して視聴することに。
19時開始のはずだったが、少し押して15分からの開始に。配信ライブで開始が遅れるとトラブルが起きたんじゃないだろうかとも思ってしまうこともあったりしたが、どうやらそういうわけではないらしい。
ようやく待機画面が切り替わると、映し出されたのは明らかにSKY-HIであろう男の後ろ姿。白衣と言っていいかもしれないくらいにロングの白いシャツを着用して、左手には光るボールのようなものを持っている。
会場は暗く、本人の顔が視認できるとはいえ、まるで影が動いているかのようにラップし始めたのは「Sky’s the Limit」。金髪のSKY-HIが早くも高速ラップをかましまくるが、その映像はスマホで見ていても実にクリアであり、Blu-ray映像作品を見ているのかと思うほど。
さらにはレーザー光線が飛び交いまくるという演出もあるのだが、
「体温のあるテクノロジーとの融合」
をこのライブのテーマに掲げており、ただ演奏するだけというものにはならなそうである。
演奏と書いたのは、この日のライブはギター、ドラム、キーボード、DJというバンドメンバーを加えたセットで行われており、そのメンバーの演奏が強いグルーヴを生み出すことによってSKY-HIのラップと歌唱がさらに引き立つというものになっている。
「Doppelganger」ではそのバンドのサウンドがギターを始めとしてかなりノイジーなものになっていたが、曲自体の展開もアップダウンが激しければ、SKY-HIの歌唱も激しい。
レーザーだけではなく、背景にこれまでリリースしてきた作品のジャケ写が次々に映し出されるという映像もここからはふんだんに使われていくことを示唆する「Persona」は
「奴隷制が選択とはカニエの失言
でも喜んで奴隷になってる奴らがいるぜ」
とアメリカの超人気ラッパーである、カニエ・ウエストの発言を歌詞に盛り込みながら、今の社会への強いメッセージを放っていく。こうした曲を聴いていると、やはり言葉という点ではヒップホップに勝る音楽はないなと思えてくる。
赤い照明に照らされるSKY-HIの姿が実にセクシーな「Run Ya」では銃声のサンプリングに合わせてSKY-HIが銃を撃つようなアクションを見せると、背景にガラスが銃弾を撃ち込まれて割れたようなものになるという歌詞をリアルタイムで表現するという映像に。これぞまさに「体温のあるテクノロジーとの融合」の一つであるだろうし、この1本の配信ライブのために本人やバンドメンバーはスタッフはどれだけの時間と労力を費やしてきたのだろうかと思ってしまう。
音源では元ぼくのりりっくのぼうよみ、現たなかとコラボしている「何様」では再び超高速ラップが火を噴き、それに合わせてドラムの手数も変化するというバンド編成ならではのアレンジを見せ、「F-3」ではそれまでは基本的にSKY-HIをメインにアップで映していたカメラがステージ全体を映し出すようになることでSKY-HIの後ろでバンドの演奏も映る。とはいえ歌うSKY-HIに合わせてカメラも移動すると、アウトロでの「オーオーオー」というコーラス部分を終えた瞬間にSKY-HIが倒れると会場も真っ暗になる。
するとSKY-HIは椅子に座っており、その状態での歌唱とアコギの演奏というアレンジで「Limo」が始まるのだが、途中でEDM的にガラッと変化すると椅子から立ち上がって歌い、三角形や四角形のレーザー光線がSKY-HIを包み込むという演出には思わず「美しいな…」という言葉が口から漏れ出そうになってしまう。
タイトルからして夜景的な映像が映し出されるであろう「TOKYO SPOTLIGHT」はむしろ夜景というよりも宇宙空間にいるかのような映像であり、SKY-HIも無重力空間下のような軽やかなダンスを披露。
この辺りからは武器の高速ラップだけでないポップスターとしての面も見せてくれるが、ラップの凄まじさは言わずもがな、この男は本当に歌が上手い。その上手さはやはり抜群のリズム感によって生まれているものであるし、それはかつて鹿野淳がKREVAを
「この人はほんっとうに歌が上手いんです。それがラップの上手さにも繋がっている」
と評していたことを彷彿とさせる。SKY-HI自身も「PROPS」でKREVAとコラボしていたが、ラッパーとして、エンターテイナーとして影響を受けているはず。
オンラインライブということで客席には観客はいないが、「Tumbler」では「Yeah」というコール&レスポンスをカメラに向かって行うあたり、SKY-HIは画面の向こうにたくさんの人がいてくれていることを信じてパフォーマンスをしているのだろうし、それは自身も軽やかに踊りながらもきらめくようなサビで
「踊ろうぜー!」
と誘いかけるところからもわかる。
「キック、スネア、キック、キック、スネア」
とSKY-HIがドラムを指揮するようなイントロからスルッとバンドが加わっていく「Chit-Chit-Chat」ではスクラッチ多めのサウンドも歌唱も実にクールなものに変化していくし、SKY-HIの爽やかな出で立ちがそうしたサウンドや歌唱に実によく似合う。
そのバンドサウンドをグルーヴさせていったと思いきや、一瞬ストップして「愛ブルーム」へ。SKY-HIはフェスなどに出演する際もバンド編成であることが多いが、そのバンドメンバーたちとももう長い付き合いであるだけに呼吸は完璧に合っているし、ギターソロではギターメンバーがアップに映し出されたかと思いきや、次の瞬間にはSKY-HIがドラムセットの横でパーカッションを叩いている。
しかも「スマイルドロップ」ではパーカッションを叩きながら歌うというとんでもないことまでやってのけてしまう。もう天才としか言いようがないが、それは授かったものではなくてSKY-HI自身の凄まじい向上心の現れでもある。(元々バンドでドラムをやっていた経験があるとはいえ)
アウトロでギターがそのまま「ナナイロホリデー」のイントロに変化するというシームレスな曲と曲の繋ぎを見せると、今度はSKY-HIがギターを弾きながら歌う。その姿はラッパーというよりもバンドのボーカルと言ってもおかしくないような。そんな男が
「こっからお前の顔見えねーぞ、でも感じてるぞ!」
と叫ぶ。自分のようにSKY-HIの器用さとバイタリティに驚いている人が画面の向こうにたくさんいることをわかっているかのように。
曲中には
「今日が最高だって思えるような1日になれば!」
と言った直後に
「必ずまた戻ってくるから It’s Alright
この冒険の続きはそこでしよう」
と歌われると、通常のライブができる日がまた戻ってくるはずだ、という気持ちにさせてくれる。
ここまではほぼ曲間もなくひたすら曲を連発してきたが、
「元気?」
とカメラに向かって問いかけると、
「熱気が直接来ないからいつもより汗かかないかと思ったら全然!」
とすでに汗だくになった体を拭きながら、やはり無観客であってもライブをやるということはこうして汗が出てくるということを示してくれる。
この日のライブはツイッターで「#SKYHI生配信」というタグで感想を投稿することを推奨しているのだが、
「ハッシュタグ見てー!これが現代のスマホ中毒の闇か!(笑)」
と自身でライブの感想を追ってみたくてしょうがないようだ。
本来はこの内容のライブをツアーとしてやるつもりだったようで、
「1できないんだったら0.5や0.7でいいやってなるんじゃなくて、1できないんだったらAかBっていう全く違うことをやるって考えていた。
最高のことばっかりじゃないが、最高に近づけることはできる!」
と持ち前のポジティビティを感じさせながらも、
「配信がライブの代替品になるっていう記事とかも見るけど、何言ってんだなるわけねーだろ」
とあくまで配信ではなくて通常のライブがやりたい胸のうちを吐露し、さらには今の音楽業界やエンタメ業界が置かれている状況について、
「音楽や本や映画がなかったらどんな人生になっていただろうか。エンタメ業界に向けられている白い目は俺がデビューした頃に向けられていたものと同じ感じがする」
と、その見た目や対応力からするとエンタメ業界がなくてもSKY-HIは生きていけそうな気もするけれど、やっぱりそうしたものに感動や刺激をもらって、今はそれを与える立場になっているのだし、SKY-HIとしてデビューした当時に「アイドルがラップの真似事してる」的な見られ方をしていて(今もそう思ってる人もまだたくさんいるだろうけれど)、それを自らの活動によって塗り替えてきたSKY-HIだからこそ、今のエンタメ業界が置かれている状況を打破できる存在になれるんじゃないかと期待してしまう。
このMCの前はどちらかというとポップサイドの曲が続いていたが、「Name Tag」からは再び高速ラップを交えたヒップホップモードに転じていき、不可能だと言われているようなことも、SKY-HIが挑みさえすればそれは可能になるんじゃないだろうか?とすら思える「Walking on Water」では背面の映像にその信念とでも言えるような歌詞が映し出される。水の上を歩くなんて絶対に人間にはできないことだけれど、そういう風に無理だと言われていることにも楽しんで挑んでいきそうな感じすら見受けられる。
途端に和風なサウンドが流れたので、ここで「新曲?」とも思ったが、これはSALUとのコラボ曲である「SS」のSKY-HIの単独ライブバージョンでのアレンジであった。これは映像を見たらコラボ相手であるSALUもビックリするんじゃないだろうか。
レーザーと映像がSKY-HI自身に降り注ぐことによって、まるでSKY-HI自身が映像なのかと思ってしまうような加工が施された「As a Sugar」を終えると、壮大な「フリージア」でカメラにアップになった歌う表情は鬼気迫るようなものであり、曲中に
「もう辞めようかと思うことも何回もあった。でも音楽はずっと隣にあった。そして今日画面の前のお前に辿り着いたんだ。君はどうやって今日に辿り着いた?君がもしどんなに最低なやつだったとしても、俺が今日肯定してやろう。
俺の音楽に辿り着いてくれてありがとう。君の生きる価値をこの音楽で証明しよう!」
と見てくれている人への最大限の感謝を告げると、「Young, Gifted and Yellow」ではSKY-HIが育ってきたであろう東京の街並みが映し出される。
すると「LUCE」では画面にキーボードを弾く手元が映し出され…と思ったら弾いているのはSKY-HI本人。歌とラップだけてだけで充分と言ってもいいはずなのに、パーカッションもギターもキーボードも弾きながら歌ってしまう。何が彼をそこまでさせるのだろうかとも思ってしまうけれども、それはやはり舐められたくないという思いの反動なのかもしれない。アリーナクラスのアーティストになってもなお、そうした思いは消えていないというか。
今年世に放たれた曲の中でも最もポップな「そこにいた」もまたキーボードを弾きながら歌うのだが、星空のような夜空が映し出される映像も含めて、この曲だけ聴いたら本当にキーボードを弾きながら歌うタイプのシンガーソングライターのようですらある。
タイトルに合わせて美しく黄色く光る満月がステージに出現し、その光に照らされるようにしてキーボードを弾きながら歌う「Over the Moon」は最初はSKY-HIのキーボードボーカルのみからバンドサウンドになるとハンドマイクで歌いながら踊るという形に。
本当に1人何役こなしているんだ、とも思うしなんなら作ろうと思えば全ての演奏を自分でやってレコーディングすることすらできそうであるが、そうしないのは演奏しているメンバーや曲を作ってくれる人への圧倒的な信頼だろう。
再びキーボードを弾きながら歌う「アイリスライト」はバラードと言っていいようなタイプの曲であり、SKY-HIも歌い上げると言っていいような歌唱法に。背面に歌詞が映し出されるだけに、そのメッセージも真っ直ぐに響いてくる。
コロナ禍という状況もそうだし、なかなか悲しくなってしまうようなニュースも多い。そうしたニュースを見ているだけでこちらもネガティブな方へ引っ張られてしまいそうになるけれど、SKY-HIの優しい歌声は生きていることを肯定してくれているかのようだ。きっと彼のことをずっと追いかけてきた人たちは、こうして彼が歌っている、ステージに立っている姿を見ているだけでも生きていく力を貰えるのだろうし、そう思えるくらいの力をSKY-HIは持っている。
自粛期間中にその状況を楽しむために生み出した「#Homesession」の前向きな歌詞をハンドマイクで歌うと、
「また会う日までStay Home」
のフレーズがこの今の状況を少しだけ前向きに捉えさせてくれるし、それはそう思えるための活動をSKY-HIがしてきたからだ。
「ありがとうございます。この距離(客席にいる)でスタッフにありがとうございますって言うのってなんかヤバイね(笑)俺にもありがとうございます(笑)」
とスタッフだけでなく、このライブを作り上げている最大の原動力である自分自身にも感謝を告げると、
「帰りたくないな〜。もう1回頭からやりたいな〜(笑)このライブに次はダンサーを入れる感じでツアーを回りたい」
とこのライブへの手応えとさらなる展望を語り、
「このライブまでたどり着いてよかったと思ってくれたらそんなに嬉しいことはない。この状況になって、分断や差別が広がっていくのが怖かった。
自分の周りにいる人を、隣にいる人を、考えが違う人のことも、そして自分のことも愛して欲しい」
と語りかけた。
このライブに辿り着いた人たちはどんな人たちなんだろうか。AAAのファンとしてデビューした時からSKY-HIを見てきた人、ヒップホップが好きで高速ラップを聴いて凄いなと思った人、アニメなどのタイアップで知った人、自分のようにロックフェスに出た時のライブを見て衝撃を受けた人。
きっとどんなタイミングで出会った、どんな考えを持つ人であっても、こうしてこの日のライブが見れて、この日に辿り着けたことに感謝し、それを翌日からの生きる力にしているはず。このライブを見て、高速ラップや歌やダンスや演奏も本当に凄いし、天才だと思った。でもそれ以上に凄いのはこの男の人間力であり、それがあってこそのスキルなのである。そんなことが画面の向こうからでもしっかり伝わってくる。これを生で見ていたら涙が出ていたかもしれない。自分ですらそう思うということは、これまでの活動をずっと追いかけてきた人たちは画面の向こうでも涙を流していたのかもしれない。
「Marble」では背面に映し出された菱形の映像が歌詞に合わせて色が変わっていき、サビではタイトル通りにマーブル模様になるという曲に合わせた演出になり、
「韓国の友達、中国の友達、タイの友達、みんな愛してるぜ」
と言ってから演奏された「I Think, I Sing, I Say」では
「この世界は君が思っているより優しい」
というフレーズが強く刺さる。そうは思えないような世知辛かったり、キツく感じるような出来事が多いけれど、こうしてSKY-HIが歌うことによって少しはそう思えるような。その後に披露された、彼のラッパーとしての技術を改めて示すようなフリースタイルラップがより一層そう思わせてくれる。
「この曲を書いた時、元ぼくのりりっくのぼうよみこと、たなかとたくさん話してた。誰かと話すっていうそれだけのことで救われることもある。
生き返ることもやり直すこともできないけれど、生き方を変えることはできる」
というメッセージをそのまま曲にしたかのような「New Verse」で軽やかなラップと歌を響かせると、さらにクライマックスに相応しいポップさを持った、SKY-HIにとってのアンセムと言えるような「カミツレベルベット」では「Oh Oh Oh」というコーラスを画面の向こうに求め、
「俺のこと考えて気持ち飛ばしてくれたら全部受け止めるからな!」
と叫ぶ。あくまでSKY-HIの曲は「ファンが求めるもの」ではなく、その時に自分が作りたいサウンドや放ちたいメッセージというのが第一にあるが、そんな自分の音楽や存在を認めてくれたファンのことを存在を全肯定しようとする。
それは「リインカーネーション」での
「何回だって俺はお前に会いに行くぜ!
こんな状況でもブラウザ越しに俺のことを見てくれているのが俺の生きる意味。俺に生きる意味を与えてくれるんだから君も大したものだよ!」
と、ファンがSKY-HIの存在や音楽に救われているように、SKY-HIもまたファンの存在に救われている。そうした自身が思っていることや伝えたいことを、SKY-HIは一点の淀みや曇りもなく自分の口から自分の言葉で伝えることができる。
これまでもそのラッパー、ミュージシャン、メッセンジャーとしてのスキルやキレ味の鋭さを自分は評価してきたつもりだったが、こうして完全にワンマンライブの尺で初めて見たSKY-HIのライブは画面越しとは思えないくらいに感動的であり、自分のそれまでの評価なんかじゃまるっきり収まりきらないものだった。
いつかこの状況が終わって、今まで通りにライブに行けるような日が来たら、なんの恥じらいも躊躇いもなくSKY-HIのワンマンに行こうと思った。毎回ライブに行っているわけではない存在のアーティストの配信ライブでここまで思える人が他にいるのだろうか。
少し小芝居の入った様子で
「アンコール来ないかな〜」
とアンコールを待ちわびるSKY-HI。このライブは視聴者がリアルタイムでチャットでコメントができるのだが、楽屋でそのコメントをチェックしていると数えきれないくらいのアンコールが寄せられているということで、すぐさま走って再びステージに向かっていく。
ここまで29曲、もう2時間くらいライブをしている。しかもほとんど間をおいたりすることはなく、常に歌っているか演奏しているか言葉を放っているか。その体力は自粛期間を経ても衰えるということは全くない。いったい日々をどれだけストイックに生きているのだろうか。
自分がこれまでに見てきたバンドの配信ライブはだいたい1時間から1時間半くらいの、普段のライブに比べたら少し短いものであった。それはバンドとしてリハーサルをする時間がなかったり、密になる時間を短くするという理由があったりすると思うのだが、バンドという形態を伴っていながらもSKY-HIは全くそんなことはない。それをできる体力と能力を所有している。
「オンラインライブは生のライブの代替品には絶対にならない。でも劣化版であってもいけない」
という言葉をSKY-HIがコメントしていたのは、自分には間違いなくそう思わせることができるという自信があったからなのだ。
ステージに戻ると曲中にもコール&レスポンスを挟む暖かなラブソング「Blanket」、SKY-HIがポケットに手を突っ込みながらラップをする姿に思わず「カッコいいな…」と同性ながら思ってしまう「Don’t Worry Baby Be Happy」、画面の向こう側にいるファンにも手を挙げてのコーラスを求め、SKY-HIはステージから降りて機材前に出てきて歌い、ラップする。
非常にロックテイストが強くなっていくが、そもそもSKY-HIは先輩であるUNISON SQUARE GARDENの斎藤宏介と曲を作り、Czecho No Republicとも曲をコライトしているくらいにロックバンドへの理解も憧憬も強い男なだけに、こうしたロックサウンドもロックシンガー、ラッパーとして歌いこなすことができる。
というか本編で29曲もやっているのに、すでにアンコールでも3曲も演奏し、しかもまだ終わる気配がない。もはやオンラインライブというか、周年での記念碑的なワンマンなどのライブの時くらいに集大成感とボリュームのある内容になっている。
それを自らの身をもって証明するかのように、「Double Down」では歌い、ラップし、軽やかなステップで踊り、再びパーカッションを叩きながら歌うと、その叩いていたスティックをバットのように持ってスイングする。そのスイングフォームすらも実に華麗で、草野球の試合に代打で出てきてもすぐにヒットを打てるような気がするくらいに。
そしと
「こんなイケてるチームなんざ他にない」
というフレーズがこのライブを作ってきたメンバーやスタッフ、さらには観客までも含めてSKY-HIチームのことを誇るように歌われる「Snatchaway」ではメロやラップ部分では暗くなっていた会場がサビで一気に明るくなる。
そして歌い終わるとすぐさま暗転して配信は終了し、一瞬で待機画面に戻るという、ダラダラとしないことによって一気に余韻に包まれるという潔すぎる終わり方。無駄な時間が1秒たりともなかった2時間半。
「圧倒的ってのはこういうモン」
というフレーズそのものなオンラインライブだった。
今、世界では圧倒的にヒップホップやR&Bが新しいポップミュージックの形になっているし、そうした音楽にロックバンドはもう勝てないとも言われている。メンバーが揃わないと活動できないバンドは非効率であり、ヒップホップやR&Bは1人でもパソコンがあれば作れるというような意味でも、言葉の自由度という意味でも。
日本で暮らしているとなかなかそうは思えないくらいにロックバンドはまだまだ元気だし、自分はロックバンドが他の音楽形態に負けているなんて1%たりとも思っていない。
でももし日本で暮らし続けていて、ロックバンドじゃ勝てないな、と思うような存在がいるとすれば、それはきっとSKY-HIという男をおいて他にいないんじゃないだろうか。それくらいにやられた。撃ち抜かれてしまった。スキルや楽曲などの音楽だけでなく、SKY-HIという1人の人間そのものの魅力に。今まで見てきた配信ライブの中でこれがベストかもしれない。
1.Sky’s The Limit
2.Doppelganger
3.Persona
4.Run Ya
5.何様
6.F-3
7.Limo
8.TOKYO SPOTLIGHT
9.Tumbler
10.Chit-Chit-Chat
11.愛ブルーム
12.スマイルドロップ
13.ナナイロホリデー
14.Name Tag
15.Walking on Water
16.SS
17.As a Sugar
18.フリージア
19.Young, Gifted and Yellow
20.LUCE
21.そこにいた
22.Over the Moon
23.アイリスライト
24.#Homesession
25.Marble
26.I Think, I Sing, I Say
27.New Verse
28.カミツレベルベット
29.リインカーネーション
encore
30.Blanket
31.Don’t Worry Baby Be Happy
32.Seaside Bound
33.Double Down
34.Snatchaway
文 ソノダマン