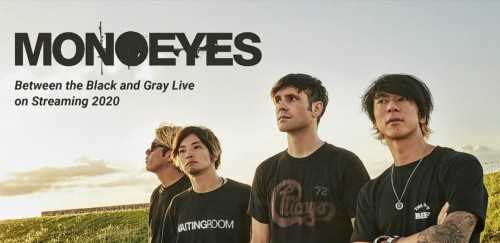それこそELLEGARDENもいろんなフェスへの出演がアナウンスされていたし、ART-SCHOOLも同じように春フェスから再始動することが発表されていたが、今年はMONOEYESの年である。
先月リリースした「Between the Black and Grey」は実に3年ぶりとなるアルバムであるが、そこまで空いた感じがしないのは昨年にも先行EP「Interstate 46 E.P.」をリリースしているからでもあるし、ロッキンオンのフェスなども含めてライブを見ることができる機会がそれなりにあるからであるが、それでもやはりアルバムが出てツアーをするというのは複数のバンドで同時にやることはできない。それゆえに今年はMONOEYESの年なのである。
(だから昨年はthe HIATUSの年だった)
しかしそんな中でのコロナ禍である。ツアーは開催するとはいえ、ただでさえチケットが取れないMONOEYESであるだけに、収容人数を減らしてはチケットが取れない人もいるし、まだまだライブに行ける状況ではない人もたくさんいる。そんな今だからこその配信ライブ。ビバラオンラインもアコースティックでの出演でアーカイブなし、観客がいるかどうかが何よりも重要なこのバンドの配信でのワンマンはどんなものになるのだろうか。
20時を少し過ぎた後に待機画面が切り替わると、映し出されたのはこれまでに発表してきた楽曲のMVのシーン。それが次々と映し出されて、バンドロゴが最後に映し出されると、画面には黒いシャツをノイジーなギターを弾く戸高賢史の姿が。「Between the Black and Grey」のオープニングを飾る重厚なサウンドの「Bygone」だ。メンバーは明らかにライブハウスの客席で円を描くようにそれぞれが中心を向いている。細美武士は1曲目だからか声の調子が本調子という感じではないが、スコット・マーフィーのコーラスがそこに重なることによって、サウンドに負けない強さをメロディが得ていく。
まさにタイトル通りに駆け出すようなサウンドの「Run Run」では一瀬正和(ドラム)の笑顔がいつにも増して眩しく見える。普段のライブでは一瀬は演奏するメンバーの顔を見ることはできない。でも今日はそれを観ることができる。そのことが何よりも嬉しそうなのだ。時には塾長というあだ名の通りに渋い男としての一面も見せてくれる一瀬であるが、本当にこのメンバーとこうしてバンドをやること、音を鳴らすことが楽しくて仕方がないのがよくわかる。この日最も印象が強く残ったのはその一瀬の笑顔かもしれない。
どこか切なさを感じさせるのはメロディとサウンドの融合っぷりであろう「Thermite」では細美が間奏で
「トディー!」
と言うと戸高が少し照れ臭そうな笑顔を浮かべながらギターソロを弾く。戸高もやはりこうしてメンバーと向き合える形ということで、いつも以上にメンバーの顔や表情、プレイをよく見ながらギターを弾いている。この姿はきっとART-SCHOOLだけでは観ることができなかった。このバンド、このメンバーだからこそ観ることができる戸高の表情だ。
「こんばんは、MONOEYESです!」
と細美が挨拶すると、かつてロッキンのLAKE STAGEのトリとしてアンコールで演奏した時のことが今も忘れられない(15年通っているあのフェスの中でもトップクラスのライブだった)「グラニート」へ。
「そういう世界があるなら行ってみたいと思った」
というフレーズはこんな世界の状況だからこそより強い意味を持って響く。みんなで汗まみれになって飛び跳ねながらこの曲、このフレーズを大声で歌いたい。今までは当たり前だった、でも少し遠くなってしまった世界。また必ず行ってみたいと思える世界。それは絶対叶うはずだ、ってなんの根拠もなくてもこのバンドがこうして音を鳴らしていれば思える。
「こういう形でライブやるのも最初で最後だろう」
と細美がこのバンドとしては変則的と言える形でのライブについて口にすると、メンバー1人ずつがアルバム、このライブについて一言ずつ口にし、最後には再び細美が
「目を細めたらみんなの姿が少し見えるような感じがする」
と言った。それはきっと細美の頭の中に観客の姿が焼きついているからだ。曲を聴いて笑顔でダイブする人、後ろでじっくり聴いている人…細美はいつも客席のことを本当に良く見ている。だからこそ危なそうな時は容赦なく演奏を止めるし、観客の年齢層が高くなっていることも口にする。そんな細美だからこそ、実際にはいない、でも確かにこのライブを観ている人たちの姿が見えるのだろう。
「玉虫色の光」というタイトル通りに「Iridescent Light」ではメンバーを美しい光の粒が照らす。思わず自分もその光を浴びていたいとすら思ってしまうが、メンバーの姿だけではなくメロディも光輝いている。音はロックバンドとしてさらに太く強くなっているが、細美の紡ぐそのメロディの美しさは普遍である。
スコットがコーラスをしないパートですらもマイクを通さずして思いっきり歌っている姿が曲のメッセージと相まって我々にこの世の中でも立ち上がる力を与えてくれる「Get Up」から、本日一発目の
「スコットが決めるぜー!」
と言ってスコットがメインボーカルを務めるのは「Between the Black and Grey」収録のスコット曲「Castle in the Sand」。
「Borders & Walls」もそうだったが、スコットはその時に自身が置かれている状況や周りのことを素直に曲にすることができるソングライターだ。その歌詞から我々はいろんな思いを感じることができる。スコットが生まれた国の今を彼がどう感じているのか、それがもたらしている閉塞感や不安はなんなのか。だからこそその国に住んでいる人のことについて他人事ではいられないと思う。
「なんで月曜日なんだと思うかもしれないけど、ここで今日ライブをすることは1年以上前から決まっていた。本当なら画面の向こうのみんなも見に来てくれるはずだった。でもそれはそれ」
と意味深なことを言う細美。そのまま「Fall Out」のイントロに入ると、メンバーの周りを覆っていた(最初はそのことにすら気付かなかった)紗幕が落ち、メンバーの背後にあるスタンドと客席があらわになる。STUDIO COASTにしては席が多い。いや、全員の後ろに客席がある。360°。メンバーの上には巨大な日の丸。そう、ここは日本武道館であり、メンバーが演奏しているのはそのど真ん中であった。
本当ならばMONOEYESがこの武道館でライブをするのが見れるはずだったのだ。それはこうして画面越しになってしまったけれど、きっとMONOEYESはまたいつかその日を我々に作ってくれる。細美武士は今まで口にしたことを反故にしたことがないから。絶対にないだろうと思っていたELLEGARDENも活動再開した。その日が来ることを信じていればそれが叶うっていうことを教えてくれたのが細美だからだ。この「Fall Out」も含め、「Between the Black and Grey」が生まれるからこその武道館だったとすれば、この姿を客席から見ていたかった。いや、必ず見る。何年後になっても。
そんな武道館でMONOEYESが演奏しているのを観ることができているという喜びが画面の向こう側でも曲に合わせて飛び跳ねたくなる「My Instant Song」、「Between the Black and Grey」の中で最もサウンドがヘヴィではあるけれど、
「Alright,alright」
という細美によるリフレインの単語が微かでも確実に我々の足を前に運んでくれるような「Nothing」、2メロではスコットがソロで歌い、細美とのツインボーカルのような形になり、メンバーの周りをぐるっと動きながら撮影するクレーンカメラから見たバンドそのものが光り輝く星であるかのような「Satellite」と、「Between the Black and Grey」のツアーのようであり、バンドの集大成のような感覚も感じる内容であるのはこの場所が武道館であることも無関係ではないであろう。
すると「Two Little Fishes」ではやはりというか何というか、ノートPCを持ってヘッドホン装着というスタッフに扮したTOSHI-LOWがステージに乱入。最初はスコットのマイクでコーラスをすると、各メンバーの隣に行ってはスタッフのフリをして画面を見せて指示をしたりというちょっかいを出すも、最後にはやはり細美の隣で踊りながらコーラスをする。
そんなTOSHI-LOWは
「家で配信を見てて、目の前でやってるみたいだなぁと思ったら目の前でやってた。画面に吸い込まれた」
と笑わせながらも、
「自ら命を落とす人もいる中で、MONOEYESが日本武道館でやるってことをわかっていれば、それだけで生きていけるっていう人だってたくさんいるから」
と、核心をサラッと口にする。そう言えるのは自身もまた武道館のステージに立ち、細美が武道館のステージに立ったのを見たことがあるからだ。その思いに応えるように細美も
「来年取れるかわからないけど、出来る限り最速で」
とこの場所での再会を約束してくれる。TOSHI-LOW自身もMONOEYESが満員の武道館でライブをするのを観たいのだろうし、TOSHI-LOWもまたMONOEYESのファンとして、ファンの気持ちをよくわかっている。
そんな武道館でやることを最も望んだのは戸高だという。戸高の夢は叶えてやりたいと。思えば細美はthe HIATUSで、一瀬はASPARAGUSでthe band apartとの2マンで武道館に立っている。でも戸高は自分のバンドで武道館に立っていない。きっとそれこそBRAHMANのような先輩やアジカンやストレイテナーなどの同年代、後輩までいろんなバンドが武道館のステージに立つのを戸高は何回も見てきたはず。自分があそこに立ったらどんなライブをやりたいか。今やアリーナに至るまでのステップの一つとも捉えられている武道館であるけれど、確かにそこに立つことを夢にしている人はたくさんいる。そういうバンドがいる限り、武道館はビートルズがライブをやってから今に至るまでずっと、ロックバンドの聖地であり続けていく。
TOSHI-LOWがステージから去ると、おなじみのスコットがベースを銃のように構えて戸高にぶっ放すというアクションがある「明日公園で」もこうしたメンバーの配置ゆえに2人は近くことはないけれど、正対したままでそれを行うことができる。細美の声も不思議なことに後半になるにつれてよく出ている。というか最近はそういうライブをよく目にするだけに、細美は尻上がりなタイプのボーカリストと言ってもいいのかもしれない。
この日2発目のスコットが決めるのは思いっきりパンクな「Roxette」。ラスサビでは細美が画面に向かって煽るように頭の上で手を叩き、武道館の2階席の上段の方まで見上げる。細美には確かにこの客席を埋める人の姿が見えている。それは細美がその光景をステージから見たことがあるからだ。観客として観に来ていた矢野顕子をして
「ダイブしてみたくなっちゃった!」
というくらいの興奮と感動に包まれた、the HIATUSの武道館ワンマン。それを体験してしまっているだけに、このMONOEYESを武道館の客席から見たらどんな感情に包まれるんだろうか。でもきっと間違いないのは、そこには汗と涙と笑顔があるということ。それを想像するだけで、TOSHI-LOWの言っていた通りに生きていく力になるかのようだ。
昨年のツアーで聴いた時もこの4人のロードムービーのテーマソングであるかのようだった「Interstate 46」はこの武道館で鳴らされることによって、バンドが辿り着いた場所であるというような過去最高の壮大さを持って響き、「Between the Black and Grey」収録のストレートな日本語歌詞の「リザードマン」と曲を経るごとにステージを、客席までをも照らす照明が観客がいないライブとは思えないくらいのクオリティを発揮している。きっとこれは実際のライブと全く変わらない照明であるはず。MONOEYESのライブでは他に演出めいたものが一切ない。ただロックバンドが演奏する様をより輝かせるための照明があるのみ。だからこそそこに妥協することが許されないのはライブに関わる人全てがわかっているはず。
そんな関わる人たち、ライブを観ている人たちの思いが全て音に集約されているかのような「Outer Rim」。MONOEYESのスタイルは変わらない。ギター、ベース、ドラムというオーソドックス極まりない形のロックバンド。ヒップホップとかR&Bなどの他のジャンルのエッセンスを取り入れたりすることもない。それだけにバンドが続くにつれて、普通ならマンネリになったり、前と似たような曲が多くなってもおかしくない。
でもMONOEYESにはそう思えることが一切ない。毎回毎回フレッシュなままだ。それはやっぱりこのメンバーでバンドをやっているのが何よりも楽しくて、その気持ちがそのまま音になっている。ライブだとそれが表情や姿からも伝わってくる。だから観ている、聴いている我々はそういう思いを抱くのだろう。
最後にメンバーそれぞれが一言ずつ挨拶し、そこにはもちろんこの場所での再会の約束も。そして最後に演奏されたのは「Between the Black and Grey」の最後に収録されている日本語歌詞曲「彼は誰の夢」。
「僕らが過ごした
当たり前の日々も
遠くなるけど
きっと
蜃気楼みたいに
朝焼けに染まって
笑ってるのさ」
というサビの歌詞は今この世の中の状況を歌っているようにしか思えない。きっとこの曲は実際にライブで聴いたらまたその意味は変わる。こうして画面越しにMONOEYESの武道館を見た日のことだって懐かしく思えるようになるはず。そんな日が来ることはきっとこのライブを見ていた人たちみんなの夢だ。
演奏が終わり、楽器を下ろす細美、戸高、スコット。しかし一瀬はまだまだここで演奏していたいとばかりに、終演SEとして流れた「When I Was A King」に合わせてドラムを叩いている。それを見てまた笑い、そしてビールを飲む細美。
そんな姿から画面はこの武道館の設営風景、リハを行なっていた姿がスタッフロールとともに流れる。それはきっとこのまま観客がいたライブで使われるはずだったもの。観客がいないということ。それはバンドにとっては1番大事なことあるけれど、それ以外は紛れもなくMONOEYES初の日本武道館ワンマンと呼んでいいくらいの、素晴らしいライブだった。
正直、配信ライブというものもそろそろ見なくてもいいかもしれないと思っていた。もちろん配信ライブじゃないと見れないという人がたくさんいることはわかっているが、徐々にではあるけれどライブ会場でライブが見れる機会が増えてきているから。それが増えてくると、やっぱり配信というものは物足りなく感じてきてしまう。
でもこのMONOEYESのライブがそんなことを全く思えないものだったのは、バンドの曲、音楽の力はもちろん、やっぱり人間力あってこそだと思うのだ。画面の向こうからでも確かに伝わってくる優しさと強さ。それが見ているこちら側の心を最も動かしてくれる。なんでこんなにも多くの人がMONOEYESが武道館でライブをやったことを喜んでいるのか。その答えは全てこの日のライブの中にあった。
音楽を好きになればなるほど、楽しいことや嬉しいことだけではない、悲しいことや辛いことも増える。好きな音楽が増えれば、それだけ大切な人やもの、居なくなって欲しくない人が増えていくから。
でもそんな悲しさからまた一歩踏み出す力を与えてくれるのもやっぱり音楽なのだ。これまでの人生の中で何度もそんな思いをしてきたことを改めて実感させてくれた、この日のライブのことはずっと忘れないと思う。
1.Bygone
2.Run Run
3.Thermite
4.グラニート
5.Iridescent Light
6.Get Up
7.Castles in the Sand
8.Fall Out
9.My Instant Song
10.Nothing
11.Satellite
12.Two Little Fishes w/ TOSHI-LOW
13.明日公園で
14.Roxette
15.Interstate 46
16.リザードマン
17.Outer Rim
18.彼は誰の夢
SE.When I Was A King
文 ソノダマン