「日本一ハイテンションなロックバンド」と称されるHEREがこのご時世でも主催フェスを開催。近年はメンバーのアイドルなどへの楽曲提供や他バンドのサポートなどの幅広い活動もあって、
folca
THE イナズマ戦隊
SaToMansion
キツネツキ
ガストバーナー
ukka
アルカラ
流れ星
HERE
というロックバンド、ユニット、アイドルから芸人に至るまで盟友たちが集結。しかし前日にはセックスマシーン!!が関係者がPCR検査で陽性になったために出演を辞退するという事態にもなってしまった。
渋谷のduo MUSIC EXCHANGEとO-Crestという、なぜ1階と最上階なのかという気しかしない2会場での開催であり、事前に会場前でリストバンドを引き換えする際に検温と消毒をするというコロナ禍でのスタイル。
14時過ぎにまずはduoの方に入場すると、客席に椅子が並べられているというのは年末にこの会場でthe telephonesのワンマンを観に来た時と同様であるが、自由席であるためにduoの客席に聳え立つ柱を回避する席を選ぶというのが重要な感じもする。
開演前にはステージにHEREの尾形回帰と流れ星の2人が登場。諸注意を兼ねた前説をするはずが、回帰がしゃべる時に流れ星の方に近づこうとして流れ星に
「ソーシャルディスタンス保って!」
と避けられるのだが、
回帰「今日はコロナは対策で大きい笑い声を出したりできないんですよ」
瀧上「じゃあなんでお笑い芸人呼んだんだよ!地獄じゃないですか!」
ちゅうえい「ずっとズベり続けろってこと!?」
と会場を盛り上げてくれるのだが、打楽器持ち込み自由ということで、ウケた際には打楽器を鳴らしたり拍手してもらうという観客のリアクションを確かめるために繰り出された、ちゅうえいのおなじみの一発ギャグ「ガンダム!」はやはりスベり、そして案の定開演時間を押す。
14:45〜 THE イナズマ戦隊 [duo MUSIC EXCHANGE]
duoのトップバッターはこの出演者の中では完全にトップクラスのベテランである、THE イナズマ戦隊。このバンドのライブを観るのは2018年のチャットモンチーのラストライブとなった「こなそんフェス」以来である。
SEが鳴ってメンバー4人が登場すると、いつものように黒のスーツでダンディに決めた上中丈弥(ボーカル)があまりイメージにないエレキギターを手にして肩にかける。ザ・モッズギタリスト的な出で立ちの山田武郎とのツインギターで始まったのは、今年の1月にリリースされたばかりの最新アルバム「夜明けのうた」収録の「THE GLORY SONG」だ。
本来ならばサビのタイトルフレーズなどはみんなで拳を上げて大合唱、というイナ戦のライブの光景が広がるはずが、こういうご時世であるがゆえにそれをすることができず、またそうした形の有観客ライブをするのも初めて(バンドにとっては1年ぶりの有観客ライブである)なだけに、どこか緊張感が強く伝わってくる。
さらに上中がおなじみのハンドマイクというスタイルになっての昨年先行配信された「WABISABIの唄」、アルバムのタイトル曲であり、
「世界は生きてこそ 生きてこそ そこが足跡となり
逞しく 頼りなく それも道になるんだ」
というフレーズがコロナ以降のこのバンドとバンドを愛する人へのテーマソングであるかのように鳴らされる「夜明けのうた」と、新作からの曲が続く。
本来ならば常にライブハウスを回りまくり、そこで新曲を育てながらアルバムを作り…という過程もなくなってしまったことにより、こうして新作の曲を観客の前で鳴らすということも初めてであるだけに、そこも含めての緊張感も感じさせるが、それとともに24年目のバンドならではの貫禄というよりもどこかフレッシュさも感じるというのは久しぶりの観客の前でのライブ、初めての新作曲の演奏という要素があるからだろう。それでも高い位置でベースを持つ中田俊哉も、こなそんフェスではチャットモンチーのドラムも叩いてくれた久保裕行も演奏中に今までのライブと同じように笑顔を浮かべながらコーラスを歌うというあたりはこと緊張もあるけれども、演奏する喜びをそれ以上に強く感じさせる。
「エンタメ業界、キツい扱いを受けることもあったけれど、俺たちにも愛してくれる人たちがいて。24年間やってきたけど、これからのバンド活動はそういう人への愛を届けに行きたい」
とコロナ禍とそれによる不要不急という扱いを受けたからこその宣言をすると、その想いを今改めて歌うような「愛じゃないか」へ。この日は配信もされているということで、上中はカメラ目線でポーズを決めながら歌ったりとサービス満点。カメラに向かって歌うということに決して慣れているわけではないだろうに、この辺りの瞬発力はさすがである。
ここまでの新作からの曲たちとは異なり、この曲は10年前にリリースされた曲であるが、そんな曲が今になってよりリアリティを持って響くというのは、イナ戦が歌っていることがずっと変わっておらず、それでもどんな時代や状況であっても変わることのない普遍性を持っているということである。
その「歌っていることが変わっていない」ということを示すメッセージを持った新作収録曲が「大切な人 幸せであれ」。もうタイトルがそのまま全てを言い表しているという感じであるが、その大切な人というのはもちろんこうしてバンドのライブを観に来てくれている人たちのことでもあり、それは
「大切な人 幸せであれ
どうか命を無駄にしないで
心残りは 無い方がいい
歳を重ねて 笑顔を見せて
歳を重ねた 貴方を見せて」
という、ともに歳を重ねてきたファンがたくさんいて、そういう人の顔を見てきたベテランバンドだからこそ説得力を強く感じることができる。
「世の中が変わって、バンドも変わらないといけなくなるかもしれないけど、大切な人に会いに行くっていうことだけは変わらずに続けていく」
と、このバンドも制限があってもこれからきっと全国のライブハウスを回っていくようになるであろうことを期待させるような上中の言葉の後に演奏されたのはやはり「応援歌」。
上中が言っていたように、エンタメ業界はすべからく不要なものとみなされ、ライブハウスは悪者というような空気すらできてしまった時期もあった。でもその標的にされた小さいライブハウスで鳴らされている
「オイ!!オマエ!!がんばれや!!
俺がそばで見ててやるから!!」
と歌うこのバンドの「応援歌」は世界中で生きているあらゆる人のために鳴らされている。久しぶりにこの曲を鳴らすメンバーもどこか感極まっていたようにも見えたし、そんな今だからこそ、今まで以上に感動的ですらあった。
「応援歌」がリリースされたのは青春パンク全盛期の、自分が高校生の頃だった。もちろんメッセージ的にTHE イナズマ戦隊もそこに片足浸かっているような感もあったし、その頃から今に至るまでバンドにとっての代表曲であり続けている曲であるけれど、リアルタイムでリリースされた時よりも今の方が圧倒的に響く。
それは誰かに応援されたくなるようなこの世の中の状況だからというのも間違いなくあるけれど、自分自身が高校生から年齢を重ね、その過程で苦しかったりキツかったりした状況や出来事が高校生の頃よりもはるかに多くなったからだ。
そしてその曲を今も形が変わらず、止まることもなくバンドが演奏していて、バンド自身もライブを重ねることによって説得力を増してきた。だからより一層響くようになっているのだろう。
演奏を終えたメンバーが深々と頭を下げてステージから去るまで、観客はずっと拍手でそのパフォーマンスに応えていたが、2階席ではアルカラの稲村太佑もずっと拍手をしていた。彼もまたいろんなことがあったバンド人生の中でこの曲に背中を押されてきたのだろう。普通に考えたら大きく浮上することはないと思われる24年目のバンドは今こそ音楽シーンや世の中に必要とされるバンドになっているように感じる。
1.THE GLORY SONG
2.WABISABIの唄
3.夜明けのうた
4.愛じゃないか
5.大切な人 幸せであれ
6.応援歌
15:40〜 ベッド・イン with パートタイムラバーズ [duo MUSIC EXCHANGE]
サウンドチェックの段階から、セクシーな衣装に身を包んだ、益子寺かおり(ボーカル)と中尊寺まい(ボーカル&ギター)の2人が喘ぎ声でマイクチェックをするという「地下セクシーアイドル」っぷりを発揮していた、ベッド・イン。バックバンドとしてパートタイムラバーズ(ドラムは前にHEREのサポートをやっていたレルレ)を引き連れてのライブ。
SEが鳴るとサウンドチェック時からそのままステージに待機していたパートタイムラバーズの演奏が響いてミラーボールが回り、益子寺と中尊寺の2人が登場。もはや今の若者が絶対にわからないであろう昭和の流行語を口にしたり、2人が纏う空気からはコロナ前に戻ったというよりももはやバブル期の日本にまでタイムスリップしたかのよう。
という完全に見た目のイメージとしてはイロモノユニットなのだが、川谷絵音の学生時代の先輩である中尊寺のギターはそのイメージだけで判断すると驚愕するくらいに上手い。前にフェスで見た時は2人だけで演奏していたが、今回はバンド編成であることによって、その中尊寺のギターがより一層強さを増して聴こえてくる。ディスコなどのバブル期の要素を取り入れながらも、ハードロックやメタルなどの要素を感じるというのはHEREにも共通する部分であろう。
2人はピンマイクをつけているので、歌いながら演奏しながらステージ上を自由に歩き回ることができるのだが、ファンも声は出せなくても2人の煽り(「オイ!オイ!」という完全にロックバンドのもの)に拳で応えたり、ジュリ扇を振ったりしており、ステージも客席も声が出せない以外は見た目の華やかさも含めて全く変わっていないようにすら思える。
「やまだかつてない」
「ポケベルで呼ばれて〜」
「センクス、モニカ〜」
という、流れ星の瀧上が
「平野ノラが2人いる感じ」
と評する、平成生まれには絶対意味不明であろう単語が飛び交うMCでは、HEREの三橋と武田が紅白の幕を持って登場し、その幕で隠すように生着替えも敢行してボディコン姿になるという、下ネタ連発も含めてパフォーマンス的には一切自粛しないというこの2人の生き様が現れているようにすら感じる。
そうして衣装替えした2人が自身の存在証明を叫ぶ「We Are “BED・IN”」から、ラストは同期のダンサブルなサウンドも取り入れながら、中尊寺がハードロックなギターを弾きまくる「C調び〜なす!」へ。
ちなみにバックバンドのパートタイムラバーズはパートタイマーの時給で雇うのがもったいないくらいの凄腕バンドなので正社員に昇格させたいくらいであるが、そんなバンドの中にもギタリストがいるのにも関わらず、リードギターはあくまでも中尊寺。それくらいにとんでもなくギターが上手いのだ。
演奏が終わると中尊寺がギターのネックを舌を出して舐めるようにしたり、益子寺はマイクを両手で擦ったりという、配信で見ていた、このユニットのことを全く知らない人はどう思うんだろうかという、ベッド・インだからこそできるパフォーマンスを連発してステージを去って行った。
そのビジュアルやパフォーマンスも一回見たら絶対に忘れられないが、曲もまたそうしたインパクトが非常に強い。これだけ曲以外の部分の主張が強いと曲や音楽の印象が薄まってしまっても仕方がないが、全くそうはならないのは2人のミュージシャンとしての力量あってこそだろう。
フェスに出たらその日のインパクトを全部掻っ攫っていくだけに、ある意味ではBRAHMANや四星球くらいのジョーカー的な強さを持っているユニットなのかもしれないと思っているが、果たしてそこまで考えて見ている人がいるんだろうかとも思う。
1.男はアイツだけじゃない
2.♀×♂×ポーカーゲーム
3.GOLDの快感
4.We Are ” BED・IN”
5.C調び〜なす!
16:35〜 キツネツキ [duo MUSIC EXCHANGE]
HEREにとってかけがえのない仲間と言えるバンドが9mm Parabellum Bulletである。武田将幸はもはや9mmの救世主と言っていいくらいに欠かせないサポートギタリストであるし、同じくギタリストの三橋隼人もサポートで参加したことがある。
そんな9mmはこのフェスには菅原卓郎と滝善充によるユニット、キツネツキで出演。さすがに会場規模的に9mmで出るのは、というところかもしれないが、そうしたところにも出ていけるフットワークの軽さは「卓郎と滝にその日ならではの取り憑かれメンバーを加える」という活動形態あってこそである。
サウンドチェックの段階から下手にギター&ボーカルの卓郎、上手にドラムの滝(キツネツキでは滝はドラムである)、中央には2人の取り憑かれメンバーがいたが、本番でも最初からベースの下上貴弘(アルカラ)、9mmのサポートでもおなじみの為川裕也(folca)というこのフェスの出演者が取り憑かれメンバーとして参加。普段は徐々にメンバーが増えて行ったり、入れ替わったりしていくという形であるだけに、最初からフルの4人編成というのは実に珍しい形だ。卓郎の真っ赤なTシャツ姿も。
なので音源などでは隙間が多いサウンドの「ケダモノダモノ」ものっけから「この4人によるオルタナバンド」としてのサウンドで鳴らされるために、音の厚みが凄まじい。滝のドラムが驚異的に上手いのはもちろんであるが、下上と為川もコーラスを務めるというくらいの取り憑かれっぷりである。
それはタイトル通りに踊れるリズムの「odoro odoro」についてもそうであるが、やはり以前までのライブのように自由に、隣の人にぶつかるくらいに体を動かしたりということはできないけれど、揺らすくらいであればこの状況でも楽しむことができる。揺らすというくらいに止めるのが難しいくらいにバンドの演奏する音は激しいけれども。
卓郎はその着ている赤いTシャツが「ハイテンションフェス」というこのフェスのタイトルに合わせてテンションが高そうな服を着てきたことを明かすが、滝と取り憑かれメンバーの2人はいつものように黒いTシャツを着ているだけに、結果的には卓郎のみが浮いてしまうという形に。
しかしながらこの状況下でも「久しぶりのライブ」感が全くないのは9mm本隊として有観客ライブを何回かやってきているという、進み続けることを選んだバンドならではのものであるが、それは
「渋谷らしい曲」
と言って演奏された、あまりにもシュールな歌詞の、コーラス部分では歌うことができないかわりに観客が腕を左右に振る「てんぐです」からも感じることができる。また、為川がいるからか、卓郎はギターをかなり為川に任せ、観客を先導するように自身で腕を振っていたのが印象的だった。取り憑かれメンバーがいないと自分しかギターを弾く人がいないだけに。
そんな中でさらなる取り憑かれメンバーとして招いたのは、この日卓郎がやたらとMCの口調をモノマネしていた(しかも全然似てない)、HEREの尾形回帰。出てきた時にメンバーがHEREの「死ぬくらい大好き愛してるバカみたい」のイントロを演奏して、尾形がタイトルだけを発するのだが、全く予定されていなかったドッキリによって尾形は大混乱。卓郎いわく、
「ロックバンドきってのドッキリに弱いボーカリストが回帰さんとアルカラの稲村さん」
だそうで、今回もまんまとハメられたというわけである。
その尾形が歌うのはキツネツキのレパートリーにある、童謡シリーズ。卓郎は「アンセム」と呼んでいたが、誰しもが耳馴染みのある曲であるだけにこうしたコラボもしやすい、歌いやすい曲である。とはいえ尾形は「証城寺の狸囃子」で思いっきり足元のカンペをガン見しながら歌っていたが。
ゲストなしでのムーディーなインスト曲「MONDAY NIGHT BEER RUN」で爽やかな空気を生み出すと、4人編成ならではの轟音サウンドがもはやシューゲイザーバンドであるかのように、このduoのステージが小さく感じるようなスケールで鳴らされる「まなつのなみだ」から、
「配信ライブとかもやったけど、やっぱり声が出せなくても目の前にみんながいるのといないのとでは全然違う」
と卓郎は口にした。それは9mmで配信もやったが、その後に有観客ライブをやったからこそ感じた素直な心境だろうし、ある意味では即興性が9mmよりも強いこのキツネツキはより一層そう感じるだろう。どんなメンバーとどんな曲をやって、それがどんなサウンドになるかというのは当日にやってみないとわからないし、そのリアクションは目の前にいる観客の表情や仕草から伝わってくるものなのだから。そういう意味でももはやキツネツキは「滝のリハビリも兼ねたユニット」という始動当初の目的とはまた違った意味合いを持ち始めているのかもしれない。
そしてラストは滝がキメを打ちまくる「QB」であるが、ステージ衣装を着たHEREの三橋と武田が乱入すると、卓郎と為川は自分のギターを2人に渡す。最初は卓郎はハンドマイクで
「イェー!」
と叫びまくり、為川はもう1本のギターで演奏していたのだが、最終的には完全にギターをHEREに任せて2人でステージに置いてある返しをひっくり返して、その上にギタースタンドを乗っけてオブジェを創り出すというあまりにもカオスな状態に。しかもそのまま終わるという、ハイテンションが極まりすぎたが故のライブとなったのだった。
確実にこの日最も「HEREの主催フェスだからこそいつもとは全く違うライブになった」というアクトとなったわけだが、それはHEREとの関係性があるが故にそうなったことでもありながら、キツネツキの新たな可能性をさらに感じさせるものになっていた。「ふたりはサイコ」どころか、この日関わったメンバーは全員がサイコであり最高だった、というくらいに笑った。ステージ上も本当にみんなが笑っていた。
リハ.ふたりはサイコ
1.ケダモノダモノ
2.odoro odoro
3.てんぐです
4.小ぎつね w/ 尾形回帰
5.証城寺の狸囃子 w/ 尾形回帰
6.MONDAY NIGHT BEER RUN
7.まなつのなみだ
8.QB w/ 三橋隼人,武田将幸
18:10〜 アルカラ [O-Crest]
duoの1階から階段で5階まで登るというO-Crestを使うからこその移動を強いられて辿り着くと、すでにライブが始まっていたガストバーナーは入場規制中。それによってライブが終わるまで階段で待機し、ライブが終わって移動する人が出て行ってから入れ替わりで中に入ることに。
duoよりもさらにキャパが小さいO-Crestにも椅子が並べられていることに驚くが、このキャパとはいえライブが始まる前からすでに満席になっているというのはさすがアルカラ。バンドにとっては慣れ親しんだ会場のトリとなる。
サウンドチェックから稲村太佑(ボーカル&ギター)がタンバリンを首にかけるいつものスタイルで演奏をすると、
「スタッフからは「時間押しまくってるから早く終わらせてくれ」って言われるし、尾形さんからは「好きなだけやってくれ」って言われるし、2方向からの指示が来てる(笑)」
と笑わせ、「アブノーマルが足りない」からスタート。
「あけましておめでとうー!」
という挨拶をしたあたりに、全国の大小様々なあらゆるライブハウスでライブをやってきたアルカラですらもこの状況になったことによってライブができていないということを思い知る。
「ハイテンションー!」
と稲村が叫んだのはフェスのタイトルであるからでもあるが、それは「夢見る少女でいたい」のフレーズでもあるから。元々仲が良いバンド同士であるということはわかっていたが、HEREとはメッセージやバンドの姿勢に通じるところがある両者であるということである。
まさにバンドも観客もハイテンションにならざるを得ない「チクショー」では
「ハイテンションドラム、疋田武史!」
と言うと疋田による激しい連打のドラムソロも挟まれるというハイテンションフェスバージョン。あまりライブをやれていないとは思えないくらいにバンドの演奏も躍動感に溢れているし、稲村の歌唱力も衰えるどころかむしろレベルアップしているんじゃないかとすら思うくらいにファルセットも含めて実に伸びやかだ。この辺りはさすがロック界の奇行士である。
「HEREの武田君が「あの曲どうなったんですか?」って言ってきたから、作ったばかりの希望の曲をやるんやけど、HEREは今ライブの準備してる時間で聴けないから、みんなが武田君にどんな曲だったか教えてあげてください!」
という新曲ももれなくハイテンションな曲であるが、稲村いわく
「みんなが手を叩くところが11拍子と13拍子やったって武田君に伝えてあげてください!」
というめちゃくちゃわかりづらいもの。それを武田に伝えるためには早くこの曲をリリースしてもらうしかないだろう。
「トリを任されたというよりも、後は適当にやっといてくれって感じ」
とトリを任された理由を話していたが。
「誘惑メヌエット」では先程の疋田に続いて、今度は
「ハイテンション下上のベースソロ!」
と、ハイテンションであっても一切表情が変わらないクールな下上のベースソロから、稲村のバイオリンソロまで入るのだが、稲村のバイオリンは最初は音が出ずに本人もビックリし、疋田は爆笑しながらドラムを叩いている。そんなアクシデントが起きて「楽しい」とメンバーも我々も思えるのは、今この場所で音を鳴らしているからだ。そうしてロックバンドとしてのカッコよさと人間としての面白さを感じさせてくれたアルカラに対して、曲間には稲村が喋り出すまでの長い時間、ずっと鳴り止まない拍手が客席から送られていた。それは稲村も間違いなく嬉しかったはずだ。自分たちが鳴らした音やパフォーマンスがしっかり伝わっていたということなのだから。
そんな稲村は
「HEREに敬礼!95段あるこの階段を登り降りしたみんなの足に敬礼!子供の頃に一緒に山に登った僕の父親にも敬礼!」
と最終的にはよくわからない感謝を語りながら、
「みんなわかってると思うけど、アルカラには楽しい、カッコいいっていう部分だけじゃなくて切ない部分もある」
と自己批評してから最後に演奏されたのはまさかの稲村がハンドマイクで歌う「ボーイスカウト8つのおきて」。稲村が少し歌詞が飛んだりしていたのはもはやご愛嬌という感じであるが、声は出せないし、ステージ前に押し寄せることもできないが、その場で飛び跳ねまくる観客の姿はこの短い時間のライブがかけがえのない楽しいものであったことを示していた。
MCでは散々HEREや尾形回帰のことをいじっていた稲村は
「みんなでHEREを観に行こうー!」
と言って自分たちのライブを締めた。アルカラは自分たちの主催フェス的なものをやってもいるけれど、O-Crestの店長主催として始まったMURO FESも含めて、基本的にはそういうバンドだ。親しい人、大事な仲間が作ってくれた場所でその人たちの想いを汲んだライブをやってみせる。それはあらゆるライブハウスに出て(千葉なら稲毛とかなかなか人気バンドが来ないような場所とか)、あらゆるバンドのライブを見てきた(実は稲村はこのO-Crestで米津玄師の初ライブを目撃した1人でもある)からこそ背負えるものでもある。そしてこの日を皮切りに今年はアルカラも自発的にライブをやっていく。ライブハウスで始まったバンドが、ライブハウスに返していく年になるのだ。そうした活動をこんなに頼もしいと思えるバンドはなかなかいない。
リハ.さすらい
1.アブノーマルが足りない
2.夢見る少女でいたい
3.チクショー
4.新曲
5.誘惑メヌエット
6.ボーイスカウト8つのおきて
18:45〜 HERE [duo MUSIC EXCHANGE]
いよいよこの日の大トリ、主催者のHEREである。前に出演していた流れ星が転換中も観客を笑わせつつ、サウンドチェックがやや押した中でのメンバー登場。すでに尾形、三橋、武田は何ステージ目なんだろうかという稼働っぷりであるが。
おなじみのスキンヘッドのベーシスト・壱とサポートドラムを含めた5人編成で、当然ながらメンバーは疲れの色も見せることなく、バッチリ決めた衣装で登場。
さすが自他共に認める「日本一ハイテンションなロックバンド」として、昨年12月にリリースされた新作アルバム「風に吹かれてる場合じゃない」の「ハイテンションなコミュニケーション」で声が出せないながらもステージと客席の、文字通りハイテンションなコミュニケーションを図っていき、さらに「最高ですから最強なんです」「BOON BOON BOONでPON PON PON」と、新作収録曲を連発。これはアルバムを出したものの、ツアーをはじめとしてなかなか新作の曲をライブでやる機会が作れないからこそ、この日をリリースライブとして捉えているところもあるのだろう。
アルバムの内容もいわゆる1人に向けたラブソングというような曲はなく、ただひたすらによりハイテンションに突き抜けたものになっている。観客もさすがHEREのフェスに来ている人たち、すでに新作の曲が完全に頭に入っており、声は出せなくてもコーラス部分で腕が上がったり、持ち込みOKの打楽器の音が鳴ったりする。
もはやタイトル以上でも以下でもない、一切の深読みの必要がないことだけを歌っているが、今ロックバンドとして伝えたいことがそれだけであり、それによってハイテンションになりたいということなのだろう。その歌詞のシンプルさや尾形のコミカルさを感じるキャラクターからは信じられないくらいにメンバーの演奏は凄まじく上手いというギャップもあるが。
その新作を畳み掛けた序盤に手応えを感じながらも、ここからはHEREの代表曲ゾーンに突入ということで、すでに曲間から観客がフリをしているくらいに定着している「ギラギラBODY&SOUL」ではそのフリをするためにベッド・インの2人がジュリ扇を持ってステージに登場して踊り、さらには流れ星のちゅうえいも乱入するというフェスならではのオールスター的なコラボに展開するのだが、ちゅうえいは尾形によって途中で追い返されるという芸人ならではの雑な扱い方。
さらには「己 STAND UP」ではガストバーナーのはるきち、folcaの山下英将がコーラスとして登場というさらなるコラボ。この日はHEREのメンバー自身も様々な出演者のステージに参加したりしていたが、こうしてHERE自身のライブにも出演者が参加してくれているというあたりにはHEREのメンバーの人間性がこのフェスの暖かさとハイテンションさを作り出している最大の原動力になっているということがよくわかる。
「まずは経済の話からしようか?大事なことだから。動員を半分以下にして、コロナ対策でスタッフを増やしたので、収支的には紅に染まっております(笑)
なんとかトントンくらいには持っていきたいので、通販で物販を買ったり、ここにいる人たちは帰ったら配信ライブのチケットを買ってもう1回見たり、投げ銭をしてくれたらと思います。
配信で観れるukkaのコメント、可愛いよ〜。卓郎君のコメント、面白いよ〜」
と、この日の出演者の中でもukkaとキツネツキ(9mm)ファンに強く訴えかけていたのは両者のファンが経済力があるということをわかっているからかもしれないが、大手のプロダクションを介さずに自分たちでバンドを運営して活動をしている(だから物販はだいたいメンバー自身がやっている)HEREだからこそリアルにそうした収支状況が把握できているのだろうし、キツいだろうなということはわかるけれども実際にどうなのかということまではわからない我々参加者にとっては、エンタメ業界が置かれている今の状況(やっても赤字、やらなくても無収入)というのが本当に厳しいものであるということを理解せざるを得ない。それだけに、こうしてこの日楽しい思いをさせてもらったからにはなんとか力になりたいし、来年のこのフェスにも繋がって欲しいと思う。
そんなロックバンドとしての今の状況を歌ったのが新作のタイトル曲「風に吹かれてる場合じゃない」。ボブ・ディランの名曲のパロディ的なタイトルはこのバンドが持つコミカルさを感じさせるが、
「覚悟決めて夢見てんだ 笑いたきゃ笑え
命懸けで自由を謳歌してる
こぼれる涙も邪魔さ 舞い散る花も目障り
俺は全速力で駆け抜けたい」
という歌詞はHEREの今の、これからの生き様を示している。このバンドでこれからもこのスタイルで生きていくという。決して泣けるような音楽やライブをするようなバンドではない(ハイテンションなバンドだから)けれど、なんだか感動にも似た感覚を覚えた瞬間だった。
そこからは再び代表曲の連発へ。尾形がタイトルに合わせて相撲を取るようなポーズをしてみせる「はっきよい」は尾形のポーズもそうだが、武田と三橋のギターがひたすら押し出しを狙うようなロックソング。
そもそもHEREのギターの上手さは9mmのサポートを見ている時からわかっていたが、2人のギターのサウンドが変わることによって曲のイメージも変わるという意味ではHEREのサウンドの骨格を担っているのは三橋と武田のギターであると言える。尾形は不器用なロックスターというイメージだけれど、ギター2人は実に器用なプレイヤーだと思うし、そこが9mmをはじめとしたバンドに求められる所以なんだろう。
キツネツキのライブの時にはタイトルコールだけだった「死ぬくらい大好き愛してるバカみたい」はそのギターのサウンドの変化によって、V系バンドのラブソング(タイトル的にも)のような怨念を感じるものへ。間奏では尾形、三橋、武田、壱の4人が中央に固まってポーズを決めるように演奏する姿が衣装の統一感もあって戦隊ヒーローのようなカッコよさを感じさせる。やはりロックバンドのライブはカッコいいし、HEREはロックバンドであるということだ。
「今回このフェスをやるって決めたら「HEREがやるんなら出るよ」って言ってくれたり、「やってくれてありがとう」って言ってくれる人がいて。少しでもミュージシャンやライブハウスが前に進める手助けができたんなら嬉しいし、やっぱりこうしてお客さんと相対して目の前で演奏するのがロックバンドだと思っているんで、現場至上主義でこれからもやっていきたいと思っています」
という言葉からは今回の出演者たちがこのフェスをきっかけにこの状況での1歩目を踏み出せるようになったこと(それこそ1年ぶりに有観客ライブをやったTHE イナズマ戦隊など)の感謝とHEREへの信頼を改めて感じさせる。小さな規模かもしれないけれど、こうして歩き出せたということは本当に大きいことだ。
「何かがあったとしても、誰も責めないように。誰も悪くないから。みなさん、帰ったらすぐにうがいをして、ビタミンを取って、今日は10時間くらい寝てください。生きて必ずまた会いましょう」
という言葉からはこうして会場に来てくれた観客への愛と優しさを感じさせた。本当にHEREはその特異な出で立ちとは裏腹に、「こんなに良い人たち過ぎて大丈夫なんだろうか」というくらいに良い人たちであるのがよくわかる。
今回はこの規模だが、もっと有名なアーティストを集めてもっと大規模なフェスをやることだったできる。例えば9mmなり私立恵比寿中学なりもオファーが来れば受けてくれるはずだ。そう思えることも、この状況下でこのたくさんのアーティストが出演してくれるのもHEREの人望と人格あってこそだ。
この日は演奏されなかったが、最新作の最後には「それではさようなら」という曲が収録されている。その曲は
「風邪だけは引かぬように 手洗いうがい忘れずに
お身体には気をつけて また会いましょう」
「次の休みはどうしようか そうだ
久しぶりにライブハウスでも行こう
大好きなあの歌をでっかい音で聴きたいぜ」
と、尾形の観客への言葉や、今ライブハウスに行くことという、この日のテーマソングになってもおかしくないような歌詞で構成されている。言葉はもちろん、音楽としてもそのメッセージを発しているのだ。それは今尾形が、HEREが聴いてくれる人に最も伝えたいことなのだろう。
ラストに演奏された「LET’S GO CRAZY」は最後までハイテンションでありながらこれからもそのままで突き進んでいくという意思を示していた。
演奏が終わると再び観客の体調を気遣うような言葉から、X JAPAN的なメンバーが手を繋いで観客に礼をするエンディング。その姿はまるで「Tears」なり「Endless Rain」なりが流れていてもおかしくないくらいの大団円っぷりであった。
最新アルバムがそうであるし、このフェスのタイトルもそうであるように、今のHEREはよりハイテンションな方向に振り切れている。そうしてバンドがハイテンションになって、聴いてくれる人もハイテンションになれば、どちらにも「楽しい」という感情が生まれる。
この日はまさにずっとそんな感情だらけの1日だった。それはHEREが目指しているハイテンションというものが一つの到達点を迎えたということである。普段生活していてハイテンションになることなんてそうそうない。だからこそたまにハイテンションになることができるこういう日が、HEREというロックバンドが必要なのだと思う。その方が楽しいと思える日々を送ることができるから。聴いている人に元気や力を与えるための「ハイテンション」。HEREというバンドはそれを見事なまでに体現している。
1.ハイテンションなコミュニケーション
2.最高ですから最強なんです
3.BOON BOON BOONでPON PON PON
4.ギラギラBODY&SOUL w/ ベッド・イン、ちゅうえい
5.己 STAND UP w/ はるきち、山下英将
6.風に吹かれてる場合じゃない
7.はっきよい
8.死ぬくらい大好き愛してるバカみたい
9.LET’S GO CRAZY
特に大規模なものであればあるほど、フェスという存在が我々の生活から遠いものになってしまって1年くらい経つ。もちろん関西ではフェスをやっていたり、関東でも秋にはBAYCAMPが開催されたりしたが、春以降のフェスは未だに厳しいであろう状況が続いている。
でもこの日こうしてこのフェスに参加して、様々なアーティストが次々に出てきてはライブが見れるという体験をすると、改めてフェスというものは本当に楽しいものであると思う。いろんなアーティストとそれぞれのファンが集まって、何か一つの旗(アーティスト主催なり、主催者がいたり)を元に全員でその日1日を作る。
そこには普段ワンマンに行くだけでは出会えないような新しい体験や出会いがあり、それがまた新しい音楽生活や人生への楽しみに繋がっていく。それを「また来年」って思いながら1年を過ごしていく。まだ規模は小さいし、形は今までとは違うけれど、こうしてフェスという1日を作ることができた。その日を作ってくれたHEREに最敬礼して、これからまたいろんなフェスに行ける日を待っていたい。
文 ソノダマン
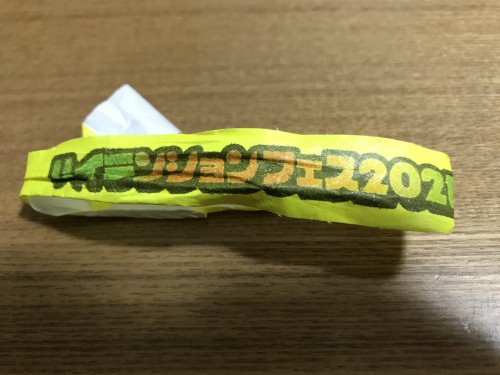

![[ALEXANDROS] Sleepless in Japan Tour さいたまスーパーアリーナ 2019.6.15 [ALEXANDROS] Sleepless in Japan Tour さいたまスーパーアリーナ 2019.6.15](https://moretzmusic.com/wp-content/uploads/2019/12/41-250x250.jpeg)



