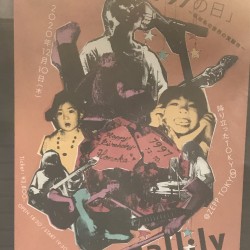昨年12月にアルバム「millions of oblivion」をリリースし、2月からそのリリースツアーを回っている、THE PINBALLS。
そのツアー初日の千葉LOOK、距離を取ることによって50人ほどしか入ることができない、声を発する、一緒に歌うことができない客席を前にして古川貴之(ボーカル&ギター)は、
「これでもやっていけるって思った」
と、この状況でもロックンロールバンドとして転がり続けていくことへの手応えを口にしていた。
そんなツアーも早くもファイナルに。バンド史上最大規模を更新するキャパの渋谷O-EASTがその会場となる。
検温と消毒を経て場内に入ると、客席にテープで立ち位置のマスが描かれたスタンディング形式。かなりマスの面積は広めなのだが、そうして客席を狭めているにもかかわらず、PAブースの後ろの方にまでたくさんの観客が来ている。今の平日の夜にこれだけ入るということは、通常時でももはやこのキャパを埋めることができると言えるだろう。
開演時間の19時になると場内が暗転し、SEが鳴るとステージ背面に「millions of oblivion」のジャケ写のツアードロップが浮かび上がる。そこに順番に登場してくるメンバーたち。石原天(ドラム)、森下拓貴(ベース)、中屋智裕(ギター)がおなじみの黒のスーツでステージに出てくる中、古川は長いコートを着て派手な赤い色の髪という出で立ちもこのツアーは変わりない。
だが古川、中屋、森下の3人が楽器を、石原がスティックを思いっきり振りかぶって1音目を鳴らし、森下が台の上に立って手拍子を煽って重いリズムとリフによるロックンロール「ニードルノット」が始まった瞬間、「変わった」と思った。それはわずか2ヶ月前に同じようにこの曲から始まったワンマンを見ていても、一瞬でそう思った。音の鳴りがもうその初日と全く違うのだ。
流れ自体は変わらないので、そこは初日の千葉LOOKのライブレポも見ていただきたい。
(http://rocknrollisnotdead.jp/blog-entry-835.html?sp)
しかしながら「狭い、見づらいでもそれも含めて愛してる」というイメージを持たれる会場である千葉LOOKの収容人数の10倍ほどという広いステージだからこそ、中屋が台の上に立ってギターを弾く姿も、序盤はサングラスをかけた森下が台の上のみならずアンプの上に乗り、さらには楽器のスタンドに足をかけるという姿すらもハッキリと見えるのだが、ただ見やすいというだけではなく、そうしたパフォーマンスが全てこのキャパで鳴らされるべきロックンロールバンドのものとして映えに映えている。
それはパフォーマンスだけではなく、千葉LOOKのくらいのキャパではなかなか使うことができない派手な照明を使っていたという点もそうだ。
「神々の豚」「アダムの肋骨」でこれでもかというくらいに歪んだギターを鳴らしまくる中屋の姿に合わせるように明滅する照明は「Lightning strikes」においてはまさに雷鳴を思わせるように光る。基本的には演出などは使わないバンドだ。あくまでも4人の鳴らしている音が主役であり、それを1番聴かせたい、見せたいバンドだからだ。それでもこのキャパでそんなバンドがライブをやるということを、ただ動員が増えたからというだけの理由ではないものであることを序盤から示している。
そんなロックンロールライブから踊り出したくなるような「放浪のマチルダ」と続くと、一息ついた瞬間におそらく客席から歓声が漏れてしまう。
古川は
「声出しちゃダメなんだよね?」
と確認しながらも、
「ついつい声が漏れちゃうというか、そういうライブが出来てるんだなっていうことが嬉しい。昔はどんなに欲しがっても歓声をもらえることなんてなかったから」
と、今にも涙が出てきそうなくらいの声のトーンで古川はMCを始めるのだが、当然声を出すのはマナー的によろしくないことは確認しなくてもわかっているはずである。それを遵守したツアーをここまで回って来たのだから。
でも頭ごなしにその声が漏れてしまった人のことを怒ったり注意したりするようなことはしない。ロックンロールバンドというとフロントマンは自分に絶対的な自信を持つオラオラなタイプも多いけれど、古川はそうしたロックンローラーとは対照的と言ってもいいような性格の男だ。だからこそその人がこの日この後会場に居づらくなるようなことを言ったりはしないのだろうし、衝動を抑えきれないくらいのライブが出来ているという手応えも確かに感じているはずだ。
「俺が今まで見た中で1番感動したライブが、観客が俺とあと1,2人しかいなかったんだけど、ボーカルの人が服を脱いでパンツだけになって歌っていて。俺はその姿を見てカッコいいなって何故か思ったんだよね。
きっとその人は俺が見ていなくてもそうしていただろうと思うし、俺もその人がそこにいなくても音だけが残ってるような、そんな感覚だった」
と古川は言葉を続ける。自身もそうして観客が数えられるくらいしかいないライブを何度となく経験してきたからこそ、その男の本気がわかるのだろう。話を聞いている時はクリトリック・リスのライブなのかと思ってしまったが。
メロディと、まるで音の出る私小説を読んでいるかのような歌詞のストーリーをじっくりと聴かせる「ストレリチアと僕の家」からはミドルテンポの曲が続くゾーンへ。サイケデリックな音と照明が太陽の光が入り込まないくらいに深い森の中に迷い込んだかのように錯覚させる「花いづる森」、
「今なら昔の曲だってまた最初から始めるように歌える!」
と言って演奏された初期曲「SLOW TRAIN」は実にレアな選曲であり、目の前で語りかけるように歌われる「(baby I’m sorry) what you want」の
「聞かせてよ 何を考えているのか」
という締めのフレーズを聴いている時に、なんでTHE PINBALLSというバンドはこんなにもカッコいいんだろうか、ということを考えていたんだ、と古川に伝えたいくらいだった。
テンポこそ序盤に比べたらゆったりとしている曲が続いたし、熱狂するようなタイプの曲たちではないのだが、そうした曲であっても今のTHE PINBALLSのグルーヴの強さがハッキリとわかるからだ。
タイプとしてはシンプルなドラマーとベーシストである石原も森下も、決して演奏そのものはド派手というわけではなく、軽く叩いたり弾いているように見えて、その一音にものすごく力がこもっているように聴こえる。そうして演奏できるような音の出し方をこのツアーで会得したのかもしれない。古川は
「このツアーで俺たちは強くなったと思う」
と言っていたが、自分たちの演奏と、かつては喉を痛めてライブを飛ばしてしまったこともあったとは思えないくらいに、遠くに飛ばせる歌い方を体得したんじゃないかと思わせるような古川の歌唱がその言葉の裏付けになっている。ただライブをやってきたんじゃなくて、今この世界の状況の中で自分たちがロックンロールバンドとしてツアーを回る意味というのをしっかりと考えて、理解、共有してライブを重ねてきた。それが音から強く伝わってくるのだ。
昨年リリースしたアコースティックアレンジアルバム「Dress Up」でのジャジーかつアダルトなアレンジも素晴らしかった「欠けた月ワンダーランド」で
「What a wonderful world!」
と古川が叫ぶと、それが再びロックンロールに振り切れ、転がっていく合図となるのだが、「惑星の子供たち」では歌い出しから石原がハープを吹く。その部分は古川の歌とギターの合間にハープの音が鳴るだけに、普通のバンドならばハープもボーカルが吹くべきなのだろう。でも古川が石原に任せたのは、石原が1番上手くハープを吹くことができるから。それは、
「やっぱりこのコロナの状況になって、家で1人で音楽をやる時間っていうのも増えて。それも楽しいなって思ったんだけど、やっぱり俺には石原がいて、モリ(森下)がいて、中屋がいて、この4人で音を鳴らしてるっていうのが1番楽しい」
という古川の言葉の通りだ。そのギターを弾く姿のクールさと熱さを兼ね備えた振る舞いでもって、ライブでのロックンロールバンドのカッコ良さの比重を最も背負っているギタリスト・中屋ですらも、THE PINBALLSのメンバーは1人だけで前面に立って音楽をやっていくようなタイプではない。そんな4人だからこそ、こうして集まった時にこそ発揮できる力があるということをわかっている。サウンドのスピード感とは裏腹に、本当にゆっくり、ゆっくりと認知と支持を獲得してきたバンドであるが、もう15年間という長きに渡って一度たりともメンバーが変わっていないというのは、4人がこのバンドだからこそ輝けるということをわかっているからなのだろう。
「WIZARD」のカップリングという「隠れた」と評されてもおかしくないような位置の曲とは思えないくらいに観客がみんな腕を上げて熱狂していた「統治せよ支配せよ」にしろ、新作収録の、タイトル通りに真っ赤な照明がバンドをさらに燃え上がらせるように機能している「赤い羊よ眠れ」、猟奇的なストーリーゆえにロックンロールのサウンドによく似合う「マーダーピールズ」にしろ、バンドの放つ熱量が後半に入ってさらに加速度的に上昇していることによって、客席もそれに応えようとすると熱狂せざるを得ないような、コロナ禍でなければどんな光景が目の前に広がっていたんだろうか、と思うようなバンド側と観客側の相互的な音のコミュニケーションが果たされていた。
ツアーが終わっていくことへの感慨を感じさせながらも、今自分たちが最高の状態にいるということを証明するかのように、ハードボイルドな映画のエンディングテーマとして流れてもおかしくないように、
「歌うなら 劇薬が歌うように
剃刀が虹を切り刻むように
演じるわ さあ終わりまで舞台を
忘れさせぬように
奪うならすべて奪い取るように
音もなく胸を撃ち抜けるように
お楽しみの夜がはじまるわ
さようなら愛しきブロードウェイ」
という歌詞だけでその映画のシーンが頭に浮かぶように見事にメロディにハマっていく「ブロードウェイ」から、キメ連発のイントロを鳴らした後に中屋が台の上に立って両腕を大きく広げてから再度ギターを鳴らす「蝙蝠と聖レオンハルト」の体が震えるくらいの、音源を聴いていてもカッコいいというのに、ライブでそれを何倍にも引き上げるあまりのカッコ良さ。
自分は好きなバンドが必ずしもバカ売れして欲しいとはあまり思っていない。それは自分だけのものであって欲しいみたいな理由では全くなくて、自分が物凄くカッコいいと思っていたり、物凄く好きなバンドだとしても、全く刺さらない人がたくさんいることをわかっているし、逆にある人が物凄く「良い」と言っている音楽であっても自分には何が良いのかサッパリわからないということも少なからずあるからである。
だけど、バカ売れしなくても、誰しもが知るようなことがなくても、せめてそのバンドが持ちうるカッコ良さに見合ったステージに立てるようにはなっていて欲しいとは思う。それはこの日、おなじみの黒の革ジャンを着て会場に現れていた、佐々木亮介のa flood of circleにも抱いている思いであるが、この日ライブを見ていて、THE PINBALLSにも同じ思いを抱いた。
今でこそアニメのタイアップとして曲を知ってもらえる機会は増えているが、きっと古川は不特定多数の人に向かって愛想良く、要領良く話ができるようはタイプのアーティストではないし、そういうことをしてバンドの認知度を上げたいとも思っていないだろう。でもこのバンドが輝けるステージはもっとたくさんあると思えるようなライブをやっているバンドであることは紛れもない事実だ。アリーナとまでは言わない。でもせめてZeppやCOASTの広いステージに立ってロックンロールを鳴らすこのバンドの姿が見たい。
THE PINBALLSの存在を知った時は、「こんななに良い曲があるのにこのくらいのキャパなの!?」とも思ったりもしたが、まだ当時はここまでのライブができるようなバンドじゃなかったと今になると思う。でも今はそうしたZeppやCOASTに立つべきものを備えているバンドだと思っている。ガラッと世界やシーンを変えなくてもいい。でもこうしてライブを見ている我々の心を少しくらいは良い方向に変えてもらいたい。それができるバンドだと思っているから。
1人で音楽をやることの楽しさもわかっていながらも、こうして4人で、たくさんの人と一緒に同じ時間と空間を共有していることの喜びや楽しさやかけがえのなさを
「それは 君が僕に出会うまでの
僕が君に出会うまでの
永い永い夜にも似ていた
星がひとつかげる夜は 目の前にない時は
消えそうな この声で叫ぶよ」
というフレーズに乗せて歌う「ひとりぼっちのジョージ」から、どうしたってライブがクライマックスに近づいていることがわかる、物語のエンドロールであるかのように響く壮大な「銀河の風」と続くと、「millions of oblivion」のオープニングテーマである「ミリオンダラーベイビー」が鳴らされる。
このツアーの初日は2月、換気対策で建物の中でも風が吹き抜けるだけに、まだ厚着をしてライブを見ていた、まだまだ冬という季節の中だった。
でも東京ではもう春の代名詞とも言える桜も散り、街中には新社会人と思しき、まだスーツの重さを感じながら歩いているような人の姿も見かけるようになった。このツアーを経る中で季節が変わったのだ。だからこそ、
「でも春雨告げる風の中で
踊るおまえを思い出せる
春時雨ゆく 時の中で 何もなかったように」
というこの曲のフレーズは、この日のために鳴らされていたかのようだった。春雨かどうかはわからないけれど、ライブ前には雨が降って、地面が濡れていた。この曲の景色に合わせるように。
そうして駆け抜けるように本編を終えると、アンコールでは最初にステージに現れた古川がまずは石原を呼び込むと、
石原「生きてて良かったって思った」
とツアーファイナルならではの手応えと感慨を口にするのだが、順番に招き入れようとした森下と中屋が
「長い(笑)」
と言って紹介する前にステージに出てきてしまう。その2人の待てなさがこのバンドのライブの凄まじいくらいのテンポの良さに繋がっているのかもしれない。中屋はスーツのジャケットを脱いでいる。
そうしてアンコールの最初に演奏されたのは「millions of oblivion」の最後に収録されている「オブリビオン」。「millions of oblivion」は初回限定盤に収録されている、古川の描いた短編小説を読むとわかるように「記憶」がテーマになっている。ここまでに演奏されたアルバム収録曲たちも、一つの物語でありながら、一つの記憶でもある。そんな記憶にまつわる物語のエピローグのように
「きっと何百年も そして何千年も 繰り返されてる
あの約束のように 塵や彗星のように
忘れ去られて
ぼくらは 消えてゆく ようにできてる」
と歌われるが、この場所にいた人たちはきっとこの日のライブのことは、忘れ去ることもなく、記憶から消えることもなく残っていく。この日はそんな記念碑的なライブだ。
そうして「millions of oblivion」の物語を完結させると、
「ここからまたライブが始まるっていうくらいの気持ちで歌いたい!そうなるならば、喉が張り裂けてもいいというくらいに歌うはず!猛獣のように!」
と言ってあまりにも獰猛な「毒蛇のロックンロール」による致死量レベルの毒が会場全体に回っていく。踊ったり体を揺らしたり腕をあげたりするというルールの中で楽しみながらも、みんなよくモッシュしたりするのを我慢できるな、それはこの場所を、このライブを守りたいからなんだよな、というのが伝わるくらいに、この状況下でなければ間違いなく衝動的にモッシュが起こるであろうくらいのバンドの演奏の激しい熱量。雄叫びをあげるようにして歌うというここに来てさらに自分を更新せんとばかりの古川の言葉の通りにまたここから始まるというフレッシュさと、もう今日で全部出し切った上でさらに絞り切ると言わんばかりの集大成感。そのどちらもが同居することによって発生する化学反応が確かにあった。
しかしながらもうライブは終わりの時を迎えている。
「最後だから笑おうぜー!」
と台の上に上がって森下が叫ぶと、中屋も再び台の上に立って両腕を広げる。森下は歌っている古川の顔を覗き込むように演奏したり、クールな中屋の表情を崩そうとばかりに寄っていって目の前で演奏したり。そんなやり取りを見ている石原の表情もやはり笑顔だ。
「二人は笑いながら涙を流しながら 言葉を探していた」
というサビの歌詞の通りに、みんなが笑いながら、その景色の幸福さに涙が流れそうになりながら。こんな瞬間が訪れるのなら、すべてを失くしてもよかったとさえ思っていた。
メンバーはステージを去ってもまださらなるアンコールを求める拍手は鳴り止まない。それくらいに、まだまだいけるというバンドの状態だったし、そんなバンドが1曲でも多く演奏するのを見たい。そんな客席の空気に応えてメンバーが再度登場すると、
「本当に予定外だから何も考えてない(笑)」
と古川は言った。確かにツアー初日もアンコールは1回だけだったために、本当に予定外だったのだろう。
「このツアーは終わってしまうけれど、またバンドを始めた時のような、最初に戻ったようなつもりでライブをやりたい。そんなライブをみんなにも見せられる時が来ると思う」
と、近い未来での再会を約束していたが、「もっと大きなところで」と言うんじゃなくて、逆に「最初に戻ったような」ということは、このバンドはやはりそうした大きな会場などに目標を定めていないのだろう。それこそが同じメンバーで15年間続いてきた理由なのかもしれないが、
「最後はシンプルな曲の方がいいよね?」
と言って演奏された「アンテナ」は、まさに新しく始まったバンドであるかのように衝動に満ち溢れながらも、この状況でツアーを回ってきたバンドの強さを確かに感じさせてくれるものだった。
今まで何回THE PINBALLSのライブを観てきたのだろうか。フェスやイベント(あんまり出ないけど)も含めたらそれなりの回数を見てきたけれど、今までの中で間違いなく1番素晴らしいライブだった。これまでの自分たちをはるかに更新するような、そこに明確に挑んでいるかのようなライブだった。
アルバムの内容自体が素晴らしいというのはもちろんであるが、何かライブにおける秘訣というか、これだ!というものをTHE PINBALLSはついに掴み取ったのかもしれない。
それを今の時点で自分がわかる範囲で言うならば、それはこんな状況の中でもTHE PINBALLSの音楽とライブを必要としている人が本当にたくさんいて、そんな人たちの姿を実際に見に行くことができたツアーだったということだ。
それはツアーをやらないと、実際に観客がいるライブハウスのステージに立たないと絶対に視認することのできないものだ。そうした人たちがいなくてもきっとこのバンドはこうして4人で音楽を鳴らすのだろうけれど、目の前に会いに来てくれる人たちから貰えるものが確かにある。決してフレンドリーと言えるようなタイプではないが、THE PINBALLSはそれを自分たちの音や力に変換するということができるバンドになった。
いつか遠い未来に体や記憶が消え去っていくようなことがあったとしても、このバンドの存在や音楽はずっと思念として残り続けていく。そんな風にすら思えた、こんな状況でもバンドの進化を明確に示したツアーだった。
この状況が終わって元のライブの光景が戻ってきたら、もっととんでもないことになるような予感しかしていない。もっと凄い、どこかへたどりつける気がしてる。
1.ニードルノット
2.神々の豚
3.アダムの肋骨
4.Lightning strikes
5.放浪のマチルダ
6.ストレリチアと僕の家
7.花いづる森
8.SLOW TRAIN
9.(baby I’m sorry) what you want
10.欠けた月ワンダーランド
11.惑星の子供たち
12.統治せよ支配せよ
13.赤い羊よ眠れ
14.マーダーピールズ
15.ブロードウェイ
16.蝙蝠と聖レオンハルト
17.ひとりぼっちのジョージ
18.銀河の風
19.ミリオンダラーベイビー
encore
20.オブリビオン
21.毒蛇のロックンロール
22.片目のウィリー
encore2
23.アンテナ
文 ソノダマン