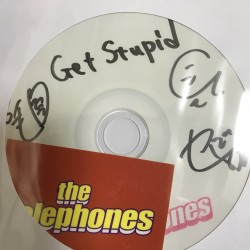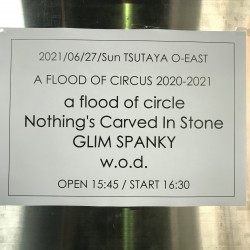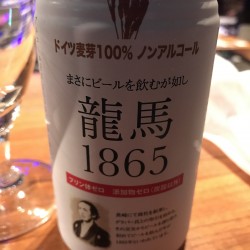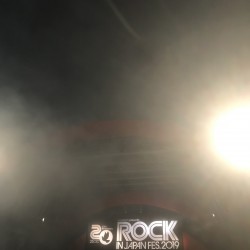東京の下北沢、新宿、渋谷というライブハウスが集合している地帯で開催されているサーキットイベント「TOKYO CALLING」。昨年は無観客配信でのサーキットという形態での開催だったが、今年は2年ぶりの有観客での開催。
朝から新宿は雨で、特にトップバッターの開演前は豪雨と言っていいくらいのレベルであった。払い戻し対応をしていることもあり、これはかなりの厳しい状況である。
この日の新宿は
Marble
MARZ
SAMURAI
BLAZE
ACB
Loft bar
Loft
SCIENCE
HOLIDAY
という歌舞伎町エリアの9会場で開催され、Zircoがリストバンド引換所として使われている。
なので新宿駅からZircoまで歩いてリストバンドを引き換え、さらに最初のアーティストを見るためにBLAZEに移動しただけでかなり心が折れるくらいの豪雨でライブ開始前からずぶ濡れになってしまった。
12:00〜 魔法少女になり隊 [BLAZE]
この新宿編の中で最大キャパのBLAZEは来月に開催されるJUNE ROCK FESTIVALとコラボしたステージになっているのだが、そのBLAZEのトップバッターは魔法少女になり隊。世の中はもちろん、バンドとしても変化があった近年である。
ステージにはドラムセットも設置されており、かつては「ドラムレスなのにラウドバンドかのように心が震えるライブをやるバンド」というイメージを持っていたが、それも変わっているようだ。それは明治(ギター)が体調不良で脱退し、火寺バジル(ボーカル)、gari(VJ、ボーカル)、ウイ・ビトン(ギター)の3人になるというパーティーメンバーの減少を経験したからかもしれないけれど。
なのでそのメンバー3人に加えてベースとドラムのサポートメンバーという5人編成で登場すると、リリースしたばかりの最新曲にして、ここからがまた新たなバンドの始まりであることを宣言するようなラウドなサウンドで、gariがまさに妖精というバンドの役回りのようにステージを舞うようにしてデスボイスを発する「NEW ME」からスタート。今やモデル的な活動も増えてきている火寺バジルも髪色こそ鮮やかでありながらも少女というよりは徐々に大人の女性になってきているのを感じる。それでも元気いっぱいに歌うというイメージは全く変わらない。
ライブではおなじみの「おジャ魔女カーニバル!!」のこのバンドだからこそのラウドアレンジではある意味では曲の肝であり、観客が1番楽しい部分でもあるコール部分でgariが口に指を当てて「声出さないようにね」というようなジェスチャーをし、観客は腕こそ上げるもコールをすることはない。なんならモッシュやダイブも当たり前というラウド由来のライブの楽しみ方も今は誰もしようともしていない。そうした楽しみ方を封印してでもこのバンドはライブをやっているし、やはりこうして演奏している姿を見ているだけで、音が聴けるだけで楽しいと思える。
そうしたラウドとアニソンなど、様々な要素を丸ごと取り入れたこのバンドが和の要素を取り入れた「ヒメサマスピリッツ」はgariの発する同期の音も含めて、彼が言う通りにお祭り感を感じさせる曲。そうした感覚も、今年はほとんど感じられることはなかっただけに本当に楽しくなる。
髪が伸びて髭が生えたことによって、見た目のイメージがかなり変わったウイ・ビトンがイントロのギターを刻む「革命のマスク」はかつてはバンドのトレードマークだったマスクが、今はライブ必需品になっていることに、それを物販で販売していたこのバンドの先見の明というか、恐ろしいまでにこの時代に合致してしまった感覚に陥る。
トランスとラウドを融合させたという点ではFear, and Loathing in Las Vegasにも通じるものがある「完全無敵のぶっとバスターX」はしかし、
「Work magic! Are you ready?
魔法をかけてよ
君ならできるよ
限界突破するんだドリーマー」
というサビの歌詞がこの状況でもサーキットフェスというものに来ている我々を肯定してくれているようでもあり、バンド側がそうしたこの状況で生き抜いていくための魔法をかけてくれているようだ。
そしてラストはドラクエのセーブデータが消えた時の音で始まることでおなじみの「冒険の書1」。そういえば、この日はgariの映像も使わないという、バンドの音と曲だけで勝負するライブになっていたことに、今まで何回も映像を観てきたこの曲を演奏した時に気付いた。それを可能にするくらいにこのバンドの音はさらに強くなっている。
「魔法少女になりたい」
の大合唱は今はできなくても、なんだか泣いてしまいそうになるくらいに心を震わせてくれるライブをするバンドというのは形が変わっても変わらない。メンバーが減ってRPGバンドという設定も薄れてきたけれど、まだゲームオーバーじゃない。喋れるようになった火寺バジルは最後に
「ありがとう」
と、かつては紙に書いていた言葉を自分の口で言えるようになった。その魔法で、今のこの世界を救ってくれるようになればいいなと思っていた。
gariはこの状況でこうしたサーキットフェスをやることを
「もう心意気しかないと思う」
と言っていた。決して精神論だけで突き進むバンドじゃないということは練られた曲のアレンジや映像、設定からもわかる。そんなバンドが主催者の意思に応えるのも、我々がバンドに応えるのも、心意気しかない。それを胸に刻み込むという意味でも、トップバッターにふさわしいバンドのライブだった。
1.NEW ME
2.おジャ魔女カーニバル!!
3.ヒメサマスピリッツ
4.革命のマスク
5.完全無敵のぶっとバスターX
6.冒険の書1
12:20〜 アラウンドザ天竺 [HOLIDAY]
魔法少女になり隊が終わってすぐに向かったHOLIDAYに到着したら、このステージのトップバッターである、アラウンドザ天竺がライブ中だった。バンド名を見るとどうしてもお笑いコンビの天竺鼠を思い出してしまうのは、彼らのキャラとネタが異様に強いからだろう。
「悪ふざけ系ラウドロックバンド」を自称していることもあり、ラウドロックという重い音を鳴らしながらも、歌詞が「そこ?」という部分を突きまくるという点では打首獄門同好会や、仲の良いイメージが強いバックドロップシンデレラというバンドに通じるものもあり、いきなりQUEENの「We Will Rock You」がほぼそのまま曲中に出てきたりと、まさに悪ふざけ系ラウドロックバンド。
しかしながらガワ(ドラム)の高速ツインペダルや、5弦ベースを弾きながらコーラスもこなすカッターと、やはりラウドロックをやっているだけあってメンバーのそもそもの技量は実に高い。つい先日、ギターが脱退したことがニュースになり、ドラムセットの前でギターを鳴らす、妙に顔が大きくて髪の長い僭越がサポートギタリストとは思えないくらいの存在感を放っている。
客席でもルールのある中で観客がその場でぐるぐる回ったりと、本当にステージも客席もお互いに楽しんでいることがよくわかるのだが、ロンドンタナカ(ボーカル&ギター。この名前も悪ふざけ系ラウドロックバンドのフロントマンにふさわしい)の
「俺たちはカッコつけることをカッコいいとは思ってなくて、ふざけてるのがカッコいいと思ってこれまでやってきた。だからみんなもルールを守りながら、自分のカッコいいと思うことを貫いてくれ!」
というMCにはこのバンドの本質が見える。それはある意味では自分の好きなヤバTやキュウソネコカミに通じるものかもしれない。
「今日、新体制になってまだ2本目のライブなんですけど、良いスタートが切れてるんじゃないでしょうか!」
と言った時に客席からは大きな拍手が起こっていたし、HOLIDAYはほとんど満員と言っていいような状況だった。正直、メインストリームで流れるにはタイトルや歌詞があまりに際どすぎる感じもあるけれど、これからいろんなところでライブを見るようになるのかもしれない。
13:20〜 the twenties [HOLIDAY]
周りの評価も曲を聴いていてもずっと気になっていた、the twenties。ようやくここでライブを観れる機会が巡ってきた。
アー写ではだいたいサングラスをかけているので、そのイメージでメンバーがステージに登場すると、タカイリョウ(ボーカル&ギター)はめちゃくちゃ髪が長くてハットを被っている、ウルマヒロユキ(ギター)はスキンヘッドに髭を生やした強面、ダイネソウ(ドラム)はファンキーなパーマがかった金髪に濃い顔、野菜くん(ベース)は正統派爽やか青年という、見た目が完全にバラバラ過ぎるのが、どうやってこの4人になったんだろうかとすら思わせる。なんならタカイリョウはエミネム、ダイネソウはPINK FLOYDと着用しているTシャツのアーティストもまるっきり違う。
しかしいざ「LET IT DIE」でライブがスタートすると、ダイネソウの思わず目を覚まされるというか、頭を引っ叩かれているかのような強いドラム、それに見合うような、真ん中の台の上に立ってソロを弾くというグルーヴの野菜くんのベース、同期の電子音かと思ったらよくよく見るとウルマヒロユキが鳴らしているシンセのサウンドかのようなギター、その見た目とエフェクトがかかっていることによって呪術的にすら聴こえるタカイリョウのボーカルと、リアルディストピアとすら言える今の新宿歌舞伎町の地下のライブハウスで音を鳴らしているのが実によく似合う、何から何まで「ヤバい」という感想に集約されていくかのような、享楽的でありながらもリアルなダンスロック。
エミネムのTシャツを着ているということはヒップホップの影響もあるのか、タカイリョウは時にはギターを置いてラップ的に歌唱し、その際はウルマヒロユキはラウドなギターを鳴らしたりと、編成もサウンドの変化も自由自在。ウルマヒロユキが観客に
「最後まで楽しんで!」
とその強面からはイメージできないくらいにフレンドリーな言葉を投げかけたりするも、基本的にMCなしで次々に曲が放たれていくので、体を揺らしっぱなしであり、その強靭なグルーヴによって踊らざるを得ない30分。
「吐き気が止まらない 夜の京王線で
砕かれた雨が 黒目をえぐり取るよ」
という昨年末にリリースされたアルバム「NASTY」収録の「Last Nite」の物々しい歌詞も、雨が降っていて京王線が通っているこの日の新宿の情景に実によく似合う。
そんな凶悪なくらいに合法ドラッグかのようなダンスロック。タカイリョウは途中でハットが落ちて長い髪を振り乱しながら歌っていたが、こんなにも法やルールの外にいそうな雰囲気を漂わせているバンドが観客も含めてちゃんと今のライブハウスのルールを守っているというところにただ「ヤバい」というだけではない希望をも感じることができるが、今まで通りのライブハウスに戻った時にこのバンドがどんなライブをやるのかを観てみたくなった。そういう意味でも、コロナ禍が早く収束するように。
14:00〜 ビレッジマンズストア [BLAZE]
今やZeppクラスにまで到達し、なかなかワンマンのチケットが取りづらい存在になりつつある、ビレッジマンズストア。なのでライブを観れるのもかなり久しぶりだ。
おなじみの赤いスーツに身を包んだ5人がステージに登場すると、水野ギイ(ボーカル)が歌うよりも前に
「TOKYO CALLINGの主役を取りに来ました、ビレッジマンズストアだ!」
と叫び、「夢の中ではない」から岩原洋平と荒金祐太朗のギターが唸りまくる。コロナ禍になって以降は当初は配信ライブも行いながら、今では精力的にライブハウスで有観客ライブを行っているバンドの強さ、ライブハウスで生きるバンドの誇りのようなものがすでに冒頭から溢れまくっている。
ジャック(ベース)と板野充(ドラム)によるリズム隊も明らかに音の迫力とグルーヴが増しながらも、声は出せなくても拳は上がるだろうとばかりに観客を煽るのだが、そんなバンドの気合いが漲りまくっている理由を水野は、
「忘れもしない3年前のTOKYO CALLING。俺たちの出番になってジングルが鳴ってステージに出ようと思ったら、
「next artist ドラマチックアラスカ」
ってアナウンスが流れた(笑)あの日から俺たちはTOKYO CALLINGの主役になるって決めたんだー!」
と、過去のこのイベントでの経験が自分たちを燃え上がらせる原動力になっているという、ロックバンドとして実に真っ当なリベンジの仕方をすることを口にして、7月にリリースされた久しぶりのフルアルバム「愛とヘイト」収録の、
「にゃあと驚く間に」
というフレーズ部分で水野が拳を猫耳のようにするのがどこか可愛らしくも感じる「猫騙し人攫い」と、水野が歌い上げるタイプの曲にもたくさんの名曲があるこのバンドが、ストレートなロックンロールで勝負する30分であることがわかる。
だからこそ「サーチライト」では観客に手を挙げさせるのだが、声が出せない、歌うことができない観客の代わりとばかりに岩原がめちゃくちゃ大きな声で、もはやコーラスというよりは叫びというレベルで歌っていたのが実に印象的だ。一緒に歌えなくてもカッコいいバンドであることはわかっていることであるが、その日が来るまでを自分たちで繋いでいるかのようですらあった。
そんな中で水野は、
「世の中も変わってしまったし、お前も変わってしまう時が来るかもしれない。でもお前が変わっても、またライブハウスに来た時に今と同じようにギターとベースとドラムを鳴らして歌うだけの、変わらないロックバンドでいようと思った。その時にお前が「ああ、変わってないな」って思ってもらうために」
という、ロックンロールバンドとして守り続けていく自分たちのスタンスを口にしたのだが、そこには強い求心力と説得力、そして貫禄のようなものがあった。その言葉に見合うようなライブをするバンドになり、こうしてサーキットフェスの1番デカいステージに立つのにふさわしいバンドになったのだ。
そして
「何回でもサヨナラって言うぜ。何回も言えるっていうことは、何回も会えるってことだからな」
と言っての「LOVE SONGS」はだからこそ
「何度でも口に出せそうだよ
サヨナラだベイベー」
は別れの曲ではなく、ライブバンドとしての再会のための歌として響き、ラストの「PINK」のここがロックの中心地であるかのような開かれたメロディたるや。それは
「今日の優勝は俺とお前だ」
という決め台詞をその通りのものにしていたし、それをバンドがキメに入る瞬間のタイミングで口にすることができる、水野のロックスターっぷりを感じさせた。ああ、なんだかもっと凄いところまで行けそうだなと思った。ロックンロールという芯の部分を全く曲げることのないままで。
1.夢の中ではない
2.ビレッジマンズ
3.猫騙し人攫い
4.サーチライト
5.LOVE SONGS
6.PINK
15:20〜 愛しておくれ [HOLIDAY]
前にライブを観たのは2020年の2月。1年半前であるが、まだコロナ禍になる前で、東京初期衝動との下北沢SHELTERでの2マンは両バンドのフロントマンが客席に飛び込みまくるという、今では遠くなってしまった景色を見れた最後のライブだった。そんな愛しておくれを久しぶりに観れる機会を与えてくれたTOKYO CALLINGに感謝である。
おなじみの金髪マッシュヘアの中山卓哉(ボーカル)、ギタースタンドをのっけからぶっ倒す小畑哲平(ギター)がストレートに衝動を炸裂させながらも歌詞がロマンチックなパンクというのは、もともとの彼らの原点に今にして向き合ったものであるが、仲沢犬助(ベース)のモータウン的なリズムであったり、突っ走りがちなパンクならではのテンポをしっかりとキープしている高原星美(ドラム)というメンバーの演奏技術は、本来ならば様々な変化球を投げることができるバンドが「俺たちはストレートで勝負したい」という思いでパンクを選んだということがよくわかる。それはやはり各々のキャリアがあってこそだろう。
中山は観客の近くまで行って歌ったりもするのだが、やはりコロナ禍になる前とは全く違うというのは、距離を保ち、客席の中に入っていったりはしないということ。パンクではあれど弁えているというか、社会的に生活していけるパンク。本人も
「うちのメンバーはみんな結婚したり就職したりしてるんで。ちゃんとした人たちですから」
と言っていたが、確かにパンクバンドのメンバーというとなかなか会社の部下にいたら困るだろうなというタイプの人も多いのだが、このバンドのメンバーはむしろ同僚だとしたら頼もしさを感じそうですらある。
そうした自分たちなりのパンクを鳴らしながらも、中山はこのコロナ禍によってなかなかライブや活動が思い通りにいかなくなってしまった期間であったことを語りながら、12月25日に新代田FEVERで開催されるワンマンライブをもって、ライブ活動の無期限休止を発表する。その理由はライブタイトルが「地獄からのハネムーン」というものであることから察してほしいということであり、これからもこの4人でバンドを続けるための選択であると、核心は言わないようにしていたのだが、その本人である高原は自分から理由を発表してしまう。その理由を尊重できるということは、3人にとっては高原も高原の家族もメンバーであり家族であるということだ。まだ公式が内容までは発表していないので書かないけれど、無期限休止というよりは休暇という表現が合っているのかもしれない。
しかし中山は
「1年経つとこういうイベントに出てるバンドも半分くらい入れ替わる。俺たちも来年このイベントに出ているかはわからない。1年経つと忘れられてしまうかもしれない。新しくファンになってくれた人が来てくれるのは嬉しいけど、来なくなってしまった人がいると凄く寂しくなる。それでもいつかまたそういう人にもライブに来てもらえたらなって」
と、止まることへの不安を口にしていた。
でもこのバンドが休んでいても自分が忘れることは決してないと思っているのは、このバンドとは音楽の原点が同じであり、こうしてライブを観ていると、自分の中にその原点の音楽が大切なものとして今も残り続けていることに気づかせてくれるからである。だからこそどこか自分のことを観ているような感覚すらある。
そんな発表をしたバンドが最後に演奏した曲は、バンド名でもある「愛しておくれ」。同じ原点だからこそ、凄いタイトル、バンド名を付けたなと思う。思い出や思い入れが強ければ強いほど勝てないと思うものに真っ向から挑んでいるからだ。その姿勢こそがこのバンドにとってのパンクなのかもしれないし、青春という時期はとっくに通り過ぎた、次の出勤日のことを頭に入れながら生きていかなければならない年齢になっても、まだキラキラ輝いていることができる。このバンドの音楽やライブはそんな力を自分にくれる。最も仕事が休みにくいクリスマス、このバンドのライブに使えるだろうか。
16:20〜 THEラブ人間 [HOLIDAY]
自身も下北沢最大級のサーキットフェス「下北沢にて」を主催している、THEラブ人間。このTOKYO CALLINGには下北沢ではなく新宿編への出演である。
金髪の金田康平(ボーカル&ギター)を中心に5人が登場(サポートベースは元Awesome City Clubのマツザカタクミ)すると、谷崎航大の美しいヴァイオリンの音色に導かれるようにして金田が歌い始めた
「鎖骨の下にあるタトゥー」
というリアル過ぎてドキッとしてしまうような描写の歌詞の曲は新曲だろうか。フォークの要素も強く感じるこのバンドならではの長尺な曲である。
金田の逞しさを感じさせる声質と、村上春樹などを愛する文学性を感じさせる歌詞の融合による、
「言わないで言わないで」
のリフレインと、そこに絡む谷崎のヴァイオリン、さらにはマイクを通さずとも歌詞を口ずさみながら演奏するツネ・モリサワのキーボードの音色がメロディの美しさと切なさを際立たせる「大人と子供(初夏のテーマ)」はやはり名曲であることを実感させてくれるし、金田の鋭くも慈悲深い眼差しは観客一人一人の目をしっかりと見ているようであり、こちらの心を見抜かれているんじゃないかと思ってしまう。
このバンドの、というか金田の描く歌詞は私小説そのものでもあり、だからこそバンドの代表曲である「砂男」の続編である「砂男II」という曲まで作ることができるのだが、このライブの際に最前列には母親と一緒に来ていた、小学生くらいの子供がいた。金田はその子に向かって
「大人になったらギターを買えよ。親の金で買ってもらうんじゃない、自分で働いた金で買うんだ」
と言っていたが、その言葉はこの「砂男II」のテーマにどこか凄くマッチしていたし、この子はこの日ステージに立っていたロックスターにそう言われたことをこれからも覚えているだろうか。そしていつかギターを買うのだろうか。そうしたことを想像するだけで、また新たなTHEラブ人間の曲になりそうな感じすらある。
「今日のリストバンドは何色だい?
(観客の挙げた腕を見ながら)赤か。その赤が、照明に照らされて夕暮れのように見えるな。俺の歌で、ギターで、次の曲で、ロックンロールで、このクソみたいな日本を生きるあんたを生きやすくしてやる!」
と、金田が本当に詩人のような言葉を口にしてから演奏したのは、やはりバンド最大の名曲である「砂男」。歌詞に「新宿HOLIDAY」など、この日だからこそのフレーズも交え、富田貴之のフレッシュさを感じさせるドラムとともに新しい響きでこの名曲がまた生まれ変わったようにすら聴こえた。
何よりもライブが終わった後の、全てを持っていってしまう感覚。それはかつておかもとえみ(フレンズ)が在籍していた時代にライブを見ていた時から変わらないこのバンドの力だ。曲がどれも長いだけに30分の持ち時間だと4曲しかできないという点では、こうしたイベントよりもワンマンなどの長い尺で見たくなるし、そうしたライブの方がさらに本領を発揮できるバンドでもあるのだけれど、たった4曲でそうして全部持っていってしまうというくらいに圧倒された。どれだけメンバーが変わっていっても、その感覚はずっと変わることがないのが懐かしくも嬉しくもあった。
17:20〜 爆弾ジョニー [HOLIDAY]
この日の前日に爆弾ジョニー、THEラブ人間、忘れらんねえよという3バンドでライブを行っていただけに、この日の流れは2日連続でその3組のライブを体験させてくれるものである。
サウンドチェックの段階からずっと確かめるように演奏していた新曲を1曲目に持ってきたのだが、この曲はりょーめー(ボーカル&ギター)のボーカルとアコギをメインにした、フォークさを感じさせる曲。そのりょーめーはメガネをかけてバンドで固定しているのだが、これはメガネをなくさないようにというものらしい。
「メンバー全員で歌います!お前(キーボードのロマンチック☆安田)はいつも1曲目が終わった瞬間に水を飲むんじゃない!(笑)」
と安田をいじってからの「なぁ〜んにも」では冒頭からメンバー全員で大合唱するのだが、それは
「みんなの分まで俺たちが歌ってるんだ!」
と、声を出すことができない我々の代わりにメンバーが思いっきり歌っているのがわかる。小堀くん(ベース)も曲中にシャウトしまくり、キョウスケ(ギター)はその場でくるっと回ったりしながらギターを弾きまくり、
「俺たちが爆弾ジョニーだ!」
と叫ぶ。10代でデビューしてシーンに衝撃を与えた、ロックンロール神の子っぷりはもうメジャーデビューからも8年ほど経っているけれど、全く変わることはないし、今でもこの曲をみんなでまた大合唱したいと思う。それ以外に、音楽以外になぁ〜んにもないのだから。
りょーめーがバンドの新グッズであるタオルを歌いながら振り回し、安田もわざわざ演奏しながら袋を開けて同じタオルを取り出して振り回すのは「ケンキョニオラツケ!」で、さりげなく物販アピールもするのだが、りょーめーも安田もタオルの値段をちゃんと把握しておらず、
「多分1500円だと思う」
ということに。
さらにイントロの安田のピアノのサウンドで観客を踊らせる「キミハキミドリ」では宇宙語のコール&レスポンス部分で安田が観客に
「独創性のある腕の挙げ方で応えてほしい」
と言うのだが、すぐに「飽きた」と割と普通の腕の挙げ方に落ち着き、タイチ(ドラム)によるラスサビ前の宇宙語の叫びでは
「今日は僕の弟に電話して、叫びをやってもらうかと思います!」
とリアルな弟のユウヤに電話すると、割とノリノリで
「行きますよ〜!」
というユウヤのシャウトでサビへ…と思ったらタイチも自身で叫んだので、
「お前が言ったら弟が言った意味がなくなるじゃん!(笑)」
とメンバーに突っ込まれまくる。しかしそうした面白いと思っていることをひたすらやりまくるというこのバンドの精神性もやはり全く変わっていない。
そんな愉快なやり取りを経ながらも、りょーめーが歌いあげる「緑」はそうしたパーティーロックンロールバンドとは違ったこのバンドの一面を見せてくれる。それはつまりメロディの良さということでもあるのだが、歌詞の視点はやはりどこか年齢や経験を重ねたことを感じさせるものになっている。
そしてラストはまさかのメンバーによるカラオケラップの「あしあとJAPAN」。タイチ、安田、小堀、キョウスケと代わる代わる前に出てきてはラップし、タイチと安田は三代目J Soul Brothers「R.Y.U.S.E.I.」のダンスを踊ったりと、やはりやりたい放題であるのだが、りょーめーとキョウスケは歌いながらケーブルを片付けたりと、ある意味では終わりの転換をしながらできる曲という、実に効率的な発想による選曲なんじゃないか、とも思うけれど、これだけ強固なグルーヴを持つバンドがカラオケをやっているというのはどこかシュールでありながらも、やっぱり爆弾ジョニーらしかった。
例えば前日に対バンした、忘れらんねえよとTHEラブ人間。あるいはキョウスケが参加していた、a flood of circleや、小堀くんが参加していた、the pillows。このバンドのメンバーたちはそれぞれがベテラン、先輩などの様々なバンドのサポートを務め、そのバンドが変わっていく様を支えてきた。そのバンドたちが止まることがなかった影にはこのバンドのメンバーたちの貢献があるのだが、そうして変わらざるを得なかったバンドを支えてきたメンバーたちのバンドがメンバーもライブのあり方も含めて、今も全く変わっていない。それがなんだか本当に嬉しかった。
1.新曲
2.なぁ〜んにも
3.ケンキョニオラツケ!
4.キミハキミドリ
5.緑
6.あしあとJAPAN
18:00〜 ガガガSP [LOFT]
前週にもこのLOFTで東京初期衝動と対バンをしている、ガガガSP。何というか、タイムテーブルを見るだけで明らかに異彩を放っているくらいに突出して実績のあるベテランが一組だけ若手バンドの中に混ざっているという感じだ。
SEもなしにメンバー4人がステージに登場したのだが、これはSEを用意するのが間に合わなかったという理由であることがメンバーの口から明かされ、
コザック前田(ボーカル)「うちのギターが9月15日で40歳になりまして。(客席から拍手が起こる)
これで全員40代のバンドになりました!」
と、40代になってもなお、まだ青春の真っ只中にいるかのような「青春時代」でスタートし、サウンドも衝動も今もずっと変わっていないことを示す。コザックは客席に入れないからこそ、代わりにステージ左右の壁に体当たりしたりというその衝動の向け方。ライブのスタイルも全く変わらないが、
コザック「どう?40代になって?」
山本聡(ギター)「いや、なんにも変わらないですよ(笑)」
と、メンバーの精神性も、なんなら桑原康伸(ベース)、田嶋悟士(ドラム)の見た目も20年近く前にこのバンドに出会った頃から何も変わっていないような感じすらする。それは今でもずっと若々しいという感じではないのだが、今でもずっと変わっていないとは思うという実に微妙に難しい感覚なのだが。
山本がイントロのギターを鳴らしただけで何の曲だかわかった観客が拍手を送ると、歌い出すより前にコザックが
「この曲を作った時、もう20年くらい前ですけど、別れた彼女に「君よ幸せになれ」って歌いながら、本心では「お前なんか俺と別れたら絶対幸せになんてなれへんわ!」って思ってた。つまり嘘をずっと歌ってた。
でも今はそういう別れた人とか、今こうしてライブを見に来てくれているあなたに心から「君よ幸せになれ」って思えるようになった。そこだけは変わったところなのかなって思う」
と、この曲に込めたメッセージは変わらないけれど、歌う気持ちが本心になっていることを告げたからこそ「国道二号線」は今までよりもさらに胸を打つ。それはきっと聴いている我々も人生の中で過ぎ去っていった人に対してそう思えるようになったからであろう。
「さっき、このステージに前に出たユタ州のライブを見てましたけど、お客さんもやっぱり今の方が年齢層が高いですね(笑)
我々も全員40代ですけど、今でも「このままバンドやっていていいんだろうか」「このままの人生でいいんだろうか」って20歳とか25歳くらいのバンドみたいに悩んだりする。
だからこういうサーキットフェスにも今でも呼んでもらえるのかなって。もう達観した175Rとかはこういうフェスには出ないでしょうけど(笑)ギャラが高くなったバンドとかも(笑)でも我々はこういう場所で今でも全力を尽くせることを本当にありがたく思ってます!」
と、そんな自分たちをそのまま肯定するかのような新曲「これでいいのだ」はもはやガガガSPでしかない、ガガガSPらしさというものが完全に我々の中にも確立されているんだなと思うくらいにガガガSPな曲。タイトルやサビから、某携帯電話会社のCMを思い出してしまったりもするけれど。
そうして今でも新しい曲を生み出しながらも、
「どうせ「卒業」とか「線香花火」だけ聴ければいいっていう人も大勢いる(笑)」
と、観客の期待に応える部分と、自分たちが今やりたいことをやるというバランスを取るように、こうした30分の持ち時間の中で演奏されるのが意外なタイプの「真夜中の恋人」は今年リリースしたシングル「ロックンロール」収録曲であり、やはりバンドが前に進んでいる、かつてのヒット曲や代表曲を毎回やるだけのバンドではないことを示しながら、
「こういう状況になって言えることは、もう生き抜いていくしかないんじゃないかと。死ぬまで生きていくしかないじゃないかと。死ぬまで生きてやろうじゃないか!」
と、曲の象徴である歌詞を口にしてから、まだ季節的には少し早いかもしれない「晩秋」を演奏し、山本も桑原もサビの
「晩秋の夕暮れは」
のフレーズを思いっきり叫ぶ。マイクスタンドに下から齧り付くかのような山本の表情も、歌った後に顔を横に振る桑原の仕草も、この曲がリリースされてライブ収録のPVで初めて見た時と全く変わっていない。それはそのまま、その当時に自分が見ていた景色や、周りにいた人のことを思い出させてくれる。それは今もこうしてガガガSPが変わっていないからこそ感じられるものだ。まだまだこの感覚を味わいたいから、死ぬまで生きてやろうじゃないかと思えるし、最後に演奏された、歌詞の物語も含めてフォークに始まり、途中からパンクに展開するというガガガSPのスタイルを1曲に詰め込んだ「明日からではなく」は、今この瞬間からまた自分にできることをやっていこう、そう思わせてくれたのだった。
オリコンTOP10入りするくらいのヒットをしたこともあるし、色々と世間に言われてしまうようなこともあった。それでも自分が出会った頃(もう18年くらい前)と全くメンバーが変わることがなく活動している。それだけでも凄いことなのに、周りが若手バンドや若い観客であるサーキットフェスというライブの最前線に今も立ち続けて、こんなにも心を揺さぶるようなライブを見せてくれる。その姿は見ている我々にこれ以上ないくらいの力を与えてくれるし、きっとこれから先もいろんなところで見れるんだろうな、と思える。
1.青春時代
2.国道二号線
3.これでいいのだ
4.真夜中の恋人
5.晩秋
6.明日からではなく
19:00〜 忘れらんねえよ [BLAZE]
いよいよTOKYO CALLING初日の各会場もトリの時間。最大キャパのBLAZEのトリは忘れらんねえよ。コロナ禍になる前から様々なフェスなどでトリを務めてきた存在である。
サウンドチェック時に柴田隆浩が中学生レベルの卑猥な単語でマイクのチェックをしていると、サポートギターのロマンチック☆安田に
「もう40歳なんですから(笑)」
と突っ込まれながら、開演前から集まってくれた人のために曲を演奏する。
いったんステージを掃けてから本番で登場すると、ベースがイガラシ(ヒトリエ)ではなく、スケジュールの都合なのか、これからはこの編成でいくのかはわからないが小堀くん(爆弾ジョニー)になっている。ギターが安田、ドラムがタイチであることから、完全に爆弾ジョニーのボーカルが変わっただけという形になっている。
柴田が朴訥と歌い始めながら、サビでは一気に照明も含めて光が射し込んでくるかのような「だっせー恋ばっかしやがって」から始まると、観客の手拍子も起こる「戦う時はひとりだ」は、まさにこうしてこの状況下で新宿のサーキットフェスに来るということを戦いとして我々のことを一人で戦っている戦士であると言ってくれているかのようだ。
「コロナに加えて台風も来ている中で、こうやって歌舞伎町の嫌な感じをも乗り越えてここに来てくれて本当にありがとう!」
と、やはり歌舞伎町の空気を好きになれそうにない(昔、バンド主催のファンを招いて開催した飲み会は歌舞伎町のつぼ八が会場だったが)柴田が観客への感謝を口にすると、フラワーカンパニーズ「真冬の盆踊り」をそのまま使った「ヨサホイ」のコール&レスポンスも手拍子を使ったものに変化しているのだが、そんな柴田の抱える内なる衝動を炸裂させる「ばかばっか」では間奏部分での、今までは客席に突入してビールを一気飲みしていたのが、ステージ上でノンアルコールビールを一気飲みするという時勢を反映したものに変更。しかしながら1人でノンアルを一気飲みするのは味気ないということから、メンバーも一緒に一気飲みするのだが、何故かめちゃくちゃ嫌がっていた(炭酸が苦手なのか?)安田を含めた爆弾ジョニー組の方が先に飲み切ってしまい、
「早く飲めよ!」
と柴田が煽られる展開になっていたのは実に面白かったのだが、ステージ上だけは無罪放免というわけではなくて、自身のライブの中心的なパフォーマンスを変えてでも、こうした長丁場のフェスでも今までのようにライブハウスで酒を飲むことができない我々と同じように今のこの状況を乗り越えようとしている。柴田のそういう我々に寄り添ってくれるというか、ともに戦ってくれる姿勢を自分は心から信頼している。
そのまま突入した「Cから始まるABC」では柴田が歌詞を
「あの娘は彼氏候補の男と
グループで涙物語に行った」
というこれまた時勢を逆の意味で考慮したものに変えており、ついつい笑ってしまうのだけれど、忘れらんねえよも千葉LOOKのワンマンを延期からの中止にしたりしなければならなかっただけに、あのフェスの開催についていろいろ思うところがあったんだろうなと思う。
「残された俺たちはJUNE ROCK FESで飲みました」
と、あくまでステージの名前にJUNE ROCKがついているのにその歌詞に変えてしまうあたり、柴田にとってはこの日はJUNE ROCK FESだったのかもしれない。(来月のJUNE ROCK FESにも忘れらんねえよは出るけど)
すると、柴田が近年おなじみの眞子さまと小室圭氏の話をし(柴田は眞子さまが好き)、安田に
「その話はなんのメッセージがあるんですか?(笑)」
と突っ込まれ、観客からも全く支持を得られていないという手応えのなさの中で、そんな話の後にやるようなタイプの曲とは思えない名曲「花火」を情感をたっぷり込めて歌い上げる。今年はこの曲を花火が上がる場所で聴くことができなかったな…とも思ってしまうのだが、それでもこうして忘れらんねえよのライブをこの状況でも見れている。それだけでどこか救われるような。
いつも「この街には君がいない」!と言って演奏されたパンクナンバー「この街には君がいない」と、初期の曲がこうして今でもフェスのセットリストに入っているというのも嬉しいところであるが、それでも「俺よ届け」という全く初期ではない曲が同じくらいの衝動を持っていて、より忘れらんねえよらしい名曲としてこうしてセトリに並んでいるというあたりに、柴田1人だけになってしまってもバンドの生み出してきた曲が全く間違いではなかったということがわかる。
すると柴田はそれまでの眞子さまとかのMCとは全く違った緊張感を漂わせながら、
「TL見てると流れてくるんですよ。「ライブ行きたいけど行っていいのかな」って。………良いに決まってんじゃん。みんなちゃんとルール守って対策してるんだから。いろいろあるだろうけど、やっぱり音楽ないとやっていけないじゃん。だから俺は今日来てくれた人のことを全部肯定してやりたいと思った。今日終わって帰る時に、来てよかったって思えるようにしてやりたいって」
と、悩んでしまいがちな観客の背中を押して、支えてくれる。柴田が、アーティストがこうして我々観客の選択を肯定してくれているように、自分も「ライブをやる」と決めてステージに立っているアーティストや、そこに関わる関係者、ライブを作ってくれている人、その全ての存在を肯定してやりたい。その人たちがいるおかげでこうしてこの状況下でも毎日目標や楽しみを持って生きていられるのだから。興味のない人にどんなことを言われても、アーティストのことも、ライブやフェスを作っている人のことも可能な限り応援したい。だからこうして毎日のようにライブに行っているのだし、会社には毎日通勤しているのに、会社よりもはるかに厳しい対策をしているライブに行くのが怖いからやめるというのは自分の中ではそうしたアーティストやライブを作ってくれている人に申し訳が立たない。
柴田がそんな思いを持っているからこそ生まれたであろう新曲は
「これだから最近の若者は、とかやめようや
アイドル猫から見たら同じ
全人類チートゴリラ
まとめると最近の我々は最強なんだ
ねえもしも愛してくれるなら
どこまでもゆけるぜ
いつまでも踊るぜ
死ぬまで歌うぜ」
という最後のサビのフレーズがやはり我々を肯定してくれるような「これだから最近の若者は最高なんだ」。柴田は「音楽と人」の連載で「めちゃくちゃ良い曲ができた」と書いていたけれど、それがこの曲なんだろうか。そうとしか思えないくらいに、今の2021年のコロナ禍の日本で忘れらんねえよが世に出す曲としてこれ以上のものはないというくらいの名曲だ。
そしてラストはやはり「忘れらんねえよ」で、おなじみの合唱パートでは場内が暗くなり、サイリウムのように光る観客のスマホライトがその暗闇を照らす。合唱パートで声が響くことはないけれど、
「もうちょっとで絶対抜けられるから!」
と柴田が言っていたように、この観客一人一人のスマホが放つ光はそのまま音楽シーン、ライブシーンの、なんなら世の中への希望のようだった。
アンコールではメンバー紹介をするのだが、当然ながら爆弾ジョニーのメンバーしか紹介しないため、
「爆弾ジョニー2号店」
「ボーカルだけシニア爆弾ジョニー」
と笑わせながら、最後に演奏されたのは
「明日には名曲がJUNE ROCKに生まれんだ」
と、やっぱりTOKYO CALLINGだと思ってないのかな、と思いながらも、曲中に気付いて
「TOKYO CALLINGでした!」
と訂正した、「この高鳴りをなんと呼ぶ」。この高鳴りは、音楽でしか感じることができない。音楽は目の前で鳴っているから。目の前で音が鳴っていることによって、笑ったり泣いたり昂ったりすることができる。いや、できるというか、心が勝手にそうなってしまう。生きていて、他にそんな瞬間があるのだろうか。自分にとってはない。それはそのまま、こんな平凡な人間を変えることができる音楽の凄さであり、音楽が不要不急なわけがない。
音楽でしか生きていくことができない人間である柴田=忘れらんねえよのライブはそんなことを実感させてくれるのだった。
リハ.バンドやろうぜ
リハ.踊れ引きこもり
1.だっせー恋ばっかしやがって
2.戦う時はひとりだ
3.ばかばっか
4.Cから始まるABC
5.花火
6.この街には君がいない
7.俺よ届け
8.これだから最近の若者は最高なんだ
9.忘れらんねえよ
encore
10.この高鳴りをなんと呼ぶ
新宿歌舞伎町というのはやはりというか何というか、こんなにライブハウスがなければ極力近づきたくないような街だ。治安の悪さで名高いBLAZE前の広場でもマスクもせずに酒を飲んで騒いでいる集団もいれば、水商売系の呼び込みであろうスーツを着た人もマスクを着けていない人が多い。なんならいかにも歌舞伎町を歩いているような人はそういう人ばかりだ。
自分はロックシーンと自分の生活範囲の事柄しかわからないというか知らないので、ロックシーンに関わる人や観客がマナーがいいのかどうかは客観的にはわからない。もっとマナーがいいところもあるかもしれないし、涙物語に比べたらやはり良いのかもしれない。
でもTOKYO CALLINGに関わる、リストバンドを付けている人でそうした歌舞伎町にいるような、これはマズイだろうと思う人は全くいなかった。なんなら外にいるよりも、1アクトごとにしっかり換気し、入場時に毎回検温と消毒をしなければ入れないライブハウスが1番安全なんじゃないかとすら思った。そこにはこうした小さなライブハウスで生きる全ての人の生き様が反映されていた。これからもそれを守っていけますように。
文 ソノダマン