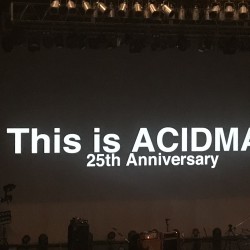9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 TOUR 2020 〜CHAOSMOLOGY〜」 (振替公演) Zepp Haneda 2021.6.6 9mm Parabellum Bullet

今年に入ってからはTHE BACK HORNとの2マンライブや渋谷LINE CUBEでのワンマンライブなど、感染対策を講じながら徐々にやれるライブを増やしてきた、9mm Parabellum Bullet。
昨年開催するはずだった全国ツアーも延期の果てにようやくこの初日を迎えてスタートすることに。
今回のツアーは事前にバンドサイドからアナウンスされていた通り、2017年にリリースされ、当時は滝善充(ギター)がライブに参加できなかったために不完全な形での開催となった「BABEL」の完全版と、インディーズ時代の「Gjallarhorn」「Phantomime」の2枚のアルバムを再現するものに。今の9mmの状態でのそれらの楽曲、アルバムの再現はどういったものになるのか。
まだ陽が落ちていないZepp Hanedaには駅から会場に向かう際に飛行機が飛んでいるのが見える中、検温と消毒だけでなくチケットの半券の裏に個人情報を記入するというのは9mmのライブの感染対策の一環である。
日曜日とはいえ17時開演という早い開演時間を少し過ぎると場内に流れるBGMが徐々に大きくなっていくと暗転し、ステージにかかった暗幕の向こう側からアコギの音などが聞こえてくる。この辺りからして普段の9mmのライブとは違う、まさに「TOUR OF BABEL」の再現ライブである。
暗幕が横に開くと(下手側がモニターに引っかかっていたのがちょっと面白かった)、そこにはすでに楽器を手にして演奏しているメンバーたちの姿が。普段のフォーメーションとは異なり、菅原卓郎(ボーカル&ギター)を真ん中に下手にかみじょうちひろのドラム、卓郎とかみじょうの間に長い髪をこの日は結くことをしていない中村和彦(ベース)、そして上手には「TOUR OF BABEL」には参加していなかった滝の姿が確かにある。この並びは為川裕也(folca)、武田将幸(HERE)のサポートギター2人を加えた「TOUR OF BABEL」ならではのものである。メンバーの背面にもこのツアー「CHAOSMOLOGY」のビジュアルが聳えている。
再現ライブであるからして曲順もアルバム通り、「ロング・グッドバイ」で滝のタッピングが冴え渡るのだが、この曲自体は「TOUR OF BABEL」の最終日の人見記念講堂でも最後に滝が出てきてこの演奏をしているとはいえ、そこにもはや9mmの名誉メンバーと言っていいくらいにバンドの宣伝活動などにも力を貸してくれているサポートギタリスト2人と、先週の新ユニット「それとこれとはべつ」のライブから髪がさっぱりしている、黒ずくめの卓郎のギターという4本のギターが重なり合う音は圧巻である。座席の位置的に、メンバーの後ろにいるサポート2人の演奏を全て目で捉えることはできないけれど、どのフレーズを誰が弾くのかという分担も滝に過度な負担がかからないように考えられていることがよくわかる。
「BABEL」の背景の話をすると、そもそもその前のアルバムである「Waltz on Life Line」がメンバー4人それぞれが作った曲を持ち寄った、ボリューム感と幅広さのある(収録曲数、時間ともに9mmのアルバムの中では最多)ものであったのだが、卓郎もイマイチその内容に確信を持てていなかったことをインタビューでも語っており、それを経て作曲:滝、作詞:卓郎という9mmの元の形で制作されたのが「BABEL」である。
つまり「BABEL」はもともとの9mmらしさに立ち返ったアルバムということなのだが、だからこそか、「Story of Glory」では和彦が客席に向かって両手をいっぱいに広げて集まった満員の観客の思いを受け止めるようにすると、滝も
「わけなんてなくて笑っていた
おれたちは今夜無敵なんだ」
というフレーズでステージ前まで出てきてそのフレーズが間違いではないということを証明するかのように観客を煽る。これはかつてのツアーでは見ることが出来なかった姿であり、これがやはり9mmの「BABEL」の完全版なのである。
滝が参加しているということは、かつての「TOUR OF BABEL」では滝以外のメンバーが担っていたパートも今は滝に任せることができるということでもあるのだが、「I.C.R.A.」のコーラスはその最たるものであり、サポートギター2人が担当していたものがようやく本家に返ってきたという感じもある。この曲を演奏しながらコーラスをしていたというところに武田と為川のギターだけならずコーラスの技量の高さも感じることができたわけでもあるけれど。
卓郎が歌詞の一部を「羽田」というこの日の、9mmが初めて立つ会場の名前に変えて客席から曲中に拍手が起こった「ガラスの街のアリス」から、ギターがメロディと轟音で分かれていることによって4本のギターの厚みを実感できる9mmならではのミドルテンポだけども紛れもなくロックバンドによるものである「眠り姫」…世界観を重視していることによってか、卓郎による挨拶的なMCを挟むこともなくアルバムの収録順通りに曲が演奏されていくのだが、やはり卓郎のボーカルは先週の「それとこれとはべつ」のライブで感じたように、間違いなくレベルを増している。それはこうした曲の速さで突っ走るタイプではない曲を聴くとよりわかる。そこには卓郎の声質ならではの色気や奥行きを感じることができる。
メンバーを包み込むくらいの大量のスモークがステージに投入されると、滝が明らかにそれをギターで振り払おうとするという、まさにギターの妖精というような無邪気さを爆音ロックサウンドに乗せる「火の鳥」ではタイトル通りにスモークもろともステージが真っ赤な照明に包まれる。
先ほども書いたように「TOUR OF BABEL」ではそれぞれのメンバーがそれぞれのやり方で滝の不在をカバーしていたのだが、9mm史上最も長いタイトルである「Everyone is fighting on this stage of lonely」ではかつてはタイトルフレーズのコーラスをかみじょうがドラムを叩きながらやるという実に珍しい形で滝のパートをカバーしていたのだが、それも今は滝がいることによってドラムに専念することができる。今もそのかみじょうのコーラスや、和彦が「黒い森の旅人」の曲前の演奏をベースで弾くという、それぞれが自分が出来ることで滝の不在をカバーしていた姿を今も鮮明に覚えているからこそ、こうして滝が参加して「BABEL」の曲を演奏しているのを見ると涙が出てきてしまう。本当に4人が思い描いた形でこのアルバムの曲を演奏できるようになったんだな、と。
そして「BABEL」のタイトル曲でもある「バベルのこどもたち」からさらに物語はシリアスになっていく。滝のコーラスもこれまで以上に強いが、どこかその声からは子供っぽさも感じるトーンの高さになっているのはやはり滝がバベルのこどもたちの中の1人だからだろうか。
「なんにも知らないふたりには戻れない
どれだけ昨日がまぶしく見えても」
という歌い出しから始まる「ホワイトアウト」はかつての「TOUR OF BABEL」では滝がライブに参加していた日々を否が応でも思い出させて涙を禁じえなかった(かつてはこの曲でスモークが大量に投入されていた)曲であるが、そんな曲すらも今はそうした感傷を抱くことなく聴くことができる。1番眩しいのは今この瞬間だからということをわかっているからである。
そして早くも「BABEL」は最終章である「それから」へ。目まぐるしく曲が展開していき、卓郎のおどろおどろしさすら感じる早口ボーカルすらも飛び出す曲であるが、「BABEL」の物語を回想するようなこの曲のサビで楽しそうに腕を上げる観客。滝が戻ってきたことで変わったのはバンドだけじゃなくファンもだ。「TOUR OF BABEL」の時は9mmの象徴的な存在と言える滝がライブに居なくなってしまったことによって、まだ我々がライブにどう向き合えばいいのかわかっていなかった。それは滝が途中でギターを弾けなくなってしまった日比谷野音ワンマンからまだ間もなかったこともあるけれど。
でも今はこの6人編成での「BABEL」のライブをネガティブなことや不安なことを考えることもなく楽しむことが出来ている。バンドも我々も最も変わったのはそこなのかもしれない。だからMCが合間に一切なくても、「BABEL」の曲をライブで聴くのがあの頃よりもずっと楽しかった。
ここでいったんメンバーがステージを去り、15分の休憩へ。それはセットチェンジもあるだろうけれど、場内の換気という理由、そしてここからガラッとライブの内容が変わるということもあるだろう。
実際に15分後に再び場内が暗転すると、今度はおなじみのATARI TEENAGE RIOT「Digital Hardcore」のSEが流れてメンバーが登場。もうSEの段階から爆音過ぎて観客も両腕を上げてメンバーを歓迎しているのだが、そのメンバーも第二部はサポートなしの4人編成で、メンバーの背後にはおなじみのバンドロゴが聳えている。
第二部は残響レコードからリリースしている2枚の作品、「Gjallarhorn」「Phantomime」の再現ライブということであり、1曲目に「(teenage)disaster」のイントロが演奏されただけでそうした内容で進むということがわかるのだが、もう冒頭から滝が広いステージを歩き回り、時にはギターをブンブン振り回しまくるという、初めて9mmを見た時の暴発っぷりがそのまま今の4人で展開されているようだ。
当時、ロッキンオンジャパンが注目の新人バンドとして大々的にページを割いて紹介していたライブレポートでも滝が振り回したギターが卓郎の頭に直撃して流血しながら(しかも卓郎は笑いながら)ライブを続行していたという掲載のされ方だったことを思い出す。今でこそこうしてZeppの広いステージに立っているが、当時の小さいライブハウスでこんなにギターをぶん回していたらそりゃあ卓郎に当たるだろうというくらいに。
再現ライブとは聞いていたが、実際に曲順を収録順そのままにやるとは思っていなかった。というのはインディーズの頃の曲は今ではある程度ライブにおける役割が決まっているからなのであるが、そのライブにおける役割という点ではアンコールなどで演奏するのがおなじみになってきている「talking machine」がアルバム収録曲順通りに早くもここで演奏される。再現ということで、ライブではおなじみの卓郎がマラカスを振ったりというアレンジも全くない、音源のまま。なのですんなりと曲に入り過ぎて逆に戸惑ってしまうくらい。サビに入る寸前には滝と和彦が楽器を抱えて高くジャンプするというおなじみの爆裂っぷりを見せてくれるが、ライブでは定番の曲であってもめちゃくちゃレアいという相反する演奏となった。
特にこの「Gjallarhorn」はまだ音源で聴く分にはバンドの拙さというか、勢いで押し切るという部分も感じられるのだが、特にそれは卓郎のボーカルから感じられるものである。
それが「interseptor」「atmosphere」というあたりの曲を聴くと、その卓郎のボーカルが比べ物にならないくらいに進化し、ただ歌を歌う役目というのではなく、9mmの持つメロディを最大限に伝えるボーカリストになったのだと実感する。それは9mm以外での活動(特にソロなど)で得たものをちゃんとバンドに還元できているということである。
観客が声を出せない状況であっても、卓郎がリズムに合わせて観客を飛び上がらせる仕草をしたり手拍子をしたりという形で楽しませてくれる「beautiful target」もこうしてライブで聴くのは実に久々な感じがする。
それは滝がステージ上で1人でダイブするかのように思いっきり飛びあがってから床に膝立ちになり、うさぎ飛びをしているかのような体制のままでギターを弾く姿や、和彦がベースをぶん投げてステージ上を這いつくばる姿に思わず笑ってしまう「marvelous」も含めて、ワンマンや対バンで20曲以上演奏し、その中に不意にこうした曲をセトリに挟んでくるという9mmのライブらしさを、事前にやる曲を知っている状況であっても思い出させてくれる。
そして「Gjallarhorn」の最後の曲である、轟音サウンドの彼方からメロディが浮かび上がってくるショートチューン「father」の余韻も残る中で卓郎はようやくこの日初めてMCらしい時間を作り、この状況の中でもこうしてライブに来てくれた人たちに改めて感謝を告げる。こんなライブをやってくれるんだからそれは来るだろう、とも思うけれども、チケットがソールドアウトしていても空いている席があったということは、やはり来るのをやめたという選択をした人もいたのだろう。それでも卓郎はこれからも感染対策をしながらライブを続けていく、このツアーを回っていく意志を目の前にいる人たちに告げ、大きく長い拍手に包まれていた。
そして演奏される曲は「Gjallarhorn」から「Phantomime」へ。あのギターのイントロから惑星が激突して崩壊するかのような爆音サウンドに展開していく「Caucasus」もライブで聴くのは本当に久しぶりだし、疲れという概念を持っていないかのように、バンド(特に滝と和彦)の爆裂っぷりはさらに極まっていく。
その爆裂っぷりは「Mr.Suicide」でイントロからさらに極まっていくのだが、自分は「Phantomime」リリース時にこの曲がスペシャで流れたことで9mmに出会った。「なんだこのカッコいいバンドは!?」と衝撃を受けたことを今でも覚えているし、あれから10年以上が経っても9mmはこの曲を演奏していて、あの頃と変わらないやり方のライブをやっていて、今でも心からそのバンドをカッコいいと思えている。それは他のどんなものを探しても思い出の身代わりにはならないのである。
さらに和彦が低い位置のマイクに向かってシャウトしまくるという、和彦が作曲した曲よりも和彦のための曲なんじゃないかと思う、まさに爆音と轟音が渦巻くような「Vortex」は今となってはかなりのレア曲であり、それは初期には珍しい爆音で押すタイプの曲ではない「少年の声」もそうであるが、この曲の持つメロディやリズムが後の9mmの曲の多様性に繋がっていったのかもしれないと思うし、今ライブで聴いても
「海だってただのみずたまりだ いつか乾くのは当たり前さ」
というサビの歌詞をどういう心境で書いたのかということを卓郎に問いただしたくなるくらいに、この曲の歌詞はインディーズ時代の曲の中では異質だと言える。
そんなインディーズ期の再現ライブのラストは高速ビートに合わせて観客の頭が振られまくる「sector」。滝は暴れながらもおなじみの両手を空に挙げるバンザイギターをわずかの時間ながらも披露し、和彦はやはり地面に向かって思いっきりシャウトする。それは今でもライブのラストに演奏される「Punishment」のインディーズ期と言ってもいいような光景であった。メジャーに進出して、いしわたり淳治がプロデューサーに就くことによって卓郎の歌詞などは大きく花ひらいたけれども、9mmというバンドのスタイルはこの時点ですでに完成されていたのかもしれない。今になってから聴くインディーズ期の2枚のアルバムの再現ライブはそんなことを感じさせてくれたのだったが、卓郎と和彦がすんなりステージから去っていったのを見ると、普段あれだけ丁寧に観客に手を振ったり頭を下げたりするのは「Punishment」の轟音の残響が残り続けているからなのかもしれないとも思っていた。
しかし客電が点いてBGMが流れてもまだ観客は帰らない。ライブが終わっていないということを知っているからだ。それはこの日の座席の上に新曲「泡沫」のCDが置かれていたからであり、やはりメンバーはその曲を演奏するために再びステージに登場。
観客に
「楽しんでいただけましたか?」
と卓郎は問うていたが、そこには絶対に楽しんでもらえるはずだという確信があったはずだ。今のバンドのコンディションで「BABEL」とインディーズ期のアルバムを演奏する。声が出せなかったりという制限はあるけれど、このライブに満足しないわけがないのである。
そして昨年は開催できなかった9月9日の9mmの日にZepp Yokohamaで為川裕也がギターを務めるfolcaを迎えるという、去年と同じ内容の、明確にリベンジを期したライブを開催することを発表すると、サポートギターに武田を加えた形で新曲「泡沫」を披露する。
すでに幻想的な映像のMVも公開されているが、青い照明に包まれる中で、ギターは轟音ではあるけれどスッと耳に入ってくるという意味では「黒い森の旅人」に近い感触もあり、9mmらしい歌謡性のメロディと融合した、9mmだからこその新しい名曲。
「Phantomime」がリリースされて、自分が9mmに出会ってからもう15年も経つ。そう考えるとビックリするくらいに長い時間が経っているけれど、今でもこうして9mmのライブに来ているのは、こうした新しく世に出る曲たちが今でも本当にカッコいいと思えたり、良い曲だと思えるから。特にこの「泡沫」はこうして振り返る意味合いもあるツアーで配布される新曲ということでメンバーも強い自信と確信があると思われる。それはライブが終わった後のメンバー(特にスティックを客席に投げ込んだかみじょう)の表情からも強く感じた。
10年以上バンドをやっていると無傷ではいられないと言っていたのは、9mmと同じ時代を駆け抜けていたDOPING PANDAのフルカワユタカであるが、まさしく9mmも無傷ではいられなかったし、「BABEL」期はまさに傷を負っていた時期であった。
それでもその傷を再生させ、そうした経験をしたことで9mmはさらに強くなった。インディーズ時代の曲を演奏している姿を見て思ったのは、そうした経験を重ねたり年齢を重ねても落ち着いた曲やライブに転換していくのではなく、あの頃と全く変わらない爆裂っぷりで、ひたすらに150kmを超えるストレート(でも9mmならではの変な回転がかかっている)をバンバン投げ込んでいる。その姿を見ていたら、それはこれから先何年、何十年経っても9mmであり続ける限りは全く変わることがないんじゃないかと思った。
「泡沫」のサビは
「どこまでも沈めてくれ」
というフレーズで始まる。何かにハマることを最近「沼に沈む」と聞くようになった。もう我々はとっくに9mmというバンドの沼に沈んでいるけれど、これから先も、どこまでも沈めてくれ。
第一部
1.ロング・グッドバイ
2.Story of Glory
3.I.C.R.A
4.ガラスの街のアリス
5.眠り姫
6.火の鳥
7.Everyone is fighting on this stage of lonely
8.バベルのこどもたち
9.ホワイトアウト
10.それから
第二部
1.(teenage)disaster
2.talking machine
3.interseptor
4.atmosphere
5.beautiful target
6.marvelous
7.father
8.Caucasus
9.Mr.Suicide
10.Vortex
11.少年の声
12.sector
encore
13.泡沫
文 ソノダマン