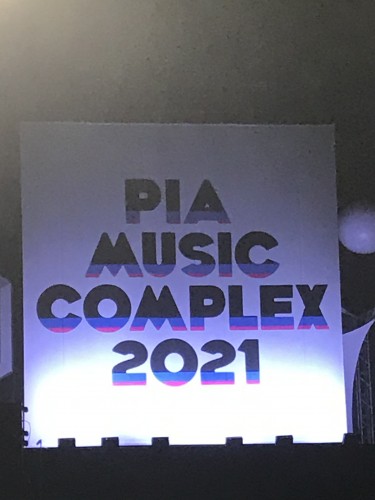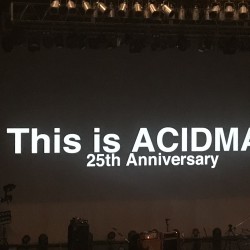チケットぴあが主催するフェス、ぴあフェスことPIA MUSIC COMPLEXが今年は帰ってきた。かつては新木場の若洲公園で開催され、数々のカオスな出演者などでも語り草になっているが、その際の終演後に
「ぴあは横浜に新しいアリーナを作ります」
と言っていた、ぴあアリーナMMでの初開催。すでに何回も来ている会場であるし、様々なライブが行われているけれど、ようやく然るべき場所で開催される日が来たというか。
入場前には接触確認アプリのダウンロード確認、検温と消毒も行ってから中に入ると、アリーナも含めて全席椅子有りの指定席という形。そもそもは最前エリアは抽選制のスタンディングを検討していたようだが、ご時世的なものもあってか、この形に。
開演前には「そういえばトリオになってたんだな」と思うお笑い芸人、ビックスモールンが登場して、全く喋らずにその体を使った芸風で注意事項をアナウンスするという斬新なオープニング。それは「声を出さないように」というフェス側からのメッセージだったのかもしれない。
11:00〜 Creepy Nuts [CONNECT STAGE]
ステージは上手側のBRIDGE STAGEと下手側のCONNECT STAGEが隣り合っているのだが、CONNECT STAGEのトップバッターにして、この日のトップバッターはCreepy Nuts。
DJ卓のみというステージにいつも通りの真っ黒な服を着たR-指定とDJ松永が登場すると、流れ出した音に合わせて早くも手拍子が起き、
「手拍子ありがとうございます!」
とR-指定が暖かく迎え入れてくれた観客のノリを確かめるように
「まずは今日の空気 今日の観客」
と「板の上の魔物」をラップし始めるのだが、この段階ですでに完全にこの日の観客、この日の空気を掴んでいたというくらいに観客の腕が上がるホーム感。
それは
「俺はこの時間まで寝ないでずっと起きてるから逆にテンション上がってる!」
という「よふかしのうた」でのR-指定の高速ラップとアウトロでの松永のターンテーブルのスクラッチがさらに観客をアゲまくっていくのだが、そこへさらに
「今日は声は出せませんが、飛んだり跳ねたり腕を上げたりするのは合法となっております!」
と「合法的トビ方ノススメ」でRはステージを左右に動きながらラップすると、観客は待ってましたとばかりに飛び跳ねまくる。
松永「俺が客だったら、朝11時から飛び跳ねさせられてたら、朝から何さしてくれてんねんって思う(笑)
R-指定「ラジオ体操とかみたいな感じじゃない?」
松永「帰りにみんなにスタンプ押しますんで(笑)」
という言葉通りに、11時というクラブ育ちの2人からしたら「早朝」に属する時間帯にも関わらずこうして集まって、飛び跳ねてくれている観客たちにラジオで鍛えたトーク力を駆使したMCで感謝を告げると、こうして100%(コロナ禍になる前に比べたら)ではないこのフェスの今の状態も、これから先の伸び代であるという、思わず唸らされるような繋ぎから最新アルバム「Case」収録の「のびしろ」、さらにはタイトル通りにオレンジ色の照明がまだ朝なのに夕焼けのように美しくかつ切なく2人を照らす「Bad Orangez」という流れはちょうど1週間前にZepp Hanedaで見た、THE SOLAR BUDOKANでのセトリと全く同じ流れであるだけに、「やはり忙しいだろうから同じくらいの持ち時間だとセトリを変える余裕もなくなるのだろうか」と思っていたのだが、Rが痛風を発症し、コーラやエナジードリンクを飲まないで、水を2リットル飲むようにしているというネタで、
R「田中みな実も毎日2リットル水飲んでるらしいから」
松永「じゃあ田中みな実も痛風ってこと!?(笑)」
と笑わせたMCの後に、先週はやっていなかった「サントラ」を入れてくるという変化をつけるというあたりはさすがだな、とも思うし、ノイジーなギターサウンドをはじめとしたバンドサウンドの曲をロックフェスでやるというあたりに2人のこうした場所での戦い方がわかる。何よりもこの曲でのRのラップというよりボーカルと言っていい歌唱が素晴らしい。ただ有名になって大きなステージに立てるようになっただけではなく、それぞれにMCとDJでNo.1のスキルを持つ2人が、それ以外の部分を今も伸ばすために努力し続けているということも本当によくわかる。
その後に「かつて天才だった俺たちへ」を全ての観客に捧げたのだが、かつてではなくこの2人は今もずっと天才であり続けているし、その陰には常人が知る由もない努力があるんだろうなと思った。そして演奏後にしっかりと客席に向かって深々と頭を下げるという謙虚さをなくすことがないことも。
コロナ禍になる前からCreepy Nutsはこうしたロックフェスに精力的に出演していたが、その頃はまだヒップホップシーンからの武者修行的なイメージも強かったし、実際にアウェー感を少しでも覆すためにRの「聖徳太子スタイル」というフリースタイルのスキルを見せつけるという、一発で凄さがわかるようなこともやったりしていたのだが、もうそうしたことをやる必要がないくらいにロックフェスは2人にとってホームと言える場所になった。それはアウェーだった頃から挑み続けてきたのをたくさんの人が見てきたからこそ、暖かく迎え入れてくれる空気が出来上がったのだ。
1.板の上の魔物
2.よふかしのうた
3.合法的トビ方ノススメ
4.のびしろ
5.Bad Orangez
6.サントラ
7.かつて天才だった俺たちへ
11:50〜 秋山黄色 [BRIDGE STAGE]
上手側のステージであるBRIDGE STAGEのトップバッターは、もちろんこのフェス、この会場に初出演となる、秋山黄色である。リハで「アイデンティティ」を1コーラス演奏したことによって、「この曲、本編でやらないつもりだろうか…?」と、アウェーな空気を覆すことができる力を持っている曲だけにリハのみだったら、と少し不安にもなったが、そんなリハの演奏を終えた秋山黄色はいったんステージから捌ける際に何やら奇声じみたものを発していた。
そんな思いも抱えながらも本編になると、SEもなしに秋山黄色が暗闇の中でひっそりとステージに登場してきたであろうことが、白いロンTを着た男がステージ中央に見えたことでわかる。そのままギターを持って幽玄なサウンドを鳴らしている間に片山タカズミ(ドラム)、辻怜次(ベース)、井手上誠(ギター)という、今年の夏からお馴染みのメンバーたちが続いてステージに登場し、秋山黄色は「モノローグ」を歌い始めるというあたりが、またライブのモードが少し変わったことを感じさせる。
しかしながら変わったのはライブモードだけではなく、やはり心境もそうなんだろうなとも思う。元からこの曲はライブでは原曲のバラードと言ってもいいようなイメージを自らぶっ壊しに行くかのように思いっきり叫ぶようにして歌っているのだが(CDTV ライブ!ライブ!に出演した時のように)、それがさらに衝動を増している。それはこの期間に自身が出るはずだったフェスがなくなってしまったり、というような要素も少なからずあったんだろうと思う。ましてや彼の地元凱旋と言えるような、ベリテンライブもなくなってしまったのだから。
片山の正確無比なリズムの一方で、井手上のギターは原曲のクールなイメージをこれまた覆すようなラウドなものとなり、辻も激しく体を揺さぶったり、飛び跳ねながらベースを弾くという、バンドメンバーの存在によってモンスターのような巨大な音の塊へと変貌した「Caffeine」はこうしたアリーナクラスの会場でこそ真価を発揮するようになったと言えるかもしれない。
それは今年リリースされたアルバム「FIZZY POP SYNDROME」のリード曲である「月と太陽だけ」にも通じるところであるが、今の秋山黄色は全ての自身の曲をこれ以上ないくらいに衝動的に鳴らし、変化させている。それはそのままこれ以上ないくらいにロックであるということである。
「みんなもそうだと思うけど、すごい何周も何周もグルグルと考えが巡っていて。ライブはやります。やらないと生きていけないから。明日になったらまたやっぱりやりませんって変わってるかもしれないけど(笑)」
と、コロナ禍における自身の活動の答えを見出したようでいて、まだ迷ってもいるというあたりに秋山黄色の人間らしさを強く感じるのだが、生きていけないというのは経済的にというのではなくて精神的にということだろう。それは我々と全く同じ視点であり、きっとステージに立つようになっていなかったとしても、秋山黄色はそうした考えに至っていたはずだ。このステージに立つべくして立っている人間だとも思っているが。
そんな中でライブでついに聴けるとファンが皆喜んだのは先月リリースされたばかりの新曲「ナイトダンサー」だろう。音源ではピアノの音がかなり強めに入っていたが、この4人の編成でのライブだとその音がないことによって、ストレートなロックさが際立つアレンジになっている。
この曲はボートレースのCMソングであるのだが、埼玉県某所や都内某所のボートレース場に近しい場所が生活圏になってきた身からすると、この世の掃き溜めというような、真っ昼間からワンカップを飲んでるおっさんたちの溜まり場的な場所のCMソングがこんなに爽やかでいいのかとも思ってしまうのだが、
「「才能」なんて言葉を口にしそうな時は
決まって諦める支度をしている」
「天才の内訳は99%努力と
多分残りの1%も努力だ」
というフレーズはボートレーサーを目指す若者たちへのテーマを、秋山黄色独自の語彙力で見事に歌詞にしている。それはもしかしたら音楽を志す上で自身に問いかけてきたものなのかもしれない。
リハでやったために本編ではやらないんじゃないかとも思っていた「アイデンティティ」も辻によるゴリゴリのベースのイントロによってフルに演奏されるのだが、やはりアニメ「約束のネバーランド」のオープニングテーマになったというのは、この曲で秋山黄色に出会った人や、ライブでこの曲が聴きたいと思っている人もたくさんいるんだなということがよくわかる。
それにしてもエフェクトも噛ませているとはいえ、秋山黄色の歌唱力、声の飛び方は本当に凄まじいものがある。初めて渋谷O-Crestでライブを見た時から「近い将来にアリーナとかで見れるんだろうな」と思っていたのがこうして現実になっているわけだが、それをライブのクオリティ、自身の能力や技術をしっかり向上させて実現している。曲という意味では当時からこの規模で鳴らされるべきスケールを持っていたけれど。
そんなスケールを当時から持っていた曲の代表格と言える「やさぐれカイドー」ではイントロの時点から秋山黄色が自身のマイクスタンドの前、つまりステージの最先端と言えるような部分に寝転がってギターを弾くという、毎回落ちて怪我をしたりしないか不安になるような衝動的なパフォーマンスを見せるのだが、この日はさすがにトーキンロックフェスの時のように客席の前を走り回るようなことはできず、ステージ上でメンバー紹介も兼ねたソロ回しもして、井手上と辻が至近距離で向かい合って音を鳴らすという、秋山黄色のバンドに参加する前からそれぞれのファンだった身としてはたまらない一幕であり、名義こそソロであるが、本当にこの4人でのバンドになったんだな、と感慨深くなるシーンも見せると、秋山黄色は最後のサビに突入する前に、
「本当に申し訳ない。みんなにばかりルール守って我慢させてしまっている。なんならこの歳まで無職でニートで親にも申し訳ない。申し訳ないことばかりだ。
お酒を飲みに行ったり、みんなでご飯食べに行ってる人もいると思う。それも個人の自由だけど、ないと生きていけないものがある。申し訳ない気持ちでいっぱいだけど、今日だけはその思いを爆発させていい日だ!楽しんでいい日だ!いろいろ言われたり、後ろめたい気持ちになったりすることもあるだろうけど、チケット買ったり、グッズ買ったことない奴に何がわかるってんだ!」
と、自身の抱える思いであり、我々の抱える思いを全て言語化して吐き出してくれる。その後の言葉は昂り過ぎて何を言っているのかわからない感じすらあったが、
「今日が初めて俺のことを見る人もたくさんいると思う。気になったら検索してくれ。たった漢字4文字、俺が噂の秋山黄色だー!」
と誰しもの脳裏にその名前、その声、その感情を刻みつけてから最後のサビに突入すると、Benthamでは「コーラスが苦手」と言っている辻すらもサビで井手上と共に声を重ねながら、秋山黄色はアウトロではマイクスタンドをぶっ倒しながらステージに倒れ込んでギターを弾きまくる。その姿は完全に音楽がないと生きていけない人間の究極系と言えるものだった。
起き上がって4人で何連発もキメを打ちまくると、
「今見たことを即座にSNSに書くように」
と言ってステージを去った。その瞬間の照明が黄色だったのは、このフェスからの秋山黄色への愛と感謝としか思えなかった。
夏からこんなに状況が悪化しなければ、きっともっといろんな場所で何回も秋山黄色のライブが見れていたはずだし、本人ももっとたくさんライブができると思っていたはずだ。でもこれから先や来年以降はきっとそうなる。こうした、広い会場での出演者の数が多くはないフェスにだって秋山黄色の名前を何回も見つけることができるはず。そしてその頃にはこうしたアリーナでもっとたくさんの曲を聴けるワンマンが見れる。その未来に用がある。
リハ.アイデンティティ
1.モノローグ
2.Caffeine
3.月と太陽だけ
4.ナイトダンサー
5.アイデンティティ
6.やさぐれカイドー
12:40〜 打首獄門同好会 [CONNECT STAGE]
アリーナならでの広いステージにはもちろんVJとスクリーンも用意されているのだが、ドラムセットの横にはまるで裁判の傍聴席かのような「静養中」という紙が貼られたテーブルも置かれている。世の中の状況も日々変化しているが、打首獄門同好会のバンドの状況も変化している。
なのでドラムの河本あす香はその静養中の席に座るという、ライブが出来なくても欠席になることはないというこのバンドの活動スタイルが見えるのだが、この日のサポートドラマーは意外にもthe telephonesの松本誠治。ただでさえtelephonesの活動もあり、DJなんかもやりながらさらにはまぜそば屋の店主として大宮の店にも出勤しているというのにこうしてサポートを務めるというバイタリティは凄まじいものがある。
着物姿が実にビシッと決まっている大澤会長が歌い始めたのはこの状況をそのまま歌うかのような「新型コロナウイルスが憎い」であるが、歌詞に「ぴあアリーナ」と入れると、スクリーンにもしっかりとこの会場の外観が映るという完璧なこのフェス仕様で始まり、それは「足の筋肉の衰えヤバイ」にも適用されるのだが、可愛いと言っていいやらなんやらという感じのアニメーションVJ(しっかりステージ左右の巨大スクリーンにも映し出されている)に見入ってしまって、なかなかステージ上のメンバーの演奏している姿と交互に見るのは視点が忙しい。
それは会長が直々にジムに行って体を鍛えている姿が映し出される「筋肉マイフレンド」もそうなのであるが、この曲では間奏でスクワットを観客含めて全員で行うというセクションがあり、椅子と自分のスペースがあるから満員のライブハウスよりもやりやすいとはいえ、アリーナ規模で4階席の人までが一斉にライブ中にスクワットをしているという構図はもはや宗教染みている感じすらするし、後々にこの日の序盤でスクワットをしたことが後半に疲れとして現れてきたという人もいるかもしれない。
すると会長は
「明日は月曜日であり、しかも今月は祝日がない。本来ならば体育の日があったのが、オリンピックに合わせて移動させられたから。ちなみに体育の日かスポーツの日かという論争もありますが、そこは岡崎体育に任せたいと思います(笑)」
と、何故か楽しいフェスの序盤にテンションが下がることを言うのだが、それは次に演奏された曲が翌日の労働意欲をさらに削ぎ取っていく「はたらきたくない」だったからである。
この曲あたりからわかってきたのは、ベースのjunkoはもちろんのこと、静養中席にいる河本もそこからボーカルとして曲に参加しているということである。演奏が出来なくても声だけで参加するというのは全員がボーカルを務めるこのバンドだからであるし、歌っている姿を見れることで安心する人もたくさんいるはずだ。そして誠治のドラムも意外なほどに違和感がない。彼の演奏技術の高さ、依頼してくれたバンドへの寄り添い方や想いへの応え方が実によくわかる。
しまじろうのアニメのテーマ曲になったことにより、演奏中にもフテネコなども混ざってアニメーションにしまじろうがカンガルーを探すという実にシュールかつ可愛らしい映像が流れる「カンガルーはどこに行ったのか」で、ラウドなサウンドでありながらもお茶の間や子供にまで浸透しているこのバンドのコミカルさを示すと、家系ラーメンの本拠地と言えるこの横浜においても「私を二郎に連れてって」で、ついつい二郎系ラーメンが食べたくなってしまう。翌日が月曜日だというのに、曲通りにトッピングを全マシにして。
「カンガルーはどこに行ったのか」も含めて、最近はタイアップの話を貰うことが多く、「極・夫婦街道」の主題歌である「シュフノミチ」もやはりアニメーションのVJ付きで演奏されるのだが、
「Netflixって便利ですよね。同じアニメを連続で観てると、オープニングとエンディングを自動で飛ばしてくれるんです。だからNetflixでアニメを観てると、主題歌なのにあんまりこの曲を聴く機会がない(笑)」
というついつい笑ってしまう話を次々に繰り出してくる会長の話術も実に巧みであるが、終盤に来て「きのこたけのこ戦争」(毎回ライブで見るとファミコンのゲームをやりたくなる)、ラーメンから寿司や刺身に食べたいものをスイッチさせる「島国DNA」という代表曲を連発するあたりのライブの運び方も実に巧みである。最新の曲もやりながらも、ちゃんとこうしてみんなが聴きたい曲もやってくれるというサービス精神の賜物である。
しかしながら会長は少しシリアスな口調で、
「このぴあアリーナでライブをやるのは今日が初めてですが、この会場には因縁がありまして。バンドの15周年ツアーのファイナルとして1月にここでワンマンをやる予定だったのが延期になりました。その振替公演として5月にやる予定だったのもやはり中止になりました。そして今日。ここに立てていますが、満足はしていません。やっぱりここでツアーファイナルをやりたい。会場が取れればですが(笑)」
というこの会場への想いを語る。確かにツイッターなどでもここでのワンマンが出来なくなった無念さを度々発信していたが、コミカルさの中に潜むそんな熱さが、観客が声を出せない代わりにメンバーがこれでもかというくらいに歌う「日本の米は世界一」に集約されていき、やっぱり牛丼が食べたいかもしれない、と思いながらも、客席では一足どころかかなり早くレキシの物販で売られている光る稲穂が、まるでこの曲のためのグッズであるかのように光り輝いていたのだった。
10曲も本編で曲をやり、さらにはMCも度々挟んだにも関わらず、全く時間が押すことがない。去り際にバンドのタオルを広げてからステージを去っていった会長が1番恐ろしいのはそのマネジメント能力かもしれない、と思っていた。
リハ.私を二郎に連れてって
1.新型コロナウイルスが憎い
2.足の筋肉の衰えヤバい
3.筋肉マイフレンド
4.はたらきたくない
5.カンガルーはどこに行ったのか
6.私を二郎に連れてって
7.シュフノミチ
8.きのこたけのこ戦争
9.島国DNA
10.日本の米は世界一
13:30〜 Saucy Dog [BRIDGE STAGE]
こうしてアリーナのステージに立つ機会も多くなってきたのは、やはり武道館でワンマンをやったバンドになったからであろう。Saucy Dogがこうした規模のフェスに名を連ねることに全く違和感を感じなくなってきた。
いつものようにせとゆいか(ドラム)、秋澤和貴(ベース)、石原慎也(ボーカル&ギター)が順番に登場してそれぞれ観客に一礼してから3人が集まって気合いを入れるようにすると、石原の声が真っ直ぐに響く「煙」からスタートし、まるで二郎系トッピング全マシのような過剰さの打首の次という順番もあって、このバンドの歌を軸にしたシンプルなスリーピースサウンドが淡麗系塩ラーメンのようにスッキリとした喉越しに感じられるが、こうしたバラードと言っていいような曲でフェスの1曲目を始められる若手バンドというのは実に稀有な存在だと思う。
「盛り上がっていこう!」
という「雀ノ欠伸」からは秋澤とせとのリズムも一気に疾走感を感じさせるが、何よりも石原のボーカルが歌詞の一字一句を全てはっきりと聞き取れるくらいにアリーナの全方位にまでクリアに響いている。音響の良さもあるだろうけれど、やはり武道館でのライブを経験したことによって自分の歌の力、飛ばし方をさらにしっかりと理解できるようになった感じがする。
「ナイトクロージング」では間奏で石原がステージ上手側のスクリーンの下まで行ってギターソロを弾くのだが、その際に自分がギターを弾く姿が映るスクリーンの方を振り返るというのが実に石原らしいあざとさを感じるのだが、当然ながら振り返るとスクリーンには後ろ姿しか映らないというのもまた面白い。
せとの挨拶的なMCの後には、リリースされたばかりのミニアルバム「レイジーサンデー」から「シンデレラボーイ」も演奏されるのだが、この曲の歌詞が実になんというか、一切共感できない類の男女のラブソング的なものであるのだが、そうした曲すらもポップという言葉で包み込んでしまえる石原のボーカルがより際立つ。というかライブで聴くとそうした歌詞もどこか美しくすら感じてしまう。
そこから失われた今年の夏を思い返しながら、来年は海に行けるようになっていたらいいなと想いを馳せざるを得ない情景が脳内に浮かぶ「シーグラス」、たくさんの観客の腕が上がる「ゴーストバスター」と、ギター、ベース、ドラムというシンプル極まりない3人の音がさらにアッパーに変化していく。秋澤のベースも自身の体の動きと連動して音がダイナミックにうねっている。
今も絶賛ホールツアー中ということで、なかなか各地で打ち上げしたりはできないだろうけれど、メンバーやスタッフで車に乗って街から街へ移動していく、そんなツアーの風景が目に浮かぶ「バンドワゴンに乗って」の後にやはりそのツアーの告知をし、ファイナルにはこの会場ほどではないが、都内屈指の規模の会場であるガーデンシアターでのワンマンという大きな挑戦が待っていることを告知し、先ほどのギターソロの際にやはり自分がスクリーンに映っている姿が気になっていたことを明かすと、おそらくそのガーデンシアターでもライブのハイライトになるであろう、「レイジーサンデー」収録の「東京」を最後に演奏する。
これまでに数々のアーティストたちがテーマにして名曲として残ってきた「東京」。東京出身ではない、音楽をやるために東京にやってきた石原の描くSaucy Dogの「東京」は
「東京。
大丈夫僕は。上手くやれているよ
諦めることにも麻痺してきたから
はじめて正しい事ばかりが
正義じゃないのが分かってきたんだ」
という自分自身に向けて言い聞かせるような、飲み込まれてしまいそうにもなるであろう東京だ。それはどこか東京に来て、いろんな経験をしたことによって大人になったことも感じさせるような、また新たな「東京」という名曲がロックシーンに誕生したことを示していた。キメとかも一切なく、潔く音が止まると去り際に深々と長くお辞儀をするメンバーの姿がこのアリーナにふさわしい歌を持った、逞しいバンドであるように映っていた。
リハ.メトロノウム
リハ.リスポーン
1.煙
2.雀ノ欠伸
3.ナイトクロージング
4.シンデレラボーイ
5.シーグラス
6.ゴーストバスター
7.バンドワゴンに乗って
8.東京
14:20〜 THE ORAL CIGARETTES [CONNECT STAGE]
ここ最近は様々なフェスでトリも務めている、THE ORAL CIGARETTES。この日はこの後に先輩も多く控えているからか、中盤での登場。
SEが鳴るとメンバーが1人ずつ登場し、最後にスマートという言葉が良く似合う山中拓也(ボーカル&ギター)が登場すると、おなじみの
「1本打って!」
から始まる前口上は
「ぴあフェスはじめまして、よろしくの回」
という初出演だからこそのものだったのだが、だいたいフェスだとこの口上の後にアッパーな曲で火をつけるという流れになりがちなところで、山中はギターを持たずにハンドマイク。そうして始まったのは、女性コーラスの音が流れ、鈴木重伸のギターも、あきらかにあきら(ベース)と中西雅哉(ドラム)のリズムも緻密な構築感を感じさせ、その上に乗る山中の声の艶を1曲目から存分に感じられる「エンドロール」という予想だにしないオープニング。シングル曲でもないし、最新アルバムの曲でもない、しかも始まりが「エンドロール」というのはこうしたフェスやイベントのライブの1本1本を決してマンネリなものにせずに、その日その場だけの記憶にしてもらいたいというバンド側の意志であるように感じる。
しかしながらそのあとはそのまま山中がハンドマイクで観客を煽りまくりながらも、やはり観客は声を出せないということで、山中以外の3人が思いっきりコーラスをする「狂乱Hey Kids!!」で文字通り暴れたいキッズの気持ちを昇華しながらも、最後のサビ前では鈴木とあきらが凄まじい跳躍力のジャンプを見せるという、1番暴れているのは紛れもなくメンバーであるという姿を見せてくれる。
それは中西の刻むビートの上に乗る微かな鈴木のギターフレーズによる曲と曲の繋ぎがこの曲に突入するためのものであることがわかる「Mr.ファントム」もそうであり、山中はこの日初めてギターを持って歌い、中西の「オイ!オイ!」という煽りに観客は声は出せないまでも腕を振り上げる。そしてやはり最後のサビ前で鈴木とあきらは高くジャンプする。その姿はまだインディーズの頃に初めてこのバンドのライブを見た時と変わらないロックバンドのカッコ良さを今も示してくれている。
そんなこの日はアーティストの物販の列が「オーラル」と「オーラル以外」に分かれており(前日はホルモンとホルモン以外だった)、ツイッターのトレンドに「オーラル以外」という単語が入ったことにより、山中は朝ツイッターを開いて目に入ってきたそれを
「ついにハブられたのかと思った(笑)」
と驚きながらも笑いに変えてみせる。結果的にその物販も盛況だったようだ。
そんな山中は今この状況になったことによって、
「フェスだからやるっていう曲よりも、今やるべきメッセージを持った曲を」
と、フェスにおけるセトリに変化をもたらしていることを明かす。
その言葉の後に演奏されたのが、全くフェスではやるイメージがない「透明な雨宿り」だったということが象徴的であるが、
「生きる全てを無くした雨は
私の心に針を刺して
きつく全てを抱き寄せあなた
透明な傘を差し私のこと見守るの」
という歌詞こそ、人と人が言葉で刺し合うような今の状況で歌いたかった、歌うべきだと思ったものなんじゃないかと思う。それはメジャーデビューアルバム「The BKW Show!!」の最後に収録されていた、もうリリースから7年も経つこの曲が、今の状況において、そしてこれから先も普遍的なメッセージを持ち続けるということである。
再び山中がハンドマイクになると、鈴木の挑発的とも言えるギターサウンドに導かれるように始まった「容姿端麗な嘘」で自身も飛び跳ねながら観客を飛び跳ねさせまくり、ステージを自由に動きながら、コーラス部分ではあきらと肩を組むようにして歌ったりする。このどれだけ巨大な存在になってもメンバーの関係性が全く変わらずに見えるというのも凄いと思うし、それもきっとこの先も変わらないものなのだろう。
そして山中は観客に、
「ロックシーンに力を貸してください!」
と告げた。一時期はむしろロックシーンから抜け出そうとするような、ロックバンド以外のカルチャーから影響を受けて自分たちの活動を進めていこうとしていたこのバンドが、この世の中の状況であったり、テレビの音楽番組でロックが聴かれていないことが可視化されたりしている状況の中で、今一度ロックシーンに火を灯すという意識を持つようになった。
そんな自身のロックバンドとしての代名詞とも言えるような「BLACK MEMORY」はやはり観客が歌えないことによって、メンバーのコーラスが実に強くなっているように感じられるのだが、そのロックバンドとしてのオーラルの最新系が、タイトル通りに真っ赤な照明に照らされながら、イントロで山中がギターをグルっとぶん回すという、ロックバンドでしかないパフォーマンスを見せるくらいにロックバンドに回帰したことがわかる「Red Criminal」。火を噴くかのような鈴木のギターリフも含めて、これはオーラルの、ロックバンドの逆襲の号砲である。
クールに映るようなアー写などもこれまでに数々作ってきたバンドであるが、ライブが終わる頃には4人全員が滴り落ちるくらいに汗に塗れている。その熱さこそが、オーラルがロックバンドであることの証明であり、今一度ロックバンドがロックバンドとしてのカッコよさを持ったままでシーンを塗り替えていく。それを牽引していくのがこのバンドだ。
1.エンドロール
2.狂乱Hey Kids!!
3.Mr.ファントム
4.透明な雨宿り
5.容姿端麗な嘘
6.BLACK MEMORY
7.Red Criminal
ここで会場は換気タイムに。そもそもこの会場は常時換気がなされており、だからこそ去年のBAYCAMPが行われた際には寒さすら感じたくらいだったのだが、扉も完全に開放された中でステージに出てきたのは、オープニングでも登場して注意喚起を行ったお笑い芸人のビックスモールン。ここではネタを存分に披露するのだが、3人になったからこそできるネタもあり、もはやベテランの域に入っているのにチロとゴンの身体能力にも全く衰えはない。昔、オンエアバトルに出ていた頃に「面白いというより凄い」と言われていたことを思い出した。
15:30〜 BLUE ENCOUNT [BRIDGE STAGE]
とかくONAKAMAを形成しているTHE ORAL CIGARETTESと同じ日になるとオーラルに重要な位置を持っていかれがちだったBLUE ENCOUNTであるが、この日は換気タイムを挟みはしたものの、オーラルの次という順番。この繋がりもこのフェスの各バンドへの理解を感じさせる。
おなじみのSEで4人が元気良くステージに登場してくるという図もこれまでとは変わらないけれど、しかしながら田邊駿一(ボーカル&ギター)の
「はじまるよー!」
という威勢の良い挨拶の後に始まったのはダンスミュージックの要素を吸収しながらもブルエンの曲でしかないというエモーションも確かに感じさせる「バッドパラドックス」。ライブではおなじみになっている曲であるが、オーラル同様に1曲目からアッパーな曲でぶち上げる、というわけではないというあたりにこの世代のバンドが自分たちの新たなフェスの闘い方を見つけようとしている気がする。田邊のサビのファルセットボーカルもそのダンスというこの曲の要素を増幅させるものになっている。
かと思えばシーン出現時に「エモロックバンド」と評されてきた(自分が「BAND OF DESTINATION」リリース時に初めてライブを見た時もそういう印象だった)ブルエンらしさを発揮するような「HALO」で辻村勇太(ベース)、高村佳秀(ドラム)のリズムもパンクかラウドバンドかというくらいに力強さを発揮する。
さらに意外だったのは江口雄也によるギターがブルエンの曲とは思えないくらいに「オシャレ」というイメージを想起させる「coffee, sugar, instant love」がここで演奏されたことである。確かにブルエンはフェスやイベントでも軸となる曲は残しながらもそれ以外の曲をかなり変えてくるバンドであるが、このタイミングでこの曲を演奏するとは。オシャレさを感じさせながらも、やはり通して聴くとブルエンだな、と思えるのは完全にそうした音楽に染まるのではなく、あくまで自分たちの音楽に加えるという取り入れ方をしているからだろう。日常の風景を描いた歌詞も新鮮でありながら、どこかこの横浜という場所が似合っているような感じもする。
ぴあフェスにはこうして毎回出演しているが、中止になった去年を除けば毎回野外で開催されてきたために、こうしてぴあアリーナのステージに立っているのが不思議な感じであると口にしながらも、
「アリーナだからどうとか言うんじゃなくて、あなたに歌います」
と自分たちの伝え方がブレないことも口にして、そのまま「もっと光を」を歌い始める。かつてのようにただひたすら熱く強く歌うというよりは、どこか抑揚をしっかりつけて歌うようになっている感じもするが、今の状況で聴くこの曲は本当にそのまま聴き手1人1人の光になっているかのような強い輝きを放っている。辻村が「オイ!オイ!」と声が出せないのがわかっていても観客を煽るのも含めて。
そしてこの日は曲に合わせたコラボドリンク(実に飲む気が湧かない色をしていた)が出されていたのは最新曲の「囮囚」。この漢字で「バケモノ」と読ませるというのも面白いが、
「今度こそ その哀の真犯人を
一思いに葬れ」
というフレーズの通りに、もしかしたらそれはこの曲が主題歌になっているドラマの内容も含んだものなのかもしれない。「バッドパラドックス」に続いての主題歌起用であるが、こちらの曲は実にブルエンらしい曲と言えるものになっているのもまた面白い。
そのブルエンらしさは江口のタッピングが唸りを上げまくる、タイトル通りにバチバチにそれぞれの音がぶつかり合う「VS」、さらには田邊が
「音楽を信じるあなたを信じる」
という言葉を曲中に入れて歌った「DAY × DAY」と、そのブルエンらしさというエモーショナルさがフルに発揮され、それがそのまま言葉だけではなくしっかりと音楽そのものになっている。
だからこそ田邊は最後に
「あなたが幸せになりますように、なんてデカいことは言わない。ただあなたの前に幸せがやってきた時に、それを幸せだってちゃんと思えるように」
と言って「ハミングバード」を演奏した。数々のライブの最後にふさわしい名曲を持つブルエンがこの日の最後に選んだこの曲は
「間違っちゃいないから
今日 乗りきった一歩は
燦然と輝く足音なんだ
間違っちゃいないから
夢中で飛び込んだ世界は正解だ」
と歌われる。こうしてこの状況下の中でもこの場所に飛び込んだことは間違っていないと肯定してくれているようであるし、この曲を演奏している時に確かに幸せだと感じていた。
この状況になって、田邊はもっと迷ったり悩んだりするんだろうなと思っていた。この状況になる前からずっと迷ったり悩んだりしてきたから。でも今のブルエンには全くそうした迷いも悩みも感じられない。むしろ、俺たちが迷っていてどうするんだ!というくらいに、迷ったり悩んだりしてしまう我々の選択を肯定してくれるかのような頼もしさを感じる。もしかしたらこの状況はブルエンというバンドを一回りどころか何周も強くしたんじゃないだろうか。
リハ.棘
リハ.ロストジンクス
1.バッドパラドックス
2.HALO
3.coffee, sugar, instant love
4.もっと光を
5.囮囚
6.VS
7.DAY × DAY
8.ハミングバード
16:20〜 クリープハイプ [CONNECT STAGE]
サウンドチェックにメンバー全員で出てきたクリープハイプは真っ暗な中で「寝癖」を演奏して観客から大きな拍手を送られていた。夏にはなくなってしまったフェスへの思いを自分たちらしい言葉で口にしていたが、こうして夏を越えてもフェスのステージに立つクリープハイプが見れるのである。
いつものようにSEもなしにメンバー4人がステージに出てくると、小川幸慈のギターが不穏な空気を醸し出す「キケンナアソビ」から始まり、尾崎世界観(ボーカル&ギター)
「危険日でも遊んであげるからさ」
と音源では収録されていないフレーズを強調するようにしてハッキリと歌うのだが、トーキンロックフェス出演時の
「代表曲をとりあえず並べるんじゃなくて、自分たちがやりたい曲をやる」
というフェスへの向き合い方の変化はこの曲が1曲目であり、ポップなシンセの音も導入された「月の逆襲」という長谷川カオナシ(ベース)がボーカルを務める曲に続くことで、逆にこれらの曲が今のクリープハイプのフェスにおけるフェスセトリになっている感すらある、というくらいに最近のライブでは毎回演奏されている。
そんな中でステージにはキーボードが置かれると、カオナシがギターからキーボードにチェンジする「5%」へ。緊急事態宣言が解除されて、ライブハウスなどでもアルコールが提供できるようになったとはいえ、このフェスではアルコールの販売や持ち込みが禁止されている。そういう意味では5%くらいで酔いながらこの曲を聴くことができるのはいつになるのだろうか、とシラフな頭で考えていた。
その編成のまま、尾崎がギターを置いてハンドマイクで演奏されたのは、先月の「クリープハイプの日」に来るべきアルバムのタイトル「夜にしがみついて、朝で溶かして」のフレーズが入っていると口にして演奏された新曲「ナイトオンザプラネット」。
「5%」よりもさらにムーディーというか、夜の自宅がそのままダンスフロアになったかのようなサウンドで、尾崎はタイトルも含めたフレーズをヒップホップ的な歌唱で歌う。時折小泉拓のドラムセットのライザーの上に座って歌うという姿も含めて、あらゆる面で新鮮な曲である。先行配信されている曲たちがどれも全くタイプの違う曲であるだけに、アルバムがどんな内容、まとまりになるのか全く想像がつかないが。
「ぴあは中学生の頃から雑誌を買って読んでいて。安かったんですよ。290円くらいだったかな。タバコと同じくらいで。チケット買う金なんてなかったから、ライブ情報のページを読んで、いろんなライブ会場に頭の中で連れて行ってもらって。金はないけど、時間はあったから。
自分でバンドやるようになって、ライブ情報のページに自分のバンドが載った時は本当に嬉しかったなぁ」
と、このフェスを主催しているぴあへの思いを語るが、もしかしたらぴあへの想いは今年の出演者の中で1番と言えるかもしれないし、そうして今のクリープハイプは自分たちがこのフェスに出る意味というものをしっかり持った上で臨んでいる。それはある意味では選曲以上にフェスへの意識が変わった部分と言えるのかもしれない。
そんな話の後に変化球的な曲が続いたこの日の中で攻め方を変えるようにストレートな「イノチミジカシコイセヨオトメ」でたくさんの観客の腕が上がりながら、バンドの持つロックさを感じさせると、それはそのままリリースされている曲の中では最新曲である「しょうもな」へと繋がっていく。
「言葉に追いつかれないスピードでほんとしょうもないただの音で
あたしは世間じゃなくてお前にお前だけに用があるんだよ」
というのは我々目の前にいる観客はもちろんのこと、
「このフェスは作っている人たちの顔が見える」
と尾崎が口にしていたこのフェスへも向けられていた歌詞であるかのようだ。
そして
「セックスの曲をやります」
と言ってカオナシがステージ前に出てきて思いっきり体をうねらせながらイントロを弾く「HE IS MINE」は「クリープハイプの日」には演奏されなかったが、こうしたフェスなどでは演奏するというあたりに尾崎なりのフェスならばこの曲は、という思いもあるのかもしれない。小川のギターも身体的に躍動感を持ってリフが鳴らされるのだが、スクリーンにアップで映った小川のハットの下には髪が少しはみ出しているような感じもする。それは髪が伸びてきたということだろうか。当然ながらこの日もこの曲の
「セックスしよう!」
は無音だったわけだが、果たして声を思いっきり上げてこのフレーズを叫ぶことで尾崎に
「よくできました」
と言ってもらえる日はいつになったら訪れるのだろうか。
そして最後に演奏されたのは「二十九、三十」なのだが、自分はこの曲がライブで演奏されただけで泣きそうになってしまうという変な体質になってしまっている。それはこの曲が銀杏BOYZによってカバーされて、2組での対バンというライブも名古屋で見て、あるいはそれ以前のライブ(NHKホールなどのワンマン)でも最後に演奏されたりして、その度に
「前に進め 前に進め 不規則な生活リズムで
ちょっとズレる もっとズレる 明日も早いな
前に進め」
というクリープハイプのものとは思えないくらいにストレートかつ前向きなフレーズに背中を押されてきたからである。だからこそやはりこの日もこの曲が実に沁みたし、派手な曲ではないけれども明日からの活力をもらえているかのようだった。
演奏が終わると尾崎は1人最後にステージに残って、観客に向かって深々と頭を下げた。それは今のクリープハイプの音楽、ライブ、フェス、そしてそれを愛する人たちへの真摯な気持ちが表れていた。
リハ.寝癖
1.キケンナアソビ
2.月の逆襲
3.5%
4.ナイトオンザプラネット
5.イノチミジカシコイセヨオトメ
6.しょうもな
7.HE IS MINE
8.二十九、三十
17:10〜 レキシ [BRIDGE STAGE]
つい先日にテレ朝ドリームフェスで見たばかりというのは、レキシの「稼働する時はフェスとか出まくるけど、そうでない時は何の活動もない」という、レキシこと池田貴史が参加していた100sの活動ペースを思い出させてくれるところもあるが、そんなわけで今年の夏からは絶賛稼働している状態なのである。
ステージには幟がたくさん掲げられており、すでにホーン隊も含めた大所帯のバンドメンバーたちがスタンバイする中で、戦の始まりを告げるにはかなり脱力してしまうような法螺貝の音が響き渡ると、いつものようにアフロヘアにサングラスで着物を召しているというよくよく考えたらなんだこの格好は、と思ってしまうようなレキシもステージに登場。
テレ朝ドリームフェスの時は、ある意味ではラインナップに名を連ねていた理由の一つであったであろう曲(クレヨンしんちゃんのタイアップだから)として少しもったいぶった位置で演奏されていた「ギガアイシテル」でスタートするというセトリの変化は、久しぶりにこうしてライブをたくさんやるようになったからこそ、いろんなところに毎回見に来てくれるファンを飽きさせないようにという意識も間違いなくあるはず。曲というかMCやパフォーマンスがその日ごとにまるっきり違うから飽きることもないのだが。そして鳥獣戯画をテーマにしたこの曲で、早くも全く関係ない、物販で販売されている光る稲穂を振る人がたくさんいるというのもお約束である。
レキシとキーボードの元気出せ!遣唐使こと渡和久(風味堂)のファルセットボーカルが乗るファンキーなサウンドが観客の体を揺らす「大奥 〜ラビリンス〜」を歌いながら、隣のCONNECT STAGEの方まで行こうとするという、この日意外にも誰もやっていなかった自由すぎるパフォーマンスで笑わせると、あまりの暑さ(観客の大半は半袖Tシャツのみ)にレキシが着物を脱ぐのだが、すぐさま十二単を渡されて着物よりも暑くなるそれを着て歌うのは、なるとなでしここと橋本絵莉子(チャットモンチー済)のボーカルが流れる「SHIKIBU」で、レキシはメロディ、リズムに合わせた振り付けで観客を踊らせ、すでに楽しい空気で会場が満たされていく。
その楽しさをさらに増幅するのが、
「みんな、古墳に行きたいかー!」
とレキシが問いかけると観客が腕を上げるので、
「古墳に行きたいかー!でイェーってなるのはおかしいだろ!」
と観客にツッコミを入れながら、「KOFUN」の文字を観客の腕で作らせる「古墳へGO!」なのだが、そこはレキシ、それだけでは済まさずにX JAPANの
「紅だー!」
という言葉からのXジャンプ、さらにはモーニング娘。「恋愛レボリューション21」や工藤静香「嵐の素顔」など小ネタをガンガンに挟んでくるので笑いが止まることがない。
そんなレキシの笑いの極地とも言えるのは、稲穂の出番である「狩りから稲作へ」なのだが、
「最近稲穂だけ買いに来てライブ見ないで帰るやつすらいる!」
「そもそも稲穂の曲ってなんだよ!縄文土器と弥生土器の曲だよ!いや、縄文土器と弥生土器の曲っていうのもおかしいけど!」
とツッコミを入れまくりながら、
「他の人のライブの時は稲穂を絶対振るなよ!でも聞いたぞ!打首獄門同好会の「日本の米は世界一」の時に振ってたって!でもあの曲の時は振っていい!両者の間でそういう協定を結んでるから(笑)
でもNUMBER GIRLの時に稲穂振ったら「OMOIDE IN MY 稲穂」になるから、そうなったら「リライト」してください!」
と相変わらずの凄まじい出演者の曲を使った上手さ。ちなみにアジカンのゴッチもハッピー八兵衛というレキシネームを持っているだけに、1%くらいは共演する可能性あるかな?と思ったのだが、当たり前のようにそれはなし。
しかしながら急に
「ほらあなたにとって大事な稲ほどすぐそばにいるの」
とMONGOL800「小さなこいのうた」を若干うる覚え気味に替え歌すると、観客全員の心の大合唱が聴こえてくるかのような、この日最高の一体感をこの日出演していないバンドの曲で生み出すというあたりがさすがレキシである。
そんな「狩りから稲作へ」でマイクを顔の前でいじるのは若干滑り気味ではあったが、
「そして、ぴあフェスが好き〜」
という締めで大きな拍手を巻き起こして、完全にこの場を持っていくのである。
しかしながらそれでもまだライブは終わらず、
「最近はキモ可愛いというよりキモいと言われている」
というレキシの言葉に若干傷ついていたイルカの着ぐるみの吉尾太郎も登場しての「KMTR645」では健介さん格さんこと奥田健介(ノーナ・リーブス)のギターソロも炸裂するのだが、やはりホーン隊がいることによってキュウソバージョンとはまた違った印象を抱く。もはやライブで聴いている回数は圧倒的にキュウソバージョンの方が多い、というくらいにライブをやりまくっているバンドであるキュウソはよくライブでこの曲を演奏しているが。
「狩りから稲作へ」が1曲がかなり長い(曲自体も、諸々も含めて)ので、持ち時間と曲数的にこれで終わりかと思ったら、さらに「きらきら武士」を演奏して再びレキシは隣のステージまで行こうとし(NUMBER GIRLの田渕ひさ子が完全にすでにステージにいた)、観客は腕を左右に振りまくり、この日も最高に楽しい瞬間を作ってくれたレキシは、山口百恵の引退コンサートをリスペクトするかのように、稲穂をステージ中央にそっと置いてステージを去っていった。
コロナ禍になってからレキシのライブではコール&レスポンスがなくなったが、それでもレキシはそうしたネガティブなことは全く口にしない。今までと変わらないように本当に楽しいレキシのライブを我々に見せてくれる。今の状況でレキシを見ると、その完璧なエンターテイナーっぷりに心から敬礼したくなる。未だに全くネタが尽きない想像力も含めて。
1.ギガアイシテル
2.ラビリンス 〜大奥〜
3.SHIKIBU
4.古墳へGO!
5.狩りから稲作へ
6.KMTR645
7.きらきら武士
18:10〜 NUMBER GIRL [CONNECT STAGE]
リハで「水色革命」を演奏していた段階でそのあまりの轟音、音圧にレキシのライブのコミカルさが一瞬で塗り替わる。このCONNECT STAGEのトリはNUMBER GIRL。こうしてフルでのライブを見るのは人生初である。(配信だったり、CDJ 19/20でちょっとだけ見たりはしたけど)
リハ終わりで向井秀徳(ボーカル&ギター)は
「それでは、また来週」
と言っていたが、その数分後に再びステージに4人が登場すると、
「福岡県博多市からやってきました、NUMBER GIRL」
と向井が口上を告げると、「日常に生きる少女」から、やはりその鳴らしている音の凄まじさたるや。もうメンバーは全員40代半ばであるが、全くそれを感じさせない田渕ひさ子(ギター)とアヒト・イナザワ(ドラム)の見た目もそうであるが、その鳴らしている音の瑞々しさはまるで20歳過ぎのバンドが放つ初期衝動を感じさせながらも、この日出演したどのバンドよりも尖っている。これが1回解散して再結成したバンドの鳴らす音なのか、と唖然としてしまう。
中尾憲太郎(ベース)のダウンピッキングのイントロからしてロックバンドの音の重さの極地であるとすら感じる「鉄風 鋭くなって」はかつてThe SALOVERSもカバーしていたのが実に懐かしく感じる。そこから「タッチ」、さらには
「ヤバイさらにやばいバリヤバ」
という、なんだそれという発明的な歌詞(かつてこの歌詞からタイトルを取った「バリヤバ」というサブカル雑誌も存在していたぐらいの影響力)の「ZEGEN VS UNDERCOVER」という曲を続けて聴いていると、何というか、凄まじいのは間違いないんだけど、こういうバンドをやってみたいなと思う人が後を絶たなかったのがよくわかるというか、この後に出てくるアジカンのゴッチやBase Ball Bearなどがこのバンドのようなバンドをやろうとしていたということが実によくわかる。なんなら初期のBase Ball BearはこのバンドとSUPERCARの影響が実に色濃い。ただ、曲をコピーしても絶対にこんな音にはならないということもよくわかる。
BiSHのアユニ・Dによるバンド、PEDROがカバーした(田渕ひさ子はPEDROでもギターを弾いている)ことによって、今やこのバンド最大の代表曲と言っていい存在になりつつある「透明少女」のどうしようもないくらい、茹だるような陽炎が視界に浮かんでくるかのような夏感から、特にベボベに強い影響を与えたであろう、
「あの子はそう、17才」
と向井が言ってからの「YOUNG GIRL 17 SEXUALLY KNOWING」と、ただひたすらに曲を、鉄の音の塊を次々に連発していく、照明などすらも最小限でしかないというストイック極まりないライブの在り方もまた、この音に集中すべしという気にさせてくれる。
向井による、
「ドラム、アヒト・イナザワ」
もそう言えば自分が生で聴くのは最初期のZAZEN BOYS以来であるのだが、中尾のベースがさらに重く太くなる「CIBICCOさん」や、向井の絶唱というべき「TATTOOあり」の
「右肩 イレズミ」
という歌唱と田渕の時折飛び跳ねながらのメタリックなギターと、4人それぞれが解散後にも様々な場所で音を鳴らし続けてきたからこそ、こんなに凄まじい演奏が出来るのだろう。自分はリアルタイムではライブを見る前に解散してしまったのだが、当時と今を比べるとどうなんだろうか。これでも当時は今よりもさらに凄かったんだろうか。それは過去の映像で見ても絶対に比べられるものではないな、と思うのは配信ライブで見てきた昨今のこのバンドのライブが目の前で見ると本当にビックリするくらいに別物だからである。
そして田渕はギターを鳴らしながら、そのギターを高く掲げる。その音が一気にドライブしていく瞬間の、ブワッと鳥肌が立つくらいに震えるような感覚。初めて生で目の前で鳴らされているのを見た「OMOIDE IN MY HEAD」はそうしたものだった。あの2コーラス目のキメも、ずっと聴いてきたものが今目の前で、音源以上の迫力をもってして鳴らされている。この日のこの思い出は自分の頭の中から決して消え去ることはないだろう。
そしてラストは向井の
「おーい!!」
の歌唱がもはやその2文字の単語であるはずなのに、なんと言っているかわからないくらいの轟音渦巻く「I Don’t Know」。それはもはやドリーミーな心地よい夢ではなくて、ただただひたすらにこの世のものとは思えないような音が鳴らされ続けていた、という意味での夢見心地であり、そこから覚めたかのように向井はメンバー紹介をすると、田渕以外のメンバーがマスクをつけてステージを去って行った。
何というか、ロックバンドというものは何故こうも面白いんだろうかと改めて思うとともに、自分が今もこうしてライブに通い続ける人生でいれて本当に良かったと思った。かつてNUMBER GIRLを聴いていた同世代の人の中には再結成後もライブとは無縁の生活を送っている人もたくさんいるだろう。でも自分はこうしてライブに行く生活のままだからこそ、ずっと「自分がライブを見れることはない」と思い込んでしまっていたバンドのライブを今になってこうして見ることが出来ている。
それは、これから先、違うバンドでもこうした経験ができる日が来るんじゃないだろうか、とこの先の人生にさらなる楽しみと希望を与えてくれる。それくらいに、ただ復活してライブが観れたのが嬉しいだけじゃなくて、ひたすらにとんでもないライブだった。全ロックバンドファンが見たほうがいいと思うくらいの。10代の人とかがライブ見たら、人生変わってしまうんじゃないだろうか。
リハ.水色革命
1.日常に生きる少女
2.鉄風 鋭くなって
3.タッチ
4.ZEGEN VS UNDERCOVER
5.透明少女
6.YOUNG GIRL 17 SEXUALLY KNOWING
7.CIBICCOさん
8.TATTOOあり
9.OMOIDE IN MY HEAD
10.I Don’t Know
19:10〜 ASIAN KUNG-FU GENERATION [BRIDGE STAGE]
そんな偉大な先輩であるNUMBER GIRLや、今最も勢いがあるバンドたちのバトンが最後に渡るのはアジカン。このフェスが若洲公園で開催された2017年に出演した際にゴッチが
「会場着いたらめちゃくちゃEDMみたいな音が流れてて、今日そんな人出てたっけ?と思ったら森高千里さんだった(笑)」
と言っていたのは今でも忘れられない。
メンバー4人とシモリョーがステージに登場すると、まず驚くのがなんといってもゴッチの髪型である。こんなに短かかった時って今まであったっけ?というくらいに耳がはっきり見えるほどに髪が短くなっている。それによってどことなく若返ったような感じすらするのだが、そのゴッチが
「難しいのは いつだって承知の上」
と、まさに今この時代を生きていく困難を歌っているかのような「ダイアローグ」でどっしりとしたロックを聴かせてくれるというのは、あれだけ人間、ロックバンドの衝動や熱量を放出するようなライブを見せていたNUMBER GIRLの後であっても、自分たちは自分たちなりの、アジカンの今のロックを鳴らすという姿勢が見える。
「こんばんは、ASIAN KUNG-FU GENERATIONです」
とゴッチが挨拶すると、山田貴洋のベースのイントロによって長いイントロが始まるのは「Re:Re:」であるが、そのイントロの段階で最後まで残っていたたくさんの観客たち(もっと少なくなるかと思っていたが、ほぼ満員レベル)が声を出せなくても腕を振り上げている。みんなこの曲が聞きたかったんだな、アジカンのライブとこの曲を待っていたんだなということがわかって胸が熱くなる。それはこのライブに至るまでに割と色々とあったからであるが、ゴッチは髪を切ったことによって、身振り手振りを交えながらの歌唱も実に爽やかに見える。
喜多建介のオリエンタルなギターのリフは、紛れもなくNUMBER GIRLがいることによって生まれ、この日も演奏されたであろう「N.G.S」であるが、伊地知潔のなんとも楽しそうな表情でのキメの連発ではゴッチが
「ハッ!」「ヨイショ!」
と、フェスという祭りにふさわしい掛け声を上げ、それに呼応して観客がジャンプするというのも実に久しぶりの光景である。今になってこの曲を聞くと、ゴッチもあんまりインターネットという仮想現実のことなんか気にしなけりゃいいのに、と思ったりもするけれど。
その「N.G.S」がNUMBER GIRL SYNDROMEの略であり、こうしてNUMBER GIRLの後にライブをやれるということの敬意を持って演奏したものであり、その偉大な先輩のライブを見て燃えているということをゴッチが口にすると、一転して切ないギターのイントロが鳴り、伊地知のリズムに合わせて手拍子が起きたのは「ソラニン」。コロナ禍になる前はフェスでこの曲が演奏されるとどよめきが起こっていたものであるが、声が上がらなかったのはみんな我慢していたからなんだな、とわかるのは少なからずイントロが鳴った瞬間に拍手が起こっていたからである。
アジカンなりの重いロックという曲をチャート上位(オリコン最高位2位)にまで送り込んだという功績とともに、カップリングバージョンのコーラスをシモリョーが加えるというマッシュアップバージョンに進化して名曲ぶりが色褪せることのない「サイレン」、室内会場だったからか、あるいはあれはJAPAN JAM限定のものかはわからないけれど、この曲が終わったら帰るという人を監視する「リライト警察」の話は出なかったが、それはたくさんの人が腕を振り上げていたからなんじゃないかと思うような「リライト」と代表曲が続くのだが、毎回ツアーに必ず行く、フェスやイベントにもアジカンが出れば行くし行けば見る、というようなタイプの自分のようなファンであっても、こうしてフェスのトリでこの曲たちが演奏されているのを見ると、まだまだアジカンを差し置いて若手バンドがトリを務めるというのはキツいものがあるな、と思う。
それはこうした、ロックファンだけならず、こういうイベントに来るような人が誰もが知るようなヒット曲を、1曲だけならず複数曲持っているバンドというのはなかなかいないからである。こうした規模が広い会場になればなるほどにその曲が持つ力を実感するし、やっぱりアジカンがトリじゃなきゃな、とこの日出演した全アーティストを好きな身としても思う。この壁は本当にめちゃくちゃ厚くて高い。
そんなアジカンのラウドさをシモリョーのキーボードも含めた5つの音の重なりで感じさせてくれる「Easter」から、ゴッチが歌い出しただけで客席からたくさんの腕が上がり、喜多がこの日も間奏で高く足を上げてギターソロを弾きまくる「荒野を歩け」と続くと、
「1分1秒幸せな時間を無駄にしないように」
とゴッチが語り、the chef cooks meの「Now’s the time」のフレーズを口ずさんでから「ボーイズ&ガールズ」へ。サビでアリーナの上空から光が降り注ぐかのような照明とともに、
「We’ve got nothing」
のフレーズが響く。
「まだ始まったばかり」
というフレーズも含めて、再スタートを切ったこのフェス、コロナ禍を生きる我々へのエールのようであった。
アンコールで再びメンバーが登場する前には、手拍子が起こる中でスクリーンにタオルを掲げたりして待つファンの姿も映し出される。アジカン、というかゴッチはフジロックが開催された時にまぁそれは酷い口撃をネット上で受けまくっており、その際に自分のようなファンにも「アジカンファンはもうみんな失望してる」的なことを言ってきた輩もいたのだけれど、この光景を見ていたら、いや、全然失望してないじゃん。もしかしたら離れた人もいるかもしれないけど、そうだとしたらその人はゴッチの発言とフジロックに関してが全然違うものだってことを理解してないような奴でしかないだろう、と思うくらいにたくさんの人がアジカンの音楽をこうして最後の最後まで待ち望んでいるじゃないかと。それはゴッチの元気な姿とともに本当に嬉しい景色であった。
そんなゴッチは
「だいたいいつも最初に俺がステージに出てくる時にみんな俺のパーマっぷりを見て笑ったりするんだけど、今日は髪切ったからそれもないだろうと思ってたんだけど、声が出せないから笑えないっていうだけかもしれない(笑)
俺は科学者でも医者でもないからわからないけれど、1年後になるのか、2年後になるのか。声が出せるようになったら俺の新しい髪型でゲラゲラ笑える日が来ますように」
と、自虐的なようでいて確かな希望を感じさせるMCから、リリースされたばかりの最新シングル「エンパシー」へ。
アニメのタイアップという「遥か彼方」から今に至るまで、アジカンの曲をさらに遠くに、たくさんの人に届けてきたものにふさわしい、王道のアジカンを行くようなギターロックであるが、近年はそうした曲は山田作曲だったのが、この曲はゴッチが作曲している。だからか、Aメロからサビまではかなり飛距離があるようなアレンジにも感じられるのだが、そこが求められているものに応えながらも、今自分たちのやりたいようにやるというアジカンなりのスタイルなのだろう。
そしてこの日のトピックスとしては、そのライブ初披露となった「エンパシー」においても不可欠なキーボードの音を鳴らし、かつて参加し始めた時には「月光」のイントロを盛大にミスったりもしていたけれど、今ではアジカン第5のメンバーとして欠かせない存在となったシモリョーが参加する最後のライブであるということ。
詳しくはシモリョー自身が書いているが、そもそもゴッチが
「こんな才能をこのまま終わらせてはいけない」
とほぼ止まっていたthe chef cooks meを自分たちのレーベルからリリースさせて再生させ、そうしてアジカンや自身のソロに参加するようになった。それはライブのキーボードやコーラスというサウンド面や、「エンパシー」ではプロデュースも担当したということ以上に、とかく「ゴッチと他3人」という構図になってしまいがちなバンド内の緩衝材的な役割として果たしてきた役割も強いはず。実際にゴッチはツアーで地方に行った際に観光についてきてくれるのはシモリョーだけだ、というようなことも話していた。
そんなこの5人の編成で最後に演奏されたのは、この5人でのアジカンをずっと見てきた人にとっては絶対にこの曲を最後にやって欲しいと思っていたであろう「今を生きて」。シモリョーが「イェーイェーイェー」のフレーズで腕を上げ、観客もそれに呼応して腕を上げる。数え切れないくらいに見てきたその光景もこの日で最後なのかと思うと途端にいろんなものが溢れてしまいそうにもなるが、この曲は
「優しく笑って
今日でさようならしようぜ Baby
永遠を このフィーリングを此処に刻み込もう
駆け出そう世界へ Say yeah!!!
肉体の躍動だ Baby
永遠を このフィーリングをずっと忘れないでいよう」
と、シモリョーを送り出す上でこの上ないくらいにふさわしいメッセージを持った曲だった。これからシモリョーも、アジカンもまた新しい世界へ駆け出していく。それがどんな形になるのか(アジカンが4人だけになるのか)はわからないが、この5人のフィーリングだけは、ずっと忘れないでいよう。
演奏が終わると、シモリョーはすぐにステージから去ろうとしたが、それをすぐさま呼び止めて5人でステージ前に並んで観客に一礼した。確かに、この日は、この日まではこの5人のASIAN KUNG-FU GENERATIONだったし、その日々を見ることができて本当に幸せだったと思う。
そうしたいろんな事柄や思いが重なった、この日のアジカンのライブ。時には自分もゴッチに「もうそんなに何もかも背負わなくていいじゃないか」と思う時もあるのだが、そうしてゴッチがいろんなものを背負ってきたからこそ、アジカンとして回った土地で出会った人や、THE FUTURE TIMESを作ったりしてきた中で出会った人たち、そうしたゴッチの活動を見てきたことによっていろんなことに興味を持ったり、考えるキッカケを与えてもらってきた自分のような奴の思いを音楽にすることができて、それを今も背負い続けているからこそ、ロックフェスのトリという場所に立って戦い続けることができているんだろうと思う。
果たしてシモリョーが居なくなってそれは大丈夫なんだろうかと思うけれども、きっと今なら3人がゴッチを支えることができる。それがわかっているから、こうしてシモリョーを送り出すことができたんじゃないかとも思っている。
2017年の若洲公園のトリ。このぴあアリーナが作られることが告知された時。あの時もトリはアジカンだった。なくなっていってしまう場所もたくさんある中で、4年後に無事にその場所でこのフェスが開催されていて、そのトリとしてライブをやっているアジカンの姿を見ることが出来ている。これから何年先もそういう人生であり続けたいと思っている。
1.ダイアローグ
2.Re:Re:
3.N.G.S
4.ソラニン
5.サイレン
6.リライト
7.Easter
8.荒野を歩け
9.Now’s the time 〜 ボーイズ&ガールズ
encore
10.エンパシー
11.今を生きて
文 ソノダマン