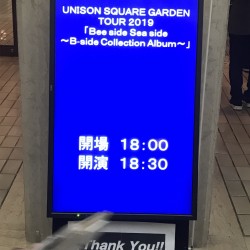フジテレビで放送されている「LOVE MUSIC」のプロデューサーである三浦ジュン氏が主催するフェス、JUNE ROCK FESTIVALがコロナ禍の去年を経て帰還。
今までは6月開催だったのがこの時期になり、さらにはオールナイトで次々にアーティストが出演するという形だったのも今は断念し、という形は変わった中であるが、それでもこうしてフェスを繋げていくという意思は守り抜くことができての開催である。
実にクセが強い出演バンドたちによるメッセージや飾り付けなどもロビーには飾られている中、何故かオフィシャルTシャツの売り子を花団のかずがやっていたりする中、客席は立ち位置を床に貼るという形のスタンディング制で、BGMとして銀杏BOYZやサンボマスター、ハルカミライにビレッジマンズストアというバンドの曲たちが流れている。
開演前には主催者の三浦ジュン氏が登場して諸注意とともに、この状況下で動員も減らしているだけに、収支が本当にギリギリであり、リストバンドが無地にならざるを得なかったので、自身がマジックで文字を書き、四星球の北島康雄、バックドロップシンデレラのでんでけあゆみ、オメでたい頭でなによりの赤飯という出演者たちも手伝ってくれたことを明かし、大きな拍手が上がる。こうしたところにもこのフェスがどういうフェスなのか、どういう人が作って、どういう人が出演しているフェスなのかがわかる。
13:00〜 オメでたい頭でなにより
トップバッターとしてステージに登場するなり、場内にはマーチのリズムが流れると、ギターのぽにきんぐだむがビールジョッキのぬいぐるみのようなものを掲げ、324(ギター)とmao(ベース)がフラッグを振って登場すると、赤飯(ボーカル)がジェントルな声で
「イタリアでやる乾杯を 言いたい 言いたい
イタリアでやる乾杯は Cin Cin
恥ずかしがらず 大声で Cin Cin
イタリアでやる乾杯を Cin Cin」
と、テレビ収録も行われているこのフェスの冒頭から収録に対応していなそうな「乾杯トゥモロー」を歌い始める。1コーラスのみで終わるというのはウェルカムドリンクバージョンというライブのSEを兼ねたものであるのだが、途中からメンバーが楽器を持ってバンド編成になるというあたりの切り替わり方は実にスムーズである。
しかしながらイントロからAメロのオシャレなアレンジ、Bメロではマキシマム ザ ホルモン2号店のボーカルとしても活動しているのがよくわかるようなデスボイス、さらには正統派アニソン的と、めまぐるしく展開していく「金太の大冒険」というこれまたテレビ収録では流せないであろう曲が続く。この曲をただカバーするのではなく、こんなにも展開しまくる形でカバーできるのは実はしっかりとそれぞれ技量を持ったミュージシャンの集まりであるこのバンドだからこそだろう。
「JUNE ROCK FESだからいつもは6月にやってたフェスだけど、今日は10月16日。16日っていうことは、JUNE ROCKの日です!」
と、一瞬これで終わりにして帰ろうとしながらも、MCも実に気が利いているが、「哀紫電一閃」では一転してラウドなこのバンドの力量をしっかりと見せてくれる。
「ただふざけてるだけじゃない、ロックバンドとして他のバンドを潰してやるっていう意識でやってやる!」
と舐められたくないという熱さも見せたかと思いきや、赤飯は女声に切り替えて、前方の観客が振るサイリウムも輝くという、アニソンやアイドルのライブのような空間にガラッと変わるのは「推しごとメモリアル」であるが、サビではメンバーが楽器を置いて振り付けを踊りまくるというまさにアイドル的な展開になり、さらには間奏ではミト充(ドラム)がステージ袖から主催者の三浦ジュン氏を引っ張ってきて、空気の入ったギターのおもちゃでエアギターをやらせ、さらにはサビでのダンスを踊らせるというこのフェスならではのコラボというか、これはもはやこのバンドからの主催者とこのフェスへの愛情表現だろう。
そしてこうしたライブハウスのフロアの熱狂を風呂場の暑さに例える「スーパー銭湯 〜オメの湯〜」ではmaoのスラップに324のメタルバンドかと思うくらいの速弾き、さらにはぽにきんぐだむのラップと、ただでさえその歌声の変容っぷりが凄まじい赤飯だけでなく、このバンドのメンバー全員がそうした凄まじいスキルを持ったメンバーであるということをあくまで音を鳴らすことに示して文字通りにフロアを熱くさせると、客席にはダブルピースが掲げられる「オメでたい頭でなにより」が最後に演奏されるのだが、その曲中に赤飯は、
「配信とかもやってきたけれど、やっぱりこうしてライブがあって、目の前にあなたがいてくれていることで生きていることを実感することができる。声を出したりとかできない状況が続いてますけど、いつかこの時期を振り返った時に「あの頃をこうやって切り抜けたんだよね」って思えるように」
という言葉からはこのバンドが本当に音楽への、ライブハウスへの愛で動いているバンドであるということがよくわかる。技術、発想、実行力も素晴らしいバンドであることはライブを見ればすぐにわかるが、それ以上にその精神が素晴らしいからこそ、様々な大型フェスやこうしたライブハウスでのフェスに出まくるようなバンドになったんだな、という実感が確かにあった。
1.乾杯トゥモロー
2.金太の大冒険
3.哀紫電一閃
4.推しごとメモリアル
5.スーパー銭湯 〜オメの湯〜
6.オメでたい頭でなにより
13:55〜 MOSHIMO
サウンドチェック時からメンバー4人で曲を演奏し、拳が上がったり手拍子が起きたりしたのを岩淵紗貴(ボーカル&ギター)が喜んで感謝を告げていた、MOSHIMO。こうした状況になってしまったが故に、ライブを見るのが実に久しぶりになった。
メンバー4人が本番で登場すると、実に力強い、なんならラウドと言ってもいいくらいの音を鳴らしながらこのフェスが開催できたことへの感謝を語り、「電光石火ジェラシー」で岩淵のどこか幼さも感じさせるボーカルが響くのだが、すぐにギターを背中に回してステージを歩き回るという姿はロックバンドのフロントマンの姿そのもので、この曲の強いフックになっている野球拳の
「アウト セーフ よよいのよいよい」
のフレーズを、レスポンスはできない観客に腕を上げたりするリアクションをしてもらいながらも、声が出せなくなる前と全くライブのやり方、形は変わっていないことがわかるし、そこに頼もしさを感じる。
「最近は若手バンドと一緒にやることも増えてきたけど、今日は我々が最年少っぽい」
と、若さを前面に押し出していく覚悟での「釣った魚にエサやれ」では汐碇真也(ベース)との女性に詰められる男女のやり取りのような掛け合いが展開されながらも、間奏では一瀬貴之(ギター)に岩淵が
「いつもすっぴんでスタジオ来るのにこの前は黒のドレス着てネイルまでして、その後出かけて行ったじゃないですか。あの後はどうなったんですか?」
と問われると、
「めちゃくちゃおめかしして行ったのに、その人にはすでに相手がいました!」
と怒りを炸裂させるようにサビのボーカルの迫力がさらに増す。この曲ではソーラン節のフレーズも使われているが、そうした誰もが知るフレーズを自分たちの曲に邪魔をしない分量で取り入れ、それをコール&レスポンス(今はレスポンス出来ないけど)として使うというあたりが実に巧みだ。
「前に別れた人に、だいぶ経ってから用があって電話したんだけど、その時にその人の声のトーンが私と付き合っていた時よりも高くなっていた。その人はもう私のものじゃないし、そもそも人も誰かのものじゃないんだけど、そうして変わったって思うのが凄く切なく感じた」
という岩淵の実体験の思いを曲にした「蜂蜜ピザ」は、ラブソングや失恋ソングという形態としては自分は全く共感ができない類の曲であるのだが、その恋愛や別れた相手の変化の機微が曲や歌詞のもとになったり、あるいはこの曲の
「大好きなピザも
一人じゃ食べきれないや
大嫌いなホラー映画は
観なくて良くなったけどね」
というフレーズも、ただ「別れた」「いなくなった」というだけではなく、それを歌詞の表現として、よりどう切なくなった、悲しくなったのか、別れる前はどんな2人だったのかということを具体的にイメージできるものになっており、毎回ライブを見るたびにフラれているようなイメージすらある岩淵のそうした人生がそのまま音楽になっているんだなと思う。
そんな「蜂蜜ピザ」はこうしたフェスやイベントなどの短い時間のライブで演奏されるには意外なバラード曲であるが、その「蜂蜜ピザ」と同様に8月にリリースされたばかりのアルバム「化かし愛」に収録されている、リード曲の「化かし愛のうた」からはロックかつ元気なMOSHIMOらしさに戻り、そのサウンドの根元を支える、力強いドラマーの高島一航が登場時にかけていたメガネを外して、肩が露出したTシャツを着ていることで腕のタトゥーが見えるようになっている。
自分がMOSHIMOのライブを初めて見たのはまだ前のメンバーだった頃であるが、そうしてライブを見る前から、メロディが抜群に良いバンドだと思っていたし、それは時にサビ前のBメロにそう感じる曲が多いところにこのバンドらしさを感じていたのだが、この「化かし愛のうた」もまさにそうしたBメロが非常に美しいメロディの曲であり、「花いちもんめ」「手の鳴る方へ」というやはりキャッチーなフックもそう感じさせる要素になっている。
そして岩淵がギターを鳴らしながら歌い始めた「命短し恋せよ乙女」はずっとライブの最後を担ってきた曲であり、曲中には観客の悩みを聞いて励ますというコーナーがあるのだが、観客が声を出せないだけにそのコーナーは果たしてどうなっているんだろうかと思っていたら、観客にスケッチブックを渡して書いてもらうという筆談スタイルになっていた。
その相談コーナーで「後輩と上手くコミュニケーションが取れない」ことを書いた女性を岩淵が励ましながら、
「命短し頑張れ○○!」「命短しファイトだ○○!」
とその人の名前を入れて歌うというのもコロナ禍になる前とは全く変わらない。
「辛いこととか悲しいことがあったらまたMOSHIMOのライブにおいで。元気にしてあげるから!」
という岩淵の言葉の通りに、久しぶりに見たMOSHIMOはコロナ禍になってもバンドのスタンスは全く変わらないどころか、我々観客側は楽しみ方も変わって、不安になったり心配になるようなことも増えただけに、その姿が今まで以上に頼もしく感じられた。
リハ.触らぬキミに祟りなし
リハ.ヤダヤダ
1.電光石火ジェラシー
2.釣った魚にエサやれ
3.蜂蜜ピザ
4.化かし愛のうた
5.命短し恋せよ乙女
14:50〜 Wienners
先月の新木場STUDIO COASTでのBAYCAMP DOORSでもライブを見ただけに、コロナ禍になってからもこうしたフェスやイベントで見れる機会も多いWienners。BAYCAMPでおなじみのバンドだからか、川崎で見るということにどこか安心感を感じる存在でもある。
メンバー4人が登場すると玉屋2060%(ボーカル&ギター)が
「JUNE ROCK、踊ろうぜー!」
と叫び、おなじみの髭を青みがかった緑に染めた560(ベース)がキックを繰り出すようにしたり、ポーズを取るようにしながら演奏し、アサミサエ(キーボード&ボーカル)の紅一点ボーカルの玉屋との歌の絡み合いも実にポップに響く「ANIMALS」からスタートしてKOZO(ドラム)のドコドコとした性急なドラムによる「TRADITIONAL」とファストパンクバンドらしさを感じさせる曲を演奏するだけに、こうして立つ場所が決まっていて、モッシュやダイブなどができない、腕を上げるしかないという状況が実に歯痒く感じる。それはもちろんバンドの演奏がそうしたくなるような衝動を沸き上がらせてくれるからだ。
そんな中でオリエンタルなサウンドに合わせて玉屋もアサミもそうした民族的な動き、パフォーマンスを見せる「恋のバングラビート」はこのバンドが様々な要素のサウンドを取り入れて、それを自分たちのダンスサウンドに昇華していることがよくわかる。
それでも
「まだまだ踊り足りないでしょ!」
と叫ぶ玉屋は主催者の三浦ジュン氏がリストバンドに直筆でフェスの名前を書いたエピソードを語りながらも、
「まぁ俺は何にもしてないんだけど(笑)」
と言っていたが、こうしてこのフェスに出ているということはその主催者の思いに応え、それを背負っているということだ。
それは「蒼天ディライト」からの曲にも確かな熱量に現れており、観客もサビではブンブン腕を左右に振りまくるのだが、その客席の様子をちょっと腰を上げるようにして奥の方まで見るKOZOの表情は実に嬉しそうであり楽しそうなのだが、ライブにおける最大のキラーチューンと言ってもいいこの曲がこうして中盤くらいに演奏されるということに、終盤には果たしてどの曲をやるのだろうかとも思う。
この状況下だからこそ生まれたであろう、音楽への切なる願いと祈りをパンクビートに込めた「GOD SAVE THE MUSIC」はこのバンドなりの今の世の中の生き方であるとともに、今こそ歌うべきテーマであるということがその音を鳴らす姿から伝わってくるのだが、そんな中で畳み掛けるように「Idol」へと、短い持ち時間の中でも自分たちの持ち得る要素を全て詰め込もうとするかのようであり、それは同時に自分たちの見せたい部分を全部見せるものであるということだ。
「もっともっと踊ろうぜー!」
とこの日は玉屋が何度もそう叫んでいたのだが、実際に560のバキバキのベースとKOZOの細かく刻むビート、アサミの手拍子が観客を踊らせまくる「FAR EAST DISCO」ではこのクラブチッタの天井に輝くミラーボールが鮮やかに輝きながら回り、それはまるでまたオールナイトで開催された時の景色を今見ているかのようだった。
そうしたディスコパンク曲で踊らせまくって終了…かと思ったら、トドメとばかりに玉屋がマイクスタンドの逆側から体を捻るようにマイクに口を近づけて叫ぶファストパンクな「Cult pop suicide」を繰り出す。こうした曲こそこの状況になる前の、めちゃくちゃにやれるようなライブハウスの景色を想起させるものであるのだが、それを今こうして演奏しているというところにこのバンドの生き様を感じるとともに、それはもう遠い未来の話ではなくて少しずつ見えてきつつあるものなのかもしれないという希望を確かに感じさせるものとなっていた。
リハ.MY LAND
リハ.おおるないとじゃっぷせっしょん
1.ANIMALS
2.TRADITIONAL
3.恋のバングラビート
4.蒼天ディライト
5.GOD SAVE THE MUSIC
6.Idol
7.FAR EAST DISCO
8.Cult pop suicide
15:45〜 忘れらんねえよ
先月のTOKYO CALLING新宿編でのJUNE ROCKコラボステージである新宿BLAZEのトリも務めた、忘れらんねえよ。そのステージに出ていたバンドの中で今回も出演しているのは忘れらんねえよだけ(他の出演バンドもBGMで曲は流れていた)というあたりに、主催者の忘れらんねえよへの強い信頼と愛情を感じることができる。
サウンドチェックの段階ですでに4人で出てきて柴田隆浩(ボーカル&ギター)が菅田将暉「まちがいさがし」を歌おうとしたり、放送禁止用語を叫びまくってマイクチェックをしたりしつつ、この日は「ばかばっか」でのノンアルビール一気飲みもこの段階でやるというのは本編でフルでやりたい曲がこれ以上にたくさんあるということだろう。
SEなしというのはテレビ放送があるという事情によるところかもしれないが、無音でステージに4人が登場すると、TOKYO CALLINGや BAYCAMPでは小堀くん(爆弾ジョニー)だったベースがイガラシ(ヒトリエ)に戻っており、これはやはり主にヒトリエのスケジュールによるもので、基本的にはイガラシがベースのポジションなのだろう。柴田1人になってからの初期はgo!go!vanillasのプリティが参加したりもしていたが。
柴田がギターを鳴らしながら歌い始める「だっせー恋ばっかしやがって」でのサビで一気に光が射してくるようなじわじわと熱量が上がっていくスタートから、たくさんの拳が上がる「戦う時はひとりだ」という流れは最近のこうしたフェスやイベントなどでもおなじみの流れであるが、柴田は
「ライブハウスに久しぶりに来た人っている?」
と問いかけると、後ろの方に少しだけ手を挙げた人がいたのを見て、
「みんなライブハウス来てるんだな!」
と嬉しそうに言い、
「ライブハウス来てるあなたたちが1番カッコいいよ。ちゃんとルール守って見てるんだもん」
とこうして今の状況下でライブハウスに来ている人を肯定してくれる。それは柴田がこの状況になったから行ってきたライブにおいて、自らでその光景を見てきたからだろう。
そんな観客を音楽で肯定するのが最新曲の「これだから最近の若者は最高なんだ」であり、忘れらんねえよの持つメロディの美しさと柴田だからこそ書ける歌詞が融合した曲であるのだが、この日の客層的に若者が多かったかというと…。いや、こうしてロックバンドのライブに目を輝かせている人はみんな若者なのかもしれない。柴田だって主催者だって、年齢的にはいい歳であるが、見た目は若者と呼んでも違和感ないように見える。それはロックの持つ蒼さを今も持ち続けているからだろう。柴田は主催者を
「おじさんの形をした天使」
という絶妙な形容で表現していたけれど。
かつて音源化する前はとんでもない下ネタソングだったのが、音源化したら美しい名曲に生まれ変わっていたというギャップが今も忘れられない「夜間飛行」はこうしたイベントなどの持ち時間で演奏されるのは久しぶりであるだけに聴けて実に嬉しいところであったが、柴田は
「ルールを守って戦って、俺たちで絶対に取り戻すんだ!」
とこの状況の中でも全く諦めることなく前に進んでいこうとし、だからこそこうしてこのフェスが開催されたことが大きな一歩であるということを噛み締めさせてくれる。
そんな言葉はまさに「この高鳴りをなんと呼ぶ」に集約されていくのだが、普段は出演しているフェスのタイトルに変えるような
「明日には名曲が○○に生まれんだ」
の部分を「ライブハウス」に変えて歌っていた。このフェスのタイトルにしても良さそうなのにあえて「ライブハウス」としたのは、柴田がこのフェスの主催者が普段からあらゆるライブハウスに足を運んでライブを見ていることをわかっているからだろう。そしてそれは柴田のMCでの言葉とも合致している歌詞である。
「ニュースでやってたから見た人もいるかもしれないけど、ライブに行く人が激減していると。ドリカムの人も、知り合いでもなんでもないけど(笑)、あのドリカムの人がだよ?「ライブに来てください」ってお願いしてるんだよ。言わんや俺たちみたいなもんたるやっていう」
という言葉からはこうしてライブで、音楽で生きていくことの厳しさも感じさせるのだが、そう言うと必ず「それを選んだんだから自業自得だ」と言ってくるような人がいる。そんなの気にしなきゃいいんだけど、Yahoo!ニュースのコメント欄でそうしたコメントを見ては良くないねボタンを押しまくっているという柴田からしたらそうした声は心を抉られるようなものなのだろう。選んだのはもちろん自分だが、柴田はどうあっても音楽でしか生きることが出来なかった。音楽を選ばざるを得なかった。だからここまでこうしてライブを、ライブハウスを、ライブ業界を救おうとしているのだ。これからも自分たちが生きていく場所だから。
そんな柴田の思いを届けるような「俺よ届け」では身を捩らせながらギターを弾きまくるロマンチック☆安田(爆弾ジョニー)の姿をさりげなく「キモい」と言ったりもしていたが、実はコーラスも務めているタイチ(ドラム)とともにこの爆弾ジョニーコンビは完全に今や忘れらんねえよのメンバーと言っていい存在であるし、普段は全く喋らないイガラシもコーラスをしつつ、コーラスをしなくても歌詞を口ずさみながらベースを弾いているという姿に、こんなに凄いプレイヤーが本当に忘れらんねえよのメンバーと言っていい存在になってくれたんだな、と思って胸が熱くなる。
そんなライブの最後はやはり「忘れらんねえよ」。柴田は観客にスマホライトを点けてサイリウムのように振らせて、会場の照明を落としていくことによってそれがどんどん美しさを増していくと、サビを心の中で合唱させる。なんだか、今までよりもそれを本当に歌える日が少し見えたような感覚もあった。それは間違いなく、0.1歩ずつくらいでもライブが、我々が前に進み続けてきたからだろう。その光景と感覚は完全にもはやフェスのトリと言っていいものだったが、それはTOKYO CALLINGはもちろん、COUNTDOWN JAPANなど、忘れらんねえよが様々なフェスでトリを務めてきた姿を見てきたからかもしれないと思った。
この日の出演者は、特にこの忘れらんねえよ以降はフェスにおいては飛び道具的な見方もされるようなコミカルなバンドばかりである。忘れらんねえよもそうしたパフォーマンスが話題になったりすることも多々あったが、そうしたバンドたちと並んだこの日の忘れらんねえよはひたすらに持ち得る熱さを放出するようなライブだった。それは他のバンドたちもそうした部分を持っているということを柴田がわかっているからだろうとも思う。
リハ.バンドやろうぜ
リハ.ばかばっか
1.だっせー恋ばっかしやがって
2.戦う時はひとりだ
3.これだから最近の若者は最高なんだ
4.夜間飛行
5.この高鳴りをなんと呼ぶ
6.俺よ届け
7.忘れらんねえよ
16:40〜 THEラブ人間
この日の出演者や客層的にはかなりアウェーと言っていいかもしれないが、主催者は先月のTOKYO CALLING新宿編においても普通に客席からこのバンドのライブを見ていた。それくらいに自分がライブを見たいバンドなのだろう。THEラブ人間がこのクラブチッタに登場である。
金田康平(ボーカル&ギター)だけならず富田貴之(ドラム)も金髪というセンターが鮮やかな体制で、サポートベースにはこの日もマツザカタクミ(ex.Awesome City Club)を迎え、TOKYO CALLINGの時と同様に谷崎航大のヴァイオリンの美しい調べとともに金田が歌い始める、
「雨の日でも君がいればどんな時も晴れだったよ」
という新曲から始まるというあたりもTOKYO CALLINGの時と変わらないが、その時の何倍も広い会場であっても金田の歌声は実に伸びやかに響いているし、だからこそこの日の出演者の中では群を抜いて文学的な歌詞の一語一句がその情景を頭の中に浮かび上がらせてくれる。
そのまま谷崎の美しいヴァイオリンと金田によるサビの
「行かないで」
のリフレインが切なく響く「大人と子供 (初夏のテーマ)」に続くという流れも同様であるが、金田は今のこのバンドのキャパを考えたらかなり広い会場、ステージであるにもかかわらず、いつもの下北沢のライブハウスでのライブと同じようにマイクスタンドから離れて肉声で
「ジュンさんもバンドやった方がいいよ。こういうイベントを開催するのもいいけど、バンドをやった方がいい」
という言葉がマイクを通さずともしっかり聴こえるというのは金田の喋る声量の大きさと、声を出せないことによる客席の集中力ゆえと言っていいだろう。
そんな言葉の後に演奏されたのは、バンドを代表する名曲「砂男」の続編である「砂男II」。随所にオリジナルバージョンのフレーズなども含まれた歌詞が、今のTHEラブ人間のものとしてリアルに響いてくる。それは希望だけに溢れていた若者だった時代を超えて、メンバーチェンジなどの様々な経験をしてきて今なおこうしてこのバンドであり続けているからこそ歌えているとでもいうような。
「ジュンさんどうせその辺(客席前方)で見てるんでしょ?(笑)
俺は今までいろんなものにガッカリしてきた。国や政治や社会や友達とか。でも音楽だけは俺をガッカリさせなかった。それがどういうことだかわかるか?それは今こうして目の前にいるあなたやジュンさんもガッカリさせたくないっていうことだよ!
13年目にして初めてのクラブチッタのメインステージ。今まで2回はDJブースだった。こうしてこのステージに立たせてくれてありがとうございます!」
と村上春樹を愛読する文学派の金田が独自の言語感覚で感謝の言葉を口にすると、
「こんなことにもならなきゃ
気づかない馬鹿たれなんです。ぼくは。
いつもごめんね。いつもありがとね。」
という歌詞が今目の前にいてくれている人に向けてのものであるかのように響く「砂男」を、マイクスタンドごと上手の方に持って行って歌う。それは主催者がその近くでライブを見ていたからなのだが、このバンドのメロディを彩るキーボードを弾いていたツネ・モリサワも含めたメンバー全員での
「砂男になるなら
…なりたくない!!」
の大合唱が響き渡ると、最後の
「やっぱりあんたらなしじゃ生きられないや」
というフレーズもまた目の前にいる人に向けて歌われているかのようで、演奏が終わると大きな拍手に包まれていた。アウェーなようにも感じていたが、その音楽と言葉でもって、もはやここにいる全員がTHEラブ人間のライブを見に来ていたかのようにこの場を持っていっていた。
そうした、バンドの規模以上の大きな会場に出てライブをして、その場を掻っ攫っていくという感覚を前にも経験したことがある。かつてTHEラブ人間がメジャーデビューした直後に所属していたビクターが開催した、くるりなどのレーベルの先輩が出演していた、Zepp DiverCityでのイベント。
その時にも完全にアウェーな空気だったのを、ライブが終わった時には完全に塗り替えていた。あの時、このバンドはいずれこの規模でワンマンをするようになるだろうなという予想は今のところ当たっていない。それでも、こうしてバンドを続けていればそれが現実になる可能性もあるし、こうしてまた大きな会場でのライブを見ていると、やっぱり今でもそこまで行けるライブをしているバンドだと思えるのだ。
リハ.東京
リハ.ズタボロの君へ
1.新曲
2.大人と子供 (初夏のテーマ)
3.砂男II
4.砂男
17:35〜 打首獄門同好会
この日も未だ療養中の河本あす香(ドラム)はバンド側が用意したスクリーンの下の療養ブースに座っているのだが、そのブースのテーブルにはサンプラーが置いてあり、今までのライブだったら観客が一緒に歌っていた「日本一!」などのフレーズが発せられるようになっている。もちろん歌という意味でもステージにいてもらわないといけないメンバーであるが、今の自身の状態でもできることを模索しながら増やしていっている。それは同時にまだドラムを叩くまでには時間がかかるということでもあり、この日もサポートドラムはthe telephonesの松本誠治である。
このバンドのライブ自体は月初にぴあアリーナで行われた、ぴあフェスでも見たばかりなのだが、ぴあフェスでは出番が割と前半であり、しかも全席指定だったので転換中などは椅子に座れるという休憩を挟むことができたのだが、クラブチッタというこの日の会場名も映像内に導入した「新型コロナウイルスが憎い」で始まったこの日はフェスももう終盤であり、トップバッターのオメでたい頭でなによりの動員を見ていても、開演からすでに5時間くらい立ちっぱなしの人たちばかりである中で、「足の筋肉の衰えヤバイ」ではそんなすでに足に疲労が蓄積しているであろう観客にスクワットをさせるという拷問のようなパフォーマンスを展開していく。正直、ぴあフェスの何倍もスクワットをするのがキツかった。そんな状態で大澤会長(ボーカル&ギター)がジムに行って鍛える映像が流れる「筋肉マイフレンド」を演奏されても、いや、もうスクワットだけで充分ですと思わざるを得ない。
そんな大澤会長はこの日はサポートドラムの誠治を
「the telephonesで活動しながら、大宮でまぜそば屋を経営していて、さらにこうして我々のサポートもやっていただいている」
と多忙っぷりを紹介すると、さらに「DISCO!」と誠治に向かって叫ぶのだが、
「ただ、本当は彼はこう思っているのかもしれない」
と言って「はたらきたくない」を演奏するという身も蓋もないことを言い放つ。こうした曲への繋ぎの上手さもまたこのバンドのライブの楽しさの一つである。
河本がしまじろうのぬいぐるみを手に装着する「カンガルーはどこに行ったのか」ではそのしまじろうやカエル、フテネコなどのキャラクターが登場する映像についつい見入ってしまう中で、ぴあフェス同様に主題歌になっているアニメがNetflixでも放送しているが、Netflixはオープニングとエンディングを飛ばすボタンがあるためにテーマ曲を聴いてもらえないという切ない事情を口にしてから演奏された「シュフノミチ」ではMOSHIMOの岩淵に目標の女性と評されたjunko(ベース)と河本のボーカルがラウドなサウンドに絡み合って響いていく。
で、このバンドの時間の後半ではすでに18時を回っている。休みなくライブを見ている人たちにとっては夕飯の時間であるが、まぁライブを見ていればそうした空腹であることを忘れてしまうのだけれど、このバンドはここに来て
「声が出せないからこそ、とびきりの手拍子で。三三七拍子を!」
と言ってその三三七拍子が
「カツオのタタキ!」「マグロの刺身!」
というフレーズに合わせて鳴らされ、その料理がスクリーンに映し出されることによって忘れかけていた空腹感を呼び覚ましてしまうと、最後にはやはり河本がサンプラーを駆使して声が出せない観客の合唱を演出する「日本の米は世界一」では様々な丼物の映像が映し出されるという、完全に空腹にトドメを刺される締め方でロックシーン屈指の飯テロバンドとしての強さを改めて感じさせてくれるのだが、客席では先日のぴあフェスで同じ日に出演し、「振ってもいい協定を結んでいる」と言われていたレキシの光る稲穂を振る観客も出現。レキシの存在を知らない人が見たら、あの光るアイテムを買いに打首の物販に行ったらそんなものが全く売られておらずに「どこに売ってるんだあれは!?」と謎に思ってしまわないかという至極どうでもいいようなことを心配してしまうようになってしまったくらいに、このバンドに思考が侵されつつある。
リハ.私を二郎に連れてって
1.新型コロナウイルスが憎い
2.足の筋肉の衰えヤバイ
3.筋肉マイフレンド
4.はたらきたくない
5.カンガルーはどこに行ったのか
6.シュフノミチ
7.島国DNA
8.日本の米は世界一
18:30〜 四星球
転換中に私服のままでサウンドチェックをしにメンバー4人が出てくると、
北島康雄(ボーカル)「何分からやっけ?」
まさやん(ギター)「25分から」
北島「え、今もう27分やん!四星球始めます!(笑)」
まさやん「時間押してんねん!(笑)」
北島「時間押してるなら安心してできるな(笑)」
まさやん「押してたら押していいみたいなんないから!(笑)」
北島「みんな行ける!?」
U太(ベース)「俺はどっちでもいい」
北島「どっちでもいいってなんやねん!モリスさんは?そういえばモリスさん、打首と結構一緒にライブやってるのに、サポートドラムに全く声かからないですよね(笑)」
モリス(ドラム)「それ気にしてんねんから言わんで!(笑)」
と、さすがコミックバンドというか、もはや開演前からネタを披露しているかのような四星球。しかしながら時間が押してる中でもサウンドチェックとして曲を演奏して、しっかり準備をするためにステージを掃けて行っただけに、どんなことをしてくれるのか期待が高まる。
本編では
「JUNE ROCK FES開催を祝って、豪華なミュージシャンたちが来てくれました!」
というアナウンスが流れ、北島は段ボール製のサックスを持った東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦、まさやんは同じく段ボール製の天使デザインのギターを持ってサングラス着用でカツラを被ったTHE ALFEEの高見沢、モリスはDJブースとともにSEKAI NO OWARIのDJ LOVE、U太はTRFのSAMに扮してキレの良いダンスを踊るという出で立ちで、特にまさやんの高見沢は全く似ていなすぎてそれだけで笑いが起こる中、そのまさやんを称える「鋼鉄の段ボーラーまさゆき」で早くもサングラスを取ってメガネという通常の姿になり、普通に自分のギターを弾くことによって、より一層見た目が誰なのかがわからなくなるのだが、北島は段ボールのサックスを吹くフリをして全く歌わず、曲中の
「竹田!」
のフレーズに合わせて、
「サックス吹くのは武田真治の方だった、ってバカやろう!(笑)」
とセルフツッコミを入れつつ、ステージ袖からカメラマンをステージに引っ張り出してきて踊るようにしたり、観客にエアギターをさせる際にSAMのように回りながら弾かせたり…と1曲目からネタを詰め込みまくるだけにめちゃくちゃに情報量が多い。
そんなネタを詰め込みまくりながらも曲間では
「声も出せないモッシュもダイブもできない僕が客席に飛び込むこともできない!そんなライブハウスで何ができるのか!それ以外全部できる!テレビで見てる人よ、これが今のライブハウスだ!」
と言ってエモーションが爆発するような「クラーク博士と僕」に突入していく。そこには
「コロナ禍になってから1番ライブをやってきたバンド」
という矜持、最もいろんなライブハウス、ライブ会場に足を運んできたバンドとしての矜持を感じられたのだが、そんな熱さの中でもまさやんは高見沢ギターを高く空中に投げてキャッチに失敗するも自分のギターは見事にキャッチする、北島はフラフープを見事に回してみせるという、ロックバンドの熱さではなくてそれはコミックバンドとしての熱さである。そしてそのライブハウスの中に今我々がいる。四星球はこの我々の姿を見てくれと言っている。その思いを絶対に裏切ってはいけないと思うし、ルールを破るようなことを絶対にやってはいけないと思う。
最近のライブではよく新曲もやっているということで、この日は森高千里の名曲「私がオバさんになっても」のアンサーソングを勝手に作ったという「君はオバさんにならない」を披露。
このフェスの主催者はLOVE MUSICのプロデューサーでもあり、LOVE MUSICには森高千里が出演しているということで、この曲が出来た段階でLOVE MUSIC出演決定だという。これでLOVE MUSICに出れなかったら「渡良瀬橋」に対抗して「明石海峡大橋」という曲を作るというが、北島は歌い方もバラードの時のものに変え、原曲のフレーズも巧みに入れているあたりはこのバンドのコミックとしてではない、バンドとしての力量の高さが感じられる。
そして今まではオールナイトで開催されていたこのフェスが今年はオールナイトではできないが、
「今年はオールナイトがない。人間生きていたらどうしても越したくない夜がある。だけど、これを見て自分が悩んでることもバカバカしいなと思ってくれたら、それだけでオールナイトだ」
という言葉とともに、終わった時にはJUNE ROCKならぬJUN SKY WALKER(S)の「すてきな夜空」が似合う夜になっているはず…というMCをしていたら、なんと北島の靴底が剥がれるというアクシデントが発生し、
北島「オールナイトじゃないから、このパーティーが終わる前にシンデレラにこの靴底を持っていきます!(笑)」
まさやん「(カツラを被って)王子様です!(笑)」
とすぐさまネタにできるあたりの反射神経はさすがであるし、きっとシンデレラはこの後に出てくるのがバックドロップシンデレラであることにかかっている。どんなことが起きても動じない経験を重ねてきているバンドとしての強さをこうしたパフォーマンスから感じることができる。
そうして「妖怪泣き笑い」に突入していって、観客を一度座らせてから飛び跳ねさせると、最後はやはりこうしたライブハウスを称えるための「ライブハウス音頭」で締めるのだが、その際に何故かエレファントカシマシ「俺たちの明日」の
「さあ頑張ろうぜ」
のフレーズを一瞬だけ入れたかと思ったら、JUN SKY WALKER(S)「すてきな夜空」とともに、スカパラ「星降る夜に」、THE ALFEE「星空のディスタンス」、TRF「寒い夜だから…」、セカオワ「Dragon Night」と、この日のコスプレしたアーティストたちの持つ夜の曲が次々に流れて、夜に終わるJUNE ROCK FESであるという回収をすると、サックスがJ、DJ LOVEの頭の飾りがU、SAMのポーズがN、高見沢のギターがEで「JUNE」の文字を作ってから、北島は靴底を山口百恵ばりにステージに置いて去っていくという、このバンドの天才集団っぷりを感じざるを得ないエンディングを作り上げた。フェスの30分の出番のためにここまで時間や労力やネタを注ぎ込むというバンドの姿勢には本当に最敬礼せざるを得ない。これからもいろんな場所でそうしたライブを見ることができる状況になりますように。
リハ.ギンヤンマ
1.鋼鉄の段ボーラーまさゆき
2.クラーク博士と僕
3.君はオバさんにならない
4.妖怪泣き笑い
5.ライブハウス音頭
19:25〜 バックドロップシンデレラ
このメンツが集まった中でのこの日のトリを任されたのは、バックドロップシンデレラ。決して若手と言えるような立ち位置の存在ではないが、この状況になったことによってシーンにおける存在感がより強くなっているバンドであることに間違いはない。
本編開始時間になって暗いステージに明かりが射すと、すでにそこには豊島”ペリー来航”渉(ギター&ボーカル)、アサヒキャナコ(ベース)、鬼ヶ島一徳(ドラム)の3人がスタンバイしており、渉はギターを弾きながら、
「毎日毎日主催者のジュンさんは思いが純粋過ぎて嫌になっちゃうよ」
と、おなじみの「およげ!たいやきくん」の替え歌を歌い始め、
「なんでこのメンツで我々がトリなのかと思ったら、「コロナでみんながウンザリしてるから、ウンザウンザで元気付けて欲しい」と言われたら、それはやるしかないだろう!」
と気合いを入れるようにすると、相変わらず身軽という言葉がこんなに似合う存在もなかなかいない機動力を発揮してステージに飛び出してきた、でんでけあゆみ(ボーカル)が「2020年はロックを聴かない」でスタートするのだが、こうして2021年にはロックバンドが集まってライブができているという現場にいられることによって、この曲のフレーズがより感慨深く突き刺さってくる。
おなじみの「フェスだして」では観客も踊りまくる中で曲中には渉が打首獄門同好会「カンガルーはどこに行ったのか」を歌い始め、観客も腕を上げ下げするという、本家のライブで先程見たばかりの光景が広がるのだが、あまりに長く続けただけにアサヒが
「もうやめてー!(笑)」
と叫ぶことによって止まり、それならばとこのコロナ禍中にバンドが編み出した、合唱ではないハミング(口を開くことなく口ずさむことによって飛沫が飛ばない)を、
「今まで使ったことがないくらいに、腹筋が切れるくらいの高音で!」
と言って観客にさせると、サビのメロディを本当に原曲よりはるかに高いキーでハミングして、渉もあゆみも思わず爆笑してしまうくらいに異様な光景が広がる。ただでさえ耳から離れなくなるようなこの曲での、この状況だからこそできる楽しみ方をこのバンドはすでに見つけているし、そこに
「テンション上がっても絶対口を開けないように!」
と注意喚起することも忘れないし、
「クラブチッタは3週間前にも来たんやけど、その時はTHE冠の主催するメタルイベントで、冠さん以外のメタルの人が怖かった(笑)
でも今日は周りがファミリーみたいなバンドばかり」
ということで、最もファミリー感のある打首の曲を歌ったりしたのだろう。渉の出で立ちも人によっては怖く見える気もするけれども。
そんなボーカル2人の掛け合いも楽しい「免許とりたい」から、そのボーカルの歌うメロディの美しさを楽しさと激しさの中にも確かに持っていることを示すような「8月。雨上がり」という曲でただ踊りまくるだけではない部分も見せながらも、「台湾フォーチュン」からは渉のスカ的なリズムのギターを軸にした曲で、このライブ、このフェスのクライマックスとばかりに踊らせまくる。妖艶な魅力を放ちながらもうねりまくるベースを弾くアサヒ、実は正確無比かつ豪快さも併せ持ったスーパードラマーであることがライブを見ればすぐにわかる鬼ヶ島と、その踊りまくれる軸にあるのはリズム隊2人の強さによるものだろう。
するとここで珍しくあゆみがマイクを持って観客に語りかける。要約すると、この日のリストバンドに主催者が一つ一つ手書きでJUNE ROCK FESという文字を書いたこと、それをできれば持って帰って思い出として振り返ることで日々を生きるための力にして欲しい、もし捨てる人は写真に撮って見返して欲しい、ということだったのだが、おそらくは喋ることを事前に整理してから美味しい部分をちゃんと伝えることができる渉(それはファミリーの大澤会長もそういうタイプ)とは違って、あゆみはむしろその時に自分の思っていることをそのまま素直に口に出さざるを得ないという不器用な人間である。でもそんな人間がそれでもなんとかこのフェスを開催している人の思いを伝えるべく必死に言葉を紡いでいる。だからこそ伝わるものが確かにあったのだし、
「初めから来てる人はわかってるだろうけど、今日はダブルピースから始まったんやろ!?」
と言って、ファミリーの1組であるオメでたい頭でなによりのダブルピースをここで掲げさせる。そのことによって、オメでたから始まってバックドロップシンデレラで終わるというこの日の流れにしっかりとした意味と軸を持たせるものになっていた。
だからこそその後の「月明かりウンザウンザを踊る」から「さらば青春のパンク」という鉄壁な流れではやはり観客は踊りまくるとともにそこには笑顔が広がっていたし、思いっきり助走を付けてからジャンプするあゆみの驚異的な跳躍力を見て、SASUKEに出場してもらうか、跳び箱を何段跳べるか挑戦してもらいたい、ということすら思っていた。それはリストバンドに文字を書く姿を見ていた主催者への想いによって高く跳べていたのかもしれないけれど、このバンドのライブにおいて踊らないやつよりも踊るやつの方が偉いとされているのは、踊るやつの方が間違いなく楽しんでいるからだ、ということを示すかのような、様々な人の思いを背負った、トリに相応しいライブだった。これからきっといろんなフェスでこうしてトリを依頼されることが増えてくるはずだ。
1.2020年はロックを聴かない
2.フェスだして
3.免許とりたい
4.8月。雨上がり
5.台湾フォーチュン
6.月あかりウンザウンザを踊る
7.さらば青春のパンク
アンコールを求める拍手も起こっていたが、時間的な制約もあってアンコールをすることはできず、主催者の三浦ジュン氏が登場して終演の挨拶をした。そこには来年またオールナイトでこのフェスを開催できるように、という確かな希望が感じられた。
この日の出演者はコミカルな部分を持ったバンドたちばかりだ。もちろんそうした要素はライブの楽しさに繋がるものであるが、みんなただ面白いだけのバンドじゃない。熱いロックバンドとしての部分を確かに持っている。それこそがこのバンドたちをライブバンドたらしめている最も大きな理由であり、それぞれのバンド同士が共鳴する理由である。何よりも、我々がライブを観たいと思う理由でもあり、観ていて感動してしまう理由でもある。
このフェスの主催者はおこがましくも自分と似ている人だと思っている。しょっちゅう同じライブに行っているし、仕事どうこうとかを度外視して、もうこれがないと生きていけないからライブに行く、そしてそれが積み重なって年間百何十本もの本数になっているという生き方が。
で、そんな生き方をしている人がこれでもかというくらいにバンドたちに愛されていて、その愛情がこのフェスという形になっている。だから今ライブハウスがどんなところなのかを知らない人たちに見せたいライブハウスの景色はここそのものだと思う。主催者、出演者、参加者が音楽への、ライブへの、ライブハウスへの、それぞれへの愛を持って作っているフェス。来年、オールナイトで開催されて、朝までこの会場で遊べるようになっていますように。それは全く無理なことじゃないような希望を確かに感じていた。
文 ソノダマン