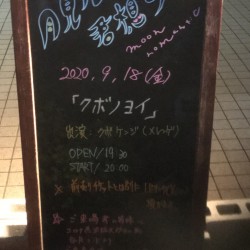リリースされたのは昨年だった。しかしUNISON SQUARE GARDENはいち早くコロナ禍のライブの自分たちなりのやり方を確立しながらも、この状況になったことによって「ライブに行きたくても行けない」という人を置いて先に進むことをよしとせず、過去のツアーのリバイバルツアーを回ることによって、バンドとして動きながらもこれまでを振り返るという手法を取り、より多くの人が来れる状況になるまでアルバム「Patrick Vegee」のツアーを開催しないことにした。
バンドに未来を見通す視点があったかどうかは定かではないが、緊急事態宣言も解除されて会場のキャパが少しではあるが緩和された(完売していたが追加でチケットも販売された)このタイミングでいよいよ「Patrick Vegee」ツアーが開催。すでに埼玉や栃木などを周り、そこで観た人が感嘆の声をあげたりしていたが、それが果たしてどんな理由によるものなのかを自分の目で確かめに行ける日が来たのだ。
来場者フォームへの入力と検温、消毒を経て場内に入ると、着いたのが開演時間の18時30分ギリギリだったために、すぐに開演前のアナウンスが流れるのだが、主催者が自己紹介しただけで拍手が起こるというのはここにいた人たちがどれだけこのライブを楽しみにしていたのかということを示している。それと同時にユニゾンファンの温かさも。
そのアナウンスが終わるとすぐに場内が暗転して、イズミカワソラ「絵の具」のSEが流れてメンバーが登場。暗闇ということもあってか、鈴木貴雄(ドラム)がやたらと白さが際立つコートを着ているという以外は斎藤宏介(ボーカル&ギター)の爽やかさも田淵智也(ベース)の挙動不審さも本当にいつものユニゾンの姿そのものである。
登場してそのままスッと斎藤は「Simple Simple Anecdote」を歌い始めるのだが、この立ち上がりからして意表をつかれるのは、アルバムの曲順では最後の曲の前、どちらかというと穏やかとも言えるサウンドの曲であるだけに、まさかこの曲からライブが始まるとは全く予想していなかったからである。
「全部嫌になったなんて簡単に言うなよ
全部が何かってことに気づいてないだけ
年月は重なって 恋をして交わるから
今日はなんとかなるぜモードでいいや
今日はなんとかなるぜモードでいいや」
という歌詞はどこかこのライブまで辿り着けた、この日まで生きて来れたことの感慨を斎藤のホールいっぱいに伸びるボーカルが我々に与えてくれるのだが、それはまさに「全部嫌になった」って思ってしまうことがたくさんあるのが人生だからであり、特に今の社会の状況だからだろう。しかしながら、
「僕の言葉がまた生まれる」
という曲の締めのフレーズは明らかに次の曲に繋がるためのものなのだが、ライブではその通りには行かないということをわからせてくれるのが、田淵がビュンビュン飛ぶようなサウンドのエフェクターを踏みながらコーラスをする「Hatch I need」でここから「Patrick Vegee」というアルバムの冒頭に至るからである。基本的にユニゾンは曲順も含めて「もうこれ絶対いじりようがないだろう」と思えるような形にしてアルバムをリリースするバンドであるが、それを自分たちで崩すことによって音源で聴いていた流れとはまた違った曲の感覚を受け取ることができる。ステージにスモークが焚かれているというライブだからこその視覚的な効果も含めて。
そのまま「マーメイドスキャンダラス」へと至る流れはそんな「Patrick Vegee」のアルバムの冒頭通りの流れなのだが、この辺りから明らかに田淵の動きがアグレッシブになっていく。それは曲がそうしたサウンドのものへと展開していくからであるのだが、「マーメイド」というテーマでの田淵のこの曲の歌詞はビックリするくらいに童話的だ。
早くも3人の鳴らす音のグルーヴの重なり合いの奇跡と神秘を感じさせてくれるのは、まさに斎藤が高らかに歌う、この日最初の曲である「Invisible Sansation」であるが、その斎藤の凄まじいまでの節回しは
「生きてほしい!」
というフレーズにたどり着く。この曲が生まれたのはこのコロナ禍になるよりもはるかに前であるが、今こうやって自分たちのライブに足を運んでくれる人たちに伝えたいこと、言いたいことがこのフレーズであるからこそ、この曲を演奏しているかのような。実際にこの曲、このフレーズを聴いたことが明日からの生きる力に繋がっていく人だって間違いなくいるはずだ。
ここでの斎藤の
「主催者が名乗っただけで拍手が起きるっていう…。今日の客はチョロいなって思いました(笑)」
という挨拶的かつ挑発的なMCはむしろ完全に褒め言葉だと言っていいだろう。自分たちのファンはそうしてライブを作ってくれている人にしっかり感謝を示せる人たちだということをわかってくれているのだから。
「Patrick Vegee」がリリースから1年以上経ったことによって、リリースツアーであってもむしろ体の中に馴染んでいるということを斎藤が言ったので、てっきりその体に馴染んでいるアルバム収録曲が演奏されるのかと思ったら、まさかの「フライデイノベルス」という「今この曲来るの!?」という選曲。サビでの鈴木の「ダンダンダダダン」という三連のドラムのリズミカルさが実にキャッチーかつ心地良いし、そのドラムを叩く鈴木の表情が実に笑顔であるがためにこちらもついつい笑顔にならざるを得ない。
その鈴木のドラムの手数が原曲の何倍にも、と言いたくなるくらいに劇的にリズムが強化された「カラクリカルカレ」では田淵はむしろステージを動き回るアクションが強化されているのだが、そんなバンドの進化が今になって初期曲を演奏することによってハッキリと感じられるのだが、そんな初期曲の後にはリリースされたばかりの「Spring Spring Spring」のリバイバルツアーの映像作品に特典ディスクとして収録された「Nihil Pip Viper」が演奏されるのだが、
「運命共同体ってオーバーオーバー過ぎるので
耳からスパゲッティで肘で茶沸かすわ」
という「なんじゃそりゃ」的な歌詞も含めてサウンドからも一聴して「カラフル」というイメージを感じた曲だったが、まさにカラフルというような照明が演奏している3人を照らし出すあたり、そのイメージは間違っていなかったんじゃないかと答え合わせできているような。それはこうしてライブで聴くことができるからこそわかることである。
どこかタイトルの語感がその「Nihil Pip Viper」と似ているから続けて演奏されたんだろうかとも思う「Dizzy Trickster」においても腕をクロスさせて叩きまくる鈴木のドラムの凄まじさにはついつい見入ってしまうのだが、そうして見入ってしまっていると、「Invisible Sansation」からは「Patrick Vegee」に収録されていない曲が続いただけに、自分が今何のツアーに来ているのかがわからなくなってしまう。それくらいにユニゾンが鳴らす1曲1曲にその都度飲み込まれてしまっているのが自分でもよくわかる。
そこまでは走り抜けるようなギターロックの流れが続いていたのがガラッと変わるのは、
「小林くん、番号教えてよ
浜崎さん、リボンかわいい」
というこれまた「何それ!?」な歌詞と重心の低いロックサウンドがアルバムの中でも異彩を放つ「摂食ビジランテ」で「Patrick Vegee」の世界に戻ってくるのだが、赤外線かのような真っ赤な照明にメンバーそれぞれが照らされたと思ったら、曲が終わりに向かうに連れてメンバーの姿は暗闇に包まれて見えなくなっていくという演出もまたこの曲の不穏さをさらに引き出すものになっている。
しかしながらそのまま曲間全くなしで「夜が揺れている」へと繋がっていくというライブアレンジはどうやったら思いつくのだろうか。確かにBPMとしても重心の低いロックサウンドとしても繋がる要素はあるのだが、数あるユニゾンの曲の中からこの曲を「摂食ビジランテ」に繋がる形で演奏しようと思い立ったメンバー(というか間違いなく田淵)の発想と実行力には恐れ入るというか、アルバムツアーでアルバムに入ってる曲と入ってない曲をこんなに自然に融合させることができるバンドが他にどれくらいいるだろうか。いや、なかなか普通はこんなことをやろうとすら思い付かないはずだ。
「秋の落ち葉と冬の澄んだ空気と君が嫌いだよ」
という歌詞を聴いていると、あまりに急に寒くなったことによって、嫌いと思えるくらいに今年は秋を感じられるのだろうか、とも思ってしまうけれど。
そんなユニゾンだからこその流れから、斎藤のノイジーでありながらもキャッチーなギターサウンドが、まるで季節が夏に巻き戻って、海辺の砂浜の上を追いかけっこしているドラマのような光景がその音から想起される「夏影テールライト」は数少ない「Patrick Vegee」の収録曲の中でもすでにライブで聴いたことがある曲だ。(8月のa flood of circleの主催ライブ出演時に演奏している)
その「夏影テールライト」は
「幻に消えたなら ジョークってことにしといて。」
と「Phantom Joke」に繋がることを示唆するようなフレーズで終わり、実際にアルバムではその直後に「Phantom Joke」に繋がり、ライブでその流れももちろん再現されて「さすがだな」と思うんだろうなと思っていたが、まさかの「Phantom Joke」に続かないとすぐにわかったのは、同期のオーケストラ的な華やかなサウンドが流れてきたからである。
それはもちろん「オーケストラを観にいこう」のイントロのサウンドなのであるが、メンバーの背後に姿を表したスクリーンには映像こそ映ることはないが、そこにオレンジ色の照明が当たることによって、まるで夕陽が燃える時間に連れ立ってオーケストラを観に行こうと歩いている2人の人間の姿が目に浮かぶようだ。決して派手な演出ではないが、だからこそひたすらにメンバーの鳴らす音から想起できる情景を強くするものとしての効果を担っていると言えるだろう。
その「オーケストラを観にいこう」を挟んでの「Phantom Joke」へ。素直に「夏影テールライト」からこの曲へと繋がらないというあたりがユニゾンならではの我々観客の期待や予想を心地良く裏切ってくれる部分であるが、田淵のアクションもより激しくなる中で斎藤のボーカルのひっくり返りそうな高さと速さのギリギリを攻めるというスリリングさもまたユニゾンならではのものであり、何回ライブで聴いても斎藤の凄まじさに恐れ入ってしまう。
その「Phantom Joke」が終わると一度斎藤と田淵がステージから捌けて、ワンマンではおなじみの鈴木のドラムソロが始まるのだが、ひたすらに手数の多さと鳴らす音の強さを見せるという内容であるために、突飛なアイデアを見せているわけではないのだが、その鬼神のようなドラムはもはや脳が指令を出しているというよりは、体がひとりでにドラムを叩きまくっているとすら思うくらいに体とドラムが一体化している感すらある。合間にここまでで1番大きな拍手が湧き上がっていたのがその凄さの証明とも言えるだろう。
斎藤と田淵がステージに戻ってきてもさらに鈴木のドラムを起点としたセッション的な演奏は続き、鈴木のカウント(もはやシャウト)を合図にして向かい合った3人が次々にキメを打ちまくる。それがバンドの演奏と観客のテンションをさらに高めてくれ、そのまま「Patrick Vegee」のリード曲であり、MV公開時からファンに衝撃を与えた「世界はファンシー」へと突入していくのだが、その衝撃は「こんな曲どうやって歌うんだよ」というくらいのスピードで詰め込まれた歌詞によるものが大きいのだが、それがライブであることによって、ここまで演奏してきたことによってさらに速いものになっている。斎藤が緑、田淵が青、鈴木が紫と、メンバーに合わせたのかそうでないのかはよくわからないが、それぞれに当てられた照明が実に鮮やかに3人のキャラを照らし出している。
あまりにその「世界はファンシー」が速すぎ&詰め込みまくりだっただけに、イントロが鳴らされた瞬間に遅くすら感じてしまったのはユニゾンにとっての憧憬であるバンドのことをタイトル、テーマにした「スロウカーヴは打てない
that made me crazy)」であるが、この曲の間奏で斎藤がギターソロを弾くと、そこにかすかに「オリオンをなぞる」のイントロを入れるというファンサービス的なマッシュアップをし、ついついニヤリとしてしまうが、それくらいに「オリオンをなぞる」のイントロの記名性が強いということでもある。
しかしながら「世界はファンシー」もまたアルバムでは
「Fancy is lonely.」
と「弥生町ロンリープラネット」へと繋がるフレーズで終わるだけに、アルバムを初めて通しで聴いた際にはその独立した曲同士をさりげなく繋いでみせるというのを連発するバンドの発想と手腕に「これは凄いな!」と思わされたものであるが、ライブにおいては全くその我々の「凄いな!」を「世界はファンシー」の後に「スロウカーヴは打てない (that made me crazy)」を演奏することによって、また違う「凄いな!」に変えてしまう。それを3人が鳴らす音のみでそう思わせてくれるユニゾン自身が何回言っても足りないくらいにやっぱり凄い。
ただ「弥生町ロンリープラネット」はライブ終盤の畳み掛けていく展開の中では入れづらい曲なのだろうか、とも思うのはライブ後にこうして改めて振り返ってみてこそ思うことであって、田淵が思いっきり高く足を交互に上げたり、テツ and トモの「昆布が海の中で出汁が出ないのはなんでだろう」を思わせるような動きをしたり、斎藤の真後ろにまで行ったりと、フィジカル的な激しさは「天国と地獄」によってピークを迎え、ライブを見ている時にはそんな冷静に分析している暇もないくらいにキラーチューンが押し寄せまくってくる。
それは過去のツアーと全く同じセトリというコンセプトで回ったリバイバルツアーでは当然ながら演奏されていない、今やユニゾンの最大の代表曲と言える曲だけれどワンマンで聴くのはライブ回数から比べたら久しぶりな気もする「シュガーソングとビターステップ」もそうであり、田淵がイントロで客席に指を差しながらピタッと静止する様も、観客が席の間隔がかなり狭いこの会場の客席で飛び跳ねまくっているのも、ロックバンドのライブの楽しさが詰まりまくっているし、その感情をバンドと観客で交換し合っているかのようですらある。
斎藤が
「ラスト!」
と言ってそんな場であったこの日のライブの最後に演奏されたのは「Patrick Vegee」の最後に収録されている曲である「101回目のプロローグ」。タイトルからしても昔のドラマから着想を得ているのは間違いないだろうけれど、
「君だけでいい 君だけでいいや こんな日を分かち合えるのは
きっと拙いイメージと でたらめな運命値でしか 描き表せないから
君だけでいい 君だけでいいや いたずらなプロローグを歌ってる
約束は小さくてもいいから よろしくね はじまりだよ」
というサビのフレーズはこうして1日を締め括りながらも新しい始まりを感じさせるものになっており、
「ごめん 全然聞いてなかった 大好きなメロディーがありすぎて
後悔はしてないから 知らないままで遊びに行こう
魔法が解けるその日まで」
というその後に続く歌詞はユニゾンというバンドのメロディの魔法にかかり続けている我々がまさにライブの最後に思っている心境をバンドが理解していて、それをそのまま歌詞にしたかのようですらある。このわからずやには解けない魔法にこれからもかかっていたいし、それはきっとこうして3人がステージに立ち続けている限りは解けそうもない。
アンコールですぐさま3人が再びステージに登場すると、斎藤は感染対策に協力してくれているからこそこうしてライブができているという感謝を告げてから、
「やるか」
と演奏を始めようとするのだが、鈴木がドラムのライザーの端に座り込んでいて始められる状態ではなく、
斎藤「なんでそんなとこに!?(驚いたような表情で)」
鈴木「人の視線に疲れたから(笑)」
と言いつつ、「Patrick Vegee」の物語を「101回目のプロローグ」で終わらせたことによって、「crazy birthday」で盛大にアンコールの始まりを鳴らすのだが、この曲はユニゾンの中ではもはや珍しいくらいにコール&レスポンスと言ってもいいフレーズがあるのだが、当然今は観客が歌うことはできず、田淵と鈴木がコーラスで斎藤に返すという形だ。しかしそれが全く違和感がないというか、あるべき姿であるかのようですらあるのがそうした一体感をバンド側が全く求めてくることがなかったユニゾンらしい部分である。
間奏では斎藤がステージ前に出てきてギターソロを弾くのだが、割と近い位置で見ていると斎藤は本当に体が細く見える。初期の頃の映像を見ると実は髪型も含めた出で立ちはその頃からは結構変わっているし、それはまだユニゾンのボーカルとしてかくあるべしという今のスタイルが定まっていなかったからかもしれないが、現在の若々しさはこれから先も全く変わる気がしない。それはもちろん斎藤だけではなく田淵と鈴木もそうである。
「絶好球 絶好球を 引っ張って 引っ張っちゃうのは
常時の稽古並々じゃないんです 当たり前と思うな素人!」
というフレーズでの「絶好球」はスロウカーヴではないだけに速球系のボールなんだろうなということがタイトルも通じている「スロウカーヴは打てない」で察することができる部分である。
さらには「オトノバ中間試験」では田淵が演奏中に斎藤の足元に座り込んでベースを弾き、斎藤はその田淵の姿をちらちら見ながら歌うという地味に面白い光景が展開される。お互いにちょっかいを出すことがないというのは両者の絶妙な距離感を示しているようでもあるのだが、立ち上がった田淵はサビのコーラスにギリギリ間に合うというあたりもまた絶妙である。もはやそのコーラスはボーカルと言ってしまってもいいくらいのレベルで声が大きいものになっているけれど、それこそが
「楽しいを答え合わせ」
のフレーズのバンドからの回答なのだろう。こんなに楽しいのならばいくらでも追試を課していただきたいくらいだ。
そして斎藤が本編同様に
「ラスト!」
とだけ言うと、同期の壮大なシンフォニーを使った「春が来て僕ら」が演奏される。ユニゾンはそもそも季節に合わせた選曲というのをほとんどしないバンドではあるけれど、今と真逆と言ってもいい遠い春の曲をこうして最後に演奏したのは、きっとこのコロナ禍を抜けて音楽シーンやライブシーン、それらを愛する我々にもきっと春は来るという願いを込めているかのようだった。それは来年の春が来た時には、と思うくらいに希望を抱かせるような温かさと強さに満ち溢れたものだった。去り際に鈴木が腕を上げるだけですんなりと去っていったのも含めて。
斎藤はMCで
「こういうライブをできるのは僕らがライブを続けてきたから」
というようなことを言っていた。その通りで、去年の早い段階からライブをやり始め、しかも地方までしっかりと回るという、ライブの見方や楽しみ方は変わってしまっても、バンドのやることは変わらない。だからこそライブを重ねていくことによって曲がより自分たちのものになり、ブランクなんて言葉とは無縁なくらいに進化し続けることができる。そんなバンドはそうそういないけれど、日常の中にロックバンドのライブがあり続けているということ。それを今のユニゾンは自分たちの演奏する姿で示している。
そしてユニゾンのファンの方々はネットリテラシーが非常に高いので、ライブを見終わった後に「凄い」「ヤバい」とは言いながらも、ライブ自体の具体的な内容に触れるようなことはしない。それはユニゾンがツアー内でセトリを変えることをしない(それも各地が公平になるようにというバンド側からのファンへの配慮だ)だけに、ネタバレをしたらガッカリしてしまう人がいることをわかっているからだ。
であるにもかかわらず、つまりはツアー内でセトリが変わることはないということをわかっている人たちが、このツアーにすでに参加しては「もっと見たい」、あまつさえ「全通したい」と言う人すらいる。それはユニゾンが鳴らしている曲と音だけで、仮に内容が同じでも(同じライブは2度とないけれど)、何回でも見たいと思ってしまうようなライブができているバンドだということだ。
そういうバンドのことこそ、「ライブバンド」と称するべき存在なんじゃないかと思っている。
1.Simple Simple Anecdote
2.Hatch I need
3.マーメイドスキャンダラス
4.Invisible Sansation
5.フライデイノベルス
6.カラクリカルカレ
7.Nihil Pip Viper
8.Dizzy Trickster
9.摂食ビジランテ
10.夜が揺れている
11.夏影テールライト
12.オーケストラを観にいこう
13.Phantom Joke
ドラムソロ
14.世界はファンシー
15.スロウカーヴは打てない (that made me crazy)
16.天国と地獄
17.シュガーソングとビターステップ
18.101回目のプロローグ
encore
19.crazy birthday
20.オトノバ中間試験
21.春が来て僕ら
文 ソノダマン