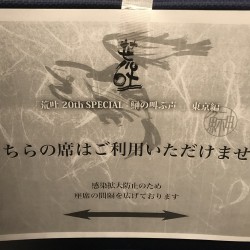何かと今年はRADWIMPSのファンにとっては苦しいというか、厳しい1年だった。野田洋次郎(ボーカル&ギター)は次々に週刊誌にコロナ禍の行動を撮影され、さらにはギターの桑原彰の不倫までもが明るみになったことによって、バンドはリリースされたばかりのアルバム「FOREVER DAZE」のツアーを桑原が参加しない形で開催することを発表。
山口智史(ドラマー)が病気でステージに立てなくなってからも3人の結束と鋼の意志でバンドを動かしてきただけに今回の選択は苦渋の決断であっただろうけれど、このライブに臨む感覚はその智史が参加出来なくなった「胎盤ツアー」の時と似ている。
消毒と検温を経てぴあアリーナの中に入ると、近年のRADWIMPSのライブではおなじみの、席は場内に入ってからわかるというシステム。これはQRチケットだからこそできることでもあり、ステージに近い席を高額で譲ろうとする転売対策としても機能していると思われる。
このぴあアリーナは今回のツアーの開幕地点であるのだが、この日は2daysの2日目の日曜日ということでちょっと早めの開演時間の17時30を少し過ぎたあたりでステージの奥からは気合いを入れるメンバーたちの(おそらく円陣を組んだと思われる)声が聞こえてきて、その時点でまだ暗転もしていないのに拍手が起こり、椅子から立ち上がる人すらもいる。バンド側も観客側もこのライブを本当に楽しみにしているということがこの時点で伝わってくる。
場内が暗転して、壮大なSEが流れるとメンバーがゾロゾロとステージに現れているのがわかるのだが、いざ照明が点くとその瞬間に光がきらめく「TWILIGHT」の演奏が始まり、エフェクトがかかった洋次郎の声とともにデジタルサウンドが広いぴあアリーナの客席に響いていく。
ステージには両サイドにドラムセットがあり、下手はもはやおなじみの森瑞希、上手は昨年から参加するようになった若手のエノマサフミで、洋次郎と森の間には武田祐介(ベース)が、洋次郎とエノの間には2人のギタリストが。そのギタリストのうちの1人は、本来なら桑原の役割だったであろう、タッピングを華麗に決めまくるTAIKING(Suchmos)で、フォーマルというよりは厳かな衣装に身を包み、ギターだけでなくシンセも操るショートカットの女性は沙田瑞紀(miida / ex.ねごと)。図らずも5人中2人がミズキという名前のメンバーになっているのだが、早くもその2人のギタリスト(というよりマルチプレイヤー)の存在によって洋次郎が自由にステージ上を歩きながら歌えていることがわかる。メンバーも愛す「ONE PIECE」とのコラボによって生まれた曲であるのだが、
「「永遠」なんかにはさ できやしないことが 俺らん中で今 飛び跳ねてんだ
渋滞起きた奇跡 両手広げ待っててよ未来」
「「俺たちならいけるさ」なんて グラッグラな星ではしゃごうか
分かってるそんな甘くないって 「だからなに?」って言える今を「アイス」」
「永遠に生きたって飽きるでしょ うまいことできてる
絶滅前夜に手をとる 君と越えていくよ
明日を迎えにいこう」
という非常に強い歌詞の一つ一つがそのままRADWIMPSの今の決意表明であるかのように響いてくる。早くもステージ両サイドの巨大なLEDビジョンにはメンバーそれぞれが演奏する姿が映し出されているのだが、心配したところもあったけれど、こうしてたくさんの人の前でステージに立っていることを楽しんでいることが心から伝わってくる。
洋次郎がギターを手にすると、「FOREVER DAZE」の中では唯一と言っていいくらいのストレートなギターロックサウンドの曲である「桃源郷」へ。ドラムのキックのリズムに合わせて観客が手拍子することで、その音すらバンドの推進力になっているかのようであるが、やはり
「僕の桃源郷はとうせんぼうで 当然今日も外、視界ゼロ
でも 君となら息を止めても 怖くもなんともねぇないんだよ」
という歌詞にはバンドとしての決意が強く感じられる。
というか「FOREVER DAZE」というアルバム自体がコロナ禍に制作されたものであるだけに、当然ながら歌詞にはそのコロナ禍の世界を生き抜いていくためのメッセージが込められているのだが、それはそのまま今のRADWIMPSがこうしてライブを行って生きていくというメッセージとなっている。だからこそ今こそ鳴らされるべき曲であると思えるし、その鳴らされているすべてに100%で応えたいと思う。
すると「ここでこの曲?」と思うくらいにクライマックス感が強い「ドリーマーズ・ハイ」が洋次郎がステージ前の花道を歩き出しながら早くも演奏され、しかも早くもここで銀テープまで飛ぶことによって、すでにライブはクライマックスを迎えているのか?とすら思ってしまうのだが、体をよじりながらタッピングを決めまくるTAIKINGの姿を見てすでに涙が出そうになっていた。
常々「仲間」の存在を何よりも重んじてきた彼のバンドSuchmosにとって、メンバーのHSUの急逝というは立ち直れないくらいの出来事であってもおかしくない。そんな経験をしたばかりのTAIKINGがこんなにも笑顔を見せながら、自身の持てる力を全てRADWIMPSとそのファンのために使ってくれている。その姿に彼の自分に頼んでくれるなら何があっても全力でやり遂げてみせるという人間性と、ミュージシャンとしての矜持を感じて泣きそうになってしまった。
スタートが「TWILIGHT」であっただけに、「FOREVER DAZE」のオープニング曲であり、ホーンのサウンドが同期音として流れる「海馬」はここで演奏される。基本的にメンバーはほぼ横一列に並んでいるという、バンドとしては珍しいフォーメーションなのだが、それは洋次郎の真後ろにピアノがあり、洋次郎が時にそれを弾きながら歌うということが、実際に洋次郎がこの曲の後半でピアノを弾く姿を見ることによってわかる。
すると早くも洋次郎が
「皆までは言わんけど、今回のツアーは桑原が参加していないので…」
と桑原のことを少しイジり(前日はもっと盛大にグチったとのこと)、客席からもクスッとした笑いが起こる中でTAIKINGと沙田のことを紹介し、
「声は出しちゃいけないけど、それで縮こまって楽しめなかったら本末転倒だから」
と観客をリラックスさせる。決して声を出していいと言っているわけではなくて、確かに楽しむためにライブに来ているのに、そうしてビクビクしていたら楽しめないし、何よりもRADWIMPSのライブの魅力を見失ってしまう。そんな我々の緊張を解き解そうとしてくれているようだった。
するとステージには同期のリズムのサウンドが流れ、エノもTAIKINGも沙田もリズムに合わせて飛び上がるように観客を煽るのは「カタルシスト」で、洋次郎とともにTAIKINGも沙田もステージ両サイドに伸びる通路まで歩いて行って演奏する。それはもはやサポートの範疇をはるかに超えた、RADWIMPSのライブを一緒に作っている一員とも感じられるし、実際に曲最後の一気に疾走するようなパートでは率先して観客を煽るように手を叩く。前日のライブを見た人の情報によって2人が参加しているということを知った時はもしかしたら違和感を感じてしまうかもしれないと思ったけれども、新鮮さを感じることはあっても違和感を感じることは全くない。もちろん桑原の姿を見れないのは寂しいけれど、その寂しさを演奏中は感じさせないようにしてくれているというか。
すると洋次郎がピアノでの弾き語りのように歌ってからバンドの演奏になったのは「DARMA GRAND PRIX」なのだが、何故だか自分のTwitterのフォロワーさんにはこの曲を演奏するのを熱望する人が非常に多いために、実際に演奏された時に少し笑いそうになってしまった。間奏での森とエノのバトル的なドラムソロも含めて、確かにライブでこそその真価を発揮する曲であるが、数あるRADWIMPSの名曲の中でもピンポイントにこの曲を熱望するとは、という。
そうしたこれまでもライブを彩ってきた曲も挟みながらも、まだほとんどの人がライブでは初めて聴く「FOREVER DAZE」の曲が次々に演奏されていく。
CMソングとしてサビの一部がオンエアされていた「MAKAFUKA」は両サイドのLEDに加えてステージ背後にもLEDが現れ、そこに巨大な木の映像が映し出される。その木の周りで生命が生まれて育まれていくような物語を見ているような気持ちになるのはこの曲の
「この宇宙が今まで観てきた悲しみや痛みのすべてを
知ってるかのような君のその涙はなに」
という神の視点へと疑問を投げかけるような歌詞によるものであるが、ハンドマイクを持って花道を歩きながら歌う洋次郎のボーカルが少し不安定であるようにも感じたのはこの曲の難易度の高さによるものだろうか。というかRADWIMPSの曲は基本的に歌うのが実に難しい曲ばかりではあるけれど。
フジロックに出演した際には菅田将暉が登場してのコラボを披露し、それがミュージックステーションでも放送された「うたかた歌」はこの日はやはり洋次郎単独ボーカルという形で演奏されたのだが、それがかえって現行の海外のポップミュージックのサウンドを多く取り入れた要素も強く感じられる「FOREVER DAZE」の中において、日本の土着的なフォークソングっぽさも感じさせてくれる。あんまり映画を見ないタイプなのだが、こうしてこの曲を聴いていると、この曲がテーマソングであり、洋次郎が出演している「キネマの神様」を観に行った方が良かったんじゃないかと思えてくるのだから不思議な力である。
するとここで今までと全く変わらないテンションで
「我々がメジャーデビューを発表した横浜BLITZがあった場所のすぐ近くのこの会場でツアーを始められることを本当に嬉しく思っています」
と、話し始めたのは武田。洋次郎がギタリスト2人を紹介したので、武田はドラマー2人を紹介するのだが、まるでジャニーズJr.にいてもおかしくないくらいに爽やかな容姿のエノは実は酒豪であり、先日みんなで食事に行った際にビール大ジョッキを4杯飲んでから日本酒を飲み始め、隣にいた武田は撃沈してしまったという。
一方でもうRADWIMPSに参加して6年が経つという森はまだ若手だった参加当時はご飯をめちゃくちゃ食べていたのに、30歳になった近年は腹が出てきたのを気にして控えているという。そんな森をこのツアーでは毎回ラーメンに誘おうとしている武田は36歳になっても体型が全く変わらない。それは洋次郎も。
その洋次郎は序盤で紹介したギタリスト2人にも話を振ると、実はTAIKINGと沙田はかねてからの知り合いだったのだが、このツアーのリハで顔を合わせるまではお互いに相手が参加していることを知らなかったという。(沙田の夫であるOKAMOTO’SのコウキもSuchmosとはバンドぐるみの深い関係である)
そんな話を沙田はRADWIMPSと観客への感謝を込めながら話すのだが、かつてねごとのライブでは「MCやらない方がいいんじゃ…」とファンが思ってしまうくらいに人前で喋るのが苦手だった彼女が、こんなにも素直かつ的確にステージで喋れるようになっているということに、見た目以上に精神が大人になったんだなということを感じた。デビューした時はまだ10代で、バンド解散までずっと見続けてきた彼女ももう30歳になった。そんなに経つんだから、彼女よりもさらに年上であるRADWIMPSもベテランというか大御所というような存在になるはずだし、我々も大人になったはずだ。
しかし洋次郎はそんなメンバーたちの話をしながらも、
「昨日の方が盛り上がってたけど、今日の負けっていうことでいい?」
と言って煽る。そうして煽ってさらなる熱狂を生み出すのは横浜の駄々っ子を観客がメンバーに見せつける「DADA」なのだが、昨年見た横浜アリーナでの15周年ライブでもアンコールの1番最後に演奏されていた(そのライブは「FOREVER DAZE」の初回盤で映像化している)曲なだけに、こんな中盤で演奏されるとは思っていなかったのだが、イントロで武田が森のドラムセットのシンバルを連打すると、桑原がそうしていたように逆サイドでは沙田がエノのドラムセットのシンバルを連打している。桑原のパフォーマンスが確かに受け継がれていて、それは彼が戻ってきた時にまたその光景が見れるということである。洋次郎が敢えて歌わないフレーズもたくさんある、つまりは観客に歌唱を委ねるこの曲で我々が声を出せないというのは昨年のそのライブやフジロックを経験してもやっぱり慣れるものではないし、慣れてはいけないものだとも思うけれど。
さらには洋次郎がギターを持ち、複雑なリズムのイントロによる「おしゃかしゃま」と、今までのライブでクライマックスを担ってきた曲が早くもこの中盤で演奏され、恒例の間奏でのドラムバトル的なセッションが始まると、その間に武田、TAIKING、沙田の3人は揃って花道の先端のミニステージに移動し、ドラムバトルの後には今までの武田と桑原のバトル的に、3人が順番にソロを演奏していくのだが、このソロを見るとブルースやミクスチャーという要素が強いTAIKINGと、フライングVを弾いているということからもグランジ、オルタナ的な要素が強い沙田という2人のギタリストのタイプが全く違うものであることがよくわかる。そんな2人がこのツアーに参加する前から仲が良いというのも面白いが、ソロを2回しするとそれぞれが演奏しながらステージに戻っていき、待ち構えていた洋次郎が合図することによって、最後のサビではより一層激しく爆発力のあるバンドアンサンブルを響かせる。何度見てきたかわからないこの曲も、やはりこうしてこの編成で見ると実に新鮮である。
そんな中でも演奏が始まった時には一瞬静寂になるというか、おそらくは何の曲が始まったのかわからない人がたくさんいたのは、ノイジーかつ厳かに鳴らされるイントロが追加された「セツナレンサ」であるのだが、2017年の「Human Bloom Tour」で久しぶりに演奏されて観客を驚かせたこの曲を、こんなに短いスパンで(4年ぶりでも短く感じるのは他にもっとやってない曲がたくさんあるからだ)聴けるとは思わなかったが、洋次郎のファルセットボーカルから切迫感を感じる
「今の僕は ここにいるよ 大事な人もいるんだよ
守っている約束もね 今は 今は 今は あるよ」
という歌詞が、どこか今のRADWIMPSの状況を示しているように感じる。大事な人もいるし、守っている約束だってきっとある。だから今またこの曲に向き合っているんじゃないかと。
そんなラウド、ミクスチャー的なサウンドから一気にUSヒップホップ、R&B的な要素が表出するのは、洋次郎の社会への痛烈なメッセージが次々に突き刺さる「匿名希望」。
洋次郎が花道を歩きながら歌う
「法律を決める国会議員がコカインキメる
やつよりもヤバい法を犯しながら今日ものうのうと生きる
総理総裁? 攻守交代?
すげ変わる首に意味はあるの?もみ消し放題? おもんない」
などの歌詞は顔の見えない人に何を言われても決して揺らぐことのない洋次郎の精神力の強さというか、そうでないと生き抜いていけないだろうなとすら感じてしまうのだが、その洋次郎は花道の先のミニステージに到達すると、上から降り注ぐレーザー光線に取り囲まれて顔がほとんど見えなくなる。それは顔が見えない人が何を言ったところで届くことはないですよ、というこの曲のメッセージを演出として視覚化しているようでもあったのだが、
「おいらのダチのがかっけーもん てか
あんたが誰だか知らねーもん
あんたら何かと ダッセーもん言うだけ言うけど やらねーもん」
という歌詞は、つい先日もどっかの週刊誌に洋次郎がBAD HOPのメンバーらと飲んでいることを撮られ、「反自粛派の急先鋒のRADWIMPSのボーカル」という、まるで重罪人だと報道するような書かれ方をしていたことを思い出してしまうのだが、洋次郎はもうそんな書かれ方をしたところで何ら反応したり対応したりすることはしないだろうと思える。言いたいことは全てこの曲のように音楽としてメッセージにし、(それはマスコミが洋次郎を狙うきっかけになったであろう「PAPARAZZI」もそうであるが)自身の行動にきっと自分なりの筋を通しているからだ。それがわかるから、どんなにマスコミに悪く書かれたとしても、こうしてたくさんの人が洋次郎を、RADWIMPSを信じてライブに足を運んでいるのだ。
そんなダークかつ不穏なサウンドから、一気に光が降り注ぐようなきらめくエレクトロサウンドの「NEVER EVER ENDER」へと飛ぶというのが今のRADWIMPSのサウンドの幅の広さを示しているのだが、なかなか観客側としては感情の切り替えが難しいところでもある。それでもシンセベースを弾く武田の姿や、誰よりも飛び跳ねながら手拍子を煽るエノの姿を見ているとすぐに幸せな気分になるのもまたRADWIMPSのライブならではのものなのである。
再び洋次郎がギターを持ったことによって、今度はまたバンドサウンドの曲を演奏することがわかるのだが、
「ロックバンドなんてもんを やっていてよかった
間違ってなんかいない
そんなふうに今はただ思えるよ」
というサビのフレーズを弾き語りのようにして歌うだけで大きな拍手が起こった「トアルハルノヒ」である。いろいろ今年は心身共に消耗することが多かったであろう洋次郎が、RADWIMPSがこのフレーズをこんなにたくさんの人の前で歌っている。今はステージに立っている正式メンバーは洋次郎と武田だけだし、バンドサウンド以外の曲もたくさん増えた。それでもRADWIMPSはロックバンドであり、ロックバンドであれていることを幸せに思えている。ある意味、今一番我々にというよりは我々がメンバー自身に歌って欲しかった曲なのかもしれない。そこからはロックバンドとしての矜持や誇りのようなものが確かに鳴っていた。
そんな「トアルハルノヒ」に曲終わりでも盛大な拍手が鳴った後に一転してドープなヒップホップトラックと言っていい「SHIWAKUCHA」を洋次郎が歌い始める。音源ではAwichが参加している曲であるのだが、曲が始まった時には紹介されることはなかったので、今日はゲストはなしか、と思っていたら、Awichのラップ部分になると洋次郎が
「盛大な拍手でお迎えください」
と紹介し、花道の先のミニステージにはすでにAwichがいてラップをしているという驚きのコラボ。黒の革ジャンを着て颯爽と、しかし力強くラップをするAwichがステージに戻ると洋次郎とハグし、まさにしわくちゃな笑顔を見せてくれる。
曲終わりに洋次郎が紹介していたように、Awichはすでに来年3月に武道館ワンマンが決まっている。それくらいに日本の大物ラッパーになりつつある彼女がこの1曲のためだけにこのライブに参加してくれるというRADWIMPSへの強い愛情と感謝。今年はNAMIMONOGATARIに出演したことによってAwichも世間から言われることもたくさんあったはずだが、RADWIMPSもそうであるように、そうしたことを音楽でもって乗り越えようとしている。本当に強い人間であり、ラッパーだと思う。洋次郎から褒められるとめちゃくちゃ喜んでいたあたりも、実に人間らしいなと思った。
そんなAwichがステージから去ると、場内には手拍子の音が流れ、武田をはじめとしたメンバーたちもその音に合わせて手拍子するのが客席にも広がっていく。その音を感じながら洋次郎が歌い始めた「いいんですか?」で明るくなった場内に幸福な空気が充満していく。
洋次郎は花道を歩きながら歌い、ギタリスト2人も左右の通路を歩いて客席の近い位置で演奏すると、コロナ禍になる前は観客が大合唱していた
「いいんですか?いいんですか?」
のフレーズはこれまでのライブでの観客の合唱音源が流され、それを、今ここにいる人の心の声をミニステージの最先端で聴いていた洋次郎は
「ありがとう」
と言って頭を下げた。「愛してるよ」ではなかったのは、その瞬間に出てきた素直な言葉だからだったのかもしれない。
でもこの曲を客席で歌えない日が来るなんて全く想像したこともなかった。これまでに数え切れないくらいに歌って、時にはその歌っている客席の姿がスクリーンに映し出されたり。当時、同級生にこの曲のMV撮影のエキストラに誘われたりしたが(映りたくないから行かなかったけど)、今でもたまにスペシャなんかでこの曲のMVが流れると、そこに一瞬だけ映っている同級生のことを思い出したりする。RADWIMPSも我々も学生から大人になった。我々が仕事を変えたりするように、RADWIMPSというバンドの形も変わった。この1〜2年で世界そのものも変わった。ライブでのこの曲における我々の楽しみ方も変わった。それでも、今でもこの曲をこうしてライブで聴けているというのは15年近く経っても変わっていない。
そんな感傷に浸っていると、洋次郎はピアノの前に座って、
「俺には音楽は絶対に必要なものだと思っている。みんなにとっても音楽が必要なものだったらいいなって思って音楽を作って、こうやってライブをやっています」
と言った。ここに来ている人は間違いなくみんなそういう人だ。みんな人生のどこかのタイミングでRADWIMPSの音楽に救われるような経験があって、それが今もずっと続いていたり、今の人生における礎になっていたりする。それこそ、RADWIMPSの音楽がなくなってしまったら生きていけないという人だっているかもしれない。そんな音楽が、RADWIMPSという存在が、やっぱりどうしたって必要だ。どんなに音楽やライブや洋次郎やRADWIMPSの存在を疎ましく思う人がいたとしても。
そんな音楽を鳴らしていく、どんなことがあろうが、誰に何を言われようがバンドを続けていくという強い意志を今一度示すように演奏されたのは、アルバムに先駆けて配信でリリースされた「鋼の羽根」。
RADWIMPSの持つ素朴さも感じるようなメロディが曲が進むにつれてどんどん飛翔していく。
「揺るぎないものがほしかった 壊れない意志がほしかった
容易い言葉はいつだって 賞味期限は持って3日
枯れない夢がほしかった 「僕」という意味がほしかった
宇宙にぽつんと咲いている 静かな理由がほしかった」
という歌詞を聴いて、自分にとっての揺るぎないものがあるかを自分自身の胸に問いかけてみる。
「それを君と二人ならば 見つけられる気がしたんだ
僕は君のを 君は僕のを 見つけられる気がしたんだ」
と歌っているように、それは今目の前にあるものだったと、洋次郎が歌い上げる美しいメロディを聴いて、確信に近いものを感じていた。
そしてそんな場内にキラキラしたエレクトロサウンドが流れ出す。フジロックの時に新曲として演奏されて観客を驚かせたダンスチューン「SUMMER DAZE 2021」だ。スクリーンには英語の歌詞が映し出されるのだが、この曲のサビと呼べる部分には歌詞がない。コーラスパートになっている。その本来ならみんなで大合唱することを想定して作られたであろうコーラスパートも当然ながら我々は歌うことはできない。
でもそれこそがこの曲のタイトルに「2021」という歴がついている理由なんだと思う。観客がライブで一緒に歌えなかった2021年を、これから先にこの曲を合唱できるようになった時に思い出せるように。いつか「信じられないかもしれないけど、この曲が出た時は世の中の状況がこうで、この曲を一緒に歌えなかったんだぜ」って後から振り返れるように。何もなかった、でもいろんなことがあった2021年の夏を忘れないものにするために。
そんなことを思いながらNew Order的とも言えるこの曲のきらめくダンスサウンドに体を預けていたら、「もし明日世界が終わるならどうする?」っていうことを何故か考えていた。欲望のままに法を犯すような行為をするでもなく、絶望に暮れるのでもなく、ただこの曲をずっと聴きながら踊って終末を迎えたいと思ったいた。きっとその瞬間に2021年の夏のゆらめきが永遠のものになるような。客席後方から大量の紙吹雪が舞う中で、そんな心地良さに包まれていた。
アンコールではまずは洋次郎と武田の2人だけが登場すると、武田はツアーグッズの青いTシャツに着替えている。その2人が花道を歩くと、ミニステージにはピアノとベースが置かれており、その今ステージに立っているRADWIMPSのメンバー2人だけで「かたわれ」を演奏する。
いわゆる、一緒に暮らしていた相手が居なくなって、部屋には自分と自分の持ち物しかなくなってしまったというのはよくある失恋ソングのパターンの一つなのかもしれないが、やはり野田洋次郎という男はそれをどこまでも野田洋次郎でしかない歌詞で描いてみせる。それが削ぎ落とされた密室間の強いサウンドで演奏されることによって、その歌詞の情景が頭に浮かび上がってくる。経験していなくても、いつか経験したことであるかのように。洋次郎の歌詞とRADWIMPSの曲にはそうした力が確かに宿っている。
2人がステージに戻ると、そこにはツアーグッズに着替えたサポートメンバーの4人の姿が。それは2人のこのステージへの帰還を待っているようでもあり、洋次郎が
「サポートメンバーっていうつもりもなくて。RADWIMPSに来てくれたっていうか」
というくらいにすでにこの4人がRADWIMPSに欠かすことのできない存在になっていることがわかる。こうして初めて音を合わせる、一緒にバンドをやるということは今になっての新鮮な、そして楽しい体験であるはずだ。
一度はピアノの前に座った洋次郎が思い出したかのように慌ててピアノからステージ前に戻ると、観客を背にして全員集合での写真撮影。前日は完全に写真を撮るのを忘れていたというが、
「今日は日曜日だから、みんなは明日仕事だったりするのかい?俺たちミュージシャンは土日に働いて月曜日が休みっていう感覚だから」
という日曜日感が洋次郎に写真を撮ることを思い出させたのだろうか。
さらに洋次郎は
「次に会える時は声を出して会話ができたらいいな」
と言って、改めてピアノの前に座ると、その神聖なサウンドに乗せるかのようにして「グランドエスケープ」の自身の歌唱バージョンを歌い始める。個人的には「FOREVER DAZE」にこの曲が収録されるなんて全く思っていなかったが、こうして今ライブでアルバム収録された洋次郎のボーカルバージョンで聴くとその理由がわかる気がした。
クラップが鳴り響く中でのゴスペル的なコーラスをメンバーたちが重ねると洋次郎がピアノから離れてステージ前まで出てきて歌う、
「夢に僕らで帆を張って 来るべき日のために夜を越え
いざ期待だけ満タンで あとはどうにかなるさと 肩を組んだ
怖くないわけない でも止まんない
ピンチの先回りしたって 僕らじゃしょうがない
僕らの恋が言う 声が言う
「行け」と言う」
という壮大なサウンドに乗る歌詞の未来へ全速力で駆け出していくような開放感。それはピンチと思われるような状況でも前に進むことを選んだRADWIMPSの今そのものだった。
そして洋次郎がギターを持つと、
「もう1曲だけやってもいいかの!?」
と問いかけて大きな拍手に包まれるようにして歌い始めたのは「有心論」だった。サビで洋次郎が煽ると一斉に観客がこの世界に足をつけて生きていることを確かめるかのように飛び跳ねる。
しかし洋次郎のラップ部分でのおなじみの
「用法・用量をお守りください」
も我々は歌うことはできない。ましてや
「息を止めると心があったよ そこを開くと君がいたんだよ
左心房に君がいるなら問題はない ない ないよね」
のフレーズも…と思っていたら、「いいんですか?」同様にこれまでのライブでの観客の大合唱が流れた。その直後の時計の針が動くような映像は、その観客の声こそがRADWIMPSを動かす原動力であったということを示すようなものだったのだが、この曲を聴いていたら、智史が離脱した直後の「胎盤」のライブを見た時のことを思い出した。
誰も智史の代わりにはなることができないバンドだからこそ、ツインドラムという今のロックバンドには珍しい、驚きの手法で智史の不在を感じさせないような、新たなRADWIMPSの形を作ったあの「胎盤」を自分が見た時にも、アンコールで演奏されたのはこの曲だった。対バン相手の米津玄師が好きで、一緒に歌いたいと言ったこの曲。そんな、ピンチをさらにバンドが成長するものへと変えてきたのがRADWIMPSというバンドだったことを、6年ぶりに感じたのがこの瞬間だった。あれから智史がライブに参加しなくなって、RADWIMPSのライブに行かなくてもいいやと思ったことがあっただろうか。いや、ない。あれからだって毎回ツアーに参加して、ずっとバンドとして音を鳴らす姿を見てきた。どんな時だってその姿からは我々が明日以降もこの世界を生きていくための力を貰ってきたからだ。この日、もしかしたら言わないかもしれないなとも思っていた、
「愛してるよ!」
を洋次郎は最後の最後で我々に向かって口にした。それを、心の中でじゃなくて、洋次郎に、RADWIMPSに向かって口に出して言える日が1日でも早く来ますように。
どんなに好きな人の行動であっても、間違っていたり、悪いことだと思ったらそう言いたい。そう言える関係性であるべきだと思うし、全肯定してしまうのはあまりに盲目的で危険だとも思う。
でも洋次郎の週刊誌に叩かれているようなことも、桑原のことも、自分は咎めたりすることができない。自分はそんなことを他人に言えるような聖人ではないということを理解しているからでもあると思うのだが、もしかしたら自分はRADWIMPSを完全にフェアな、フラットな視点では見ることが出来なくなっているのかもしれない。そう見るには、余りにも思い入れが強くなりすぎた。思い出や、たくさんのものを貰ってきすぎた。でも、それでもいいのかもしれないと思った。こんな素晴らしいライブを見ることができるのならば。
1.TWILIGHT
2.桃源郷
3.ドリーマーズ・ハイ
4.海馬
5.カタルシスト
6.DARMA GRAND PRIX
7.MAKAFUKA
8.うたかた歌
9.DADA
10.おしゃかしゃま
11.セツナレンサ
12.匿名希望
13.NEVER EVER ENDER
14.トアルハルノヒ
15.SHIWAKUCHA feat.Awich
16.いいんですか?
17.鋼の羽根
18.SUMMER DAZE 2021
encore
19.かたわれ
20.グランドエスケープ
21.有心論
文 ソノダマン
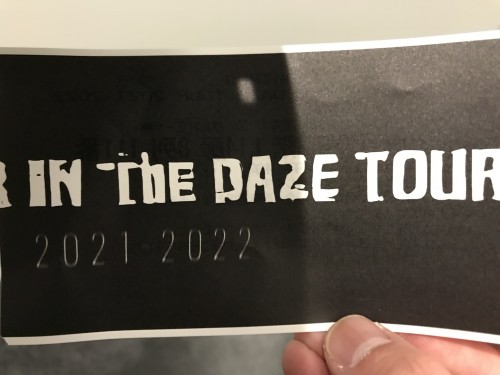
![[Alexandros] presents 「THIS SUMMER FESTIVAL 2020」day1 Zepp Haneda 2020.8.14 [Alexandros] presents 「THIS SUMMER FESTIVAL 2020」day1 Zepp Haneda 2020.8.14](https://moretzmusic.com/wp-content/uploads/2020/08/23-250x250.jpg)