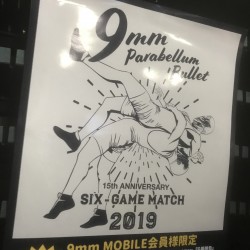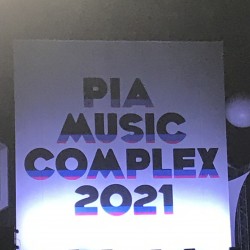2日目。明らかに入場時の待機列が長くなっているし、何よりも前日は1席空けだったのが全席埋まっていることによって前日との集客力の違いを感じざるを得ない。
12:00〜 KEYTALK
2日目のトップバッターは今やロックシーンが誇るお祭りバンドである、KEYTALK。前日のキュウソもそうであるが、やはりこのイベントのスタッフはそうした順番を良くわかっている。
おなじみのSE「物販」で勢いよくメンバーが登場して、八木優樹(ドラム)がステージ中央に居座って巨匠(ボーカル&ギター)にどかされそうになるという姿を見せてくれるのだが、2022年の1発目のライブの最初に演奏されたのは、小野武正(ギター)が泣きのメロディを奏でる「黄昏シンフォニー」という意外すぎる選曲。これはフェスやイベントでのセトリもこれからガンガン変わっていく年になるということを示唆しているのかはわからないけれども、個人的に「KEYTALKの中でめちゃくちゃ良い曲だと思うのに全然ライブでやらない曲」の最たる曲であるだけに、これからもガンガンライブでやっていただきたいと思う。なんならミュージックステーションだってこの曲で出演したんだし。
世代きっての夏バンド感をこの日に示す「MABOROSHI SUMMER」では観客も振り付けを踊りまくっているのだが、武正もステージ上で踊っている。首藤義勝(ベース&ボーカル)のサビのハイトーンボイスも実に伸びやかであり、1年の始めのライブに合わせてきていることを感じさせてくれる状態の良さである。
その義勝のボーカルが怪しげなサウンドに実に良く似合うのが「暁のザナドゥ」なのだが、これは果たして持ち時間35分のイベントなんだろうか?実は60分くらいある対バンライブなんじゃないだろうかと錯覚してしまうくらいの意外性のある曲の連発っぷりである。
さらにはピアノの音も取り入れた「Orion」と、冬の曲という意味ではこの時期にピッタリであるのだが、そもそも冬でも夏を待ち侘びるように夏の曲をやりまくるバンドであるだけに冬に冬の曲を聴くことがどこか違和感を感じてしまう。いわゆるバラードという枠に入る曲なのかもしれないが、八木と義勝によるリズムも実に重いし、武正のギターのサウンドも含めて単なるバラードではなくて、ライブで聴くと特にロックさを強く感じる曲である。
この日が今年初ライブではあるけれども、今年はバンド史上最長の50本という全国ツアーを開催して、コロナ禍になったことでなかなか会いに行けなかった場所の人たちにも会いに行くことを告知すると、やはり短い持ち時間の中に曲を詰め込みたいからか、かなりMCは急ぎ気味で各メンバーに一言ずつ振ると、そこからは義勝のスラップベースが冴え渡りまくる「MATSURI BAYASHI」からフェスなどでもおなじみのお祭り曲へと転じていくのだが、巨匠が歌っている横で武正が義勝を鬼ごっこみたいに追いかけ回して、義勝がマイクスタンドの前でスッと静止すると武正も追うのをやめるという姿が実に面白い。
さらに畳み掛けるように「MONSTER DANCE」と続けると、振り付けを観客が踊りまくるのに合わせるように振り付けを踊った武正が漲りまくっているかのようにこれでもかとギターを弾きまくる。自分は武正のギターや武正の作る曲が非常に好きなだけに、いつかそうしたセトリのライブもやってくれないだろうかと思う。
そしてそんなライブの最後を昨年リリースしたアルバム「ACTION!」のオープニングに収録されている「宴はヨイヨイ恋しぐれ」が担うというのがバンドの確実な進化を示しているのだが、
「この恋 叶うのでしょうか?
「いやーわかりません」」
という義勝と巨匠のツインボーカルならではのやり取りはこのバンドでしか生み出せない新しいパーティーチューンであり、そうしてアップデートされたバンドが今年50本ものツアーを回ったら果たしてどうなるのだろうか。トークパートでの武正の言葉からは、ツアー中も全然やっていない曲もやることを予感させたが、それはこうしたフェスやイベントにも反映されていく予感もする。つまりはさらに毎回のライブが見逃せないバンドになる気がしているということだ。
1.黄昏シンフォニー
2.MABOROSHI SUMMER
3.暁のザナドゥ
4.Orion
5.MATSURI BAYASHI
6.MONSTER DANCE
7.宴はヨイヨイ恋しぐれ
13:00〜 go!go!vanillas
アリーナツアーを行った2021年から引き続いて2022年もすでに所属するSEEZ RECORDSの新年会的なライブを行ったりと、積極的にライブをやりまくっている、go!go!vanillas。なので今年初ライブのバンドも多い中ですでに新年の挨拶を交わしている存在でもある。
アイリッシュ的なサウンドの新SE「RUN RUN RUN」でメンバーが登場すると、サイドを剃り上げたモヒカンのジェットセイヤ(ドラム)、青と緑が混ざったような髪色の長谷川プリティ敬祐(ベース)、黒の革ジャンというロックンロールスタイルの柳沢進太郎(ギター)の3人はおなじみの姿と言えるが、牧達弥(ボーカル&ギター)はハンドマイクで深緑色というようなツナギを着ているというのが珍しく映る。
その牧がハンドマイクでサビを高らかに歌い上げてから始まるのは昨年リリースの傑作アルバム「PANDORA」収録の「one shot kill」から始まるのだが、ワンマンでは特効などがあったのでついつい耳と体が身構えてしまう。イベントでさすがにそれはあるわけがないのだけれど、牧はステージサイドから映すカメラに目線を合わせながら歌ったりと、アリーナツアーを経たことによってこの規模のステージのライブにも実に慣れてきている感じがする。
プリティが幼い感じでタイトルコールするのがおなじみである「クライベイビー」もこの日はプリティは
「SPACE SHOWER TV、今年もブチ上がって行こうぜー!」
と縁の深いスペシャ(トークパートでレギュラー番組をやりたいと言いまくっていた)のイベントだからこそ、今年も一緒にライブを作っていきたいという思いを爆発させ、それが牧と柳沢によるツインボーカルという形でメロディに乗って観客にも届いていく。
さらには「お子さまプレート」と今年も「PANDORA」モードは継続中であり、それはやはりあのアルバムに大きな手答えを感じているからこそだろうけれど、間奏では牧、柳沢、プリティの3人が揃ってステップを踏み、セイヤもその動きに合わせて体を左右に動かしているのが見ていて本当に楽しいし、そこにはこんな状況だからこそ楽しませたいという思いが間違いなくあるはず。何よりもちょっと脱力するようなタイトルだけれど、牧の幼少期の回顧的な歌詞も含めて曲が抜群に良いからそう思うことができる。
「大変な状況になってしまっているけど、みんなの人生が美しいと思えるものになりますように」
という思いを込めて、牧がアコギを鳴らしながら歌い始めた「LIFE IS BEAUTIFUL」はSEと同じようにアイリッシュ的な要素をバンドが取り入れ、そのサウンドがまさに祝福として鳴らされるという、これまでに様々な音楽を吸収して自分たちのロックンロールにしてきたバニラズがまた新しい扉を開いた曲と言っていいだろう。何よりも牧のボーカルが本当にこの規模にふさわしい響き方をしている。ライブハウスで生きてきた、これからも生きていくバンドだけれど、そのボーカルの力はこうした広い会場でこそ改めてわかるものだ。
そしてプリティが腕で「E・M・A」と文字を作って観客と一緒にタイトルを作る「エマ」からはライブ定番曲にしてバンド代表曲の連発へ。その「エマ」ではダンサブルなサウンドで観客が飛び跳ね、柳沢も独特のステップで踊るようにギターを弾くと、ワンマンにもいつも行っているであろう、バニラズを見たくてこのライブに来たであろうファンたちがサビで左右の腕を交互に上げ下げする。もうすっかりフェスやイベントでもおなじみになっている観客側のパフォーマンスだと言っていいだろう。
さらには
「この世の中を照らすのは俺たちだー!」
と牧が自分たちの意志を叫んでから「平成ペイン」が演奏され、やはりサビでは振り付けを踊っている人たちがたくさんいる。その光景を見ていると、本当にバニラズのロックンロールによってこの今の世の中が照らされて欲しいと思うし、このバンドにそれができると思うのは、
「この暗闇に目が慣れているのは僕らだ」
という世代だからこそ、この暗闇を切り裂いてくれるって期待したくなるのだ。
そしてラストはロックンロールの魔法をこの会場にいる人たち全員にかけるための「マジック」。この魔法がずっと続いていて欲しいと思うのは、
「騙されたままがいいんだ」
という歌詞の通りだ。やっぱりロックンロールは楽しい。そんなことをバニラズはこの状況でも実感させてくれる。それはこれから先に世の中や自分たちやバンドがどんな状況になっても変わらないということだ。願わくばライブハウスツアーのチケットがもう少し当たるようになって欲しいと思うくらいにチケット当たらなくなったけれど、それもまたバニラズのロックンロールがたくさんの人に求められている証拠だ。
リハ.ヒンキーディンキーパーティークルー
リハ.No.999
1.one shot kill
2.クライベイビー
3.お子さまプレート
4.LIFE IS BEAUTIFUL
5.エマ
6.平成ペイン
7.マジック
14:00〜 ストレイテナー
ガラッと会場の空気というか雰囲気というか、そうしたものが変わるのはここまでの流れとは一変してベテランのストレイテナーが出演するからであるが、かつてホリエアツシ(ボーカル&ギター&キーボード)がgo!go!vanillasのプロデュースに携わった師匠的な存在でもあるだけに、この弟子のバニラズからのテナーという流れもさすがこのイベントである。
おなじみの「STNR Rock and Roll」のSEが流れて手拍子に迎えられてメンバーが登場すると、ナカヤマシンペイ(ドラム)は長く伸びた金髪の髪を後ろで結いており、ホリエの爽やかな見た目も相まってこのオリジナルメンバー2人はパッと見ではベテランに見えないだろう。もはや貫禄があり過ぎるひなっちこと日向秀和(ベース)と髪こそさっぱりしているが、蓄えた髭からはベテランさしか感じないOJこと大山純(ギター)は年相応であるけれど。
そんな若々しい見た目のシンペイがリズムを刻み出し、そこにうねりまくるひなっちのベース、そしてホリエとOJのギターが重なって実に久しぶりに感じる「KILLER TUNE」からスタートするのだが、シンペイのリズムはライブで聴くたびに変化している感もあり、このバンドが新しい曲や作品も出しながらも既存の曲も自分たちの技術と経験を持ってアップデートし続けているということがよくわかる。
そんなバンドの最新作から演奏されたのは「宇宙の夜 二人の朝」であるが、年齢とキャリアを重ねたことによってテナーは「丸くなった」「優しくなった」と言われることも多くなったし、実際にかつてよりもそうした大人になったからこそ書ける曲も生まれてきたし、ホリエの言葉も温かくも面白いものになってきてもいるのだが、今またこうしてエモーショナルなギターロックの曲が生まれている(収録作「Crank Up」はそうした音像でまとめられている)というのはこのバンドの消えないロックバンドとしての魂が今なお燃え続けているということである。ホリエがアウトロだけキーボードを弾くというのも今までにあったようでなかったような要素だ。
それはOJのギターがまさに叫んでいるというか唸っているかのような「叫ぶ星」もそうであるが、そうしてギターロックサウンドで押しまくった後だからこそ、キーボードの音色も含めて「さよならだけがおしえてくれた」の美しいメロディが際立つ。この辺りの緩急の付け方というか、短い持ち時間の中でどうやって自分たちの多彩な持ち味を見せていくかというライブの構成もさすがである。
それは心地良いサウンドの「彩雲」へと続く流れもそうであり、この曲を演奏している時のひなっちの笑顔は本当にこうしてライブをやっていることが楽しくて仕方がないと思ってるんだろうなと感じさせてくれる。決して自身が目立つようなゴリゴリのサウンドではないけれど、それよりもバンドとして良い曲を作っているという自負があるのだろう。
するとホリエがギターを掻き鳴らしながら「シーグラス」を歌い始める。季節としては真逆の、夏の曲、海の曲であるが、それを今こうして演奏するということは今年の夏こそはこの曲を去年全く開催出来なかった夏の野外フェスでも聴けるようにという願いを込めて鳴らされているということだ。だからこそバンドの演奏もホリエの歌唱もよりエモーショナルに聴こえる。今年こそは何度も今年最後の海へ向かうことができて、そこでこの曲を聴くことができますように。
そしてホリエはここで、
「音楽、ライブが好きな俺たちにとってはまだ苦しい日々が続くけど、みんなみたいに面白いこと、感動できることを探してる人がいることが心の支えになってる」
と今の状況を冷静に見据えた上で、自分たちが何のためにこうしてライブをやっているのか、そのライブをやる原動力がなんなのかについて口にする。ストレイテナーというバンドの凄さを数え切れないくらいに味わってきた身としてはホリエがそう言ってくれるというのが本当に嬉しいし、出会ってからの長い年月、特に2020年の夏にまだほとんどライブが開催できなかった時期にもライブをやってくれたことで得られた感情や思いを少しでもバンドに返せているんじゃないかって思える。そう思えることが自分自身にとっての心の支えになっている。
そんなMCの後に演奏されたのは、そうして言葉にできるものもあるけれど、言葉にできない願いや思いを音に乗せて、その音をさらに風に乗せて我々に届けるような「Melodic Storm」。コーラスパートを一緒に歌うことはまだできないけれど、だからこそシンペイのコーラスが本当によく聞こえるし、ホリエは観客の心の声を聞くようにステージ前に出てきて観客の姿を眺めていた。そこには確かに我々の思いや心の声も乗っていたはずだ。
そうして感動的に終わるのかと思ったら最後に「TRAIN」をブッ込んでくるのだから本当に痛快だし最高である。我々の予想を良い意味で裏切ってくれているし、35分という持ち時間を一切無駄にすることなく、その全てを必要な時間として使い切っている。改めてテナーがどれだけフェスやイベントでのライブの作り方が上手いバンドかがよくわかるのだが、思えばテナーは今のバンドのキャリアからしたら出なくてもいいようなMURO FESみたいな若手の見本市的なフェスにまで積極時に出演してきた。そうして常に最前線に立ってきたからこそそうしたライブが出来ているんだと思うと、そうしたフェスに出てきたのも決して無駄ではなかったし、そこでテナーに出会えた人だって少なからずいたはずだ。
演奏を終えるといつものようにシンペイはドラムセットを裸足で乗り越えるようにしてステージ前まで出てきて4人で肩を組んでからステージを去っていった。数え切れないくらいにライブを見てきても、やっぱりテナーは凄いと思えるし、並んだ時のホリエとシンペイの姿はやはりベテランとは思えないくらいに若々しかった。
1.KILLER TUNE
2.宇宙の夜 二人の朝
3.叫ぶ星
4.さよならだけがおしえてくれた
5.彩雲
6.シーグラス
7.Melodic Storm
8.TRAIN
15:00〜 マカロニえんぴつ
これだけの豪華なバンドたちの中であっても、このバンドのライブを観たくて来たという人もたくさんいたんじゃないかと思う。マカロニえんぴつは今間違いなくそうした状況にいるバンドである。
CDJの時には本編で演奏していた「愛のレンタル」をサウンドチェックで演奏するというあたりがその時とは違うライブになる予感を感じさせるのだが、実際におなじみのビートルズ「Hey Bulldog」のSEでメンバーが登場すると、このライブを走り抜けていくという意志を疾走感あふれるバンドサウンドで示すような「はしりがき」からスタート。
「仮面より起こせアクション」
というタイアップに合わせたはっとりの歌詞もさすがであるが、そのはっとりのボーカルのいつ聴いても揺らぐことのない安定感はさすがであるし、フライングVを掻き鳴らし、マイケル・シェンカーを崇拝する田辺由明のギターサウンドがこのバンドのロックさを担っている。
高浦”suzzy”充孝のリズミカルなドラムのイントロによって始まった、イベントなどでは久しぶりに演奏された感もある「洗濯機と君とラヂオ」ではライブならではのテンポが速くなる演奏の中、長谷川大喜(キーボード)はエアベースをしながら演奏している高野賢也(ベース)に近づくのだが、あまりに近づきすぎて高野がしゃがんでしまうくらい。今やテレビの音楽番組などにも積極的に出演しているだけに忙しい日々を送っていると思われるが、やっぱりライブという場で目の前にいる人に向けて音を鳴らしているが1番楽しそうなのは間違いない。
さらにはタイトルに合わせた黄色い照明がメンバーを照らし、バンドのブレイクの入り口にもなった「レモンパイ」の温かいキャッチーさへとつながっていくのだが、CDJに出演した時は「裸の旅人」などの「今、バンドがやりたい曲をやる」というモードであったが、この日はそれよりもはるかにわかりやすいモードであるようだ。
こうしてこの状況の中でもライブに来てくれるあなたへの感謝を
「音楽イベントが1番マナーやルールを守ってると思います!」
と口にすると、
「あなたといる時のマカロニえんぴつが好きだ」
と言って演奏されたのは「なんでもないや、」であるのだが、もはやこの曲が最も待たれている曲になっていることがライブでの観客のリアクションを見ているとよくわかるし、そうなるのもわかるくらいのメロディの美しさである。
「君といる時の僕が好きだ」
という締めの歌詞は演奏前のはっとりの言葉のあとだと、本当にライブで観客を前にしている自分たちが好きだというように聞こえてくるし、実際にライブではそうした思いを込めて演奏しているのだろう。
さらにははっとり以外のメンバーがカウントしてから、長谷川のシンセがストリングスのサウンドを響かせて始まる「恋人ごっこ」と、バンドをこの位置まで連れてきた曲を連発。普段は高浦がメインでコーラスをやっている(サポートなのにそこまでしてくれるのが本当にすごい)のだが、コーラスの高低によってコーラスをするメンバーが変わるというあたりも、全員が曲を作ることができるということと同じようにこのバンドのメンバーの器用さを示しているし、それはこれからも大きな武器になるはずだ。
そしてはっとりが思いっきり感情を込めるようにして
「いつか手を引っ張ってよ」
と歌い始めたのは「愛の手」。CDJでも演奏された曲であるが、その時は
「「12月の空は青さが足りない」」
というフレーズを12月のフェスに合わせて演奏したのかと思っていたが、こうして「なんでもないよ、」「恋人ごっこ」に連なる形で演奏されたということはその曲たちの後を担う曲として今この曲を演奏するべきだとバンドが思っているということであるし、すでにこの曲を作った時期から後に名曲を連発できるバンドだったんだなということが改めて聴いているとよくわかるし、
「忘れて生きる」
という締めのフレーズのはっとりの熱唱は今こそこの曲の持つ力を100%伝えられるようになったことを示している。
するとはっとりは音楽という存在について語り始める。
「音楽はそんなに真面目なやつじゃないんです。適当なところもあったりする。そんな音楽だから答えをもらったり、救いになってもらうんじゃなくて、ヒントを貰うくらいの感じでいたい」
とはっとりの今の音楽観について話すのだが、それは音楽をあまりに大事過ぎるもの、崇高なものとして捉えてしまうと、またこうした状況の中でライブがなくなってしまったり、不要不急と言われてしまった時に病んでいってしまう。そうならないように、深刻に捉えすぎないようにするというか。音楽を大事にし過ぎたり、縋ったりするほどになくなってしまった時や攻撃されてしまった時のダメージが大きくなってしまうから。
だがそんなはっとりが誰よりもそんな音楽という存在を最も大事なものに思っているからこそこうした曲たちを生み出すことができているのだろうし、「ヤングアダルト」の
「夜を越えるための歌が死なないように」
というフレーズをこれだけ説得力を持って響かせることができる。今、マカロニえんぴつという音楽に救われている人がたくさんいることを自分自身でわかっているのだろう。
「あなたが愛した、マカロニえんぴつという音楽でした」
とはっとりは最後に言ったのもそういうことだが、マイクを通さずにいろんな方向の観客に向かって
「ありがとう」
と口にしていた田辺の姿を見て、どんなに大きな存在になってもこのバンド、このメンバーの持つ純粋さは絶対に変わらないだろうなと思ったし、そこが信頼できるところなんだよなと思った。
リハ.愛のレンタル
1.はしりがき
2.洗濯機と君とラヂオ
3.レモンパイ
4.なんでもないよ、
5.恋人ごっこ
6.愛の手
7.ヤングアダルト
16:00〜 GRAPEVINE
この2日間での最ベテランバンドであるが、かつてこのイベントが横浜BayHallで開催された時にこのバンドとマカロニえんぴつの2マンという形で、このバンドに影響を受けてきたはっとりと長谷川がアンコールで「hope (軽め)」の演奏に参加しただけに、この順番もそうしたかつての共演を彷彿とさせるものだ。
いつものようにまさにサウンドチェックという感じの、曲を演奏しないでセッション的に音を鳴らすようにしてから本番でもはや不動の5人がステージに登場すると、田中和将(ボーカル&ギター)の
「どうもこんにちは、GRAPEVINEですー」
という挨拶から、金戸覚のベースがうねりまくってこのバンド特有のグルーヴの強さを生み出す、昨年リリースのアルバム「新しい果実」収録の「阿」からスタート。飄々としながらも亀井亨のドラムも西川弘剛のギターも、これがロックバンドのグルーヴであるということをたくさんの人に見せつけているかのようだ。田中の「あ行」の言葉を次々に発する、言葉遊び感と奥行きの強い歌詞もそのリズムと溶け合っているあたりはベテランだからこそできる技術である。
一転して美しいメロディの「Arma」では高野勲(キーボード&ギターetc)がホーンなどの様々なサウンドを駆使してそのメロディを際立たせるのだが、この曲がフェスやイベントも含めたライブでの定番になっているというあたりにバインのライブの作り方が明らかに昔と変化していることを感じさせる。つまり昔よりはこうしたフェスやイベントで初めて見る、聴くような人にも少しは入っていきやすいライブになっていると思われる。そこは長年見てきているだけにわかるようでもあり、麻痺してきていることでもあるのかもしれないけれど。
しかしながら「新しい果実」の先行曲であり、今の悪化し続けている社会の状況の中で聴くとまるでこの状況を予見していたのではないかとすら思えてくる「Gifted」、トラック的とも言えるサウンドをあくまでバンドの生演奏で作り出すことによってこのバンドならではのグルーヴが生まれ、そこに田中の不穏さを感じさせるファルセットボーカルによる、アルバムのテーマ的な歌詞が乗る「ねずみ浄土」と、「新しい果実」の曲を続けるというあたりは変わることのない「最新作が最高作」というこのバンドの姿勢であるが、わかりやすいシングル曲だけではなくてこうした一聴しただけではわからないような曲もフェスやイベントで演奏するということによってバンドの持つあらゆる要素を短い時間の中でしっかり見せてくれる。
そんな中でも今やフェスやイベントでも毎回演奏するようになったということが昔からしたら信じられない至上の名曲「光について」は演奏するメンバーの手元などがかろうじて見えるくらいのうっすらとした照明の中で演奏される。それが最後の
「僕らはまだここにあるさ」
というフレーズを歌った瞬間に一気に青い照明がメンバーを照らす。それはワンマンでの演出と同じものであり、それをこうしたイベントでもやってくれているというところにこのイベントを作っている人たちのバインへの無上の愛を感じる。それこそがマカロニえんぴつとの対バンやこのイベントへのバインの出演理由になっているのだろうし、このイベントのスタッフたちも普段からバインのワンマンを見に行っているのだろうと思う。
そしてラストは青春の二次会こと「Alright」で間奏から田中が手を叩くと、それに合わせて観客も手を叩き、そのスピードが速くなっていく。その客席を見て、少しはバインを知らなかった人にも届いたんだろうかと思った。多分、本人たちは全くそんなことは考えずに、いつもの自分たちの曲をいつもの自分たちの演奏でやるというくらいの意識だったと思うけれど、そういうバインの変わらなさをずっと信頼し続けている。
若手バンドが見れるのももちろん嬉しい。でも自分がライブに行き始めた時からフェスに出ていたACIDMAN、ストレイテナー、GRAPEVINEが今も変わらずにカッコいいと思えるライブをこの状況でも見せてくれていると、なんだかお前は間違ってないと言ってくれているような気持ちになる。それこそ、バインなんか初めてライブを見る前はNHKの音楽番組にも出演したりしていたような、テレビの中の存在的なバンドだった。だからこそ初めてライブで見た時は「あのGRAPEVINEが目の前にいる」と感動したことを今でも覚えている。そんなバンドが変わらずに最前線に立ち続けていることの頼もしさも、この2日間で改めて感じたものだった。
1.阿
2.Arma
3.Gifted
4.ねずみ浄土
5.光について
6.Alright
17:00〜 04 Limited Sazabys
今やこの幕張メッセ、しかもイベントホールではなく9〜11ホールの規模でワンマンをやるバンドになった、フォーリミ。この2日間のパンク代表的な存在にもなっているが、CDJに続いてタイムテーブルの後半での出演というあたりにもバンドの位置が変わってきていることを感じる。
おなじみのSEで元気良くメンバーがステージに登場して、KOUHEI(ドラム)がステージ中央に立って観客の期待をさらに煽るように腕を上げる。HIROKAZ(ギター)はパーマがかかった髪の量がさらに増えている感じであり、RYU-TAは半袖Tシャツに短パンといういつものライブキッズスタイル。そこに金髪がちょっと伸びたような感じもあるGEN(ボーカル&ベース)がステージに登場すると、HIROKAZがギターを鳴らして、レーザー光線が飛び交うというアリーナ規模になったバンドだからこその演出の「fiction」からスタートし、さらにGENが思いっきり腕を振りかぶるようにしてから演奏された「monolith」と連発。モッシュやダイブはできないけれど、その演奏にはロック、パンクとしての衝動が溢れており、やはりフォーリミもこうしてライブをすることで生きている実感を得ているバンドであることがよくわかる。
昨年リリースしたシングルからは、GENのボーカルの進化があるからこそ歌えるようになったことがよくわかるくらいにハイトーンさが曲後半に向かってさらに高く強くなっていく「fade」が演奏されるのだが、KOUHEIの連打するドラムからも新たなフォーリミの核となるパンクさを持った曲であることが伝わってくる。
さらにはHIROKAZとRYU-TAによるギターだけならずコーラスもキャッチーな「Jumper」と曲を次々に連発していくが、そのスピード感こそがパンクバンドとしての武器であるということを示しているかのようである。
「LIVE HOLICを愛し、LIVE HOLICに愛されたバンド、04 Limited Sazabysです」
というGENの挨拶からもこのイベントへの愛情と気合いを感じさせるが、
「さっきぶーやん(SUPER BEAVERの渋谷)に会ったら、ONE PIECEのドフラミンゴみたいな服を着ていた」
という楽屋裏情報も開陳しつつ、手拍子のタイミングもバッチリ決まる「Kitchen」からは後半へと突入し、観客もリズムに合わせて本当に楽しそうに踊り、RYU-TAもそんな客席の姿を見てか、片足を高く上げてギターを弾くのだが、そのアクションが激し過ぎて被っていたキャップが落ちてしまう。それくらいにメンバーも夢中になって楽しんでいる。
HIROKAZによるキャッチーなギターフレーズとKOUHEIの高速ツービートが引っ張る「My HERO」はまさにこうした幕張メッセなどの規模の会場でライブをやるようになったフォーリミこそがパンクシーンの、ロックシーンのヒーローであるということを示すようであるが、実際にGENも口にしていたとおりに11月にワンマン、12月にCDJ、1月にこの日と、3ヶ月連続で幕張メッセの大きいステージに立てるバンドはそうそういない。そういう意味でも紛れもなくフォーリミはヒーローと言える存在である。
今の時刻を口にしてから、
「まだ少し早いけど、流星群を降らせちゃおうかな!」
と言って演奏された「midnight cruising」ではRYU-TAがKOUHEIのドラムセットに近付いて2人で顔を見合わせながら演奏するというおなじみのシーンもありつつ、その2人がそれぞれカメラに目線を合わせて演奏する表情の違いも実に面白い。こうしたカメラに向けたパフォーマンスもこの規模でライブができるようになったバンドだからこそだろう。
するとGENは
「ここに5000人いたら1000個の耳があって…」
と良いことを言ってるように見えて計算を間違えている(後のトークパートでも突っ込まれていた)MCによってなかなか内容が頭に入って来ないのだが、
「さっきまでORANGE RANGEのHIROKIさんが袖でライブを見ていてくれたんだけど、それまで全然接点のなかったORANGE RANGEと対バンさせてくれて、仲良くなるきっかけを与えてくれたのもこのイベントだった」
と、LIVE HOLICのスタッフに感謝を伝える。それはGENたちにとっては世代的に多大な影響を受けてきたORANGE RANGEと出会えたというのは本当に嬉しいことだったというのがよくわかるのだが、そうした言葉があったからこそ、
「再会の曲を」
という「Terminal」がより沁みる。お互いにずっと続けてきて、このイベントも続いてきてくれたからこそ、こうしてまたここで再会できているのだから。今はなかなかそう思うことが難しい状況になってきてしまっているが、そういう場所があるというだけで「最高な世界」だと少しは思えるような気がしてくるし、そう思えることで明日からの日々をまた生き抜いていけると思えるのだ。
そしてラストはKOUHEIの力強いビートによって始まる、自分自身に生まれ変わるための「Squall」。こんな状況であってもこの曲を最後に聴くことによって「まだやれる」と思える。そう思わせてくれるフォーリミの頼もしさは今年も変わることはない。
来月以降もまた会える機会はたくさんあるだろうけれど、今年こそはバンドの地元である愛知のモリコロパークで、YON FESでまた春に会えますように。
リハ.nem…
リハ.knife
1.fiction
2.monolith
3.fade
4.Jumper
5.Kitchen
6.My HERO
7.midnight cruising
8.Terminal
9.Squall
18:00〜 ORANGE RANGE
GENのMCにもあった通りに、このイベントでフォーリミと対バンしたりと、もう完全にベテランバンドであってもこうしたイベントや対バンライブなどでバンドとして新たな出会いを経験している、ORANGE RANGE。
しかしいつもと違うのは、この日は事前にアナウンスされていた通りにベースのYOHが体調不良でライブに参加出来なくなってしまったために、残る4人+サポートドラマーという形でのライブとなる。ある意味では貴重でもあるけれど、どんなライブになるのか全く想像ができない。
フォーリミのRYU-TA同様に完全にキッズかつ夏仕様の格好のHIROKI、キャップを被ったYAMATO、サングラスをかけてより見た目がいかつく感じるRYOの三者三様なボーカルと、全く普段と変わることのないNAOTO(ギターなど)がステージに登場すると、打ち込みのサウンドが流れる中で昨年リリースされた「ラビリンス」を歌い始めるのだが、ステージにはいつものようにYOHのベースとアンプもセッティングされている。それは変わらずに5人で戦っているというバンドとしての姿勢を感じさせる。
なのでHIROKIもその現状を説明しつつ、
「皆さん、我々のピンチを助けてくれませんかー!」
と、観客も一緒になってこのピンチを乗り越えていこうとしていることを呼びかけると、大ヒット曲「チャンピオーネ」を演奏するのだが、
「サビだから盛り上がろう」
という身も蓋もないというか、ある意味メタ視点的な歌詞は今聴いてもこのフレーズをサビに使ってるのは本当に凄いなと思うのだが、さらにORANGE RANGEの持つキャッチーさが炸裂する、個人的に屈指の夏ソングだと思っている「イカSUMMER」と続くことによって、完全にこの幕張メッセの中だけは真冬から夏に変わってしまう。それはHIROKIの出で立ちによるところも強いのかもしれないが、誰もが知るヒット曲が目の前で演奏されて歌われているということが客席の温度もさらに高くしてくれる。
とはいえ、普段のライブではゴリゴリのベースを鳴らす、バンドのロックさ、ラウドさ、ミクスチャー感を最も担い、実際にそうしたラウド、パンクバンドとも深い共鳴を果たしているYOHの不在はライブの音という点では実に大きい。一応YOHのベースの音を流す形ではあれど、彼のベースを演奏する音がバンドのライブにとってどれだけ大きいものだったかということを、いないことでより強く実感する。
しかしながらそんなピンチを通常ならば考えつかないような方法で切り抜けるのが、かつて音楽シーン屈指の策士にして愉快犯とも称されたNAOTO率いるこのバンドである。
打ち込みのトラックというベースの不在をあまり感じさせないサウンドが流れる中で、ボーカル3人がエクササイズ的なダンスをするように踊りながら歌う、昨年リリースの20周年記念ソングにして、まさかのタニタとのコラボを果たした、公式ワークアウトソングの「HEALTH」で間違いなくたくさんの人の「なんだこれ!?」という驚きを生み出す。
「リズムに合わせ踊れば ほらシェイプアップ シェイプアップ
イライラ ストレス解消 ほらシェイプアップ シェイプアップ」
という本当にそのまんま過ぎるサビの歌詞はもの凄くクセになるというか、一回聴いたら絶対忘れられないという点ではORANGE RANGEが大ヒット曲を生み出してきたバンドであるということを感じさせてくれる曲なのかもしれない。ボーカルの動きがシュール過ぎてどう反応すればいいかわからないような人もたくさんいただろうけれど。
するとYOHの実弟でもあるRYOは
「YOHがいないことによってやる曲を変えたりもして。次はフェスとかではあまりやってない曲」
とどこか兄弟としての責任も含んだかのような言葉を口にするのだが、その「あまりやらない曲」としてHIROKIが歌い始めたのはバンド最大の大ヒット曲である「花」であった。もう15年以上前の曲であるが、今でも全歌詞が頭に浮かんでくるし、こんな状況じゃないライブでメンバーが「歌って!」と言ったらすぐに歌える曲。確かロッキンのGRASS STAGEに出た2018年には演奏していたが、それでも確かに毎回やるような曲じゃない。というかそれは「チャンピオーネ」も「イカSUMMER」もそうであるが、そうした曲をやらなくても成立するようなライブができる、そうした曲をやらなくてもいいくらいに他にもみんなが知っている曲をたくさん持っている。メジャーデビューからかつての現象とも言えるくらいのメガヒット期も全てリアルタイムで体験してきたけれど、そのORANGE RANGEの凄さがライブに行きまくるようになった今だからこそより強くわかるようになった。かつては批判されたりすることもたくさんあったこの曲がどれだけ素晴らしい曲なのかということも。
さらには浮遊感を感じる同期のサウンドは宇宙のことを表していたんだろうなと思うのは、その後に3人が歌い始めたのが「✳︎ 〜アスタリスク〜」だからであり、この曲もまた決してライブでは毎回やるような曲ではないというところにもはや恐ろしさすら感じてしまうのだが、最新の曲でもインパクトを与えながらも、こうして世代的にはあらゆる思い出や記憶が去来してしまうような大ヒット曲までも演奏してくれるというのは、ORANGE RANGEというバンドの強さをライブという場で証明するものになっている。
そんなライブの最後に、
「今日はYOHがいないけどね、離れていても繋がってるよ、っていう曲を最後に歌いたいと思います。ライブに来てくれる人も、今は来れないっていう人も、離れてても繋がってるよって」
と言って演奏されたのはもちろん「以心電信」。リリース当時は携帯電話のCMとしてどんな世代のどんな人でも耳にしていたこの曲が、今の世の中で最も必要なメッセージのようにして鳴らされ、まさに今目の前で繋がっている観客たちは本当に楽しそうに飛び跳ねまくっている。ORANGE RANGEはこのYOH不在のピンチをこれ以上ないくらいの逆転ホームラン的なライブをすることによってチャンスに変えてしまった。これまでにも何回もライブを観てきているけれど、改めて強過ぎるなこのバンドは、と思うライブだった。
というのは、かつてのメガヒット期のORANGE RANGEは世代問わずに誰でも曲を知っている存在だった。当時学生だった我々世代はカラオケに行けば誰がORANGE RANGEのどの曲を歌うかをこぞって先に歌いたい曲を入れ、親くらいの世代でも曲を聴けばタイトルがわかるくらいにテレビで流れまくっていた。
そうした存在になるとやはりORANGE RANGEを嫌いな人だってたくさんいた。それは売れまくったアーティストの宿命とも言えるけれど、そうして嫌いな人ですら曲は知っているというくらいの存在だった。生きていれば絶対に曲が耳に入ってくるというくらいの。
それはもう「バズる」なんていうレベルではなく、社会現象と言っていいくらいだったのだが、果たして今そういうアーティストがいるかと言ったらあそこまでのレベルのアーティストは自分はいないと思う。もう今は嫌いなアーティストの曲だったら耳に入るようなこともないような時代になったし、音楽に興味がない人はそうした存在すらも全てスルーし、遮断できるような時代でもある。もうそうした存在が生まれようもないというか。
そう考えるとORANGE RANGEは誰しもが一緒に曲を、音楽を共有することができる最後の存在なんじゃないかとすら思えてくるし、そのバンドがデビューしてから今に至るまでを見ることができる世代として生きてこれたのは本当に幸せなことだったと思える。またすぐに5人揃ったライブも見れますように。
1.ラビリンス
2.チャンピオーネ
3.イカSUMMER
4.HEALTH
5.花
6.✳︎ 〜アスタリスク〜
7.以心電信
19:00〜 SUPER BEAVER
前日の夜にまさかのNHKで特番が組まれていたSUPER BEAVERがこの2日間のトリという願ってもないタイミング。それは狙ってのことではないかもしれないが、SUPER BEAVERがさらに多くの人に存在が知られた、どんなバンドなのか伝わった後でのライブとなる。
先に柳沢亮太(ギター)、上杉研太(ベース)、藤原広明(ドラム)の3人がステージに登場して、この日は一発ド派手なキメを打つとその後に渋谷龍太(ボーカル)が長い髪を結いた状態でステージに登場し、
「17年目のバンド、SUPER BEAVERです」
と挨拶するとそのまま
「心から 心の奥まで わかるのは自分しかいない」
と最近では珍しい「証明」を歌い始めるというスタート。フォーリミのライブでGENが「ドフラミンゴみたい」と評していたが、さすがに本番ではそんな服ではなくて柄シャツを着用しているのだが、目を剥いてステージ前に出てきてギターを弾いていた柳沢といきなりぶつかってしまうという一幕も。それもこのバンドが決まり事ばかりのライブをしているのではなくて、その日その時のテンションによるライブをしているという証明であるのだが、ありふれたようにも感じるけれど、このバンドだからこそのメンバーのコーラスの押し引きによって伝えたいことを強調するというビーバーにしかできないこの曲が自分は大好きであり、なんならビーバーのライブに行くようになったきっかけの曲でもある。その曲が久しぶりに聴けたことが実に嬉しい。
さらに
「今をやめない」
という歌詞が今この状況のこのバンド、このイベントの意思として推進力を感じる藤原と上杉のリズムに乗って届く「突破口」はきっとこれからもこのバンドの生き様として鳴らされていく曲になるんだろうと思う。「正々堂々」も「威風堂々」もこのバンドに本当にふさわしい単語であると思うだけに。
すると柳沢が
「幕張、両手を見せてくれよ!」
と言って観客の両手が高く上がり、だからこそ手拍子をする手もきっとバンド側からハッキリと見えるのであろう、渋谷のマイクスタンド捌きも鮮やかな「青い春」とバンドのキラーチューンが次々に演奏されていく。それはこの状況の楽しみ方でも変わることがないどころか、この状況だからこそ
「会いたい人がいる」
というメッセージも含めてライブを観れていることの尊さを強く感じられるようになっている。
渋谷はきっと今いろんなライブがまた中止にせざるを得ない状況になってきていることをわかっているからだろうけれど、
「このイベント開催できて本当に良かったと思ってます。できない理由はたくさんあるかもしれないけど、できる中で正解を探す、正義を貫く。そういうイベントであってくれて良かったです」
というこの状況でライブをやるという選択も自分たちの中でしっかり考え抜いて結論を出していることだというのがわかる。
そんな言葉を言い、バンドの思考や理念がしっかり伝わるからこそ、
「名前を呼ぶよ 会いに行くよ」
という「名前を呼ぶよ」のフレーズが綺麗事ではなくてまさに今この瞬間のリアルとして響く。バンドの存在を広く知らしめることになった曲でもあるわけだが、そうしてタイアップをきっかけにしてこのバンドを知った人にもライブというバンドが1番大切にしている現場でこの曲を聴いて欲しいと思う。柳沢と上杉の振り絞るような声でのタイトルフレーズのコーラス含めて、ライブで聴く、観るということが1番この曲が伝わるから。
藤原の軽快かつダンサブルなビートに柳沢のギターフレーズが重なっていくというライブならではのアレンジによって始まる「予感」もまた、
「楽しい予感がする方へ」「会いたい自分がいる方へ」
というフレーズがこうして今の状況の中でライブに来ることを選んだ我々1人1人を肯定してくれているかのように響く。こんな状況でも楽しいと感じることは禁止されていないし、会いたい自分に会えるからこそ、渋谷が言うように明日からの生活の糧になっていく。
「俺たちの音楽は現実逃避するためのものじゃない」
と渋谷はこの日も言っていたけれど、だからこそコロナ禍という状況を無視することはできないし、それを全て忘れることはできない。ただ、そこに今この瞬間からできる限りの方法と力で対峙していく。それがSUPER BEAVERというバンドのライブであり音楽である。
その渋谷は
「このイベントに出れたからスペシャ列伝にも出れるかな?出たことないから出たいなってスタッフの人に言ったら、もう若手じゃないから無理ですって言われました(笑)
我々はそういう登竜門的なライブに全然出て来なかったバンドです。拒んでいたんじゃなくて、単純に出れなかった。そういうバンドだからこそ、他のアーティストよりもたくさんの人に助けられてここまで来たバンドだと思ってます」
と、いやいや、今からスペシャ列伝出なくていいでしょ、とも思うのだが、例えばフォーリミであったり、周りの出演経験のあるバンドたちが出ていた姿を見てうらやましく思っていたりしたからこそ、今でも出たいと思っているのかもしれないし、このバンドはオファーが来たら間違いなく出るという選択をするだろう。
そんなバンドだから、たくさんの人が助けてくれたり、手を貸してくれたんだろう。それは4人だけで再出発をしようと決めた時も、またメジャーに戻るという選択をした時も。そんなたくさんの人に助けられてきたバンドが今はたくさんの人を助けているバンドにもなっている。そんな人と人の存在や思いを繋ぐバンドだからこそ、「人として」という曲の
「信じ続けるしかないじゃないか
愛し続けるしかないじゃないか」
「カッコ悪い人にはなりたくないじゃないか
人として 人として かっこよく生きていたいじゃないか」
というフレーズがそのままこのバンドの生き様、メンバーの人間性そのものとして響くのだし、自分もその歌詞に真正面から対峙できる人間でありたいと思わせてくれる。それは少しでも自分本位の行動をしたらたくさんの人に迷惑をかけてしまう今の状況でライブに行くことを選択しているからこそ。
そして渋谷が真っ向から目の前にいる人への思いを伝えるかのような「アイラヴユー」はいわゆるラブソングであるけれど、でも特定の2人の恋愛というにはあまりに猛々し過ぎる。やはりこれはバンドの目の前にいてくれる「あなた」へのラブソングだ。だからこそこんなに思いを込めて「愛してる」と歌うことができる。ありふれたタイトルの曲でも全くありふれていないどころか、このバンドじゃないと歌えない、鳴らせない感情を込めることができている。柳沢と上杉のコーラスも、マイクを通さずとも真っ直ぐ観客の方に向かって歌っている藤原も。やはりビーバーはビーバーにしか歌えない歌を歌っている。
そうしてライブも、イベント自体も大団円を迎えるのかと思いきや、
「トリを仰せ付かりましたので、アンコールの時間をもらっております。まだ年が明けたばかりではありますが、今年1年の厄払いということで!」
と言って藤原がビートを叩き出して柳沢と上杉が歌い始めたのは「さよなら絶望」。急加速してパンクと言ってもいいようなリズムになる中で渋谷は中指を突き立てながら歌う。それは我々1人1人に降りかかる絶望に向かって中指を突き立てるかのように。それはギターを弾きながらの柳沢もそうだったのだが、この曲をライブで聴くたびに今のような状況に流されることも諦めることもなく、でもルールやマナーを破るようなことはせずに抗っていきたいと思う。この先にこのバンドと一緒にもっと笑える、そして一緒に歌える未来が来ることを願いながら。
まだアウトロが鳴らされてる間に渋谷はステージを去り、演奏が終わると上杉は腕を上げて観客の拍手に応えながらステージを去り、藤原はおなじみの投げキスを連発、そして柳沢はイベントのタオルとともに[NOiD]のタオルを掲げてからステージを去って行った。
渋谷はこの日スタッフが楽屋に置いてくれた手紙に
「明日からの希望になるようなステージを」
と書いてあったことに、
「我々以上に適任はいないじゃないですか!」
と言った。変わらないようでいて、そこには今のこのバンドだからこその責任を背負った風格が確かにあった。これから先、このバンドをこうした巨大なフェスのトリで数え切れないくらいに見るようになるんだろうな。
1.証明
2.突破口
3.青い春
4.名前を呼ぶよ
5.予感
6.人として
7.アイラヴユー
8.さよなら絶望
このイベントはスペシャのスタッフによって作られている。スペシャのライブ、イベントと言えばやはり山中湖でのSWEET LOVE SHOWERだ。この2日間が繋がって、このライブを作ってくれたスペシャの皆さんと、あの場所で暮らしている人たちに今年こそは夏に山中湖で会えますように。
文 ソノダマン