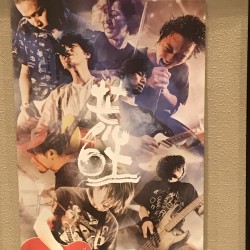DIR EN GREY 「The World You Live In」 -Live Concert Behind Closed Doors- Zepp KT Yokohama 2020.3.28 DIR EN GREY

本来ならば月初のSuchmosが松任谷由実を招いた2マンを皮切りに、新しい首都圏の大規模ライブハウスとしてオープンし、すでに様々なアーティストがライブを行っているはずだった、Zepp KT Yokohamaはしかし、コロナウィルスによるライブやイベントの自粛要請によって、未だに誰も観客として足を踏み入れておらず、誰もライブを行えていない。
そんな新しいライブハウスのステージは、無観客ライブ配信という意外な形によってアーティストが立つことになった。そのアーティストはこの3月28日にこの会場でライブを行う予定であった、DIR EN GREY。
すでに当日昼からバックエリア(当然ながら楽屋がめちゃくちゃキレイである)にて行われたメンバーのインタビューが配信されており、そこから含めるとかなりの長丁場の視聴時間となる。
ちなみにボーカルの京は「会場入りしてから何を食べていた?」という質問に対して、
「バナナを食べていた」
と笑顔で答え、画面の向こうにいる観客に手を振るなど、ライブ中のオーラとは全く違うリラックスした表情と語り口でインタビューに応じていた。
19時になるとメンバーがステージに現れる。いつものライブと変わらないような出で立ちであるが、京はジョーカーを彷彿とさせるようなメイクを施しており、やはり先ほどのインタビューの姿とは別人のようにすら見える。
ただ一つ普段と違うであろうことは、そんなメンバーたちがステージに出てきても歓声がないということ。それがライブ映像作品ではなくて、この日リアルタイムで行われている無観客ライブであることを強く感じさせる。
1曲目「人間を被る」。この日のインタビューの合間にもMVが流されていたが、映像の一部分に規制がかかるくらいにグロテスクな、しかしリアルな「人間」という生き物を描写した曲。
しかし驚くのは、メンバー背面のスクリーンに映し出される映像も、ステージに放たれる照明も紛れもなく本番と全く変わらないものであるということ。客席ではなくて画面越しに見ているので、メンバーそれぞれの演奏している姿や表情、手元に足元なども映し出されるが故に、その映像や照明の全てを俯瞰して見ることはできないけれど、これは本当に観客がいないということ以外は本番のライブそのものである。
それをさらに強く感じさせるのは、やはりメンバーの鳴らす音とパフォーマンス。「軽蔑と始まり」という「人間を被る」と同様にアルバムとしては最新作となる2018年の「The Insulated World」の収録曲から、2005年リリースの「Withering to death.」の収録曲である「Merciless Cult」「朔 -saku-」という産まれに10年以上の幅がある曲たちすらも全て「今、現在」のものとして同一線状で鳴らす、あまりにもラウドであまりにもダークなバンドのサウンド。
特にToshiya(ベース)とShinya(ドラム)によるリズム隊は見た目もそうだが、鳴らしている音の強さ、深さが40代をすでに超えているベテランらしい落ち着きみたいなものを良い意味で全く感じさせない。ましてやToshiyaは無観客であるにもかかわらずステージ前まで出てきてベースを弾く。まるで客席に姿はなくても、今自分たちが演奏している姿を見ている人たちが世界中にたくさんいることをわかっているかのように。
この辺りまではまだ本調子ではないというか、自身もインタビューで
「リハでちょっと歌って、本番でどんどんギアが上がっていく」
と言っていたように、ややボーカル、特にシャウトやスクリームがしっかり出切っていないように感じた京の喉も曲を歌いこなすことによって本当にギアが上がっていくというか、声が出るようになると同時にパフォーマンスにも引き込まれていくような凄みを感じさせる。
ライブ前にインタビュアーが
「DIR EN GREYの音楽はバックグラウンド再生というか、料理をしたりゲームをしながら聴くことができない。ちゃんと「DIR EN GREYの音楽を聴く」ということに向き合わないと聴くことができない」
と言っていたが、それはライブを見る時だけではなくてCDを聴く時も、ましてやこうしてライブ映像を見ている時もそうだ。何か他のことをしようとしてもできない。自分の目や耳や、その他音楽を聞いたりライブを見たりする時に使う感覚の全てが他のことへ意識が向くのを許してくれない。
それはことライブにおいてはMCも曲間も全くない、ひたすらに曲を演奏するだけというストイックなスタイルによってより一層そう感じさせるのだが、
「愛してください この日に この価値を」 (Merciless Cult)
「「生きてること そうそれだけだ」」 (絶縁体)
「苦しみの中 愛に飢える
尊い命を懸ける程の世界があると?
春よ、私を行かせて」 (赫)
「まだ間に合うだろうって?
それはどうだろうね
こんな世界で」 (Downfall)
という産まれた時期がバラバラなはずの、この日演奏された曲たちを聴いていると、その曲のフレーズのあらゆる部分からもまさに「今、この状況、この世界」に向けたメッセージであるかのように感じさせる。
基本的にセトリ自体は前回のツアーから大きく変わってはいないようであるが、メンバーがどんな思いを込めて演奏するか、どんな意志を持って音を鳴らすかによって、その曲が見せる表情は変わる。でもそれはどんなバンドでもできることではない。それをできるバンドこそがライブバンドとして長い年月生き残っていく。もう20年以上にも及ぶ歴史を持つこのバンドが今でも最前線にして誰も他に並ぶことのない場所で音を鳴らし続けているのはこのバンドがそうした表現力を持っているバンドだからである。
さらに深く潜っていくかのような「腐海」では京の描く歌詞と日本語の美しさを、「谿壑の欲」では人間の欺瞞を暴くような痛烈な言葉を。1曲ごとにガラッと入れ替わる表現もまた道化師のようでは決してなく、人間の持つ二面性を自身の音とパフォーマンスでもって表現していくのだが、リリース前後の時にライブで見た時は明らかにこの曲に向かうようなライブの作り方をしていた、壮大なサウンドと映像による「Rununculus」、そして10分以上にも及ぶ組曲のような最新曲「The World of Mercy」は紛れもなくこのライブのハイライトであった。
タイトルからもわかるように、DIR EN GREYの音楽は「世界」を描いたものが多い。でも彼らが描く世界は、生きているだけで素晴らしいというような、希望に溢れた世界ではない。目を背けたくなるようなグロテスクな映像や、広い空間を切り裂くような京のスクリームも重いサウンドも、全ては自分たちがこれまでに生きてきた世界を描くため。京が自身の胸を何度も強く叩くのも、マイクのコードを鞭のようにして叩きつけるのも、この世界で生きていくということは痛みや喪失と向かい合い続けていくということを示している。そこにメンバーの音とパフォーマンスの全てが説得力を持たせている。
でもそこから我々が感じるのは世界の醜さによる絶望ではない。そんな世界であっても、生きていかなければならないということであり、ライブを見ていてそうした想いを感じることができる感情があるということ。だからこそ、「Rununculus」の最後は
「叫び生きろ 私は生きてる」
というフレーズで締められるし、「The World of Mercy」もまた、
「お前は生きてる
お前の自由を探せ」
と最後に京は歌う。それはこのバンドのメンバー自身がこれまでそうして生きてきたかのように。
もしかしたら、本来ならこれで本編が終わっても良かったのかもしれない。現にここでスクリーンには赤い文字でツアータイトルが映し出された。だからこそ「SUSTAIN THE UNTRUTH」「詩踏み」という近年のこのバンドの代表曲にして定番曲のような2曲すらもどこかアンコールのように感じたのだ。
曲数だけを見たらワンマンにしたら少ないのかもしれない。でも10分以上に及ぶ曲があったり、MCや曲間がなかったりと、濃度は曲数以上に濃いものだった。
少し前に、どこかの音楽番組だかサイトだかで「海外でライブを行ってる代表的な日本のアーティスト」的なランキングが組まれていた。「もっとやってる人いるでしょ?」と各方面からツッコミが入りまくっていたが、DIR EN GREYも紛れもなくそこに入るべきバンドだ。
V系という日本独自の表現は海外で受けやすいとも言われるが、今このバンドをいわゆる「V系」として捉えられるような位置にはいないだろう。もしかしたらまだそのイメージがあるが故に音楽を聴いたりライブを見たことがないという人がいるのであれば実にもったいないというか、惜しいことであるが。
現にこのバンドが海外で受けているという理由がV系的な要素でないということは、海外のラウドバンドが揃うようなフェスに名を連ねていることからもわかるように、ただ海外のバンドとも遜色ない音の重さを持っているからだし、このバンドはサウンドの変化や進化を果たしてきたバンドではあるけれど、いわゆる世界に出ていくために自分たちの音楽を変えたり、流行りの要素を取り入れたりということは全くしていない。
それどころかむしろ全く真逆の、自分たちの表現により説得力を持たせるような重さや深さを追求するという、自分たちの信念を1ミリも揺るがせない活動をしていたら、海外からも評価されていた、という感じすらある。それは同時にこれからもこのバンドが何があっても揺らぐことはないけれど、このバンドの表現はどんな時代、どんな社会、どんな世界になっても変わらぬ説得力を持ち続けるということでもある。
演奏が終わると京はステージに倒れ込み、Dieは「ありがとう」と口にしながらスタッフにギターを渡し、Toshiyaは丁寧に敬礼をし、薫はピックを投げないかわりにカメラにアップで写して見せた。その姿はただひたすらにカッコいいロックバンドであると同時に、とんでもなく「人間」らしいものだった。
そのDIR EN GREYというバンドのカッコよさ、そしてメンバーの人間力の強さを、こうして画面越しではなくて会場の客席で感じることができるように。その日が1日でも早く訪れますように。
1.人間を被る
2.軽蔑と始まり
3.Merciless Cult
4.朔 -saku-
5.絶縁体
6.赫
7.Downfall
8.腐海
9.谿壑の欲
10.Ranunculus
11.The World of Mercy
12.SUSTAIN THE UNTRUTH
13.詩踏み
文 ソノダマン