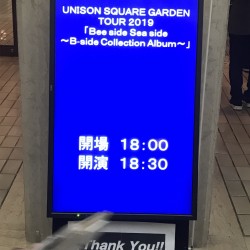カントーロード vol.18 a flood of circle / Large House Satisfaction 水戸LIGHT HOUSE 2021.8.16 a flood of circle, Large House Satisfaction, カントーロード

これまでにも数々の「このキャパで?」という対バンライブを開催してきた、水戸LIGHT HOUSEと千葉LOOKという関東の老舗ライブハウス合同のライブイベント「カントーロード」。
千葉県民としては「このバンドを千葉LOOKで見れるとは!」という思いができるイベントでもあるのだが、今回はa flood of circleとLarge House Satisfactionという、このイベントじゃなくても千葉LOOKで対バンしてきたのを見てきた、ロックンロールな2バンド。この日は初日の水戸LIGHT HOUSE編ということで、奇しくも前日、前々日に行くはずだったロッキンの近くの水戸に同じ時期に行くことに。
月曜日の18時くらいだというのに駅から会場までの商店街の店のほとんどが閉まっているという、ちょっと来ない間に変わってしまった風景に切なくなる中、検温、消毒、個人情報の記入を経て場内に入ると、立ち位置のマークが床に貼られたスタンディングという形式でソーシャルディスタンスを保つ。チケットソールドアウトということで、2階席も開放されている。
・Large House Satisfaction
19時になると場内が暗転し、要司(ボーカル&ギター)、賢司(ベース)の小林兄弟と、サポートドラマーのSHOZOの3人がステージに登場。
SEが鳴り止むな否や、要司の鳴らすギターがまだ曲が始まるこの段階で最大限までデカい音を鳴らしてやろうというような爆音であるのがわかる。
先月のMURO FESに出演した際にもライブを見ているのだが、その時にも演奏されていた、情景が浮かぶような「黄昏の荒野」などのフレーズが並ぶ「NONONO」でスタートするのだが、SHOZOのぶっ叩くとんでもない手数と強さっぷりのドラムによって、小林兄弟の鳴らす音もさらに大きくなっているというイメージだ。
「Phantom」という獰猛なロックンロールサウンドの曲ではそれがより顕著であるが、こんなにデカい音を鳴らしていてみんな聴力的に大丈夫なんだろうかと思ってしまうレベルですらある。
要司「今日ここ着いて、昼飯食べに行こうと思ったんですよ。そしたらあの人だけ頑なに「行かない」って言ってて。なんで?って聞いたら「ライブは痩せる場所だから」って(笑)」
賢司「久しぶりに来たらここの店長には「太った?」って言われるし、フラッドの亮介には「白髪増えた?」って言われるし!(笑)
もうスタッフや共演者なんか嫌いだ!(笑)
俺にはみんながいればそれでいい!(笑)」
と、かつては全員殺してやるくらいの殺気を持ったライブをしていたし、それがこのバンドのロックンロールさに繋がっていた部分もあったかもしれないが、今のラージは演奏中はロックンロールの獰猛さも持ちながらも、こうしたMCでは見た目のいかつさ以上に親しみやすい人間性をより強く見せてくれるようになった。そこはある意味では体制やメンバーや状況が変わった以上にバンドが変わったと感じる部分でもありつつ、そうした変化を経験せざるを得なかったことによって変わった部分だとも思う。
漆黒のダンスロックンロールとでも言うような「トワイライト」はメロディーも立った、いわばキャッチーとも言える曲であるのだが、そんな曲でもそのキャッチーさはそのままにサウンドがもの凄く強く激しくなっているし、それは要司の獣が吠えるようなボーカルもあってこそ。
そのバンドのサウンドが最も爆発していたのは、SHOZOが立ち上がってドラムをぶっ叩きまくっていた「愛悩」から、最大のライブ定番曲「Traffic」という流れだろう。「Traffic」にはコロナ禍になる前には観客も一緒になって歌っていたコーラスパートがあるのだが、今はそれを歌うことができないため、1コーラス目はメンバーだけで歌い、2コーラス目はメンバーすらも歌わないのだが、それはかつてと同じように観客に歌わせるようにボーカルを預けているからだ。もちろん観客は歌うことはできないのだが、
「水戸の魂の声、確かに聞こえました」
と要司が観客の思いを受け取り、その声を自身のギターに宿らせるようなソロを炸裂させる。要司はとかくその初期Oasisのリアム・ギャラガー的なボーカル(小林兄弟がギャラガー兄弟みたいな関係性じゃなくて本当に良かったと思う)に注目が集まりがちだし、そこが最大の持ち味であることも間違いないのだが、こうしてライブを見ていると、これはボーカルやりながら弾くようなレベルのギターじゃないな、と思えるギターを平然と弾いているという素晴らしいギタリストでもあることがよくわかる。
「最後にフラッドと対バンしたのは去年の2月の大阪での2マンかな。コロナが騒がれるようになり始めた頃だったけど、あの時はもうパンッパンに客入れてた。こんなに入れるの?ってくらいに。
…でも俺たちがやることはこうなっても変わらない。良い曲を作って、良いライブをやるだけ」
というMCからはかつてのライブハウスの光景を懐かしんでいるようであり、ラージはラージなりのやり方でそれを取り戻そうと戦っていることを感じさせた。元々、見た目や音楽のイメージ以上に優しい人たちであるというのは意外なくらいに物販を自分たちが立ってやったり(今は物販をやっていないが、賢司は「金欲しくてやってるんじゃないから!(笑)」とのこと)していた時に会話させてもらって感じていたことでもあるのだが、今はそれに加えて音楽に向かう姿勢が本当に真摯なバンドであると感じるようになった。
それは叙情的なサウンドと歌詞の新曲(これもMURO FESでもやっていた)を聴いていても感じられることであるが、そこから一気に再び爆音ロックンロールに転じると、最後には「こんなにも耳にくる音って他にある!?」と思ってしまうくらいのエフェクトをかけたギターとリフレインする要司の声が残響する中、SHOZOも含めて曲が終わってすぐにステージから去っていく、でも機材のバラしを全部自分たちでやるという潔さがロックンロールバンドとしてのカッコ良さに満ちていた。
昔、Large House Satisfactionはメジャーと契約して、ロッキンやラブシャという大型フェスだけならず、まさかの地上波の音楽番組にまで出演するという推されっぷりだった。それだけ期待されていたし、本人たちもライブを観るといつも自信に満ち溢れていた。(それは今でも変わらないけれど)
でもそうした推され方に見合うような結果を出すことはできなかったと言っていいだろう。そもそもがメジャーシーンや大型フェスでたくさんの人に聴かれるようなタイプのバンドではなかった。(本人たちは自分たちのやり方でそれを変えたかったからメジャーに行ったのかもしれないけど)
なんなら当時の、バズらないけど炎上はする、という賢司のSNSでの発言などを見ていても、田中秀作(前任ドラマー)が脱退した時に全部放り投げてバンドを終わらせるという選択を取ってもおかしくなかった、と脱退がアナウンスされた時に思っていた。
でも小林兄弟はこのバンドを続けることを選んだ。しかもとんでもない凄腕ドラマーを見つけてきて。そうして続けている今の姿からは、本当にロックンロールが好きで仕方なくて、俺たちにはこれしかやりたいことがないという(そもそもこの2人がまともに働ける感じも全然しないけど)、純粋なロックンロールへの愛情によってバンドを続けているように見える。SHOZOというドラマーの力もあるが、そのロックンロールへの愛情によって昔よりも圧倒的に凄まじいライブをするようになったようにも感じる。
あの頃出ていたフェスなどに今の形で出たらどうだろうか。もちろんそもそも見てもらわないことには、出演するステージに集まってもらわないことにはどうにもならないのだけれど、今のラージがフェスに出て、たくさんの人にライブを見てもらえる機会があったら、きっとそこにいる人は
「なんだこのとんでもないバンドは…」
って思うんじゃないだろうか。それくらいのライブをやるバンドであるということを、距離を空けて体がぶつかることは全くないのに汗にまみれた、ロックンロールが大好きな観客たちの姿していた。
・a flood of circle
それなりに素早い転換を終えて、後攻はa flood of circle。去年からの動きを見ていても、あるいは佐々木亮介(ボーカル&ギター)はTHE KEBABSでも活動しているが、そちらも含めてどんな状況になっても止まるという選択はないようだ。それは今までのこのバンドの生き方をそのまま表していると言ってもいいだろう。
SEが鳴って場内が暗転すると、この日は亮介は赤い革ジャンを着て登場。HISAYO(ベース)も青木テツ(ギター)も黒で統一される中、未だに髪が短くなったのが見慣れない渡邊一丘(ドラム)は柄シャツを着ている。テツは2ヶ月前の渋谷O-EASTでの自主企画ライブの時からまたさらに痩せたようにも感じるが。
「おはようございます。a flood of circleです」
と亮介がおなじみの挨拶をすると、亮介をはじめ、テツとHISAYOも渡邊のドラムセットの方を向いて、キメを連発するイントロの音と呼吸を合わせるような「博士の異常な愛情」という、あまりに意表を突かれるようなスタート。何故今この曲から?とも思うが、ラージのロックンロールサウンドを迎える礼儀とも言えるような音のロックンロールっぷり。コーラスを観客が歌うことができないのは寂しいが、最後には亮介以外の3人全員によるコーラスが重なり、それがアウトロの再びのキメ連発の演奏へと繋がっていく。フラッドはリリースツアー以外では毎回ライブごとにセトリをかなり変えることも多いバンドであるが、この時点でこの日はどんな曲が演奏されるのかが全くわからなくなる。
かと思えば亮介がギターを刻み出したのは「The Beautiful Monkeys」という完全なるロックンロール仕様。観客もその場で飛び跳ねまくるのだが、そのあまりのバンドの演奏の激しさ、コロナ禍でもライブを止めることなく続けてきたバンドだからこその強さと進化を感じざるを得ないようなサウンドに、ああ、この状況じゃなかったら、モッシュやダイブができるようなライブだったら、というかそういうライブであって欲しかった、とすら思った。
コロナ禍になってからもそれなりにいろんなライブを見てきたけれど、こんなにもそう思うようなバンド、ライブはそうそうない。それはやはりフラッドのライブ、フラッドの音楽が自分をこの上ないくらいに昂らせてくれる、燃え上がらせてくれるからである。
亮介がギターを下ろしてハンドマイクになると、その編成で演奏されたのはリリースされたばかりの「リスペクトするアーティストたちから曲を貰う」という形で制作された「GIFT ROCKS」収録の、Reiが提供した「I’M ALIVE」。音源だと歌い出しから亮介のボーカルにReiのコーラスが重なるという形だったが、フラッド単体でのライブだと当然それがないため、最初はこれ何の曲だっけ?と思ってしまうくらいに、音源での「ギターからメロディーからReiの曲過ぎる!」と思ったイメージをライブという場で演奏することによって吹っ飛ばされるくらいに完全にフラッドの曲になっている。ハンドマイクということで亮介はステージを動き回りながら歌い、客席前の柵に足をかけたりもするのだが、さすがにかつてのコロナ禍前のように客席の中に突入していったりということはしない。
「日本で1番音がデカいロックバンドのライブの後だから、みんな耳がおかしくなってるんじゃない?大丈夫?」
と、確かに耳がやられ気味な状態である我々観客のことを気遣いながらも演奏されたのは、こちらはSIX LOUNGEが提供した「LADY LUCK」。
そもそも今月末には提供アーティストたちを迎えたライブも新木場STUDIO COASTで開催されるため、「GIFT ROCKS」の曲はそこでお披露目するのかと思っていただけに、こうして短い時間の対バンで2曲も演奏されるとは思っていなかったのだが、この曲もまた同じロックンロールバンドと言っていい両者でありながらも、メロディにSIX LOUNGE節を強く感じるという、聴いた時は「SIX LOUNGEの新曲をフラッドにくれたんだろうか」とすら思うくらいにSIX LOUNGEなラブソングであるのだが(それは「GIFT ROCKS」内でフラッドがカバーした「メリールー」に通じるものでもある)、そんなSIX LOUNGE節すらもライブでフラッドが演奏すると、音源以上に完全にフラッドのものになっている。それは亮介の、亮介でしかないボーカルによるところが大きいけれど、弾き語りライブなどでいろんなアーティストのカバーをやっても完全にフラッド、亮介の曲になるということをバンドでの演奏でも示している。
一転してテツのギターがロマンチックなサウンドを奏でるのは、こんな状況の時代だからこそ、月に行くというきっと当時は無謀だ、無茶だと言われまくったであろう人類の歴史が、またコロナ禍前のようなライブをやるということが無謀でも無茶でもなく、希望であるかのように響く「Honey Moon Song」。そう思えるのはこうした形のライブになってからの1年でこの曲を何回も聴いてきた、すなわちフラッドのライブを何回も見ることができたからだろう。
「未来のことは誰も知らない」
こうなることすらも誰も知らなかったんだから、この先どうなるのかなんてことも誰にもわからない。でもこうしてフラッドのライブを見ることができているということがわずかでも希望を感じさせてくれるのは紛れもない事実だ。
このLIGHT HOUSEのキャパの割に高い天井から真っ赤な照明がステージに向かって降り注ぐのは実に久しぶりに演奏された感じもする「Blood & Bones」で、「Honey Moon Song」で少ししんみりした客席に歌詞の通りに火をつけるかのようだ。そうしたバンドの演奏に客席が燃え上がるのは、生きてるから。バンドの姿が、その音とパフォーマンスに反応する我々の心が、そうした生の実感をこれでもかというくらいに感じさせてくれる。何者でもない自分がここまでそれを実感できる場所はライブハウスだけだ。
冒頭でも書いたように、フラッドはラージとこれまでにも何度も対バンしており、その度に亮介はラージとの出会いを語るのだが、それは自身にとってそれが忘れられない思い出だからということで、この日も改めてその出会いを語る。
「もう15年くらい前。俺たちが20歳くらいの頃。いきなりLarge House Satisfactionからメールが来て。ライブ出てくれないかって。それで下北沢251にライブしに行ったんだけど、まだお互いレーベルとかにも所属してないから、俺たちがライブしてる時のお客さん、0人(笑)
さすがに気まずいから、ライブ終わったらすぐ帰ろうかと思ってたんだけど、ラージのお兄ちゃん(賢司)が
「交通費くらいでも貰ってくれよ」
って言って、1万円くれて(笑)客0人なのにギャラくれるっていう(笑)しかもそれがフラッドにとって初めてのギャラだった(笑)」
というMCは両者の付き合いの歴史の長さと、やはりラージの人間性があるからこそそうして長く続いてきたんだよな、ということを感じさせてくれる。何回も聞いたことのある話だが、何回聞いても面白いし、少しほっこりもする。
そんな両者がお互いにロックンロールというスタイルを貫いてここまでバンドを続けてきたからこそ、こうやって今でも対バンができているという事実を愛おしく思うような話の後には渡邊のリズムに合わせて観客が手拍子を叩く「Dancing Zombiez」で間奏ではテツが亮介に促されるまでもなくステージ前まで出てきて強烈なロックンロールギターソロをお見舞いすると、それはライブならではのアウトロのアレンジではより一層激しくなる。コーラスの声の張り方も含めて、この日のテツは本当に漲っていた。というかテツは主催イベントの時もそうだったが、わかりやすいくらいに対バンのカッコいいライブを観ると燃えるタイプだ。そういう意味ではこの日のライブに燃えないわけがない。
「俺たちとあんたたちの明日に捧げる!」
とおなじみの亮介の口上から始まった「シーガル」では亮介の「YEAH」という声に合わせて、観客たちがまるで誰が1番高く跳べるかを競っているかのように高くジャンプするのだが、この日のフラッドのライブはそうやってどこまでも高く跳べそうな感覚を与えてくれた。それはこの音楽、このライブ、このバンドがあれば我々は無敵だ、どんなことだって乗り越えられると思うような。だからこそ、コロナ禍前までは亮介が客席にマイクを向けて大合唱していたこの曲を、またそうしてみんなで歌えるような日が必ず来るという約束のように受け取ることができる。
そして
「今日はアンコールもない。俺たちもみんなもこの曲で最後!」
と言いながら、渡邊が軽快なリズムのドラムを叩き出すのは「世界は君のもの」。コロナ禍になる前、2019年の「CENTER OF THE EARTH」のツアーでこのLIGHT HOUSEに来た時も最後にこの曲をやっていた。あの時はこうして距離を空けることなく、みんなが体をぶつけ合うようにしながら、ラストサビ前の
「飛ぶだけ!」
のフレーズを大合唱していた。そんな景色を思い出してつい涙が出そうになってしまう。気付くとHISAYOもその瞬間に右手の人差し指を天井に向けて高く挙げている。最後に思いっきりタメるようなアレンジをしたからこそ、アウトロでは観客が最後だからと言わんばかりに踊りまくる。こんなライブをしてくれる、こんな姿を見せてくれるんだから、どんな状況、どんな時代であっても、この曲をこうして聴いている時は世界は自分のものであり、ここにいる我々のものだと思える。
もうだいぶ見知った顔ばかりの客席になってきたけれど、こんな衝動を突き動かされるようなライブを見ても、誰も声を上げたりしないというフラッドのファンたちを自分は本当にカッコいい人たちだとも思っている。
そりゃあバンド側がこんなにとんでもなくカッコいいんだから、観客もそうなるというか、このバンドのカッコ良さを我々が貶めるようなことは絶対にあってはならないと思っている。
翌日は自分にとっても亮介やフラッドにとってもホームと言える、千葉LOOKでこの2マンをまた見ることができる。そんな、明日がやってくる、それを知ってるからまたこの手を伸ばす。
1.博士の異常な愛情
2.The Beautiful Monkeys
3.I’M ALIVE
4.LADY LUCK
5.Honey Moon Song
6.Blood & Bones
7.Dancing Zombiez
8.シーガル
9.世界は君のもの
文 ソノダマン