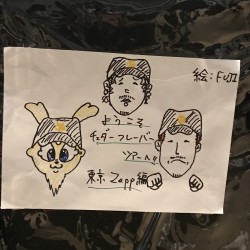配信ライブを全く自発的に行いそうにないスタンスのMONOEYESはちょうど1年前くらいと言える昨年の10月に配信でのワンマンライブを行った。
絶対に配信ライブをやらなそうなMONOEYESが配信をやるということは何らかの理由があるだろうとは思っていたが、演奏が始まってもすぐにはわからなかった配信ライブの会場は日本武道館であり、もともとバンドがその日に会場を押さえていたことによって、配信ライブをやることにしたというが、武道館を熱望したのは戸高賢史(ギター)だったという。その時は無観客だったMONOEYESが1年越しに武道館で観客を前にしてワンマンを行う。間違いなく特別な夜になるのは始まる前からわかる。それはthe HIATUSの日本武道館公演が、観客として会場にいた矢野顕子が「私もダイブしてみたくなっちゃった!」と言うくらいに素晴らしいものだっただけに。
九段下駅から坂を登って武道館へ向かう。その際に久しぶりだなと思った。ライブがでも、武道館がでもない。どちらも今や当たり前のように来ている。しかしその道に「チケット譲ってください」のボードを持った人がたくさんいる。その光景を見るのが久しぶりだと思った。MONOEYESが武道館でも行きたくてもチケットが取れずに行けない人がたくさんいるくらいのバンドであることも。
それは消毒と検温を経て入場した場内がキャパを減らしているからという要素もあるのだなということが空いた席からわかるだけに、またいつかはフルキャパで開催できたらいいなと思う。
開演前の諸注意を告げるアナウンスが流れると、そのアナウンスの終わりで客席から拍手が起こるというあたりにこの日のライブをこの会場に集まった人たちがどれだけ楽しみにしていたのかがわかる中、開演時間の19時を少し過ぎたあたりで流れていたBGMが止まって場内が暗転。自分はZepp Tokyoや新木場STUDIO COASTなど、このツアーのライブハウス公演にことごとくチケットが当たらず、このライブがこのツアー中での最初で最後のライブ(セミアコースティックツアーは行ったけれど)となるために、他の会場がどうだったかはわからないのだが、SEがスターウォーズではなくなっており、それがより一層このライブへの期待を高める。
暗闇の中でメンバーがステージに登場すると、細美武士(ボーカル&ギター)は赤いTシャツを着ているというのが微かにわかるのだが、ステージ両サイドにスクリーンがあり、そこにメンバーの姿が映し出されるということも歌い始めた瞬間にわかるのだが、細美が歌い始めた
「Hello again」
というフレーズがバンドと我々の再会を祝すかのように演奏された、この記念すべき武道館のオープニング曲は「Fall Out」。昨年の配信ライブ時にこの会場がどこなのかが判明した曲であるが、その「Hello again」のフレーズが映し出されたメンバー背面のスクリーンには映像が映し出されるというのは武道館ならではの演出と言えるが、ステージ上にはアンプと楽器とモニターしかないという、メンバーが立つための台すらもないというストイックなステージの作りからしたら少し意外なものであったが、それは終始映像にばかり目が行くというものではなく、あくまでメンバーの演奏する姿の背後に映るもの、というくらいにバンド以上にはならないものだ。
しかしながら冒頭から戸高は前に出てきてギターを弾きながら、客席をじっと見つめている。それはまるで自身が見たかったこの景色を自身の脳内に焼き付けようとしているかのようであり、それが「Bygone」とライブタイトルになっている、コロナ禍にリリースされた「Between the Black and Gray」の収録曲の持つ感情をより強くしてくれる。細美が観客を煽るように手拍子をしていたのも、今のライブのガイドラインにおいては我々が他に感情表現をする手段がないということをわかってくれているというところもあるはずだ。
バンドの勢いをさらに増すように自分たちのサウンドをさらに走らせるような「Run Run」での客席のアリーナからスタンド2階席まで腕が上がり、戸高はモニターに足をかけるようにしてギターを鳴らしているのだが、そうしたメンバーそれぞれの姿や表情がステージ両サイドのスクリーンにはしっかり映し出されている。それは一瀬正和(ドラム)の、このバンドのメンバーでいれて、ここに立てていることへの幸せを感じさせる、去年の配信でも最も印象的だったと言える表情もスクリーンにはアップで映し出されており、もはや戸高や一瀬のその顔を見ているだけで泣きそうになってしまう。
サビ入り前に細美と戸高、さらにはスコット・マーフィー(ベース&ボーカル)が楽器を抱えて高くジャンプするというあたりにMONOEYESのロックバンドさ、なんならパンクバンドさが表れている「Free Throw」ではこの日本武道館という、日本を象徴すると言っていい会場のステージにスコットが立っていて、そこで「Morning glory」というフレーズをコーラスしているという姿を見るだけでもなんだか胸が熱くなる。やはりロックリスナーからしたらそのフレーズはOasisの金字塔的なセカンドアルバムのタイトルであるのだが、Oasisほどではないとはいえ、アメリカの人気バンドであるALLiSTERのメンバーがこうして日本でバンドをやっていて、武道館のステージに立っているのだから。そのバンドのボーカルが細美武士だなんて、どうも浮き足立つというか、ライブを見ていてもフワフワしてしまうのは高所恐怖症の自分が2階席の最前列でライブを見ていたという要素もあったのだろうか。
「夏の終わりの歌」
という細美の言葉に合わせたかのようにオレンジ色の照明がメンバーを照らす「Interstate 46」は、その言葉や照明も相まって、今年もこの曲が1番似合うような夏の野外フェスでこの曲を演奏する姿を見ることが出来なかったな…とも思ってしまうし、戸高のギターのフレーズがその切なくなるような気持ちをより強く感じさせる。この曲を演奏している姿を見たい会場が日本にはたくさんある。
この日最初のMCでは
「俺はせっかちだから、映画を見始めてもすぐに「終わっちゃうな」と思ってしまう。でも今日はまだあと1時間半くらいライブができる。それが本当に楽しみ」
と気合いが漲っていることを細美が口にしていたが、立体的なオブジェの映像がスクリーンに映し出された「Cold Reaction」から、やはり戸高と細美がギターを抱えてジャンプする(だからこそ細美の声はマイクが拾わない瞬間もある)「Like We’ve Never Lost」という1stアルバムからの選曲は「Between the Black and Gray」のリリースツアーでありながらも、武道館という会場ゆえにバンドのここまでの集大成という意識も少なからずあったはずだ。
この日最初の
「スコットが決めるぜー!」
からのスコットメインボーカルは「Roxette」であるが、自身メインボーカルにもかかわらずスコットはイントロでベースを鳴らしながら少しでも観客の近くに行くというあたりに彼の人間性がわかるし、2サビからは細美と位置を入れ替わってスコットがセンター、細美が下手に。なかなかこの位置でギターを弾いている細美の姿を見るというのもレアな光景であるが、何よりも堂々としたスコットのボーカル。特に
「why’d summer have to end?」
というサビの最後のフレーズで細美のコーラスが重なる瞬間は今がまるで夏なのかと(メンバーも基本的にTシャツだったり、一瀬は短パンだし)思うほどにエモーショナルだ。
そんな疾走感から上に飛び跳ねるようなビートへと変わるのは、戸高のイントロのギターがどこか「終わっていく」という切ない感覚を感じさせる「Get Up」。当然ながらビートに合わせて観客も飛び跳ねるのだが、かつてARABAKI ROCK FESの開催地の町長が震災で被災した東北の復興の象徴のフェスの開催宣言でこの曲のサビのフレーズを口にしていた。それが今はこのコロナ禍の時代、世の中を生きる我々を奮い立たせるように鳴らされている。その感覚が鳴らしている音にメンバーの人間性も乗っかってダイレクトに伝わってくる。
するとここでメンバー紹介も兼ねて、それぞれが一言ずつMC。最初に紹介されたスコットは
「7年前に細美さんから「バンドやろうぜ」って誘われて。日本で暮らしながらバンドをやることが少し不安だったし、家族も心配したと思うんだけど、今日のこの景色を見たらきっと安心してくれるし、日本に行って良かったなって思ってくれるはず」
と、相変わらず完璧な日本語で語り、細美と抱き合う。もうMONOEYESも始動してから7年も経つのか、と改めて月日の経つ速さに驚いてしまうが、この2人の関係性はずっと全く変わらないように見える。
続く一瀬はいつものムードメーカーっぷりも口調からは感じさせながらも、
「今日、チケット取れなくて魂飛ばしますって人や、理由があって行けない人もいて。今日はみなさんにお願いがあります。来れなかった人の分まで拍手をお願いします。今日はDVDになるけど、来れなくてもそれを見た人と繋がれるんじゃないかって」
と、この日会場に来れなかったファンへの最大限の配慮を感じさせる言葉にすぐさま、次の言葉を口にするまで鳴り止まない拍手が湧き上がる。みんなが一瀬のその言葉を受け止め、来れなかった人の思いを改めて受け取った、背負ったというスイッチが入ったように感じた。しかしながら
細美「良いこと言うね〜」
一瀬「モテたいからね(笑)」
と戯けてみせるあたりが一瀬らしくもある。
細美がthe HIATUSで、一瀬はASPARAGUS(the band apartの対バン)ですでにこの武道館のステージに立っているが、まだ立ったことがなかった戸高は自身にとって夢の場所に立っているわけであるが、
「僕が飲みの席で言った「武道館でやりたい」っていうのが現実になってるっていう。でも僕の個人的な夢っていうと少しニュアンスが違っていて。…僕はこのバンドで武道館に立ちたかったんです」
と、この武道館でやりたいという思いがこのバンドの存在によるものであることを明かして、やはり割れんばかりの拍手が湧き上がる。戸高もいろいろあった音楽人生だけれど、そう思えるバンドで活動していて、こんなにも楽しそうに演奏している姿を見ることができているということにその言葉が重なってさらに胸が熱くなる。細美からは髪の色も含めて全身緑色なだけに、
「前世はカエルだったの?(笑)」
と言われていたが。
そんな3人それぞれのこの日のライブへの想いを明かした後に演奏された「Iridescent Light」ではステージ後方と上方でミラーボールが輝き、タイトル通りに玉虫色の明かりに武道館が包まれていく。この曲が生まれなかったらMONOEYESのライブでこうした景色が見れることもなかっただろうと思うと、「Between the Black and Gray」はバンドとファンに新たな景色を見せてくれたアルバムであると言える。MONOEYESのメンバーはステージに立つと一人一人が輝いて見えるが、このステージの輝きはそれを可視化してくれているかのようだ。
一転してグランジ的なダークなギターサウンドによる「Nothing」へと続いていき、「Iridescent Light」の次に演奏されることによって、サウンドとしても照明や映像という演出としても光と闇という人生の対極のコントラストを描いているかのようであるし、それこそが「Between the Black and Gray」のタイトルの意味を示しているとも言えるが、こうしたパンク的なサウンドではない曲が続くからこそ、細美武士のボーカルが武道館の天井までいっぱいに伸びていっているのがよくわかるし、それを最大限に堪能することができるのは主戦場と言っていいライブハウスよりもこうした広くて天井が高い会場なんじゃないかとすら思える。
細美が
「行こうぜ!」
と言って早くもこの中盤で演奏された「グラニート」では
「そういう世界があるなら
行ってみたいと思った
ここは風が吹いていて
いつか明日が終わるなら
今日はともにすごそう
外は白い朝だ」
というサビの歌詞に合わせて観客もスコットも戸高も飛び跳ねまくる。まさに、こういう世界に行ってみたかったという世界が今目の前に広がっている。そんな世界を作ってくれているバンドと、今日をともにすごせている。そんな思いが溢れてきてどうしようもないくらいに感動してしまっていた。
「いつだってほらこんな風にさ」
ってこれから先何回でも思うことができる人生でありますように。
「こういう状況になって、ライブができるだけで、お前たちが目の前にいてくれるだけでいいって思えるようになった。でも俺たちもお前たちもバカだから忘れてしまうけど、ライブハウスでビールが飲めることとか、そうした小さな幸せを少しでも忘れないように。
この状況が終わったら、やりたいことをやろう。ショートケーキのイチゴを最初に食べちまうような、やりたいことをやりにいく人生にしよう。
きっとまたみんなで歌えたりする日が来るだろうけど、モッシュもダイブもなくてもいいって思ってる。でもこの曲の時だけは、またリフトしたりするお前たちの姿を見せてくれ」
と祈りや願いを曲に込めるようにして演奏されたのは、これまでにもMONOEYESのライブのハイライトを担ってきた、曲始まりから大きな手拍子が起こる「When I Was A King」。モッシュもダイブも合唱も起きようがないけれども、でも確かに脳内には見えている。この武道館のアリーナがモッシュピットになっていて、ダイバーが人の上を転がって、スコットや戸高がダイバーと拳を合わせ、屈強なセキュリティーの人たちがステージ前で忙しなく人を受け止める姿が。
もうそういうライブが見れなくなって1年半以上になる。ずいぶん昔のようなことにも感じてしまうくらいに、今のライブの形に慣れてしまってもきている。それでもこうしたバンドのこうした曲はその頃に自分をまた連れて行ってくれる。
コロナ禍が終わってやりたいこと。細美のその言葉を聞いた時に自分がやりたいと思ったのは、そういう景色を見にいきたいということ。結局、やりたいことも欲しいものも見たいものも、音楽の中に、ライブの中にしかない。スコットがグルグルと回りながらベースを弾いたりという、コロナ禍になる前と変わらないパフォーマンスを見せてくれたメンバーの姿を見て、そんなことを思っていた。そう思えるのはこういうバンドがいてくれるからだとも。
今や完全にMONOEYESの曲になりつつあるくらいにライブでは毎回演奏されている、スコットのバンド、ALLiSTERの「Somewhere On Fullerton」のキャッチーなサビのメロディとコーラスがただひたすらにこの場を「楽しい」と思えるような空間に変えてくれると、スコットが戸高を狙撃するようにベースを構えて立ち位置を入れ替わったりというパフォーマンスもやはり楽しいという感情で満たしてくれる「明日公園で」のストレートな日本語の歌詞が刺さってくるが、戸高がMCで
「コロナ禍の中でいろんな想いを抱えながら全国を回ってきたから、俺たちは強くなっているはず」
と言っていた通りに、それぞれのメンバーが目立つ瞬間や場面はあれど、ライブが進むに連れてどんどんバンドの鳴らす音がより巨大な一つの塊になってきている。つまりライブで1曲1曲演奏するたびにバンドが進化している。そこには技術や知識なんかを超えた(もちろんそれらを持っているメンバーのバンドだけど)、この4人でしか作り出せないものが確かにあることを感じさせてくれる。
それは細美がTシャツを脱いで上半身裸になってから演奏された(すぐにまた着たけど)、スコットボーカルの疾走するパンク曲にして、スコットなりの世の中へのメッセージを含んだ「Borders & Walls」もそうであり、こうしてMONOEYESは人種や国籍の壁を超えてバンドとなっている姿を見せてくれているだけに、コロナ禍で顕になってしまった人と人の間にある壁なんかもぶっ壊れてしまえばいいのに、と楽しい中でもそんなことを考えたりしていた。
「新しいもの好きな性格なんで、1回やったらもういいって思ってたんですけど、武道館楽しいですね。そういうこと言うとお前らはバカだからすぐに「細美さんがまた武道館でやるって!」ってツイートするんだろうけど(笑)」
と、そうツイートしたくなる気持ちもわかるのは、その言葉を聞いて、ここまでのライブを見ていて、また武道館に立つMONOEYESの姿を見たいと思ったからだ。その時はアリーナには椅子がなくて、みんなで歌ったり、モッシュやダイブができるように。
「このライブは普段は全く輝いてないおっさんたちが作ってくれてる。その時はおっさんたちが輝いている。音響、照明、設営してくれた人たち、本当にありがとうございます」
という細美の言葉を聞いていて、そのおじさんたちがこの武道館で輝いている姿をこれからも何回も見たいと思ったのだ。
自分はこの日、東スタンドという戸高サイドで真横からステージを見るという位置だった。なので下手のステージ袖がバッチリ見えていたのだが、「Two Little Fishes」の演奏が始まった時にそこでパンダの着ぐるみが蠢いている姿もしっかり見えていた。
演奏中に黒い幕に覆われたボードの後ろに隠れてステージに現れたパンダがそのボードの幕を外すと、そこにはこのライブのために作られた、MONOEYESの武道館を祝した大漁旗のようなフラッグが。そもそもこの曲で出てくるというだけでパンダの正体はすでに割れていると言っていいが、その旗はこれまでもBRAHMANのライブで描かれてきたものである。
つまりはパンダの正体はTOSHI-LOWであり、一瀬に向かってシャドーボクシングをしたり、戸高をヤンキー座りで睨みつけたり(パンダだから視線は変わらないけど)する中、サビではコーラスをしながら、間奏ではコーラスに合わせて腕を上下に振るという昭和世代ならではの振り付けが令和を駆け抜けているパンクバンドの武道館の客席に広がっていくのだが、最後のサビでようやくパンダの頭部を外すと、TOSHI-LOWの顔にもパンダのメイクが施されており、これには笑うなという方が絶対に無理だというくらいに場内が笑いに包まれる。
しかもTOSHI-LOWはそのパンダメイクのままで曲終わりに
「去年のバンドとごく少数のスタッフしかいなかった配信ライブの時に俺はそこにいたんだよ!その時に「また来年観客を入れたMONOEYESの武道館が見たいな」って言った俺の無茶振りを4人は叶えてくれた!辛いことやプレッシャーもたくさんあったと思うけど、MONOEYESは最高のバンドだ!」
と感動的なことを言うのだが、それでもやはり表情がパンダメイクのままで変化していくだけに、良いことを言っているのに笑いが起きてしまうという状態に。これには細美も
「良いこと言ってるけど、かおがパンダだぞ(笑)」
と突っ込んでいたが、「俺の最高の親友」と紹介して抱き合う姿を見ながら、いろんな意味で日本のロックシーンの最強ボーカリストと言えるこの2人がそうした関係性になったからこそ、こうした光景も目にすることができている。何度も見てきた共演が、こんなにも大人になってからの人生が素晴らしいものだと感じられるということを噛み締めていた。
夜の都市のビル群のような映像がこの日最大クラスに曲とマッチしている「Outer Rim」を聴きながら、パンク的な激しさやラウドさは少し減少したようにも感じる「Between the Black and Gray」の軸にある、なんなら細美武士の音楽全ての軸にあるのはメロディの美しさであるということがこの曲を聴いていると改めてわかる。
そしてイントロからメンバーも観客も飛び跳ねまくる「My Instant Song」ではメンバーのコーラスが歌うことができない観客の想いをも乗せているかのようであるが、細美はサビでマイクから離れるようにして飛び跳ねながら歌う姿が、観客の声が響くのを聞こうとしているかのような、待っているかのようだった。次に武道館で見れる時には、その瞬間に我々の声が響いていますように。
そして本編ラストとなるのはやはり「Between the Black and Gray」の中でも屈指のパンクさを持った「リザードマン」であるが、
「いこうぜ
四月の雨なら
寒くはないよね
今ならまだ追いつけるはずさ」
というサビの歌詞が我々の背中を強く押してくれる。細美も戸高もあらゆる方向、階層にいる観客を指差したり、笑顔を見せたりしている。その姿と「いこうぜ」という、この日細美が何度も発した言葉がこれからもこのバンドと一緒にいろんなところへ、いろんな景色を観に行きたいと思わせてくれる。最後に細美、スコット、戸高が一瀬のキメに合わせて高くジャンプした姿は、ロックバンドのカッコ良さというものをこの日本国旗が天井からぶら下がる武道館に、そして我々の脳内に刻みつけるかのようだった。
一瀬の言葉の通りに待っている間も大きな手拍子が客席から鳴る中、すぐさまアンコールでメンバーが登場すると、細美は人生で初めてライブに母親を招いたことを明かす。ステージ正面の1階席最前列ど真ん中という関係者席でしかない位置で控えめに手を振っていた女性がその人であろうけれど、
「母ちゃん、ありがとう!」
と細美が言ったのも、こうしてライブに招いたのも、見せることができる日に見せておかないと、これから先に見せることができないかもしれないということをコロナ禍になって思ったということもあるのだろうし、今のMONOEYESというバンドの姿を見てもらいたいという思いもあったんじゃないかと思う。
しかしながら、バンドをやることに反対する親も非常に多い中で、自分の息子が作っている音楽や存在がこんなにたくさんの人の生きる希望や力になっているというのは親としてどんな心境なんだろうか。あまり家族のことを話さない人だから、その関係性を知れたことがなんだか嬉しくなった。
そんな母親への感謝の後に演奏されたのは、サビのタイトルフレーズに合わせて観客が指を3本、2本、1本とカウントしていく「3,2,1 Go」。それがまたここから始まっていく、ここからまた行くぞというポジティブな気持ちにしてくれる。我々を走らせてくれるのだ。細美、スコット、戸高はやはり何度も楽器を抱えたままジャンプする。自分たちの持つ衝動をそうした形で表すかのように。
そして「Between the Black and Gray」の終曲である「彼は誰の夢」が「もう終わってしまう…」というこの場所にいた誰しもの想いを乗せるようにして鳴らされるのだが、
「僕らが過ごした
当たり前の日々も
遠くなるけど
まぶたの裏には
笑った顔だけ
思い出すけど
きっと
ここには静かな
雲が流れてるって
笑ってるのさ」
という歌詞は今を生きる我々の心境そのものを歌ったようであり、再会の約束だ。そしてこの日本武道館にMONOEYESが立つという景色は他の誰でもなく、メンバーやスタッフ、そして我々の夢であった。それが現実になったこの日のことは映像作品を見返すことをしなかったとしても絶対に忘れないだろうし、
「朝焼けに染まって
笑ってるのさ」
という締めのフレーズが、ライブを終えて笑顔になったメンバーの姿と美しいくらいにリンクしていた。やはり、この場所で鳴らされるべき曲だったのだ。
しかしそうして大団円となってもおかしくないようなアンコールを終えても、まだ客電が点かず、メンバーが慌てて走ってステージへ再登場。
「まだギリギリ行ける」
というのは音を鳴らしていい時間が決まっているからだろうけれど、
「みんな違うバンドもやってるから、来年はMONOEYESで会える機会は少なくなるかもしれない。それでも、忘れないでね」
と優しい口調で言ってから最後の最後に鳴らされたのは、その想いを曲にしたかのような「Remember Me」だった。
忘れるわけがない、というか忘れることなんて絶対にできない。こんなに、特別なことを何もしていないのに、それが特別な夜になるというライブを見ることができたのだから。メンバーが客席のあらゆる方向を見ながら演奏していたのは、感謝と名残惜しさが共存しているように見えた。
全ての演奏を終えると、一瀬がメンバーに提案するようにステージに横一列に並び、手を繋いで一礼して、細美は
「ありがとうございました!」
と叫んでステージから去っていった。スクリーンでアップになった顔を見ていると、本当にずっと年齢が変わらないように見える。こうしてライブが見れるっていうことも、変わらないでいてくれたらと心から思っていると、客電が点いて会場が明るくなり、この日演奏されなかった「Wish It Was Snowing Out」や「Just A Little More Time」という曲が流れながら、スクリーンには
「東北、沖縄に行ってきます!」
という文字が映し出されていた。いろんな人の夢ではあったけれど、この日は終着点でも目標でもなく、MONOEYESにとっての1つのライブだ。だからこそ、またここで見れるような気がしていた。
自分もそうだが、この日会場に来ていた人たちもこのライブが終わった時には視点がこれからに、未来に向いていた気がする。それはやはりMONOEYESというバンドが、そのメンバー1人1人が、そうした方向に向かわせてくれる力をくれるからだ。何のギミックもない、ただひたすらに音を鳴らすだけのロックバンドが見ている人や聴いている人にそこまで力を与えてくれる。細美の言う通りにそれぞれ他の活動もあるし、それも全て素晴らしいものだけども、それが仮になかったとしても、これから先もずっとそうやって一緒に生きていきたいバンドだ。こういう世界があるから、行ってみたいって思えるんだ。
1.Fall Out
2.Bygone
3.Run Run
4.Free Throw
5.Interstate 46
6.Cold Reaction
7.Like We’ve Never Lost
8.Roxette
9.Get Up
10.Iridescent Light
11.Nothing
12.グラニート
13.When I Was A King
14.Somewhere On Fullerton
15.明日公園で
16.Borders & Walls
17.Two Little Fishes w/ TOSHI-LOW
18.Outer Rim
19.My Instant Song
20.リザードマン
encore
21.3,2,1 Go
22.彼は誰の夢
encore2
23.Remember Me
文 ソノダマン