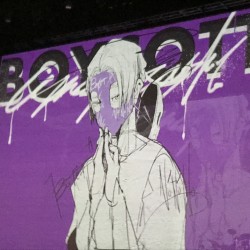2日目。初日はまだ平日の開催だったからか、明らかに同じ時間でも入場列がはるかに長い。それはそのまま最初のアーティストを見る人の数が多いということでもあるのだが、翌日以降にさらに入場をスムーズにしようとしても認証システムなどを通過しなければならないだけに、もぎりの箇所を増やすという従来の対応ができないのは実に難しいと思う。
10:20〜 打首獄門同好会
そんな朝早くから観客みんなが見たがっていたバンドがこの日のトップバッターの打首獄門同好会である。かつてはGALAXY STAGEの年明け後の大トリを務めたりもしたが、もはや完全にEARTH STAGEじゃないと収まらない存在になっている。
ロッキンオン社長の渋谷陽一が朝礼で、
「大澤君は僕がずっとやってるNHK FMの洋楽のラジオ番組にレッド・ツェッペリンの曲をリクエストしてきたことがある。この朝礼の時にかかる曲もレッド・ツェッペリンです。つまり彼は本物のロックスターです!」
と紹介された大澤会長(ボーカル&ギター)が長かった髪をバッサリ切り落としてサッパリとした髪型になっていることに驚いていると、最近のライブではおなじみの「新型コロナウィルスが憎い」のメンバー全員での合唱でスタート。ステージ両サイドのスクリーンにはメンバーが演奏する姿が、ステージ背面のLEDにはバンドが作った曲に合わせた映像が流れるというのは実にこのバンドのためのステージなんじゃないかとすら思えてくる。療養中につき椅子に座ってボーカル、コーラスに専念している河本あす香もこのスタイルにだいぶ慣れてきたようであるし、サポートドラマーの中でも最もこのバンドに近い存在であるバックドロップシンデレラの鬼ヶ島一徳のドラムは全くドラマーが違うという違和感を感じさせない。そこは彼なりに打首に合わせるというバンドへのリスペクトを込めてもいるのだろう。
幕張メッセの写真なども使われた、CDJ仕様の「足の筋肉の衰えヤバイ」から、朝10時台のライブというまだ脳も体も寝ていると言っていいくらいの状態の中でスクワットを何回もさせられるというラジオ体操にしてはあまりにもキツすぎる「筋肉マイフレンド」ではjunko(ベース)も平然とスクワットをしているあたり、この健康的な姿勢とスタイルこそが還暦を過ぎているとは思えない若さに繋がっているのだろうし、我々が朝からスクワットはキツいなんて言ってられないなとも思う。
飲食エリアに売っているマグロ丼などの海鮮メニューの売れ行きに多大な貢献を果たしているであろう「島国DNA」から、
「今年の痛みは今年のうちに!」
と言うと、大澤会長の主治医であるDr.COYASSも登場して(映像内にも普通に出てくるので若干リアルと映像の区別がつかなくなりがち)、歯科医であるGReeeeNの存在や「キセキ」を「歯石」に絡めたりと実は練られまくっているラップをかますのだが、そのラップを聞いていて自分が夏頃から歯医者に行くのをサボっているということを思い出してしまった。虫歯の恐ろしさを歌っている曲であるだけに、そこまでいかないうちになんとかしたい。
「今日、我々の出番10時20分からですよ。寒波も来てることだし、起きた時にはこう思ったことでしょう」
と言って、可愛らしいコウペンちゃんのイラストが使われた「はたらきたくない」、
「皆さんは仕事納めをしてここに来てるのかもしれません。1年間お疲れ様です。でもこのフェスをスタッフの方々は今働いてくれております」
と「はたらきたくない」と、相変わらずその曲と曲を繋ぐMCの上手さは抜群であるし、それによってどれもがこの日のための曲であるかのようにすら思えてくる。それは毎回やっている曲であってもこの日見たこのライブが特別なものとして記憶されていくということである。
河本がしまじろうのぬいぐるみを自身を寄りで撮るカメラに向かって見せる「カンガルーはどこに行ったのか」という今年リリースの曲ももちろん演奏して、カンガルーが出てくる部分では観客も腕を上下に動かすのが面白いが、そんな中で会長が
「今、酪農業界がピンチです。牛乳が大量に余っています。皆さん、年末年始は牛乳を飲みましょう」
と言って、会長が大ファンであるTEAM NACSの森崎博之が牛乳を一気飲みする映像が流れる中で演奏された「牛乳推奨月間」は大澤会長の、打首獄門同好会の優しさを感じざるを得ない。牛乳が大量に廃棄されそうになっているというのは最近度々ニュースで報じられているだけにみんな知っているだろうけれど、音楽シーン、ライブシーンはもちろんのこと、困っているあらゆる業界の人たちを救うために自分たちの音楽を持ってして戦う。そこに自分たちへの見返りは全くと言っていいくらいにない。ただ真面目に頑張っているのに困っている人がいる。そんな人たちのために音楽を鳴らす打首獄門同好会はバンド名こそ処刑人であるが、世界を平和にするために奮闘しているヒーローのようにすら感じる。
さらに話題のアニメのタイアップとしてバンドの名前を広げた「シュフノミチ」もそうであるが、メンバーが演奏する姿も見たいし、映像も見たいしということで視線が実に忙しい。河本とjunkoの歌う主婦・主夫の生活を描いた歌詞も本当に唸らされるくらいに上手い。
多くのバンドがそうであるようにこのバンドもこの日が今年最後のライブということもあってか、明らかに持ち時間45分の中に詰め込めるだけ曲を詰め込もうとしているし、それが朝早くから来てくれた人への最大限の感謝の表現であるということをわかっているからであるが、最後に世代的に名作ゲーム画面が次々に映る「きのこたけのこ戦争」から、
「2021年はここにいる皆さんにとって大豊作の年になりますように!」
と言って、観客がタイトルを口にすることはできないけれど「日本の米は世界一」を演奏して大団円を迎える(ひたすら丼もののメニューを口にする曲で大団円を迎えるというのも凄い話だが)というあたりに打首というバンドの姿勢が表れている。それは自分たちのやりたい、歌いたい曲を作りながらも、みんなが聴きたいであろう曲をちゃんと演奏するということだ。まだ朝早い時間ではあるが、飲食ブースで丼ものが食べたくなってしまった人もたくさんいたはず。
1.新型コロナウィルスが憎い
2.足の筋肉の衰えヤバイ
3.筋肉マイフレンド
4.島国DNA
5.歯痛くて feat.Dr.COYASS
6.布団の中から出たくない
7.はたらきたくない
8.カンガルーはどこに行ったのか
9.牛乳推奨月間
10.シュフノミチ
11.きのこたけのこ戦争
12.日本の米は世界一
11:35〜 きゃりーぱみゅぱみゅ
JAPAN JAMに続いての出演となる、きゃりーぱみゅぱみゅ。何というか、この日のラインアップを眺めていると実に異色感を放っているアクトであるが、ロッキンオンのフェスに出続けているだけに欠かせない存在であるとも言える。
先にダンサーたちがステージに登場(AC/DCやメタリカなどのTシャツを着た、外人だと思われる方々になっている)すると、鮮やかな赤い衣装を着たきゃりーぱみゅぱみゅは猫耳型のヘッドホンを装着している。暗い中だとその猫耳部分が発光するというのも衣装以上に鮮やかかつ華やかであるのだが、「キャンディレーサー」で始まると、もはやロックバンド以上なんじゃないかと思うくらいに凄まじい爆音の重低音が流れ、きゃりーも歌いながらも軽やかにステップを踏んで踊っている。続くリズムを歌詞として言語化したような、それがLEDに映し出されるのがシュールな「どどんぱ」と、リリースされたばかりの最新アルバム「キャンディレーサー」収録曲が連発されるのだが、そのサウンドからして明らかに自身のモード、フェスに対するモードが変わったのがよくわかる。観客もやや「え?」という感じで驚いている感じであるが、幕張メッセでこうしたバキバキのクラブサウンドが流れているというのは会場の民度が最高に良いSONIC MANIAに来たかのような気分になる。
それはヒット曲もそうであり、「つけまつける」もダンサブルなextended ver.として鳴らされるのだが、このあたりできゃりーはヘッドホンを外して身軽な姿になったことで曲の振り付けも自在に踊るのだが、きゃりー自身がライブでのアレンジに触れてから歌い始めたのは「にんじゃりばんばん -Steve Aoki Remix-」であり、スクリーンにはSteve Aokiの姿やゲームのキャラクターらしきもの(ゲームやらないからわからない)が次々に映し出されていくのだが、キャッチーさは微かに残したままで「こんなに!?」と思うくらいに大胆にダンスミュージックにアレンジされていて、そのバージョンをこのフェスでやるというのが本当に凄い。
それは「CANDY CANDY」もまたそうしたアレンジのバージョンでの披露となっているのだが、それはプロデューサーの中田ヤスタカらの思惑もあるだろうけれど、ライブハウス同様にダンスミュージックを浴びる場所であるクラブもまた危機的な状態になっていて、かねてから「クラブに来たことのない人に来てもらえるように」という健全なイベントを行ってきたきゃりーがその自分が育ったシーンに少しでも還元して、ダンスミュージックの楽しさ、面白さをたくさんの人に伝えたいと思うが故の変化なんじゃないかとも思う。
そんなきゃりーぱみゅぱみゅという人だからこそというか、きゃりーぱみゅぱみゅにしか歌えない、意味を持たない曲である「原宿いやほい」から、自身が10周年を迎えたことを口にするのだが、
「10年で本当に色々あって、私はリボンをつけるのが大好きなんですけど、TV番組ででっかいリボンをつけていたら後ろのジャニーズの方をリボンが隠しちゃって、炎上したりして(笑)
でも10年の中でリボンはつけたいけど、人に迷惑をかけないようにしたりとか小さいリボンにしたりして、先に進みながらも原点に回帰しているようなこともしていて」
とこの10年の中で最初に出てくるのがその事件かい、と思いながらもその思いを中田ヤスタカがそのまま曲にしたかのような「原点回避」という最新アルバム収録曲から、こちらは美しいメロディを強調するかのように原曲通りという形だったのだが、歌い終わった後にきゃりーは
「みんなが楽しそうにしているのが見れて本当に嬉しい。ずっとライブ出来なかったから…」
とステージ上にも関わらず涙を流す。そこには自分自身でもこの曲が沁み過ぎたことによるものもあったようだが、その姿にきゃりーのライブへの想いを感じることができる。やっぱり何よりもアーティストであるからこそ、このフェスにもずっと出演し続けていたんだと。
そして最後に演奏されたのはきゃりーが振り付けをレクチャーしてからの「最&高」なのだが、その声はまた少し震えているように聞こえた。きゃりーの感情が確かに声から滲み出ていた。これまでもたくさんのヒット曲でフェスを沸かせてきたきゃりーぱみゅぱみゅは明らかに変わろうとしている。いや、変わった。みんなが知ってる曲を歌って踊って楽しくなって…というものではなくなった。それがこれからもフェスできゃりーぱみゅぱみゅのライブを見たい理由になった。
1.キャンディレーサー
2.どどんぱ
3.つけまつける
4.にんじゃりばんばん -Steve Aoki Remix-
5.CANDY CANDY
6.原宿いやほい
7.原点回避
8.キズナミ
9.最&高
12:50〜 My Hair is Bad
春のJAPAN JAMも夏のロッキンも出演したことがあるが、このCDJは意外にも初出演となる、My Hair is Bad。リハで曲を演奏すると捌けることなくそのままステージに止まり、時間になるとすぐさまライブが始まるというのはフェスでのマイヘアのスタイルである。
「CDJ、初出演。ずっと雑誌の中の世界のことだった。新潟県上越市、My Hair is Badよろしくお願いします!」
と椎木知仁(ボーカル&ギター)が言ってギターを鳴らした瞬間に背面LEDにはバンドロゴが映し出される。ワンマンでも演出などがほとんどないバンドなだけにこのLEDに映像を映したりするつもりがないということはすぐにわかるのだが、
「ドキドキしようぜ!」
と言って「アフターアワー」から始まり、観客がリズムに合わせて手拍子をする「グッバイ・マイマリー」とマイヘアのストレートかつエモーショナルなギターロック曲が続くと、
「もう今は思い出すこともなくなったけど、昔好きだった人に向けて作った曲。過去の俺の経験で笑ってくれ!」
と曲が自身の実体験であることを口にしてから演奏されたのは「真赤」。先日Zepp Hanedaでワンマンを見た時も感じたことだが、山本大樹(ベース)と山田淳(ドラム)によるリズムがさらに強くなっているし、椎木のボーカルもさいたまスーパーアリーナなどを経てきているとはいえ、なかなかこの規模で歌う機会がなかった(RED LINEなどで幕張メッセではライブをしているが)とは思えないくらいに伸びやかだ。コロナ禍の中でもライブをし、直近でもツアーを回ってきたバンドとして状態が良いというか脂が乗っているのがよくわかる。
知らない人からしたら曲が始まった瞬間に終わったんじゃないかというくらいのショートチューン「クリサンセマム」から、椎木は
「YouTubeでもrockin’on JAPANの中でもない!目の前にいる俺たちを見てくれ!」
とハードなサウンドの「ディアウェンディ」に入るや否や言葉を次々に放ち始めると、
「遅くなりましたが、クリスマスにサンタは来ましたか?俺がサンタになってやる!ロックバンドからのプレゼントだよ!」
とクリスマスネタまでも飛び出し、椎木と立ち位置を入れ替わっていた山本は自身のアゴをサンタの髭があるかのように触る。そうした山本のお茶目な姿がワンマンだけでなくフェスでも見れるというのは嬉しい。
「ディアウェンディ」は椎木の即興の言葉ではない原曲部分でもリアルかつ残酷とも言える歌詞が並んでいる曲でもあるのだが、それは原曲よりもさらに速く激しく演奏される、椎木のポエトリーリーディング的なスタイルの「戦争を知らない大人たち」へと引き継がれていく。まさかこの曲が今になってこんなにライブで毎回演奏されるような大事な位置を担う曲になるとは思っていなかった。それくらいに他の曲よりも言葉の持つ意味合いが強い曲だから。しかし今のマイヘアはそれをしっかりライブの流れから浮くことのないようにセトリに組み込んでいる。
その椎木の言葉は「フロムナウオン」に入っていく前にさらに加速していく。
「みんながチケット代15000円払って来てくれてることを知ってる!だからそのチケット代以上のものを見せる!その値段の倍!さらに倍のものを見せてやる!」
とこのライブ、フェスだからこそのワードさえも飛び出してくるあたり、本当に椎木の反射神経は素晴らしいと思わされるのだが、
「体揺らしたり腕挙げさせたり歌わせたりしたいわけじゃない!ただその胸を焦がしたいだけ!売れたいわけじゃない!ロックスターになりたいわけじゃない!ステージで光り輝いていたいだけ!」
というのはこの状況であってもライブバンドであり続けてきたマイヘアだからこそだ。その言葉を口にしてギターを鳴らし、「フロムナウオン」を歌う椎木も山本と山田も間違いなく光り輝いていた。
「フロムナウオン」までは怒涛のスピードで言葉を連打しまくっていた椎木がクールダウンしたかのように、
「丸くなったとか棘がなくなったとか言われることもあるけど、失くしてから気付くことばっかり今まであって、どうしたら失くさないようにできるかがわかってきた。話し方とか、こういうことは言わない方がいいとか。あなたを守ることができるんなら俺は戦わない。守れるんなら全力で逃げる」
と自身の言葉が少し変化してきたことを認めるように口にしてから演奏されたのは
「本当のヒーローは意外と近くにいるんだ
きっとこれからも僕は正義にも悪にもなれないけど
誰よりも君の味方だ」
と歌われる「味方」。この曲が特定の誰か1人に向けて作られたものであっても、こうしてこのフェスで演奏されているのを聴いている時は我々のためにそう歌っていると思える。それくらいに今のこの曲の椎木の歌唱とバンドの演奏にはこの会場を丸ごと包み込むような温かい力がある。丸くなるのは決して悪いことじゃないと思える。椎木の、マイヘアの優しさをもっと素直に感じることができるから。
そんな一面も見せるというのはフェスとは思えない緩急の付け方と流れの作り方であるが、やはり最後には思いっきり突っ走るという2022年以降のマイヘアの変わらぬスタイルを示すかのように「告白」を演奏する。
「いつか死んでしまうんだ」
と歌っているバンドだからこそ、その時が来るまでは自分たちがやりたいことをやりたいようにやって生きていく。そんな意思が確かに感じられた。フェスではたまに空振りしてしまうようなライブを見せる時もあるけれど(ファンの人以外に刺せなかったという意味合いで)、この日は自分たちのスイングをしっかりした結果としてホームランが打てたんじゃないかと思う。
さいたまスーパーアリーナや新木場STUDIO COASTやZepp Haneda。今年の状況の中でもマイヘアのワンマンや主催ライブを何本も見ることができた。ラブソングに共感できないという自分のスタンスは変わらないけれど、それ以上に今の時代を生きる人間として椎木に共感できる言葉がたくさんあった。そんな2021年だった。コロナ前は年間100本をゆうに超えるくらいにライブをして生きてきたバンドを、来年は今年よりもたくさん見れますように。
リハ.宿り
リハ.ドラマみたいだ
1.アフターアワー
2.グッバイ・マイマリー
3.真赤
4.クリサンセマム
5.ディアウェンディ
6.戦争を知らない大人たち
7.フロムナウオン
8.味方
9.告白
14:05〜 the HIATUS
フロントマンの細美武士(ボーカル&ギター)は今年はMONOEYESで日本武道館ワンマンを行い、ELLEGARDENでは10-FEET、マキシマム ザ ホルモンと合同ツアーを行ったりしてきただけに、the HIATUSのライブを見るのは実に久しぶりだ。細美自身も
「今年最初で最後のフルバンドでのthe HIATUSのライブ」
と言っていたが、その貴重な今年唯一のライブがこのCDJである。
メンバー5人がステージに登場すると、細美はハンドマイクを手にして客席に正対するように、そのがっしりとした体つきがよくわかるように立って「Regrets」を歌い始める。じっくりと確かめ合うように音を構築していくかのようなメンバーの演奏に観客も熱狂というよりも集中しながら体を揺らすという形で向き合うのだが、ドラムを叩く姿もその音も柏倉隆史でしかないというのがすぐにわかる「Thirst」ではその演奏がじわじわと熱量を高めていき、masasucksのギターも歪みを強めていく。近年は他の現場では完全にお喋りな酒飲みおじさん的なイメージが強くなってきているウエノコウジ(ベース)もthe HIATUSのライブではダンディかつ頼もしく見える。演奏はどこのライブでも頼もしいのは間違いないけれども。
もはやこのバンドのファンであったり、曲を良く知る人以外から見たら、なんて難解な曲をフェスでやっているんだろうかと思ったりするのだろうかなんて思ってしまう、伊澤一葉のキーボードのメロディが複雑な柏倉のドラムのリズムと絡み合う「Bonfire」から、しかし「Unhurt」では細美の飛び跳ねながら歌う姿に合わせるようにして観客も飛び跳ねまくる。それはなかなかのブランクと言っていいくらいにライブの期間が空いたとは思えないくらいにバンドが変わらず鉄壁の演奏を見せてくれているからであるが、このバンドとMONOEYESとELLEGARDENを並行することによってさらにシンガーとして強く、懐が深くなっているようにすら思えてくる細美の歌声は我々に勇気や力をもたらしてくれるような感覚になる。そんなボーカリストが他にどれくらいいるだろうか。
「JAPANが財政難らしくて、あれだけ豪華なケータリングやバックステージを用意してくれていたこのフェスも今回は冷たい弁当が置かれているだけです(笑)
いつも豪華なことばっかりしている山崎洋一郎(rockin’on JAPAN編集長にして細美武士インタビュー担当)にさっき会ったら
「金はかけられないけど、気持ちは込めたから」
って言ってて。初めてあの人から人間らしい言葉が聞けたなって(笑)
でもそうやってでも今年このフェスを開催してる。きっと来年の夏のロッキンはもっと最高なものになるよ」
と、主催者のボスクラスと深い仲である細美だからこそ言える、ロッキンオンにエールというかコメントというかなんとも微妙なラインの言葉を送ると、「Hunger」でまた音楽の深淵の部分に潜っていく。身振り手振りをするようにしながら歌う細美の姿がまた歌声に強い説得力をもたらしているように感じる。
きっとMONOEYESだったらというか、実際にMONOEYESで出演した時には背面のLEDは全く使うことはしていなかったのだが、the HIATUSは音楽性としてもそうだし、実際にワンマンでも映像とのコラボ的なライブも行ってきているだけにこの日も背面には曲ごとに様々な映像が映し出されていたのだが、エレクトロなサウンドの要素も取り入れた「Something Ever After」でのオレンジ色の、夕焼けを思わせるような映像はより曲の持つイメージを強く際立たせていた。
それはMVのアニメーション映像が映し出される「Clone」もまたそうであるが、難解そうでいて、実際にどうやったらこんな曲が生まれるのかと思ってしまうような曲でもバンドの熱が高まっていく演奏によって確実に客席の熱量も高くなってきているのがよくわかる。
すると細美は
「今回のこのフェスのテーマは「音楽を止めない」らしいけど、JAPANが頑張らなくたって音楽は止まらないから。
オミクロン株とかあってなかなかそううまくはいかないけど、ガードは下げることなく、お正月は仲の良い少人数で酒を飲みまくりましょう。
こうやってルールを守ってお行儀よくライブを見ているお前たちがもっとめちゃくちゃになった姿を来年見れることを楽しみにしてます。ありがとうございました!」
と実に細美らしい(「ガードは下げずに〜」はメッセージボードにも書いてある)言葉で挨拶すると、細美がギターを弾きながらも、こんなにも腹の奥底から歌声というものを発することができるんだなと思う「Insomnia」でバンドの演奏が爆発するようにバチバチに鳴らされる。この音と細美の
「Save me」
という切実な叫びによる迫力はthe HIATUSのライブでしか得ることができないものであるのだが、最後の「紺碧の夜に」ではAメロで観客の手拍子が響く。深く深く潜ってきた先にこの曲のような光があったということを示すような流れで演奏されたこの曲は
「月の影にそって 歩き続けるんだ」
というフレーズが来年以降への微かでも確実な希望として響く。来年はきっとthe HIATUSのライブを見る機会も増える。最後に細美がギターを抱えてジャンプすると、着地の瞬間に映像からバンドロゴにスクリーンが切り替わった。ゾクっとするくらいにカッコ良すぎた。
大晦日にはELLEGARDENはBRAHMANと2マンを行う。それが最後のZepp Tokyoで開催されるライブであるが、ELLEGARDENはすでにアルバムを作ることをアナウンスしている。もちろんELLEGARDENを見れたら物凄く嬉しいけれど、the HIATUSでしか満たすことができない感情や感覚が間違いなくある。本当に久しぶりのthe HIATUSのライブはそれを改めて自分自身に突きつけてくるかのようだった。2022年はどんな場所でどれくらいこのバンドのライブを見れるだろうか。
リハ.Time Is Running Out
1.Regrets
2.Thirst
3.Bonfire
4.Unhurt
5.Hunger
6.Something Ever After
7.Clone
8.Insomnia
9.紺碧の夜に
15:20〜 Cocco
結果的に開催できなかったけれど、昨年のCDJも今年のロッキンもCoccoは出演者に名を連ねていた。活動しない時は全然ライブをやることがないCoccoがこのコロナ禍の中でワンマンだけではなくフェスにも積極的に出演しようとしている。それは少し意外でもあったけれど、こうしてこんな状況でもライブが見れるというのはやはり実に嬉しいことである。
背面のLEDに何も映らない、ステージも薄暗いという中にバンドメンバーが次々に現れるのが見えると、最後にステージ中央に出てきたCoccoは暗い中でも真っ赤なドレスを着ているのがわかる。そのCoccoがアコギのメロディに乗せて歌い始めたのは
「君がいない でも君の声が聞こえる」
という強い喪失感に襲われた主人公の心境が切なさを最大限に引き出すようなCoccoの歌唱から伝わってくるような新曲「君の声」。さらに突如としてプロデューサーでもある長田進のギターが唸りを上げて爆音になる「White Dress」と、冒頭はどちらも1分ちょっとのショートチューンであり、その爆音に驚きながらもこれはCoccoをよく知らない人はもちろん、かつてのヒット曲を期待して観ているであろう人でも「?」が浮かぶようなオープニングだと言っていいだろう。
しかし長田のノイジーなギターから一気に海上を漂うような音へと変化するイントロが鳴らされるのは大名曲「強く儚い者たち」で、Coccoはいつものように自身の体を前後に揺らすようにして歌うのだが、この曲が始まった段階で会場、観客が完全にCoccoの世界に引き込まれていることがわかる。
「人は弱いものよ とても弱いものよ」
「人は強いものよ そして儚いもの」
という歌詞が、2021年にいなくなってしまったり、自らそれを選んでしまった人のことを思い浮かばせる。もうリリースから20年以上も経っている曲なのに間違いなく今の曲として響いている。それはCoccoの変わることない歌の魔力によるものである。
それはやはり大名曲にしてヒット曲「樹海の糸」もそうであるが、イントロではかつてこの前に出演したthe HIATUSに参加していた堀江博久のキーボードが美しく響き、間奏では長田がギターを思いっきりノイジーに響かせる。
「永遠を願うなら
一度だけ 抱きしめて
その手から 離せばいい
わたしさえ いなければ
その夢を 守れるわ
溢れ出る憎しみを 織りあげ
わたしを奏でればいい」
というサビの歌詞を、まさに目の前にいる人を抱きしめるような慈しみを持った声でCoccoは歌う。その曲による声の変化も意図的にそうしているというよりはその曲を歌うと声がひとりでにそうなっているという感覚になる。そんな曲は
「やさしく殺めるように」
という、何度聴いてもゾクっとする言葉で締められる。その言語、歌詞の感覚こそCoccoだよなとも思うけれど。
そんなCoccoも2021年にアルバム「クチナシ」をリリースしてこの状況の中でも前に進んでいるのであるが、その中から演奏された「ひとひら」からは一気にサウンドがロックなモードに転じていく。ずっとCoccoのライブを支え続けてきたドラマーの椎野恭一のビートも一気に強く激しくなっていき、それは
「走るんだ
手に追えやしない
でも走るんだ
かすかに 光るよ」
「だって見てよ
こんな空なんだぜ
きっと来てよ
もう どうしろっての」
という希望と絶望が絡み合うかのような「BEAUTIFUL DAYS」へと繋がり、さらにファンを驚かせたのは重厚なサウンドの中でCoccoが
「ぶっ殺す」
と繰り返し歌う「花柄」が演奏されたということ。それでもサビでは一気にパッと視界が開けていくようにポップに展開していくのだが、今この曲が演奏された意味とは。かつて2005年のロッキンにくるりの岸田繁と佐藤征史らとのユニット、SINGER SONGERで出演した時に最後にこの曲が新曲として演奏された時の衝撃は今も強く残っているが、そうしてこの曲をお披露目したロッキンオンのフェスだからということもあるのだろうか。
そしてダンサブルなサウンドがステージのメンバーたちと客席の温度を高めていくようにして鳴らされ、Coccoも叫ぶように声を発する「音速パンチ」は久しぶりに見るCoccoのライブであってもこのイントロが鳴った時点でこの曲であるということが脳内に染み付いているのがわかる。かつてCoccoが一時的な休止から再生した時に生まれた曲は今もステージ上で歌い続けているCoccoを光り輝かせている。
ここまでMC一切なし。映像なども全く使わず、照明も暗い状態がほとんどなので、全員の姿や出で立ちがはっきりわかる瞬間は集中していないとほとんど見れない。そんな、ここまでの2日間で最もストイックな、かつロックなライブの最後はやはり轟音ロックサウンドが鳴らされる中で
「I don’t wanna be your Rockstar
Never ever
I don’t wanna be your Rockstar
Never again」
と歌われる全英語歌詞の最新作収録の「Rockstar」。
Coccoにロックスターという感覚を抱いている人はそうそういないだろう。どちらかというと「歌姫」的に呼ばれていることの方が多いように思う。でも個人的には歌姫って感じもまたちょっと違う。Coccoのライブを初めて見た15年以上前から変わらずに感じる、上手いとかいうレベルを超越した魔力を持った、ただひたすらそこで立ちすくみながら聴くしかないような歌声はもはや並の人間がどんなに努力したって手に入れられるようなものではない。
その初めて見た時の感覚を、今に至るまでライブを見るたびにずっと味わい続けている。初日の宮本浩次の時もそう思ったが、やっぱりどこか歌うことを選ばれた存在なのだと思う。歌の精霊というような。だからその歌声を聴いているといつも感情を体の奥底から全て掘り起こされるような感覚になる。
「ありがとうございました」
とだけ言ってCoccoはステージから去っていったが、確かにこのライブに他に言葉はいらなかった。歌の中に全ての感情が込められていたから。そんなCoccoが何度も音楽をやめようとしながらもこうして歌い続けていることで救われている人もたくさんいるはずだ。
1.君の声
2.White Dress
3.強く儚い者たち
4.樹海の糸
5.ひとひら
6.BEAUTIFUL DAYS
7.花柄
8.音速パンチ
9.Rockstar
16:35〜 マキシマム ザ ホルモン
明らかにこの日はこのバンドのTシャツなどのグッズを身につけた人がたくさんいるというのはもはやフェスにこのバンドが出た時のおなじみの光景である。ここからのラウド勢3連発の口火を切るのはライブシーン随一のモンスターバンド、マキシマム ザ ホルモンである。
異様とも言えるくらいのテンションの観客が待ち受ける中でそのテンションをさらに高くするようなSEが流れてメンバー4人がステージに登場すると、いつものように上半身裸の上ちゃん(ベース・コーラス)は髪を編み込んではいるが、長さは少しサッパリしているようにも見える。ダイスケはん(ボーカル)が頭を振って長くなった金髪を振り乱しながら「シミ」が演奏されると、凄まじい轟音の中でマキシマムザ亮君(ボーカル&ギター)のボーカル、ダイスケはんのデスボイス、ナヲ(ドラム&ボーカル)のキャッチーな声が次々にリレーされていく。そんなボーカルの変化があるからこそ、サビに入った時の爆発力がとてつもないものになっている。ホルモンがこんなにもモンスターバンド化している最大の理由はやっぱりその音であり、ライブである。
ナヲ「さっき細美さん(the HIATUS)も言ってたけど、今年ケータリングなくて。お弁当も私たちの楽屋に届いてなくて!スタッフも私たちが誰よりも食にこだわる出演者だった知ってるはずなのに!だから他の人の弁当貰おうと思って、きゃりーちゃんの楽屋に貰いに行った」
ダイスケはん「きゃりーちゃんの楽屋に食べ物はマカロンと綿飴しかないやろ!(笑)」
ナヲ「打首の楽屋に行ったら普通におばちゃん同士の世間話になっちゃって。人間ドックやった方がいいよ〜って」
ダイスケはん「まぁ美魔女がおるからな」
ナヲ「美ではないな〜」
ダイスケはん&ナヲ「ってオイ!」
とのっけから爆笑トークを繰り広げるのだが、弁当は無事にその後に楽屋に届けられたという。
そんなMCの後にはスクリーンに歌詞などの映像が映し出された「maximum the hormone II 〜これからの麺カタコッテリの話をしよう〜」ではナヲがステージ前まで出てきて歌うというおなじみのパートで沸かせるのだが、そもそも亮君が太ってしまって健康的にヤバい、痩せないといけないという経験をそのまま曲にしたという実にホルモンらしいラウドとキャッチーを融合させた曲であるのだが、亮君は体は痩せたままだけれど、顔はちょっとまた丸みを帯びてきた感じもしているのはライブがかつてよりも減ってしまった影響もあるのだろうか。
そんなライブが減ってしまった中でも大きなタイアップによって生み出された「ハングリー・プライド」は先程のMC通りに食に人一倍旺盛なホルモンだからこその曲であるが、その曲がホルモンの凶暴性を今の状況になっても感じさせてくれるし、その後にバンドの中で最も知られている曲であろう「絶望ビリー」を入れてくるという、新しい曲の後に代表曲を入れてくるあたりもさすがホルモンである。タイアップ先に合わせた歌詞を踏まえた部分のダイスケはんの歌唱のキレ味は今も全く変わることはない。
するとそのダイスケはんは、
「僕の義理のおじいちゃんの渋谷陽一(rockin’on社長)が「今年はみんなに甘えさせてくれ。演出も装飾もなくてごめん」と言ってましたが、甘えていたのは我々の方じゃないのか?これまで最高のホスピタリティを用意してくれたこのフェスに恩返しするのは今!1人1人が演出になるんだ!」
と毎年出演してきたこのフェスへの、ロッキンオンのフェスへの思いを口にする。正直、義理のおじいちゃんというのも意味がわからないけれど、ダイスケはんのこのストレートに熱い人間性が自分は好きだったりする。スペシャのレギュラー番組で「反核」という反原発の意思表示を示す服を着ていたりと、ダイスケはんはユーモア溢れる人間性の中に自身なりの考えや姿勢をしっかり表して生きている。だからこそこの発言も、我々は「チケット代が高い」とか思ってしまいがちであるのだが、これまでロッキンオンのフェスに貰ってきたものの多さと大きさを思い返して実感するのである。
するとこのタイミングで何故?と思いながらもサウンドが完全に現在のホルモンの形にアップデートされているのは「平成ストロベリーバイブ」の最新バージョン「令和ストロベリーバイブ」であり、このバージョンのMVも公開されているが、ホルモンがこれまでにも初期曲などを最新のバンドに見合う形にアップデートしてきたことを思い出す。ある意味では新曲をリリースしているのに等しいアレンジである。
するとここでダイスケはんが、
「今までは大晦日に朝まで開催されてきたこのフェスも今年は年越しすることができないから、おそらく世界一早いカウントダウンをやりたいと思います!」
と言って、しっかり作り込んできた映像は5秒前から、
5=郷ひろみ
4=フォーリミ
3=サンボマスター
2=西川きよし
1=ACIDMAN一悟
というカウントに合わせた人がスクリーンに映し出されて0秒になると、ファンにはおなじみのダイスケはんの母親の光江によるメッセージが流れる。カウントダウン自体はすでに前日にホルモンの影響を強く受けているヤバTが行っているが、それは両者が同じことを考えているということを示している。
その光江によるコメントから「恐喝 〜kyokatsu〜」へと突入していくのだが、亮君が明らかに怪訝そうな表情でドラムの方を見ているので、これは何かあったなと思っていたらナヲが入りを間違えていたらしく、光江のメッセージ部分まで巻き戻してもう1回演奏し直すのだが、ナヲがそれすらも間違えてダイスケはんの号令でステージ中央にメンバー全員を集めて緊急会議が行われて曲の入り方を確認してようやく正しい形で演奏される。これもまた演出だったのかと思いきや、どうやらガチでミスっていたようである。
緊急会議で入り方をナヲが思い出したかのようで、そのまま「恐喝 〜kyokatsu〜」を演奏すると、ここでまさかの敬愛するTHE BLUE HEARTSの曲を自分たちのものとして獰猛に血肉化した「皆殺しのメロディ」までもが演奏され、この曲もまたナヲがボーカルを務めるフレーズがあったりというふうにこの時代になってもなお進化している。
そのナヲは自身のミスによって持ち時間がなくなっていることを口にしながらも、
「今日2回目のきゃりーぱみゅぱみゅだよ!八王子いやほい!」
と小ネタを挟みながら一発勝負の「恋のおまじない」(時間がないから一発勝負と言いながらも何かとやり直しをしていたが)を敢行してから、スクリーンに映像が映し出される「恋のスペルマ」へ。
ホルモンはいろんなフェスやイベントや対バンなどに積極的に出演していて、そうしたライブでは「恋のメガラバ」などを最後に演奏している時もあるらしいが、JAPAN JAMの時もそうだったように、フェスの出演の締めをこの曲に託している。それはこの曲のMVの「フェスでの楽しみ方講座」という、コロナ禍の現状ではそうした楽しみ方ができない今の世の中、ライブシーンを自分たちの音を鳴らす姿で取り戻そうとしていることに他ならない。メンバーそれぞれもコミカルかつ器用なキャラクターがほとんどであるが、そのライブへの熱さは全く変わることはない。どんなに新譜や新曲が何年もインターバルが空いたとしても、このフェスなどあらゆるフェスに何回も出演してきたからである。そしてそのフェスでこの日のように確かな爪痕を残してきたバンドでもある。
去り際にダイスケはんはこのフェス入場時に配られる
「フェスを止めない」
と書かれたラバーバンドを装着した腕をカメラに向けた。それはホルモンが来年以降もフェスを止めないために動き続けていくということだ。そんなホルモンの頼もしさを改めて感じた2021年だったが、来年はその今年のホルモンのライブや活動の結果が少しで見える年になって欲しい。またスタンディングのフェスのライブで靴紐が解けた人を守ったりという、バカ極まりないけど愛しかないフェスの客席の光景が戻ってきますように。
1.シミ
2.maximum the hormone II 〜これからの麺カタコッテリの話をしよう〜
3.ハングリー・プライド
4.絶望ビリー
5.令和ストロベリーバイブ
6.恐喝 〜kyokatsu〜
7.皆殺しのメロディ
8.恋のスペルマ
17:50〜 MAN WITH A MISSION
2021年は様々なフェスに出演し、自分たちのツアーもアリーナ規模で開催してきたことによって「音楽を止めない、フェスを止めない」ということを自分たちの活動をもって体現してきた、MAN WITH A MISSION。立ち位置的にはトリでもおかしくないバンドであるが、そこは先輩(?)の10-FEETに譲り、今回はトリ前での出演となる。
おなじみの勇壮なSEでメンバーたちが登場し、観客もガウガウポーズで待ち構えると、早くもスクリーンには宇宙などを想起させる映像が映し出される「Change the World」からスタートし、ストレートなマンウィズのロックサウンドの曲であるが故に、そこに乗るメッセージが英語歌詞メインであっても強く響く。
「夢見た景色 手にするまで」
「道無き道を 切り開いて」
というそこにわずかに差し込まれる日本語のフレーズはまさに今この世界の状況の中で戦っている狼たちの姿そのものである。今みたいな世界を変えたい。その思いがマイクを握りしめて前屈みになって歌うトーキョー・タナカ(ボーカル)の姿や声から強く滲み出ている。
するとここで E・D・ヴェダー(サポートギター)ではない狼ではない人間がマイクを持って颯爽とステージに登場。それはこの次に出てくる10-FEETのTAKUMAであり、同じ日だからこそやるだろうなと思っていた「database」をコラボバージョンで披露してTAKUMAはラップをかますのだが、曲後半でTAKUMAがステージ袖の方を手招きする。最初はカメラマンをもっと近くに呼んでいるのかと思ったのだが、いざ出てきたのはNAOKIとKOUICHIで、10-FEETの3人が自分たちの出番前にステージに揃うのだが、2人は演奏や歌唱に参加するわけではなく、NAOKIはステージ上で何故かひたすら腹筋ローラーをし続け、KOUICHIがそれを見守っているという姿に観客だけならず、ジャン・ケン・ジョニー(ボーカル&ギター)も爆笑している。フェスそのもの、ライブそのものをこうしてさらに楽しいものにしてくれる両バンドは本当にカッコいいロックバンドでありながらも最高のエンターテイナーだと思う。
曲が終わってもジャン・ケンは
「あれ反則だろ!面白すぎる!(笑)」
と笑いながらも、
「2年ぶりに開催のこのフェス。これがないと1年が終わるっていう感じがしない!」
と、かつてこのステージの年越しという大役を務めたバンドだからこそのこのフェスへの思いを口にして、アルバム「Break and Cross the Walls I」を今年リリースしたことを告げると、そのオープニング曲である「yoake」を、まさにライブシーン、フェスシーンの夜明けが今年の冬から始まるとばかりに太陽が輝き、それがリンゴの形になるという人類創世を思わせるような壮大な映像をバックに演奏する。
ちなみにアルバムはこの曲で始まった直後にAC / DC「Thunderstruck」のカバーが収録されているという狼たちのロック精神が炸裂しているアルバムで、最初に聴いた時は「ここでもうこのカバー来るの!?」とビックリした。
そしてカミカゼ・ボーイ(ベース)とスペア・リブ(ドラム)のリズムを中心にさらに爆音スタジアムロックが響く「Take Me Under」、タイトル通りに感情を伸びやかなメロディに込めながらもサビで爆発するかのような「Emotions」と狼たちの代表曲にして現在のロックシーンのアンセムが次々に連打されていくのだが、ロッキンオンのフェスに出るのが久しぶり(ちょうど2年前のCDJ1920の同じ12/29以来)ということもあってか、スクリーンには見えてはいけないであろう部分も多々映り込んでいるように見えるのは後の放送でちゃんと使えるのだろうかというところが不安にもなる。
近未来的な映像がもはや完全にワンマン並みのクオリティであり、このバンドがそうした部分にも力を入れてきたライブを行ってきたことがよくわかる「INTO THE DEEP」ではDJサンタモニカが自身の近くのカメラに向かって目線を送りながらパーカッションなどを叩くという姿が実に可愛らしく見えるのであるが、深く潜ったところからサビで一気に飛翔するような展開はこうした大規模な会場であればあるほど映える曲だと言えるだろう。
そんな中でジャン・ケンは観客に
「今年はたくさん笑いましたか?」
と問いかけると、そんなに拍手が起こらなかったので、
「そんなに笑えなかった1年みたいですね。来年はもっと笑える年になるように、我々で掴み取りに行きましょう!」
と言って、笑うというよりも曲のあまりの切なさと美しさに泣けてきてしまう「Remember Me」を演奏するのだが、いつも表情が変わらないように見える狼たちも笑うのだろうか。というよりもきっと、狼たちは我々目の前にいる人たちが笑う顔を音楽で掴み取りにいきたいんだと思う。それはそのまま今年何を言われようと自分たちの音楽と、それを鳴らせる場所を作ってくれた人たちを信じ続けてきたマンウィズの姿勢そのものだ。
それはラストの「FLY AGAIN」でマスク越しではあるが、ここにいた人だけは全員笑顔になれているということにも繋がる。カミカゼの目が鋭く発光しながら、ジャン・ケンは観客を煽りまくり、その観客たちは腕を振り上げてサンタモニカの動きに合わせて踊りまくる。今こうして笑えているということが、間違いなく来年はもっとその場が増えていくような、そんな感覚を確かに抱かせてくれた。スペア・リブの無言での演奏後のおなじみの
「1,2,3ダー!」
も、あまりにシュール過ぎて笑えてきてしまった。
ツアーこそ行けなかったけれど、今年はいろんなところでマンウィズのライブを見れた。そこではいつも自分たちが先頭に立って音楽と音楽が鳴る場所を守ろうとする強い意志を感じられた。音楽をやるために生まれてきた5匹だから、音楽が不要なものになったらきっとまた冷凍保存されたりしてしまう(設定上)。
そんな5匹だからこそ、音楽が生きる上で必要なものであることを証明するために戦い続けているし、ロックバンドが何よりもそのエネルギーを持っているということも証明しようとしている。来年は今年よりさらにたくさんライブを見れて、さらに笑えていますように。
1.Change the World
2.database feat.10-FEET
3.yoake
4.Take Me Under
5.Emotions
6.INTO THE DEEP
7.Remember Me
8.FLY AGAIN
19:05〜 10-FEET
すでにMAN WITH A MISSIONの時にも全員がステージに出てきた10-FEETはこれまでにこのフェスのEARTH STAGEとGALAXY STAGEの両方で年越しを務めたことがあるという、盟友のサンボマスターとともに数少ないバンドである。年越し以外にも何度もトリを務めたりと、自分たちのフェスがあるにもかかわらずこのフェスを背負ってきただけに、この日の出演者の中でトリを務めるというのも実に納得できることである。
時間になって場内が暗転してもなかなかおなじみの「そして伝説へ…」のSEが流れずにステージ裏から明らかにツッコミ的な声が聞こえてくる中、観客はみんなタオルを掲げて3人がステージに登場するのを待ち構えている。様々なルールがたくさんある今のライブやフェスだけれど、この光景だけはずっと変わらない。いや、ロッキンオンのフェスでは禁止されているとはいえ、他の場所でも肩車したりできないという点では変わっているのか。
そうして3人がステージに登場すると、TAKUMA(ボーカル&ギター)が
「よっしゃ行くぞー!」
と気合いを入れてギターを弾き始めたのはいきなりの「RIVER」のイントロで、歌詞が「花見川」に変わるのはこれまでに数え切れないくらいに見てきた幕張メッセでの「RIVER」であるのだが、間奏部分でTAKUMAは観客を椅子に座らせてスマホライトを点けさせると、そのライトを前から後ろに、さらには後ろから前にというウェーブのように光らせる。その光景は規模や動員数が縮小されたとはいえ、こんなにもたくさんの人がこのフェスに来ている、10-FEETのライブを見ているということを視認させてくれて感動してしまうのだが、後ろから前へのスマホライトのウェーブの終着点としてKOUICHI(ドラム)にスポットライトが当たるとKOUICHIが立ち上がってポーズを取ったためにリズムが止まってしまうという茶番によって感動が一気に笑いに変わる。その感動と笑いの2つをライブで同時に感じさせてくれるのが10-FEETだよなと改めて実感しながらも、観客は椅子から立ち上がるタイミングを失ってしまったために、TAKUMAが最後のサビの前を歌い始めると慌てて観客を立ち上がらせるというあたりも実に10-FEETらしい綺麗に決まらない感だ。
「RIVER」を演奏するとTAKUMAは
「ありがとうございました!10-FEETでした!」
と早くもライブを終わらせて、
「アンコールやります!」
と2曲目からアンコールになるというのもいつもの10-FEETのやり口であるが、ここで先ほどのお返しとばかりに「super stomper」ではMAN WITH A MISSIONのジャン・ケン・ジョニーとトーキョー・タナカのボーカル2人が登場してTAKUMAとともに歌うのだが、それを上回る存在感を放ったのが、虎の被り物を自身の頭部につけて、リュックを背負ってステージに出てきたカミカゼ・ボーイ。ステージ中央に座ると自身の両脇に鏡餅を置くという姿には先ほどのNAOKIの腹筋ローラーを超えるインパクトを与えられる。まさかこんなに笑えるようなコラボがマンウィズがゲストで参加する側で見れるとは。去り際にTAKUMAにいじられまくる姿も含めて本当に楽しい時間を作ってくれている。
そんな爆笑するような後に演奏されたのがNAOKI(ベース)のコーラスとの掛け合いも含めて歌詞、特に某ロック好きな作家の著作のタイトルにもなった
「また同じ夢を見ていた」
というフレーズが沁みる「蜃気楼」というこのギャップは感情を整理するのが実に難しいのだが、やはりアルバムこそ毎回のようにかなりスパンが空いているとはいえ、近年リリースされてきたシングル曲たちもまたラウドなサウンドでアッパーに盛り上がるというよりはどちらかというと聴き入るような曲が多い。
同期の音も使った「ハローフィクサー」こそそのサウンドも含めた爆発力を感じさせるが、今年リリースされた
「信じたいから 疑いました
傷つく前に 傷つけました
守りたいから ウソをつきました
次第に痛みも 分からなくなって」
というフレーズによって始まる「アオ」はやはりその歌詞を噛み締めながら聴かざるを得ない。タイトル通りに真っ青な、蒼さというよりも沈むような色合いの照明がステージを照らす中で最後に放たれる
「そっと優しさを知って」
というフレーズは、その後のTAKUMAの
「SNSとかでの誹謗中傷。自分がその言葉を言われたらどう思うか。送信する前に一度立ち止まって冷静になって考えてみたらそういうことも減るんちゃうかなって。
優しさは想像力。言われたらなんて思うか。直接伝えられない文字では伝わりきらないものもある。「ありがとう」も口に出すと言い方によって受け取り方は変わる。(実際に言い方を変えて何度か口にする)」
というMCにつながっているし、それがさらに次に演奏された「シエラのように」へと繋がっていく。
「僕らみんな分かり合えてないよ
やさしくもできてないけど
それでもみんな なんとかやってるのさ
よろしくやってるのさ」
という歌詞通りの世の中なのかもしれないけれど、こうして10-FEETのライブを見れば少しは優しくなれるような、そんな温かさがその音と鳴らす姿には宿っている。それこそが10-FEETというバンドと、そのバンドが主催するフェスがこんなにも信頼されるものになった要因なんじゃないかと思う。
「持ち時間、アンコールの分までもらってるけど、捌ける時間ももったいないから、出来る限り曲やるわ」
と言うと、そこからは「VIBES BY VIBES」でアッパーに転じると、ここにいる全員の2021年の様々なモヤモヤしたものを全て遥か彼方へ放り投げるような渾身のボーカルと演奏の「その向こうへ」、さらにはNAOKIは体操の選手になるのかとすら思えるくらいに開脚しながらベースを弾く姿が、
「スマホとかネットとかがなかったら
今より少しは分かり合えたかな」
と歌詞を変えてまでシリアスなメッセージの曲を演奏しているのに笑えてきてしまう「ヒトリセカイ」と曲を次々に連発していく。こうしてこれまでのライブで演奏してきたキラーチューンも逃すことなく聴けるのは持ち時間が多いトリだからこそでもある。
しかしそれももう
「時間的に次で最後の曲や」
ということで、最後に演奏されたのはこれまでも何度となくこのフェスのトリとして演奏してきた「CHERRY BLOSSOM」であるのだが、今までと違うのは客席でタオルが舞わないということ。それはこのフェスがタオル回しを飛沫拡散防止の意味で禁止しているから(投げるのはどうなのかはわからなかったけど)であり、観客側がそのフェスの意志をしっかりと汲んでいたということでもある。だからこそ、タオルが舞う瞬間の感動とはまた違う感動を確かに感じられた。それは2021年に計り知れないくらいに悔しい思いをしてきたであろう、10-FEETを愛する人たちがバンドとライブとフェスを守ろうとしている姿だった。
そんな「CHERRY BLOSSOM」で大団円かと思ったら、
「まだちょっとだけ時間あるからもう1曲だけやるわ」
と言って「RIVER」を1フレーズだけ演奏した。それは四星球の「時間がない時のRIVER」の逆輸入であるが、もはやそれは完全に10-FEETの持ちネタみたいになっている。四星球はこうなることを想定していただろうか。
TAKUMAが口にしていたSNSなどの誹謗中傷によって命を絶ってしまった人もいるし、プロ野球などのスポーツ界でも今それは本当に切実な問題になっている。それはきっと今年10-FEETの3人が実際に言われまくったことでもあるのだと思う。開催直前になっての京都大作戦の2週目の中止。バンドやメンバーが言われたり、参加者やファンにそういう言葉が飛び交うところだって目に入ったりしてしまったことと思う。
そんな3人が来年は笑顔で自分たちのフェスの閉幕宣言ができますように。そして来年の年末もここでこうして3人と一緒に笑顔になれていますように。
1.RIVER
encore
2.super stomper w/ ジャン・ケン・ジョニー、トーキョー・タナカ、カミカゼ・ボーイ
3.蜃気楼
4.ハローフィクサー
5.アオ
6.シエラのように
7.VIBES BY VIBES
8.その向こうへ
9.ヒトリセカイ
10.CHERRY BLOSSOM
11.時間がない時のRIVER
文 ソノダマン