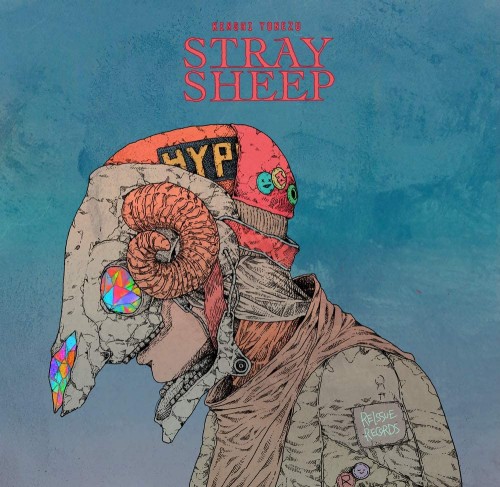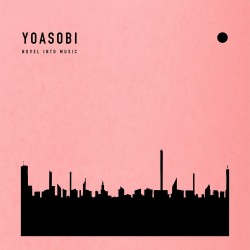“Lemon”、“パプリカ”といった国民的ヒット曲を生み出し、満を持して発売された米津玄師の最新アルバム。このアルバムには米津玄師にとって2つのエポックメイキングがあって、ひとつはボーカル。いままでの米津玄師はマイクの前で直立不動で歌うような、すごく日本のバンドマン的なお行儀のいい歌唱法だったんだけれども、今作では曲の世界をより表現するためにはどのように歌えばいいか、どの筋肉を使ってどういった声で歌えば曲に入り込めるかというところに焦点を当てているように感じます。それは「こっちのほうが正解でしょ。普通の歌い方よりも自分をむき出しにして曲が伝わるほうがいいじゃん。『昔の米津くんのほうがよかった』とかいうなら昔の曲を聴いてなよ」とでもいうような、身をよじったり、悶えたり、飛び跳ねたり、暴れまわったりしながら歌う姿が目に浮かぶほど強烈なもので。それが結果的に米津玄師が日本トップクラスの表現力を獲得するに至ったのだと思います。
もうひとつのエポックメイキングはサウンド。もともと米津玄師はボカロP時代からすべての音を自分で生み出していたけれど、音選びの感度が抜群に良くなっていて、そこでこの音選ぶ!? みたいな驚きがどの曲にもあります。ボカロP時代や『diorama』では騒がしいくらいにいろんな音をぶっこみまくっていて、音の情報量が洪水みたいだったけれど、今作のトラック数はおそらく過去のどのアルバムよりも多くて。でも騒がしいというわけではなく、正解の音が1/8章節ごとに飛び込んでくるような、サウンド的な展開を可視化すると目まぐるしいんだけれど、それを感じさせない音の整理、計算がすさまじいのです。
殻を破ったというか一皮むけたというか、米津玄師はもともととんでもないところにいたけれど、さらに高みに上ってしまったなあ。だけども芸術的なプログレッシブな方向に行くではなく、ポップの枠にギリギリ留まりつつ、そのポップの枠を内側からハンマーでガンガンぶっ叩いてポップの枠を広げているような、ポップの枠組みすら「米津玄師以前」「米津玄師以降」にわけられることになるんだろうなと思う、時代の分岐点になるアーティスト、そしてアルバムです。
文 高橋数菜
今年随一のメガヒットアルバムにして、毎月愛読している某雑誌では年間ベストアルバム1位に輝いた、米津玄師の名前を完全に世の中に浸透させたアルバム。
とはいえ自分は未だに「diorama」の衝撃、「YANKEE」と「Bremen」の楽曲の素晴らしさにどっぷりと浸ったままなので(その3作は全て年間ベスト1位にした)、その頃のサウンドからしたらかなり変化しているが、そもそも米津玄師は近年のライブでのMCにおいて
「変わり続けていくけれど、この船からは誰も落としたくない」
と自身の音楽性が変わり続けていくことについて口にしている。実際にここまで変わっても「感電」のような2020年を代表するような大名曲に加え、菅田将暉に提供した「まちがいさがし」、Foorinに提供した「パプリカ」をガラッとアレンジを変えることによって完全に「米津玄師の曲」にしてしまうのは流石という言葉では足りないくらいだ。
米津玄師はこのアルバムのリリース前、タイミング的にはシングル「馬と鹿」のリリース後にアリーナツアー「HYPE」を開催した。コロナの影響でそれは完遂することは出来なくなってしまったが、それは150人規模のライブハウスから始まって、今まで見てきた米津玄師のどのライブよりも素晴らしい、今の音楽性を手に入れた米津玄師でしかできないものだったことが2020年の数少ない収穫だった。
文 ソノダマン