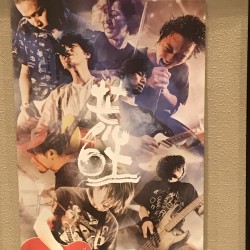コロナ禍によって昨年は様々なライブやイベントやフェスが中止や延期になってしまったが、それを違った形でリベンジするという選択肢もある。
Saucy Dogは初の武道館ワンマンへの道のりの一つとして、昨年に豪華なバンドたちとの対バンツアーを予定していた。そのツアーも中止になってしまったのだが、そのツアーに出るはずだったバンドたちを1日に一箇所に集めるという形でのリベンジをそのまま「リベンジエピソード」というタイトルのライブとして開催することに。
ASIAN KUNG-FU GENERATION、THE BAWDIES、ハルカミライという豪華なバンドたちが日本武道館に集結。Saucy Dogは前日にこの日本武道館でのワンマンを完遂しているだけに、この武道館で何回もライブをやってきた先輩や、武道館を超えるキャパにまで達した同世代の豪華な対バンの後にどんなライブを見せるのか。
日本武道館は昨年改修工事(オリンピックに向けての改修でもあっただろうに、そのオリンピックが未だに開催の目処が立っていないのは実に皮肉なことだ)を経て、敷地内に新たなレストランが建設され、武道館内の通路やトイレなどは実にキレイになっている。それでも中に入ると今まで数え切れないくらいに見てきた武道館と全く変わらない独特の圧力を感じる。(客席内は改修されていないだけに)
武道館を1席おきにするとこんなにも空いて見えるのかという景色が新鮮に思えるのは改修してから武道館に来るのが初めてというのもあるが、緊急事態宣言を受けて開演時間を大幅に繰り上げた16時になると、それまではこの日のイベントのビジュアルが映し出されていたスクリーンが消え、暗転した場内の中をステージ上のミラーボールが照らす。これまでに何回も見てきた、あのバンドの武道館ライブだ。
・THE BAWDIES
そうしてミラーボールが輝く中、おなじみの「SOUL MAN」のSEが鳴ってステージに登場したのはキャメルカラーのスーツを身に纏った4人組ロックンロールバンド、THE BAWDIES。この日本武道館では3回ワンマンライブを行っており、その3回のライブで武道館への特別な思いを言葉や音にしてきたバンドであるだけに、こうしてまた武道館で観ることができるのが本当に嬉しい限りだ。
いきなりの「IT’S TOO LATE」から完全に爆音のロックンロールが武道館に響くのだが、そもそもがSaucy Dogの対バンにTHE BAWDIESが誘われるのが実に意外というのは自分も感じていたことであるが、座席に座ったままという人も多いし、明らかに「THE BAWDIESのことを知らない」というアウェー感を客席から感じる。近年はフェスでもメインステージではないステージに出ることが多くなっているが、ここまでのアウェー感を感じるのは久しぶりな感じがする。
しかしながらこの「IT’S TOO LATE」の曲の締めとなるおなじみのROY(ベース&ボーカル)の超ロングシャウトが響くと、「あれ?めっちゃ凄くない?カッコ良くない?」という空気が武道館の中に広がっていくのを確かに感じることができたし、そういう意味ではこの曲を1曲目、この日の最初に鳴らされた曲として選んだのは間違いなく正解だろう。
とはいえ「IT’S TOO LATE」しかり、「LET’S GO BACK」しかり、今までずっとライブを観てきたファンの身としては、やはりTHE BAWDIESのライブで声を出すことができない、メンバーと一緒に歌うことができないというのは拷問に近いものを感じてしまう。それこそ「LET’S GO BACK」はサビが歌詞がないということからも、明確に何も考えることなくみんなで大きな声で歌うという目的を持って作られた曲であるだけに。それでも早くもJIM(ギター)はこの広い武道館のステージに久しぶりに立てている喜びを爆発させるように飛び跳ねたり、動き回りながらギターを弾いたりと、メンバーは実に楽しそうであるというのはこうした状況でも全く変わることがない。
とはいえやはりタイトルからして観客も一緒に歌ってこその曲である「SING YOUR SONG」ではライブではおなじみの間奏のコール&レスポンスパートすらもないという、声が出せない状況になってしまったからこその音源のままのバージョンで演奏されるというのはむしろこの状況でのライブじゃないともう観れないものと言えるかもしれない。とはいえやっぱりROYに悪戯っぽく煽られながら、普段生きていたら絶対に出すことのない声量でサビを思いっきり歌いたいとも思ってしまうのだが。
ここでの最初のMCでROYが
「ロックンロールバンドは怖くないですよ〜!」
とアピールしながら、普段はフェスでもやることのないメンバー紹介をするというあたりはやはりメンバーもこの普段とは違うアウェー感を感じていたのかもしれないが、
JIM=クレイジーホース(ニール・ヤングへのリスペクトも込めて?)
MARCY=幼稚園の頃からROYが大事に育ててきた、可愛いペットみたいな存在
と、2人を丁寧に紹介したのにTAXMAN(ギター)だけは名前を呼んだだけといういじりっぷりにTHE BAWDIESの楽しいバンドらしさが現れている。
「辛い物ばかり食べるのもキツいと思うので、カレーにおけるラッシー的な飲み物を」
と言ってから演奏されたのはTHE BAWDIESの持つメロディの良さを世に知らしめたミドルテンポの「LEMONADE」。CMなどでも使われていた曲だけに、THE BAWDIESのことを知らなくてもこの曲は聴いたことがあるという人もいたと思われるし、そういう曲を持っていることの強さというものを、熱いロックンロールではない部分からも感じることができる。
そのままアウトロとイントロをMARCYのドラムが繋ぐような形で演奏されたのは「KEEP YOU HAPPY」。近年はメドレーの中に組み込まれるという形でライブで演奏されることも多い曲であるだけにフルで聴けるのは嬉しいし、オープニング同様にミラーボールが輝く中でこの曲が演奏されるという楽しさは何物にも変え難い幸福さを感じることができる。個人的には今でも2011年11月に開催された、初の日本武道館でのあまりに最高過ぎたワンマンを思い出してしまう。
そんな中で最新のTHE BAWDIESを見せる意味を持って演奏されたのは世に出ている曲としては最新の曲になる「SUN AFTER THE RAIN」。TAXMANのエフェクターによる空間的とも言えるイントロのギターサウンドはバンドにとっての新たな挑戦とも感じられるが、サビではやはり爆音のギターサウンドに転じたTAXMANがステージ前まで出てきて最前列の観客の目の前でギターを弾いているという姿もまた新曲であっても観ている側のハートに火をつけてくれる。
すると初めてライブを観る人のために
「準備に入ります」
と宣言してから、おなじみの「HOT DOG劇場」へ。
今回もこれをやるのか!?とも思ったけれど、よくよく考えたらどんなに持ち時間が短いフェスやイベントでも毎回やっては爆笑を巻き起こしてきたのであった。
今回は近年続いていたシリーズものではなく、ROYが魔女のキキ役として、ジジ役(原作を見たことがないので正直よくわからない)のTAXMANとともにソーセージに乗って配達をするという「魔女の宅急便」バージョン。
おばあちゃん役(相変わらずボーカルではないのに役に合わせた声の変えっぷりが素晴らしい)のJIMから孫役のMARCYにパンを配達するのだが、MARCYが「マズイからいらない」と言ったことに怒ったROYがソーセージで殴りかかるとMARCYがパンで受け止めてホットドッグが完成、という劇場を経ての「HOT DOG」は明らかにTHE BAWDIESというバンドがカッコよくも面白いということを初めて見る人にも伝わるものになっていたし、マスクをしていても笑い声が漏れて聞こえてきた。最近はやたらと長尺化(ROY以外がセリフを覚えきれずに録音したものを流すくらいに)してきている劇場が、バンドとメンバーのパーソナリティを伝えるための大事なものになっているということはアウェーだからこそ感じられたことなのかもしれない。
だからこそリズミカルかつポップな「SKIPPIN’ STONES」(最高傑作だと思っているアルバム「Section #11」の曲を武道館で聞くことができるというのはTHE BAWDIESのファンにとっては心から嬉しいことなのである)から、
「最後にでっかい花火を打ち上げましょう!」
と言ってから演奏された「JUST BE COOL」では最初の方には座って見ていた人たちもみんな立ち上がって曲に合わせて飛び跳ねているという、アウェーな空気を45分間で完全にホームなものに変えてしまっていた。
その景色を見ていたら、自分自身まだTHE BAWDIESのことを全然知らなかったメジャーデビュー時のライブのことを思い出さざるを得なかった。ライブハウスの中で盛り上がっているのは最前列の2列くらい。完全なるアウェー。でも終わった時にはそこにいるみんなが汗をかいて笑顔になっている。そんな楽しさとカッコ良さを知ってしまったから、それからずっとこのバンドのライブを観てきた。
そんな、THE BAWDIESというバンドの凄さの原点を確かめさせてくれるとともに、今も昔からロックンロールの魔法がこのバンドには宿ったままであることを実感させてくれた。
この日初めてTHE BAWDIESのライブを観たSaucy Dogや他のバンドのファンがまたTHE BAWDIESのライブを観てくれたら、THE BAWDIESのライブをずっと観てきたファンの人たちがまたこの武道館でTHE BAWDIESのライブが見れる日が来てくれたら。そう願わずにはいられないくらいに、この日の出演者の中では最も「日本武道館にロックンロールバンドが立つ意味」を自覚しているバンドだから。
1.IT’S TOO LATE
2.LET’S GO BACK
3.SING YOUR SONG
4.LEMONADE
5.KEEP YOU HAPPY
6.SUN AFTER THE RAIN
7.HOT DOG
8.SKIPPIN’ STONES
9.JUST BE COOL
・ハルカミライ
コロナ禍になるまでは年間130本くらいライブを観てきた身として、近年の若手バンドの中では最もライブが凄まじいと思っているのがハルカミライである。
であるが、2020年はアルバム「THE BAND STAR」をリリースしてツアーを行ったにもかかわらず、ハルカミライのライブを観ることができない1年だった。ただでさえキャパの小さいライブハウスを感染対策で動員数を減らしているので、チケットが全く取れなかったのである。(そのためにライブに行きたい人が全員行けるように、12月には前年よりもさらにキャパを広げた幕張メッセでのワンマンを開催するつもりだったらしい)
そのため、COUNTDOWN JAPAN 19/20のCOSMO STAGE以来に観るハルカミライ。ちなみにCOUNTDOWN 20/21が開催されていた場合は同じ時間にGALAXY STAGEのトリがハルカミライ、EARTH STAGEのトリがアジカンだったため、この日はその厳しい被りを回収できるライブでもあったのである。
ステージ転換が終わって場内が暗転した時にはすでに関大地(ギター)、須藤俊(ベース)、上半身裸の小松謙太(ドラム)の3人が位置についており「NEXT ARTIST IS ハルカミライ」の文字がスクリーンに映った瞬間にメンバーが音を鳴らし、白いロンTを着た橋本学(ボーカル)もステージに現れると、「君にしか」でスタートし、客席では自分の席から動かないままで観客が一斉に腕を高く上げる。ステージ上では関が最も上手の方まで歩いていき、須藤はベースを置き去りにして踊りまくり、ロンTを脱ぎかけながら歌う橋本は目元にフェイスペインティングを施している。
コーラス部分を観客が歌うことができないだけに純粋にメンバーの声だけが響く「カントリーロード」と、まさか常に観客の大合唱が響いてきたハルカミライのライブで歌えないライブが来るとは思っていなかったが、メンバーのライブハウスと全く変わらないどころか、ステージが広いことでより自由になっているようにすら感じる暴れっぷりと、この冒頭2曲の始まり方によって、自分が2019年までに観てきたハルカミライのライブとメンバーがやっていることは全く変わらないと実感できる。
「今日が新年初ライブだから昨日までずっと正月気分だった。ずっと餅ばかり食べてた」
という橋本のことを須藤はなぜか「0802」と呼ぶのだが、それは橋本が8月2日生まれだからだそうだが、どうにも番号で呼んでいると刑務所の中のように聞こえて来る。
新年初ライブと言っても予定がなかったわけではなくて本来やるはずだったライブが延期になってしまったからだが、およそ1ヶ月以上ライブをしていない時期というのが今までほとんどなかったであろうバンドであるにもかかわらず、これぞハルカミライなパンクショートチューン「ファイト!!」から「俺達が呼んでいる」という流れのスムーズさはライブのブランクを全く感じさせないが、その暴れっぷりはライブができないという檻の中から解き放たれた獣のごとしである。
この日のライブはステージの上のスクリーンにもライブ中の姿が映し出されていたのだが、ハルカミライの時はそれが全編モノクロになっていた。それは数十年後にこの映像を見た時に「伝説のパンクバンドの初武道館の映像」という感じでそのまま語り継がれていくようでもあったし、ブルーハーツがこの武道館でライブをやった時もこんな感じだったんだろうかと思う。
それでもメンバーは至って無邪気に、
「それぞれが動けない、その席こそが世界の真ん中!」
と橋本が言って、小松のドラムセットの周りにメンバーが集まり、頭上から映し出されている映像がどんな風になっているのかを気にしながら「春のテーマ」を演奏したりする。
日の丸信仰的な感覚は全く持ってないけれど、それでもやはりこの改修しても変わらずに武道館に吊るされている日の丸の国旗の下で演奏するハルカミライの姿を見ていると、紛れもなく今この瞬間、ここが、僕らが世界の真ん中にいるんじゃないかと思えてくる。
今この状況下で聴くことによって、このコロナ禍の世界を終わらせて、自分たちで新しい世界を作っていくという宣誓のようにすら聞こえる「世界を終わらせて」で橋本がロンTを脱いで上半身裸になったかと思いきや、そのロンTとマイクのコードが絡まってしまう。すぐさまそれを直してはロンTを着るというか被るようにしている姿がどこかお茶目で笑えてくるのだが、そんな橋本は
「カメラマンの兄ちゃん、そこにTHE BAWDIESのピックが落ちてるからそこの姉ちゃんに渡してくれ。形に残るものがあった方がこの日の思い出になるから。今日はそういうものを残しに来ました!」
と、武道館の歴史に残るんじゃないかというくらいの名言をあっさりと放ってみせる。
そもそもが先輩バンドのピックであるが、あれだけ激しいライブをしていても床に落ちているそれに気付くことができて、それをどうするべきかということを橋本はしっかりと理解して口にすることができている。それは橋本が普段からどんなことを考えて、どうやって人間と関わり合って生きているのかということがわかることでもある。気を使ったり媚びるのではなくて、1対1で向き合いながら、目の前にいる人がどうしたら喜んでくれるかということをよくわかっている。本当に優しい人間であると思うし、そのピックが貰えなかった側である自分を含めた何千人の人も、形に残るものは手にできなくても、この日のライブの記憶こそがこの日の思い出としてずっと残っていく。ハルカミライの初武道館ライブはこんなことがあったんだ、とここにいた人全員が後の時代の語り部になれるような。
そんなやり取りがあってからの「predawn」の
「それなら夜は煌めくだろう
そのうち夜は明けるだろう」
というフレーズがこの自由にライブを楽しむことができない今の状況からの夜明けを待ち望む我々のためのテーマソングのように鳴らされると、「THE BAND STAR」の中からは「100億年先のずっと先まで」を演奏。
ノイジーな関のギターはパンクというよりはオルタナ・シューゲイズという感触を与えてくれるくらいにバンドにとって新しいものであるが、懐の広さを感じさせる橋本のボーカルは本当に武道館を丸ごと包み込んでしまうくらいに素晴らしい。めちゃくちゃ歌が上手いというタイプではないけれど、その声量を生かした歌の飛距離はシンプルなバンドサウンドだからこそどこまでも飛ばせる。そこには確かな優しさや彼の人間らしさを感じることもできる。
「ハルカミライの初武道館はワンマンが良かったって言う奴がいるのはわかってる。でも友達が呼んでくれたんだ。それなら武道館だろうとどこでも行くよ」
と、橋本はこの武道館に立つことにした理由を話した。それはSaucy Dogが呼んでくれたからだと。
自分はこのライブにハルカミライが出るのが決まった時、座席がある武道館に出るのは今のモッシュやダイブをすることができない状況だからだと思っていた。ライブハウスでもステージや隣の観客との距離を取ることが必要とされる。それなら席指定の会場でもやることは同じであると。
でもハルカミライの理由はもっとシンプルだった。自分たちやファンの理想や希望のために断るんじゃなくて、友達のために初めてを捧げる。最初を守りとおすという美しさもあるけれど、それを待っていたらこの日のこのライブを観ることはできなかったし、音楽性としては全くと言っていいくらいに違うSaucy Dogのことをハルカミライは心から信頼している。
だから橋本は
「慎ちゃん(Saucy Dogの石原慎也)はどこで見てるかな?」
と石原の姿を探しながら、
「眠れない夜に私…」
と「アストロビスタ」を歌い始めるのだが、その後のフレーズを
「坂道を登った先の暗がり 星が綺麗に見えるってさ
地べたに寝ころんじゃうあたり あぁ君らしいなって思ったり」
と、Saucy Dogの「いつか」の歌詞に変えて歌った。この日だけは、ブルーハーツへの憧憬ではなくて、仲間のバンドへの愛情を歌うために。だからこそ曲の最後にも
「君の見る景色を全部
僕のものにしてみたかったんだ
あぁ君を忘れられんなぁ」
という「いつか」のサビをこれでもかというくらいにパワフルなボーカルで歌ってみせた。この日、自分たちがここにいる意味、ここへライブをしに来た理由。それを言葉だけでなく音で示す。話すのが仕事でもメインでもなく、音を鳴らして生きるバンドだから。きっと映像に残ることはない、ハルカミライが初武道館に立った理由をこのステージに刻みつけた、この場所にいた人しか観ることができない瞬間だった。
そんな感動的な雰囲気を自ら切り裂くようにおなじみのコートを脱ぎ、バンダナすらも外していた須藤はこの日2回目の「ファイト!!」を演奏しているのだが本人はやはりベースを置き去りにしてステージ前や下手側まで出て行ってはしゃぎまくるという自由っぷりを見せると、
「もし俺のこと 選ぶやつがいるならば
どうか どうか 負けずに追って来い
憧れはいつかライバルに変わる
葛藤はいつか希望に変わる」
という歌詞が仲間や先輩と同じステージに立つ対バンライブでのクライマックスだからこそリアルな感触を持って響く「僕らは街を光らせた」を武道館をバンドが飲み込むくらいのスケール感でもって響かせる。
そもそもがもう幕張メッセという武道館すら飛び越えた会場でライブをやっているバンドであるだけに、武道館に特別な感情を持っているというわけではないだろう。それでも、
「希望の果てを
音楽の果てを
この歌の果てを
歓声の果てを」
というサビのフレーズは2階の最上階からだとかなり距離があるようでいても物理的な距離感よりはるかに近く感じられる、何千もの上からの視線が真っ直ぐにステージに向けられる武道館のステージで鳴らされるからこそ響くような、本当の意味でこのスケールの会場のステージに立つようなバンドになったんだなと思えて、油断していると涙が溢れてきそうになってしまった。
「俺たち強く生きていかなきゃね」
という最後のフレーズは、変わっていく街の景色や周りにいた友人のことを思ってのものであるが、リリース時からは想像できなかったくらいに世界そのものが変わってしまった今だからこそまた違う意味を持って響く。でも大丈夫だ。こうして目の前でハルカミライが音を鳴らしていて、ハルカミライでしかいライブをやっているのを見れている限りは、我々は強く生きていくことができる。久しぶりに見たハルカミライのライブはやはりそう思えるくらいに輝いていて、瑞々しい生命力に満ち溢れていた。
そして最後に演奏された「PEAK’D YELLOW」の性急なパンクサウンドとメンバー全員で歌うサビとコーラスが、観客の拳を振り上げさせながら、座席指定であってもどこか以前までのぐちゃぐちゃになったライブハウスで見ているような感覚を感じさせる。そんなエネルギーをこのバンドのライブは放出している。夢というか、我々が思い描く美しい景色を音によって見せてくれるというか。
「灯りの先を覗き込んでる
明るい場所を探し望んでる
スーパースターもヒーローも
意味が無くなっちまうくらいの」
と歌いながらも、客席から見ている我々にとってはハルカミライがスーパースターでありヒーローなのだ。年上とか年下とか、職業や性別とか一切関係なく。またみんなで大きな声を出してこの曲を歌えるような、明るい場所に辿り着くための先導者として。
しかしこれで終わりかと思っていたら、須藤が
「まだ時間あるみたいなんで、もうちょっとやりまーす」
と言ってすぐさま「Tough to be a Hugh」「フュージョン」というショートチューンを連発してみせた。その持ち時間と自分たちのどの曲をあとどのくらいできるのかということを瞬時に見極めることができる洞察力は、めちゃくちゃやってるように見えてあらゆることに目を向けて空気を嗅ぎ取ることができるこのバンドの強かさを感じさせるものでもあった。
コロナ禍になってからハルカミライのライブを観るのは初めてだった。今まで野外フェスなどでは「大丈夫か?怪我人出ないか?」と思うくらいに激しいライブをやってはメンバーも小松以外が全員客席に突入していくというスタイルのライブをやっていただけに、果たして大丈夫だろうかとも思っていた。
それはメンバーというよりも客席側が、禁止されている大きな声を出したり、自分の席以外の場所に移動してしまったりという、我慢出来なくなってしまうんじゃないだろうかという意味で。
でもこの日、そうしたことをしている人は全くいなかった。それはバンド自身がダイブ禁止のフェスでは絶対にステージから降りない、客にもそういうことをさせないという、ルールを守るということのカッコ良さを観客に自分たちの姿を見せることによって伝えてきたバンドだからだ。
ルールやマナーを無視してまでめちゃくちゃやるのがパンクの在り方ではない。それは橋本がインタビューで
「俺にとってパンクっていうのは殴ることじゃなくて、抱きしめること。スピード違反するよりも決められたスピードで運転してる方がカッコいい」
と言っていた生き方そのものだ。そんなバンドの姿勢はバンドを見ている観客にも確実に伝わっている。ハルカミライはバンドだけではなくてファンも本当にカッコいい人たちだ。
「カッコいいバンドにはカッコいいファンがついている」というのはこの光景を見ると真実であると思えるし、これならばこの危機的な状況を越えていけると思える。
そしていつか、やっぱりこの会場でハルカミライのワンマンが見たい。その時にはディスタンスを気にすることもなく、武道館を揺らすくらいの満員の観客の大きな声が響くような状況でありますように。
武道館の2階席はかなり高い。高所恐怖症である自分からしたら怖くなるくらいに。でもこのライブが終わった時に足が震えていたのはその高さに怯えていたからではない。
1.君にしか
2.カントリーロード
3.ファイト!!
4.俺達が呼んでいる
5.春のテーマ
6.世界を終わらせて
7.predawn
8.100億年先のずっと先まで
9.アストロビスタ
10.ファイト!!
11.僕らは街を光らせた
12.PEAK’D YELLOW
13.Tough to be a Hugh
14.フュージョン
・ASIAN KUNG-FU GENERATION
ハルカミライが残した余韻の中、転換したステージには絨毯が敷かれ、この日の出演者の中では唯一のキーボードもセッティングされる。昨年には若手バンドを中心としたゲストを迎えた有観客ライブを行ったアジカンが、この日は若手バンド主催のライブのゲストとして武道館のステージに立つ。
SEもなしにシモリョー(the chef cooks me)を加えた5人編成でメンバーがステージに登場すると、昨年リリースの最新シングル「ダイアローグ」からスタート。これまでにこの武道館に何度となく立ってきたバンドとしての貫禄を感じさせる中、隙間の多いどっしりとしたサウンドはバンドの音の一つ一つがとてもクリアに聴こえてくる。決して爆音でも轟音でもないが、だからこそ伊地知潔のバスドラなどの低音の強さがよくわかる。「ホームタウン」から取り組んできた、ヒップホップやR&Bがポップミュージックとなった時代におけるロックバンドとしてのサウンドの刷新は音源はもちろんライブでもしっかりと身を結んでいる。ゴッチはパーマのかかり具合がさらに強くなっている。
アジカンはツアーやワンマンなどの自分たちの主催ライブとフェスやイベントという招かれて出演するライブとではセトリがかなり違うバンドである。それはそれぞれの場所に来る人たちが自分たちに何を求めているのかということをよくわかっているからであり、だからこそ主催ライブではレア曲なども多く演奏され、逆に代表曲的な曲はあえて演奏しないのだが、フェスやこうしたイベントではそうした代表曲をズラッと並べるようなセトリになる。
だからこそこの日は2曲目に早くも「君という花」を演奏し、後のギターロックバンドに多大な影響を与えた4つ打ちのリズムで踊らせる。とはいえやはり声が出せない状況ということもあって、おなじみの間奏での
「らっせーらっせー!」
のコールがないというのは「絶対に声を出してはいけないアジカンライブ」みたいな企画なんじゃないかと思ってしまうくらいに違和感がある。それはゴッチも喜多建介(ギター)もコールをしなかったというのもあるけれど。
続く「ソラニン」も普段ならばイントロのギターの音だけで歓声が起こるような曲であるし、実際にフェスでは何度となくそうした場面を見てきたのであるが、それがないからこそ実に静粛に曲と向き合う感じというか。
メンバーの背後から夕焼けを思わせるような赤い照明が発される中、それまではメンバーが演奏する姿が映し出されていたスクリーンにはこの曲の演奏時だけは何も映されていなかった。それは同名タイトルの映画の主題歌として生み出された曲であるだけに聴き手それぞれが様々な情景を脳内に描きながら聴くことができるようにというバンドサイドの配慮もあってこそのものだろうと思う。
この「ソラニン」の最後にはゴッチによる絶叫するようなボーカルパートもあるのだが、そこをこの日はキーを下げて歌っていたし、主催ライブではよく発するような掛け声的なものもほとんどこの日はなかった。
しかしそれはテンションが低かったということでは全くなく、勢いのある若手バンドもいるからこそ自分たちらしい演奏を丁寧に、かつ今の状況でライブができているということを慈しむような感情が音にこもっている。かつての長いツアーの中での「今日あんまり入ってないな」というような感じは今のアジカンには一切ない。
音に合わせて光の柱のような照明がメンバーを照らすのが美しいのはライブではおなじみの「ブルートレイン」のイントロでのセッション的なアレンジ。山田貴洋(ベース)がゴッチや潔の方を向いて演奏しているあたりにあらゆる意味でアジカンを支える献身的な彼の姿勢を感じることができる中、やはりこの曲を今聴くということは、
「日々に潜む憂鬱
それすら消えて無くなってしまうまで
生きたい…」
という締めのフレーズと向き合うということだ。潜むどころか表出しまくりの憂鬱的な出来事ばかりが次々に襲ってくる世の中になってしまったけれど、それらが消えて無くなってしまうまで生きていたいのである。
そんな憂鬱を切り裂くように我らがギターヒーロー喜多建介のソロが鳴り響く「荒野を歩け」ではシモリョーが率先して手拍子を促したりして、この日を楽しいものにしようという気概が伝わってくる。
それはやはりこうしたライブでは欠かさずに演奏される「リライト」においてもそうであるが、間奏のダブっぽいサウンドになるパートでのコール&レスポンスもなくゴッチが歌うのみ、当然ながらサビの
「消して リライトして」
を歌うことすらできないというのはやはり今まで生きてきた世界線とは違う場所に生きているということを実感せざるを得なかったけれど、ここまでヒットシングル、代表曲を連発できる、かつまだまだ演奏されていないそうした曲もあるということに、メジャーデビューから20年近く経った今もなお武道館をはじめとしたアリーナ規模のステージに立ち続け、フェスではメインステージのトリという最前線にして最高峰に立つバンドとしての強さをこれでもかとばかりに見せつけるようですらある。
そんな中でゴッチは
「Saucy Dogもスタッフもみんなも、いつもより一個何かしらの決断をしてここに来てると思う。
100%晴れやかな気持ちで来たわけではないと思うけれど、やっぱりこうして音を鳴らせば「来て良かったな」って思えるし、時間をかけてでもこういう場所を取り戻さないといけない」
と語った。
その言葉にこれ以上ないくらいの説得力があるのは、アジカンがこれまでの活動の中で手にしてきたものや作ってきたもの、今も様々なバンドやシーンに受け継がれているものがあるということをずっと見てきたからだ。
アーティスト主催フェスという今では当たり前になったものの礎を作り、そこで海外の音楽に触れられるような環境を作って音楽体験の広がりを作ってくれたり、2011年の震災以降は社会や生活に1人の人間としてどうコミットしていくのかということをその身を持って示してきた。そんな人間力を持った人だからこそ、その言葉に込められた決意の強さは我々にとって何よりも頼もしいものだ。きっとアジカンはこれからもまたそうした日々や場所を取り戻すための活動をしていくのだろうし、我々をその場所に招いてくれるはずだ。そこでまた一緒にこれからのことを考えながら。
そんな思いをthe chef cooks meの「Now’s the time」の
「We are all alone
We are not the same」
というフレーズに乗せて歌ってからそのまま曲へと繋がっていったのは「ボーイズ&ガールズ」。どっしりとしたテンポの曲であるが、だからこそ
「まだ始まったばかり」
という希望しか感じることのないフレーズがしっかりと響き、あくまでロックバンドとしてこの世界に対峙していくという意志を示すかのようにゴッチも喜多もステージ最前まで出て行ってギターを思いっきり弾く。その姿はこれまでにも様々なものを背負ってはそれに翻弄されたり、力に変えながら一度も止まることなく続いてきたアジカンがまた新たな何かを背負ったようにすら感じられた。演奏が終わってメンバーがステージから去った後の拍手はライブそのものに加えてアジカンという巨大な存在がこの時期にこうしてライブをやってくれていることへの感謝であるかのようでもあった。
1.ダイアローグ
2.君という花
3.ソラニン
4.ブルートレイン
5.荒野を歩け
6.リライト
7.Now’s the time 〜 ボーイズ&ガールズ
・Saucy Dog
そしてトリにしてこのライブの主催バンドであるSaucy Dogへ。前日にもこの武道館でワンマンを行っているとはいえ、前に出た3バンドによってあまりに高いハードルを設置されて、重いバトンを渡された状態でのライブとなる。
SEとともにせとゆいか(ドラム)、秋澤和貴(ベース)、石原慎也(ボーカル&ギター)が1人ずつステージに現れて来てくれた観客に対して頭を下げてから自分の立ち位置に着くというスタイルはこのバンドならではのオープニングであるが、出で立ちからも武道館だからと言って派手にめかしこむようなことは全くなく、至ってシンプルかつラフな自然体。
後でせとゆいかがMCで言っていたように、この日は「今更だって僕は言うかな」というじっくりとしたスタート。前日のワンマンはこの曲を本編の最後に演奏し、1曲目は「真昼の月」だったようなので対照的なスタートと言えるが、それがこの日の対バンライブということになるとアッパーに振り切れるだけではなく、そうした歌モノのバンドとしての自分たちのスタイルを示すようなものになっている。
「日本武道館ー!」
と石原が叫んでからの「シーグラス」からは一気にポジティブかつアッパーな、ロックバンドとしてのSaucy Dogとしてのライブに転じていくのだが、自分の世代からするとすでに同タイトルの名曲を生み出している先輩バンドの存在を知っていると思われるのにあえてそこに挑むというところにこのバンドの気概を感じる。
タイトル通りに青い照明がメンバーを包み込む「BLUE」とシンプルでありながらも
「運命なんか知らない 僕らで作ればいいや」
という力強いバンドの意思を感じさせる。その思いこそがバンドをこの武道館まで連れてきた原動力と言えるだろう。
「もう今日の出演者が発表された段階で今日が最高な日になるのはわかっていたけど、それ以上に本当に最高な日になったね!」
というせとのMCからはそうした日を自分たちが作ることができたことの喜びを感じさせたが、「雀ノ欠伸」からはさらにバンドの演奏が躍動感を増す中、歌詞も若手バンドならではのキャッチーさを感じさせるものになっているが、ラストサビ前の
「死ななければ」
というフレーズにハッとさせられる。無邪気なようでいてその中にはシリアスな死生観の上に成り立っていることがわかる。メロディもサウンドも歌詞もキャッチーそのものであるが、だからこそこうした1行の言葉があることによってそれだけではない重さを感じられるというか。
石原が
「コロナなんかぶっ飛ばしてやる!」
と力強く口にしてから演奏された「ゴーストバスター」はまさにゴーストをコロナに見立てればその通りに力強いサウンドによるロックナンバーであるが、
「「言いたいやつらには勝手に言わせておけばいいさ」
今度は僕がお前を救ってあげるよ」
という締めのフレーズは今の状況でライブをやると決めたことについてバンドがバンド自身にかけてやりたい言葉であるかのようだ。こうしてライブをすることによって救われる人がたくさんいるように、もしかしたらバンド自身はこの曲をはじめとした自分たちが生み出してきた曲によって救われているのかもしれない。
まさに車が高速道路を走るかのように疾走するようなせとと秋澤のリズムの上で石原が明らかに歌詞を飛ばしてしまって戸惑いながら歌っていたのは「バンドワゴンに乗って」であるが、その石原はステージの中央で固まるスリーピースバンドとしての形から1人大きくはみ出すようにステージ端まで駆けて行ってギターを弾いたり、大きくジャンプしたりする。その姿と、
「今日楽しかったって思える人ー!」
という観客への問いかけからは、このバンドにおけるライブというものが来てくれた人を楽しませるものという捉え方をしていることがわかるし、バンドの演奏のみによってそれを実践しようとしている。
そんな中ですれ違う男女2人の情景を、そのままドラマなりアニメなり映画なりにできるようなリアルな描写で描く「sugar」はワンマンではない持ち時間でこうしたバラードと言えるようなラブソングを持ってくることができるこのバンドの強さを感じさせる。もちろんそれは主催バンドだからできるということでもあるだろうけれど、そこに説得力を与えているのはこの武道館の大きさに見合うようなスケールを獲得するに至った石原のハイトーンに伸びるボーカルあってこそだ。若手バンドには確かにこうした高いキーと細い声質のボーカルが多いけれど、この日は他にそうしたバンドはいない。このライブ猛者たちとはまた違う武器であり、石原はそれを磨き続けてここに立てるまでになったということだ。
するとその石原がこの日出演してくれたそれぞれのバンドを紹介しながら、自分にとってどんな存在なのかを語る。
「THE BAWDIESを初めて見た人っている?(かなりの手が上がる)
ジャンルが全然違うもんね。でも僕らはいつも楽しいライブを作りたいって思っていて、THE BAWDIESはずっとそういうライブをやり続けている。僕らにとっては先生のようなバンド。
ハルカミライは関以外が同い年なんだけど、前に飲んだ時に学…0802だっけ?(笑)が、
「俺は本当はSaucy Dogみたいな歌のバンドがやりたかった」
って言ってて。逆に俺はハルカミライみたいなパンクバンドがやりたかった。ブルーハーツが好きだったから。お互いに描いていたバンドとは違うけれど、今は自分たちがやってることが最高だって思える。それが本当に嬉しい。
アジカンは本当に高校の時からコピーさせてもらっていて。「崩壊アンプリファー」を聴いて「羅針盤」とか、今日やってくれた「リライト」とか。
前にゴッチさんとはサシでご飯に行ったことがあって。やっぱりめちゃくちゃ緊張するじゃないですか。昔から憧れの人だから。タクシー乗った時に
「いやー、緊張します〜」
って言ったらゴッチさんが
「そう?俺はしないけど」
って(笑)そりゃゴッチさんは俺とご飯食べるの緊張しないでしょ(笑)」
と、THE BAWDIESを呼んだ理由、ハルカミライとスタイルは違えどお互いに認め合い、刺激をもらっていること、「羅針盤」という曲が出てくるというところにガチのアジカンファンであることを感じさせると、次があっという間に最後の曲であることを告げる。
だいたいこういうライブイベントの時はゲストが持ち時間が短くて主催が長いというものだし、この日もそうなんじゃないかと思っていた。でもゲストも45分という4組も出演する対バン側としてはかなり長い時間をもらっていた。その分、Saucy Dog自身も同じ持ち時間になったわけだけれど、そこに出てくれたバンドへのリスペクトと、「主催とオープニングゲスト」ではない文字通りの対バンライブであったことを感じさせたのである。
そんなライブの最後に演奏されたのは、
「心の中で歌って!昨日までの弱い自分に!」
と言って演奏された「グッバイ」。歌詞自体は確かに精神的に弱いというか情けない男の自省的なものであるが、今のSaucy Dogからはそうした弱さは全く感じない。こんな凄いバンドを3組も呼んで、その後にライブをやってもその3組に持っていかれることがない、派手なパフォーマンスも演出もないという自分たちのスタイルでこの日を自分たちの日にしてみせたからだ。
そんなバンドの姿を真上から映し出したスクリーンは本当に美しいトライアングルを形成していたし、もう弱い自分に別れを告げる必要がないからこそ、コロナが蔓延る今の状況にグッバイできたらいいのにな、と思いながら聴いていた。
武道館は改修されて、トイレや通路がびっくりするくらいにキレイになった。そんな内装も、1つずつ空いた客席も、自分の知っている武道館とは変わったことを実感せざるを得なかったが、「グッバイ」の最後で客電が点いて場内が明るくなった瞬間は、紛れもなく何度となく見てきた武道館のライブそのものだった。いつ、誰が始めた演出なのかは知らないけれど、武道館だからこそ見れる美しい景色。武道館が特別な場所であるというのはこの瞬間にあると言っても過言ではないくらいに、いつもとは違う見え方がする。今までいろんなバンドで何度となく見てきたこの瞬間は、これからもきっと変わることがない。
しかしメンバーがステージを去ろうとしている中、白いパーカーを着たスタッフがステージに出てきてメンバーを集めて何やら相談をしている。それが終わると石原は
「まだ時間があるみたいなんで、もう1曲やってもいいですか?」
と自主的にアンコールに突入。
「昨日、久しぶりに…2年ぶりくらいにやった曲なんだけど、最後にバラードでもいいですか?」
と言って演奏されたのは、ハルカミライが「アストロビスタ」の中でも引用していたバンドの代表曲「いつか」。
そんなに演奏されていなかった曲なのかと驚きもしたが、確かにバラードだけれどもこの日はそこに癒しや切なさというバラードが持ちうるような感情は全くなかった。ただただロックバンドの鳴らすバラードとしての強さと、これから先も進んでいくという意思。ゴッチが
「本当に歌が上手いよね」
と最大限に評した石原のボーカルがそう感じさせずにはいられなかったのだ。これから先、バンドがこの曲をどんな頻度で演奏していくかはわからないが、その聞こえ方はこの曲がリリースされてバンドの存在が注目され始めた時とは全く変わるものになるはずだ。
演奏が終わると、この日の出演バンドたちを招いての写真撮影。そうして少なくない人数が集まることに懸念する人もいるかもしれないが、今ライブやイベントをやる人たちはスタッフなども含めて全員が自主的に資金を投じてPCR検査をしているという。
(メンバーの感染がわかってライブが直前に中止になったり、舞台に出演する予定の演者が降板することになるのはそのためだろう)
ただ観客への配慮(ライブに来ていたことがわかって他の人に何か言われないように)から、今はまだこの写真を公開することはしないらしい。そこまで考えての写真撮影なら絶対に大丈夫だと思いながら、撮影が終わってアジカンとハルカミライのメンバーがステージから去っていくのに、THE BAWDIESのROYが全く帰ろうとせずにメンバー3人に強制的に連れて行かれるという実にROYらしい姿が本当に面白くて、その後に最後の挨拶をしたSaucy Dogのメンバーがより一層真面目に見えたのだった。
自分はこれまでにSaucy Dogのライブをフェスやイベントで何回かしか見たことがない。それはその時に感じたのが良くも悪くもあらゆる意味で「普通のバンドだな」というもので、何か突出したものが感じられず、唯一感じたものは、
「昔はa flood of circleのギターの青木テツがこのバンドにいたんだよな」
という自分の愛するバンドとの共通点くらいだった。
そうしたフェスで見た時とやっている曲はそこまで変わっていない。でも印象は全く違っていた。普通だと感じた曲は普遍性を持ったものとして、バンドのパフォーマンスは石原の歌によってもはや普通とは絶対に言えないレベルにまで達していた。つまり、ライブバンドとして確実に飛び抜けたものを感じさせる存在に進化していたのだ。
自分が10代の頃にライブに行くきっかけになったアジカン、年間100本くらいライブを見るような生活を選んだ頃に出会ったTHE BAWDIES、今もその生活をしているのが幸せだと感じさせてくれるハルカミライという3組も集めてくれて、そのバンドたちのライブを今の状況で見せてくれたということにも本当に感謝しかない。まだそんなにしょっちゅうライブを見れるような状況ではないけれど、やっぱり家で配信ライブを見たり音楽を聴くだけだとやっぱり物足りないんだ。そんな中でこんな日を作ってくれたバンドなのだから、近いうちにまた、いつか。
1.今更だって僕は言うかな
2.シーグラス
3.BLUE
4.雀ノ欠伸
5.ゴーストバスター
6.バンドワゴンに乗って
7.sugar
8.グッバイ
encore
9.いつか
文 ソノダマン