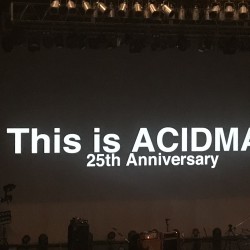2年ぶりの開催はこれまでの洋楽アーティストを軸にしたものではなく、情勢を鑑みて国内アーティストだけの出演になった、フジロック。
しかしながら同じ週末に開催されるはずだった、香川のMONSTER BASHが直前になって中止せざるを得ないという無念の状況になったことによって、フジロックも中止にしろという意見が寄せられることになった。
そんな中で初日だけの参加とはいえ、行くことを決めた自分が自身に課したのは、
「送られてきた抗原検査キット(2日前とかに送られてきた)で陽性反応が出たら行かない」
「着くまでの間に少しでも体調不良だと思うことがあったらやめる」
「会場内に「これはダメだ」「ヤバい」と思うことがあったり、人がいたらすぐにスタッフに言う」
という3点。キットを使った検査(説明読んで「こんな感じでやるのか」と思った)は陰性、体温も36.2℃だったために初のフジロックへ向かうことに。
会場近くのオフィシャル駐車場に車を停めたのだが、その周りにも店を営む方々が民間の駐車場に車を誘導しているというのは「フジロックは会場に近い駐車場がすぐ埋まるからチケットを取るタイミングによっては駐車場からシャトルバスに乗ることになる」というイメージもあった自分からしたら少し驚きだったのだが、やはり動員者を大幅に減らしていることによって、会場から遠い駐車場を使う必要がなくなったということだろう。
それに、本当に会場のすぐ近くで店をやったり、そこに住んでいる人たちが決して来場者を拒むことなく、店のトイレを貸し出ししていたりと、商売という面ももちろん重要でありながらも、きっと例年と同じように参加者を招いてくれているであろう姿に、会場に入る前から泣きそうになってしまった。
「地元民です。フジロック開催に反対します。新潟に来ないでください」
というSNSの意見もたくさんあったが、どこの誰のものかもしれないつぶやきではなく、自分の目で見た地元の方の姿はこれだった。それはこうして自分が実際に行かなかったら絶対にわからなかったことだ。
スキーもスノボーも全くやろうと思わない(学生時代にやったことはあるけど)人生だったので、スキー場というのが、特に雪のない夏はこういう景色なんだな、ということに少し驚きながらも会場に到着。
改めての入場前の検温はもちろん、フジロック公式アプリにて登録した顔写真と個人情報を含めた問診票をスタッフが確認してから中に入り、その際も小さなカバンやリュックでも警備員の方が中身を確認して、今年禁止されているアルコールの持ち込みをさせないという、従来のフジロックからは正反対とも言えるような体制はロッキンの入場時の手荷物検査も思い出す。そうした、開催することが出来なくなってしまったフェスたちの思いもきっとSMASHをはじめとした主催者側は背負っている。それを参加者である自分たちも心に刻んだ上で行動しないといけないな、と改めて思う。
入場し、初めてのフジロックなので各ステージの位置確認も含めて場内を一周歩いてみる。SNSで見ていた、裸足で入れる川はこのところ天国というエリアなのか、よく大雨の時に通行止めになるというボードウォークはこんなにも森の中なのか、など本当に自然と共存して続いてきたフェスであり、なぜ自分の好きなアーティストたちや、音楽ファンの先輩方が毎年ここに来ているのかということが、この会場の姿や雰囲気を見るだけでわかるような気がした。
10:30〜 KOTORI [RED MARQUEE]
初日のあらゆるステージの中で最初に音が鳴らされるのは、テント型ステージである、RED MARQUEE。そこにトップバッターとして登場するのは2年前にROOKIE A GO! GO!という新人枠で出演して、今年この位置でフジロックに戻ってきた、KOTORI。
このRED MARQUEEももちろん、各ステージの床には観客同士のディスタンスを保つための立ち位置マークが貼られている。個人的にはJAPAN JAMのように特に前方エリアはマスなどで1人1マスとして完全に区切った方が、配信を見ている人にも客席が距離を取っていることがハッキリと伝わったのでは、と思うし参加者にもわかりやすかったんじゃないかと思う。
2日目に出演するThe Birthdayのチバユウスケは今年豊洲PITで行われた、動員人数を半分に絞ったライブの感想を
「来ていた人は両隣がいなくて寂しかったかもしれないけど、ステージから見たらそこまで少ないって感じはしないもんだね。あんまり変わらないように見える」
と言っていただけに、ステージからのカメラに映った映像と実際の客席にはかなりの違いが生じることも含めて。
そんな中でステージにメンバー4人が登場すると、横山優也(ボーカル&ギター)が
「音楽で大切なものを 守れますように」
と歌う「We Are The Future」でスタートし、バンドの音がその横山の音に重なる瞬間に背後のスクリーンにバンドロゴが映り、横山は
「フジロックー!」
と叫ぶ。その声を合図にバンドの鳴らす音が力強くなる。この瞬間にたどり着くまでの数日間の間、本当に精神が削られていくようなことばかり(モンバスの中止やフジロックへ向けられた、人命を考えてのものとは思えない中止を求める発言、様々な主催者が声明を発表したり、出演辞退せざるを得なくなった状況など)だっただけに、このバンドの音が鳴った瞬間、
「響け
この声よどこまでも
We are the music.
We are the future.」
というサビをメンバー全員が歌い、観客たちが一緒には歌えなくても拳を挙げる姿に涙が出てきてしまった。そうだ、主催者も、出演者も、スタッフも、観客も、飲食や物販で働く人たちも、音楽で大切なものを守るためにここに来たんだ。それは開催に反対する人からしたら「綺麗事」と言って切り捨てられることであったとしても、この日この場所にいた人にとっては何よりもリアルな感情だった。細川千弘が立ち上がって吠えながらドラムのキックを踏む頼もしい姿がその感情をさらに後押ししてくれる。
「雨が止んで 窓の向こう
遠くに未来が見えたら
もうその手を離してもいい
君はもう何処へでも行ける」
というフレーズが雨が降ることが多いというフジロックに合わせたような、我々のここへ来た選択を真正面から肯定してくれるような「羽」、
「奇跡みたいな日々 最高の仲間よ」
と、この瞬間のことを歌ったかのようなフレーズで始まる「unity」と、前半はエモーショナルなギターロックを連発。少し緊張感もメンバーからは感じられるが、それ以上にこのステージに立つことが出来ている、演奏することができている、という喜びが、上坂仁志(ギター)の腰を深く落としてギターを弾く姿からも、基本的にはメンバーとリズムと呼吸を合わせるようにずっと横山らメンバーの方を向いて演奏しながらも、時折客席の方を向いた時の佐藤知己(ベース)の表情からも感じられる。
「フジロックで演奏するために作った」
という最新アルバム「We Are The Future」収録の「Anywhere」ではメンバー背後のスクリーンに歌詞のフレーズや、そのイメージに合わせた色などが映し出されていく。すでに両国国技館という会場でのライブも決まっているが、こうした演出とそれが似合うような曲を見せられるようになったということはバンドの新しい可能性を広げられるものだと言えるだろう。落ち着いたサウンドかと思いきや、後半に一気にノイジーになるという曲の構成も含めて。
ここに立てている喜びとともに、
「僕らは音楽を演奏することしかできないんで」
という横山の言葉からはそれ以外の様々な感情も持っていることも伺えたが、そうした絡み合うような、こんがらがるようなものを全て抱えながらも、音楽だけは真っ直ぐにこちらに飛び込んでくるかのような、KOTORI随一のキャッチーな曲である「トーキョーナイトダイブ」がまだ午前中であるにもかかわらず、この瞬間のためのアンセムであるかのように、メンバーも思いっきり感情を込めて鳴らされる。
「ここに君はいないのに」
というフレーズが、ここに来たくても来れなかった、来ることをやめた人の存在を思い出させてまた深く感情を揺さぶられる。それは丁寧に、というよりもひたすらに感情を吐き出すような演奏を見せるこの日のバンドのパフォーマンスによってより強く感じることだ。
そんな曲の後には、佐藤が左手で持ったトランペットを吹きながら、右手で開放弦のベースを鳴らすという二刀流であり器用な一面を見せる「雨のあと」という、この日はこの段階では快晴であったが、雨がよく降るフジロックに、去年の日比谷野音ワンマンが土砂降り、今年の東武動物公園での主催フェスも雨と、今や若手ロックシーン随一の雨バンドとして認知されるようになったこのバンドだからこそと言えるような選曲。
そしてラストに鳴らされたのは、上坂がOrangeのギターアンプに自身のギターを擦り付けるようにしてノイジーなサウンドを発するとともに、スクリーンにはタイトル通りに黄色い光が投影された「Yellow」。その選曲は、自分たちの主催フェスの2つのステージを、このRED MARQUEEと、メインステージのGREEN STAGEをイメージして作ったと言っていたKOTORIならではの、このフェスで鳴らしたい曲で構成されたライブであることを示していた。横山の思いっきり感情を込めて歌う姿も、ギターを肩から下ろして床の上で鳴らす上坂、立ち上がってドラムを叩く細川、それを見守るように変わらずにベースを弾く佐藤。4人の姿はこれまでで最も頼もしく見えた。
それは今年の状況の中で野外会場で主催フェスを開催したりと、規模はまるっきり違うし、フジロックのようにたくさんの人に知られていないフェスであっても、そうした活動を積み重ねてきた姿を見てきたからこそ、それが僅かながらでもこの日に繋がっていると思える。
今年のスペシャ列伝ツアーでようやく初めてライブを見た時は、このバンドにこんなに救われるようになるなんて思ってなかった。でもこの日はリハで演奏していた曲の歌詞のように、ビールを飲むことも、全てを忘れることも出来なくても、ただただ素晴らしい世界だ、と思える世の中であって欲しいと思い続けているくらいに、今の自分はこのバンドの音楽や存在、こうして音を鳴らす姿に救われている。
リハ.素晴らしい世界
1.We Are The Future
2.羽
3.unity
4.Anywhere
5.トーキョーナイトダイブ
6.雨のあと
7.YELLOW
12:00〜 TENDOUJI [RED MARQUEE]
リハでNirvanaの「Smells Like Teen Spirit」を演奏していたりと、バンドの持つ陽性の雰囲気とキャラクターがフジロックに実によく似合う感じのある、TENDOUJI。2年前は苗場食堂のステージに出演していたが、今年はこのRED MARQUEEにジャンプアップ。
メンバーがステージに登場すると、「COCO」からそのキャラクターそのもののような、踊り出したくならざるを得ないロックサウンドがテントの中を満たしていく。スクリーンには常にメンバーの演奏する姿が映し出されているが、モリタナオヒコとアサノケンジという2人のボーカル&ギターの異なるタイプの声の絡み合いが、タイトル通りに燃え上がるような照明がメンバーを照らし、RED MARQUEEというステージによく似合う「FIREBALL」、ベーシストとしては珍しくステージ中央に立つヨシダタカマサ、その個性的なメンバーの音を支えるようにドラムを叩くオオイナオユキというメンバー全員によるコーラスが超絶キャッチーな「KILLING HEADS」とテンポ良く曲が続いていくが、パンクやサーフロック、グランジ、オルタナという激しさや楽しさというあらゆるロックの要素-それはきっとこのフジロックの存在から獲得したものである-を融合させたサウンドを鳴らす中、モリタが自身が好きなもの=音楽への感情を思いっきり乗せるように歌っていた「STEADY」の時の表情が実に印象的だった。
コロナ禍になる前は北浦和KYARAがなくなる直前のthe telephones主催イベントに出演した際の打ち上げで記憶がなくなるほどに泥酔していたという見た目通りに楽しいエピソードを持つアサノも、
「観客とか出演者に関わらず、ダセェことだけはすんな。この状況でルールを破るってクソダセェからな。
酒が飲めないとか、いつもとは違う状況のフジロックだけど、今日は音楽一本だけで楽しみましょう」
と真剣に今の状況だからこその楽しみ方を誰しもがするべきであるということを伝える。それが決して説教臭いものにはならないというのはこのバンドのメンバーの持つキャラクターによるものだろう。
この日は事前にスペシャルゲストが出演することが発表されていたが、予告通りにステージに招かれたのは、この後に自身もバンドでこのRED MARQUEEに出演する、THE BAWDIESのROYで、リリースされたばかりの最新アルバム「MONSTER」の1曲目に収録されている「CRAZY」のシャウトを聞かせてくれるのだが、現在のバンドのライブ時の衣装とは異なるスーツを着ながらも、実に自然にこのTENDOUJIの中に溶け合っているのは、ともにロックの楽しさを伝えるバンドであるとともに、この会場で聴くことによって、フジロックを愛するバンド同士であるからであるとも思う。去り際に山口百恵の引退時のように丁寧にマイクをステージ上に置いていくROYの仕草にはついつい笑ってしまう。
そこからはどちらかというとグランジやオルタナというようなサウンドの要素が強い曲が演奏されていくのだが、そうした曲を巨漢のアサノの歌声がより内省的に感じさせてくれるという見た目とのギャップも面白い。
なのでファニーな曲のボーカルを担う割合はモリタの方が多いのだが、そのモリタは
「バンドを初めて、こういう景色が見れたらいいなっていう景色が今目の前に広がっている」
と改めてこのステージに立てている感慨を口にすると、
「いろいろな思いがそれぞれにあると思うけど、昔から客として来てた時に、会場に着いた時のやっぱりここに来ないと1年始まらないよな、終わらないよなっていう感覚を今日みんなが久しぶりに味わったと思う。それは俺らもそう。このフェスのステージに立つのをずっと目標にしてきた。これから先、もっと大きいステージに立てるように頑張ります」
と、観客として来ていたからこそわかる参加者の気持ちを代弁し、「THE DAY」から「GROUPEEEE」という最高にハッピーになれるような曲を連発して、こういう状況での開催となったが故に少しというか、もしかしたら必要以上に気を張っていたかもしれない我々の心を軽くしてくれた。いつか、2021年にTENDOUJIをRED MARQUEEで見たということを自慢できるくらいの存在になって欲しい。すぐ近くの街の出身であるバンドであるだけに。
1.COCO
2.FIREBALL
3.KILLING HEADS
4.KIDS IN THE DARK
5.STEADY
6.HEART BEAT
7.CRAZY feat.ROY (THE BAWDIES)
8.D.T.A.
9.PEACE BOMB
10.HAPPY MAN
11.THE DAY
12.GROUPEEEE
12:50〜 yonige [GREEN STAGE]
2日目に出演するSIRUPが出演するにあたっての声明を発表していたが、この日の前日、つまりは開催直前にyonigeも声明を発表していた。「出演を辞退することも考えた」と。実際にyonigeは翌週に開催するはずだった、渋谷LINE CUBEでのコンセプチュアルなワンマンライブを早い段階で開催延期にしている。それだけ今ライブをやるということが自分たちにとって正しいことなのかどうかということの判断の決着がまだついていないのだと思うけれど、2人にそこまで考えさせてしまう、そうした声明を出さざるを得なくなってしまうこの状況が本当に憎くなってしまう。
今やアー写によっては一緒に映っているおなじみのサポートメンバーのホリエ(ドラム)と土器大洋(ギター)の2人とともに、髪が黒くなりかつスマートになったように見えるごっきん(ベース)と、上下白の服装こそ夜中にコンビニに行くようでもあるが、どこかより麗しくなったようにすら見える牛丸ありさ(ボーカル&ギター)の2人が登場すると、牛丸の囁くようなボーカルから淡々と始まり、途中からホリエのドラムの連打が激しくこの広大なGREEN STAGEに響き、会場の空気を飲み込んでいく「11月24日」からスタート。
yonigeにとって巨大なフェスのメインステージは初めての体験、つまりは過去最大のキャパでのライブとなるわけだが、エモーショナルなギターロックからの脱皮を図ったミニアルバム「HOUSE」以降、というよりも「ここじゃない場所」も含めて昨年リリースの「健全な社会」以降のモードという、求められているものやバンドのパブリックイメージに応えるというのではなく、自分たちの今やりたいことをこのステージでやるという、自分たちの気持ちに最も正直な向き合い方でこのステージに立っているということがよくわかる。
なのでジャキジャキとしたオルタナティブなギターサウンドの「2月の水槽」も決してアッパーなテンポのものではないし、それは牛丸が歌詞を飛ばしながらも数少ない初期の曲から演奏された「バッドエンド週末」もそうであるが、牛丸のボーカルが苦手な早い時間であるにもかかわらず、この大自然の環境の中に伸びやかに響き渡っていく姿を見ていると、ああ、この規模のステージに立っても違和感がないバンドになれたんだな、と思う。
基本的に牛丸もごっきんも喋ることなくひたすら曲を連発していくというスタイルは近年おなじみのものであるが、その姿はもしかしたら初めて見る人にはこの状況で出演することによる迷いが出ているようにも見えるかもしれない(配信もされていたし)けれど、むしろいつもワンマンを観に行っている身としてはそうした逡巡を振り解いた上でこのステージに立っているからこそ、こうしてここまで堂々たる歌唱や演奏を見せることができているのだと思う。それくらい、2019年までは朝イチや昼の時間に出演したフェスでは明らかに本調子ではないのが目に見えてわかるような感じだった。バンド名からしてyonigeだし、自分は某空港で飛行機の時間に間に合わずに放送で牛丸が呼び出しされた機会に遭遇している。
そんな、このステージに立てているということを高田馬場の小さなライブハウスで見ていた頃のことを思い出したりして勝手に感慨深くなっていると、ごっきんのベースがうねりまくり、牛丸のボーカルはサビでより一層伸びやかになる「往生際」から、この開催日の2日前に発売されたばかりの最新ミニアルバム「三千世界」から、土器がシンセを弾くことも含めて、ライブで聴くとファンキーさが際立って聞こえる「催眠療法」を皮切りに、その収録曲を連発していく。
「マサカリかついで」
という、まるで昔話を紡ぐかのようなフレーズで始まる、牛丸の歌詞の発想力の進化っぷり(ロッキンオンジャパンの連載が終わってしまったのは本当に惜しい)を感じさせる「わたしを見つけて」、インタールード的な「どこかのチャイム」がメンバー演奏としてではなく、あくまで曲と曲を繋ぐものとしてアルバムの収録曲順通りに流れてからの「子どもは見ている」、さらにはノイジーなギターサウンドがかつてこのGREEN STAGEに立ってきた海外のシューゲイザーバンドの姿を彷彿とさせる「27歳」と、まさかここまで「三千世界」の曲を早くもライブで聴けるとは、と思うくらいの連発っぷり。「アボカド」あたりのイメージで見に来た人からしたらバンドのイメージが一変するであろうくらいの初見殺しっぷりであるが。
なので初期の「サイケデリックイエスタデイ」も牛丸がアコギに持ち替えるというオーガニックなアレンジで演奏されることによって、初期曲も今の曲と統一した雰囲気で演奏されていたし、「ピオニー」はまだしも「トラック」までも演奏されたというのはある意味では「リボルバー」すらやらなくなった今のバンドのモードを示していると言える。
延期になったワンマンも「MCをしないで映像との融合」というコンセプトがアナウンスされていただけに、こうした内容のライブになる予定だったのかもしれない。
60分という持ち時間はかなり長めであるが、MCを挟まずに曲を連発してきただけに、かなりの曲数となっている。そんな中で牛丸がついに口を開く。
「出演するかどうか本当に悩んだし、色々な考えがあるだろうけど、yonige初のGREEN STAGEをこうして見届けてくれて本当にありがとうございます。
みんな、自分の体調を1番大切にしてください。少しでも体調が悪いと思ったら自分で判断して」
という言葉からは、デビュー当時は責任という単語からは程遠いイメージがあった牛丸が、自分たち以外の人のことに気を遣える、そうした人のことを考えられる大人になったということを感じさせた。それは去年バンドでのライブが次々に中止や延期になり、1人で弾き語りをしたり、何度も延期になっても払い戻しをせずにライブに来てくれたファンの姿を見て至った心境なのかもしれない。
そんな牛丸の変化を音楽面でも示すのが、MVも公開された「三千世界」のリード曲「対岸の彼女」。すでにリリース前からライブでも何回も演奏されている曲であるが、どれだけ先鋭的な方向に舵を切ってもyonigeの持つメロディの良さは失われることはないということを示す曲である。
そして最後に演奏されたのは真昼間、しかもアルコールを飲むことができない環境下で、音だけでこれ以上ないくらいに酩酊感を与えてくれる轟音サウンドによる「最愛の恋人たち」。この曲も含めて今のyonigeのサウンドのスタンスはきっとどのフェスよりもこのフジロックの観客や環境に似合っているんじゃないかとも思えたが、14曲やっても10分近く時間は巻いていた。まるでパンクバンドかのようなテンポのライブだった。
yonigeは最終的にこうして出演することを選んだけれど、出演者の中には検査で陽性になって出れなくなったアーティストや、自ら出演辞退したアーティストもいる。それぞれがそれぞれの考えや信念に基づいた判断をしている。それは観客側もそうだし、そのどの判断も尊重されるべきものだ。
でも辞退することも考え、それについての声明を発表したyonigeを、こうしてフジロックのメインステージで見ることができたのは自分にとっては本当に嬉しいことだった。本人たちには感慨みたいなものはなかったかもしれないが、自分はこのライブを見ていて、ずっとこのバンドを見てきて、その果てにこのライブが見れて本当に良かったなと思った。ステージに立って演奏することで、そうして救われる気持ちになる、これまでの人生や経験を肯定できる人がいるというのもまた一つの事実だ。延期になってしまったワンマンも、近いうちに必ず見れますように。どれだけ延期してもいつか必ずやるということをこの1年で証明してくれたバンドなだけに。
1.11月24日
2.ここじゃない場所
3.2月の水槽
4.バッドエンド週末
5.往生際
6.催眠療法
7.わたしを見つけて
8.子どもは見ている
9.27歳
10.サイケデリックイエスタデイ
11.ピオニー
12.トラック
13.対岸の彼女
14.最愛の恋人たち
14:50〜 くるり [GREEN STAGE]
GREEN STAGEの転換中にはスマイリー原島(声がだいぶ変わった感じがする)によるMCもあり、このタイミングではこのGREEN STAGEの MCを一緒にやっていた方や、フジロックの機材チームの方が2年前の開催以降に亡くなったということがSMASH代表の日高氏とともに語られるのだが、こうしてこのステージを間近で見ていると、これを設営、バラしたりするのにどれくらいの人員と時間と金銭がかかるのだろうかと思ってしまう。直前で中止になってしまったら、誰にも使われることなくバラさなければならなくなるということも。
黎明期のフジロックに観客として来ていたということが今も語種であるくるりは日本のアーティストとしてはこのフェスおなじみの存在でもある。岸田繁(ボーカル&ギター)、佐藤征史(ベース)に加えて、松本大樹(ギター)、石若駿(ドラム)、野崎泰弘(キーボード)という近年のライブではおなじみのメンバーによる5人体制である。
5人がステージに登場すると、岸田の声かけからそれぞれの重い音が重なる「HOW TO GO」からスタートし、さらに「花の水鉄砲」と「アンテナ」期のロックなくるりサウンドによる立ち上がり。くるりのライブ自体は今年にZepp Hanedaでのツアーにも行って見ているけれども、それでもこのステージでのライブを見ているというのはどこか夢見心地になるし、
「いつかは想像を超える日が待っているのだろう」
という「HOW TO GO」のフレーズからは、今の状況だからこその微かな希望を感じることができる。いつかはこの日、このライブを超える日が我々に待っているのだろうか。
今や岸田と佐藤の2人以外ではバンド最古参となった松本のハードロックなギターから始まり、石若がスネアに財布を乗せてミュートしているのがスクリーンに映し出されるのが実にシュールな、もはやプログレとすら言える目まぐるしい展開を高い演奏技術で乗りこなしていく「Tokyo OP」で一気にロックからくるりの持つ変態性と言える部分を感じさせてくれる展開になるのだが、その後に至極の名曲「琥珀色の街、上海蟹の朝」が演奏されるのだから選曲も、それを聴いている我々の感情も起伏が実に激しい。
今やくるりの代表曲の一つと言える曲でもあるのだが、この自然の中、山の中という、Beautiful cityでもなければ上海でもない会場でこの曲が演奏されることのなんと似合うことだろうか。それは気持ちよさそうに体を揺らす観客の姿、このフェスで数々の名場面を作ってきたであろうくるりへのリスペクトを感じさせる姿も含めて。
野崎の美しいピアノに導かれて始まる「ばらの花」はサビで岸田が1人で歌う、コーラスがないという形にファンファンはもうこのバンドにいないんだな…とも思ってしまうけれど、
「ララララ…」
という曲終盤のコーラスはハイの佐藤とロー野崎という新たなアレンジで発せられ、それが今のくるりによるこの曲の形なんだと思わせてくれる。僕らは安心というわけではないけれど、思い切り泣いたり笑ったりしたい。それは音楽があるからこそできることだ。
そんなくるりの、日本ロックシーンの名曲に続いて演奏されたのは、ツアーでも演奏されていた新曲。
「クマゼミとアブラゼミ」
などの日本の都会ではなく田舎と言われるような地域の夏の光景を歌うこの曲もまた、この会場に本当によく似合っている。これから先、何回もこのステージで演奏されることになるのかもしれない。いや、そうであって欲しい。そうなるということはこのフェスが続いているということだから。
かつて映画の主題歌としてリリースされ、昨年ファンファン在籍時に3人でリモートで演奏されたのが動画で公開されていた「キャメル」もまたそれを経てこの5人バージョンとして演奏されると、岸田のアコギの音が森の中に溶け合っていく「ハイウェイ」へ。我々は今は声を出すことはできないが、コーラスのフレーズを会場にいた誰もが心の中で歌っていたのだと思うし、こうした穏やかなタイプの曲であっても腕を上げてバンドの演奏に応える観客の姿を見ていると、やはりくるりとこのフェスの相性は抜群だと思う。
そんなくるりの今年リリースした最新アルバム「天才の愛」収録曲の中でもトップクラスに美しいメロディによる「潮風のアリア」が、ほんの少しだけ雨が降ってくるという、ひたすらに暑かったこの日に文字通り涼しい風を吹かせてくれると、長い髪が汗で濡れた岸田がバンドメンバーを紹介する。
ワンマンでは大谷翔平(佐藤も大ファンになっている)の話など、野球好きとして止まらないトークをしていた岸田は、このメンバー紹介しか喋ることはなかった。でもそれでいいと思うくらい、こうしてこの会場でくるりのライブを見ているということが幸せなことであるとすら思ってしまった。そう思ってはいけない状況なのかもしれないけれど、最後に演奏された「奇跡」の
「いつまでも そのままで 泣いたり 笑ったりできるように
曇りがちな その空を 一面晴れ間に できるように」
「退屈な毎日も 当然のように過ぎてゆく
気づかないような隙間に咲いた花 来年も会いましょう」
という歌詞と、その曲を鳴らす芳醇なバンドの演奏は、やはり幸せであるとしか思えない瞬間だった。来年もここで会えたら、と思えるくらいに。
リハ.pray
1. HOW TO GO
2.花の水鉄砲
3.Tokyo OP
4.琥珀色の街、上海蟹の朝
5.ばらの花
6.新曲
7.キャメル
8.ハイウェイ
9.潮風のアリア
10.奇跡
15:50〜 THE BAWDIES [RED MARQUEE]
すでにROY(ボーカル&ベース)がTENDOUJIのライブにゲストボーカルとして出演している、THE BAWDIES。メンバーも愛するこのフェスに実に5年ぶりの帰還となる。
「ダンス天国」のSEで、新しくなった上が黒、下が黄色というスーツ姿でメンバーが登場すると、
「みなさん、5年ぶりにRED MARQUEEに戻ってまいりました!」
とROYが叫んで、その日に戻ろうかというような「LET’S GO BACK」からスタート。軽やかに舞うようにギターを弾くJIMの姿からはこのステージに立てていることの喜びをこれ以上ないくらいに感じさせてくれるが、金髪になったTAXMAN(ギター)を含めたコーラス部分を一緒に歌うことができなくても、バンドが演奏している姿を見ているだけで本当に楽しい。テント型のステージであるだけに、爆音のロックンロールが壁に反響しているのがわかる。
「遅れないでくださいね!遅れたらこうなりますよ!」
と言ったROYが最後に超ロングシャウトをかます「IT’S TOO LATE」で観客が飛び跳ねまくり、腕を振るのだが、このROYのシャウトには声を上げて讃えたくなりそうなものであるが、それをしないでみんなが楽しんでいる。楽しむためのロックンロールでありながら、守るためのロックンロールでもある。
そのまま一人一人が打ち上げ花火のように飛び跳ねまくる「YOU GOTTA DANCE」、リリースされている曲としては最新曲となる、思わずコーラスを口ずさみたくなる「OH NO!」、雨が降りやすいフジロックの会場に合わせたであろう爽やかなTAXMANボーカル曲「RAINY DAY」と新旧の名曲たちを連発していき、自分たちがWHITE STAGE、GREEN STAGEにも立ってきたこのフジロックにこうして戻ってくることができたことへの感謝を口にするのだが、TAXMANによると高校3年生の時にメンバーで客としてこのフェスに来てからちょうど20年ということ。間違いなくTHE BAWDIESというバンドの歴史にはこのフェスの存在が欠かせないというか、このフェスがなかったらTHE BAWDIESはなかったかもしれないというくらいのものだ。高校生の頃のメンバーはここでどんなアーティストのライブを見て、どんなことを話したり、共有しあったりしていたんだろうか。そんな光景を想像したりもしてしまう。
そんな想像をより鮮明に浮かび上がらせるのは「LEMONADE」というミドルテンポの名曲が演奏されたからであるが、そこからさらにフェスではメドレー的に演奏されることも多い「KEEP YOU HAPPY」をフルで演奏して観客を踊らせてくれるが、これは持ち時間が長いフジロックならではと言えるだろう。
そして来月リリースを控えるニューアルバムから、すでにMVが公開されている「T.Y.I.A.」をライブ初披露。タイトルフレーズのコーラスが実にキャッチーでありながらもロックンロールでしかないというこの曲は、バンドの最高傑作と名高い前作「Section #11」を超えるアルバムになるんじゃないかという期待が膨らむ曲だ。
そんな中でROYの
「「HOT DOG」という曲の準備に入ります」
という言葉から、スターウォーズバージョン(このバージョン、もう10回くらい見ている気がする)の劇場を披露して、棒読みのMARCYのC3POも、めちゃくちゃ上手いJIMのヨーダのモノマネもかなりウケていたのだが、配信もあるし、こういう状況下だし、もしかしたらこのくだりは今日はやらないんじゃないかとも思っていた。でもこうしてやったということ、劇場も含めていつもと何一つ変わることがないライブをやったということは、これから先どんな状況、どんな状態でのライブであろうと、THE BAWDIESはこれまでと全く変わらずに我々の心も体も元気にしてくれる、笑わせてくれるということだ。
もちろんそこにはこの状況になってからも昨年の中野サンプラザワンマンを皮切りに、止まらないロックンロールバンドとしてライブをやり続けてきたバンドだからこその強さを感じられるバンドの演奏があってこそで、アルバムのツアーが完走出来なかった中でもそうして鍛え上げられた「SKIPPIN’ STONES」がラスサビの一気にパンクに加速する部分も含めて完全にライブアンセムの一つとなり、リリースされる前からずっとそのライブアンセムという位置を担ってきた「JUST BE COOL」でさらに飛び跳ねさせまくると、それでもまだ終わらず、
「KEEP ON FUJI ROCKですよ!」
と言って最後に演奏されたのは「KEEP ON ROCKIN’」。コール&レスポンスはご時世としてバンドのコールに手拍子を観客が返すという形に変わっているが、自分たちの愛するフジロックが自分たちの意思と同じように、止まることなく転がり続けることを選んだということがメンバーたちは凄く嬉しかっただろうし、出演者としてそのフェスの意思を肯定したいという気持ちもあったのだろう。それだけに、ロックンロールし続けるというこの曲がこの日の最後に演奏されたというのは必然でしかなかった。
演奏が終わると、最近はフェスではトリ以外ではあまりやらないことも多いTAXMANの「わっしょい」も、フジロックに幸あれバージョンとして行われた。そこからも、メンバーのフジロックに対する愛が溢れていた。GREEN STAGEやWHITE STAGEに出た時のライブも見てみたかったと思うくらいに。
こうした状況であるが故に、果たして心から楽しんでいいんだろうか?という葛藤もある。全部忘れて、というのもなかなか難しい状況だからだ。それでもTHE BAWDIESのライブはやっぱり楽しい。世の中や社会や自分自身がどんな状況であってもそう感じさせてくれるし、その楽しいという感情をまた味わいたくて、これからもライブを見れるようでありたいと思う。
そのためには健康でいないといけないし、生きていないといけない。だからこそ感染しないように注意を払う。そんな風に思わせてくれるバンドがいてくれる、ライブをやってくれているということが本当に嬉しく思えた。
「みんなから深く愛されてきたからこその魔法があるフェス」
とROYはフジロックのことを評していたが、それはフェスの部分をバンドに変えたのがTHE BAWDIESというバンドである。限られたバンドにしかないロックンロールの魔法が、今もこのバンドにはある。
1.LET’S GO BACK
2.IT’S TOO LATE
3.YOU GOTTA DANCE
4.OH NO!
5.RAINY DAY
6.LEMONADE
7.KEEP YOU HAPPY
8.T.Y.I.A.
9.HOT DOG
10.SKIPPIN’ STONES
11.JUST BE COOL
12.KEEP ON ROCKIN’
16:50〜 SiM [GREEN STAGE]
6月末には主催フェスのDEAD POP FESTiVALを無事に開催、成功させた(この成功させたの意味が本当に大事)SiMがこのフジロックにも出演。あのフェスでトリとして圧巻のライブを見せてくれたバンドなだけに、このまだ陽が落ちる前の時間に見れるということ、フジロックのメインステージで見れるということが少し不思議な感じがする。
メンバーがステージに登場すると、ここまではこのバンドのようにラウドかつ激しいサウンドやノリのバンドがいないために、そうした浸るように、体を揺らすようにライブを見ていた体を目覚めさせるかのような「Get Up, Get Up」からスタートし、いつもより目元のメイクが濃い感じもするMAH(ボーカル)をはじめとしたメンバーも、観客も飛び跳ねまくるのだが、ステージ前から火柱が上がりまくるというあたりはさすがフジロックのメインステージでのライブである。
しかしながら「CAPTAiN HOOK」を演奏した後にMAHは、
「ちょっと待って。あの火はなんなの?MAN WITH A MISSIONやRADWIMPSが使うような。(スタッフに確認して)え?俺たちが発注して入れたやつなの?」
と、その火柱に驚いていたのだが、続く「Blah Blah Blah」でも火柱が上がる。しかしながらDPFの時のように煽るような、でもそれに耐えさせようとするようなMCをしなかったというのは少なからずこのフェスがバンドにとって100%ホームではない、自分たちのライブを初めて見る、自分たちの曲を初めて聞くという人がたくさんいるということをわかっているのだろう。
SHOW-HATEがシンセを操作し、座って見ていた人も立ち上がってモンキーダンスをすることを促す「GUNSHOTS」で自分たちのライブにおける光景やノリを示すと、
「こういう感じで、俺たちのライブは普段ならモッシュとかが起こるような激しい感じだし、フジロックはお酒飲んで音に任せて楽しむっていうフェスだと思うんだけど、今は来年以降のフジロックや、他の全ての日本のロックフェスを守るために、それは我慢して楽しんでくれ!」
というこの状況下だからこその言葉は、さすがに自分たちが野外フェスを主催するバンドとしての責任感を感じさせるものだった。この日はSiMのTシャツやDPFのTシャツを着た観客もたくさん来ていたけれど、その人たちはみんなこのバンドの意思をしっかりと共有している。だからこそ声を出したり、モッシュしたりせずにルールを守っているのだし、DPFを含めたいろんなライブでバンドがそうしてフェスを守ろうとしてきた姿を見てきたからであろう。
そんな中で
「フジロックのこのステージに似合うと思う曲」
と言って演奏された、昨年リリースの神盤こと「THANKS GOD, THERE ARE HUNDREDS OF WAYS TO KiLL ENEMiES」収録の「Smoke in the Sky」、さらにはレゲエパンクバンドであるSiMのレゲエの要素を感じさせる「The Sound Of Breath」という、DPFや主催ライブでは必ず演奏するバラードタイプの曲を2曲続けることができるのも持ち時間が60分という長いものであるこのフェスならではだろう。とりわけ「Sound Of Breath」では日本語の歌詞がスクリーンに映し出され、それはまるで今この状況の我々に向けて放たれているかのようなメッセージだ。
するとMAHがバットを持ってきて、
「この爽やかな曲をラジオ局の人から「高校野球のテーマソングに使いたい」と言われたんだけど、歌詞が「このバットでお前を殴りたい」っていうものですって言ったらその話は流れました!」
と言って観客を笑わせながら、西海岸パンクのようなメジャーコードの、まさに爽やかな「BASEBALL BAT」でMAHがバットを振り上げて観客を煽り、ドラムセットに取り付けられたカメラにコーラスする姿がアップで映し出されるGODRiを含めた3人の「KILL YOU」というコーラスすらも爽やかに響く。
「この曲をみんなで歌いたかった」
という言葉にはこの形式のライブに満足していないけれど、それでも今はこの形でやるしかないというMAHの思いが「Devil in Your Heart」のラウドなサウンドから滲み、
「今日配信もあるんで、SiMも是非配信させてくださいって主催者とかに言われたんだけど、でもこの場所の空気とか草の匂いとか、そういうものを共有できる目の前にいる人だけに今日のライブは見てもらいたいと思った」
と、自分たちのライブを配信しなかった理由を口にしながら、
「俺たちの中で1番有名な次の曲を2文字で説明します!死ねー!」
と「KiLLiNG ME」ではSiNがツーステを踏みながらベースを弾き、観客をその場にしゃがませてから(距離を取っているからすぐに全員しゃがめる)ジャンプさせ、フジロックのGREEN STAGEでも堂々たるSiMのライブを見せつけるのだが、演奏が終わると何やら4人がGODRiのドラムセットに集まって会議を始める。
「時間がめちゃくちゃ余ってる(笑)」
ということでどうするかを話し合っていたようであるが、そんな時間を埋めるようにMAHは話し始める。
「「SiMがフジロックって草www」みたいに言う連中もいるんだけど、もう出るの3回目なんですよ。ちゃんと隅々までチェックしてないからわからないんですね、そこまで出てるって。
最初に出た時はROOKIE A GO GO!で、苗場プリンスホテルを用意してもらえるわけもなく、なんとか頼み込んだらキャンプサイトのチケットを1枚だけくれて、4人でキャンプしたんだけど、テント張れる場所が斜面しかなくて、寝てると落ちていくみたいな感じになってた(笑)
そんな憧れのフジのGREEN STAGE。でも思ってたのと違う。やっぱり海外アーティストもたくさんいて、客席も満員でみんながビール飲んだりモッシュして。それができる時にまたこのステージに出たい。その時にもSiMがこのステージにふさわしい存在だって主催に思わせるために今日は来た!」
と、今までのフジロックのど真ん中に自分たちのロックを鳴らしたいという、今なお燃え上がるバンドの野心を語ると、観客にリクエストを聞こうとして結局聞かないという形で急遽追加された「Amy」でSiNとともに観客も間隔が空いていることでツーステを踊りまくり、ラストはコロナ禍になってからおなじみの、前髪を両サイドに分けてグシャグシャにすることによってウォールオブデスを再現するという「f.a.i.t.h」。それはSiMのメンバーの持つ面白い人間性を感じさせるとともに、この状況の中で自分たちのやり方で戦いながらも前に進もうとしているSiMの姿だった。本物のウォールオブデスが発生するのを見れないのはやっぱり寂しいし、物足りないけど、それでもこうしてSiMのライブを見れるのは、全くライブがないよりはいいよな、と思っていた。
DEAD POP FESTiVALでのSiMのライブでのMAHのMCは忘れられない。
「世の中にはライブやフェスなんか明日にでもなくなってもいい人がたくさんいる。でも俺はどうだ?お前はどうだ?俺はライブやフェスが、音楽があったからこのクソみたいな国でこれまで生き抜いてこれた」
その言葉が、あのフェスを成功させたということが、夏に繋がると思っていた。ロッキンもラブシャもその他のフェスも、今年はいろんなところへ行けると思っていた。それがことごとくなくなってしまったからこそ、無力感や絶望感を感じてもしまうけれど、このフジロックのSiMのライブがこの上なく愛おしいものに感じられた。来年以降、また今までみたいなフジロックのGREEN STAGEにSiMが立つ姿が見れたらいいな。
1.Get Up, Get Up
2.CAPTAiN HOOK
3.Blah, Blah, Blah
4.GUNSHOTS
5.Smoke in the Sky
6.The Sound Of Breath
7.BASEBALL BAT
8.Devil in Your Heart
9.KiLLiNG ME
10.Amy
11.f.a.i.t.h
18:50〜 MAN WITH A MISSION [GREEN STAGE]
タイテ的なものもあるけれど、ライブとライブの合間にいつも以上にフェス飯を食べた。フジロックに来ないと食べれなそうな店舗がたくさんあって、それを味わってみたかったし、もしかしたらフェス飯を食べれるのは今年はこれが最後かもしれないとも思っていたから。
他のフェスよりもはるかに多い飲食ブースの数ということは、そこで働く人の仕事がたくさんあって、消費される、参加者の空腹を満たしてくれて、音楽以外の部分で笑顔にしてくれる食材がたくさんあるということ。もし直前で中止になっていたら、それらの人の仕事や食材はどうなっていたんだろうか。
そんな中でGREEN STAGEにはまるでこのバンドのワンマンが始まるかのような、巨大なセットが組み上げられている。それはきっとこの MAN WITH A MISSIONが去年開催するはずだった主催ライブで使用する予定だったものだろう。1年越しでついにそのセットも日の目を見る時が来たのである。
5人に加えて、サポートのE.D.ヴェダーも加えたおなじみのメンバーたちがステージに登場すると、たくさんの人が狼のように両腕を高く掲げながら待ち構える中で最初に演奏されたのは、まるでこのGREEN STAGEのために作られたかのような「evergreen」。このオープニングからもバンドのこのステージに対する想いが伝わってくるが、ジャン・ケン・ジョニー(ボーカル&ギター)はどこか声が詰まり気味だったのは、喉の調子が悪かったのではなくて、感極まっていたからなんじゃないだろうか。表情は全く変わることはないけれど。
観客はどんなアンセム(それはマンウィズのアンセム=日本のロックシーンのアンセム)が演奏されても歓声を上げることはできないが、「Raise your flag」の勇壮なコーラスによるイントロが始まると腕を高く掲げ、さらには1コーラス終わると間奏部分で大きな拍手が起こる。それは初めから全身全霊を尽くして演奏するバンドへの感謝、この曲を演奏してくれたことによる感謝を示すものである。その光景に思わず胸が熱くなる。
どこかこの広大なフェスの会場を想起させるような歌詞が並ぶ「higher」という選曲にはやはりこの会場で主催ライブをやろうとしていたバンドが練り上げてきたセトリであるということを感じさせてくれるが、そんな中でもリリースされたばかりの、まさに深い場所へ潜っていくかのようなデジタルサウンドによる「INTO THE DEEP」は山の中にいるのにまるで海の底に沈んでいくような感覚に陥らせてくれる。
「この時間のライブで実にありがたい(笑)」
という言葉にはあらゆる意味が含まれていそうで思わず笑ってしまうけれど、トーキョー・タナカのボーカルにも文字通り感情が思いっきり込められた「Emotions」ではカミカゼ・ボーイもステージ中央まで歩み出てきてベースを弾く。間奏ではスペア・リブの叩き出すビートに合わせてDJサンタモニカも煽るように腕を振る。5人全員の力を最大限に結集して臨んでいる、それはいつもそうであるが、この日はなおさらその気持ちが強かったであろうことがわかる。
するとここでジャン・ケンがゲストに招いたのは翌日に出演予定のmilet。なのでまぁ薄々この「Reiwa」のコラボはやるだろうとは思っていたが、それでもやはりこうして広大なステージでmiletの美しく透き通った、まるでこの会場の空気のような歌声を聴いていると心が洗われるような感覚になる。しかし、この曲がリリースされた時(2019年に「Dark Crow」のカップリング)には令和という時代がこんなにも最悪かつ残酷なものになるなんて全く思っていなかった。だからこそ祈りや願いを込めるかのようであったが、余韻を残さないようにか、miletはアウトロ演奏中にステージから去って行った。
そうしたこのバンドの持つ歌心やメロディの部分にフォーカスを当てたコラボの後は、曲と曲を繋げるようにして「Hey Now」、10-FEETのTAKUMAが登場しないことでジャン・ケンとタナカだけで歌うバージョンの「database」、さらにはDJサンタモニカがステージ前まで出てきて腕を上下させる「Get Off of My Way」ではジャン・ケンがおなじみの、
「人間の皆様、かかってきなさい!」
という煽りを入れることによって、まるで狼主催のロックなダンスパーティーであるかのように観客も踊りまくる。もはや全てがアンセムの連打に次ぐ連打である。
するとスペア・リブがドラムを叩き続け、そこにサンタモニカがスクラッチなどを重ねまくるという2人によるセッションが展開され、その間に他のメンバーはステージから去ってしまう。2人の演奏がフィーチャーされるというのはフェスではほとんど見れないだけにありがたいのだが、演奏が終わると2人がステージ前に出てきて手を繋ぐのかと思ったらやっぱり繋がないという、狼の可愛らしい部分を存分にアピールして2人もステージから去って行くので、客席には盛大な「?」マークが浮かぶのだが、そこにジャン・ケンとE.D.ヴェダーの2人がステージへ戻ってくると、
「もう1人スペシャルゲスト、BIGMAMAから真緒ちゃん!」
と、BIGMAMAの東出真緒を招き、ジャン・ケンの弾き語りに東出のヴァイオリンとヴェダーのギターを重ねるというアレンジで「フォーカスライト」を歌う。
ラウドなロックだけでなく、こうしたアコースティックな、メロディを最大限に引き出すようなアレンジも施すことができるというあたりに改めてジャン・ケンの異才っぷりを感じさせるが、その温もりを感じるアレンジも含め、
「『もうここにいる場合じゃない』なんて 無理に涙のむより
泣きじゃくりながらも走る方が 生きて行ける気がするんだ」
「取るに足らぬ幸せを見つけちゃはしゃいでいた
君が残した足跡 誰にも消させないから
世界の終わりがすぐそこに来たとしても
あなたがくれた魔法を 僕らは忘れないから」
というこの曲の歌詞が、まさに今このフジロックにいる我々のために歌われているかのように思わせてくれる。そこに花を添えた東出は初めてこの会場に来たという。BIGMAMAはどちらかというとサマソニのイメージが強いだけにフジロックに出たことがないから。いつか、RED MARQUEEあたりにBIGMAMAが出演してくれたらいいのにな、と東出の話を聞いて思っていた。
するとここでジャン・ケンはこのライブをするにあたっての抱えていた思いを語る。
「いろんな意見や考えがありますが、我々は何も分断や対立を煽りたくてフェスを、ライブをやっているわけじゃない。ただ、今回「行かない」っていう選択をした人たちに、「このやり方でフェスがやれたよ、ライブができたよ」っていうことを、こうして来てくれた人たちと一緒に分かち合いたいだけ」
という言葉には、アラバキが中止になった直後の配信も含めて、災害などが起こった際に真っ先に駆けつけたり支援をしたりするという活動をしてきたマンウィズの優しさが滲み出ていたとともに、こうして会場に来ていた身としても本当にその通りなんだよと思いながら聞いていた。
きっとこのフェス自体はもちろん、こうして出演したことによって、心ない声がバンド自体にも飛んでくるかもしれない。でもそうした人すらも災害にあったりした時にはきっとこのバンドは嫌な顔一つせずに助けに行くはずだ。究極の生命体はそのビジュアルや体力だけでなく、精神が最も究極形であり、我々凡人の人間をはるかに凌駕している部分である。
そんなMCの後にはマンウィズのバラードとしての美メロの極地である「Remember Me」が演奏されるものだから、涙を堪えられなかった。
「覚えていてくれ」「忘れないでくれ」と歌うこの曲を聴きながら、忘れようがない。この2021年のフジロックの初日にマンウィズのライブを見たということは絶対に忘れることはないと思っていた。
そしてカミカゼとサンタモニカの目が発光するという、野外では夜だからこそのギミックも全開になる中で披露された最新曲「Merry-Go-R ound」は紛れもなくこのコロナ禍を生きる我々を思って書かれた曲だろう。だからこそ、
「Merry-Go-Round
Revolving around
きっと未来で僕は
戦って打ち克って
笑顔で泣いてる
いつだって 今だって
立ち上がりあなたの様に守りたい
And now it’s our round」
と歌われる。打ち克った後に、また「FLY AGAIN」をみんなで大合唱したい。できればなくなってしまったこのバンドの主催ライブの場で。そんなことを考えながら聴いていた「FLY AGAIN」は今までで見て来た中で1番感動的だった。
最後にはカミカゼがステージに寝転がるようにして演奏するくらいに出し尽くしていたのだが、それでも最後には声が出せなくても観客と「1,2,3 ダー!」という無音のやり取りでこのライブの喜びを分かち合う。なぜこのバンドが究極の生命体であり、この会場で主催ライブができるような巨大な存在になったのか。その理由が全て凝縮されていたかのようなライブだった。
この日、おそらくはこのバンドのライブを見るためにこのフェスに来たであろう、今までフジロックには来たことがなさそうな10代と思しき若い人も結構来ていた。その人たちがこの状況でこのフェスに来たことを後悔するような結果にだけはならないように。願わくば、来年以降に「あの時フジロックにマンウィズを観に行って本当に良かった」と思える人生であるように。ライブが終わった後のその人たちの笑顔を見ていたら、そんなことを思っていた。
1.evergreen
2.Raise your flag
3.higher
4.INTO THE DEEP
5.Emotions
6.Reiwa feat.milet
7.Hey Now
8.database
9.Get Off of My Way
10.フォーカスライト feat.東出真緒 (BIGMAMA) ジャン・ケン弾き語り
11.Remember Me
12.Merry-Go-Round
13.FLY AGAIN
21:00〜 RADWIMPS [GREEN STAGE]
毎年必ずと言っていいくらいに雨が降ると言われるフジロックも、この日はくるりの時に気にならないレベルでしか雨は降らなかった。それは時期が例年よりも1ヶ月遅いというのもあるかもしれないけれど、「天気の子」の音楽を担当したこのバンドがこの日のトリだからだったんじゃないだろうか。RADWIMPSが今年のフジロック初日のトリである。
サポートとしてバンドを支えてくれていた畑利樹が東京事変の活動に専念するためにバンドを離れたことによって、森瑞希に加えてエノマサフミという若い2人によるツインドラム編成でメンバーがステージに登場すると、2人のビートの上に野田洋次郎のピアノとボーカルが重なっていく、確実にこの時期、夏の野外フェスくらいでしか演奏される機会はそうないであろう「夏のせい」でスタートする。
「夏のせいにして 僕らどこへ行こう
恋のせいにして どこまででも行こう」
というフレーズが、必ずしも夏のせいというだけではないけれども、夏フェスがこうして開催されたからこそ我々はこうしてここに来て、RADWIMPSのライブを観れているということを実感させてくれるオープニングである。
洋次郎がピアノからギターに変わると、武田祐介(ベース)がシンセを弾くという形で、リリースされたばかりのデジタルロック曲「TWILIGHT」が演奏されるのだが、その瞬間のステージから放たれるミラーボールなどの光のなんと鮮やかなこと。それはまるでRADWIMPSが放つ強大な光、生のエネルギーそのものであり、フジロックに携わるスタッフのとてつもない本気度も感じさせるものだ。
そうした近年のRADWIMPSのサウンドの振れ幅の広さをたった2曲だけで示すような立ち上がりから、たくさんの人をイントロの段階で歓喜させた「前前前世」へ。近年はワンマンでも演奏されないことも多い(去年の横浜アリーナでは演奏されていない)のだが、こうしてこの曲を演奏するというあたりにバンド側のフェスに出る意義を感じるけれど、あくまでこの曲がクライマックスになるような構成にはしないというところにはバンド側の矜持を感じる。
桑原彰(ギター)がシンセで煌びやかなフレーズを奏でる「NEVER EVER ENDER」ではスクリーンに歌詞も映し出され、それが「カタルシスト」になると曲のイメージを増強する映像へと切り替わる。スポーツ選手を鼓舞するための曲というイメージだった「カタルシスト」にこんなにも今自分が励まされることになるとは全く思っていなかったが、そこにはこの序盤の段階で洋次郎だけでなく、武田も桑原もこうしてここでライブが出来ている喜びを語るところからも発せられるエネルギーによるものだろう。
洋次郎がピアノに座って切ないメロディを奏でたのは「君の名は。」からの「三葉のテーマ」であるが、この曲から繋がるのはその「君の名は。」の中でも重要な役割を担った「スパークル」。スクリーンには星空を思わせるような映像が流れ、まるで苗場から映画の舞台の飛騨高山にワープしたかのようですらある。かつてロッキンのトリで演奏した時のこの曲も素晴らしかったが、やはり夜の野外というシチュエーションで聴くこの曲の素晴らしさはもはや筆舌に尽くし難いレベルというか、一生、いや、何生でも経験したい光景である。
しかしその感動的な「スパークル」で歌詞が飛び気味、間違え気味だったのは、ピアノを弾く洋次郎の顔に蛾が直撃したり、指に虫が乗ったりしたからだということであるが、それを
「虫たちは普段からここに住んでるから、むしろ俺たちがお邪魔している」
というあたりは実に洋次郎らしい。
するとここでこの日予告されていたスペシャルゲストとして、ステージには菅田将暉が人生初の野外フェス出演を果たすべく登場。イメージよりもかなり髪が長くなっている感じがしたが(リアルで見たのは米津玄師の武道館にゲストで登場して以来だが)、その菅田将暉と洋次郎が向き合うように歌いはじめたのはリリースされたばかりの「うたかた歌」。
タイトル通りの儚さを感じるような歌詞が、洋次郎と菅田将暉の声のコントラストによってより一層この瞬間そのものを儚く感じさせる。このコラボはミュージックステーションでも放送されたらしいが、テレビ中継があるとは思えないくらいにライブのテンポが悪くなることなく演奏されたので、実際の放送がどんな感じだったのか、現地にいる側が逆に気になるくらいだ。
コラボを終えた菅田将暉がステージから去ると、スクリーンには何故だかカエルなどの映像が映し出された「おしゃかしゃま」で、間奏ではおなじみの武田&森チーム、桑原&エノチームに分けた、洋次郎が指揮者のように音量と演奏を操るセッションが行われ、それぞれの演奏技術の高さを改めて証明してくれるのだが、桑原は去年までよりも明らかに痩せたように見えるな…とも思いながら、セッションを加えたことによって10分以上に及ぶ長尺的な曲に変化していた。フェスで演奏されてきた中でも歴代最長レベルなんじゃないだろうかというくらいに。
そんな演奏の後にはセンセーショナル過ぎて配信して大丈夫なのかとすら思ってしまう歌詞の「洗脳」までもがこのフェスで演奏される。その際のメンバーの姿をハッキリとは映さない薄暗い照明が、まるでビリー・アイリッシュがこのステージに立ったらこういう景色が観れるんじゃないかとすら感じるものになっている。
すると洋次郎は、このステージをありとあらゆるプロフェッショナルたちが作り上げていることを話し、彼らへのリスペクトを告げる。それはこうしたフェスがなくなってしまったら彼らの仕事もなくなってしまうし、それが続いてしまったら彼らがライブを作ることがなくなってしまうという演者側としての悲痛なメッセージのようにも聞こえた。だからこそ自身は信念を持って生きていこうと思うということも。
ツインドラムのスネアやパーカッションの音が期待を煽る「DADA」は曲中のあらゆる、観客が洋次郎の歌へのリアクションのように歌っていた部分が無音になってしまったことによって、洋次郎もやはり自分たちのライブはファンの声があって初めて成立する、完成するものであるということを改めて確認するとともに、だからこそまたそうしてみんなで歌える日のためにこうやってつないでいかなければならないということを口にする。だからこそ洋次郎は観客が歌っていたところをそのまま自分で歌うことなく、観客に預けているのだろう。これまでずっとそうやってお互いの存在を肯定し合ってきたのだから。
「星は出てる?」
という言葉に観客が拍手で応えていたのは、満天の空に洋次郎の声が響いてもいいような、この日のように綺麗な夜のための「トレモロ」が演奏されたからであるが、この日演奏された曲の中ではこの曲が1番古い曲である。そんな時期の中でもこの曲をやるべきシチュエーションでしっかり聴かせてくれるRADWIMPSはさすがであるし、ラストサビに入る前のキメでの武田と桑原の高い跳躍力によるジャンプは、同世代の者としてはその姿を見るだけで大きな力を貰えるような気になる。
そんなアッパーな展開は手拍子が鳴り響く「いいんですか?」で少しほっこりもするのだが、観客が歌う場面では事前に録音されていたファンの声が流された。これまでに数え切れないくらいに歌ってきたそのフレーズを今は歌うことができない。それはやはり物凄くショックというか、現実を知らされてしまうことでもあるのだが、それはお互いにまた生きてこの曲をみんなで歌えるようにという約束でもある。それこそが、我々が選んだ道だからである。
そんなライブの締めは、先日急遽公開された新曲「SUMMER DAZE」。タイミング的にも紛れもなくこのライブのために、このライブに合わせて作られたものであるが、去年と同じように今年もまた夏フェスがなくなってきている。RADWIMPSも出演するはずだったロッキンがなくなってしまった。だからこそ、夏の思い出はきっとこの日だけになってしまう。そんな2021年の夏を少しでも輝かしいものにするために友人達と作ったという、4つ打ちのダンスポップ。それは誰よりも洋次郎が、メンバー自身が今年の夏の虚無感も悔しさも全て忘れないために、でも一瞬だけでも楽しかったと言えるようにという思いを込めたものであったように感じさせた。
アンコールでは
「この曲も夏の曲」
と言って、映画「天気の子」のメイン楽曲の一つとして、三浦透子という存在を世の中に引き出した「グランドエスケープ」が演奏され、その三浦透子の声が同期として洋次郎の声に重なる中で武田と桑原に合わせるように観客たちの大きな手拍子が鳴り響く。それは声を出して一緒に歌うことができない今の状況だからこそ、より一層美しい光景であるように見えた。
そして洋次郎が袖にいる関係者の方を見ながら
「またフジロックに呼んでもらえますかね?」
と確認するほどに楽しいものであったことを感じさせるこのライブのラストはコール&レスポンスはまた声が出せるようになった時までのお楽しみとばかりに、原曲通りの尺で演奏されたと思いきや、最後に高速化したアウトロを一回しだけ追加する形となった「君と羊と青」。喜怒哀楽の全方位というほどに怒も哀もない、でもそれを上回るくらいの喜と楽が確かにこの瞬間にはあったのだった。
2006年にロッキンのWING TENTで見てから、夏のRADWIMPSのライブを何回も見てきた。それはフェスだったり、時にはスタジアムでのワンマンだったりもしたのだが、その中でも最も「夏」を感じられるライブだった。いや、それはバンド側が夏を感じたかったからだろう。また何にもないまま過ぎていってしまうであろう2021年の夏は、フジロックが開催されて、RADWIMPSのライブを見ることができた。それを記憶に、人生に焼き付けるために。そのためのRADWIMPSの1日限りの夏だった。胸踊るものだけが呼吸するこの季節にいついつまでも 取り残されていたかった。
1.夏のせい
2.TWILIGHT
3.前前前世
4.NEVER EVER ENDER
5.カタルシスト
6.三葉のテーマ
7.スパークル
8.うたかた歌 w/ 菅田将暉
9.おしゃかしゃま
10.洗脳
11.DADA
12.トレモロ
13.いいんですか?
14.SUMMER DAZE
encore
15.グランドエスケープ
16.君と羊と青
今年のフジロックは「厳戒態勢」で行われていたらしい。そんなニュースがネットに出ていた。でも現地は厳戒態勢というほどにピリピリとしたムードはなかった。むしろこれがフジロックの空気なんだろうな、という雰囲気も強く感じられた。
だからこそ、感染対策も含めて厳戒態勢というほどのものではなかったし、そこに関してはJAPAN JAMやDPFの方が遥かに厳戒態勢だった。それは冒頭の方に書いた客席の立ち位置に関してもそうだし、スタッフの数や見回りというあたりもそう感じたが、きっとそれはフジロックが今までそうしたスタッフが参加者に強く注意したりすることがないフェスだったからだろう。
そういう意味でも、自分は「フジロッカー」という言葉も、フジロックの自由さも全く信用していなかった。2年前に配信で見た時の最前エリアに椅子を置いて座っている人がたくさんいる光景や、ずっとステージの動画を撮影している人がいることなど、果たして自分がこのフェスに行って100%楽しむことができるだろうか?と思っていたし、それは自由というよりも自分勝手が行き着いた結果だと思っていた。
それを経ての去年のフジロックの「変わります宣言」は、むしろこの状況になって変わらざるを得なくなった。すでに総攻撃を受けまくっている中で2年前と同じ感じで運営されていたら、音楽ファンからも擁護の余地はなかったであろうくらいに。
感染対策で言えば消毒を何回もしたくなるようなメッセージ付きの消毒場は良いアイデアだと思ったが、こういう状況だからこそ、日本のあらゆるフェス同士で良い部分をシェアし合って、より安全性の高いフェスを作れれば、とも思う。JAPAN JAMやDPFが屋外でどうやって観客同士の距離を保っていたか。ライブ中以外も密にならないように規制退場とかを行うにはどうやっていたか。個人的にはそこまでして欲しかったし、守ろうとしている、繋げようとしている人もたくさんいた、フジロックの自分の良くないイメージを塗り替えてくれるようなところもたくさんあったからこそ、興味がない人や叩きたい人に何も言わせないというくらいの状態にまでして欲しかった。
でもすでにフジロックは来年の開催を発表している。さすがにまだ発表するのは早すぎじゃない?とも思うけれど、今年泣く泣く行くのをやめることを選んだ人にとってはその発表が来年までの生きる希望になるかもしれない。そこまでに秋以降、冬や来年の春のフェスが開催されて、来年は誰もが重く考えることがなく、今までのようなフジロックの形で開催できるように。自分もその今までの形のフジロックもまた体験してみたいから。行く前よりも、今はまた来年あそこに行きたいと確かに思えるようになっていた、初参加のフジロックだった。
文 ソノダマン